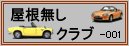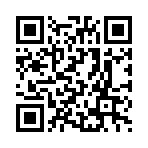スポンサーリンク
この広告は一定期間(1ヶ月以上)更新のないブログに表示されます。
ブログ記事の情報が古い場合がありますのでご注意下さい。
(ブログオーナーが新しい記事を投稿すると非表示になります。)
ブログ記事の情報が古い場合がありますのでご注意下さい。
(ブログオーナーが新しい記事を投稿すると非表示になります。)
2011年07月16日
6周年感謝パーティー
Ciao. spockです。
暑いですねぇ。
暑い暑いと言いながら、夏大好き人間のオレとしては、ワクワクしてますけど。
これだけ暑いのだったら、市民プールもオープンを前倒しすれば良かったのにねぇ。
さて、前回のブログにも書いた、LA FENICE 6周年感謝パーティーが、9日の夜にありました。
毎年、声をかけた方のうち、だいたい6割くらいの方が来て下さるので、それを目安にして声をかけているのですが、今年は土曜日に開催した事もあってか、予想以上に多くの方に来て頂き、30人を超えました・・・・人数的には、今迄で一番多いんじゃないかと思います。
そんな事もあって、賑やかなパーティーになりましたが、一部の方には窮屈な思いをさせてしまったのではないかと・・・・
オレは料理を作るのにかかりっきりになりますから、お客さんには、それぞれお好きなようにやって下さい、というのがウチのパーティーの決まり・・・・初めて来られた方は、最初のうちは戸惑っておられるようですが、しばらくすれば、たいてい慣れて、他のお客さんとの話も弾みます。
また、贈って下さった花は、カウンターに飾らせてもらいました。

例年、お客さんが揃うのが、予定時刻より30分くらい遅れますから、そのつもりで準備していたら、今年は結構早い時間に集まって下さったので、結構慌てました。
定刻の10分前にはカウンターが一杯になり、席の方へ移動してもらおうと思ったのですが、話が盛り上がっていて・・・・
とにかく、急いで前菜を準備して、テーブルに並べましたが、その流れのまま、最後までバタバタしていたような気がします。
このブログに書くために、料理の写真を撮っておこうと思っていましたが、前菜の段階で断念し、ひたすら料理を作る事に専念しました。
そんなわけで、今回はあまり画像がありません。
まず最初は、ウチの前菜の定番、生ハムとサラミの盛り合わせ。
 それから、ボイル野菜の焦がしバターソース
それから、ボイル野菜の焦がしバターソース
ボイルしたジャガイモ、ニンジン、セロリ、ブロッコリに、パン粉を加えて焦がしたバターをかけてあります。
普段のコースで出す事はありませんが、食べた事のある人には人気のメニューです。
今回も、初めて食べた、と言われる人が多かったし、評判も良かったですね。

グリーンアスパラのミラノ風
ゆでたアスパラに、半熟の目玉焼きを載せ、パルミジャーノ レッジャーノとバターをかけてあります。
アスパラに、チーズとバターと半熟の卵黄を絡めて食べます。
これも、普段は出しませんが、人気の一品です。
そして、ニッツァ風 海の幸のサラダ(ここからは画像なしです)
ニッツァとは、現在のニースの事・・・・昔はイタリアの領地だったので、古典的なイタリア料理には alla nizzarda (ニース風の)という名前がついたものが結構あります。
アンチョビの効いたドレッシングを、ボイルした魚介類に合わせてあります。
続いてパスタが出ますが、まずは、オレッキエッテ。
Orecchiette とは、小さい耳、の意味ですが、粉を水で練った柔らかいパスタを小さく切り、ひとつひとつ指で押さえて耳の形にしたものです。
このオレッキエッテに、チーズを溶かし込んでドロっとした濃度をつけた、少し辛口のミートソースを合わせてあります。
いわゆる『アルデンテ』ではないパスタですが、これを好む人は結構多いですね。
次は、自家製フェットゥッチーネのベーコン入りトマトクリームソース。
これはホント、北イタリアらしい一品です。
オレ自身、一番好きなソースのひとつです。
次は、ちょうど今年初の収穫をしたばかりのトマト・・・・ウチのために特別に作ってもらっているトマトを使った、トマト入りカルボナーラです。
トマトの入ったカルボナーラは珍しいと思うけど、オレはこっちの方が好きです。
カルボナーラが嫌いだと言う人でも、これなら食べれると言われる事が多いですね。
ここで余興をはさんで、その次は、ポルチーニ茸入りミラノ風リゾット。
サフランをたっぷりと使って黄金色に仕上げたミラノ風のリゾットは、贅沢なリゾットと言われますが、そこへさらにポルチーニを加えた、最高に贅沢なリゾットです。
ウチでは、バターもパルミジャーノ レッジャーノも、ケチらずにたっぷりと使いますから、本当に濃厚な味に仕上がります。
まだ用意してあるパスタはあったのですが、ここから魚料理です。
まずは、スズキの岩塩包み焼き。
もちろん、ホールを暗くして火を着ける演出付きです。
続いて、タイのモンテカルロ風バターソース。
これは、ウチの料理の中でも、ハマる人が一番多い料理です。
ムニエルにしたタイに、ニンニクとアンチョビとバターを同時に焦がしたソースを絡めたものですが、このソースは、パンに付けて食べるには最高のソースなので、イタリア産のクロスティーナとフォカッチャも一緒にお出ししました。
次は、鶏料理で、鶏のヴァッレダオスタ風チーズ焼きです。
スイスとの国境にある、アオスタ峡谷の名物料理で、仔牛を使う時と鶏を使う時では、上に載せるチーズが変わります。
寒い地方の料理だけあって、カロリーのかたまりみたいな料理ですが、「カロリーが高いほど美味い」という言葉を納得してしまう料理です。
もう一品の鶏は、魔女風の鉄板焼き。
本来は、鶏を背開きにして使うのですが、その形がマントを着た魔女のシルエットに似ているため、alla Diavola (魔女風の)という名前がついたのだそうです。
今回は、味のあるモモを使いました。
塩コショウとローズマリーで味付けし、重しを載せて、皮がパリパリになるまで焼きます。
シンプルだけど、鶏そのものの味を楽しめる一品ですね。
肉料理は、まず、トリッパ(牛の胃袋)の煮込み。
香味野菜と共に、5時間ほど下ゆでしたあと、ソッフリット(煮込み用炒め野菜)とトマトで煮込んであります。
時間をかけて煮込んであるので、蕩けそうなくらいの軟らかさになっています。
次は、この前このブログにも書いた、仔牛骨付きロースのミラノ風カツです。
最後に、遅れて来られた方のために、ホウレン草入り自家製タリアテッレのボローニャ風ミートソースをお出ししました。
ホウレン草を練り込んだ自家製のパスタに、10時間以上煮込んだ濃厚なミートソースを合わせてありますが、これだけ濃厚なミートソースは他にないと思いますよ。
去年は、とにかくいろいろ食べてもらおうと、料理の品数を増やしたのですが、すべての方に行き渡らなかった料理があったようなので、今年は品数を減らして一品ごとの量を増やし、すべての人に確実に一品ずつ食べてもらえるようにしました。
まぁ、これが正解なんじゃないかと思います。
今回初めて参加して下さった方の中に、音楽関係の方がおられたので、余興をお願いしていたのですが、わざわざ楽器まで持ってきて頂いて、演奏して頂きました。
高山室内合奏団の団長、鴨宮誠さんのチェロ、奥さんの雅子さんのピアノ、コンサートミストレスの町川加代子さんによるピアノトリオで、エリック・サティの ”Je te veux” ジュ トゥ ヴー(あなたが欲しい)が演奏されました。

続いて、鴨宮雅子さんのピアノで、同じくサティの『ジムノペティ第1番』、さらに、ヴァイオリンの発表会で伴奏をしてもらった細江美津子さんのピアノで、『星に願いを』と『アメイジング グレイス』を演奏して頂きました。
クラヴィノーヴァが、早速活躍してくれましたが、こんな感じでミニコンサートができるといいですよね。
そのうちに、定期的にコンサートが開けるようにしたいと思っています。
今回は参加できなかった、一緒にヴァイオリンを習っている加藤秀一君から花が届いたのですが、添えられたカードにこんな事が書かれていました。

ぜひ、やりたいものですね。
ヴァイオリンやチェロのビギナーの人達から、身内だけの発表会をやりたい、という声を聞いていますが、そういう会をやれば、演奏技術を向上させるためにも、きっと効果があると思います。
今年参加して下さった方は、あまり飲めない方が多かったせいか、ワインを20本空けた去年に比べれば、飲んだ量は少なかったようですが、でも、皆さん楽しんで頂けたようです。
来て頂く予定だったのに、仕事の都合で来れなくなった方も何人かおられたようだし、声をかけるのを忘れた方も何人か後になって思い出しましたが、来年はぜひ参加してもらえるように、今からリストを作っておかないといけませんね。
来年、7周年のパーティーができるように、また頑張ってやっていこうと思っています。
7年目の LA FENICE を、これからもよろしくお願いします。
では、また。
CIao. Arrivederci!!
暑いですねぇ。
暑い暑いと言いながら、夏大好き人間のオレとしては、ワクワクしてますけど。
これだけ暑いのだったら、市民プールもオープンを前倒しすれば良かったのにねぇ。
さて、前回のブログにも書いた、LA FENICE 6周年感謝パーティーが、9日の夜にありました。
毎年、声をかけた方のうち、だいたい6割くらいの方が来て下さるので、それを目安にして声をかけているのですが、今年は土曜日に開催した事もあってか、予想以上に多くの方に来て頂き、30人を超えました・・・・人数的には、今迄で一番多いんじゃないかと思います。
そんな事もあって、賑やかなパーティーになりましたが、一部の方には窮屈な思いをさせてしまったのではないかと・・・・
オレは料理を作るのにかかりっきりになりますから、お客さんには、それぞれお好きなようにやって下さい、というのがウチのパーティーの決まり・・・・初めて来られた方は、最初のうちは戸惑っておられるようですが、しばらくすれば、たいてい慣れて、他のお客さんとの話も弾みます。
また、贈って下さった花は、カウンターに飾らせてもらいました。

例年、お客さんが揃うのが、予定時刻より30分くらい遅れますから、そのつもりで準備していたら、今年は結構早い時間に集まって下さったので、結構慌てました。
定刻の10分前にはカウンターが一杯になり、席の方へ移動してもらおうと思ったのですが、話が盛り上がっていて・・・・
とにかく、急いで前菜を準備して、テーブルに並べましたが、その流れのまま、最後までバタバタしていたような気がします。
このブログに書くために、料理の写真を撮っておこうと思っていましたが、前菜の段階で断念し、ひたすら料理を作る事に専念しました。
そんなわけで、今回はあまり画像がありません。
まず最初は、ウチの前菜の定番、生ハムとサラミの盛り合わせ。
 それから、ボイル野菜の焦がしバターソース
それから、ボイル野菜の焦がしバターソースボイルしたジャガイモ、ニンジン、セロリ、ブロッコリに、パン粉を加えて焦がしたバターをかけてあります。
普段のコースで出す事はありませんが、食べた事のある人には人気のメニューです。
今回も、初めて食べた、と言われる人が多かったし、評判も良かったですね。

グリーンアスパラのミラノ風
ゆでたアスパラに、半熟の目玉焼きを載せ、パルミジャーノ レッジャーノとバターをかけてあります。
アスパラに、チーズとバターと半熟の卵黄を絡めて食べます。
これも、普段は出しませんが、人気の一品です。
そして、ニッツァ風 海の幸のサラダ(ここからは画像なしです)
ニッツァとは、現在のニースの事・・・・昔はイタリアの領地だったので、古典的なイタリア料理には alla nizzarda (ニース風の)という名前がついたものが結構あります。
アンチョビの効いたドレッシングを、ボイルした魚介類に合わせてあります。
続いてパスタが出ますが、まずは、オレッキエッテ。
Orecchiette とは、小さい耳、の意味ですが、粉を水で練った柔らかいパスタを小さく切り、ひとつひとつ指で押さえて耳の形にしたものです。
このオレッキエッテに、チーズを溶かし込んでドロっとした濃度をつけた、少し辛口のミートソースを合わせてあります。
いわゆる『アルデンテ』ではないパスタですが、これを好む人は結構多いですね。
次は、自家製フェットゥッチーネのベーコン入りトマトクリームソース。
これはホント、北イタリアらしい一品です。
オレ自身、一番好きなソースのひとつです。
次は、ちょうど今年初の収穫をしたばかりのトマト・・・・ウチのために特別に作ってもらっているトマトを使った、トマト入りカルボナーラです。
トマトの入ったカルボナーラは珍しいと思うけど、オレはこっちの方が好きです。
カルボナーラが嫌いだと言う人でも、これなら食べれると言われる事が多いですね。
ここで余興をはさんで、その次は、ポルチーニ茸入りミラノ風リゾット。
サフランをたっぷりと使って黄金色に仕上げたミラノ風のリゾットは、贅沢なリゾットと言われますが、そこへさらにポルチーニを加えた、最高に贅沢なリゾットです。
ウチでは、バターもパルミジャーノ レッジャーノも、ケチらずにたっぷりと使いますから、本当に濃厚な味に仕上がります。
まだ用意してあるパスタはあったのですが、ここから魚料理です。
まずは、スズキの岩塩包み焼き。
もちろん、ホールを暗くして火を着ける演出付きです。
続いて、タイのモンテカルロ風バターソース。
これは、ウチの料理の中でも、ハマる人が一番多い料理です。
ムニエルにしたタイに、ニンニクとアンチョビとバターを同時に焦がしたソースを絡めたものですが、このソースは、パンに付けて食べるには最高のソースなので、イタリア産のクロスティーナとフォカッチャも一緒にお出ししました。
次は、鶏料理で、鶏のヴァッレダオスタ風チーズ焼きです。
スイスとの国境にある、アオスタ峡谷の名物料理で、仔牛を使う時と鶏を使う時では、上に載せるチーズが変わります。
寒い地方の料理だけあって、カロリーのかたまりみたいな料理ですが、「カロリーが高いほど美味い」という言葉を納得してしまう料理です。
もう一品の鶏は、魔女風の鉄板焼き。
本来は、鶏を背開きにして使うのですが、その形がマントを着た魔女のシルエットに似ているため、alla Diavola (魔女風の)という名前がついたのだそうです。
今回は、味のあるモモを使いました。
塩コショウとローズマリーで味付けし、重しを載せて、皮がパリパリになるまで焼きます。
シンプルだけど、鶏そのものの味を楽しめる一品ですね。
肉料理は、まず、トリッパ(牛の胃袋)の煮込み。
香味野菜と共に、5時間ほど下ゆでしたあと、ソッフリット(煮込み用炒め野菜)とトマトで煮込んであります。
時間をかけて煮込んであるので、蕩けそうなくらいの軟らかさになっています。
次は、この前このブログにも書いた、仔牛骨付きロースのミラノ風カツです。
最後に、遅れて来られた方のために、ホウレン草入り自家製タリアテッレのボローニャ風ミートソースをお出ししました。
ホウレン草を練り込んだ自家製のパスタに、10時間以上煮込んだ濃厚なミートソースを合わせてありますが、これだけ濃厚なミートソースは他にないと思いますよ。
去年は、とにかくいろいろ食べてもらおうと、料理の品数を増やしたのですが、すべての方に行き渡らなかった料理があったようなので、今年は品数を減らして一品ごとの量を増やし、すべての人に確実に一品ずつ食べてもらえるようにしました。
まぁ、これが正解なんじゃないかと思います。
今回初めて参加して下さった方の中に、音楽関係の方がおられたので、余興をお願いしていたのですが、わざわざ楽器まで持ってきて頂いて、演奏して頂きました。
高山室内合奏団の団長、鴨宮誠さんのチェロ、奥さんの雅子さんのピアノ、コンサートミストレスの町川加代子さんによるピアノトリオで、エリック・サティの ”Je te veux” ジュ トゥ ヴー(あなたが欲しい)が演奏されました。

続いて、鴨宮雅子さんのピアノで、同じくサティの『ジムノペティ第1番』、さらに、ヴァイオリンの発表会で伴奏をしてもらった細江美津子さんのピアノで、『星に願いを』と『アメイジング グレイス』を演奏して頂きました。
クラヴィノーヴァが、早速活躍してくれましたが、こんな感じでミニコンサートができるといいですよね。
そのうちに、定期的にコンサートが開けるようにしたいと思っています。
今回は参加できなかった、一緒にヴァイオリンを習っている加藤秀一君から花が届いたのですが、添えられたカードにこんな事が書かれていました。

ぜひ、やりたいものですね。
ヴァイオリンやチェロのビギナーの人達から、身内だけの発表会をやりたい、という声を聞いていますが、そういう会をやれば、演奏技術を向上させるためにも、きっと効果があると思います。
今年参加して下さった方は、あまり飲めない方が多かったせいか、ワインを20本空けた去年に比べれば、飲んだ量は少なかったようですが、でも、皆さん楽しんで頂けたようです。
来て頂く予定だったのに、仕事の都合で来れなくなった方も何人かおられたようだし、声をかけるのを忘れた方も何人か後になって思い出しましたが、来年はぜひ参加してもらえるように、今からリストを作っておかないといけませんね。
来年、7周年のパーティーができるように、また頑張ってやっていこうと思っています。
7年目の LA FENICE を、これからもよろしくお願いします。
では、また。
CIao. Arrivederci!!
2011年07月09日
パーティー準備中
Ciao. spockです。
いよいよ今夜は LA FENICE 6周年感謝パーティーです。
今日は朝から、その準備に追われています。
テーブルの上のセットはまだだけれど、イスとテーブルはパーティー用の配置に。

使う材料の一部。


それから、ちょうど昨日、今年初の収穫をしたOさんのトマト。

今夜のパーティーでは、久しぶりに『トマト入りのカルボナーラ』を作れますね。
この前、妹のところから来た、クラヴィノーヴァ。

今夜は、これも使って余興をやってもらいます。
今回初めて、土曜日に開催する事にしましたが、明日の事を心配せずに楽しんでもらえると思います。
もっとも、仕事の都合で遅れる、と言われる方も結構おられますが。
来て下さる方に楽しんでもらえるよう、パーティー開始時刻まで、準備は続きます。
では、お待ちしております。
Ciao. Arrivederci!!
いよいよ今夜は LA FENICE 6周年感謝パーティーです。
今日は朝から、その準備に追われています。
テーブルの上のセットはまだだけれど、イスとテーブルはパーティー用の配置に。

使う材料の一部。


それから、ちょうど昨日、今年初の収穫をしたOさんのトマト。

今夜のパーティーでは、久しぶりに『トマト入りのカルボナーラ』を作れますね。
この前、妹のところから来た、クラヴィノーヴァ。

今夜は、これも使って余興をやってもらいます。
今回初めて、土曜日に開催する事にしましたが、明日の事を心配せずに楽しんでもらえると思います。
もっとも、仕事の都合で遅れる、と言われる方も結構おられますが。
来て下さる方に楽しんでもらえるよう、パーティー開始時刻まで、準備は続きます。
では、お待ちしております。
Ciao. Arrivederci!!
2011年07月01日
仔牛骨付きロースのミラノ風カツ
Ciao. spockです。
前回にも書きましたが、LA FENICE がオープンしたのは、6年前の7月1日でした。
だから、今日から7年目に入ります。
こんな儲けの出ない商売をしている店が6年も潰れずに続いている事が、奇跡みたいな事だと思っていますが、ここまでやって来れたのも、ウチの料理を愛して下さるお客さんのおかげです。
本当に、ありがとうございます。
これからも、よろしくお願いします。
この7月1日という日、オレは3軒の店をオープンさせているんです。
1987年、タベルナ・デル・オルソ Taverna dell'Orso(神戸、北野町)
1991年、タベルナ・デル・コッレオーニ Taverna del Colleoni(東京、赤坂)
2005年、ラ フェニーチェ LA FENICE
全くの偶然なんですが、ウチがこの日にオープンしたのも、何か必然性があったのかな・・・・って思う事があります。
まぁ、ここまで続いたのですから、それが良かったのだろうと思うのですが、これからも歴史を積み重ねていけたらいいと思っています。
さて、今回は久しぶりに、料理の話をしましょう。
今回取り上げる料理はコレ。

仔牛骨付きロースのミラノ風カツ Costoletta di vitello alla milanese. です。
この『ミラノ風カツ』は、料理の本を見ると、本の数だけ違う作り方が書いてあるんじゃないかと思うくらい、いろんな作り方が書かれています。
だから、どれが本当の作り方なんだ?、と疑問に思ってしまうくらいなんですが、オレは敢えて、ウチでやっているのが本当の『ミラノ風カツ』だと言ってしまいます。
それには、ちゃんとした理由があるからです。
オレが修行した、神戸『ベルゲン』の安田さんは、ミラノのサヴィーニ Ristorante SAVINI で修行されたのですが、このサヴィーニは、イタリアで一番の格式を誇る店であり、ミラノ料理の最高峰でもあります。
そのサヴィーニのやり方を、オレは安田さんを通して受け継いでいるわけですが、安田さんに教わった時、「これだけの事をすべてやって、初めて『ミラノ風』と名乗れるんだ」と言われたので、オレはそのやり方を、そっくりそのままやっています。
それ故に、正統派の『ミラノ風』だと言っていいと思います。
イタリア料理において、一番良く使われる肉は仔牛です。
厳密に言えば、母牛の乳を飲んでいる状態の牛、という事になりますが、供給量の問題もあって、ある程度草を食べて育った牛も、仔牛として流通している事があるようです。
仔牛の肉は脂肪が少ないので、カロリーが低く、消化も良いのですが、肉質は成牛にくらべてパサパサした感じがします。
そのため、濃度のあるソースと合わせたり、チーズを載せて焼いたり、衣をつけて焼いたりと、必然的にコッテリした料理になる事が多いですね。
まぁ、そのおかげで、赤ワインと合わせる楽しみがあるのですが。
今でこそ、仔牛の部位ごとに分けられたものが冷凍で入ってきますから、必要な部位だけ仕入れる事ができますが、オレがこの世界に入った30年前は、仔牛を手に入れること自体が難しい時代でしたから、いわゆる「売り手市場」というやつで、半頭でしか売ってくれないわけですよ。
で、半頭で仕入れた仔牛を、2日がかりで、骨付きロース、Tボーン、モモ、スネ、スジ等、部位ごとに分けていました。
そのおかげで、構造をしっかりと覚える事ができましたけどね。
さて、その『骨付きロース』ですが、イタリア語では Costoletta コストレッタ と言います。
仔牛が Vitello ヴィテッロ なので、仔牛の骨付きロースは、Costoletta di vitello コストレッタ ディ ヴィテッロ、となるわけです。
仔牛の中でも、一番高級な部分と言っていいと思います。
冷凍で入ってきた『骨付きロース』を解凍すると、こんなふうになります。

左右、7本ずつの骨がついています。
筋が結構多いので、不必要な部分を取り除きながら、分けていきます。
まず、この状態から、

取り外せるものを外しながら、バラしていきます。

左側の尖がったのが『フィレ』の先端で、ここに続くロースとフィレの付いた部分を骨ごと切ったものが、いわゆる『Tボーン』です。
Tボーンは、T字型の骨の片側にロース、もう片側にフィレがついているわけです。
ちなみに、イタリア語では Nodino ノディーノ と言います。
で、骨の間に包丁を入れ、分けていくと、

こんなふうになります。

さらに、筋や骨など、不必要な部分を取ると、こんな感じ。

他の取り外した部分も、肉と筋を分けます。

で、全部分けたのが、この状態。

筋は、ブロード(ブイヨン)を取る時に使います。
さぁ、これでやっと、料理に使える状態になりました。
まず、肉を叩いて、薄く伸ばさなければならないのですが、このままでは厚過ぎるので、半分に削ぎます。

見て分かるとおり、細い筋が結構多いんですよ。
取れる筋は取ってから、叩いて伸ばします。
これは、叩いて伸ばした肉を裏返して見たところですが、筋が良く見えますね。

で、筋切りをします。

見えやすいように、黒いところに置くと、筋切りをしたところが良く分かりますね。

筋切りをきちんとしておかないと、焼いた時に縮んでしまうし、歯応えも良くないので、丁寧にやっておく必要があります。
さらに、叩いて伸ばして筋切りをした肉を張り合わせ、きれいな形に整えます。

厚さはだいたい2mmくらい。
これでやっと、下準備ができました。
日本でカツというと、厚みの厚い物の方がいいように思われていますが、ヨーロッパでは、厚くてもせいぜい5mmまでですね。
衣と肉の両方が美味いバランスを考えると、そういう結論に達するわけです。
おそらくは、あまり肉を食べる習慣がなかった日本にカツレツという料理が入ってきた時、厚い肉を使った方が高級だろう、というような考え方がされたんじゃないかな、って思いますけどね。
この状態の肉は、他の料理に使う事もあり、たとえば、卵をつけて焼き、その上に生クリームで和えたポルチーニ、生ハム、チーズを載せてオーヴンで焼き、パルミジャーノ レッジャーノをふって、セージ入りの焦がしバターをかければ、ヴァッレダオスタ風のチーズ焼き Costoletta di vitello alla valdostana. になります。
また、粉をつけて焼き、マルサーラと赤ワイン、デミソースで味付けし、生ハムとチーズを載せてオーヴンで焼くと、ボローニャ風のチーズ焼き Costoletta di vitello alla bolognese. になります。
今回はミラノ風のカツ、という事で、衣をつけていきます。
塩コショウをして粉をつけ、溶き卵をくぐらせてパン粉の上に載せ、味付けをしてから、パン粉を載せて、しっかりと押さえます。

これを、こんがりと焼き色がつくように焼きます。

焼き上がったのが、こんな感じ。

これに、バターとセージの香りをつけてオーヴンで焼くと、ミラノ風カツの完成です。
好みで絞ってかけてもらうように、レモンを添えて出します。

ところで、この料理に限った事ではありませんが、料理に添えられたレモン・・・・あくまでも『好み』でかけてもらうものですから、まずその料理を食べてみて、必要ならかけてもらえばいいわけですよ。
(オレ自身はたいていの場合、レモンをかけずに食べるのが好きですけどね。)
ところがね、味も見ないうちに、いきなりかけてしまう人が結構いるんですよね。
オレには全く理解できない行為なんですが、皆さんはどう思われますか?
では、また。
Ciao. Arrivederci!!
前回にも書きましたが、LA FENICE がオープンしたのは、6年前の7月1日でした。
だから、今日から7年目に入ります。
こんな儲けの出ない商売をしている店が6年も潰れずに続いている事が、奇跡みたいな事だと思っていますが、ここまでやって来れたのも、ウチの料理を愛して下さるお客さんのおかげです。
本当に、ありがとうございます。
これからも、よろしくお願いします。
この7月1日という日、オレは3軒の店をオープンさせているんです。
1987年、タベルナ・デル・オルソ Taverna dell'Orso(神戸、北野町)
1991年、タベルナ・デル・コッレオーニ Taverna del Colleoni(東京、赤坂)
2005年、ラ フェニーチェ LA FENICE
全くの偶然なんですが、ウチがこの日にオープンしたのも、何か必然性があったのかな・・・・って思う事があります。
まぁ、ここまで続いたのですから、それが良かったのだろうと思うのですが、これからも歴史を積み重ねていけたらいいと思っています。
さて、今回は久しぶりに、料理の話をしましょう。
今回取り上げる料理はコレ。

仔牛骨付きロースのミラノ風カツ Costoletta di vitello alla milanese. です。
この『ミラノ風カツ』は、料理の本を見ると、本の数だけ違う作り方が書いてあるんじゃないかと思うくらい、いろんな作り方が書かれています。
だから、どれが本当の作り方なんだ?、と疑問に思ってしまうくらいなんですが、オレは敢えて、ウチでやっているのが本当の『ミラノ風カツ』だと言ってしまいます。
それには、ちゃんとした理由があるからです。
オレが修行した、神戸『ベルゲン』の安田さんは、ミラノのサヴィーニ Ristorante SAVINI で修行されたのですが、このサヴィーニは、イタリアで一番の格式を誇る店であり、ミラノ料理の最高峰でもあります。
そのサヴィーニのやり方を、オレは安田さんを通して受け継いでいるわけですが、安田さんに教わった時、「これだけの事をすべてやって、初めて『ミラノ風』と名乗れるんだ」と言われたので、オレはそのやり方を、そっくりそのままやっています。
それ故に、正統派の『ミラノ風』だと言っていいと思います。
イタリア料理において、一番良く使われる肉は仔牛です。
厳密に言えば、母牛の乳を飲んでいる状態の牛、という事になりますが、供給量の問題もあって、ある程度草を食べて育った牛も、仔牛として流通している事があるようです。
仔牛の肉は脂肪が少ないので、カロリーが低く、消化も良いのですが、肉質は成牛にくらべてパサパサした感じがします。
そのため、濃度のあるソースと合わせたり、チーズを載せて焼いたり、衣をつけて焼いたりと、必然的にコッテリした料理になる事が多いですね。
まぁ、そのおかげで、赤ワインと合わせる楽しみがあるのですが。
今でこそ、仔牛の部位ごとに分けられたものが冷凍で入ってきますから、必要な部位だけ仕入れる事ができますが、オレがこの世界に入った30年前は、仔牛を手に入れること自体が難しい時代でしたから、いわゆる「売り手市場」というやつで、半頭でしか売ってくれないわけですよ。
で、半頭で仕入れた仔牛を、2日がかりで、骨付きロース、Tボーン、モモ、スネ、スジ等、部位ごとに分けていました。
そのおかげで、構造をしっかりと覚える事ができましたけどね。
さて、その『骨付きロース』ですが、イタリア語では Costoletta コストレッタ と言います。
仔牛が Vitello ヴィテッロ なので、仔牛の骨付きロースは、Costoletta di vitello コストレッタ ディ ヴィテッロ、となるわけです。
仔牛の中でも、一番高級な部分と言っていいと思います。
冷凍で入ってきた『骨付きロース』を解凍すると、こんなふうになります。

左右、7本ずつの骨がついています。
筋が結構多いので、不必要な部分を取り除きながら、分けていきます。
まず、この状態から、

取り外せるものを外しながら、バラしていきます。

左側の尖がったのが『フィレ』の先端で、ここに続くロースとフィレの付いた部分を骨ごと切ったものが、いわゆる『Tボーン』です。
Tボーンは、T字型の骨の片側にロース、もう片側にフィレがついているわけです。
ちなみに、イタリア語では Nodino ノディーノ と言います。
で、骨の間に包丁を入れ、分けていくと、

こんなふうになります。

さらに、筋や骨など、不必要な部分を取ると、こんな感じ。

他の取り外した部分も、肉と筋を分けます。

で、全部分けたのが、この状態。

筋は、ブロード(ブイヨン)を取る時に使います。
さぁ、これでやっと、料理に使える状態になりました。
まず、肉を叩いて、薄く伸ばさなければならないのですが、このままでは厚過ぎるので、半分に削ぎます。

見て分かるとおり、細い筋が結構多いんですよ。
取れる筋は取ってから、叩いて伸ばします。
これは、叩いて伸ばした肉を裏返して見たところですが、筋が良く見えますね。

で、筋切りをします。

見えやすいように、黒いところに置くと、筋切りをしたところが良く分かりますね。

筋切りをきちんとしておかないと、焼いた時に縮んでしまうし、歯応えも良くないので、丁寧にやっておく必要があります。
さらに、叩いて伸ばして筋切りをした肉を張り合わせ、きれいな形に整えます。

厚さはだいたい2mmくらい。
これでやっと、下準備ができました。
日本でカツというと、厚みの厚い物の方がいいように思われていますが、ヨーロッパでは、厚くてもせいぜい5mmまでですね。
衣と肉の両方が美味いバランスを考えると、そういう結論に達するわけです。
おそらくは、あまり肉を食べる習慣がなかった日本にカツレツという料理が入ってきた時、厚い肉を使った方が高級だろう、というような考え方がされたんじゃないかな、って思いますけどね。
この状態の肉は、他の料理に使う事もあり、たとえば、卵をつけて焼き、その上に生クリームで和えたポルチーニ、生ハム、チーズを載せてオーヴンで焼き、パルミジャーノ レッジャーノをふって、セージ入りの焦がしバターをかければ、ヴァッレダオスタ風のチーズ焼き Costoletta di vitello alla valdostana. になります。
また、粉をつけて焼き、マルサーラと赤ワイン、デミソースで味付けし、生ハムとチーズを載せてオーヴンで焼くと、ボローニャ風のチーズ焼き Costoletta di vitello alla bolognese. になります。
今回はミラノ風のカツ、という事で、衣をつけていきます。
塩コショウをして粉をつけ、溶き卵をくぐらせてパン粉の上に載せ、味付けをしてから、パン粉を載せて、しっかりと押さえます。

これを、こんがりと焼き色がつくように焼きます。

焼き上がったのが、こんな感じ。

これに、バターとセージの香りをつけてオーヴンで焼くと、ミラノ風カツの完成です。
好みで絞ってかけてもらうように、レモンを添えて出します。

ところで、この料理に限った事ではありませんが、料理に添えられたレモン・・・・あくまでも『好み』でかけてもらうものですから、まずその料理を食べてみて、必要ならかけてもらえばいいわけですよ。
(オレ自身はたいていの場合、レモンをかけずに食べるのが好きですけどね。)
ところがね、味も見ないうちに、いきなりかけてしまう人が結構いるんですよね。
オレには全く理解できない行為なんですが、皆さんはどう思われますか?
では、また。
Ciao. Arrivederci!!