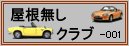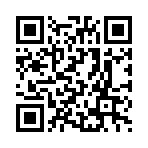スポンサーリンク
この広告は一定期間(1ヶ月以上)更新のないブログに表示されます。
ブログ記事の情報が古い場合がありますのでご注意下さい。
(ブログオーナーが新しい記事を投稿すると非表示になります。)
ブログ記事の情報が古い場合がありますのでご注意下さい。
(ブログオーナーが新しい記事を投稿すると非表示になります。)
2010年01月15日
敢えてレシピを変える その1
Ciao. spockです。
寒い日が続きますねぇ。
あんまり寒いので、ここしばらくはランチタイムに薪ストーブを焚いています・・・・普段は夜にしか焚かないんですけどね。
炎を見ているだけで、気分的にも暖かくなりますが・・・・このところ、お客さんが少ないんで、どうせなら、こういう日に来てもらえばいいのに、って思ってしまいますね。
この前、山ちゃんが来てくれた時に、冷え切った足をストーブで暖めてもらえましたから、そういう時、焚いていて良かったと思います。
これからも、寒い日には薪ストーブを焚く事にしようと思ってますけど。
12月の忙しさに比べると、1月は本当~にヒマです。
楽天的な性格のオレも、ここしばらくはあまりのヒマさに、ウチの店はいつまで続くかな、なんて本気で考えたりもしていたのですが、そういう時に助けられるのは、やはりお客さんですね。
12月にパーティーで初めて来られたお客さんが、今度は個人的に予約を入れて下さったり、カウンターに来られたお客さんから、「本物ほど広く認められるには時間がかかるんだから、この店はこれからだよ」なんて言ってもらえると、すぐに立ち直りますからね。
立ち直りが早いのが、楽天的な人間の長所ですから・・・・
『本物』という言葉を聞いて思い出す事があります。
オレも出演させてもらった、劇団無尽舎のヴィデオ映画『大めいかい』の中で、オレの台詞に「本物は高くつく、という事だ」というのがありましたが、この台詞は、鋭く真実を突いていると思います。
でもね、その台詞を言ったオレが言うのもなんですが、ウチの店に関しては、それは当てはまらないと思いますね。
ウチほど本物を安く出している店は他に無いだろう、って自負してますから。
ここで、お知らせです。
モバイル会員の方にお送りした、新年のメールの特典は、来週の土曜日(23日)が期限です。
お早めにお出で下さい。
また、会員登録していただいた際の特典(焼き菓子)を、まだ受け取っておられない方は、お申し付け下さい。
さて、今回は久しぶりに、料理について書くことにしましょう。
先日、お客さんと、そんな話をしたので。
ウチの料理は基本的に、イタリアでやっているのと全く同じか、できる限り近い状態でお出しすることにしています。
古典的な北イタリア料理を出す事が基本の店ですから、当然なんですけどね。
古典的な料理というのは、長い年月を経て、本当に美味い料理だけが残されてきたわけですから、伝えられてきたレシピの通りにきっちりと作れば、美味い物ができるのが当然なんですね。
そういう料理は、絶妙なバランスの上で成り立っているので、ちょっと色気を出してアレンジしたりすると、一気にバランスが崩れて、訳の分からない料理になってしまうんですよ。
ウチでは基本的に飛騨牛を使わないのも、そういう理由からなんですが(その事についても、近いうちに書くことになると思いますが)、逆に、日本で手に入る食材を使う以上、変えなければならない部分がある事も事実ですね。
まぁ、その見極めが大切なんですが・・・・
ウチでは、今のところ、敢えてレシピを変えて作っている料理が2つあります。
今回は、その料理について書くことにします。
まずはコレ。
ジャガイモのニョッキ Gnocchi di patate です。
 ニョッキは、簡単に言えば『団子』みたいなものですが、ジャガイモのニョッキの場合、茹でて裏ごししたジャガイモに、卵黄、塩、ナツメッグ、パルミジャーノ・レッジャーノ、粉を加えて合わせ、フォークで形を作って茹でたものなんですよ。
ニョッキは、簡単に言えば『団子』みたいなものですが、ジャガイモのニョッキの場合、茹でて裏ごししたジャガイモに、卵黄、塩、ナツメッグ、パルミジャーノ・レッジャーノ、粉を加えて合わせ、フォークで形を作って茹でたものなんですよ。
ウチでは、イモの味を引き立てるために、シンプルな『ピエモンテ風バターソース』でお出ししています。
ウチのニョッキを食べられたお客さんは、たいてい、こんなニョッキは初めて食べた、って言われます。
独自のレシピでやっているのですから、そう言われるのは当然なんですが、ウチのニョッキにハマる方が多い事は事実だと思います。
今でこそ、イタリア料理は広く普及しましたから、そんな事を訊かれる事はなくなりましたが、昔はよく、どうしてイタリア料理を選んだんですか、って訊かれましたねぇ。
そういう時、オレはいつも「ウチの家系は例外なくイモと麺類が好きだから」って答えてました。
冗談半分みたいに聞こえるかもしれないけれど、これは本当の事で、さらに言うなら「ご飯も麺類も硬いのが好きだから」という事になるんですけどね。
そんなイモ大好き人間のオレにとって、ニョッキって、ある意味で中途半端なパスタだったんですよ。
歯応えがあるわけでもないし、イモの味が濃厚なわけでもないし・・・・
もっとイモの味が強く出た方が美味い、ってオレは思っていたわけです。
で、自分なりにいろいろやってみた結果、イモの味をしっかりと出すには、本来のレシピより粉を少なくする事が一番いいと分かったのですよ。
本来のレシピでは、粉はイモの3分の1、ということになっていますが、ウチではその半分位でしょうかね。
まぁ、その時のイモの状態を見て加減するので、ハッキリと数字には出せませんけどね。
ただね、粉を少なくするという事は、当然、食べた時の食感が全く変わってしまいますね。
だから、食感と味のどちらを取るか、と考えた時、オレは味を取ったわけです。
でも、実際に食べてみると、その食感は悪くない・・・・むしろ、この食感を好む人の方が多いんじゃないかと思いましたね。
そう決まれば、その作り方で作るだけですね。
粉を少なくする、という事は、パスタ自体がかなり柔らかくなるわけですから、取り扱いが厄介になります。
形は作りにくいし、下手をすれば、すぐに潰れてしまうし、少しでも長くゆでると、解けて崩れてしまう。
でも、この味を出すにはこれしかない、と思って作れば、それが特別な問題になる程の事ではなかったですね。
ニョッキを作る場合、粘り気を出さないために、熱いうちに、あまりこねくり回さないように合わせるのですが、必然的に、どうしても粉や卵黄が混ざりきらない『部分的なムラ』ができてしまうものなんですよ。
粉を少なくすると、そういう部分的なムラが、さらに多くなってしまう事は避けられません。
粉や卵黄が混ざらなかったイモだけの部分は、ゆでると解けてしまい、バラバラに散ってしまいますから、そういう部分を見極めながらゆでるのが、一番難しいですね。
1人前に1個か2個、一部分崩れたものが混じるのは、避けようがない事ではありますけどね。
ニョッキには、粘り気の弱い『男爵』系のいもが向いているのですが、『インカの目覚め』という、粘り気の強い品種のイモを使ってニョッキを作った事があります。
インカの目覚めの粘り気が、ニョッキに向いていない事は分かっていても、その味と色に惹かれて、どうしても作ってみたくなったわけなんですよ。
で、粘り気を出さないようにしながら、さらに粉を少なくして作ってみたところ、本当に美味いニョッキになったのだけれど、やはり、ゆでるのが難しかったですね。
でも、今度また作ってみたいと思わされる味でした。
そうして作った、イモの味が濃厚なニョッキに合わせるソースは、ニョッキそのものの味を引き立てる、シンプルなソースがいいですね。
ですからウチでは『ピエモンテ風のバターソース』でお出ししています。
北イタリアで良く使われるソースに、ブッロ エ サルヴィア Burro e salvia、または、ブッロ ヴェルザート Burro versato、と呼ばれるものがあります。
ラヴィオリやニョッキのソースに使われる事が多いのですが、チーズ焼きにした肉料理の仕上げに使われる事もあります。
そのやり方は、ゆで上がったパスタにパルミジャーノ・レッジャーノをかけ、そこへセージ(イタリア語ではサルヴィア)を加えて焦がしたバターをかけるという、シンプルなソースです。
シンプルゆえにヴァリエーションも結構あり、その中のひとつが、パルミジャーノ・レッジャーノの上に少量のトマトソースを載せてから焦がしバターをかける『ピエモンテ風』なんですよ。
白いニョッキに、赤いトマトソース、緑のサルヴィアと、いろどりもいいですね。
ウチでは、自家栽培のセージを使いますが、冬の間だけは、どうしても乾燥もののセージに頼るしかないのは、仕方ないですね。
まぁ、一度ウチのニョッキを食べてみてください。
特に、スーパーなんかで売っている袋詰めのものなんかを食べて、あまりいいイメージを持ってない方には、ぜひ食べて頂きたいですね。
目からウロコが10枚くらい落ちる事は請合いますよ。
ニョッキの事だけで長くなりましたから、レシピを敢えて変えている、もうひとつの料理の事は、次回に書く事にします。
では、また。
Ciao. Arrivederci!!
寒い日が続きますねぇ。
あんまり寒いので、ここしばらくはランチタイムに薪ストーブを焚いています・・・・普段は夜にしか焚かないんですけどね。
炎を見ているだけで、気分的にも暖かくなりますが・・・・このところ、お客さんが少ないんで、どうせなら、こういう日に来てもらえばいいのに、って思ってしまいますね。
この前、山ちゃんが来てくれた時に、冷え切った足をストーブで暖めてもらえましたから、そういう時、焚いていて良かったと思います。
これからも、寒い日には薪ストーブを焚く事にしようと思ってますけど。
12月の忙しさに比べると、1月は本当~にヒマです。
楽天的な性格のオレも、ここしばらくはあまりのヒマさに、ウチの店はいつまで続くかな、なんて本気で考えたりもしていたのですが、そういう時に助けられるのは、やはりお客さんですね。
12月にパーティーで初めて来られたお客さんが、今度は個人的に予約を入れて下さったり、カウンターに来られたお客さんから、「本物ほど広く認められるには時間がかかるんだから、この店はこれからだよ」なんて言ってもらえると、すぐに立ち直りますからね。
立ち直りが早いのが、楽天的な人間の長所ですから・・・・
『本物』という言葉を聞いて思い出す事があります。
オレも出演させてもらった、劇団無尽舎のヴィデオ映画『大めいかい』の中で、オレの台詞に「本物は高くつく、という事だ」というのがありましたが、この台詞は、鋭く真実を突いていると思います。
でもね、その台詞を言ったオレが言うのもなんですが、ウチの店に関しては、それは当てはまらないと思いますね。
ウチほど本物を安く出している店は他に無いだろう、って自負してますから。
ここで、お知らせです。
モバイル会員の方にお送りした、新年のメールの特典は、来週の土曜日(23日)が期限です。
お早めにお出で下さい。
また、会員登録していただいた際の特典(焼き菓子)を、まだ受け取っておられない方は、お申し付け下さい。
さて、今回は久しぶりに、料理について書くことにしましょう。
先日、お客さんと、そんな話をしたので。
ウチの料理は基本的に、イタリアでやっているのと全く同じか、できる限り近い状態でお出しすることにしています。
古典的な北イタリア料理を出す事が基本の店ですから、当然なんですけどね。
古典的な料理というのは、長い年月を経て、本当に美味い料理だけが残されてきたわけですから、伝えられてきたレシピの通りにきっちりと作れば、美味い物ができるのが当然なんですね。
そういう料理は、絶妙なバランスの上で成り立っているので、ちょっと色気を出してアレンジしたりすると、一気にバランスが崩れて、訳の分からない料理になってしまうんですよ。
ウチでは基本的に飛騨牛を使わないのも、そういう理由からなんですが(その事についても、近いうちに書くことになると思いますが)、逆に、日本で手に入る食材を使う以上、変えなければならない部分がある事も事実ですね。
まぁ、その見極めが大切なんですが・・・・
ウチでは、今のところ、敢えてレシピを変えて作っている料理が2つあります。
今回は、その料理について書くことにします。
まずはコレ。
ジャガイモのニョッキ Gnocchi di patate です。
ウチでは、イモの味を引き立てるために、シンプルな『ピエモンテ風バターソース』でお出ししています。
ウチのニョッキを食べられたお客さんは、たいてい、こんなニョッキは初めて食べた、って言われます。
独自のレシピでやっているのですから、そう言われるのは当然なんですが、ウチのニョッキにハマる方が多い事は事実だと思います。
今でこそ、イタリア料理は広く普及しましたから、そんな事を訊かれる事はなくなりましたが、昔はよく、どうしてイタリア料理を選んだんですか、って訊かれましたねぇ。
そういう時、オレはいつも「ウチの家系は例外なくイモと麺類が好きだから」って答えてました。
冗談半分みたいに聞こえるかもしれないけれど、これは本当の事で、さらに言うなら「ご飯も麺類も硬いのが好きだから」という事になるんですけどね。
そんなイモ大好き人間のオレにとって、ニョッキって、ある意味で中途半端なパスタだったんですよ。
歯応えがあるわけでもないし、イモの味が濃厚なわけでもないし・・・・
もっとイモの味が強く出た方が美味い、ってオレは思っていたわけです。
で、自分なりにいろいろやってみた結果、イモの味をしっかりと出すには、本来のレシピより粉を少なくする事が一番いいと分かったのですよ。
本来のレシピでは、粉はイモの3分の1、ということになっていますが、ウチではその半分位でしょうかね。
まぁ、その時のイモの状態を見て加減するので、ハッキリと数字には出せませんけどね。
ただね、粉を少なくするという事は、当然、食べた時の食感が全く変わってしまいますね。
だから、食感と味のどちらを取るか、と考えた時、オレは味を取ったわけです。
でも、実際に食べてみると、その食感は悪くない・・・・むしろ、この食感を好む人の方が多いんじゃないかと思いましたね。
そう決まれば、その作り方で作るだけですね。
粉を少なくする、という事は、パスタ自体がかなり柔らかくなるわけですから、取り扱いが厄介になります。
形は作りにくいし、下手をすれば、すぐに潰れてしまうし、少しでも長くゆでると、解けて崩れてしまう。
でも、この味を出すにはこれしかない、と思って作れば、それが特別な問題になる程の事ではなかったですね。
ニョッキを作る場合、粘り気を出さないために、熱いうちに、あまりこねくり回さないように合わせるのですが、必然的に、どうしても粉や卵黄が混ざりきらない『部分的なムラ』ができてしまうものなんですよ。
粉を少なくすると、そういう部分的なムラが、さらに多くなってしまう事は避けられません。
粉や卵黄が混ざらなかったイモだけの部分は、ゆでると解けてしまい、バラバラに散ってしまいますから、そういう部分を見極めながらゆでるのが、一番難しいですね。
1人前に1個か2個、一部分崩れたものが混じるのは、避けようがない事ではありますけどね。
ニョッキには、粘り気の弱い『男爵』系のいもが向いているのですが、『インカの目覚め』という、粘り気の強い品種のイモを使ってニョッキを作った事があります。
インカの目覚めの粘り気が、ニョッキに向いていない事は分かっていても、その味と色に惹かれて、どうしても作ってみたくなったわけなんですよ。
で、粘り気を出さないようにしながら、さらに粉を少なくして作ってみたところ、本当に美味いニョッキになったのだけれど、やはり、ゆでるのが難しかったですね。
でも、今度また作ってみたいと思わされる味でした。
そうして作った、イモの味が濃厚なニョッキに合わせるソースは、ニョッキそのものの味を引き立てる、シンプルなソースがいいですね。
ですからウチでは『ピエモンテ風のバターソース』でお出ししています。
北イタリアで良く使われるソースに、ブッロ エ サルヴィア Burro e salvia、または、ブッロ ヴェルザート Burro versato、と呼ばれるものがあります。
ラヴィオリやニョッキのソースに使われる事が多いのですが、チーズ焼きにした肉料理の仕上げに使われる事もあります。
そのやり方は、ゆで上がったパスタにパルミジャーノ・レッジャーノをかけ、そこへセージ(イタリア語ではサルヴィア)を加えて焦がしたバターをかけるという、シンプルなソースです。
シンプルゆえにヴァリエーションも結構あり、その中のひとつが、パルミジャーノ・レッジャーノの上に少量のトマトソースを載せてから焦がしバターをかける『ピエモンテ風』なんですよ。
白いニョッキに、赤いトマトソース、緑のサルヴィアと、いろどりもいいですね。
ウチでは、自家栽培のセージを使いますが、冬の間だけは、どうしても乾燥もののセージに頼るしかないのは、仕方ないですね。
まぁ、一度ウチのニョッキを食べてみてください。
特に、スーパーなんかで売っている袋詰めのものなんかを食べて、あまりいいイメージを持ってない方には、ぜひ食べて頂きたいですね。
目からウロコが10枚くらい落ちる事は請合いますよ。
ニョッキの事だけで長くなりましたから、レシピを敢えて変えている、もうひとつの料理の事は、次回に書く事にします。
では、また。
Ciao. Arrivederci!!
2010年01月02日
いろいろあって・・・・11〜12月編 前編
Buon Anno. spockです。
旧年中は、ありがとうございました。
本年もよろしくお願いします。
歳をとるほど月日の経つのが早く感じるようになる、と聞いた事がありますが、その事を実感する歳になったのだと、改めて思わされます。
ここまで来たら、後は「いかにみずみずしく歳をとるか」を考えようと思いますね。
この12月は、ありがたい事に本当に忙しく、毎日ディナーの準備に追われていました。
ただ、予約は例年以上に入っていましたが、2~4人の予約が多く、大きいパーティーがないのは、今の世相を反映しているのでしょうかね。
のんびりと年賀状を印刷していた前年とは違い、年賀状には未だ全く手付かずの状態で新年を迎えてしまいました。(年賀状を下さった方、ごめんなさい!!)
去年の9月下旬から新しいパンフレットを配り始めたのですが、パンフレットを見た、といって予約を入れて下さるお客さんが多くなってきた事を実感するようになってきました。
A5版16ページのパンフレットは、いささかマニアックに過ぎたか、と思わないでもなかったのですが、自分の思いや考えを、しっかりと伝える事が大切だと、改めて思いますね。
また、初めてランチを食べに来られたお客さんが、ディナーの予約を入れて帰られる事も結構あり、本当にうれしいと言うか、ありがたい事だと思っています。
今年の7月で、オープンから丸5年になるわけですが、これからも、皆さんに喜んでもらえる料理を出し続けていけるよう、頑張ります。
5周年のパーティーは、盛大にやりたいですね。
さて今回は、今まで書き溜めていたものの中から、久しぶりに、『いろいろあって』の11~12月編、その前編です。
同級生のテノール歌手、水口 聡の本が出ました。
市民時報にも載ったので、知っておられる方も多いと思いますが、詳しい内容についてはこちらを見てもらうといいでしょう。
早速買って読んでみたところ、オペラ好きのオレにとっては、面白く、興味深い内容でしたが、ハッキリ言って・・・・あまり売れる本ではないでしょうね。
でも、音楽が好きな人、歌う事が好きな人にはお勧めです。
最小限の声の力で、最大限の響きを作り出すテクニックは、カラオケで喉を嗄らす事が多い人には、すごく参考になると思いますよ。
もっとも、そのテクニックが身に着くかどうかは、人によるでしょうけどね。
この本の中に、日本人の顔とイタリア人の顔に共通性があるという事が書かれているのですが、その事については、オレもこのブログに書いた事があります。
やっぱり、こういう事はあるんだと、改めて思いましたね。
水口の高山でのマネージャーを自認している西春彦先生が、もしも売れなかったら全部自分が引き取る約束で、この本をブックスアイオーさんに20冊置いてもらった、と言われていたのですが、オレが買いに行った時にはかなり残っていた本も、その後全て売れたようです。
ブックスアイオーの池田さん(高山室内合奏団のチェリスト)にお聞きしたところ、すでに追加注文を入れたとの事でしたが、その後も売り切れたようですから、意外と売れているのでしょう。
もっと売れるといいですね。
水口が高山へ帰ってきた時に、ウチで出版記念パーティーをやろう、という話も出てきたので、実現に向けて動きたいと思っています。
11月最後の日曜日、今年も『奥飛騨朴念そばの会』の収穫感謝祭がありました。
 今年は、夏の長雨のせいで、全国的にそばの生産量が激減したそうですが、種を蒔いた直後に水を被ると、全く育たなくなるのだそうです。
今年は、夏の長雨のせいで、全国的にそばの生産量が激減したそうですが、種を蒔いた直後に水を被ると、全く育たなくなるのだそうです。
この会が取り組んでいる、奥飛騨在来種と越前在来種を交配させた「飛越在来種」も、最悪の状況は免れたものの、収穫量がかなり少なかったため、初のお披露目となった今年は、一人一枚だけ振舞われる事になりました。
来年のために、種は必要なだけ確保してあるそうですから、来年を楽しみにしましょう。
今回は、第1回からずーっと参加していた母が、胃腸風邪のせいで行けなくなり、代わりに甥の大地を連れて行く事になりましたが、オレ以上に大食漢の大地がどれだけ食べるのか、見ものではあります。
 最初に、一人一枚ずつ出される『飛越在来種』のそばが出てきました。
最初に、一人一枚ずつ出される『飛越在来種』のそばが出てきました。
微かに緑がかった色と、すごく強い香りが、新しいそばである事を主張してきます。
そばを打つ場合、香りと味の兼合いは常に問題になる点だと思いますが、今回の飛越在来種の鮮烈な香りとのどごしに、オレは完全に参りましたね。
その後で出された、越前在来種のそばも、本当に味のある美味いそばなのだけれど、飛越在来種の後では分が悪く、微かにある種のエグ味を感じてしまうのです。
もちろん、それは好みの問題でもあるのでしょうけど、オレの好みは飛越在来種ですね。
今回は、飛越在来種のざると越前在来種のおろしそばを各1枚、越前在来種のざるを9枚の計11枚、それに、かき揚げを3個いただきました。
大地は8枚で止めて、オレが食べるのを、呆れながら見てましたけどね。
美味いそばを腹一杯食べられるなんて、本当に贅沢な時間ですね。
来年は、飛越在来種のそばを腹一杯食べられる事を期待しましょう。
NFLのシーズンも終盤ですが、開幕6連勝と絶好調だったデンヴァー・ブロンコスが、その後4連敗・・・・一時は3ゲーム差をつけていた、サンディエゴ・チャージャースに地区優勝をさらわれてしまいました。
開幕前の予想からすればウソのような6連勝は、あきらかに出来過ぎだったのですが、高山とデンヴァーの姉妹都市提携50周年を、スーパーボウル出場で祝えたら・・・・なんて、なまじ夢を見てしまっただけに、余計に切ないですね。
第12週と第13週では、4連敗がウソのような試合運びで勝ちましたが、間違いなく勝てるはずだったオークランド・レイダースに1点差で敗れ、さらにはフィラデルフィア・イーグルスに3点差で敗れ、これでプレイオフ出場は微妙な感じになってきました。
チーフスとの再戦に勝てるかどうかにかかっているのですが、なんとかプレイオフには行ってほしいと思いますね。
ウチのお客さんの中にも、アメフトファンはおられますが、一番よく話すのは、人力車夫の山ちゃんと、Takechi君こと、かみなか旅館のたけし君です。
Takechi君は、新婚旅行にプロボウルを観に行ったという、筋金入りのNFLファンで、ルールやプレイヤーのプロフィールについては、オレより遥かに詳しいですね。
山ちゃんは、いつもウチの前に人力車を停めて、ランチを食べてくれるのですが、お互いに元フットボーラーという事もあり、いつもアメフトを話題に盛り上がります。
高山とデンヴァーの姉妹都市提携50周年をきっかけに、アメフトでの交流ができないものだろうかという話も出てきましたが、実現できたら面白いと思うのですが・・・・
アメフトというスポーツ自体が、かなりマニアックなスポーツですから、話を始めると、だんだんディープな話になって行きますね。
この前、山ちゃんと話していた時、話題に上がったのが、ヴィデオ判定の話とアイシールドの話。
ちょうどその頃、サッカーの試合で、手を使ったのが問題になっていたのですが、サッカーファンに怒られる事を承知の上で、アメフト側の人間から言わせてもらうなら、サッカーって、完全に欠陥スポーツですよ。
審判の判定ひとつ見ても、いかに何でもアバウト過ぎる。
アメフトのチャレンジは、試合をフェアに進めるためにも、見ている人を楽しませるためにも、実に良く考えられていると思うけど、なんでサッカーではヴィデオ判定を導入しないのだろうか、という疑問を持ってしまうんですね。
以前、読んでいて思わず納得したのが、こんな文章でした。
『世界に広めるために、ルールが進化するのを止めてしまったのがサッカー。ルールを進化させるために、世界に広めるのを止めてしまったのがアメフト。』
確かに、サッカーにヴィデオ判定が導入されたら、先進国と発展途上国の間に、大きな隔たりができてしまう事は免れない、という理由もあるのでしょう。
でも、八百長の話なんかを聞くと、本当の理由は、ヴィデオ判定を取り入れると困る人が多いからなんじゃないかな、と勘ぐってしまうのは、オレだけじゃないと思いますね。
でもね、考えてみると、ヴィデオ判定を最初に取り入れたスポーツって、相撲なんですよね。
調べてみると、1969年5月から開始されたそうですから、かなり早い時期からやっていたんですね。
それを可能にしたのは、NHKの技術があったからなんでしょうけど、1956年から始まった『NHKイタリアオペラ』の公演では、TVの生中継に対訳字幕を入れるという、当時としては超ウルトラ級の技術を使ったくらいですから、日本の技術って、ホントにすごかったんですね。
『アイシールド21』で、広く知られる事になったアイシールド・・・・以前このブログにも書いた事がありますが、色つきのものが使えない現在の日本のルールでは、眼の保護のためだけに使われているわけだけれど、実際は、視線の向きから次のプレイを読まれる事を防ぐために使う事の方が重要だったわけで、そういう意味では、ヘンなルールだと思います。
この前店に来られた、やはり元フットボーラーのお客さんが、店に置いているヘルメットのアイシールドを見て、懐かしそうに同じ事を言っていましたからね。
当然アメリカ本国では、今でも色つきやミラーのものが使われているわけですから、日本では以前から、顔の見えないスポーツは流行らない、と言われている所為なんじゃないかと勘ぐってみたりしますね。
もっとも、相手のラインが全員、カラーとかミラーのアイシールドを着けていたら、それはそれで不気味ではありますけどね。
ただ、当然の事ながら、曇ったり泥が付いた場合、視界の妨げになるという欠点もあり(雨中の試合で、内側に泥ハネが付いたりしたら、もう大変です)、さらには、天候とカラーが合わないと、暗すぎて見えないという事態にもなりかねませんが、カラーのアイシールドには、それ以上の効果があると思いますね。
で、この前見つけた、ラダニアン・トムリンソン LaDainian Tomlinson(アイシールド21のモデルだと言われている)の出演したCMの動画・・・・実にバカバカしいけど、笑ってしまった!!
オレがマニアックな人間であるという事は、もう知れ渡っているようですが・・・・それだからというわけでもないのでしょうが、かなりマニアックなお客さんが来られる事がよくあります。
そういう場合、意気投合する事も結構あり、食事の時間より、食後に話をしている時間の方が長い事もよくありますね。
まぁね、マニアックに生きるには強い好奇心が必要ですから、当然、好奇心の強い者同士、話も次々に広がっていくわけですよ。
でも、そういうお客さんが、新しいお客さんを連れてきて下さる事が多いのも事実で、オレは本当にありがたい事だと思っています。
先日来て頂いた、あるお客さんも、その前に、友人に連れられてウチに来られた方なんですが、気に入って頂けたようで、別の友人を連れて来られたのです 。
で、例によって、食事の後に話をしていたのですが、以前持って帰られたウチのパンフレットを取り出して、面白かったので何回も読み返してみたんだが、変換ミスや打ち間違いが結構あるぞ、って言われたのですよ。
見てみると、間違いのところに、ピンクのマーカーでラインが引いてあったので、それを借りて、早速訂正しましたけどね。
でもね、そこまで読んでもらえるとうれしいですね。
 ウチのパンフレットを喜んで読んでくださる方って、やっぱりマニアックな方なんだろうと思います。
ウチのパンフレットを喜んで読んでくださる方って、やっぱりマニアックな方なんだろうと思います。
オレの思いや、知ってもらいたい事を、目一杯詰め込んだパンフレットですから、やはり共感してくださるのはマニアックな方なんでしょうね。
この『マニアック』という言葉、いわゆる『オタク』と同義語のように解釈される事もあり、ある種のネガティヴな・・・・と言うか、引きこもり的な暗いイメージを持たれる場合もあるようですが、実際は、もっとポディティヴな生き方だと思いますね。
オレは、マニアックな生き方って、すごく素敵な生き方だ、って思ってますからね。
そのお客さんと話している時に、その方の妹さんが、オレの高校時代の同級生だと言われたのですよ。
なんでも、その頃から変わった人だったと、その妹さんが言っていたとか・・・・
妹さんがパンフレットの写真を見て、すぐにオレだと分かったのだそうですが、30年以上も経っているというのに、よく分かったものだと感心しました。
ところがある日、『フェニり』に来てカウンターに着いた黒雷鳥さんが、ニコニコ(ニヤニヤ?)しながら携帯電話の画面に出した画像は・・・・何と、オレの高校時代の写真ではないの。
これって斐太高校の卒業アルバムの写真だけど、どうやって見つけたのかと思ったら、シェフの顔は全然変わっていないのですぐに見つかりました、って言うんですよ。
う~ん・・・・変わってないのかぁ・・・・
まぁね、この歳にもなると、シワも増えたし、骨張ってきたけど、基本的な形は、さほど変わっていないという事なんでしょうかね。
変わっていない、というのはいい事なんだろうと思います。
オレの最も敬愛する指揮者、ブルーノ ワルターが、ナチの手を逃れてアメリカへ亡命し、戦後ヨーロッパへ帰って演奏会を開いた時、皮肉屋で有名な指揮者のオットー クレンペラーが、進歩していないという意味で「全然変わってないじゃないか」と言うと、ワルターは若々しいという意味だと思って「ありがとう」と答えたというエピソードがありますが、オレは常に、ワルターのような考え方でいたいと思いますね。
でもねぇ・・・・若い頃の写真を見られるのって、素っ裸を見られるのと同じくらい恥かしいですよね。
先日、カウンターで、来年の年賀状をどうしようか、という話をしていたのですが、全くアイデアが浮かばないんですよね。
2009年は、この仕事を始めて30年という事もあって、前から暖めていた考えがあったところへ、ちょうど新しいカメラを買ったばかりの黒雷鳥さんが、気合を入れて撮ってくれたので、思っていた以上の年賀状ができたわけなんですが、2010年は特別な事もないしなぁ・・・・
ありきたりのものではつまらないですから、どうせ作るなら インパクトのあるものがいいですよね。
年賀状に限った事ではありませんが、わざわざ作る以上は、それを見てもらうために目立たなければならないし、そのためには強いインパクトがある事が重要ですね。
そういう意味で2009年の年賀状は、何人もの人から、インパクトがある、って言ってもらえましたから、成功だったと思います。
まぁね、あんな恥かしい思いをした価値があったというものです。
とまぁ、そんな事を話していたら、横で聞いていた優子さんが意外そうに言いました。
「へぇ~、あれ、恥かしいと思ってるんだ」・・・・
あのねぇ、オレだって一応、人並み以上の羞恥心は・・・・多分あるはずなんだけど・・・・
ただ、オレの場合は、人と同じ事をやらない、という信念が強すぎて、恥を超越してしまう部分がある事は認めますけどね。
人と同じことをやらない、というのは、逆に言えば、いかに人と違う事をやるか、という事になりますが、敢えて一人だけ違う事をやるのには、いろんな意味で、すごくパワーが必要です。
他の人と横並びである事が良しとされる日本人としては、失敗すれば、物笑いの種になってしまうわけですから、ひしひしと感じる無言のプレッシャーに対して、緊張感も感じますね。
だから時々、なんでこんな事をやっているんだろう、って思う事もあります。
もっと分かり易いやり方をすれば、ウチの店にもお客さんが増えるかもしれないし、トレンドに沿った格好をしていれば、人の目を気にする事もないでしょう。
でもね、解る人にしか解ってもらえなくても、別にかまわないと思うんですよね。
一切手抜きなしで料理を出すためには予約制にするしかない、と確信して、こんな流行らない店をやっているわけだし、世間ではダボパンの腰穿きが流行っていても、タイトなパンツを目一杯たくし上げて穿くのがオレには絶対似合う、と思うわけですよ。
かなりきわどい状況でやっているのですから、常に緊張感を持って生きているわけですが、それを『信念』と言うのは間違っていないと思います。
結局のところ、オレはそういう緊張感を感じながら生きるのが好きなんでしょうね。
時々、ふと思い出す歌があります。
1966年に、水前寺清子が歌った『いっぽんどっこの唄』
ぼろは着てても こころの錦
どんな花よりきれいだぜ
若いときゃ 二度とない
どんとやれ 男なら
人のやれない ことをやれ
何はなくても 根性だけは
俺の自慢のひとつだぜ
春が来りゃ 夢の木に
花が咲く 男なら
行くぜこの道 どこまでも
作詞:星野哲郎
なんか、オレのための応援歌みたいな気がするんですよね。
『若い時』は過ぎてしまいましたけど、死ぬまで変わる事なく、こんな生き方をするんだろうな、って思います。
いくつになっても「ひとの~やれな~い ことを~やれ~」とか「いくぜ~このみ~ち どこま~でも~」って歌いながら生きるのって、幸せなんじゃないかなぁ、って思うんですけどね。
まぁ、これからもこんな調子でやっていくんでしょうねぇ。
本年もLA FENICEをよろしくお願いします。
ところで、年賀状はどうしよう・・・・
では、また。
Ciao. Arrivederci!!
旧年中は、ありがとうございました。
本年もよろしくお願いします。
歳をとるほど月日の経つのが早く感じるようになる、と聞いた事がありますが、その事を実感する歳になったのだと、改めて思わされます。
ここまで来たら、後は「いかにみずみずしく歳をとるか」を考えようと思いますね。
この12月は、ありがたい事に本当に忙しく、毎日ディナーの準備に追われていました。
ただ、予約は例年以上に入っていましたが、2~4人の予約が多く、大きいパーティーがないのは、今の世相を反映しているのでしょうかね。
のんびりと年賀状を印刷していた前年とは違い、年賀状には未だ全く手付かずの状態で新年を迎えてしまいました。(年賀状を下さった方、ごめんなさい!!)
去年の9月下旬から新しいパンフレットを配り始めたのですが、パンフレットを見た、といって予約を入れて下さるお客さんが多くなってきた事を実感するようになってきました。
A5版16ページのパンフレットは、いささかマニアックに過ぎたか、と思わないでもなかったのですが、自分の思いや考えを、しっかりと伝える事が大切だと、改めて思いますね。
また、初めてランチを食べに来られたお客さんが、ディナーの予約を入れて帰られる事も結構あり、本当にうれしいと言うか、ありがたい事だと思っています。
今年の7月で、オープンから丸5年になるわけですが、これからも、皆さんに喜んでもらえる料理を出し続けていけるよう、頑張ります。
5周年のパーティーは、盛大にやりたいですね。
さて今回は、今まで書き溜めていたものの中から、久しぶりに、『いろいろあって』の11~12月編、その前編です。
同級生のテノール歌手、水口 聡の本が出ました。
市民時報にも載ったので、知っておられる方も多いと思いますが、詳しい内容についてはこちらを見てもらうといいでしょう。
早速買って読んでみたところ、オペラ好きのオレにとっては、面白く、興味深い内容でしたが、ハッキリ言って・・・・あまり売れる本ではないでしょうね。
でも、音楽が好きな人、歌う事が好きな人にはお勧めです。
最小限の声の力で、最大限の響きを作り出すテクニックは、カラオケで喉を嗄らす事が多い人には、すごく参考になると思いますよ。
もっとも、そのテクニックが身に着くかどうかは、人によるでしょうけどね。
この本の中に、日本人の顔とイタリア人の顔に共通性があるという事が書かれているのですが、その事については、オレもこのブログに書いた事があります。
やっぱり、こういう事はあるんだと、改めて思いましたね。
水口の高山でのマネージャーを自認している西春彦先生が、もしも売れなかったら全部自分が引き取る約束で、この本をブックスアイオーさんに20冊置いてもらった、と言われていたのですが、オレが買いに行った時にはかなり残っていた本も、その後全て売れたようです。
ブックスアイオーの池田さん(高山室内合奏団のチェリスト)にお聞きしたところ、すでに追加注文を入れたとの事でしたが、その後も売り切れたようですから、意外と売れているのでしょう。
もっと売れるといいですね。
水口が高山へ帰ってきた時に、ウチで出版記念パーティーをやろう、という話も出てきたので、実現に向けて動きたいと思っています。
11月最後の日曜日、今年も『奥飛騨朴念そばの会』の収穫感謝祭がありました。
この会が取り組んでいる、奥飛騨在来種と越前在来種を交配させた「飛越在来種」も、最悪の状況は免れたものの、収穫量がかなり少なかったため、初のお披露目となった今年は、一人一枚だけ振舞われる事になりました。
来年のために、種は必要なだけ確保してあるそうですから、来年を楽しみにしましょう。
今回は、第1回からずーっと参加していた母が、胃腸風邪のせいで行けなくなり、代わりに甥の大地を連れて行く事になりましたが、オレ以上に大食漢の大地がどれだけ食べるのか、見ものではあります。
微かに緑がかった色と、すごく強い香りが、新しいそばである事を主張してきます。
そばを打つ場合、香りと味の兼合いは常に問題になる点だと思いますが、今回の飛越在来種の鮮烈な香りとのどごしに、オレは完全に参りましたね。
その後で出された、越前在来種のそばも、本当に味のある美味いそばなのだけれど、飛越在来種の後では分が悪く、微かにある種のエグ味を感じてしまうのです。
もちろん、それは好みの問題でもあるのでしょうけど、オレの好みは飛越在来種ですね。
今回は、飛越在来種のざると越前在来種のおろしそばを各1枚、越前在来種のざるを9枚の計11枚、それに、かき揚げを3個いただきました。
大地は8枚で止めて、オレが食べるのを、呆れながら見てましたけどね。
美味いそばを腹一杯食べられるなんて、本当に贅沢な時間ですね。
来年は、飛越在来種のそばを腹一杯食べられる事を期待しましょう。
NFLのシーズンも終盤ですが、開幕6連勝と絶好調だったデンヴァー・ブロンコスが、その後4連敗・・・・一時は3ゲーム差をつけていた、サンディエゴ・チャージャースに地区優勝をさらわれてしまいました。
開幕前の予想からすればウソのような6連勝は、あきらかに出来過ぎだったのですが、高山とデンヴァーの姉妹都市提携50周年を、スーパーボウル出場で祝えたら・・・・なんて、なまじ夢を見てしまっただけに、余計に切ないですね。
第12週と第13週では、4連敗がウソのような試合運びで勝ちましたが、間違いなく勝てるはずだったオークランド・レイダースに1点差で敗れ、さらにはフィラデルフィア・イーグルスに3点差で敗れ、これでプレイオフ出場は微妙な感じになってきました。
チーフスとの再戦に勝てるかどうかにかかっているのですが、なんとかプレイオフには行ってほしいと思いますね。
ウチのお客さんの中にも、アメフトファンはおられますが、一番よく話すのは、人力車夫の山ちゃんと、Takechi君こと、かみなか旅館のたけし君です。
Takechi君は、新婚旅行にプロボウルを観に行ったという、筋金入りのNFLファンで、ルールやプレイヤーのプロフィールについては、オレより遥かに詳しいですね。
山ちゃんは、いつもウチの前に人力車を停めて、ランチを食べてくれるのですが、お互いに元フットボーラーという事もあり、いつもアメフトを話題に盛り上がります。
高山とデンヴァーの姉妹都市提携50周年をきっかけに、アメフトでの交流ができないものだろうかという話も出てきましたが、実現できたら面白いと思うのですが・・・・
アメフトというスポーツ自体が、かなりマニアックなスポーツですから、話を始めると、だんだんディープな話になって行きますね。
この前、山ちゃんと話していた時、話題に上がったのが、ヴィデオ判定の話とアイシールドの話。
ちょうどその頃、サッカーの試合で、手を使ったのが問題になっていたのですが、サッカーファンに怒られる事を承知の上で、アメフト側の人間から言わせてもらうなら、サッカーって、完全に欠陥スポーツですよ。
審判の判定ひとつ見ても、いかに何でもアバウト過ぎる。
アメフトのチャレンジは、試合をフェアに進めるためにも、見ている人を楽しませるためにも、実に良く考えられていると思うけど、なんでサッカーではヴィデオ判定を導入しないのだろうか、という疑問を持ってしまうんですね。
以前、読んでいて思わず納得したのが、こんな文章でした。
『世界に広めるために、ルールが進化するのを止めてしまったのがサッカー。ルールを進化させるために、世界に広めるのを止めてしまったのがアメフト。』
確かに、サッカーにヴィデオ判定が導入されたら、先進国と発展途上国の間に、大きな隔たりができてしまう事は免れない、という理由もあるのでしょう。
でも、八百長の話なんかを聞くと、本当の理由は、ヴィデオ判定を取り入れると困る人が多いからなんじゃないかな、と勘ぐってしまうのは、オレだけじゃないと思いますね。
でもね、考えてみると、ヴィデオ判定を最初に取り入れたスポーツって、相撲なんですよね。
調べてみると、1969年5月から開始されたそうですから、かなり早い時期からやっていたんですね。
それを可能にしたのは、NHKの技術があったからなんでしょうけど、1956年から始まった『NHKイタリアオペラ』の公演では、TVの生中継に対訳字幕を入れるという、当時としては超ウルトラ級の技術を使ったくらいですから、日本の技術って、ホントにすごかったんですね。
『アイシールド21』で、広く知られる事になったアイシールド・・・・以前このブログにも書いた事がありますが、色つきのものが使えない現在の日本のルールでは、眼の保護のためだけに使われているわけだけれど、実際は、視線の向きから次のプレイを読まれる事を防ぐために使う事の方が重要だったわけで、そういう意味では、ヘンなルールだと思います。
この前店に来られた、やはり元フットボーラーのお客さんが、店に置いているヘルメットのアイシールドを見て、懐かしそうに同じ事を言っていましたからね。
当然アメリカ本国では、今でも色つきやミラーのものが使われているわけですから、日本では以前から、顔の見えないスポーツは流行らない、と言われている所為なんじゃないかと勘ぐってみたりしますね。
もっとも、相手のラインが全員、カラーとかミラーのアイシールドを着けていたら、それはそれで不気味ではありますけどね。
ただ、当然の事ながら、曇ったり泥が付いた場合、視界の妨げになるという欠点もあり(雨中の試合で、内側に泥ハネが付いたりしたら、もう大変です)、さらには、天候とカラーが合わないと、暗すぎて見えないという事態にもなりかねませんが、カラーのアイシールドには、それ以上の効果があると思いますね。
で、この前見つけた、ラダニアン・トムリンソン LaDainian Tomlinson(アイシールド21のモデルだと言われている)の出演したCMの動画・・・・実にバカバカしいけど、笑ってしまった!!
オレがマニアックな人間であるという事は、もう知れ渡っているようですが・・・・それだからというわけでもないのでしょうが、かなりマニアックなお客さんが来られる事がよくあります。
そういう場合、意気投合する事も結構あり、食事の時間より、食後に話をしている時間の方が長い事もよくありますね。
まぁね、マニアックに生きるには強い好奇心が必要ですから、当然、好奇心の強い者同士、話も次々に広がっていくわけですよ。
でも、そういうお客さんが、新しいお客さんを連れてきて下さる事が多いのも事実で、オレは本当にありがたい事だと思っています。
先日来て頂いた、あるお客さんも、その前に、友人に連れられてウチに来られた方なんですが、気に入って頂けたようで、別の友人を連れて来られたのです 。
で、例によって、食事の後に話をしていたのですが、以前持って帰られたウチのパンフレットを取り出して、面白かったので何回も読み返してみたんだが、変換ミスや打ち間違いが結構あるぞ、って言われたのですよ。
見てみると、間違いのところに、ピンクのマーカーでラインが引いてあったので、それを借りて、早速訂正しましたけどね。
でもね、そこまで読んでもらえるとうれしいですね。
オレの思いや、知ってもらいたい事を、目一杯詰め込んだパンフレットですから、やはり共感してくださるのはマニアックな方なんでしょうね。
この『マニアック』という言葉、いわゆる『オタク』と同義語のように解釈される事もあり、ある種のネガティヴな・・・・と言うか、引きこもり的な暗いイメージを持たれる場合もあるようですが、実際は、もっとポディティヴな生き方だと思いますね。
オレは、マニアックな生き方って、すごく素敵な生き方だ、って思ってますからね。
そのお客さんと話している時に、その方の妹さんが、オレの高校時代の同級生だと言われたのですよ。
なんでも、その頃から変わった人だったと、その妹さんが言っていたとか・・・・
妹さんがパンフレットの写真を見て、すぐにオレだと分かったのだそうですが、30年以上も経っているというのに、よく分かったものだと感心しました。
ところがある日、『フェニり』に来てカウンターに着いた黒雷鳥さんが、ニコニコ(ニヤニヤ?)しながら携帯電話の画面に出した画像は・・・・何と、オレの高校時代の写真ではないの。
これって斐太高校の卒業アルバムの写真だけど、どうやって見つけたのかと思ったら、シェフの顔は全然変わっていないのですぐに見つかりました、って言うんですよ。
う~ん・・・・変わってないのかぁ・・・・
まぁね、この歳にもなると、シワも増えたし、骨張ってきたけど、基本的な形は、さほど変わっていないという事なんでしょうかね。
変わっていない、というのはいい事なんだろうと思います。
オレの最も敬愛する指揮者、ブルーノ ワルターが、ナチの手を逃れてアメリカへ亡命し、戦後ヨーロッパへ帰って演奏会を開いた時、皮肉屋で有名な指揮者のオットー クレンペラーが、進歩していないという意味で「全然変わってないじゃないか」と言うと、ワルターは若々しいという意味だと思って「ありがとう」と答えたというエピソードがありますが、オレは常に、ワルターのような考え方でいたいと思いますね。
でもねぇ・・・・若い頃の写真を見られるのって、素っ裸を見られるのと同じくらい恥かしいですよね。
先日、カウンターで、来年の年賀状をどうしようか、という話をしていたのですが、全くアイデアが浮かばないんですよね。
2009年は、この仕事を始めて30年という事もあって、前から暖めていた考えがあったところへ、ちょうど新しいカメラを買ったばかりの黒雷鳥さんが、気合を入れて撮ってくれたので、思っていた以上の年賀状ができたわけなんですが、2010年は特別な事もないしなぁ・・・・
ありきたりのものではつまらないですから、どうせ作るなら インパクトのあるものがいいですよね。
年賀状に限った事ではありませんが、わざわざ作る以上は、それを見てもらうために目立たなければならないし、そのためには強いインパクトがある事が重要ですね。
そういう意味で2009年の年賀状は、何人もの人から、インパクトがある、って言ってもらえましたから、成功だったと思います。
まぁね、あんな恥かしい思いをした価値があったというものです。
とまぁ、そんな事を話していたら、横で聞いていた優子さんが意外そうに言いました。
「へぇ~、あれ、恥かしいと思ってるんだ」・・・・
あのねぇ、オレだって一応、人並み以上の羞恥心は・・・・多分あるはずなんだけど・・・・
ただ、オレの場合は、人と同じ事をやらない、という信念が強すぎて、恥を超越してしまう部分がある事は認めますけどね。
人と同じことをやらない、というのは、逆に言えば、いかに人と違う事をやるか、という事になりますが、敢えて一人だけ違う事をやるのには、いろんな意味で、すごくパワーが必要です。
他の人と横並びである事が良しとされる日本人としては、失敗すれば、物笑いの種になってしまうわけですから、ひしひしと感じる無言のプレッシャーに対して、緊張感も感じますね。
だから時々、なんでこんな事をやっているんだろう、って思う事もあります。
もっと分かり易いやり方をすれば、ウチの店にもお客さんが増えるかもしれないし、トレンドに沿った格好をしていれば、人の目を気にする事もないでしょう。
でもね、解る人にしか解ってもらえなくても、別にかまわないと思うんですよね。
一切手抜きなしで料理を出すためには予約制にするしかない、と確信して、こんな流行らない店をやっているわけだし、世間ではダボパンの腰穿きが流行っていても、タイトなパンツを目一杯たくし上げて穿くのがオレには絶対似合う、と思うわけですよ。
かなりきわどい状況でやっているのですから、常に緊張感を持って生きているわけですが、それを『信念』と言うのは間違っていないと思います。
結局のところ、オレはそういう緊張感を感じながら生きるのが好きなんでしょうね。
時々、ふと思い出す歌があります。
1966年に、水前寺清子が歌った『いっぽんどっこの唄』
ぼろは着てても こころの錦
どんな花よりきれいだぜ
若いときゃ 二度とない
どんとやれ 男なら
人のやれない ことをやれ
何はなくても 根性だけは
俺の自慢のひとつだぜ
春が来りゃ 夢の木に
花が咲く 男なら
行くぜこの道 どこまでも
作詞:星野哲郎
なんか、オレのための応援歌みたいな気がするんですよね。
『若い時』は過ぎてしまいましたけど、死ぬまで変わる事なく、こんな生き方をするんだろうな、って思います。
いくつになっても「ひとの~やれな~い ことを~やれ~」とか「いくぜ~このみ~ち どこま~でも~」って歌いながら生きるのって、幸せなんじゃないかなぁ、って思うんですけどね。
まぁ、これからもこんな調子でやっていくんでしょうねぇ。
本年もLA FENICEをよろしくお願いします。
ところで、年賀状はどうしよう・・・・
では、また。
Ciao. Arrivederci!!