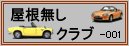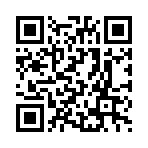スポンサーリンク
この広告は一定期間(1ヶ月以上)更新のないブログに表示されます。
ブログ記事の情報が古い場合がありますのでご注意下さい。
(ブログオーナーが新しい記事を投稿すると非表示になります。)
ブログ記事の情報が古い場合がありますのでご注意下さい。
(ブログオーナーが新しい記事を投稿すると非表示になります。)
2017年12月09日
いろいろあって 2017年初夏~秋 後編
Ciao. spockです。
天気の週間予報に、雪のマークが並んでいますが、いよいよ冬らしくなってきましたねぇ。
今年は夏が短かった分、冬が長くなるんじゃないかと心配している今日この頃ですが、相手が自然ですから、どう足掻いたところで仕方がないんですけどね。
でもまぁ、雪があんまり降らなければいいなぁ、と思っているのは、オレだけではないんでしょうけど。
この前、東京の某ホテルのコンシェルジュから、団体のお客さんのランチコースの問合せがあって、20名でと言われたのだけれど、ウチでは16名までしか無理なのでお断りしたのだが、翌日、どうしてもそちらでとお客さんが言われるので16名での予約をお願いします、という電話が改めて入ったので、お受けすることになった。
その日は同業者である妹に手伝ってもらう事にして準備を進めていたのだが、前日の電話で、そのお客さんが海外からの方だと分かり、不思議に思って訊いてみた・・・・「ウチの事を、どうやって見つけられたのですか?」
すると、その答えが、「お客様の方から指定がありました。」
ウチのウェブサイトは日本語にしか対応していないのに、外国の人がどうやって調べたのだろうと不思議に思ったのだが、香港から来られたそのお客さんに訊いてみたところ、少し日本語のできる人がインターネットで調べてウチを見つけたとの事。
ウチに予約を入れて下さる方の中で、高山(及び飛騨地区)以外の方の比率は、ここ数年上がり続けて、今では8割を超えているんだけれど、その中に海外の方も入ってくるようになったとはねぇ。
いつも名古屋から来て下さるお客さん達から、「この店の真価は高山では理解されないんだから、早く名古屋へ出て来いよ。」って、以前から結構真剣に言われているんだけれど、これ以上高山の人の比率が下がるようであれば、考えなければならないのかもしれないなぁ。
ここでひとつお知らせです。
この夏にも行われた『TAKAYAMA DE KANPAI』の第2回が、現在行われています。
ウチは、参加店の中でも一番毛色が変わった店であるという自覚があったので、誰も投稿してくれないんじゃないかと心配していたのだけれど、投稿して下さった方がおられたので、今回も参加する事にしました。
今回は、さらに特典が増えているので、ぜひ写真を撮って投稿してみて下さい。
詳しい事は、こちらで。
さて、だいぶ間が空きましたが「いろいろあって 2017年初夏~秋 前編」に続く、後編です。
前編と同様に、Facebook にアップしたものを元に書いていますが、初出の文もあるので、Facebook で既読の方も読んでみて下さい。
おかげ様で、高山室内合奏団 第14回定期演奏会は、無事終了する事ができました。
ありがとうございました。

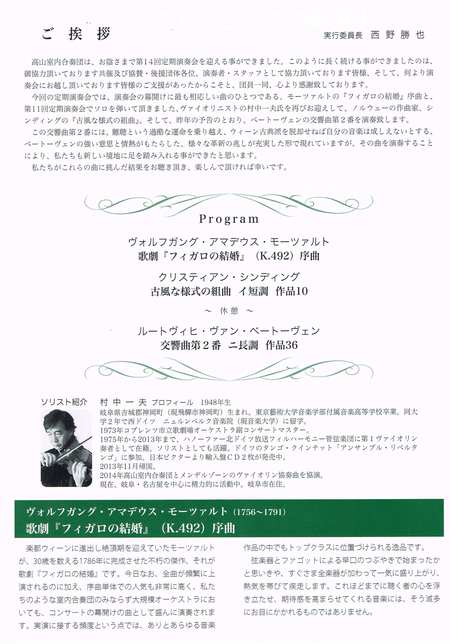
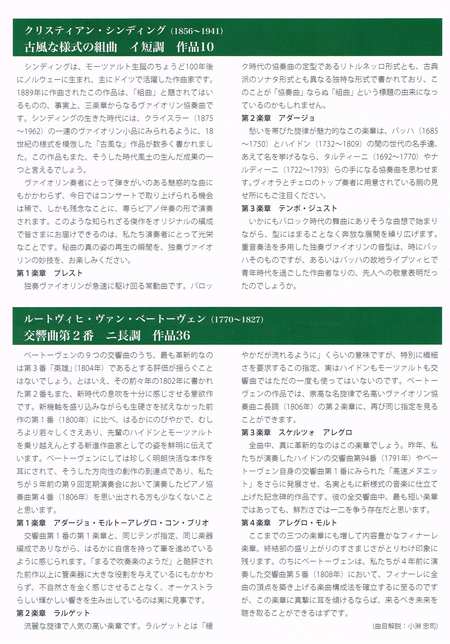

予想していたより来場者数が伸びなかったのですが、アンケート用紙の回収率がかつてないほど高く、また、その多くがかなり踏み込んだ内容まで書かれていて、読んだ団員一同、本当にありがたく思いました。
今年は、演奏会に参加する団員の数が少なく、演奏面でも、運営面でも、財政面でも、かなり苦しい演奏会になり、また去年と同様に、指揮者が演奏会間近に入院するという、かなり綱渡り的な状況でしたが、多くの方々から協力を頂いた事で、なんとか乗り切る事ができました。
協力頂いた方々には、本当に感謝しております。
個人的にも、仕事が忙しくて練習に行けない事が多かったし、実行委員の仕事も遅れがちで、プログラムの挨拶文を書いて印刷所に送ったのが、本番の5日前という慌しさでした。
今回は、その練習中に、「選曲をミスったのではないか」という意見が出るほど難しい曲を選んだため、団員それぞれに、かなり苦労したと思いますが、その分、演奏会が終わった今、よくやったよなぁ、という充実感は、例年より強く感じますね。
指揮者に質問中

団員間での打ち合わせ

毎年参加してくれるエキストラの人達



指揮者、ステージマネージャー、コンサートマスター

リハーサル中



楽譜への書き込み

アンコール曲を練習する余裕がなかったため、今回は、アンコール無しになりましたが、その事は、お客さんにも解ってもらえたのではないかと思います。
3ヵ月後には、クリスマス ファミリーコンサートが控えているので、近々、その練習が始まります。
来年は、第15回という事で、特別な演奏会にしたいという気持ちはありますが、合奏団の転換期に来ている事も確かで、みんなで話し合って最良の道を探しながら、次のステップへ進んで行きたいと思っています。
今年は、夏らしい気候になりきらないうちに、秋になってしまいましたねぇ。
夏らしい事を何もしないうちに夏が終わってしまって、なんか悔しい!!
以前ここに、「夏のプールシーズンまでに身体を引き締め直そうって思っている」って書いたのだけれど、身体の方はそれなりに締まったものの、ヘンな天気のうえに、仕事や演奏会の練習で忙しくて、結局、プールには1回しか行けなかった。
1年ぶりの市民プールで泳いでみたら、全然思うように泳げない・・・・やっぱり、1年も間が空くとだめですねぇ。
で、その1回だけのプールでも身体は焼けたわけだけれど、前と後ろの焼け方が違っていて変・・・・もう1度プールへ焼きに行きたかったけど、行けそうになかったので、天気が良い日に、ウチの3階のバルコニーに寝っ転がって焼いてみたら、結構きれいに焼けたみたい。
その時に撮った画像を、以前書いた事に対する「まだ十分ではないけど一応ここまでは身体を引き締めたよ」、という結果報告としてアップするので、「そんなもの見たくないわ」という人はスルーしてね。

実のところ、この画像を Facebook にアップするのには、躊躇がなくもなかったのだけれど、普通じゃない事をやるのが身上のオレが躊躇しちゃダメだな、という気持ちと、iPad に入れていたこの画像を見た女性のお客さんが、「うわー、きれい」って言ってくれた事で、アップに踏み切ったわけ。
まぁ、無視されるか非難されるかだろうな、と思っていたのに、結果として、個人と店の両方で30人から「いいね」をもらえたのは意外だったのだが、こうして晒してしまった以上、これより体形を崩すことはできないし、来年はさらに身体を引き締めようと思っている。
さて、この画像で穿いているのは、以前にも書いた MIZUNO の RQ-632 のウォーターポロ(通称ポロパン)で、赤と白の地に黄色のステッチが入っている。
実のところ、オレは若い頃から、赤と紫のものを身に着けた事が殆ど無かった。
何となく好みに合わなかったし、以前、自分に合う波長の色を調べた時も、赤と紫は全然合わなかった事もあって避けていたのだけれど、ここ2年ほどで「赤もいいよなぁ」って思うようになった。
これって、還暦を意識する歳になったからなのかなぁ。
打ち上げ後、7年という長い時間をかけて土星に到達し、その後、当初の計画より9年も長い13年間続けられた周回探査では、50万枚近い画像と、635GBにおよぶ貴重なデータを送り続け、最後は土星に突入して燃え尽きた、土星探査機『カッシーニ』
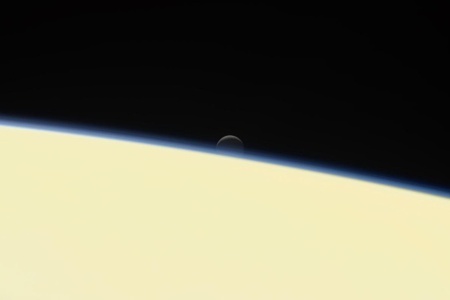
最後に送られてきた画像を見ながら、その健気さに、目がうるうるしてしまった。
http://natgeo.nikkeibp.co.jp/atcl/news/17/092000358/
20年前といえば、Power Macintosh がG3になる前であり、Windows95 の時代だったわけだけれど、そんな時代の、今と比べれば遥かに遅く、容量も小さい機械を使って、必死にデータを送り続けた カッシーニ。
カッシーニから切り離されてタイタンに着陸した、惑星探査機『ホイヘンス プローブ』と共に「健気」という言葉しか思いつかない。
そういえば7年前、3年間も行方不明になりながら、補助エンジンを使って地球に帰って来た『はやぶさ』の時も、最後は燃え尽きてしまって、その映像を見ながら、目がうるうるしたものだが、(その時に書いたブログ http://lafenice.hida-ch.com/e209922.html を読み返すと、些か気恥ずかしく思うほど感動していたみたい)、今回のカッシーニは、全く見えないところで、大気の組成データを予定より30秒も長く送信しながら消滅していった事を思うと、はやぶさの時以上にうるうるしてしまう。(子供の頃から感傷的だったのでね)
34億ドルと、20年の歳月を費やしたカッシーニのミッションも終わり、現在、木星を探査している『ジュノー』も、来年には木星に突入して消滅してしまう。
寂しくなるなぁ・・・・
9月25日って、オレにとっては、ある意味、記念日みたいな日。
17年前のこの日に、母方の祖母が100歳を目前に亡くなった事もあって、余計に忘れられない日になったのだが、1979年のこの日が、生まれて初めてオペラを観に行った日だった。
コヴェントガーデン 王立歌劇場の引越し公演で、演目はモーツァルトの『魔笛』、会場は大阪中之島のフェスティバルホール。
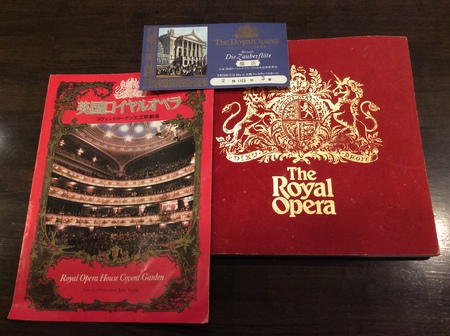
この時、隣の席に座っていたのは、当時付き合っていた1歳年下のえっちゃん・・・・音大の声楽科に通いながら店のレジのアルバイトに来ていた、すごくきれいな子で、狙っていた先輩も多かったのだけれど、音楽の、それもオペラの話ができるのはオレだけだったから、それをきっかけに付き合い始めたわけ。
魔笛を観に行こう、って誘ってパンフレットを見せた時、一番安い席なら行ける、って言われたのだけれど、当然安い席は売り切れているはずなので、「オレがひとりで高い席で観るより2人で一緒に観るほうが絶対に楽しいから、差額はオレが出す」と言って、OKをもらった。
まぁ、19歳のオレにしてみれば、精一杯の背伸びだったのかも。
で、ティケットを買いにいったら、当然、高い席しか残っていなくて、あちこち探してみたけど買える値段の席はなく、ふと思いついて、予約を受け付けていた事務所に電話してみたら、なんとか買えるB席が2枚だけ残っているというので、昼の休憩時間に大阪まで買いに行ってきた。(昼メシも食べずに飛び出していって、帰ってきてからティケットを買ってきたと言ったら、みんな呆れていたけど)

今でこそ『魔笛』は、『バラの騎士』『ラ ボエーム』『イル トロヴァトーレ』と並んで最も好きなオペラのひとつなんだけれど、当時は大雑把なあらすじくらいしか知らなかったので、対訳書を買ってきて大体のやりとりを頭に叩き込み、当日に備えた。
調理師学校の入学式と卒業式がフェスティバルホールで行われたので、ホールの事や行き方は分かっていたけれど、オペラを観に行くなんてのは初めての事なので、どんな格好で行ったらいいのかも分からなかったのだけれど、結局は卒業式の時に着たスーツで行った・・・・と思う。
自分の事はあまり憶えていないのだが、えっちゃんが白い小さな模様の入った紺のワンピースを着ていた事や、ロングヘヤーを編みこんでいて、メガネがかけれないって言っていた事をハッキリと憶えている。
で、肝心の演奏については、初めてのオペラだった事もあって、ハッキリとは憶えていない。
ただ、パパゲーノを歌ったトーマス アレンが芸達者で、随所で笑わせてくれた。
特に憶えているのは、3人の侍女が殺した大蛇に気がついた時の驚き方・・・・あんな自然な驚き方は、実演、VTR共に、その後に観たどの上演でも、お目にかかった事がない。
後に手に入れた、バイエルン国立歌劇場での公演のレーザーディスクで、この時と全く同じエファーディング演出の舞台を観る事ができて、あの時の感動を思い出すことができるのだが、ただ、誰もが『魔笛』の中で一番楽しみにしているであろう『パパパの2重唱』を、タミーノとパミーナの試練の場の前に移動させた事だけは、許し難い暴挙だと思う。
で、この日の公演の最後、カーテンコールが終わったところで、オーケストラが Happy birthday to you. を演奏し始めた。
この日は、指揮者のコーリン デイヴィスの誕生日だったのだが、そんな事も、この日を忘れ難いものにしているのだろうな。
公演が終わった後、北新地まで歩いて、当時、イタリア料理の人気店だった『ジジ』で食事をして、神戸に帰ってきたのだけれど、まぁ、これがオレの10代最後の大イヴェントだった事は間違いない。
その後もいろいろあったけど、付き合いは続き、オレが東京へ移ってからは、えっちゃんが仕事で東京へ来た時に、朝、仕事の前に彼女の泊まっているホテルに行って、一緒に朝食を食べたりもしていたけれど、神戸の地震の後に電話で話したのを最後に、音信不通。
おそらく彼女も、オレと同様に結婚はしていないと思う。
まぁ、お互い、そういう生き方の人間なんだろうな。
いつか会う事があるなら、お互いにいい歳の取り方ができたな、って言えるようになっていたい。
10月10日の昼、ランチコースを予約して来られた方と食後に話をした時に、「祭だという事を知らずに来たのだけれど、今から見に行くのならどこがいいですか?」と訊かれた。
2時近くになっていたので、八幡神社へ行っても見るものはないだろうと判断し、「3時から下一通りで布袋台がからくりをやるので、今から行けばいい場所で見る事ができると思いますよ」と答えると、そういうのに興味があるので行くとの事。
下一之町への行き方を説明したところで、そのお客さんから名刺を渡され、挨拶された。
郡上で店をやっておられる同業者の方で、お客さんから「高山のラ フェニーチェ」という名前をよく聞くので、以前からすごく気になっていたんです、と言われた。
まぁ、同業者にそう言われるのは、うれしいものですね。
で、そのお客さんをお見送りした後、オレも下一之町へ布袋台のからくりを見に行った。
毎年、布袋台を屋台蔵に入れる前に、下一通りでからくりを披露するのだが、人でごった返す八幡神社の境内よりも、ずっと落ち着いて観る事ができるので、毎年観に行く事にしているわけです。
ランチの営業を終えて、昼メシをかっ込んで、下一通りまで走って行ったら、2時50分・・・・開演まで10分。
もう、布袋台の前には、びっしりと人だかりができている。
屋台の横、からくりがぎりぎり見えるところに陣取って、反対側を見ると、三味線や太鼓を構えた人達が並んで座っている・・・・今年の伴奏は生演奏だったのだと気がついた。
伴奏を生でやるのは何年ぶりかな。
小さい子供が屋台の上段に立ち、開演を告げると、からくりが始まった。
生伴奏の影響もあったのか、実にスムースに進んでいく・・・・今までに見た中でも、ベスト3に入るくらいの出来だったのではないかな。
唐子が布袋さんの肩と手に乗る時、唐子の首を動かすための「噛み合わせ」が、ほぼ一発でピッタリ嵌ったのが見ていて分かったくらいだから。
数年前にからくりの練習を見せてもらった時、当時の『綾元』(リーダー)の鍋島勝雄さんに話を聞かせてもらったのだが、その時に、「からくりを見に来る人の中には、失敗する事を期待している人もいる筈だから、上手くいっている時でも、わざと動かなくなったように見せる事もある。」って言われた事をハッキリと憶えている。
でも、今回のからくりは、そんな事を気にするまでもないほどに上手く行ったんじゃないかと思う。
そんなすごいからくりを見て、終演後に気持ちよく下一通りを歩いていたのだが、鍋島さんの前で奥さんと目があったので挨拶したら、「お茶を飲んでいって」と言われた。
ありがたく頂く事にして、店内の椅子に座ろうとしたら、「あなたにはお抹茶を出してあげるから座敷へ上がって」と言われ、準備を始められたので、恐縮しつつ座敷に上がらせてもらった。
初めに『栗よせ』が、続いて、きれいに泡のたった抹茶が出てきたが、どちらも本当に美味かった。
向かいに奥さんが座って、例によって音楽の話が始まったのだが、その後、話が八幡祭の起源の事になり、そういう分野は得意なので、いろいろと話していたわけです。
で、八幡祭が10月の9日と10日になったのはオレが小学校の3年の時だったから、来年でちょうど50年になるなぁ・・・・という事は、初めて祭に屋台が登場した事が文献に書かれた享保3年から、来年でちょうど300年になるんだな、なんて話をしていたら、布袋台のからくり人形が運び込まれてきた。

ここで、それぞれの人形や器財が箱に入れられて、その後、屋台蔵に仕舞われ、来年の祭りまで眠りにつく。
今年は4月にもからくりの上演があったので、その分ゆっくりと休んでね、って思いながらお暇してきた。
で、その後、市役所の人と話をした時に、屋台の登場から300年の事を訊いてみたら、今年の春に大々的な行事をやったのでお金も残ってないし、特に何かをやる予定はない、という答えだったが、それだったら、創建300年を迎える神馬台や仙人台などの屋台だけでも、なにか記念行事をするべきなんじゃないかと思うのだが・・・・
高山市文化協会 ワンコインシアターの『オケ老人』を観てきた。
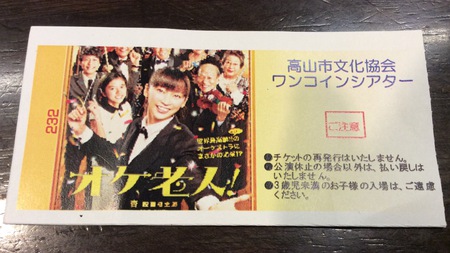
開演時間に間に合わなければ諦めるつもりでいたのだが、ランチの予約が早く終わったので、文化会館まで、半分走り、半分歩いて行ったら、着いたのが開演1分前。
顔見知りの職員の人に「ギリギリでしたね」って言われた。
思っていた以上に来場者は多く、空いた席を探して座ると、すぐに上映開始。
コメディー映画という事もあって、随所で笑い声があがる・・・・こういう雰囲気もいいもんだねぇ。
映画の内容を一言で言えば、『ウォーターボーイズ』や『スウィングガールズ』の老人版と言ったところだが、一番の違いは、最後のパフォーマンスが「吹き替え」という事で、『ウォーターボーイズ』や『スウィングガールズ』では、出演者本人たちによるパフォーマンスが見せ場だったわけだが、流石にオーケストラは無理だという事だろう。
オレ自身が合奏団で演奏していて、そんな事ができるわけがないのはよく分かっているので、逆に割り切って観る事ができたんじゃないかと思うし、ストーリーも十分楽しめた。
日本人にとって、「みんなで何かを作り上げる事」って、一番感動できる事だと思うのだけれど、この映画は、そのツボにピッタリはまっているんじゃないかな。
『スウィングガールズ』を観て、自分も演奏したくなって楽器を買った人が結構多くいたそうだが(その後続ける事ができたかどうかは別だが)、この『オケ老人』を観て、同じように思った人もいるんじゃないかな。
出口の前に、「高山室内合奏団 団員募集中」というポスターを貼っておけばよかったなって、映画を観ながら思う事しきり・・・・
でも、周りの人達も楽しんでいるのが分かる雰囲気の中で観る映画は、本当にいいものだな。
映画館で観る事ができなかった『ウォーターボーイズ』を、こういう雰囲気の中で観てみたいと心底思う。
いつか是非、できるなら6月か7月に、このワンコインシアターで『ウォーターボーイズ』をやって下さい。
夜中に、台風21号による強風が吹き荒れた23日の朝、家の玄関を出ると、こんな状態になっていた。

外へ出て、周りを見てみると、お隣にも。

まぁ、仕方がないんで、不燃物のゴミ箱に入れたけど・・・・
昼の営業が終わった後、3階のバルコニーに出てみたら、ここにもあった。

どこから飛んできたんだろうと思いながら、ふと見ると・・・・あった!!

右端と、左側の手前半分が吹き飛んでいる。
で、これがどこかというと、上で既出の、オレの裸体が写っている画像の左上の隅っこに見える、近所の家の物干しだった。
ここ ↓

この家の方は、高齢のため、自分の力で物干しに上がる事も出来ないそうなので、このままにしておくしかなさそう。
でも、なんか寂しいですね。
(後になって分かったのだが、このブログを投稿した時には、もう亡くなられていたそうだ。 合掌 )
ウチの町内(総和町1丁目)は、オレが子供の頃は飲み屋街だったけど、いつの間にか食べ物屋の町になっていて、そのうちに『グルメタウン総和一』なんて名前で売り出したらどうかと思っているくらいなんだけれど、思いつくまま挙げてみても、これだけある。
居酒屋・・・・あんらく亭、ヒダやんさ、樽平、こうぼう
寿司・・・・松喜すし
割烹・和食・・・・真山、かめ吉、ぞん家、やました、さくら
中華そば・・・・なかつぼ、麺屋とと
ステーキハウス・・・・ワンポンド
焼肉・・・・山武
フランス料理・・・・ビストロ ミュー
イタリア料理・・・・ラ フェニーチェ
高山市の中でも、これだけいろんな種類の食べ物を食べられる店が揃っている町は他にない。
ただ、問題なのは、店をやっているだけで、そこには住んでいないところが多い事。
年寄りが多いこともあって、誰も住まなくなった『空き家』が多く、それを借りて店をやっている人が多いわけなんですが、以前、町内会長をやった時、飛騨総社の祭礼の出仕についての話し合いで、宮司さんから「一番心配しているのは総和町1丁目なんですよ」って言われたくらい、年寄りの多い町内なんですよね。
独身で子供のいないオレがこんな事を言うのもなんだが、一番多かった頃の半分以下になってしまった町内の世帯数を、少しでも増やしていかなければ、って痛切に思います。
まぁ、そのためにも、少しでもウチの店をはやらせて続けていかなければならないし、ここに住んで商売をやっていく人を増やして、共存共栄でやっていく事が重要だと思いますね。
町内の人達にも、働きかけようか。
お客さんと話している時に、「やっぱりイタリアって、いいところですか?」って訊かれる事が結構ある。
そういう時には、「神経質な人には薦められないけど、何かあっても、イタ公のやる事はこんなもの、って笑える人だったら、絶対に楽しめるよ」って答えます。
まぁ、実際にそのとおりなんだけれど、とにかく、ちょっとした事にいちいちイライラしていたら、何も進まないのがイタリアなんですよね。
日本にいても、イタリアの製品を使うときに、それを痛感する事が結構ある。
ウチで前菜と一緒にお出しするグリッシーニは、トリノ産のものなんだけれど、一応、きちんとパックされている・・・・筈なんだけど、まぁ、なんと言うか、やっぱりイタリアの製品だなぁ、と実感する事が多い。
小分けされてパック詰めされたものが、さらに大きい袋に入って送られてくるわけなのだが、グラム数で表示されているので、入っている量は間違いないと思う。
でも、その小分けされたパックの内容量がバラバラで、見ただけでも全然違うのが分かる事もあるくらいだし、過去に一度だけ、中身がカラのパックが入っていた事もある。
こっちも慣れたもので、特に腹を立てる事もなく、イタ公のやる事だからなぁ、って思って見てますけどね。
先日、袋からパックを取り出そうとしたら、カラのパックが出てきたので、「うゎー、久しぶりに見たよ」って思いながらもうひとつ取り出そうとしたら、きちんと封がされてなくて、中身が全部出てしまった。

流石にこの時は、思わずムッとしてしまったのだけれど、まだまだ修行が足りませんなぁ。
次はまた、『いろいろあって 冬編』で。
では、また。
Ciao. Arrivederci!!
天気の週間予報に、雪のマークが並んでいますが、いよいよ冬らしくなってきましたねぇ。
今年は夏が短かった分、冬が長くなるんじゃないかと心配している今日この頃ですが、相手が自然ですから、どう足掻いたところで仕方がないんですけどね。
でもまぁ、雪があんまり降らなければいいなぁ、と思っているのは、オレだけではないんでしょうけど。
この前、東京の某ホテルのコンシェルジュから、団体のお客さんのランチコースの問合せがあって、20名でと言われたのだけれど、ウチでは16名までしか無理なのでお断りしたのだが、翌日、どうしてもそちらでとお客さんが言われるので16名での予約をお願いします、という電話が改めて入ったので、お受けすることになった。
その日は同業者である妹に手伝ってもらう事にして準備を進めていたのだが、前日の電話で、そのお客さんが海外からの方だと分かり、不思議に思って訊いてみた・・・・「ウチの事を、どうやって見つけられたのですか?」
すると、その答えが、「お客様の方から指定がありました。」
ウチのウェブサイトは日本語にしか対応していないのに、外国の人がどうやって調べたのだろうと不思議に思ったのだが、香港から来られたそのお客さんに訊いてみたところ、少し日本語のできる人がインターネットで調べてウチを見つけたとの事。
ウチに予約を入れて下さる方の中で、高山(及び飛騨地区)以外の方の比率は、ここ数年上がり続けて、今では8割を超えているんだけれど、その中に海外の方も入ってくるようになったとはねぇ。
いつも名古屋から来て下さるお客さん達から、「この店の真価は高山では理解されないんだから、早く名古屋へ出て来いよ。」って、以前から結構真剣に言われているんだけれど、これ以上高山の人の比率が下がるようであれば、考えなければならないのかもしれないなぁ。
ここでひとつお知らせです。
この夏にも行われた『TAKAYAMA DE KANPAI』の第2回が、現在行われています。
ウチは、参加店の中でも一番毛色が変わった店であるという自覚があったので、誰も投稿してくれないんじゃないかと心配していたのだけれど、投稿して下さった方がおられたので、今回も参加する事にしました。
今回は、さらに特典が増えているので、ぜひ写真を撮って投稿してみて下さい。
詳しい事は、こちらで。
さて、だいぶ間が空きましたが「いろいろあって 2017年初夏~秋 前編」に続く、後編です。
前編と同様に、Facebook にアップしたものを元に書いていますが、初出の文もあるので、Facebook で既読の方も読んでみて下さい。
おかげ様で、高山室内合奏団 第14回定期演奏会は、無事終了する事ができました。
ありがとうございました。
予想していたより来場者数が伸びなかったのですが、アンケート用紙の回収率がかつてないほど高く、また、その多くがかなり踏み込んだ内容まで書かれていて、読んだ団員一同、本当にありがたく思いました。
今年は、演奏会に参加する団員の数が少なく、演奏面でも、運営面でも、財政面でも、かなり苦しい演奏会になり、また去年と同様に、指揮者が演奏会間近に入院するという、かなり綱渡り的な状況でしたが、多くの方々から協力を頂いた事で、なんとか乗り切る事ができました。
協力頂いた方々には、本当に感謝しております。
個人的にも、仕事が忙しくて練習に行けない事が多かったし、実行委員の仕事も遅れがちで、プログラムの挨拶文を書いて印刷所に送ったのが、本番の5日前という慌しさでした。
今回は、その練習中に、「選曲をミスったのではないか」という意見が出るほど難しい曲を選んだため、団員それぞれに、かなり苦労したと思いますが、その分、演奏会が終わった今、よくやったよなぁ、という充実感は、例年より強く感じますね。
指揮者に質問中
団員間での打ち合わせ
毎年参加してくれるエキストラの人達
指揮者、ステージマネージャー、コンサートマスター
リハーサル中
楽譜への書き込み
アンコール曲を練習する余裕がなかったため、今回は、アンコール無しになりましたが、その事は、お客さんにも解ってもらえたのではないかと思います。
3ヵ月後には、クリスマス ファミリーコンサートが控えているので、近々、その練習が始まります。
来年は、第15回という事で、特別な演奏会にしたいという気持ちはありますが、合奏団の転換期に来ている事も確かで、みんなで話し合って最良の道を探しながら、次のステップへ進んで行きたいと思っています。
今年は、夏らしい気候になりきらないうちに、秋になってしまいましたねぇ。
夏らしい事を何もしないうちに夏が終わってしまって、なんか悔しい!!
以前ここに、「夏のプールシーズンまでに身体を引き締め直そうって思っている」って書いたのだけれど、身体の方はそれなりに締まったものの、ヘンな天気のうえに、仕事や演奏会の練習で忙しくて、結局、プールには1回しか行けなかった。
1年ぶりの市民プールで泳いでみたら、全然思うように泳げない・・・・やっぱり、1年も間が空くとだめですねぇ。
で、その1回だけのプールでも身体は焼けたわけだけれど、前と後ろの焼け方が違っていて変・・・・もう1度プールへ焼きに行きたかったけど、行けそうになかったので、天気が良い日に、ウチの3階のバルコニーに寝っ転がって焼いてみたら、結構きれいに焼けたみたい。
その時に撮った画像を、以前書いた事に対する「まだ十分ではないけど一応ここまでは身体を引き締めたよ」、という結果報告としてアップするので、「そんなもの見たくないわ」という人はスルーしてね。
実のところ、この画像を Facebook にアップするのには、躊躇がなくもなかったのだけれど、普通じゃない事をやるのが身上のオレが躊躇しちゃダメだな、という気持ちと、iPad に入れていたこの画像を見た女性のお客さんが、「うわー、きれい」って言ってくれた事で、アップに踏み切ったわけ。
まぁ、無視されるか非難されるかだろうな、と思っていたのに、結果として、個人と店の両方で30人から「いいね」をもらえたのは意外だったのだが、こうして晒してしまった以上、これより体形を崩すことはできないし、来年はさらに身体を引き締めようと思っている。
さて、この画像で穿いているのは、以前にも書いた MIZUNO の RQ-632 のウォーターポロ(通称ポロパン)で、赤と白の地に黄色のステッチが入っている。
実のところ、オレは若い頃から、赤と紫のものを身に着けた事が殆ど無かった。
何となく好みに合わなかったし、以前、自分に合う波長の色を調べた時も、赤と紫は全然合わなかった事もあって避けていたのだけれど、ここ2年ほどで「赤もいいよなぁ」って思うようになった。
これって、還暦を意識する歳になったからなのかなぁ。
打ち上げ後、7年という長い時間をかけて土星に到達し、その後、当初の計画より9年も長い13年間続けられた周回探査では、50万枚近い画像と、635GBにおよぶ貴重なデータを送り続け、最後は土星に突入して燃え尽きた、土星探査機『カッシーニ』
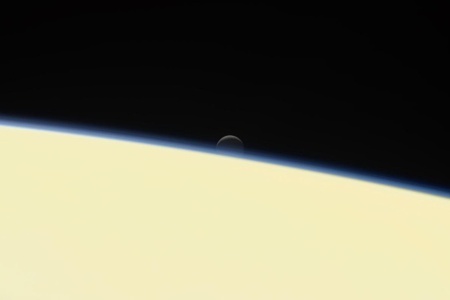
最後に送られてきた画像を見ながら、その健気さに、目がうるうるしてしまった。
http://natgeo.nikkeibp.co.jp/atcl/news/17/092000358/
20年前といえば、Power Macintosh がG3になる前であり、Windows95 の時代だったわけだけれど、そんな時代の、今と比べれば遥かに遅く、容量も小さい機械を使って、必死にデータを送り続けた カッシーニ。
カッシーニから切り離されてタイタンに着陸した、惑星探査機『ホイヘンス プローブ』と共に「健気」という言葉しか思いつかない。
そういえば7年前、3年間も行方不明になりながら、補助エンジンを使って地球に帰って来た『はやぶさ』の時も、最後は燃え尽きてしまって、その映像を見ながら、目がうるうるしたものだが、(その時に書いたブログ http://lafenice.hida-ch.com/e209922.html を読み返すと、些か気恥ずかしく思うほど感動していたみたい)、今回のカッシーニは、全く見えないところで、大気の組成データを予定より30秒も長く送信しながら消滅していった事を思うと、はやぶさの時以上にうるうるしてしまう。(子供の頃から感傷的だったのでね)
34億ドルと、20年の歳月を費やしたカッシーニのミッションも終わり、現在、木星を探査している『ジュノー』も、来年には木星に突入して消滅してしまう。
寂しくなるなぁ・・・・
9月25日って、オレにとっては、ある意味、記念日みたいな日。
17年前のこの日に、母方の祖母が100歳を目前に亡くなった事もあって、余計に忘れられない日になったのだが、1979年のこの日が、生まれて初めてオペラを観に行った日だった。
コヴェントガーデン 王立歌劇場の引越し公演で、演目はモーツァルトの『魔笛』、会場は大阪中之島のフェスティバルホール。
この時、隣の席に座っていたのは、当時付き合っていた1歳年下のえっちゃん・・・・音大の声楽科に通いながら店のレジのアルバイトに来ていた、すごくきれいな子で、狙っていた先輩も多かったのだけれど、音楽の、それもオペラの話ができるのはオレだけだったから、それをきっかけに付き合い始めたわけ。
魔笛を観に行こう、って誘ってパンフレットを見せた時、一番安い席なら行ける、って言われたのだけれど、当然安い席は売り切れているはずなので、「オレがひとりで高い席で観るより2人で一緒に観るほうが絶対に楽しいから、差額はオレが出す」と言って、OKをもらった。
まぁ、19歳のオレにしてみれば、精一杯の背伸びだったのかも。
で、ティケットを買いにいったら、当然、高い席しか残っていなくて、あちこち探してみたけど買える値段の席はなく、ふと思いついて、予約を受け付けていた事務所に電話してみたら、なんとか買えるB席が2枚だけ残っているというので、昼の休憩時間に大阪まで買いに行ってきた。(昼メシも食べずに飛び出していって、帰ってきてからティケットを買ってきたと言ったら、みんな呆れていたけど)
今でこそ『魔笛』は、『バラの騎士』『ラ ボエーム』『イル トロヴァトーレ』と並んで最も好きなオペラのひとつなんだけれど、当時は大雑把なあらすじくらいしか知らなかったので、対訳書を買ってきて大体のやりとりを頭に叩き込み、当日に備えた。
調理師学校の入学式と卒業式がフェスティバルホールで行われたので、ホールの事や行き方は分かっていたけれど、オペラを観に行くなんてのは初めての事なので、どんな格好で行ったらいいのかも分からなかったのだけれど、結局は卒業式の時に着たスーツで行った・・・・と思う。
自分の事はあまり憶えていないのだが、えっちゃんが白い小さな模様の入った紺のワンピースを着ていた事や、ロングヘヤーを編みこんでいて、メガネがかけれないって言っていた事をハッキリと憶えている。
で、肝心の演奏については、初めてのオペラだった事もあって、ハッキリとは憶えていない。
ただ、パパゲーノを歌ったトーマス アレンが芸達者で、随所で笑わせてくれた。
特に憶えているのは、3人の侍女が殺した大蛇に気がついた時の驚き方・・・・あんな自然な驚き方は、実演、VTR共に、その後に観たどの上演でも、お目にかかった事がない。
後に手に入れた、バイエルン国立歌劇場での公演のレーザーディスクで、この時と全く同じエファーディング演出の舞台を観る事ができて、あの時の感動を思い出すことができるのだが、ただ、誰もが『魔笛』の中で一番楽しみにしているであろう『パパパの2重唱』を、タミーノとパミーナの試練の場の前に移動させた事だけは、許し難い暴挙だと思う。
で、この日の公演の最後、カーテンコールが終わったところで、オーケストラが Happy birthday to you. を演奏し始めた。
この日は、指揮者のコーリン デイヴィスの誕生日だったのだが、そんな事も、この日を忘れ難いものにしているのだろうな。
公演が終わった後、北新地まで歩いて、当時、イタリア料理の人気店だった『ジジ』で食事をして、神戸に帰ってきたのだけれど、まぁ、これがオレの10代最後の大イヴェントだった事は間違いない。
その後もいろいろあったけど、付き合いは続き、オレが東京へ移ってからは、えっちゃんが仕事で東京へ来た時に、朝、仕事の前に彼女の泊まっているホテルに行って、一緒に朝食を食べたりもしていたけれど、神戸の地震の後に電話で話したのを最後に、音信不通。
おそらく彼女も、オレと同様に結婚はしていないと思う。
まぁ、お互い、そういう生き方の人間なんだろうな。
いつか会う事があるなら、お互いにいい歳の取り方ができたな、って言えるようになっていたい。
10月10日の昼、ランチコースを予約して来られた方と食後に話をした時に、「祭だという事を知らずに来たのだけれど、今から見に行くのならどこがいいですか?」と訊かれた。
2時近くになっていたので、八幡神社へ行っても見るものはないだろうと判断し、「3時から下一通りで布袋台がからくりをやるので、今から行けばいい場所で見る事ができると思いますよ」と答えると、そういうのに興味があるので行くとの事。
下一之町への行き方を説明したところで、そのお客さんから名刺を渡され、挨拶された。
郡上で店をやっておられる同業者の方で、お客さんから「高山のラ フェニーチェ」という名前をよく聞くので、以前からすごく気になっていたんです、と言われた。
まぁ、同業者にそう言われるのは、うれしいものですね。
で、そのお客さんをお見送りした後、オレも下一之町へ布袋台のからくりを見に行った。
毎年、布袋台を屋台蔵に入れる前に、下一通りでからくりを披露するのだが、人でごった返す八幡神社の境内よりも、ずっと落ち着いて観る事ができるので、毎年観に行く事にしているわけです。
ランチの営業を終えて、昼メシをかっ込んで、下一通りまで走って行ったら、2時50分・・・・開演まで10分。
もう、布袋台の前には、びっしりと人だかりができている。
屋台の横、からくりがぎりぎり見えるところに陣取って、反対側を見ると、三味線や太鼓を構えた人達が並んで座っている・・・・今年の伴奏は生演奏だったのだと気がついた。
伴奏を生でやるのは何年ぶりかな。
小さい子供が屋台の上段に立ち、開演を告げると、からくりが始まった。
生伴奏の影響もあったのか、実にスムースに進んでいく・・・・今までに見た中でも、ベスト3に入るくらいの出来だったのではないかな。
唐子が布袋さんの肩と手に乗る時、唐子の首を動かすための「噛み合わせ」が、ほぼ一発でピッタリ嵌ったのが見ていて分かったくらいだから。
数年前にからくりの練習を見せてもらった時、当時の『綾元』(リーダー)の鍋島勝雄さんに話を聞かせてもらったのだが、その時に、「からくりを見に来る人の中には、失敗する事を期待している人もいる筈だから、上手くいっている時でも、わざと動かなくなったように見せる事もある。」って言われた事をハッキリと憶えている。
でも、今回のからくりは、そんな事を気にするまでもないほどに上手く行ったんじゃないかと思う。
そんなすごいからくりを見て、終演後に気持ちよく下一通りを歩いていたのだが、鍋島さんの前で奥さんと目があったので挨拶したら、「お茶を飲んでいって」と言われた。
ありがたく頂く事にして、店内の椅子に座ろうとしたら、「あなたにはお抹茶を出してあげるから座敷へ上がって」と言われ、準備を始められたので、恐縮しつつ座敷に上がらせてもらった。
初めに『栗よせ』が、続いて、きれいに泡のたった抹茶が出てきたが、どちらも本当に美味かった。
向かいに奥さんが座って、例によって音楽の話が始まったのだが、その後、話が八幡祭の起源の事になり、そういう分野は得意なので、いろいろと話していたわけです。
で、八幡祭が10月の9日と10日になったのはオレが小学校の3年の時だったから、来年でちょうど50年になるなぁ・・・・という事は、初めて祭に屋台が登場した事が文献に書かれた享保3年から、来年でちょうど300年になるんだな、なんて話をしていたら、布袋台のからくり人形が運び込まれてきた。
ここで、それぞれの人形や器財が箱に入れられて、その後、屋台蔵に仕舞われ、来年の祭りまで眠りにつく。
今年は4月にもからくりの上演があったので、その分ゆっくりと休んでね、って思いながらお暇してきた。
で、その後、市役所の人と話をした時に、屋台の登場から300年の事を訊いてみたら、今年の春に大々的な行事をやったのでお金も残ってないし、特に何かをやる予定はない、という答えだったが、それだったら、創建300年を迎える神馬台や仙人台などの屋台だけでも、なにか記念行事をするべきなんじゃないかと思うのだが・・・・
高山市文化協会 ワンコインシアターの『オケ老人』を観てきた。
開演時間に間に合わなければ諦めるつもりでいたのだが、ランチの予約が早く終わったので、文化会館まで、半分走り、半分歩いて行ったら、着いたのが開演1分前。
顔見知りの職員の人に「ギリギリでしたね」って言われた。
思っていた以上に来場者は多く、空いた席を探して座ると、すぐに上映開始。
コメディー映画という事もあって、随所で笑い声があがる・・・・こういう雰囲気もいいもんだねぇ。
映画の内容を一言で言えば、『ウォーターボーイズ』や『スウィングガールズ』の老人版と言ったところだが、一番の違いは、最後のパフォーマンスが「吹き替え」という事で、『ウォーターボーイズ』や『スウィングガールズ』では、出演者本人たちによるパフォーマンスが見せ場だったわけだが、流石にオーケストラは無理だという事だろう。
オレ自身が合奏団で演奏していて、そんな事ができるわけがないのはよく分かっているので、逆に割り切って観る事ができたんじゃないかと思うし、ストーリーも十分楽しめた。
日本人にとって、「みんなで何かを作り上げる事」って、一番感動できる事だと思うのだけれど、この映画は、そのツボにピッタリはまっているんじゃないかな。
『スウィングガールズ』を観て、自分も演奏したくなって楽器を買った人が結構多くいたそうだが(その後続ける事ができたかどうかは別だが)、この『オケ老人』を観て、同じように思った人もいるんじゃないかな。
出口の前に、「高山室内合奏団 団員募集中」というポスターを貼っておけばよかったなって、映画を観ながら思う事しきり・・・・
でも、周りの人達も楽しんでいるのが分かる雰囲気の中で観る映画は、本当にいいものだな。
映画館で観る事ができなかった『ウォーターボーイズ』を、こういう雰囲気の中で観てみたいと心底思う。
いつか是非、できるなら6月か7月に、このワンコインシアターで『ウォーターボーイズ』をやって下さい。
夜中に、台風21号による強風が吹き荒れた23日の朝、家の玄関を出ると、こんな状態になっていた。
外へ出て、周りを見てみると、お隣にも。
まぁ、仕方がないんで、不燃物のゴミ箱に入れたけど・・・・
昼の営業が終わった後、3階のバルコニーに出てみたら、ここにもあった。
どこから飛んできたんだろうと思いながら、ふと見ると・・・・あった!!
右端と、左側の手前半分が吹き飛んでいる。
で、これがどこかというと、上で既出の、オレの裸体が写っている画像の左上の隅っこに見える、近所の家の物干しだった。
ここ ↓
この家の方は、高齢のため、自分の力で物干しに上がる事も出来ないそうなので、このままにしておくしかなさそう。
でも、なんか寂しいですね。
(後になって分かったのだが、このブログを投稿した時には、もう亡くなられていたそうだ。 合掌 )
ウチの町内(総和町1丁目)は、オレが子供の頃は飲み屋街だったけど、いつの間にか食べ物屋の町になっていて、そのうちに『グルメタウン総和一』なんて名前で売り出したらどうかと思っているくらいなんだけれど、思いつくまま挙げてみても、これだけある。
居酒屋・・・・あんらく亭、ヒダやんさ、樽平、こうぼう
寿司・・・・松喜すし
割烹・和食・・・・真山、かめ吉、ぞん家、やました、さくら
中華そば・・・・なかつぼ、麺屋とと
ステーキハウス・・・・ワンポンド
焼肉・・・・山武
フランス料理・・・・ビストロ ミュー
イタリア料理・・・・ラ フェニーチェ
高山市の中でも、これだけいろんな種類の食べ物を食べられる店が揃っている町は他にない。
ただ、問題なのは、店をやっているだけで、そこには住んでいないところが多い事。
年寄りが多いこともあって、誰も住まなくなった『空き家』が多く、それを借りて店をやっている人が多いわけなんですが、以前、町内会長をやった時、飛騨総社の祭礼の出仕についての話し合いで、宮司さんから「一番心配しているのは総和町1丁目なんですよ」って言われたくらい、年寄りの多い町内なんですよね。
独身で子供のいないオレがこんな事を言うのもなんだが、一番多かった頃の半分以下になってしまった町内の世帯数を、少しでも増やしていかなければ、って痛切に思います。
まぁ、そのためにも、少しでもウチの店をはやらせて続けていかなければならないし、ここに住んで商売をやっていく人を増やして、共存共栄でやっていく事が重要だと思いますね。
町内の人達にも、働きかけようか。
お客さんと話している時に、「やっぱりイタリアって、いいところですか?」って訊かれる事が結構ある。
そういう時には、「神経質な人には薦められないけど、何かあっても、イタ公のやる事はこんなもの、って笑える人だったら、絶対に楽しめるよ」って答えます。
まぁ、実際にそのとおりなんだけれど、とにかく、ちょっとした事にいちいちイライラしていたら、何も進まないのがイタリアなんですよね。
日本にいても、イタリアの製品を使うときに、それを痛感する事が結構ある。
ウチで前菜と一緒にお出しするグリッシーニは、トリノ産のものなんだけれど、一応、きちんとパックされている・・・・筈なんだけど、まぁ、なんと言うか、やっぱりイタリアの製品だなぁ、と実感する事が多い。
小分けされてパック詰めされたものが、さらに大きい袋に入って送られてくるわけなのだが、グラム数で表示されているので、入っている量は間違いないと思う。
でも、その小分けされたパックの内容量がバラバラで、見ただけでも全然違うのが分かる事もあるくらいだし、過去に一度だけ、中身がカラのパックが入っていた事もある。
こっちも慣れたもので、特に腹を立てる事もなく、イタ公のやる事だからなぁ、って思って見てますけどね。
先日、袋からパックを取り出そうとしたら、カラのパックが出てきたので、「うゎー、久しぶりに見たよ」って思いながらもうひとつ取り出そうとしたら、きちんと封がされてなくて、中身が全部出てしまった。
流石にこの時は、思わずムッとしてしまったのだけれど、まだまだ修行が足りませんなぁ。
次はまた、『いろいろあって 冬編』で。
では、また。
Ciao. Arrivederci!!
2017年10月03日
いろいろあって 2017年初夏~秋 前編
Ciao. spockです。
もう10月かぁ・・・・
毎日、バタバタとすごしているうちに、朝晩もめっきり涼しくなり、月日の経つのは速いなぁ、ってしみじみ思います。
この夏は、ヘンな天気が続き、夏らしい事がなにもできないうちに終わってしまい、欲求不満気味・・・・9月に入ってからは天気のいい日が多かったけれど、こんな天気が8月に続けばよかったのにって、ずーっと思ってました。
北朝鮮の不穏な動きや、解散総選挙で浮き足立つ政界など、おかしな空気が流れ続けた9月も終わりましたが、そんな中でも感動した出来事は、土星探査機『カッシーニ』のミッション終了でした。
20年にわたって、膨大な画像と貴重なデータを地球に送り続けたカッシーニも、燃料切れ直前に土星に突入し、大気の組成データを送信しながら消滅・・・・最後に送られてきた画像を見ながら、目をうるうるさせてしまった。(この事は、このブログの後編で詳しく書きますが)

なかなか以前のような長い文章を書くヒマがなく、このブログの更新も滞り気味ですが、今回は、Facebook に書いたものを元にいろいろ書き加え、また、Facebook には書いていない文章も加えてまとめてみました。
結構長くなったので、前編と後編に分けてアップしますが。
Facebook を見てもらっている方には、もう読んだ、って言われるかもしれませんが、初めて書いた文も結構あるので、もう一度読んでもらうのもいいのではないかと・・・・
さて、本文に入る前に、ひとつお知らせです。
昨年に引き続き、大人のための音楽会 Viva La Musica Ⅱ が、12月23日(祝) 15:30から ホテル アソシア 3階 天翔の間 で開催されます。
アコースティック楽器の演奏か声楽であれば、始めて間もない方からヴェテランまで、どなたでも参加して頂けます。
コンサート終了後は、ラ フェニーチェで懇親会が行われます。
懇親会は自由参加で、懇親会のみの参加もOKですが、どちらも10月10日までに申し込んで下さい。
もう8割方埋まっているようなので、お早めにどうぞ。
問合せ、申込みは、細江音楽教室 34-6796 まで。

では、本文に戻って、5月の話から。
5月4日、飛騨総社の祭礼に出仕のため、ランチを休業して、行列の旗持ちをしてきました。

8年前に、裃を着て警固に出た事はあったけど、今回は歩くだけでなく、旗を持たなければならないので、班長さんから、「大変な役でほんとに申し訳ないな」って言われていたのだけれど、大事な氏神様の事ですから。
もっとも、実際にやってみたら、それほど大変でもなかった、というのが本当のところなんですけどね。
指定の時間にお隣の霊雲寺へ行くと、世話係りのオバチャン達が待ち構えていて、着付けやら何やら、すべてやってもらえた。
さらしを輪にしたものを首からかけて、そこに旗の棹の先を引っ掛けるようにしてくれたので、これならそれほどしんどい事はないなと思ったしだい。
行列が出発するまで、結構時間があったので、飛騨総社の境内で、世話係のおじさんと話をしていたのだが、過去のいろんな話や裏話を聞かせてもらった上で行き着くのは、人口減少と高齢化の中で今後の祭をどう維持していくのか、という事。
今回、オレが持った旗は、端の方が結構擦り切れていたのだが、この旗を1本新調するだけでも、数十万円かかるそうだ。
オレが子供の頃、飛騨総社の祭行列の長さは大変なものだったが、それが今は半分くらいしかないんじゃないだろうか。
昔に比べ、人も減ったし使えるカネも減ったという事なのだが、なんか寂しいよなぁ。
オレが持つ『朱雀旗』の位置は、神輿の右前。
旗自体はそれほど重いものでもないし、首からかけた晒の輪に引っ掛けるので、重労働というわけではないのだけど、風が吹くと煽られて大変です。
出発すると、結構ペースが速くて、前を歩いている雅楽の人達が、「えらい速いな」と言っているのが聞こえたけど、あまりのんびり進むよりはいいんじゃないかと思って歩いていたのだが、全体の3分の1を過ぎたくらいのところで、後ろから、役員のリボンを付けた裃のおっちゃんが来て、「位置がおかしい」って言い始めた。
そのおっちゃんは正しい事を言っているのだろうし、言っている事はよく分かる・・・・でも、今初めて聞く事だし、あんまりにも上から目線の言い方だったので、思わず言ってしまった。
「そこまで言うんなら、あんたがスピードを調整して位置を合わせればいいやろ。オレたちは、こんな事をやるのは初めてやし、いきなりそんな事を聞かされて、すぐにできるわけがないやろが。」
そのおっちゃんは、一瞬口ごもった後、「ここの係は何をしとるんや」って言いながら、後ろの方へ戻って行った。
で、その後も行列は進み、もうじき角を曲がるという時、さっきのおっちゃんが来て、今度はまったく穏やかな口調で、「次の角を曲がると急に風が強くなるんで、旗を持っている人は煽られんように注意して」と言った。
へー、このおっちゃん、こんなふうに言えるんや、と思って見ていたら、むこうもオレの視線に気がついて、まぁ、『目は口ほどにものを言う』という事か、「危ないと思ったら、旗は倒してもいいからね」とも言ってくれた。
オレは、目上の人に対しては、一応は敬意を表すことにしているんだけれど、時々、こういう事をやってしまうんだよなぁ。
まぁ、自分のやった事は間違っていない、という確信があるけど、でもやっぱり、まわりの雰囲気を悪くするような事は、できればしたくない。
で、その後、日進木工で休憩に入り、他の分隊との時間調整もあって、1時間以上も待たなければならなかったのだけれど、そこを出発する少し前に、そのおっちゃんが話しかけてきて、この辺りは昔から風の強いところで、祭りの行列はいつも大変だった、というような話を、ニコニコとしながら話してくれて、オレもそういう話を聞くのが好きなので、質問しながら聞いていたのだが、まぁ、結果オーライという事かな。
その他にも、行列の中のあるグループの先頭の2人が、趣味の話に熱中してだんだん遅れるようになってきたので、速く進むように言ったら、露骨に嫌そうな顔をされて、その後は完全無視されたけど、スムースに進むようになったので、それで正解だったと思う。(そんなヤツとお友達になる気もないし)
その後、他の分隊と合流して、御旅所での祝詞や獅子舞、闘鶏楽など、結構な時間がかかったけど、5時前には飛騨総社に戻り、無事役目を終了する事ができた。
次にやるのは、何年後になるんだろうな。
以前、ランチに来られた若い女性のグループと話をしていた時、何の話からだったか忘れたが、「オレ、いくつに見える?」って訊いたら、「42歳」って言われて、なんか嬉しかったんだけれど、実際のところ、還暦を意識する歳になると、身体のあちこちに不具合が出てくるのは仕方がない事なんだろうな。
中でも一番痛切に感じるのは『老眼』ですね。
20代の初めの頃、40歳で新聞を読むのに老眼鏡をかけていた先輩から、「目がいいと早く老眼になるぞ」って、よく言われたものだが、視力検査ではいつも1.5か2.0だったオレも、老眼が始まるのが早かったし、速く進んだのだと思う。
だからスマートフォンを使うのも難儀で、以前 iPhone 4s を2年間使ったけど、その後はガラケーと iPad の2台持ち・・・・その iPad でも、拡大しないと見難いのだから大変です。
そんなわけで、前回の投稿から画像のサイズを大きくしたのだけれど、今回からは更に大きくしたので、老眼の人でも見やすくなったんじゃないかと・・・・
で、去年の12月に受けた市の検診で、前立腺癌に関して「要精密検査」という連絡が来たので、1月に精密検査を受けたのだが、今まで病院には全く縁が無く、点滴すら打った事のなかったオレにとって、人生初のCTと点滴、それにMRIの体験をした。


これであと経験してないのは入院だけだなぁ、なんて思っていたのだが、3月に検査の結果を訊きに行った時、問題はなさそうだけれど直接細胞を取り出して検査してみますか、と言われたので、お願いしたら、一晩入院する必要があると言われ、ついに人生初の入院を経験する事になるのかぁ、って思っていたわけです。
と同時に、ここで無入院記録も終わりかぁ、っていう気持ちもあったんですけどね。
で、ゴールデン ウィーク明けに、入院の準備をして病院に行き、最初に血液検査を受けたのだが、その結果を見た先生が、「これなら大丈夫でしょう、今日はもういいですよ。8月にもう一度検査しましょう。」って・・・・
結局、入院する事無く帰って来たわけだけれど、3月からゴールデン ウィークまでの、あの気持ちはなんだったんだろう。
でも、このまま人生が終わる時まで入院を経験する事無く過ごせたら、それは幸せな事なんだろうな、って思いますね。
以前、『ウォーターボーイズ』のDVDを見て「夏までに身体を引き締め直そう」って思っている、と書いたのだけれど、夏のプールシーズンまで2ヵ月となった5月の中旬・・・・始めましたよ。
インターネットで検索した中から、「これは効きそう」と思ったエクササイズを4つ、毎晩寝る前にやる事にした。
慣れるに従って、同じエクササイズをどんどんハードにしていく予定でいたのだが、インターネットで調べると、いろいろ効きそうなエクササイズが出てくるので、実際にやってみて効きそうなものと入れ替えながらやってみた。
どこまで効果があるのかは未知数だけれど、何とかプールに行く時期には間に合うんじゃないかと思ってやっていたわけ。
まぁ、こんな事をわざわざ公言したのも、そうする事で自分にプレッシャーをかけていたわけなんだけど・・・・
ふと思い出して探してみたら、23年前の夏、西伊豆の土肥へダイヴィングに行った時に、THE101のプール横のセンターテラスで撮った写真が出てきた。

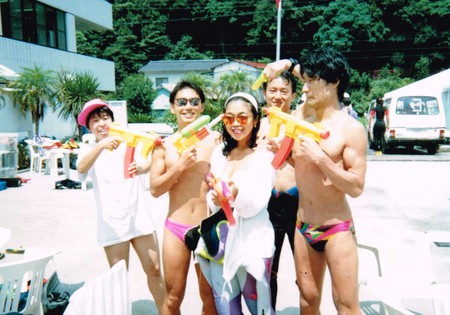
そこに写っているのは、30代前半の自分の身体。
週に3日、赤坂のティップネスに通って、ウエイトトレーニングと水泳をしていた時期なので、きれいに腹筋が割れている。
実を言うと、その当時、この写真を見るまで、自分の腹筋が割れている事に気がつかなかったくらいなので、今考えると、それほど真剣にやっていたわけではなかったのかもしれない。
だから、その写真を見て、その頃の事を思いながら、イメージトレーニングをしていたわけですよ。
まぁ、何とかなるだろう、って。
もっとも、お客さんにはメチャメチャカロリーの高い料理を出しておいて、自分だけシェイプアップするのも、チョッと気が引けますがね。
で、その結果がどうなったかは、近日公開予定の、このブログの後編で見てもらう事にしましょう。
(そんなものは見たくない、という人はスルーして下さい)
毎年、ジャガイモが新物に替わると、水分が多すぎて美味くないので、水分が落ち着くまでニョッキを作るのを止めるのだけれど、それから少し遅れて、真赤なトマトが出回るようになると、入れ替わりに作り始めるのが、トマト入りカルボナーラ。

オレ自身、他所の店で見た事がないので、イタリアでも、ごく限られたところでしか作られていないのだと思う。
一般的なカルボナーラに比べても、味付けはシンプルそのもの。
でも、トマトの旨味が加わる事で、本当に美味くなる。
「普通のカルボナーラより好き」と言われる事が多いけど、オレ自身も、こっちの方がずっと好きです。
去年、料理の出張講習会をやった時も、これがすごく好評だったし。
真赤なトマトが出回る時期だけの『季節限定メニュー』なんだけれど、これを作り始めると、夏が近づいている事を実感します。
キリッと冷やした白ワインを合わせると最高ですよ。
うれしい再会ができた。
スポーツが大嫌いだったオレが、雑誌『ターザン』の取材を受けた事をきっかけに、スポーツにのめりこみ始めた事は、5年も前に『人生を変えた出来事』というタイトルの超長編ブログに書いたのだけれど、まず最初に始めたのが、ウェイトトレーニングと水泳だった。
ウェイトトレーニングに関しては、マシンを買って、自室でやっていたのだけれど、水泳はプールに行かない事には始まらないので、電話帳で三ノ宮から行きやすいスウィミングスクールをいくつか探し、実際に電話で問い合わせてみて、ここにしようと決めたのが『本山スポーツセンター』だった。
三ノ宮から阪神電車で青木まで行き、そこから10分ほど歩くと、本山スポーツセンターはあった。
1986年の秋に行き始めてから、1991年の6月に東京へ行くまで、4年半と少し、週1回の休みの日の夜はたいてい行っていたので、今考えると、本当に真面目に通ったよなぁ、って思う。
休みの日に風邪で熱を出した時も、夜、プールで泳いで来たら、次の朝には熱が引いていたし、イタリアから帰って来た時も、その足でプールに行って泳ぎ、時差ボケを直したし、当時は健康管理のためにプールに行っていたように思える。
で、その本山スポーツセンターのスウィミングスクールで、初期の水慣れから、クロール、バック、ブレストストローク、バタフライと、時間はかかったけれど、泳げるようになるのが楽しかったし、一緒に習っている仲間や、教えてもらうコーチとのフランクな雰囲気が、オレにはすごく合っていたんだと思う。
で、そのコーチには、センターの社員の人と、大学の水泳部員がアルバイトでやっている人がいたのだが、年齢が近い事もあって、水泳部員のコーチから指導を受ける事が多かった。
だから、そういう若いコーチに無理矢理お願いして、センターの水泳のVTRをダヴィングしてもらった事もあったし、そういう関係は良好だったと思う。
オレが東京へ行く事になり、その事は一応みんなには話してあったのだけれど、最後に行くときには、ちゃんとお礼と挨拶をしようと思っていたのに、最後の週に急な用事が入って行けなくなり、みんなに挨拶もできないまま東京へ行ってしまった事が、その後もずーっと心に引っ掛かっていた。
で、5月のある日、ディナーの予約の電話が入ったのだが、日時や内容など、一通り聞き終わったところで、そのお客さんからこう言われた。
「本山スポーツセンターで、アルバイトで水泳のコーチをやっていた者なんですけど・・・・」
オレは一瞬、頭が混乱したね・・・・オレがここで店をやっている事なんか、分かるはずがないんだから。
思わず「どうして分かったの?」って訊いたのだけれど、説明されて納得した。
高山に旅行する事になったので、どこで食事をしようかと探していて、ウチのウェブサイトを見た時に、オレの写真の横顔から、『あの』西野さんに間違いない、と思ったそうだ。
よく顔も名前も憶えていてくれたよなぁ、って感動しましたね。
予約の当日は、お土産を用意して待っていた・・・・で、26年ぶりの再会。
とにかく料理を食べてもらって、デザートも食べ終わったところで、昔の話に花を咲かせた。
まぁ、こういう時って、あぁ、そんな事もあったよなぁ、って話が結構出てくるもので、30年前に戻ったような時間を楽しむ事ができました。
最後に絵の前で記念撮影。
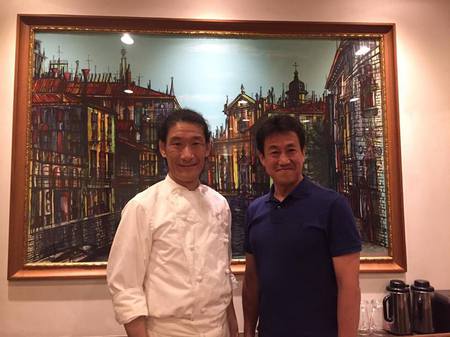
コーチ、本当にありがとうございました。
また来て下さいね。
ヨーロッパの食文化を、映画『スウィングガールズ』に出てきたセリフ風に言うと、こんなふうになる。
「ヨーロッパの食文化は2種類に分けられる。オリーヴ・ワイン文化と、バター・ビール文化だ。」
ところが、北のバター・ビール文化と、南のオリーヴ・ワイン文化の境目にある北イタリアは、その中間とも言うべき、バター・ワイン文化なんですよ。
だから、料理に合わせるには、基本的にワインをお勧めするけれど、バターを多用する料理なので、ビールを合わせるのも悪くないと思う。
ただし、こってりとした料理が多いので、濃厚なビールでないと負けてしまう。
なので、ウチでは『ブラウマイスター』の生をお出ししているわけなのだけれど、これは本当に美味いビールだと思います。
生ビールは、クラスに注ぐ事で商品になるわけですから、注ぎ方はもちろんの事、グラスの状態やサーヴァーのメンテナンスなど、気を遣う点が多いのだけれど、ウチではビールの劣化を防ぐため、樽ごとビールを冷やす、樽冷却式のビールサーヴァーを使っています。
この方式のサーヴァーは、現在では手に入らないそうで、きちんとメンテナンスをしてもらいながら、大切に使っているのですが、この前、ビールが通るホースを新しいものに取り換えてもらったら、なぜか泡の出方が変わってしまい、メンテナンス担当の人にいろいろやってもらったけれど、どうしても納得のいく泡にはならなかった。
先日、その担当の人が、廃棄されたサーヴァーの中から部品を探し出してきれいに磨き上げ、ウチのサーヴァーの部品と交換して、ホースを内径の小さいものに取り換えてくれたら、以前よりもきめの細かい、クリームのような泡が出るようになった。
本当にありがたい事です。

最高の状態のブラウマイスター〈生〉を、ぜひ料理に合わせて飲んでみて下さい。(カウンターで、生ハムやチーズをつまみに飲むのもいいですよ)

ただし、ビールの泡は油に弱いので、飲む前に唇の油を拭き取ることをお忘れなく!!
TAKAYAMA DE KANPAI
高山で乾杯~!
面白い企画なので、参加させてもらいました。
結構な数の店が参加されてますが、その中でもウチは、一番毛色の変わった店なんじゃないかと・・・・
まぁ、ウチの場合、乾杯しながら騒ぐ店ではないし、料理の見た目も素っ気ないし・・・・でも、そういう店が参加している方が、敢えてそういう店を選ぶ楽しさがあって面白いでしょう。
とにかく、楽しんでもらえればいいとは思っていたのだけれど、だれも投稿してくれなかったらどうしよう、と思っていた事も確か。
でも、3名の方が投稿してくださったので良かった。
ウチが紹介されたページは今後も残るそうなので、そちらも見てもらえればいいかと。
おかげ様で、『ラ フェニーチェ 12周年感謝パーティー』は、30名のお客さんに来て頂き、食べて飲んで頂いて、無事終える事ができました。
今年は、常連のお客さんと、世話になっている方に限って声をかけさせてもらったのだけれど、遠くは大分から、わざわざこのパーティーのために来て下さった方もあり、本当にありがたく思っています。
例によって、オレはひたすら料理を作っていたので、料理を出した後は、すべてお客さん任せなのですが、それでもキチンとパーティーが成り立ってしまうのが、ウチのお客さんのすごいところ。
改めて、ウチのお客さんのレヴェルの高さに感心してしまいました。
今回お出しした料理は、次の通りです。
生ハム、サラミ、コッパの盛り合わせ
魚介類のサラダ ニース風
グリーンアスパラのミラノ風
温野菜の焦がしバターソース
カポナータ
パルマ風リゾット
ホウレン草入りラザーニェのボローニャ風
スパゲッティ エトナ風ミートソース
手作りマカロニのソーセージ入りトマトソース
ペンネリガーテの4種チーズソース
スズキの岩塩包み焼き
タイのモンテカルロ風バターソース
オマールと魚介類のワイン蒸し
鶏の魔女風鉄板焼き
ローマ風サルティンボッカ
野菜サラダ トマトドレッシング
パンナコッタ
あと2品ほど用意していたのですが、もう食べられないと言われたので、ここでストップしました。
写真を撮っているヒマがなかったので、料理の画像はなし。
調理場から撮った写真も何枚かあったのだけれど、なぜかピントが合ってなくて、その中でもまともなのがコレ。

まぁ、雰囲気は分かると思いますが・・・・
今年は、例年に比べ、花をもってきて下さった方が少なかったけれど、その代わり、ワインや酒を持ってきて下さった方が多く、それはそれでうれしいものですね。


来年、13周年のパーティーができるように、また1年頑張ってやっていきたいと思っています。
13年目に入ったラ フェニーチェを、これからもよろしくお願いします。
8月の6日と7日は、毎年恒例の『しもいち通りの七夕まつり』・・・・残念な事に今年は、台風接近のため2日目が中止になり、6日だけの営業になりましたが、多くの方に来て頂き、本当に楽しくやらせてもらいました。
途中で急な雨に降られて「もう終わりか」と思ったのに、その後も途切れる事無くお客さんが来て下さった事は、本当にありがたかったですね。
ブラウマイスター、ワイン、スプマンテ、ランブルスコ、イタリアンカクテルetcと、他所では絶対に飲めないであろうものを取り揃えてやっているわけですが、毎年わざわざ、ブラウマイスターを飲みに来て下さる方も何人かみえるし、目の前でカクテルを作るのを喜んで見てくれるお客さんも多いので、年々、メニューが増えていますけどね。


今年はすぐ隣で、初参加の飛騨乃キッチンさんが営業されましたが(FBでは友達になっていたのに、お会いするのは初めてでしたが)、いろいろ話をしながら営業できて、楽しかったです。

飛騨乃キッチンさんは、9時前には完売されてましたが、ウチも土日だった去年よりは少なかったものの、予想以上に売れました。
もう1日やりたかったなぁ、というのが本当のところですが、相手が自然では仕方がない・・・・まぁ、1日楽しませてもらった事で、良しとしておきましょう。
中田酒店の中田祐一君が、営業中の画像をアップしてくれたので、シェアさせてもらいましたが、よく雰囲気がとらえられていますね。
https://www.facebook.com/nakadasaketen/posts/906658882818764
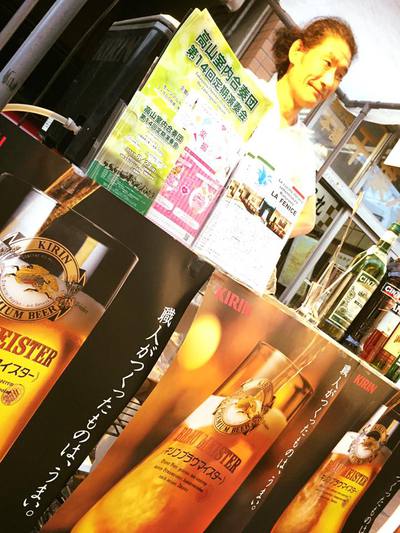



毎年ここでは、パーカにフットボールパンツを組合わせた、オレの定番スタイルでやっているのだけれど、夫妻で今回初めて覗きに来てくれた、ウチの常連で高名なミュージシャンの浦田恵司さん(日本のシンセサイザープログラミングの第一人者で、奥さんは歌手のAZAMIさん)に、「勝ちゃん、今日は面白いスタイルだね」と言われたので、「ミック ジャガーも、こんなスタイルでステージに立っていたでしょう」って答えたら、「確かに」って納得されていた。
毎年、この七夕が終わると、夏が半分終わったな、って思うのだけれど、今年は夏らしい事を、まだ何もやってない・・・・今度晴れたら、プールだな。
長くなったので、続きは「後編」で。
では、また。
Ciao. Arrivederci!!
もう10月かぁ・・・・
毎日、バタバタとすごしているうちに、朝晩もめっきり涼しくなり、月日の経つのは速いなぁ、ってしみじみ思います。
この夏は、ヘンな天気が続き、夏らしい事がなにもできないうちに終わってしまい、欲求不満気味・・・・9月に入ってからは天気のいい日が多かったけれど、こんな天気が8月に続けばよかったのにって、ずーっと思ってました。
北朝鮮の不穏な動きや、解散総選挙で浮き足立つ政界など、おかしな空気が流れ続けた9月も終わりましたが、そんな中でも感動した出来事は、土星探査機『カッシーニ』のミッション終了でした。
20年にわたって、膨大な画像と貴重なデータを地球に送り続けたカッシーニも、燃料切れ直前に土星に突入し、大気の組成データを送信しながら消滅・・・・最後に送られてきた画像を見ながら、目をうるうるさせてしまった。(この事は、このブログの後編で詳しく書きますが)

なかなか以前のような長い文章を書くヒマがなく、このブログの更新も滞り気味ですが、今回は、Facebook に書いたものを元にいろいろ書き加え、また、Facebook には書いていない文章も加えてまとめてみました。
結構長くなったので、前編と後編に分けてアップしますが。
Facebook を見てもらっている方には、もう読んだ、って言われるかもしれませんが、初めて書いた文も結構あるので、もう一度読んでもらうのもいいのではないかと・・・・
さて、本文に入る前に、ひとつお知らせです。
昨年に引き続き、大人のための音楽会 Viva La Musica Ⅱ が、12月23日(祝) 15:30から ホテル アソシア 3階 天翔の間 で開催されます。
アコースティック楽器の演奏か声楽であれば、始めて間もない方からヴェテランまで、どなたでも参加して頂けます。
コンサート終了後は、ラ フェニーチェで懇親会が行われます。
懇親会は自由参加で、懇親会のみの参加もOKですが、どちらも10月10日までに申し込んで下さい。
もう8割方埋まっているようなので、お早めにどうぞ。
問合せ、申込みは、細江音楽教室 34-6796 まで。
では、本文に戻って、5月の話から。
5月4日、飛騨総社の祭礼に出仕のため、ランチを休業して、行列の旗持ちをしてきました。
8年前に、裃を着て警固に出た事はあったけど、今回は歩くだけでなく、旗を持たなければならないので、班長さんから、「大変な役でほんとに申し訳ないな」って言われていたのだけれど、大事な氏神様の事ですから。
もっとも、実際にやってみたら、それほど大変でもなかった、というのが本当のところなんですけどね。
指定の時間にお隣の霊雲寺へ行くと、世話係りのオバチャン達が待ち構えていて、着付けやら何やら、すべてやってもらえた。
さらしを輪にしたものを首からかけて、そこに旗の棹の先を引っ掛けるようにしてくれたので、これならそれほどしんどい事はないなと思ったしだい。
行列が出発するまで、結構時間があったので、飛騨総社の境内で、世話係のおじさんと話をしていたのだが、過去のいろんな話や裏話を聞かせてもらった上で行き着くのは、人口減少と高齢化の中で今後の祭をどう維持していくのか、という事。
今回、オレが持った旗は、端の方が結構擦り切れていたのだが、この旗を1本新調するだけでも、数十万円かかるそうだ。
オレが子供の頃、飛騨総社の祭行列の長さは大変なものだったが、それが今は半分くらいしかないんじゃないだろうか。
昔に比べ、人も減ったし使えるカネも減ったという事なのだが、なんか寂しいよなぁ。
オレが持つ『朱雀旗』の位置は、神輿の右前。
旗自体はそれほど重いものでもないし、首からかけた晒の輪に引っ掛けるので、重労働というわけではないのだけど、風が吹くと煽られて大変です。
出発すると、結構ペースが速くて、前を歩いている雅楽の人達が、「えらい速いな」と言っているのが聞こえたけど、あまりのんびり進むよりはいいんじゃないかと思って歩いていたのだが、全体の3分の1を過ぎたくらいのところで、後ろから、役員のリボンを付けた裃のおっちゃんが来て、「位置がおかしい」って言い始めた。
そのおっちゃんは正しい事を言っているのだろうし、言っている事はよく分かる・・・・でも、今初めて聞く事だし、あんまりにも上から目線の言い方だったので、思わず言ってしまった。
「そこまで言うんなら、あんたがスピードを調整して位置を合わせればいいやろ。オレたちは、こんな事をやるのは初めてやし、いきなりそんな事を聞かされて、すぐにできるわけがないやろが。」
そのおっちゃんは、一瞬口ごもった後、「ここの係は何をしとるんや」って言いながら、後ろの方へ戻って行った。
で、その後も行列は進み、もうじき角を曲がるという時、さっきのおっちゃんが来て、今度はまったく穏やかな口調で、「次の角を曲がると急に風が強くなるんで、旗を持っている人は煽られんように注意して」と言った。
へー、このおっちゃん、こんなふうに言えるんや、と思って見ていたら、むこうもオレの視線に気がついて、まぁ、『目は口ほどにものを言う』という事か、「危ないと思ったら、旗は倒してもいいからね」とも言ってくれた。
オレは、目上の人に対しては、一応は敬意を表すことにしているんだけれど、時々、こういう事をやってしまうんだよなぁ。
まぁ、自分のやった事は間違っていない、という確信があるけど、でもやっぱり、まわりの雰囲気を悪くするような事は、できればしたくない。
で、その後、日進木工で休憩に入り、他の分隊との時間調整もあって、1時間以上も待たなければならなかったのだけれど、そこを出発する少し前に、そのおっちゃんが話しかけてきて、この辺りは昔から風の強いところで、祭りの行列はいつも大変だった、というような話を、ニコニコとしながら話してくれて、オレもそういう話を聞くのが好きなので、質問しながら聞いていたのだが、まぁ、結果オーライという事かな。
その他にも、行列の中のあるグループの先頭の2人が、趣味の話に熱中してだんだん遅れるようになってきたので、速く進むように言ったら、露骨に嫌そうな顔をされて、その後は完全無視されたけど、スムースに進むようになったので、それで正解だったと思う。(そんなヤツとお友達になる気もないし)
その後、他の分隊と合流して、御旅所での祝詞や獅子舞、闘鶏楽など、結構な時間がかかったけど、5時前には飛騨総社に戻り、無事役目を終了する事ができた。
次にやるのは、何年後になるんだろうな。
以前、ランチに来られた若い女性のグループと話をしていた時、何の話からだったか忘れたが、「オレ、いくつに見える?」って訊いたら、「42歳」って言われて、なんか嬉しかったんだけれど、実際のところ、還暦を意識する歳になると、身体のあちこちに不具合が出てくるのは仕方がない事なんだろうな。
中でも一番痛切に感じるのは『老眼』ですね。
20代の初めの頃、40歳で新聞を読むのに老眼鏡をかけていた先輩から、「目がいいと早く老眼になるぞ」って、よく言われたものだが、視力検査ではいつも1.5か2.0だったオレも、老眼が始まるのが早かったし、速く進んだのだと思う。
だからスマートフォンを使うのも難儀で、以前 iPhone 4s を2年間使ったけど、その後はガラケーと iPad の2台持ち・・・・その iPad でも、拡大しないと見難いのだから大変です。
そんなわけで、前回の投稿から画像のサイズを大きくしたのだけれど、今回からは更に大きくしたので、老眼の人でも見やすくなったんじゃないかと・・・・
で、去年の12月に受けた市の検診で、前立腺癌に関して「要精密検査」という連絡が来たので、1月に精密検査を受けたのだが、今まで病院には全く縁が無く、点滴すら打った事のなかったオレにとって、人生初のCTと点滴、それにMRIの体験をした。


これであと経験してないのは入院だけだなぁ、なんて思っていたのだが、3月に検査の結果を訊きに行った時、問題はなさそうだけれど直接細胞を取り出して検査してみますか、と言われたので、お願いしたら、一晩入院する必要があると言われ、ついに人生初の入院を経験する事になるのかぁ、って思っていたわけです。
と同時に、ここで無入院記録も終わりかぁ、っていう気持ちもあったんですけどね。
で、ゴールデン ウィーク明けに、入院の準備をして病院に行き、最初に血液検査を受けたのだが、その結果を見た先生が、「これなら大丈夫でしょう、今日はもういいですよ。8月にもう一度検査しましょう。」って・・・・
結局、入院する事無く帰って来たわけだけれど、3月からゴールデン ウィークまでの、あの気持ちはなんだったんだろう。
でも、このまま人生が終わる時まで入院を経験する事無く過ごせたら、それは幸せな事なんだろうな、って思いますね。
以前、『ウォーターボーイズ』のDVDを見て「夏までに身体を引き締め直そう」って思っている、と書いたのだけれど、夏のプールシーズンまで2ヵ月となった5月の中旬・・・・始めましたよ。
インターネットで検索した中から、「これは効きそう」と思ったエクササイズを4つ、毎晩寝る前にやる事にした。
慣れるに従って、同じエクササイズをどんどんハードにしていく予定でいたのだが、インターネットで調べると、いろいろ効きそうなエクササイズが出てくるので、実際にやってみて効きそうなものと入れ替えながらやってみた。
どこまで効果があるのかは未知数だけれど、何とかプールに行く時期には間に合うんじゃないかと思ってやっていたわけ。
まぁ、こんな事をわざわざ公言したのも、そうする事で自分にプレッシャーをかけていたわけなんだけど・・・・
ふと思い出して探してみたら、23年前の夏、西伊豆の土肥へダイヴィングに行った時に、THE101のプール横のセンターテラスで撮った写真が出てきた。

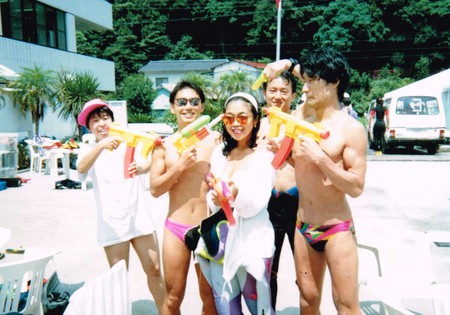
そこに写っているのは、30代前半の自分の身体。
週に3日、赤坂のティップネスに通って、ウエイトトレーニングと水泳をしていた時期なので、きれいに腹筋が割れている。
実を言うと、その当時、この写真を見るまで、自分の腹筋が割れている事に気がつかなかったくらいなので、今考えると、それほど真剣にやっていたわけではなかったのかもしれない。
だから、その写真を見て、その頃の事を思いながら、イメージトレーニングをしていたわけですよ。
まぁ、何とかなるだろう、って。
もっとも、お客さんにはメチャメチャカロリーの高い料理を出しておいて、自分だけシェイプアップするのも、チョッと気が引けますがね。
で、その結果がどうなったかは、近日公開予定の、このブログの後編で見てもらう事にしましょう。
(そんなものは見たくない、という人はスルーして下さい)
毎年、ジャガイモが新物に替わると、水分が多すぎて美味くないので、水分が落ち着くまでニョッキを作るのを止めるのだけれど、それから少し遅れて、真赤なトマトが出回るようになると、入れ替わりに作り始めるのが、トマト入りカルボナーラ。
オレ自身、他所の店で見た事がないので、イタリアでも、ごく限られたところでしか作られていないのだと思う。
一般的なカルボナーラに比べても、味付けはシンプルそのもの。
でも、トマトの旨味が加わる事で、本当に美味くなる。
「普通のカルボナーラより好き」と言われる事が多いけど、オレ自身も、こっちの方がずっと好きです。
去年、料理の出張講習会をやった時も、これがすごく好評だったし。
真赤なトマトが出回る時期だけの『季節限定メニュー』なんだけれど、これを作り始めると、夏が近づいている事を実感します。
キリッと冷やした白ワインを合わせると最高ですよ。
うれしい再会ができた。
スポーツが大嫌いだったオレが、雑誌『ターザン』の取材を受けた事をきっかけに、スポーツにのめりこみ始めた事は、5年も前に『人生を変えた出来事』というタイトルの超長編ブログに書いたのだけれど、まず最初に始めたのが、ウェイトトレーニングと水泳だった。
ウェイトトレーニングに関しては、マシンを買って、自室でやっていたのだけれど、水泳はプールに行かない事には始まらないので、電話帳で三ノ宮から行きやすいスウィミングスクールをいくつか探し、実際に電話で問い合わせてみて、ここにしようと決めたのが『本山スポーツセンター』だった。
三ノ宮から阪神電車で青木まで行き、そこから10分ほど歩くと、本山スポーツセンターはあった。
1986年の秋に行き始めてから、1991年の6月に東京へ行くまで、4年半と少し、週1回の休みの日の夜はたいてい行っていたので、今考えると、本当に真面目に通ったよなぁ、って思う。
休みの日に風邪で熱を出した時も、夜、プールで泳いで来たら、次の朝には熱が引いていたし、イタリアから帰って来た時も、その足でプールに行って泳ぎ、時差ボケを直したし、当時は健康管理のためにプールに行っていたように思える。
で、その本山スポーツセンターのスウィミングスクールで、初期の水慣れから、クロール、バック、ブレストストローク、バタフライと、時間はかかったけれど、泳げるようになるのが楽しかったし、一緒に習っている仲間や、教えてもらうコーチとのフランクな雰囲気が、オレにはすごく合っていたんだと思う。
で、そのコーチには、センターの社員の人と、大学の水泳部員がアルバイトでやっている人がいたのだが、年齢が近い事もあって、水泳部員のコーチから指導を受ける事が多かった。
だから、そういう若いコーチに無理矢理お願いして、センターの水泳のVTRをダヴィングしてもらった事もあったし、そういう関係は良好だったと思う。
オレが東京へ行く事になり、その事は一応みんなには話してあったのだけれど、最後に行くときには、ちゃんとお礼と挨拶をしようと思っていたのに、最後の週に急な用事が入って行けなくなり、みんなに挨拶もできないまま東京へ行ってしまった事が、その後もずーっと心に引っ掛かっていた。
で、5月のある日、ディナーの予約の電話が入ったのだが、日時や内容など、一通り聞き終わったところで、そのお客さんからこう言われた。
「本山スポーツセンターで、アルバイトで水泳のコーチをやっていた者なんですけど・・・・」
オレは一瞬、頭が混乱したね・・・・オレがここで店をやっている事なんか、分かるはずがないんだから。
思わず「どうして分かったの?」って訊いたのだけれど、説明されて納得した。
高山に旅行する事になったので、どこで食事をしようかと探していて、ウチのウェブサイトを見た時に、オレの写真の横顔から、『あの』西野さんに間違いない、と思ったそうだ。
よく顔も名前も憶えていてくれたよなぁ、って感動しましたね。
予約の当日は、お土産を用意して待っていた・・・・で、26年ぶりの再会。
とにかく料理を食べてもらって、デザートも食べ終わったところで、昔の話に花を咲かせた。
まぁ、こういう時って、あぁ、そんな事もあったよなぁ、って話が結構出てくるもので、30年前に戻ったような時間を楽しむ事ができました。
最後に絵の前で記念撮影。
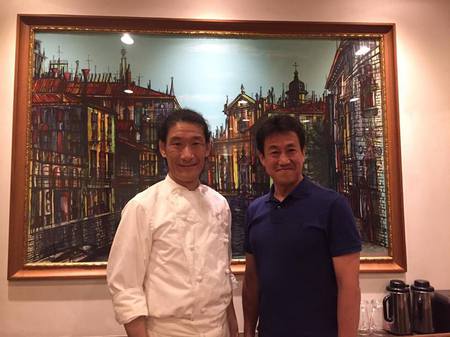
コーチ、本当にありがとうございました。
また来て下さいね。
ヨーロッパの食文化を、映画『スウィングガールズ』に出てきたセリフ風に言うと、こんなふうになる。
「ヨーロッパの食文化は2種類に分けられる。オリーヴ・ワイン文化と、バター・ビール文化だ。」
ところが、北のバター・ビール文化と、南のオリーヴ・ワイン文化の境目にある北イタリアは、その中間とも言うべき、バター・ワイン文化なんですよ。
だから、料理に合わせるには、基本的にワインをお勧めするけれど、バターを多用する料理なので、ビールを合わせるのも悪くないと思う。
ただし、こってりとした料理が多いので、濃厚なビールでないと負けてしまう。
なので、ウチでは『ブラウマイスター』の生をお出ししているわけなのだけれど、これは本当に美味いビールだと思います。
生ビールは、クラスに注ぐ事で商品になるわけですから、注ぎ方はもちろんの事、グラスの状態やサーヴァーのメンテナンスなど、気を遣う点が多いのだけれど、ウチではビールの劣化を防ぐため、樽ごとビールを冷やす、樽冷却式のビールサーヴァーを使っています。
この方式のサーヴァーは、現在では手に入らないそうで、きちんとメンテナンスをしてもらいながら、大切に使っているのですが、この前、ビールが通るホースを新しいものに取り換えてもらったら、なぜか泡の出方が変わってしまい、メンテナンス担当の人にいろいろやってもらったけれど、どうしても納得のいく泡にはならなかった。
先日、その担当の人が、廃棄されたサーヴァーの中から部品を探し出してきれいに磨き上げ、ウチのサーヴァーの部品と交換して、ホースを内径の小さいものに取り換えてくれたら、以前よりもきめの細かい、クリームのような泡が出るようになった。
本当にありがたい事です。
最高の状態のブラウマイスター〈生〉を、ぜひ料理に合わせて飲んでみて下さい。(カウンターで、生ハムやチーズをつまみに飲むのもいいですよ)
ただし、ビールの泡は油に弱いので、飲む前に唇の油を拭き取ることをお忘れなく!!
TAKAYAMA DE KANPAI
高山で乾杯~!
面白い企画なので、参加させてもらいました。
結構な数の店が参加されてますが、その中でもウチは、一番毛色の変わった店なんじゃないかと・・・・
まぁ、ウチの場合、乾杯しながら騒ぐ店ではないし、料理の見た目も素っ気ないし・・・・でも、そういう店が参加している方が、敢えてそういう店を選ぶ楽しさがあって面白いでしょう。
とにかく、楽しんでもらえればいいとは思っていたのだけれど、だれも投稿してくれなかったらどうしよう、と思っていた事も確か。
でも、3名の方が投稿してくださったので良かった。
ウチが紹介されたページは今後も残るそうなので、そちらも見てもらえればいいかと。
おかげ様で、『ラ フェニーチェ 12周年感謝パーティー』は、30名のお客さんに来て頂き、食べて飲んで頂いて、無事終える事ができました。
今年は、常連のお客さんと、世話になっている方に限って声をかけさせてもらったのだけれど、遠くは大分から、わざわざこのパーティーのために来て下さった方もあり、本当にありがたく思っています。
例によって、オレはひたすら料理を作っていたので、料理を出した後は、すべてお客さん任せなのですが、それでもキチンとパーティーが成り立ってしまうのが、ウチのお客さんのすごいところ。
改めて、ウチのお客さんのレヴェルの高さに感心してしまいました。
今回お出しした料理は、次の通りです。
生ハム、サラミ、コッパの盛り合わせ
魚介類のサラダ ニース風
グリーンアスパラのミラノ風
温野菜の焦がしバターソース
カポナータ
パルマ風リゾット
ホウレン草入りラザーニェのボローニャ風
スパゲッティ エトナ風ミートソース
手作りマカロニのソーセージ入りトマトソース
ペンネリガーテの4種チーズソース
スズキの岩塩包み焼き
タイのモンテカルロ風バターソース
オマールと魚介類のワイン蒸し
鶏の魔女風鉄板焼き
ローマ風サルティンボッカ
野菜サラダ トマトドレッシング
パンナコッタ
あと2品ほど用意していたのですが、もう食べられないと言われたので、ここでストップしました。
写真を撮っているヒマがなかったので、料理の画像はなし。
調理場から撮った写真も何枚かあったのだけれど、なぜかピントが合ってなくて、その中でもまともなのがコレ。
まぁ、雰囲気は分かると思いますが・・・・
今年は、例年に比べ、花をもってきて下さった方が少なかったけれど、その代わり、ワインや酒を持ってきて下さった方が多く、それはそれでうれしいものですね。
来年、13周年のパーティーができるように、また1年頑張ってやっていきたいと思っています。
13年目に入ったラ フェニーチェを、これからもよろしくお願いします。
8月の6日と7日は、毎年恒例の『しもいち通りの七夕まつり』・・・・残念な事に今年は、台風接近のため2日目が中止になり、6日だけの営業になりましたが、多くの方に来て頂き、本当に楽しくやらせてもらいました。
途中で急な雨に降られて「もう終わりか」と思ったのに、その後も途切れる事無くお客さんが来て下さった事は、本当にありがたかったですね。
ブラウマイスター、ワイン、スプマンテ、ランブルスコ、イタリアンカクテルetcと、他所では絶対に飲めないであろうものを取り揃えてやっているわけですが、毎年わざわざ、ブラウマイスターを飲みに来て下さる方も何人かみえるし、目の前でカクテルを作るのを喜んで見てくれるお客さんも多いので、年々、メニューが増えていますけどね。
今年はすぐ隣で、初参加の飛騨乃キッチンさんが営業されましたが(FBでは友達になっていたのに、お会いするのは初めてでしたが)、いろいろ話をしながら営業できて、楽しかったです。

飛騨乃キッチンさんは、9時前には完売されてましたが、ウチも土日だった去年よりは少なかったものの、予想以上に売れました。
もう1日やりたかったなぁ、というのが本当のところですが、相手が自然では仕方がない・・・・まぁ、1日楽しませてもらった事で、良しとしておきましょう。
中田酒店の中田祐一君が、営業中の画像をアップしてくれたので、シェアさせてもらいましたが、よく雰囲気がとらえられていますね。
https://www.facebook.com/nakadasaketen/posts/906658882818764
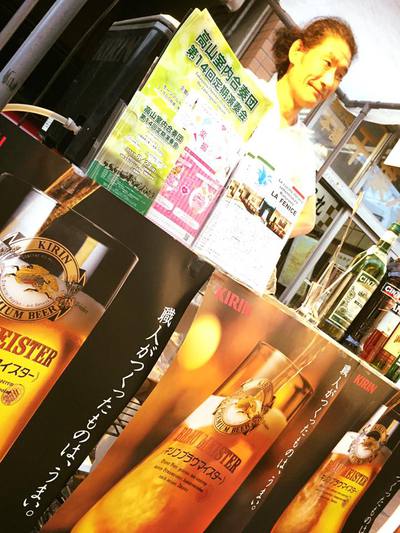



毎年ここでは、パーカにフットボールパンツを組合わせた、オレの定番スタイルでやっているのだけれど、夫妻で今回初めて覗きに来てくれた、ウチの常連で高名なミュージシャンの浦田恵司さん(日本のシンセサイザープログラミングの第一人者で、奥さんは歌手のAZAMIさん)に、「勝ちゃん、今日は面白いスタイルだね」と言われたので、「ミック ジャガーも、こんなスタイルでステージに立っていたでしょう」って答えたら、「確かに」って納得されていた。
毎年、この七夕が終わると、夏が半分終わったな、って思うのだけれど、今年は夏らしい事を、まだ何もやってない・・・・今度晴れたら、プールだな。
長くなったので、続きは「後編」で。
では、また。
Ciao. Arrivederci!!
2017年04月11日
いろいろあって 久しぶり編 その2
Ciao. spockです。
前回の投稿から、もう2ヶ月が経ってしまいましたが、前回の続きの『その2』を、なんとかまとめる事ができました・・・・例によって、長くなりましたが。
去年の後半から最近の事まで、Facebookに投稿したものを手直しして使ったところも結構あるので、これ見た事ある、って思われるかもしれませんが・・・・
やっと、最近の事まで書く事ができましたから、これからは、このブログとFacebookを同時進行で書いていきたいと思っています。
店の事をすべてひとりでやっている現状では、以前のような長い文章を書くのは難しいのですが、時々は、マニアックな超長い文章も書きたいと思うので、そういう時は、長い文章に付き合って下さい。
では、『いろいろあって 久しぶり編 その2』です。
《 3年ぶりの伊豆で 》
今から20年以上も前、スキューバ ダイヴィングにハマっていた事があり、時間が取れなくなって断念したのだけれど、一時はダイヴマスター(プロ)を目指していたほどのめり込んでいた。
忘れもしない94年の3月20日、富戸と伊豆海洋公園を潜るツアーに参加した時、一緒になったメンバーとすごく気が合って、それ以来、いつも一緒に潜りに行ったり、遊びにいったりしていたのだけれど、オレが東京を離れる直前には房総半島をめぐる旅行を企画してくれたり、高山へ遊びに来てくれたりと、今でも付き合いが続いている。
ちなみに、そのメンバーは全員、オレのことを普通に Spock と呼ぶ。
6月のある日、いつもみんなが集まる企画をしてくれるメンバーから、久しぶりに「タライ乗り競走」に出よう、というメールが来た。
タライ乗り競走、正式には『松川タライ乗り競走』は、毎年7月最初の日曜日に、伊東温泉の真ん中を流れる松川を、タライ船に乗って約400m下るレースで、個人戦、団体戦など、いくつかのカテゴリーに分かれて参加できるのだが、3年前に一度参加した事がある。
その時は、前日に伊東に集まって一晩泊り、翌日レースに参加するという予定だったのだけれど、その数日前になって、前日の夜にパーティーの予約が入ったため、当日の朝、出かける事になった。
結局、パーティーが終わってから2時間ほど寝て、3時過ぎに出発し、順調に河口湖大橋を過ぎたところまで行ったのだが、そこで道を1本間違えたらもとに戻れなくなり、頼りにしていた iPhone のナビアプリもリセットされてしまって使い物にならず、自分がどこにいるのか分からないまま、ひたすら伊豆方面に向かってクルマを走らせたが、当日合流する予定の、地元出身のメンバーに助けを求めて、何とか時間に間に合い、個人戦に参加して、完走(?)する事ができた。
そのあとは、久しぶりにみんなと食事をし、3時過ぎには帰途についたのだが、沼津市内を走っている時、東京で世話になった人が沼津に引っ越した事を思い出し、そこへ寄って話をしているうちに遅くなり、結局、高山へ帰り着いたのは、夜中の2時。
丸1日で、650kmを走破するという強行軍ではあったけど、本当に楽しかった。
前回の経験をふまえて、今回は道に迷う事無く行けるように、あらかじめ地図を頭に叩き込み、間違えやすいところもチェックして紙に書いておいて、3時半過ぎ、伊東へ向かって出発した。
途中で2~3回、少しだけ遠回りもしたけど、11時前に、何とか伊東駅に到着。
駅前の駐車場にクルマを停め、スタート地点の『いでゆ橋』に向かうと、みんなが待っていてくれた。
3年前に揃えた黒いTシャツに着替えると、ちょうどオレの名前が呼ばれ・・・・ギリギリ間に合った。

河原に下りていくと、仮装したグループや、浴衣姿の観光客、外人の参加者などでごった返している中、レースが行われていたが、1回のレースに5分程度はかかるので、待ち時間は結構長い。
今回グループで揃えたのは、アラレちゃんの帽子とメガネ・・・・あんまりオッサンに似合うとは思わないが、まぁいいか。
他のメンバーは、すでに団体戦に出た後だったが、結果は散々なものだったらしい。
偶然にも、その時の動画が Youtube にアップされていた。(一番手前のグループ)
で、いよいよ名前を呼ばれ、スタート台へ行く。
5人並んでスタートなのだが、オレは左から2番目・・・・左の方が流れが速そうなので、ちょうどいいかも。
直径1m弱、深さ30cmくらいのタライに乗るわけだが、胡坐をかいて、膝を前につけて乗るように言われる。
意外と不安定で、結構ひっくり返る人が多いのも分かるが、流れに乗ってしまえば、それなりに安定する事は、前回経験済み。
両手に、大きいしゃもじのような櫂を持って、スタートのピストルを待つ。
スタートと同時に、左側の女の子が流れに乗って飛び出し、オレより少し前を行っているのだが、その子が一生懸命掻いた水が、全部オレにかかった。
アッタマにきたんで、こいつだけは絶対に抜いてやる、と思いながら流れに乗って行ったら、いつの間にか先頭に出ていた。
ちょうど半分くらいまで行った時、川の中に何人もの人が立っていたのだが、どうもそのあたりは岩の多いエリアのようで、サポートのために立っているらしいのだけれど、そこへ近づいていっても、全く何もしない。
で、仕方がないので、流れに乗ったまま進んで行ったら、岩に乗り上げた・・・・おっちゃん、見てないで教えてよ。
タライに乗ったまま、押し出してもらってレースに復帰したけど、10秒くらいはロスしたかな。
でも、先頭を譲ることなく、1位でゴールし、1着の旗を受け取った。
その後、大会本部へ行って 参加賞をもらい、後はもらった入浴券で温泉に浸かってゆっくりしようか、と思っていたら、メンバーのひとりが、Spockの名前が出てるよ、って呼びに来た。
で、行ってみると、個人成績の2位のところに、オレの名前とタイムが出ていた。

1位との差は4秒・・・・岩に乗り上げていなければオレが1位だっただろうな、とは思ったけれど、これは仕方がない。
表彰式があるそうなので、全部のレースが終わるまで、待っていなければならないのだが、そういう時って、結構長く感じるものですよね。
で、待っていると、本部のテントが吹き飛ばされそうになるくらいの強風が吹き始め、その追い風で次々に好タイムが出始めたので、ヤバいなぁと思いながら見ていたら、最後の最後で、オレのタイム上回る人が出た。

結局、3位という結果で終わったわけだけれど、毎年参加している人が多い中でのこの結果は、上出来なんじゃないだろうか。

でも、いつかリベンジしないとね。
表彰式で、賞金と賞品を受け取ったけど、もらった賞金5000円は、ガソリン代の一部になったから、まぁ、それでよしとしよう。
参加賞に入っていた入浴券を持って、指定された『東海館』へ行くと、そこは昭和初期に建てられた木造建築の古い旅館で、時間の関係で小浴場に案内されたのだけれど、いかにも昔を感じさせる、味わいのある雰囲気の浴場だった。
で、その後は、3年前と同様に、伊東駅前の居酒屋に行き、食事をしながら、積もる話に花を咲かせ、来年も参加しようという事を決めて、駅前で解散した。
その後は、3年前を思い出しながら、国道414号線(ダイヴィングをやっていた頃、大瀬崎へ行く時に通った懐かしい道だ)を通って沼津市内へ入り、港大橋を渡って、『沼津みなとアートビル』へ行き、1階の和風カフェ『ねこや』へ入る。
名前の通り、この店には何匹もの猫がいて、猫好きの人にはたまらない店なんだけど、実はこのビルの中には、全部で20匹近い猫がいるのである。
で、優美子さんと、3年ぶりの再会。
優美子さんは、オレの大好きな画家で、スウェーデンのアトリエにまで遊びに行った事のある、中島由夫先生の絵を中心に扱うギャラリーをやってみえて、赤坂で働いていた時に本当に世話になったのだが、まるで親戚の叔母さんのようにオレのことをかわいがってくれた。
どうしようもないくらい落ち込んだ時、優美子さんに電話すると、「晩御飯を作って待っているから、いらっしゃい」と言ってくれて、中央林間駅近くの、そのギャラリーへ行って話をしていると、そのホンワカした雰囲気に、いつの間にか気持ちが落ち着く・・・・本当に何回も助けてもらった。
数年前、ずっと手伝っていた圭三さんと一緒に、ギャラリーごと沼津へ移転し、和風カフェの『ねこや』は、地元の人が集まる人気店になっているようだが、これも優美子さんの人柄のせいかな。
前回(3年前)は、沼津市内を走っている時に急に思いついて行ったので、お土産も持たずに行ったのだけれど、今回は谷松のこくせんを持って行った。
前回は話だけして帰ったのだが、今回は「朝早く起こしてあげるから、今夜は泊まっていきなさい」という言葉に甘える事にした。
この沼津みなとアートビルのすぐそばには、沼津港深海水族館があり、その一角には居酒屋やカフェなどが立ち並んでいて、その巨大な居酒屋で晩御飯をごちそうになったのだが、話のタネにという事で、深海魚のグリルを頼んでみた。
ハッキリ言って、特に美味いというわけではなく、ホントに『話のタネ』だったが、その他のものは美味かった。

優美子さんの部屋で休んでいると、1匹の猫がオレのそばに来て、じっとオレを見ている。
他の猫たちは、侵入者であるオレに全く興味を示さないのに、その猫だけ、なんでだろうと思っていると、優美子さんに「その子は中央林間から連れてきたの、覚えてるでしょう」と言われ、思い出した。
ある時、優美子さんと話しているうちに終電が出てしまい、その部屋に泊めてもらう事になったのだが、オレの布団を敷くと、優美子さんは友達のところへ泊まりに行って、その部屋にはオレと3匹の猫だけになり、夜中にその猫たちが布団の中に潜り込んできて、朝まで一緒に寝た猫のうちの1匹だというわけ。
ちゃんと仲間だと覚えているんだね。
翌朝、5時に起きて、屋上に上がってみると、富士山が大きく見えた。
少し霞んではいたけれど、やっぱり日本一の山だな。

朝食をもらって、6時過ぎに出発し、246-138-137-甲州街道とガンガン飛ばしながら高山へ向かったのだが、なんとか11時過ぎに到着・・・・昼の営業に間に合った。
今年の『タライ乗り競争』は7月2日で、ぜひまた参加したいと思っているのだが、その前日がウチの12周年感謝パーティーなので、行けるかどうか微妙なところなんだよなぁ・・・・
さて、どうなることやら・・・・
《 海に行きたい!! 》
考えてみると、2003年の夏に、伊豆の鄙びた海水浴場に行って以来、一度も海に行っていないので、「今年こそ店を1日休んで海に行こう」と思っていたのだけれど、いろいろ調べてみた結果、「北陸のハワイ」水島でシュノーケリングをする事に決めた。

そんな話を店に来た友人にしたら、水島ならオレも行きたい、と言うので、オッサンふたりで行くのもどうかとは思ったけれど、一緒に行く事になり、急遽アマゾンから簡易テントを取り寄せたり、シュノーケリングの機材を引っ張り出してきたりした。

ところが前日になって、友人から(文字通りの「家庭の事情」というヤツで)急に行けなくなったと言われた。
まぁ、仕方がないんで、ひとりで行こうかと、機材をバッグに詰めようとしたら、なんと、シュノーケルがバラバラに壊れた。

20年以上も前に買ったやつだから、素材の「経年劣化」なんだろうけど、これは「行くな」という天からのお告げなんだろうな、と思ったので、残念だけど行くのを諦めた。
当日、店は開けたのだけれど、夜、友人はわざわざ謝りに来てくれて、ワインを飲んで帰った。
いいヤツだな。(この友人とは、世界で活躍するテノール歌手、と言えば分かるでしょ)
《 マニアックなスウィムパンツ 》
水島行のフェリーは、8月いっぱい運航しているそうなので、なんとか行きたいと思っていたのだけれど、ありがたい事に予約が続いたため、行けそうにもなく・・・・でも、あんまりいい天気だったので、昼の休憩時間に、市民プールへ行ってきた。
3年ぶりだったけど、入場料は変わらず、250円!!

競泳用のビキニで人前に出るにはそれなりの覚悟がいるけど、その緊張感のおかげで、若い頃とあまり変わらない体形でいられるのだと思う。
まだ『ミカエルの菱形』もハッキリ見えるけど、歳をとった分、身体に丸みが出てきた事も確か・・・・引き締めないといけないな。
早速泳いでみたけど、久しぶりに泳ぐせいか、泳ぎ方を忘れているなぁ。
オレはブレストストローカー(平泳ぎ専門)なんだけど、以前は50メートルを、水中でのひと掻きひと蹴りの後、22ストロークで泳いでいたのに、水がキャッチできていない上、腹筋の使い方が悪いせいか、上下の動きのない、平面的な泳ぎになってしまって、効果的に水を蹴る事ができていないため、24ストロークに増えてしまった。
300m泳いだあたりで、ようやく感覚が少し戻ってきて、22ストロークに戻ったけど、なんかまだ納得できないなぁ・・・・
でも、そのあと仕事もあるので、後半はプールサイドに寝っ転がって、のんびりと過ごした。
プールから上がって更衣室へ向かう時、たまたま目が合ったスタッフの人と挨拶した事から、少し立ち話をしていると、その人がオレの穿いているパンツを指差して、「今はそんなのがあるんですねぇ」って言うと、さらに素材を確かめるように触ってみて、「これ、水球用でしょう。さっきプールサイドで見て気になっていたんだけど、水球やってたんですか?」って訊かれた。
オレが穿いていたのは、水中で掴まれても破れないように特殊コーティングされた、独特の光沢をもつ水球用パンツ(ウォーターポロパンツ、通称『ポロパン』)で、素材の性質上、水に入った時に水圧で緩む事がないので、その点を気に入って使っているわけなんだけれど、その事を話したら、水球をやっていたというその人は、「確かに」って納得してましたね。
(後で知人が教えてくれたのだが、このスタッフの人は、西小学校で着衣水泳の講師をしてみえるそうで、バルセロナ オリンピックの時、水球のナショナルチームで出場直前までいった(予選の最後で敗退した)というスゴイ人だそうだが、そんな人が、なぜ高山にいるのか不思議ではあるけれど、もし高山に深いプールがあったら、コーチとして子供たちに水球を教えてもらえるんだろうけどね。)
で、オレが気に入って穿いているこの『ポロパン』は、スポーツ用品メーカーのミズノが作っている、れっきとした競技用アイテムなのに、インターネット上で「フェティッシュアイテム」扱いされている事もあって、これを穿いてプールで泳ぐのには、ある種の勇気がいるみたいなのだけれど、オレは他人の目より自分の感覚を優先する人間なので、全く気にせずに穿いているわけです。
自分にとってベストのスウィムパンツを見つけて喜んでいたのだが、すごく残念な事に、ミズノがこのタイプ(RQ-632)の競泳用・水球用ビキニの製造中止を発表した。(その理由は、本来の用途ではない使い方をしている動画や画像が、インターネット上で多く見られるようになったからだと言われている。実を言うと、このポロパンは、そっち系のショップで見つけて買ったのだけれど、今後はミズノ製のものを扱う事はなさそうなので、もうそのショップで買う事はないだろう。)
あわてて、自分のサイズで残っていた最後の1枚を手に入れたので、今のところ全部で3枚持っているけど、ポロパンは、劣化しやすいポリウレタンでコーティングされているため、寿命があまり長くないらしく、少しでも寿命を伸ばすように扱わなければならないわけですよ。

もっとも、9年前に買ったポロパンは、今もまだ使える状態なので、意外と長く使えるのかもしれませんが・・・・
聞いた話では、密封袋に入れて空気を抜いた状態で保存するといいらしいのだが、どんなものなのか、やってみるかな。
《 定期演奏会、無事終了 》
おかげ様で、高山室内合奏団 第13回定期演奏会を無事終了する事ができました。
ありがとうございました。




実のところ今年は、演奏会までにトラブルが続きました。
例年より選曲が遅れた事から始まり、ヴァイオリン独奏をお願いしていた村中さんに、腱鞘炎でドクターストップがかかったため、曲が変更になり、極めつけは、演奏会の2日前に指揮者の鴨宮さんが急遽入院し、前日夜のゲネプロ(総練習)にギリギリで退院するという、今考えても、よくできたよなぁ、って感心するくらいの綱渡り状態が続きました。
(画像は、ゲネプロと、当日朝のリハーサルのものです)
ヴァイオリンの人達。

低音域を支えるコントラバス。

指揮者の鴨宮さん。病み上がりで、結構しんどそう。

毎年参加してもらっている、木管楽器の人達。

岡山県から毎年来てくれる、ヴィオラの和田さん。

オレの前にヴィオラを弾いていた小淵さん。オレが借りて弾いていたのは、この画像のヴィオラ。

チェロの人達。

指揮者と、ステージマネージャーの打ち合わせ。

フルートとオーボエの人達。

本番直前の舞台袖。


また、毎年、8月最後の日曜日は、行事が重なるのですが、今年はそれが特に多く、クラシックの演奏会だけでも3つ重なったため、お客さんが分散してしまうという、あまりありがたくない状況でもありました。
そんな状況の中、例年より少なかったとはいえ、予想していたより多くのお客さんに来て頂けた事を、本当にありがたく思うとともに、例年以上に多数のアンケート用紙が返ってきて、多くのご意見を頂けた事は、団員一同、心から感謝致しております。
例年に比べて演奏時間が短くなり、物足りなく思われたのではないかと心配していたのですが、今までで一番良かった、と言って下さった方もおられた上、アンコール曲(ワーグナーの歌劇ローエングリン第2幕から エルザの大聖堂への行列)の演奏を、多くの方が喜んで下さったようで、ホッとしました。
プログラムのあいさつにも書いたように、今年の定期演奏会では、ベートーヴェンの交響曲第2番に挑戦します。
今年も8月最後の日曜日に定期演奏会がありますので、今から予定に入れておいて下さい。
お待ちしております。
高山室内合奏団 第14回定期演奏会
2017年8月27日(日) 飛騨芸術堂にて 14時開演 入場無料
予定演奏曲目
レスピーギ リュートのための古風な舞曲とアリア 組曲第3番
シンディング 古風な様式の組曲 作品10
ヴァイオリン独奏 村中 一夫
ベートーヴェン 交響曲第2番 ニ長調 作品36
《 高山でアメフトを 》
10月2日に、中山公園陸上競技場で行われた「富士通フロンティアーズ アメフト体験教室」を見てきました。
市内の小中学生を対象に、希望者を募って行われたようですが、参加希望者に、スポーツ少年団の団員が加わって、30人ほどでの開催になったとの事です。



社会人になってから、プライヴェートチームで一から教えてもらいながらアメフトをやったオレからすれば、子供のうちにこういう経験をできるのは、本当に羨ましい。
ただ、全く不可解なのは、その参加申込用紙を見た人以外には全く知らされていなかった事。
オレは、上仲剛司君が電話をくれたので知ったけど、高山市全体に告知されていれば、見に行く人も、もっと多かっただろうと思うし、少しでも多くの人に見に来てもらえるようにする事が、わざわざ来てくれたフロンティアーズの人達に対しての礼儀だと思うのだが・・・・
最後に応援グッズをもらいに行った時、プレイヤーやスタッフに「高山まで来て頂いて、本当にありがとうございます」と言って頭を下げてきたけど、今一つ吹っ切れない思いではありますね。

でも、30年以上も前から「高山にアメフトチームを作ってデンヴァーと交流したい」と言っては、みんなにスルーされていたオレからすれば、すごい進歩だと思います。
さて、その「高山にアメフトチームを作る」という話なのだけれど、夢物語ではなくなってきた。
ウチのお客さんに、日大フェニックスで日本一になり、現在は、本業の傍ら、大学でコーチをしている方がおられるのだが、近い将来、高山でアメフトを教えたいと言われた。
過去に、多くの高校生をアメフトの推薦で大学へ進学させた実績があり、当然そのための技術や経験、それにコネも持っておられるわけだし、高山を活性化させる方法なども、かなり考えておられる方なので、期待できると思っている。
その内容については、いずれ書く事になると思うので、詳細はその時に。
《 絵を1枚、店内に掛けました 》

冬のパリを描いた、荻須高徳のリトグラフで、バブルの頃に手に入れてからずっと持っていたのですが、イタリア料理の店にフランスの風景画を掛けるのもどうかと思って、掛けるのを躊躇していたわけです。
もっとも、オープンしてから3年位の間、『南フランス』というタイトルの絵を飾っていた事があって、その時は「南フランスと北イタリアは緯度的に同じようなところだから」と言い訳していたのだけれど、さすがにパリの風景画となるとねぇ・・・・
この前、あるお客さんにこの絵を見せたら、絶対飾った方がいいよ、と言われ、その言葉に背中を押されて掛けてみたのですが、これはこれで、結構いいんじゃないかと。

カウンターの横の壁にピッタリと納まったのを見て、ここに掛けるためにオレのところに来たんだ、と勝手に思ったりして・・・・
《 料理の道へ進むきっかけのひとつ 》
先日、ふと思いついて検索してみたら・・・・出てきたよ、『世界の料理ショー』
もう40年も前、オレが高校生の頃の平日(確か水曜日だったと思う)の昼間にやっていたので、祝日か学校が休みの時にしか見れなかったのだけれど、それでも4~5回は見たと思う。
グラハム カーが、かなり適当ながらも、いかにも楽しそうに料理をしているのを見た事が、オレが料理の道に進むきっかけのひとつになったのは間違いない。
もっとも、料理の事より、最初の小噺の事をしっかりと覚えていたりするんだけど。
調理師学校で教えていた時、『世界の料理ショー』のノリでやったら面白いだろうな、って思っていたのだけれど、今でも結構本気で、『世界の料理ショー』のノリで料理講習会をやってみたい、と思っている。
最後にお客さんを引っ張り込んで、一緒に食べながら感想を聞くなんて、すっごく楽しいと思うね。
《 コンサート 》
12月4日、さくらホールで行われた、『水口 聡 with オーケストラ アンサンブル金沢 テノールとストリングスの競演』は、本当にすごかった。

満席とは言えない入りだったのが、ちょっと残念だったけど、水口は「空席以外は満席だ」と言って客を笑わせていた。
オーケストラだけの演奏をはさみながら、9曲が歌われたのだけれど、水口はノリノリで、声を張り上げて高音を目いっぱい伸ばし、客席からだけではなく、オーケストラの団員からも拍手を受けていた。
弦楽器16人のアンサンブルで、指揮者なしの伴奏のため、少しずれた部分もあったけど、そんなのは些細な事で、最後まで本当に楽しませてもらった。
水口は、リハーサルの時まで、指揮者(過去に共演した事のある井上道義さん)が来るものだと思っていたそうなのだが、指揮者なしで合わせるのには、それなりに苦労したらしい。
終演後、楽屋へ行って、持って来たスプマンテを渡したら、今夜行ってもいいか、と言われたので、合奏団の練習が終わった9時半に、という事で話は決まった。

で、9時半に総勢6人が集まり、途中からオレも加わって、ワインを飲みながら、コンサートの事や音楽の事など、熱く語り合っているうちに、気がついたら12時近くになっていた。




自分の身近に、こういうすごい歌手がいる事や、楽しみを共有できる仲間がいる事は、本当に幸せだと思う。
《 クリスマス ファミリーコンサート 無事終了 》
おかげ様で、高山室内合奏団のクリスマス ファミリーコンサートは、多くの方々にご来場頂き、盛況のうちに無事終了する事ができました。
ありがとうございました。


今年も例年と同様に、飛騨市民病院(非公開)、船津座、高山市民文化会館での3公演を行いましたが、高山、神岡公演ともに、準備していた席がいっぱいになり、特に高山では、立ち見の方が結構おられたので、休憩中に追加の椅子を用意しましたが、来て頂いた皆様には、本当に感謝しております









今年は、新しい曲を多く取り入れた事もあり、練習不足かな、と思っていたのですが、思っていた以上に上手くいったというか、結構弾けていたと思います。
また、いつも高山室内合奏団の演奏会で、ステージマネージャーとして取り仕切ってもらっている、伊藤健生さんに、歌手として『世の人忘るな』を歌ってもらいました。
いつも裏方なので、今回は一番目立つ役をやってもらったわけです。
高山公演では、毎年恒例の(株)なべしまさんの協賛による、出来立てポップコーンが大人気で、かなりの量を追加で作ってもらいました。

今年も司会をやりましたが、船津座では、なぜかマイクが使えず、声を張り上げて話していたら、結構かみましたが、2日目の高山公演では、マイクも使えたし、馴れた事もあってか、リラックスして、大部分をアドリブでやれたので、よかったのではないかと・・・・
このコンサートの事は、13日の中日新聞に取り上げられましたが、写真の右端に、オレが写ってました。

《 クリスマス 》
毎年、12月に入ると、世の中はクリスマス一色になるし、特にこの業界では、一大イヴェントと言ってもいいくらいの扱いになるわけだが、ウチはここ何年か、全く『クリスマス』には関係なく営業している。
もちろん、クリスマスメニューをやってほしいと言われれば、喜んでやらせてもらうし、薪ストーヴを焚いたり、中庭に電飾をつけたりして、雰囲気を盛り上げ、全力でサーヴィスしますよ。

でも、オレの方から「クリスマスメニューはどうですか?」とは言いたくない。
だって、仏教徒のオレがそんな事を言ったら、めちゃくちゃウソ臭いでしょ。
まぁね、客を集めるためには宗教の違いなんか構ってられない、というのが大多数の日本人の考え方なのかもしれないし、世の中とはそういうもの、と言ってしまえばそれまでなんだけど・・・・
でもオレは、やっぱり正直に生きたいですね。
《 発表会 》
2月26日、今年も新宮の教会で、ヴァイオリンの発表会がありました。
毎年の事とはいえ、やっぱり緊張しますね。
今年選んだ曲は、ヴィヴァルディのイ短調のコンチェルト。
毎年誰かがやる曲なので、敢えて避けていたんだけれど、先生に「ヴァイオリンをやる以上避けて通る事ができない曲でしょう」って言われて、まぁ確かにそうだなぁ、って納得したので、挑戦する事にしたわけです。

で、教本に載っている楽譜を見ながら練習していたのだけれど、参考にと思って、大好きなヴァイオリニスト、ヘンリク シェリングの演奏を聴いてみたところ、なんか違う・・・・フレージングだけでなく、音程も結構変わっている。
楽譜を無料でダウンロードできるサイト『ペトルッチ』で調べてみたところ、教本に載っている楽譜は、ヴィヴァルディのオリジナルに、かなり手を入れたものだと分かった。
おそらく、スズキメソッドあたりが、練習用に変えたものなんだろう。
そう分かったら、オリジナルでやろうと思い、先生に言うと、いつものように半ば呆れながら、「それはいいけど、これは難しいよ」って言われた。
一見、オリジナルの方が簡単そうに見えるのだが、4音、あるいは8音を、移弦しながら一弓でレガートで弾かなければならないところが結構あって、これをきれいに弾くのが難しい・・・・音が途切れたり、雑音が混じったりしやすいのだ。
教本に載っている楽譜は、そこを上手くごまかせるようにしてあるんだな。
でも、敢えてやってみようと決心して練習はしたものの、やっぱり手強いなぁ。
本来、速いテンポで弾くように書かれている曲なのだけれど、技術的に追いつかないので、ゆっくり目のテンポで弾くと、逆に粗が目立ちやすくなるところがあったりして、途方にくれたり・・・・
そんなこんなで、なんとか最後までたどりつけるようになり、本番では、多少のミスがあっても、最後まで弾ききれればいいかな、と開き直って構えていた。
本番当日の午前中にリハーサルをやったけど、まぁこんなものかな、といったところ。
完璧には程遠いけど、なんとか弾き通せるかな、と・・・・
本番は、午後1時からなんだけれど、少し早めに行ったら、もうみんな来ていた。
オレの出番は、後ろから3番目・・・・オレより上手い人の方が多いんだから、もっと前の方が気がラクなんだけど、なぜか毎年、最後の方なんだよね。
出番を待っているうちに、緊張感だけがどんどん高まっていくから・・・・

いよいよオレの出番。
ステージに上がって、まず、これから演奏するのがヴィヴァルディのオリジナル版で、教本に載っているのとは別のものである事を話すと、一部の人が興味を持ったみたい。
で、演奏を始める。
緊張していたせいか、いつもより速めのテンポで合図を出してしまい、ちょっとヤバイかな、と思いながら弾いていたのだけれど、やっぱり、指が追いつかずにとちったところが何ヶ所かあった。
曲の半分が過ぎ、最初のテーマが戻ってきたところで、急に伴奏と音が合わなくなった。
あれっ、違うところに入ってしまったかな、と思ったら、伴奏の細江さんが「ごめんなさい」って言って、伴奏を止めた。
後で聞いた話では、伴奏譜のページをめくっているヒマがない曲なので、全ページを開いて譜面台に置くはずだったのに、一箇所折りたたんだままになっていたそうだ。
どこから弾きなおそうか、って言ったら、最初からやりましょう、って言われて、結局、もう一度最初から弾く事になった。
1回目の方が上手くいったところも、2回目の方が上手くいったところもあったけど、なんとか最後まで弾き通す事ができたので、良しとしておこう。
聴きに来ていた人から「長く弾けてよかったね」って言われたけど、こっちはもう、大変なんですから。

発表会の後の反省会では、みんな、来年こそ練習してもっと上手く弾けるようにしたい、って言うんだけれど、なかなかそれができないんだよなぁ。
でも、目標は少し高めにして、それを超える事で上手くなるわけだから、やるしかないんですけどね。
オレには、いつか弾けるようになりたいと思っている曲があるんだけれど、それが超難曲で、いつだったか先生の前で少しだけ弾いたら、なにやってるの?、って言われてしまった。
全く曲として聴こえなかったみたい。
まぁ、少しずつ練習して、身体で憶えるしかないんですけどね。
それが、この曲。
まぁ、いつかは弾けるように、がんばりましょう。
《 ウォーターボーイズ 》
オレの大好きな映画『ウォーターボーイズ』・・・・突っ込みどころは結構あるけれど、「思い入れ」と「ノリ」と「勢い」で駆け抜ける潔さは、実にイイ!!
2月の終わりに、初回生産限定デジパック仕様のDVDがメチャメチャ安く売られているのを見つけて、思わずポチってしまったのだが、それが届いたので、ホールのスクリーンにプロジェクターで投影して大画面で観た。(確定申告でバタバタしているのにねぇ)

長期の合宿までして練習を重ねた出演者たちが、実際に観客の前で演技をして撮影された10分に及ぶ演技のシーン(下の動画の1:16:35から)は、何回観ても惹き込まれる。(下の動画は音が少し遅れるし、著作権絡みのせいか、一部の音声が消えている)
昔懐かしいベンチャーズの『ダイヤモンド ヘッド』に合わせての陸ダンスから始まり、『カルメン』前奏曲から、シルヴィー ヴァルタンの『あなたのとりこ』での水中でのフォーメイションシーンのスゴさもさる事ながら、みんなで出し合った意見をすべて取り入れて、陸上と水中の両方ではじけまくる、Only you~愛のしるし~学園天国、と続くあたり(1:20:57から)は、後のテレビドラマシリーズで、さらに高度なシンクロの技術を持ってしても超える事のできなかった、最高のパフォーマンスシーンだと思っているし、そのために張り巡らされた伏線には、ホント、感心してしまう。
(映画版、テレビドラマ版、テレビドラマ版2を見比べると、後のものほどシンクロ技術のレヴェルは高くなっているのだが、そこから受ける「感銘度」は、後のものほど低くなるのが皮肉ではある。)




マニアックな見方になるけれど、この映画でのボーイズのビキニの穿きこなし方は、競泳用といえばビキニしかなかった時代に水泳をやっていたオレの目から見ても、実に様になっていると思う。
実際のところ、本当に「泳げそう」に見えるのは、2サイズ以上小さめのものを尻の割れ目が少しだけ見えるくらいに穿く、というのがビキニ時代のスウィマーの一致する認識だと思うが、ボーイズが(サイズはともかく)そこをキチンとおさえた穿き方をしているのは、本当に解った人が指導したからだろうし、後のテレビドラマ版で使われたArenaのものよりシャープなフォルムの旧Speedo(現Mizuno)のビキニが使われているのもイイ!!
自分の目標の1つに「いつまでもビキニの似合う身体でいる事」というのがあるので、オレは今でもプールでは競泳用のビキニしか穿かないし、そのおかげで何とか体形を維持できていると思っているけれど、改めてこの映画を観た今、夏までに身体を引き締め直そう、って思っている。

と、Facebookに書いたら、それを読んだお客さんに言われた。
「あのボーイズの年齢設定って17才でしょ。40才も若い子に対抗意識を持つのってどうなの?」
大人気のなさでは誰にも負けない事は、よ~く分かっているんですけどね・・・・まぁ、ハードルは高くしておいた方が、下をくぐりりやすいですから・・・・
《 久しぶりにラザーニェを 》
ウチのお客さんを、飛騨地区の人と、それ以外の人に分けると、後者の方が多い事は分かっていたのだが、ここ2年ほどに関して言えば、ディナーを予約して来店されるお客さんの85%以上が飛騨地区以外の人なんです。
さらに言うなら、年に2回以上、予約を入れて下さる方も、飛騨地区以外の人が圧倒的に多く、岐阜、名古屋はもとより、東京、横浜、金沢、富山、大阪、神戸、広島などから、定期的に予約を入れて下さる方がおられる事を、本当にありがたく思うわけです。
まぁ、専門店なんていうのは、マニアックな、というか、ある程度解った人を対象にやっているわけですから、高山の人でウチに来てくれる人が限られるのは当然の事なんだけれど、ちょっと寂しい気もする。
でも、州ざき、角正、萬代へ普段から出入りしている人が高山にどれだけいるか、と考えると、まぁ、そんなものなんでしょうね。
先日、年に3~4回、名古屋から来て下さるお客さんが、誕生日に予約を入れて下さったのだが、ラザーニェをリクエストされたので、久しぶりに作った。
ラザーニェって、結構手間がかかるのだが、まずはホウレン草を練り込んだパスタを作るところから始める。


ミートソースには、ベシャメルソースを混ぜておき、重ねる時に、エメンタールと炒めたハムを載せる。


実を言うと、ラザーニェの出来を決めるのは、このソースの混ぜ方だったりする。
4段重ねたら、最後にベシャメルソースで覆って完成。



Lasagne verdi alla bolognese.
グリーン ラザーニェのボローニャ風
オーヴンから出したらすぐにお客さんのところへ持っていくので、焼き上がりの画像はナシ!!
あと3人前ほど残ってますよ。
例によって長くなりましたが、最後のラザーニェの話を書き終わったところで、久しぶりに、「書いたなぁ」って気がしました。
上にも書いた通り、これからはFacebookと同時進行で、ちょくちょく書いていこうと思っていますので、時々覗いてみて下さい。
では、また。
Ciao. Arrivederci!!
前回の投稿から、もう2ヶ月が経ってしまいましたが、前回の続きの『その2』を、なんとかまとめる事ができました・・・・例によって、長くなりましたが。
去年の後半から最近の事まで、Facebookに投稿したものを手直しして使ったところも結構あるので、これ見た事ある、って思われるかもしれませんが・・・・
やっと、最近の事まで書く事ができましたから、これからは、このブログとFacebookを同時進行で書いていきたいと思っています。
店の事をすべてひとりでやっている現状では、以前のような長い文章を書くのは難しいのですが、時々は、マニアックな超長い文章も書きたいと思うので、そういう時は、長い文章に付き合って下さい。
では、『いろいろあって 久しぶり編 その2』です。
《 3年ぶりの伊豆で 》
今から20年以上も前、スキューバ ダイヴィングにハマっていた事があり、時間が取れなくなって断念したのだけれど、一時はダイヴマスター(プロ)を目指していたほどのめり込んでいた。
忘れもしない94年の3月20日、富戸と伊豆海洋公園を潜るツアーに参加した時、一緒になったメンバーとすごく気が合って、それ以来、いつも一緒に潜りに行ったり、遊びにいったりしていたのだけれど、オレが東京を離れる直前には房総半島をめぐる旅行を企画してくれたり、高山へ遊びに来てくれたりと、今でも付き合いが続いている。
ちなみに、そのメンバーは全員、オレのことを普通に Spock と呼ぶ。
6月のある日、いつもみんなが集まる企画をしてくれるメンバーから、久しぶりに「タライ乗り競走」に出よう、というメールが来た。
タライ乗り競走、正式には『松川タライ乗り競走』は、毎年7月最初の日曜日に、伊東温泉の真ん中を流れる松川を、タライ船に乗って約400m下るレースで、個人戦、団体戦など、いくつかのカテゴリーに分かれて参加できるのだが、3年前に一度参加した事がある。
その時は、前日に伊東に集まって一晩泊り、翌日レースに参加するという予定だったのだけれど、その数日前になって、前日の夜にパーティーの予約が入ったため、当日の朝、出かける事になった。
結局、パーティーが終わってから2時間ほど寝て、3時過ぎに出発し、順調に河口湖大橋を過ぎたところまで行ったのだが、そこで道を1本間違えたらもとに戻れなくなり、頼りにしていた iPhone のナビアプリもリセットされてしまって使い物にならず、自分がどこにいるのか分からないまま、ひたすら伊豆方面に向かってクルマを走らせたが、当日合流する予定の、地元出身のメンバーに助けを求めて、何とか時間に間に合い、個人戦に参加して、完走(?)する事ができた。
そのあとは、久しぶりにみんなと食事をし、3時過ぎには帰途についたのだが、沼津市内を走っている時、東京で世話になった人が沼津に引っ越した事を思い出し、そこへ寄って話をしているうちに遅くなり、結局、高山へ帰り着いたのは、夜中の2時。
丸1日で、650kmを走破するという強行軍ではあったけど、本当に楽しかった。
前回の経験をふまえて、今回は道に迷う事無く行けるように、あらかじめ地図を頭に叩き込み、間違えやすいところもチェックして紙に書いておいて、3時半過ぎ、伊東へ向かって出発した。
途中で2~3回、少しだけ遠回りもしたけど、11時前に、何とか伊東駅に到着。
駅前の駐車場にクルマを停め、スタート地点の『いでゆ橋』に向かうと、みんなが待っていてくれた。
3年前に揃えた黒いTシャツに着替えると、ちょうどオレの名前が呼ばれ・・・・ギリギリ間に合った。
河原に下りていくと、仮装したグループや、浴衣姿の観光客、外人の参加者などでごった返している中、レースが行われていたが、1回のレースに5分程度はかかるので、待ち時間は結構長い。
今回グループで揃えたのは、アラレちゃんの帽子とメガネ・・・・あんまりオッサンに似合うとは思わないが、まぁいいか。
他のメンバーは、すでに団体戦に出た後だったが、結果は散々なものだったらしい。
偶然にも、その時の動画が Youtube にアップされていた。(一番手前のグループ)
で、いよいよ名前を呼ばれ、スタート台へ行く。
5人並んでスタートなのだが、オレは左から2番目・・・・左の方が流れが速そうなので、ちょうどいいかも。
直径1m弱、深さ30cmくらいのタライに乗るわけだが、胡坐をかいて、膝を前につけて乗るように言われる。
意外と不安定で、結構ひっくり返る人が多いのも分かるが、流れに乗ってしまえば、それなりに安定する事は、前回経験済み。
両手に、大きいしゃもじのような櫂を持って、スタートのピストルを待つ。
スタートと同時に、左側の女の子が流れに乗って飛び出し、オレより少し前を行っているのだが、その子が一生懸命掻いた水が、全部オレにかかった。
アッタマにきたんで、こいつだけは絶対に抜いてやる、と思いながら流れに乗って行ったら、いつの間にか先頭に出ていた。
ちょうど半分くらいまで行った時、川の中に何人もの人が立っていたのだが、どうもそのあたりは岩の多いエリアのようで、サポートのために立っているらしいのだけれど、そこへ近づいていっても、全く何もしない。
で、仕方がないので、流れに乗ったまま進んで行ったら、岩に乗り上げた・・・・おっちゃん、見てないで教えてよ。
タライに乗ったまま、押し出してもらってレースに復帰したけど、10秒くらいはロスしたかな。
でも、先頭を譲ることなく、1位でゴールし、1着の旗を受け取った。
その後、大会本部へ行って 参加賞をもらい、後はもらった入浴券で温泉に浸かってゆっくりしようか、と思っていたら、メンバーのひとりが、Spockの名前が出てるよ、って呼びに来た。
で、行ってみると、個人成績の2位のところに、オレの名前とタイムが出ていた。
1位との差は4秒・・・・岩に乗り上げていなければオレが1位だっただろうな、とは思ったけれど、これは仕方がない。
表彰式があるそうなので、全部のレースが終わるまで、待っていなければならないのだが、そういう時って、結構長く感じるものですよね。
で、待っていると、本部のテントが吹き飛ばされそうになるくらいの強風が吹き始め、その追い風で次々に好タイムが出始めたので、ヤバいなぁと思いながら見ていたら、最後の最後で、オレのタイム上回る人が出た。
結局、3位という結果で終わったわけだけれど、毎年参加している人が多い中でのこの結果は、上出来なんじゃないだろうか。
でも、いつかリベンジしないとね。
表彰式で、賞金と賞品を受け取ったけど、もらった賞金5000円は、ガソリン代の一部になったから、まぁ、それでよしとしよう。
参加賞に入っていた入浴券を持って、指定された『東海館』へ行くと、そこは昭和初期に建てられた木造建築の古い旅館で、時間の関係で小浴場に案内されたのだけれど、いかにも昔を感じさせる、味わいのある雰囲気の浴場だった。
で、その後は、3年前と同様に、伊東駅前の居酒屋に行き、食事をしながら、積もる話に花を咲かせ、来年も参加しようという事を決めて、駅前で解散した。
その後は、3年前を思い出しながら、国道414号線(ダイヴィングをやっていた頃、大瀬崎へ行く時に通った懐かしい道だ)を通って沼津市内へ入り、港大橋を渡って、『沼津みなとアートビル』へ行き、1階の和風カフェ『ねこや』へ入る。
名前の通り、この店には何匹もの猫がいて、猫好きの人にはたまらない店なんだけど、実はこのビルの中には、全部で20匹近い猫がいるのである。
で、優美子さんと、3年ぶりの再会。
優美子さんは、オレの大好きな画家で、スウェーデンのアトリエにまで遊びに行った事のある、中島由夫先生の絵を中心に扱うギャラリーをやってみえて、赤坂で働いていた時に本当に世話になったのだが、まるで親戚の叔母さんのようにオレのことをかわいがってくれた。
どうしようもないくらい落ち込んだ時、優美子さんに電話すると、「晩御飯を作って待っているから、いらっしゃい」と言ってくれて、中央林間駅近くの、そのギャラリーへ行って話をしていると、そのホンワカした雰囲気に、いつの間にか気持ちが落ち着く・・・・本当に何回も助けてもらった。
数年前、ずっと手伝っていた圭三さんと一緒に、ギャラリーごと沼津へ移転し、和風カフェの『ねこや』は、地元の人が集まる人気店になっているようだが、これも優美子さんの人柄のせいかな。
前回(3年前)は、沼津市内を走っている時に急に思いついて行ったので、お土産も持たずに行ったのだけれど、今回は谷松のこくせんを持って行った。
前回は話だけして帰ったのだが、今回は「朝早く起こしてあげるから、今夜は泊まっていきなさい」という言葉に甘える事にした。
この沼津みなとアートビルのすぐそばには、沼津港深海水族館があり、その一角には居酒屋やカフェなどが立ち並んでいて、その巨大な居酒屋で晩御飯をごちそうになったのだが、話のタネにという事で、深海魚のグリルを頼んでみた。
ハッキリ言って、特に美味いというわけではなく、ホントに『話のタネ』だったが、その他のものは美味かった。
優美子さんの部屋で休んでいると、1匹の猫がオレのそばに来て、じっとオレを見ている。
他の猫たちは、侵入者であるオレに全く興味を示さないのに、その猫だけ、なんでだろうと思っていると、優美子さんに「その子は中央林間から連れてきたの、覚えてるでしょう」と言われ、思い出した。
ある時、優美子さんと話しているうちに終電が出てしまい、その部屋に泊めてもらう事になったのだが、オレの布団を敷くと、優美子さんは友達のところへ泊まりに行って、その部屋にはオレと3匹の猫だけになり、夜中にその猫たちが布団の中に潜り込んできて、朝まで一緒に寝た猫のうちの1匹だというわけ。
ちゃんと仲間だと覚えているんだね。
翌朝、5時に起きて、屋上に上がってみると、富士山が大きく見えた。
少し霞んではいたけれど、やっぱり日本一の山だな。
朝食をもらって、6時過ぎに出発し、246-138-137-甲州街道とガンガン飛ばしながら高山へ向かったのだが、なんとか11時過ぎに到着・・・・昼の営業に間に合った。
今年の『タライ乗り競争』は7月2日で、ぜひまた参加したいと思っているのだが、その前日がウチの12周年感謝パーティーなので、行けるかどうか微妙なところなんだよなぁ・・・・
さて、どうなることやら・・・・
《 海に行きたい!! 》
考えてみると、2003年の夏に、伊豆の鄙びた海水浴場に行って以来、一度も海に行っていないので、「今年こそ店を1日休んで海に行こう」と思っていたのだけれど、いろいろ調べてみた結果、「北陸のハワイ」水島でシュノーケリングをする事に決めた。

そんな話を店に来た友人にしたら、水島ならオレも行きたい、と言うので、オッサンふたりで行くのもどうかとは思ったけれど、一緒に行く事になり、急遽アマゾンから簡易テントを取り寄せたり、シュノーケリングの機材を引っ張り出してきたりした。
ところが前日になって、友人から(文字通りの「家庭の事情」というヤツで)急に行けなくなったと言われた。
まぁ、仕方がないんで、ひとりで行こうかと、機材をバッグに詰めようとしたら、なんと、シュノーケルがバラバラに壊れた。
20年以上も前に買ったやつだから、素材の「経年劣化」なんだろうけど、これは「行くな」という天からのお告げなんだろうな、と思ったので、残念だけど行くのを諦めた。
当日、店は開けたのだけれど、夜、友人はわざわざ謝りに来てくれて、ワインを飲んで帰った。
いいヤツだな。(この友人とは、世界で活躍するテノール歌手、と言えば分かるでしょ)
《 マニアックなスウィムパンツ 》
水島行のフェリーは、8月いっぱい運航しているそうなので、なんとか行きたいと思っていたのだけれど、ありがたい事に予約が続いたため、行けそうにもなく・・・・でも、あんまりいい天気だったので、昼の休憩時間に、市民プールへ行ってきた。
3年ぶりだったけど、入場料は変わらず、250円!!
競泳用のビキニで人前に出るにはそれなりの覚悟がいるけど、その緊張感のおかげで、若い頃とあまり変わらない体形でいられるのだと思う。
まだ『ミカエルの菱形』もハッキリ見えるけど、歳をとった分、身体に丸みが出てきた事も確か・・・・引き締めないといけないな。
早速泳いでみたけど、久しぶりに泳ぐせいか、泳ぎ方を忘れているなぁ。
オレはブレストストローカー(平泳ぎ専門)なんだけど、以前は50メートルを、水中でのひと掻きひと蹴りの後、22ストロークで泳いでいたのに、水がキャッチできていない上、腹筋の使い方が悪いせいか、上下の動きのない、平面的な泳ぎになってしまって、効果的に水を蹴る事ができていないため、24ストロークに増えてしまった。
300m泳いだあたりで、ようやく感覚が少し戻ってきて、22ストロークに戻ったけど、なんかまだ納得できないなぁ・・・・
でも、そのあと仕事もあるので、後半はプールサイドに寝っ転がって、のんびりと過ごした。
プールから上がって更衣室へ向かう時、たまたま目が合ったスタッフの人と挨拶した事から、少し立ち話をしていると、その人がオレの穿いているパンツを指差して、「今はそんなのがあるんですねぇ」って言うと、さらに素材を確かめるように触ってみて、「これ、水球用でしょう。さっきプールサイドで見て気になっていたんだけど、水球やってたんですか?」って訊かれた。
オレが穿いていたのは、水中で掴まれても破れないように特殊コーティングされた、独特の光沢をもつ水球用パンツ(ウォーターポロパンツ、通称『ポロパン』)で、素材の性質上、水に入った時に水圧で緩む事がないので、その点を気に入って使っているわけなんだけれど、その事を話したら、水球をやっていたというその人は、「確かに」って納得してましたね。
(後で知人が教えてくれたのだが、このスタッフの人は、西小学校で着衣水泳の講師をしてみえるそうで、バルセロナ オリンピックの時、水球のナショナルチームで出場直前までいった(予選の最後で敗退した)というスゴイ人だそうだが、そんな人が、なぜ高山にいるのか不思議ではあるけれど、もし高山に深いプールがあったら、コーチとして子供たちに水球を教えてもらえるんだろうけどね。)
で、オレが気に入って穿いているこの『ポロパン』は、スポーツ用品メーカーのミズノが作っている、れっきとした競技用アイテムなのに、インターネット上で「フェティッシュアイテム」扱いされている事もあって、これを穿いてプールで泳ぐのには、ある種の勇気がいるみたいなのだけれど、オレは他人の目より自分の感覚を優先する人間なので、全く気にせずに穿いているわけです。
自分にとってベストのスウィムパンツを見つけて喜んでいたのだが、すごく残念な事に、ミズノがこのタイプ(RQ-632)の競泳用・水球用ビキニの製造中止を発表した。(その理由は、本来の用途ではない使い方をしている動画や画像が、インターネット上で多く見られるようになったからだと言われている。実を言うと、このポロパンは、そっち系のショップで見つけて買ったのだけれど、今後はミズノ製のものを扱う事はなさそうなので、もうそのショップで買う事はないだろう。)
あわてて、自分のサイズで残っていた最後の1枚を手に入れたので、今のところ全部で3枚持っているけど、ポロパンは、劣化しやすいポリウレタンでコーティングされているため、寿命があまり長くないらしく、少しでも寿命を伸ばすように扱わなければならないわけですよ。
もっとも、9年前に買ったポロパンは、今もまだ使える状態なので、意外と長く使えるのかもしれませんが・・・・
聞いた話では、密封袋に入れて空気を抜いた状態で保存するといいらしいのだが、どんなものなのか、やってみるかな。
《 定期演奏会、無事終了 》
おかげ様で、高山室内合奏団 第13回定期演奏会を無事終了する事ができました。
ありがとうございました。




実のところ今年は、演奏会までにトラブルが続きました。
例年より選曲が遅れた事から始まり、ヴァイオリン独奏をお願いしていた村中さんに、腱鞘炎でドクターストップがかかったため、曲が変更になり、極めつけは、演奏会の2日前に指揮者の鴨宮さんが急遽入院し、前日夜のゲネプロ(総練習)にギリギリで退院するという、今考えても、よくできたよなぁ、って感心するくらいの綱渡り状態が続きました。
(画像は、ゲネプロと、当日朝のリハーサルのものです)
ヴァイオリンの人達。

低音域を支えるコントラバス。

指揮者の鴨宮さん。病み上がりで、結構しんどそう。

毎年参加してもらっている、木管楽器の人達。

岡山県から毎年来てくれる、ヴィオラの和田さん。

オレの前にヴィオラを弾いていた小淵さん。オレが借りて弾いていたのは、この画像のヴィオラ。

チェロの人達。

指揮者と、ステージマネージャーの打ち合わせ。

フルートとオーボエの人達。

本番直前の舞台袖。


また、毎年、8月最後の日曜日は、行事が重なるのですが、今年はそれが特に多く、クラシックの演奏会だけでも3つ重なったため、お客さんが分散してしまうという、あまりありがたくない状況でもありました。
そんな状況の中、例年より少なかったとはいえ、予想していたより多くのお客さんに来て頂けた事を、本当にありがたく思うとともに、例年以上に多数のアンケート用紙が返ってきて、多くのご意見を頂けた事は、団員一同、心から感謝致しております。
例年に比べて演奏時間が短くなり、物足りなく思われたのではないかと心配していたのですが、今までで一番良かった、と言って下さった方もおられた上、アンコール曲(ワーグナーの歌劇ローエングリン第2幕から エルザの大聖堂への行列)の演奏を、多くの方が喜んで下さったようで、ホッとしました。
プログラムのあいさつにも書いたように、今年の定期演奏会では、ベートーヴェンの交響曲第2番に挑戦します。
今年も8月最後の日曜日に定期演奏会がありますので、今から予定に入れておいて下さい。
お待ちしております。
高山室内合奏団 第14回定期演奏会
2017年8月27日(日) 飛騨芸術堂にて 14時開演 入場無料
予定演奏曲目
レスピーギ リュートのための古風な舞曲とアリア 組曲第3番
シンディング 古風な様式の組曲 作品10
ヴァイオリン独奏 村中 一夫
ベートーヴェン 交響曲第2番 ニ長調 作品36
《 高山でアメフトを 》
10月2日に、中山公園陸上競技場で行われた「富士通フロンティアーズ アメフト体験教室」を見てきました。
市内の小中学生を対象に、希望者を募って行われたようですが、参加希望者に、スポーツ少年団の団員が加わって、30人ほどでの開催になったとの事です。
社会人になってから、プライヴェートチームで一から教えてもらいながらアメフトをやったオレからすれば、子供のうちにこういう経験をできるのは、本当に羨ましい。
ただ、全く不可解なのは、その参加申込用紙を見た人以外には全く知らされていなかった事。
オレは、上仲剛司君が電話をくれたので知ったけど、高山市全体に告知されていれば、見に行く人も、もっと多かっただろうと思うし、少しでも多くの人に見に来てもらえるようにする事が、わざわざ来てくれたフロンティアーズの人達に対しての礼儀だと思うのだが・・・・
最後に応援グッズをもらいに行った時、プレイヤーやスタッフに「高山まで来て頂いて、本当にありがとうございます」と言って頭を下げてきたけど、今一つ吹っ切れない思いではありますね。
でも、30年以上も前から「高山にアメフトチームを作ってデンヴァーと交流したい」と言っては、みんなにスルーされていたオレからすれば、すごい進歩だと思います。
さて、その「高山にアメフトチームを作る」という話なのだけれど、夢物語ではなくなってきた。
ウチのお客さんに、日大フェニックスで日本一になり、現在は、本業の傍ら、大学でコーチをしている方がおられるのだが、近い将来、高山でアメフトを教えたいと言われた。
過去に、多くの高校生をアメフトの推薦で大学へ進学させた実績があり、当然そのための技術や経験、それにコネも持っておられるわけだし、高山を活性化させる方法なども、かなり考えておられる方なので、期待できると思っている。
その内容については、いずれ書く事になると思うので、詳細はその時に。
《 絵を1枚、店内に掛けました 》
冬のパリを描いた、荻須高徳のリトグラフで、バブルの頃に手に入れてからずっと持っていたのですが、イタリア料理の店にフランスの風景画を掛けるのもどうかと思って、掛けるのを躊躇していたわけです。
もっとも、オープンしてから3年位の間、『南フランス』というタイトルの絵を飾っていた事があって、その時は「南フランスと北イタリアは緯度的に同じようなところだから」と言い訳していたのだけれど、さすがにパリの風景画となるとねぇ・・・・
この前、あるお客さんにこの絵を見せたら、絶対飾った方がいいよ、と言われ、その言葉に背中を押されて掛けてみたのですが、これはこれで、結構いいんじゃないかと。
カウンターの横の壁にピッタリと納まったのを見て、ここに掛けるためにオレのところに来たんだ、と勝手に思ったりして・・・・
《 料理の道へ進むきっかけのひとつ 》
先日、ふと思いついて検索してみたら・・・・出てきたよ、『世界の料理ショー』
もう40年も前、オレが高校生の頃の平日(確か水曜日だったと思う)の昼間にやっていたので、祝日か学校が休みの時にしか見れなかったのだけれど、それでも4~5回は見たと思う。
グラハム カーが、かなり適当ながらも、いかにも楽しそうに料理をしているのを見た事が、オレが料理の道に進むきっかけのひとつになったのは間違いない。
もっとも、料理の事より、最初の小噺の事をしっかりと覚えていたりするんだけど。
調理師学校で教えていた時、『世界の料理ショー』のノリでやったら面白いだろうな、って思っていたのだけれど、今でも結構本気で、『世界の料理ショー』のノリで料理講習会をやってみたい、と思っている。
最後にお客さんを引っ張り込んで、一緒に食べながら感想を聞くなんて、すっごく楽しいと思うね。
《 コンサート 》
12月4日、さくらホールで行われた、『水口 聡 with オーケストラ アンサンブル金沢 テノールとストリングスの競演』は、本当にすごかった。
満席とは言えない入りだったのが、ちょっと残念だったけど、水口は「空席以外は満席だ」と言って客を笑わせていた。
オーケストラだけの演奏をはさみながら、9曲が歌われたのだけれど、水口はノリノリで、声を張り上げて高音を目いっぱい伸ばし、客席からだけではなく、オーケストラの団員からも拍手を受けていた。
弦楽器16人のアンサンブルで、指揮者なしの伴奏のため、少しずれた部分もあったけど、そんなのは些細な事で、最後まで本当に楽しませてもらった。
水口は、リハーサルの時まで、指揮者(過去に共演した事のある井上道義さん)が来るものだと思っていたそうなのだが、指揮者なしで合わせるのには、それなりに苦労したらしい。
終演後、楽屋へ行って、持って来たスプマンテを渡したら、今夜行ってもいいか、と言われたので、合奏団の練習が終わった9時半に、という事で話は決まった。
で、9時半に総勢6人が集まり、途中からオレも加わって、ワインを飲みながら、コンサートの事や音楽の事など、熱く語り合っているうちに、気がついたら12時近くになっていた。
自分の身近に、こういうすごい歌手がいる事や、楽しみを共有できる仲間がいる事は、本当に幸せだと思う。
《 クリスマス ファミリーコンサート 無事終了 》
おかげ様で、高山室内合奏団のクリスマス ファミリーコンサートは、多くの方々にご来場頂き、盛況のうちに無事終了する事ができました。
ありがとうございました。
今年も例年と同様に、飛騨市民病院(非公開)、船津座、高山市民文化会館での3公演を行いましたが、高山、神岡公演ともに、準備していた席がいっぱいになり、特に高山では、立ち見の方が結構おられたので、休憩中に追加の椅子を用意しましたが、来て頂いた皆様には、本当に感謝しております
今年は、新しい曲を多く取り入れた事もあり、練習不足かな、と思っていたのですが、思っていた以上に上手くいったというか、結構弾けていたと思います。
また、いつも高山室内合奏団の演奏会で、ステージマネージャーとして取り仕切ってもらっている、伊藤健生さんに、歌手として『世の人忘るな』を歌ってもらいました。
いつも裏方なので、今回は一番目立つ役をやってもらったわけです。
高山公演では、毎年恒例の(株)なべしまさんの協賛による、出来立てポップコーンが大人気で、かなりの量を追加で作ってもらいました。
今年も司会をやりましたが、船津座では、なぜかマイクが使えず、声を張り上げて話していたら、結構かみましたが、2日目の高山公演では、マイクも使えたし、馴れた事もあってか、リラックスして、大部分をアドリブでやれたので、よかったのではないかと・・・・
このコンサートの事は、13日の中日新聞に取り上げられましたが、写真の右端に、オレが写ってました。
《 クリスマス 》
毎年、12月に入ると、世の中はクリスマス一色になるし、特にこの業界では、一大イヴェントと言ってもいいくらいの扱いになるわけだが、ウチはここ何年か、全く『クリスマス』には関係なく営業している。
もちろん、クリスマスメニューをやってほしいと言われれば、喜んでやらせてもらうし、薪ストーヴを焚いたり、中庭に電飾をつけたりして、雰囲気を盛り上げ、全力でサーヴィスしますよ。
でも、オレの方から「クリスマスメニューはどうですか?」とは言いたくない。
だって、仏教徒のオレがそんな事を言ったら、めちゃくちゃウソ臭いでしょ。
まぁね、客を集めるためには宗教の違いなんか構ってられない、というのが大多数の日本人の考え方なのかもしれないし、世の中とはそういうもの、と言ってしまえばそれまでなんだけど・・・・
でもオレは、やっぱり正直に生きたいですね。
《 発表会 》
2月26日、今年も新宮の教会で、ヴァイオリンの発表会がありました。
毎年の事とはいえ、やっぱり緊張しますね。
今年選んだ曲は、ヴィヴァルディのイ短調のコンチェルト。
毎年誰かがやる曲なので、敢えて避けていたんだけれど、先生に「ヴァイオリンをやる以上避けて通る事ができない曲でしょう」って言われて、まぁ確かにそうだなぁ、って納得したので、挑戦する事にしたわけです。
で、教本に載っている楽譜を見ながら練習していたのだけれど、参考にと思って、大好きなヴァイオリニスト、ヘンリク シェリングの演奏を聴いてみたところ、なんか違う・・・・フレージングだけでなく、音程も結構変わっている。
楽譜を無料でダウンロードできるサイト『ペトルッチ』で調べてみたところ、教本に載っている楽譜は、ヴィヴァルディのオリジナルに、かなり手を入れたものだと分かった。
おそらく、スズキメソッドあたりが、練習用に変えたものなんだろう。
そう分かったら、オリジナルでやろうと思い、先生に言うと、いつものように半ば呆れながら、「それはいいけど、これは難しいよ」って言われた。
一見、オリジナルの方が簡単そうに見えるのだが、4音、あるいは8音を、移弦しながら一弓でレガートで弾かなければならないところが結構あって、これをきれいに弾くのが難しい・・・・音が途切れたり、雑音が混じったりしやすいのだ。
教本に載っている楽譜は、そこを上手くごまかせるようにしてあるんだな。
でも、敢えてやってみようと決心して練習はしたものの、やっぱり手強いなぁ。
本来、速いテンポで弾くように書かれている曲なのだけれど、技術的に追いつかないので、ゆっくり目のテンポで弾くと、逆に粗が目立ちやすくなるところがあったりして、途方にくれたり・・・・
そんなこんなで、なんとか最後までたどりつけるようになり、本番では、多少のミスがあっても、最後まで弾ききれればいいかな、と開き直って構えていた。
本番当日の午前中にリハーサルをやったけど、まぁこんなものかな、といったところ。
完璧には程遠いけど、なんとか弾き通せるかな、と・・・・
本番は、午後1時からなんだけれど、少し早めに行ったら、もうみんな来ていた。
オレの出番は、後ろから3番目・・・・オレより上手い人の方が多いんだから、もっと前の方が気がラクなんだけど、なぜか毎年、最後の方なんだよね。
出番を待っているうちに、緊張感だけがどんどん高まっていくから・・・・
いよいよオレの出番。
ステージに上がって、まず、これから演奏するのがヴィヴァルディのオリジナル版で、教本に載っているのとは別のものである事を話すと、一部の人が興味を持ったみたい。
で、演奏を始める。
緊張していたせいか、いつもより速めのテンポで合図を出してしまい、ちょっとヤバイかな、と思いながら弾いていたのだけれど、やっぱり、指が追いつかずにとちったところが何ヶ所かあった。
曲の半分が過ぎ、最初のテーマが戻ってきたところで、急に伴奏と音が合わなくなった。
あれっ、違うところに入ってしまったかな、と思ったら、伴奏の細江さんが「ごめんなさい」って言って、伴奏を止めた。
後で聞いた話では、伴奏譜のページをめくっているヒマがない曲なので、全ページを開いて譜面台に置くはずだったのに、一箇所折りたたんだままになっていたそうだ。
どこから弾きなおそうか、って言ったら、最初からやりましょう、って言われて、結局、もう一度最初から弾く事になった。
1回目の方が上手くいったところも、2回目の方が上手くいったところもあったけど、なんとか最後まで弾き通す事ができたので、良しとしておこう。
聴きに来ていた人から「長く弾けてよかったね」って言われたけど、こっちはもう、大変なんですから。

発表会の後の反省会では、みんな、来年こそ練習してもっと上手く弾けるようにしたい、って言うんだけれど、なかなかそれができないんだよなぁ。
でも、目標は少し高めにして、それを超える事で上手くなるわけだから、やるしかないんですけどね。
オレには、いつか弾けるようになりたいと思っている曲があるんだけれど、それが超難曲で、いつだったか先生の前で少しだけ弾いたら、なにやってるの?、って言われてしまった。
全く曲として聴こえなかったみたい。
まぁ、少しずつ練習して、身体で憶えるしかないんですけどね。
それが、この曲。
まぁ、いつかは弾けるように、がんばりましょう。
《 ウォーターボーイズ 》
オレの大好きな映画『ウォーターボーイズ』・・・・突っ込みどころは結構あるけれど、「思い入れ」と「ノリ」と「勢い」で駆け抜ける潔さは、実にイイ!!
2月の終わりに、初回生産限定デジパック仕様のDVDがメチャメチャ安く売られているのを見つけて、思わずポチってしまったのだが、それが届いたので、ホールのスクリーンにプロジェクターで投影して大画面で観た。(確定申告でバタバタしているのにねぇ)
長期の合宿までして練習を重ねた出演者たちが、実際に観客の前で演技をして撮影された10分に及ぶ演技のシーン(下の動画の1:16:35から)は、何回観ても惹き込まれる。(下の動画は音が少し遅れるし、著作権絡みのせいか、一部の音声が消えている)
昔懐かしいベンチャーズの『ダイヤモンド ヘッド』に合わせての陸ダンスから始まり、『カルメン』前奏曲から、シルヴィー ヴァルタンの『あなたのとりこ』での水中でのフォーメイションシーンのスゴさもさる事ながら、みんなで出し合った意見をすべて取り入れて、陸上と水中の両方ではじけまくる、Only you~愛のしるし~学園天国、と続くあたり(1:20:57から)は、後のテレビドラマシリーズで、さらに高度なシンクロの技術を持ってしても超える事のできなかった、最高のパフォーマンスシーンだと思っているし、そのために張り巡らされた伏線には、ホント、感心してしまう。
(映画版、テレビドラマ版、テレビドラマ版2を見比べると、後のものほどシンクロ技術のレヴェルは高くなっているのだが、そこから受ける「感銘度」は、後のものほど低くなるのが皮肉ではある。)
マニアックな見方になるけれど、この映画でのボーイズのビキニの穿きこなし方は、競泳用といえばビキニしかなかった時代に水泳をやっていたオレの目から見ても、実に様になっていると思う。
実際のところ、本当に「泳げそう」に見えるのは、2サイズ以上小さめのものを尻の割れ目が少しだけ見えるくらいに穿く、というのがビキニ時代のスウィマーの一致する認識だと思うが、ボーイズが(サイズはともかく)そこをキチンとおさえた穿き方をしているのは、本当に解った人が指導したからだろうし、後のテレビドラマ版で使われたArenaのものよりシャープなフォルムの旧Speedo(現Mizuno)のビキニが使われているのもイイ!!
自分の目標の1つに「いつまでもビキニの似合う身体でいる事」というのがあるので、オレは今でもプールでは競泳用のビキニしか穿かないし、そのおかげで何とか体形を維持できていると思っているけれど、改めてこの映画を観た今、夏までに身体を引き締め直そう、って思っている。

と、Facebookに書いたら、それを読んだお客さんに言われた。
「あのボーイズの年齢設定って17才でしょ。40才も若い子に対抗意識を持つのってどうなの?」
大人気のなさでは誰にも負けない事は、よ~く分かっているんですけどね・・・・まぁ、ハードルは高くしておいた方が、下をくぐりりやすいですから・・・・
《 久しぶりにラザーニェを 》
ウチのお客さんを、飛騨地区の人と、それ以外の人に分けると、後者の方が多い事は分かっていたのだが、ここ2年ほどに関して言えば、ディナーを予約して来店されるお客さんの85%以上が飛騨地区以外の人なんです。
さらに言うなら、年に2回以上、予約を入れて下さる方も、飛騨地区以外の人が圧倒的に多く、岐阜、名古屋はもとより、東京、横浜、金沢、富山、大阪、神戸、広島などから、定期的に予約を入れて下さる方がおられる事を、本当にありがたく思うわけです。
まぁ、専門店なんていうのは、マニアックな、というか、ある程度解った人を対象にやっているわけですから、高山の人でウチに来てくれる人が限られるのは当然の事なんだけれど、ちょっと寂しい気もする。
でも、州ざき、角正、萬代へ普段から出入りしている人が高山にどれだけいるか、と考えると、まぁ、そんなものなんでしょうね。
先日、年に3~4回、名古屋から来て下さるお客さんが、誕生日に予約を入れて下さったのだが、ラザーニェをリクエストされたので、久しぶりに作った。
ラザーニェって、結構手間がかかるのだが、まずはホウレン草を練り込んだパスタを作るところから始める。
ミートソースには、ベシャメルソースを混ぜておき、重ねる時に、エメンタールと炒めたハムを載せる。
実を言うと、ラザーニェの出来を決めるのは、このソースの混ぜ方だったりする。
4段重ねたら、最後にベシャメルソースで覆って完成。
Lasagne verdi alla bolognese.
グリーン ラザーニェのボローニャ風
オーヴンから出したらすぐにお客さんのところへ持っていくので、焼き上がりの画像はナシ!!
あと3人前ほど残ってますよ。
例によって長くなりましたが、最後のラザーニェの話を書き終わったところで、久しぶりに、「書いたなぁ」って気がしました。
上にも書いた通り、これからはFacebookと同時進行で、ちょくちょく書いていこうと思っていますので、時々覗いてみて下さい。
では、また。
Ciao. Arrivederci!!
2017年02月06日
いろいろあって 久しぶり編 その1
Ciao. spockです。
久しぶりの投稿なんですが、今、見てみたら、9ヵ月半も更新してなかった・・・・決して、忘れていたわけではないんですが。
その間、覗いて下さった方々、ありがとうございます。
今は、店の事をすべて1人でやっているので、以前のように、思う存分長い文章を書くのは、かなり難しい状態で、Facebook にちょこっと書いてごまかしている状態なんですが、書きたいと思う事が溜まってきたので、思いついた勢いで書いてみようと思います。
中には、Facebook に書いた事と重複するところもありますが・・・・
とにかく、長編になるので、2回に分けてアップします。
ではまず、前回書いた、『こだまーれ 2016』のオープニングセレモニーの話から始めましょうか。
オープニングセレモニーは、4月24日の午後1時半の開演だったのですが、文化会館大ホールでのリハーサルは、その前々日と前日の夜、それに当日の昼前の3回という事で、予約が入っていなかったので、ホールに慣れるため、すべて参加しました。
それと、春慶塗の楽器がどこまで鳴るか、という事を実際に試してみたかったというのもありましたが。

文化会館の大ホールで演奏するのは初めての事で、どんな響きになるのかは、実際にやってみるまで分からなかったのですが、ホームグラウンドである『飛騨芸術堂』に比べて、ホール自体の容積が大きく、ステージ上に反響版がないため、客席に十分な音量が届くのかが問題になるわけです。
まぁ、結果としては、客席の後ろの方まで、ちゃんと音は届いていたそうですが、ごく控えめにPAを併用する事になりました。
最初のリハーサルに行った時、ホールに入ると、一面のスモークで、ホールの中が霞んでいるのに驚いた。
演出のため、という事だったけど、そこまでやる事が必要なんですかねぇ。

ステージに上がり、配置を決めるところから始まったのだけれど、これがまた厄介なんですよね。
いわゆる『多目的ホール』の場合、その構造から、ステージ上で発された音の大部分が、ステージの上と横に逃げてしまうため、少しでも多くの音が客席に届く位置を見つけなければならないわけです。
今回は、ステージの後ろの方の頭上に、発光版が4枚吊り下げられていたので、その前に並ぶ形で配置が決まりました。

スモークが充満する客席

演奏する曲は、
モーツァルト アイネ クライネ ナハトムジーク 第1楽章
ワーグナー 歌劇 ローエングリン 第2幕から エルザの大聖堂への行列
ハルヴォルシェン ヴァイオリンとヴィオラのためのパッサカリア
シベリウス アンダンテ フェスティーヴォ
の4曲で、ハルヴォルシェンの曲は、ヴァイオリニストの村中 一夫さんと、元団員でヴィオラの専門家である、小瀬 直統さんのデュオによる演奏。
過去に何回も演奏している曲ばかりなので、楽器ごとのバランスや、ホール内での響きを確認する方が重要な目的、といった感じでしたが、やはり、いつもとは違う感触でしたね。
でも、2日に亘るリハーサルで、結構響くようになったと思いました。
喉の弱い人は、スモークに咳き込みながらのリハーサルで大変でしたが、2日目からはマスクが用意されました。
で、いよいよ当日。
集合時間より早めに行ったのだけれど、もう、みんな集まって、指慣らしや楽譜のチェックをしていた・・・・気合が入っているな。



楽器の調整のために、府中市から駆け付けてくれたドンマイヤーさんも、調整に余念がない。

前日から、合奏団のメンバーの楽器も調整してもらったのだが、オレはヴィオラだけでなく、ヴァイオリンの調整もしてもらえた。
デュオの演奏をする、村中さんと小瀬君も、楽屋で練習中。

リハーサルの時間が来て、ステージの席に着く。



元団員の平塚さんも、今回の演奏に参加する事になり、久しぶりに一緒に演奏する。

配られたオープニングセレモニーのプログラムを見ると、春慶楽器には、それぞれ名前が付けられているとの事・・・・全然知らんかったわ。

でも、その名前が、作曲家の名前とオペラのタイトルをごちゃまぜにしたのは、いかがなものかと・・・・
iPad で写真を撮っていたら、すぐ隣のチェロの広田さんが、オレを撮ってくれた。

春慶塗のヴィオラは、小瀬君に渡したので、ここで弾いているのは自分の楽器。
リハーサルの間、ずっと春慶楽器を弾いていたのに、いきなり自分の楽器に戻ったら、少し小さい分、高めに音程を取ってしまい、感覚が戻るまで、ちょっと苦労しましたね。
でも、腕の長い自分には、大きいサイズのヴィオラが合っている事が分かったのは収穫でした。
最終リハーサルが始まり、アイネ クライネ ナハトムジークを弾き始めたのだけれど、前日までとは打って変わって、全然音が出ていない。
特に緊張しているわけではないのだけれど、自分自身も含めて、なんか萎縮している感じ。
とにかく、全曲通して弾いたら、最後のアンダンテ フェスティーヴォのあたりで、やっといつもの調子になったかな。
このアンダンテ フェスティーヴォの最後に加わるティンパニは、いつも演奏に参加してもらっている、高山市民吹奏楽団の小林さんにお願いしていたのだけれど、クレッシェンドして最強打になるトレモロが、客席ではあまり聴こえないという指摘があった。
それで、ヴァイオリンの後ろから、横へ移動したところ、聴こえるようになったとの事。
ステージ上の位置決めって、本当に重要だな、と改めて思った次第。

あとは、本番まで、しばし休憩。
その間も、ドンマイヤーさんは、団員の楽器の調整をしてくれました。
で、いよいよ本番。
ステージまでの通路で時間調整。
少し緊張してる、

と思ったけど・・・・そうでもないみたい。

ステージに上がって席に着き、静かに待っていると、幕の向こう側で、セレモニーが進んで行く。

そして、いよいよ幕が開き、アイネ クライネ ナハトムジークの演奏を始める。
たいていの場合、最初の曲の演奏は、幾分手探りというか、醒めた状態で演奏する事が多いのだけれど、この時もそんな感じ。
それなりの拍手をもらって、2曲目の「エルザの大聖堂への行列」に入る。
この曲は、弾いていて気持ちのいいところが結構あるので、だんだんノッてくるんですよね。
まぁ、ワーグナーの曲なんていうのは、ある種の「自己陶酔」がなければ成り立たないようなところがあるので、それでいいんじゃないかと思いますけどね。
後から聞いた話では、お客さんからの反応が一番良かったのが、この曲だったそうです。
続いてのハルヴォルシェンの『パッサカリア』は、殆どの人が初めて聴く曲だと思うし、あまり取っ付きやすい曲でもないのだけれど、変奏曲という事もあって、段々と引き込まれていくんですよね。
技術的にも難しい曲で、オレも挑戦してみたけど、第4変奏で挫折してしまったのだが、さすがに村中さんと小瀬君は、まったく危なげなく、全曲を弾ききった。
その上で、春慶楽器が、ちゃんとホールの一番端まで通る音を出せる事を証明してみせたわけです。
最後は、シベリウスの『アンダンテ フェスティーヴォ』
こういう式典で演奏するには、打って付けの曲ですね。
過去に何回も演奏している事もあって、合奏団のメンバーも、のびのびと弾いていたと思うし、弾き終えた後の達成感も、結構ありましたね。
今回初めて、文化会館の大ホールで演奏したわけだけれど、いい経験になりました。
これからも、機会があれば、いろいろなところで演奏していきたいですね。
高山市制施行80周年記念「高山祭屋臺からくり競演」
布袋台が、初めて安川通りを越えて上町へ入った、記念すべき出来事ですね。
オレ自身の興味は、4台のからくり屋台が揃う事より、布袋台が上町を通るところにありました。
で、中橋を渡った後、上一之町を下って蔵に向かうところを、布袋台に付いて移動しながらVTRに収めたのですが、その一部を You Tube にアップしました。
こういう事が、次はいつあるか分かりませんから、結構貴重なVTRなんじゃないかと思っています。
今年もGWに、全屋台の曳き揃えがあるそうですが、今から楽しみですね。
Musica Libera Ⅵ
5年前に始まった Musica Libera も、今回で6回目。
第1回から、楽器経験の一番短い(要するに、一番下手な)演奏者として参加していたのだけれど、段々レヴェルの高い参加者が増えてきたので、今回は参加しなくてもいいかな、と思っていたら、いつの間にかチラシに名前が載っていた・・・・
とりあえず練習中の、ベートーヴェンの『ト調のメヌエット』を弾く事にして、演奏会のための練習を始めたけれど、付焼き刃的演奏になる事は仕方ないか。
毎回、「恥をかくほど上手くなる」という言葉を信じて、恥をかきに行っているようなものだけれど、さて今回はどうなるやら・・・・
たまたま、当日の朝にヴァイオリンのレッスンがあったので、とにかく聴けるように、という事で、先生にいくつかのポイントを集中的に手直ししてもらったのだけれど・・・・実際に本番ではきちんと弾けたのか、自分では分かりません。
ステージに上がって弾き始めたら、こんなふうに演奏しようなんて考えているヒマもなく、それまでの練習で身体が覚えた事がそのまま出てしまうだけなんですよね。

先生がわざわざ聴きに来て下さった事も、余計に緊張感を高める事になったのだけれど、弓が飛び跳ねてしまう事もなかったし、自分の出した音がホールの残響として聴こえてきたので、しっかりとした音が出せたのだと思う。
そういう意味では、少しは進歩したのではないか思います。
毎回恥をかきにいっているようなものだ、と上に書いたけど、700年も前に、兼好法師が『徒然草』の第150段に書いた事を、オレは信じたいですね。
ちなみに、それを現代語訳したのがコレ。
これから芸事を身につけようとする人は、とかく「ヘタクソなうちは誰にも見せたくない。こっそり練習して、ある程度見られるようになってから披露するのがカッコいい」と言うものだけど、そういうことを言っている人が最終的にモノになった例はひとつもない。
まだ未熟で下手な頃から、経験が長く上手な人たちに混ざり、バカにされようと笑われようと、恥ずかしがらないで気にしないで、才能がなかったとしても立ち止まらず、踏み外すこともなく年を送っていけば、最終的に、その道の極みを嗜まなかった人よりも上の立ち場になれるし、人望も備わって、多くの人に尊敬され、天下一の名声も得られるようになるものだ。
”神レベル”に上手いと言われている人でも、最初は未熟だという評価を受けてきたのだし、そのパフォーマンスには欠陥があったりもした。それでも、道の掟に従い、これを重んじて真剣にやった人が、その道のプロとして、様々な人の先生となってきたのだ。この事は、どの分野でも変わらない話だ。
大きいヴィオラがやってきた!!
実を言うと、今まで使っていたヴィオラは、オレの前に合奏団でヴィオラを弾いていた小淵さんから借りていたのだけれど、オレより小さい人なので、そのヴィオラも小さめの、390mmのものだった。
ヴィオラという楽器は、その大きさにかなり無理がある楽器で、音域から考えると、もっと大きくなければならないのに、それでは肩に乗せて弾けないので、無理やり今の大きさになったわけです。
だから、ヴァイオリンの胴長が355mmくらいと決まっているのに対し、ヴィオラは決まったサイズがなくて、380~420mmまであるサイズ(海外には、さらに大きいものもある)の中から、扱いやすいサイズのもの、あるいは、自分が扱える中で(低音がよく出るように)一番大きいサイズのもの、という選び方をされるんですね。
この前弾いた春慶塗のヴィオラは、415mmという大き目のものだったのだけれど、腕が長いせいもあってか、すごく弾きやすかったし、音程も取りやすく思えたわけです。
そんな経験から大きいヴィオラが気になって、中国のショッピングサイト AliExpress で探していたら、安いのにすごく良さそうな、ストラディヴァーリのコピーで16.5インチ(420mm)のヴィオラをみつけたのだけれど、それが期間限定で8%off になり、さらに少し円高になったので、思わずポチってしまった。
本体に弓とケースと松脂付き、8%offで368ドル、それに送料50ドルを加えて418ドル・・・・カード会社の利用明細では、46400円ほどだった。(それからしばらくして急に円高になったので、ちょっと悔しかったけど)
そのショップからは、以前にもヴァイオリンの弓を取り寄せたことがあり、送料無料なのに、きちんと梱包されて送られて来たので、まぁ間違いはないだろうと判断したわけだけど、多少はギャンブル的要素もありますね。
一番気になったのは、サイトにアップされている画像には、裏板の杢目がすごくキレイなものが写っているのだけれど、実際に送られてくるものはどうなのだろうか、という事。
相手が自然の木を使ったものだけに、個体差というのは避けられないわけだけれど、やっぱりキレイなものの方がいいに決まってますからね。
オーダーしてから約2週間・・・・EMSで荷物が届いた。

大きさは想像していた通りだけれど、持ってみると異様に軽く感じたので、大丈夫かな、と思いながら箱から出してみると、

ケースの中に、ヴィオラと弓と松脂がキチンと入っていた。

ケースが発砲スチロール製のものなので、すごく軽く感じたわけです。
裏板を見てみると、ウェブサイトの画像にアップされていた個体が送られてきた事が分かり、やはりこの店はしっかりしているな、と感心した。

ちなみに、現在は別の個体の画像がアップされているので、各個体ごとに画像を変えているみたいだ。
今まで使っていたヴィオラと、大きさを比べてみると、胴体の長さだけでも、約3cm長い。

その分弦長も長くなるので、音程の取り方も微妙に変えなければならないわけです。
このヴィオラはすごく軽くて、今まで使っていた小さめのヴィオラよりも軽いので、左腕に負担はかからないのだけれど、手が大きいわりに指はそれほど長くないオレにとっては、弦が長くなった分、指を広げて押さえなければならないので、特に小指に負担がかかりそう。
でも、一番指を拡げなければならない、C線のGと、G線のAsを同時に押さえることができるので、なんとかなりそうではありますが。
付属の、いかにも安っぽい音のスティール弦(値段が値段だけに仕方がないんだけど)を、以前使っていた弦に張り替え、駒の位置を調整して音を出してみると、予想以上によく響く。
ただ、よく響くんだけど、なんか違う・・・・奥行きのない、薄っぺらい音・・・・
でも、いろいろ弾いているうちに、音の出し方が分かってきたのか、だんだん音が変わってきた。
その10日後に牧歌の里で演奏する曲を一通り弾いてみたら、音に芯が出てきて、それらしい響きが出るようになった。

この工房で製作された楽器を扱っている人が書いた文によると、この楽器に使われている木材は、古い建造物を取り壊した時に出る「建築古材」のスプルース(マツ科トウヒ属の木材 楽器や建築に使われる)を使って作られているので、完全に乾燥しているため、必要十分な厚さがあっても、軽くてよく響くのとの事。
複数のプロの演奏家から、音だけに関して言えば、入念に調整することで数百万円レベルの楽器と遜色ない音が出る、と言われたとか、この工房のヴィオラでコンクールに入賞したとか、書いてあって、それが嘘か本当かは分からないけれど、実際のところ、この値段で、これだけ良く響いてくれるのだったら、中途半端に高い楽器を買うより、こっちの方がいいんじゃないかと思ってしまった。
とは言っても、やっぱり、値段相応の部分がある事も否めないわけです。
駒の上に刻んである、弦を載せるための溝が、1つだけずれていたので、やすりを使って手直ししました。
また、本来は黒檀が使われる指板に、黒く塗った木が使われているので、時期を見て、黒檀のものに交換してもらわないといけませんね。
あとは、自分で出来ることを少しずつやって、弾きやすくしていかなければならないわけですが、まず手始めに、少し回しにくいペグをなんとかしたい。
というわけで、Lapella のペグ コンパウンドを手に入れて塗ってみた。
以前使っていた、Hill のペグ コンポジションは、色が茶色で、なんか汚く見えてしまうのだけれど、今回手に入れたものは、色もきれいで、ペグの回りもよくなった。


それから、高さも形も、自分にはいまいち合っていなかった顎あては、ヴァイオリンにも使っていて、すごく気に入っているSASのものに替えた。

ヴァイオリンには、一番軽いペアーウッド(梨木)のものを使っているが、ヴィオラ用にはメイプルウッド(楓)をチョイス・・・・杢目がきれいに出ていて、見た目もいいと思う。
ちなみに、ヴァイオリンもヴィオラも、肩当てから顎当てまでの高さが同じになるように調整してある。
ヴァイオリンとヴィオラをダブルケースに入れると、いかにもそれらしい雰囲気になります。

以前、これを見た人から、「プロみたい」って言われた事があったけど、まぁ、見た目も大切というか・・・・ヘタなんだから、見た目くらいは良くしておかないとね。
実際に、合奏団の練習の時に、このヴィオラを弾いていたら、周りの人から、「良く鳴るねぇ」って言われたので、そういう意味で、このヴィオラは「当たり」だったと思う。
あとは、自分の楽器として、地道に弾き込んでいくだけ・・・・まぁね、技術的にはまだまだなんだけど、
ところで、この前、あるサイトを見ていたら、17.5インチのヴィオラの話が出てきて、それがすごく気になっているんだけれど・・・
出張料理講習会
今までに、料理を教えてほしい、といわれた事は何回かあったのだけれど、最終的に詰めるところまで行かず、立ち消えになったのですが、今回は、希望された方がきちんと話を進めて下さったので、実現する事になりました。

参加者は、主婦の方6名で、その中の1人の方のお宅で行いました。
いきなり初めての場所で、家庭用の火力の弱いガスコンロを使ってやる事には、むつかしい点もありますが、そこは専門家ですから、何とでもします。

「先生」なんて呼ばれるのは、調理師学校で、イタリア料理主任講師として教えていた時以来、20数年ぶりなので、少し気恥ずかしい気もしたけれど、すぐに慣れた。
「誰でも簡単に失敗なくできる」なんて料理ではなく、初めの何回かは失敗するかもしれないけれど、その後は自分の技術として応用が利かせられるようなる事を目標にしているので、店で実際にやっている事をそのまま見てもらい、ポイントになるところをできるだけ解りやすく解説する、というスタイルで進めました。
作った料理は、次の5種。
パルマ風リゾット
スパゲッティ トマト入りカルボナーラ
スパゲッティ ベーコン・ブロッコリ入り アーリオ オーリオ ペペロンチーノ
スパゲッティ ナポリ風トマトソース
トマトドレッシング



時々ダジャレを混ぜたりして、笑いを加えながら進めました(もともと落語家になりたかった人間ですから、そういうのは得意です)が、簡単なところを手伝ってもらったり、洗い物をしてもらったりと、すごくやりやすかったし、こちらも楽しませてもらいました。

一通り、作り方を見てもらったところで、ご主人やお婆ちゃんも加わって、試食タイム。
味見をしてもらうと共に、しっかりと味を憶えてもらう。


最後に、「とにかく何回も作ってみて、失敗を乗り越えて、自分の技術にしてほしい」と話し、すぐに作れるように、パルミジャーノ レッジャーノと岩塩を、ほぼ原価でお分けしました。
翌日電話をしてみたら、さっそく作ってみました、と言われたので、皆さん頑張ってみえるなぁ、と思った次第。
講習中に、ダジャレを連発して笑わせていた時、「店で見た時は気難しそうな人に見えたけど、こんなに気さくで面白い人だったんですね」と言われた。
以前、あるお客さんから、「マスターはすごいツンデレですよね」って言われた事もあるし、どうも取っ付きにくい人に見えてしまうみたい。
そういうイメージを払拭するためにも、これからどんどん人前に出て行くほうがいいんだろうな。
講習会の要望があれば、どこへでも出かけて行きますので、お気軽にご相談下さい。
思いつくまま書いたら、例によって長くなりましたが、久しぶりに、「書いたなぁ」って気がしました。
Facebook に書いた文章を手直しして使ったところもありますが、それでもやっぱり、書くという事はいいですね。
またこれからも、ちょくちょく書いていこうと思っています。
次回は「その2」です。
では、また。
Ciao. Arrivederci!!
久しぶりの投稿なんですが、今、見てみたら、9ヵ月半も更新してなかった・・・・決して、忘れていたわけではないんですが。
その間、覗いて下さった方々、ありがとうございます。
今は、店の事をすべて1人でやっているので、以前のように、思う存分長い文章を書くのは、かなり難しい状態で、Facebook にちょこっと書いてごまかしている状態なんですが、書きたいと思う事が溜まってきたので、思いついた勢いで書いてみようと思います。
中には、Facebook に書いた事と重複するところもありますが・・・・
とにかく、長編になるので、2回に分けてアップします。
ではまず、前回書いた、『こだまーれ 2016』のオープニングセレモニーの話から始めましょうか。
オープニングセレモニーは、4月24日の午後1時半の開演だったのですが、文化会館大ホールでのリハーサルは、その前々日と前日の夜、それに当日の昼前の3回という事で、予約が入っていなかったので、ホールに慣れるため、すべて参加しました。
それと、春慶塗の楽器がどこまで鳴るか、という事を実際に試してみたかったというのもありましたが。

文化会館の大ホールで演奏するのは初めての事で、どんな響きになるのかは、実際にやってみるまで分からなかったのですが、ホームグラウンドである『飛騨芸術堂』に比べて、ホール自体の容積が大きく、ステージ上に反響版がないため、客席に十分な音量が届くのかが問題になるわけです。
まぁ、結果としては、客席の後ろの方まで、ちゃんと音は届いていたそうですが、ごく控えめにPAを併用する事になりました。
最初のリハーサルに行った時、ホールに入ると、一面のスモークで、ホールの中が霞んでいるのに驚いた。
演出のため、という事だったけど、そこまでやる事が必要なんですかねぇ。

ステージに上がり、配置を決めるところから始まったのだけれど、これがまた厄介なんですよね。
いわゆる『多目的ホール』の場合、その構造から、ステージ上で発された音の大部分が、ステージの上と横に逃げてしまうため、少しでも多くの音が客席に届く位置を見つけなければならないわけです。
今回は、ステージの後ろの方の頭上に、発光版が4枚吊り下げられていたので、その前に並ぶ形で配置が決まりました。

スモークが充満する客席

演奏する曲は、
モーツァルト アイネ クライネ ナハトムジーク 第1楽章
ワーグナー 歌劇 ローエングリン 第2幕から エルザの大聖堂への行列
ハルヴォルシェン ヴァイオリンとヴィオラのためのパッサカリア
シベリウス アンダンテ フェスティーヴォ
の4曲で、ハルヴォルシェンの曲は、ヴァイオリニストの村中 一夫さんと、元団員でヴィオラの専門家である、小瀬 直統さんのデュオによる演奏。
過去に何回も演奏している曲ばかりなので、楽器ごとのバランスや、ホール内での響きを確認する方が重要な目的、といった感じでしたが、やはり、いつもとは違う感触でしたね。
でも、2日に亘るリハーサルで、結構響くようになったと思いました。
喉の弱い人は、スモークに咳き込みながらのリハーサルで大変でしたが、2日目からはマスクが用意されました。
で、いよいよ当日。
集合時間より早めに行ったのだけれど、もう、みんな集まって、指慣らしや楽譜のチェックをしていた・・・・気合が入っているな。



楽器の調整のために、府中市から駆け付けてくれたドンマイヤーさんも、調整に余念がない。

前日から、合奏団のメンバーの楽器も調整してもらったのだが、オレはヴィオラだけでなく、ヴァイオリンの調整もしてもらえた。
デュオの演奏をする、村中さんと小瀬君も、楽屋で練習中。

リハーサルの時間が来て、ステージの席に着く。



元団員の平塚さんも、今回の演奏に参加する事になり、久しぶりに一緒に演奏する。

配られたオープニングセレモニーのプログラムを見ると、春慶楽器には、それぞれ名前が付けられているとの事・・・・全然知らんかったわ。

でも、その名前が、作曲家の名前とオペラのタイトルをごちゃまぜにしたのは、いかがなものかと・・・・
iPad で写真を撮っていたら、すぐ隣のチェロの広田さんが、オレを撮ってくれた。

春慶塗のヴィオラは、小瀬君に渡したので、ここで弾いているのは自分の楽器。
リハーサルの間、ずっと春慶楽器を弾いていたのに、いきなり自分の楽器に戻ったら、少し小さい分、高めに音程を取ってしまい、感覚が戻るまで、ちょっと苦労しましたね。
でも、腕の長い自分には、大きいサイズのヴィオラが合っている事が分かったのは収穫でした。
最終リハーサルが始まり、アイネ クライネ ナハトムジークを弾き始めたのだけれど、前日までとは打って変わって、全然音が出ていない。
特に緊張しているわけではないのだけれど、自分自身も含めて、なんか萎縮している感じ。
とにかく、全曲通して弾いたら、最後のアンダンテ フェスティーヴォのあたりで、やっといつもの調子になったかな。
このアンダンテ フェスティーヴォの最後に加わるティンパニは、いつも演奏に参加してもらっている、高山市民吹奏楽団の小林さんにお願いしていたのだけれど、クレッシェンドして最強打になるトレモロが、客席ではあまり聴こえないという指摘があった。
それで、ヴァイオリンの後ろから、横へ移動したところ、聴こえるようになったとの事。
ステージ上の位置決めって、本当に重要だな、と改めて思った次第。
あとは、本番まで、しばし休憩。
その間も、ドンマイヤーさんは、団員の楽器の調整をしてくれました。
で、いよいよ本番。
ステージまでの通路で時間調整。
少し緊張してる、

と思ったけど・・・・そうでもないみたい。

ステージに上がって席に着き、静かに待っていると、幕の向こう側で、セレモニーが進んで行く。

そして、いよいよ幕が開き、アイネ クライネ ナハトムジークの演奏を始める。
たいていの場合、最初の曲の演奏は、幾分手探りというか、醒めた状態で演奏する事が多いのだけれど、この時もそんな感じ。
それなりの拍手をもらって、2曲目の「エルザの大聖堂への行列」に入る。
この曲は、弾いていて気持ちのいいところが結構あるので、だんだんノッてくるんですよね。
まぁ、ワーグナーの曲なんていうのは、ある種の「自己陶酔」がなければ成り立たないようなところがあるので、それでいいんじゃないかと思いますけどね。
後から聞いた話では、お客さんからの反応が一番良かったのが、この曲だったそうです。
続いてのハルヴォルシェンの『パッサカリア』は、殆どの人が初めて聴く曲だと思うし、あまり取っ付きやすい曲でもないのだけれど、変奏曲という事もあって、段々と引き込まれていくんですよね。
技術的にも難しい曲で、オレも挑戦してみたけど、第4変奏で挫折してしまったのだが、さすがに村中さんと小瀬君は、まったく危なげなく、全曲を弾ききった。
その上で、春慶楽器が、ちゃんとホールの一番端まで通る音を出せる事を証明してみせたわけです。
最後は、シベリウスの『アンダンテ フェスティーヴォ』
こういう式典で演奏するには、打って付けの曲ですね。
過去に何回も演奏している事もあって、合奏団のメンバーも、のびのびと弾いていたと思うし、弾き終えた後の達成感も、結構ありましたね。
今回初めて、文化会館の大ホールで演奏したわけだけれど、いい経験になりました。
これからも、機会があれば、いろいろなところで演奏していきたいですね。
高山市制施行80周年記念「高山祭屋臺からくり競演」
布袋台が、初めて安川通りを越えて上町へ入った、記念すべき出来事ですね。
オレ自身の興味は、4台のからくり屋台が揃う事より、布袋台が上町を通るところにありました。
で、中橋を渡った後、上一之町を下って蔵に向かうところを、布袋台に付いて移動しながらVTRに収めたのですが、その一部を You Tube にアップしました。
こういう事が、次はいつあるか分かりませんから、結構貴重なVTRなんじゃないかと思っています。
今年もGWに、全屋台の曳き揃えがあるそうですが、今から楽しみですね。
Musica Libera Ⅵ
5年前に始まった Musica Libera も、今回で6回目。
第1回から、楽器経験の一番短い(要するに、一番下手な)演奏者として参加していたのだけれど、段々レヴェルの高い参加者が増えてきたので、今回は参加しなくてもいいかな、と思っていたら、いつの間にかチラシに名前が載っていた・・・・
とりあえず練習中の、ベートーヴェンの『ト調のメヌエット』を弾く事にして、演奏会のための練習を始めたけれど、付焼き刃的演奏になる事は仕方ないか。
毎回、「恥をかくほど上手くなる」という言葉を信じて、恥をかきに行っているようなものだけれど、さて今回はどうなるやら・・・・
たまたま、当日の朝にヴァイオリンのレッスンがあったので、とにかく聴けるように、という事で、先生にいくつかのポイントを集中的に手直ししてもらったのだけれど・・・・実際に本番ではきちんと弾けたのか、自分では分かりません。
ステージに上がって弾き始めたら、こんなふうに演奏しようなんて考えているヒマもなく、それまでの練習で身体が覚えた事がそのまま出てしまうだけなんですよね。

先生がわざわざ聴きに来て下さった事も、余計に緊張感を高める事になったのだけれど、弓が飛び跳ねてしまう事もなかったし、自分の出した音がホールの残響として聴こえてきたので、しっかりとした音が出せたのだと思う。
そういう意味では、少しは進歩したのではないか思います。
毎回恥をかきにいっているようなものだ、と上に書いたけど、700年も前に、兼好法師が『徒然草』の第150段に書いた事を、オレは信じたいですね。
ちなみに、それを現代語訳したのがコレ。
これから芸事を身につけようとする人は、とかく「ヘタクソなうちは誰にも見せたくない。こっそり練習して、ある程度見られるようになってから披露するのがカッコいい」と言うものだけど、そういうことを言っている人が最終的にモノになった例はひとつもない。
まだ未熟で下手な頃から、経験が長く上手な人たちに混ざり、バカにされようと笑われようと、恥ずかしがらないで気にしないで、才能がなかったとしても立ち止まらず、踏み外すこともなく年を送っていけば、最終的に、その道の極みを嗜まなかった人よりも上の立ち場になれるし、人望も備わって、多くの人に尊敬され、天下一の名声も得られるようになるものだ。
”神レベル”に上手いと言われている人でも、最初は未熟だという評価を受けてきたのだし、そのパフォーマンスには欠陥があったりもした。それでも、道の掟に従い、これを重んじて真剣にやった人が、その道のプロとして、様々な人の先生となってきたのだ。この事は、どの分野でも変わらない話だ。
大きいヴィオラがやってきた!!
実を言うと、今まで使っていたヴィオラは、オレの前に合奏団でヴィオラを弾いていた小淵さんから借りていたのだけれど、オレより小さい人なので、そのヴィオラも小さめの、390mmのものだった。
ヴィオラという楽器は、その大きさにかなり無理がある楽器で、音域から考えると、もっと大きくなければならないのに、それでは肩に乗せて弾けないので、無理やり今の大きさになったわけです。
だから、ヴァイオリンの胴長が355mmくらいと決まっているのに対し、ヴィオラは決まったサイズがなくて、380~420mmまであるサイズ(海外には、さらに大きいものもある)の中から、扱いやすいサイズのもの、あるいは、自分が扱える中で(低音がよく出るように)一番大きいサイズのもの、という選び方をされるんですね。
この前弾いた春慶塗のヴィオラは、415mmという大き目のものだったのだけれど、腕が長いせいもあってか、すごく弾きやすかったし、音程も取りやすく思えたわけです。
そんな経験から大きいヴィオラが気になって、中国のショッピングサイト AliExpress で探していたら、安いのにすごく良さそうな、ストラディヴァーリのコピーで16.5インチ(420mm)のヴィオラをみつけたのだけれど、それが期間限定で8%off になり、さらに少し円高になったので、思わずポチってしまった。
本体に弓とケースと松脂付き、8%offで368ドル、それに送料50ドルを加えて418ドル・・・・カード会社の利用明細では、46400円ほどだった。(それからしばらくして急に円高になったので、ちょっと悔しかったけど)
そのショップからは、以前にもヴァイオリンの弓を取り寄せたことがあり、送料無料なのに、きちんと梱包されて送られて来たので、まぁ間違いはないだろうと判断したわけだけど、多少はギャンブル的要素もありますね。
一番気になったのは、サイトにアップされている画像には、裏板の杢目がすごくキレイなものが写っているのだけれど、実際に送られてくるものはどうなのだろうか、という事。
相手が自然の木を使ったものだけに、個体差というのは避けられないわけだけれど、やっぱりキレイなものの方がいいに決まってますからね。
オーダーしてから約2週間・・・・EMSで荷物が届いた。

大きさは想像していた通りだけれど、持ってみると異様に軽く感じたので、大丈夫かな、と思いながら箱から出してみると、

ケースの中に、ヴィオラと弓と松脂がキチンと入っていた。

ケースが発砲スチロール製のものなので、すごく軽く感じたわけです。
裏板を見てみると、ウェブサイトの画像にアップされていた個体が送られてきた事が分かり、やはりこの店はしっかりしているな、と感心した。

ちなみに、現在は別の個体の画像がアップされているので、各個体ごとに画像を変えているみたいだ。
今まで使っていたヴィオラと、大きさを比べてみると、胴体の長さだけでも、約3cm長い。

その分弦長も長くなるので、音程の取り方も微妙に変えなければならないわけです。
このヴィオラはすごく軽くて、今まで使っていた小さめのヴィオラよりも軽いので、左腕に負担はかからないのだけれど、手が大きいわりに指はそれほど長くないオレにとっては、弦が長くなった分、指を広げて押さえなければならないので、特に小指に負担がかかりそう。
でも、一番指を拡げなければならない、C線のGと、G線のAsを同時に押さえることができるので、なんとかなりそうではありますが。
付属の、いかにも安っぽい音のスティール弦(値段が値段だけに仕方がないんだけど)を、以前使っていた弦に張り替え、駒の位置を調整して音を出してみると、予想以上によく響く。
ただ、よく響くんだけど、なんか違う・・・・奥行きのない、薄っぺらい音・・・・
でも、いろいろ弾いているうちに、音の出し方が分かってきたのか、だんだん音が変わってきた。
その10日後に牧歌の里で演奏する曲を一通り弾いてみたら、音に芯が出てきて、それらしい響きが出るようになった。

この工房で製作された楽器を扱っている人が書いた文によると、この楽器に使われている木材は、古い建造物を取り壊した時に出る「建築古材」のスプルース(マツ科トウヒ属の木材 楽器や建築に使われる)を使って作られているので、完全に乾燥しているため、必要十分な厚さがあっても、軽くてよく響くのとの事。
複数のプロの演奏家から、音だけに関して言えば、入念に調整することで数百万円レベルの楽器と遜色ない音が出る、と言われたとか、この工房のヴィオラでコンクールに入賞したとか、書いてあって、それが嘘か本当かは分からないけれど、実際のところ、この値段で、これだけ良く響いてくれるのだったら、中途半端に高い楽器を買うより、こっちの方がいいんじゃないかと思ってしまった。
とは言っても、やっぱり、値段相応の部分がある事も否めないわけです。
駒の上に刻んである、弦を載せるための溝が、1つだけずれていたので、やすりを使って手直ししました。
また、本来は黒檀が使われる指板に、黒く塗った木が使われているので、時期を見て、黒檀のものに交換してもらわないといけませんね。
あとは、自分で出来ることを少しずつやって、弾きやすくしていかなければならないわけですが、まず手始めに、少し回しにくいペグをなんとかしたい。
というわけで、Lapella のペグ コンパウンドを手に入れて塗ってみた。
以前使っていた、Hill のペグ コンポジションは、色が茶色で、なんか汚く見えてしまうのだけれど、今回手に入れたものは、色もきれいで、ペグの回りもよくなった。
それから、高さも形も、自分にはいまいち合っていなかった顎あては、ヴァイオリンにも使っていて、すごく気に入っているSASのものに替えた。
ヴァイオリンには、一番軽いペアーウッド(梨木)のものを使っているが、ヴィオラ用にはメイプルウッド(楓)をチョイス・・・・杢目がきれいに出ていて、見た目もいいと思う。
ちなみに、ヴァイオリンもヴィオラも、肩当てから顎当てまでの高さが同じになるように調整してある。
ヴァイオリンとヴィオラをダブルケースに入れると、いかにもそれらしい雰囲気になります。
以前、これを見た人から、「プロみたい」って言われた事があったけど、まぁ、見た目も大切というか・・・・ヘタなんだから、見た目くらいは良くしておかないとね。
実際に、合奏団の練習の時に、このヴィオラを弾いていたら、周りの人から、「良く鳴るねぇ」って言われたので、そういう意味で、このヴィオラは「当たり」だったと思う。
あとは、自分の楽器として、地道に弾き込んでいくだけ・・・・まぁね、技術的にはまだまだなんだけど、
ところで、この前、あるサイトを見ていたら、17.5インチのヴィオラの話が出てきて、それがすごく気になっているんだけれど・・・
出張料理講習会
今までに、料理を教えてほしい、といわれた事は何回かあったのだけれど、最終的に詰めるところまで行かず、立ち消えになったのですが、今回は、希望された方がきちんと話を進めて下さったので、実現する事になりました。

参加者は、主婦の方6名で、その中の1人の方のお宅で行いました。
いきなり初めての場所で、家庭用の火力の弱いガスコンロを使ってやる事には、むつかしい点もありますが、そこは専門家ですから、何とでもします。

「先生」なんて呼ばれるのは、調理師学校で、イタリア料理主任講師として教えていた時以来、20数年ぶりなので、少し気恥ずかしい気もしたけれど、すぐに慣れた。
「誰でも簡単に失敗なくできる」なんて料理ではなく、初めの何回かは失敗するかもしれないけれど、その後は自分の技術として応用が利かせられるようなる事を目標にしているので、店で実際にやっている事をそのまま見てもらい、ポイントになるところをできるだけ解りやすく解説する、というスタイルで進めました。
作った料理は、次の5種。
パルマ風リゾット
スパゲッティ トマト入りカルボナーラ
スパゲッティ ベーコン・ブロッコリ入り アーリオ オーリオ ペペロンチーノ
スパゲッティ ナポリ風トマトソース
トマトドレッシング



時々ダジャレを混ぜたりして、笑いを加えながら進めました(もともと落語家になりたかった人間ですから、そういうのは得意です)が、簡単なところを手伝ってもらったり、洗い物をしてもらったりと、すごくやりやすかったし、こちらも楽しませてもらいました。

一通り、作り方を見てもらったところで、ご主人やお婆ちゃんも加わって、試食タイム。
味見をしてもらうと共に、しっかりと味を憶えてもらう。


最後に、「とにかく何回も作ってみて、失敗を乗り越えて、自分の技術にしてほしい」と話し、すぐに作れるように、パルミジャーノ レッジャーノと岩塩を、ほぼ原価でお分けしました。
翌日電話をしてみたら、さっそく作ってみました、と言われたので、皆さん頑張ってみえるなぁ、と思った次第。
講習中に、ダジャレを連発して笑わせていた時、「店で見た時は気難しそうな人に見えたけど、こんなに気さくで面白い人だったんですね」と言われた。
以前、あるお客さんから、「マスターはすごいツンデレですよね」って言われた事もあるし、どうも取っ付きにくい人に見えてしまうみたい。
そういうイメージを払拭するためにも、これからどんどん人前に出て行くほうがいいんだろうな。
講習会の要望があれば、どこへでも出かけて行きますので、お気軽にご相談下さい。
思いつくまま書いたら、例によって長くなりましたが、久しぶりに、「書いたなぁ」って気がしました。
Facebook に書いた文章を手直しして使ったところもありますが、それでもやっぱり、書くという事はいいですね。
またこれからも、ちょくちょく書いていこうと思っています。
次回は「その2」です。
では、また。
Ciao. Arrivederci!!
2012年02月07日
人生を変えた出来事
Ciao. spockです。
久しぶりの更新です・・・・って、前回から、もう7週間も経ったのですね。
なんせ、今年初の更新ですから。
12月の後半、特に23日以降は予約がびっしりと詰まっていたため(こんな事はオープン以来初めてでしたが)、年賀状を書くヒマもなく、年賀状を頂いた方には御無礼をしたままになっていますが、いつか近況報告的なはがきを出そうと思っているところです。
まぁ、忙しかったのは本当にありがたい事ですが、必ずしも「忙しい=儲けが多い」とはならないところが辛いところなんですけどね。
1月はその反動か、全くヒマで、1月としては最低なんじゃないかと思うのですが、そんなヒマな時でも、やる事は少なくならないんですよね。
その上、2月のヴァイオリンの発表会の曲に「難曲」を選んだ(習い始めて2年そこそこでクライスラーを弾こうというのが異常な事なのかもしれませんが)事もあって、そっちにも時間を取らなければならないし・・・・
まぁ、そんなこんなで、相変わらずバタバタしてますけど、充実した日々を過ごしている事には間違いないと思います。
あ、遅くなりましたが、今年もよろしくお願いします。
考えてみたら、このブログを書き始めて、もう5年経ったんですよね。
2007年の1月、劇団無尽舍の新年会に参加した時に、団員の1人から「ひだっち」という名前を聞き、それでこのブログを知って書き始めたわけです。
最初は当然、料理やワインの事を書くつもりでいたのだけれど、書き始めてみたら、料理の事は少しで、音楽やスポーツ、クルマの事ばかり書く事になりましたけどね。
もちろん、このブログに書いた料理の話を読んで、予約を入れて下さる方もおられますから、料理の事を書くのが宣伝になっている事は確かです。
でもね、自分の作る料理に関しては、どんなに詳しく書いたところで、実際に食べてもらわなければ解らないわけで・・・・逆に言えば、料理を食べてもらえば解る事なんですよ。
それ故、料理について書く事には、あまり気が乗らない事も確かなんですよね。
まぁ、根本的に捻くれた人間ですから、余計にそう思うのかもしれませんが。
でもね、こんなマニアックな一般的ではないブログ・・・・言い換えれば、不人気ブログ・・・・ですが、現在11人もの方に読者登録して頂いている事は、本当にありがたい事です。
ウチの料理と同じで、一般受けはしないけど「解る人には解る」という事なんだと思います。
これからも、超マニアックなブログを書いて行こうと思っていますので、引き続きご愛読のほど、よろしくお願いします。
さて今回は、極め付けのマニアック超長編です。
覚悟して読んで下さい。(笑)
この前(といっても去年の事なんだけれど)何気なくカレンダーを見ていて、ふと、あれから25年も経ったんだなぁ、と気がついたのですが、それはオレの人生を大きく変えた出来事でした。
その事をきっかけに生き方が180度変わった、と言ったら大袈裟かもしれないけれど、それくらいオレにとっては大きな出来事だったのです。
今回はその事について、思い出しながら書いてみます。
また、かなり長くなりそう・・・・というか、過去最長のブログになりそうですが。
今でこそ、アメフトだ、自転車だ、水泳だ、って言っているけれど、オレ、子供の頃は「スポーツ大嫌い少年」だったんですよね。
まぁ、球技が全くヘタ・・・・というか、球技というものに対して、ホンの僅かな興味さえ持つ事が無かったんで、経験もないし、上手くなろうなんて気持ちもないから、いきなり体育の時間にやらされても、できるわけがない。
それが、スポーツ嫌いになった原因だったわけです。
当時は、スポーツが得意なヤツは例外なくなく野球をやっていたけれど、オレは今でも、あんな小さい球をあんな細いバットで打つ、という行為が異常としか思えませんからね。
サッカーも体育の時間に結構やらされたけど、全員が右に左に大移動しているだけのつまらなさ、あるいは不毛さを、どうすれば面白く思えるのか、いまだに理解不能です。
やりたいという気持ちが全く無い人間が、(体育の時間という限られた時間であっても)無理やりやらされる事ほど悲惨な事はないわけですよ。
小学3年の時、体育の授業でキックベースボールというのをやったのですが、転がってきたボールを目で追っていたら、先生が飛んで来て、何をしてる、って言われて思いっきり背中を叩かれた事がありました。
今思えば、そのボールを拾ってランナーにぶつけなければならなかったのだが、その頃は、そうしなければいけないという事も知らなかったし、そうしようという気もなかったわけです。
まぁ、そんな事もあって、自然にというより、必然的にスポーツ嫌いになっていったのだと思います。
とは言っても、身体能力は人並み以上にあったみたいで、クラスで北山へ走りに行った時も、1位になった事が何回かあったから、持久力も結構あったのだと思うし、後に肺活量を量ったら5000ccありましたから、他の人よりラクに走っていたのかもしれません。
50m走の記録なんかでは、たいていクラスで5番前後だったから、『選手リレー』なんていうのには出た事はなかったけれど、速い、普通、遅い、と分ければ、速い方には入ったと思いますね。
だから、運動会は結構楽しめたけど、球技大会なんて、苦痛以外の何物でもなかったですね。
まぁね、下手なりにそういう事を分析できていた事が、その後スポーツに興味を持ち始めた時の、進むべき指針になった事は確かだと思いますけどね。
ただ、スポーツはやらないけれど、見るのが好きなスポーツもあったわけで、そういう好みを分析すると、性格的な自分の好き嫌いというものがハッキリと見えてくるんですね。
オレの場合、1回動き出すごとにハッキリと結果の出るもの、を好む傾向にあるんですよ。
で、なおかつ、進行がスピーディーなものじゃないとダメなんです。
だから、サッカーみたいに、常にダラダラと動いているのは生理的に合わないし、野球は、ピッチャーだけは動いているけれど、肝心のバッターが動くまでに時間がかかりすぎるので、面白さが持続しない。
バレーボールなんかが合っていそうな気もしたけど、当時はバレーボール人気が最高の時代だったので、臍曲りなオレは見る気にもならず、むしろスピーディーなバスケットボールの方が面白いと思ってましたね。(とは言っても、あまり見る機会はなかったけど)
ゴルフなんかは、1回打った後、ダラダラと歩いているのがうっとおしい・・・・走っていけばいいのにねぇ。(スピードも得点に入れたら面白いと思うけど。)
一番面白いと思って見ていたのがボウリングでしたけどね。
そんな時、たまたまテレビで見て興味を持ったのがフットボール(アメフト)でした。
当時はフットボールの試合がテレビで中継される事なんて、年に2〜3回もあればいいところでしたが、そういう時はテレビの前で、ルールもよく分からないまま、真剣に見てましたからね。
日米選抜ティームの試合が日本であり、それで来日したボブ・ヘイズ(東京オリンピックの100メートル金メダリスト。その後、ダラス カウボーイズのWRとしてプレイし、72年のスーパーボウル制覇。誰も追いつく事ができないヘイズをカヴァーするために「ゾーン ディフェンス」が発達した。)がフルスタイルで『徹子の部屋』に出演したのもこの頃の事でした。(フルスタイルで登場したヘイズを見て黒柳徹子が「このお衣装はアメリカンフットボールの・・・・」って言ったのが笑えましたけど)
ただ、フットボールの情報なんて全然ないわけで、たまに週刊誌の特集なんかの記事があると、切り抜いて保存し、そういう少ない情報の中でルールを覚えていったわけですが、高校3年のある日、たまたま立ち寄った本町の中田書店で『アメリカンフットボールマガジン』という雑誌を見つけたのです。
すぐに買って帰りましたねぇ。
当時高山で、その雑誌を扱っていたのは中田書店だけで、月に3冊だけしか入らなかったので、発売日には必ず買いに行って、貪るように読んでいましたが、残りの2冊は、いつも売れ残っていたみたいでした。(笑)
まぁね、子供の頃から、他人と同じことはやりたくない、という性格でしたから、そういう状況も楽しんでいたのかもしれませんが。
見るスポーツは、そんな状態でしたが、実際にスポーツをやろうと思う事は全くなかったので、スポーツとは全く無縁の生き方をしていましたが、そんな中で、やるスポーツとして唯一興味を持てたのがボウリングでした。
投げればすぐに結果が出るし、交互に投げるのですから、緊張感を維持したまま速いペースで進める事ができる・・・・オレの求めるものがあったわけです。
高校生の頃は、ちょうどボウリングブームが過ぎ去った時期だったので、投げ放題500円、なんてのもありましたから、結構やりに行ってましたね。
社会人になり、20代の初めの頃、自分の投げ方に合うレーンコンディションのボウリング場を大阪で見つけたので、神戸から毎週通っているうちにボールを作る事になり、休日のたびに15ポンドのボールをかかえて大阪へ通ってました。
ボールを入れたバッグをかかえて一日中歩き回っていたのですから、今考えると、体力があり余っていたんだなぁ、って思いますが、ウデの方はあまり上達せず、ハイゲームが208でしたから、まぁ、そんな程度のものだったんでしょうね。
ボウリング熱が冷めた後、しばらくは何をする事もなかったのですが、20代から老化は始まる、なんて聞いていましたから、なんか運動をしないとダメだ、って意識だけはありました。
「25歳はお肌の曲がり角」なんてCMがありましたが、同様に体力も落ちていくはずですからね。
でも、そうは思いながらも、何をしたらいいのか、皆目見当もつかずにいる状態が続いていました。
そんなある日・・・・忘れもしない1986年8月8日でしたが、当時働いていた『ベルゲン』に、ある雑誌が取材に来たのです。
その雑誌は、創刊されて間もない『ターザン』で、「パスタでダイエット」という特集のための取材でした。

こんな封筒で送られて来たのを、今でも大切に保管しています。

その時作ったのが『イカ墨入りタリアテッレのカルディナーレ風』で、その作り方まで紹介されています。

 25年前のオレです。
25年前のオレです。
その2日前に、店の仲間で夜中にクルマをとばして日本海まで行き、竹野浜で海水浴をして来たばかりだったので、日に焼けて顔が赤いんですけどね。
当時オレはセカンドをやってましたが、なぜかシェフとしてオレの写真が出る事になり、初めて全国紙に載ったわけです。(支店のチーフをやっていた先輩から、なんでお前が載るんだ、ってイヤミを言われたりもしましたけどね。)
取材にみえたのが、グーフィー森さんと、カメラマンの村林真叉夫さんでしたが、その時、見本紙として置いていかれた『ターザン』が、その後のオレの生き方を変えたのだと思います。
ちょうどその頃は、いわゆる『フィットネス』のブームが始まった頃で、その牽引役となったのが『ターザン』でした。
当時は、レオタードにレッグウォーマーとリーボックでエアロビクス、というのが流行りましたからね。
身体を動かさなければ、と考えていたオレにとって、ターザンは格好の指針となったわけです。
近所の本屋へ、ターザンのバックナンバーを全部注文し、ターザンを毎号買って読んでいました。
で、載っていた広告を見て、エクスサイズマシーンを注文し、筋トレを始めたのですが、想像していたほど筋肉が付かないんですよね。
いろいろ調べた結果、体質的にムキムキになるタイプではないようだ、という事が分かったのはずっと後の事ですが、その頃は諦めずに、しまいにはソロフレックスまで手に入れて、一生懸命やってましたけどね。
ちなみに、そのソロフレックスは、その後の度重なる引っ越しにも手放す事無く、今もウチにありますが。
で、その後届いたバックナンバー(本屋の手違いで2冊だけ入手できなかったけれど)の第6号の中に、『見栄を張るならバタフライ』という特集があって、見開きで載っていた、当時の世界記録保持者ミヒャエル・グロスが泳いでいる写真を見て「わぁー、カッコエエ!!」って思いましたね。

それはミーハー的なカッコよさではなく、人間の身体の躍動感が、見開き2ページの写真いっぱいに表れていたんですよ。
で、その内容を読むと、バタフライの難しさについて書いてあり、スウィミングスクールでもバタフライのクラスになると急に落伍者が続出する、と書かれていたのですが、もともと捻くれた人間ですから、難しいって言われると、敢えて挑戦したくなるんですよね・・・・で、水泳を習いに行くことにしたのです。
週に一度、休日の夜にスクールに通い、初歩の水慣れから、クロールとバック、ブレストストロークを修了するのに5ヶ月・・・・週一にしては結構早く進んだと思います。
特にブレストストロークは、コーチから「速いですねぇ」というお褒めの言葉をもらって4回で修了しましたが、根本的にオレはブレストストローカーなんだと思います。
今でもプールに行くと、ブレストストロークしかやりませんからね。
で、いよいよバタフライのコースに入ったのですが、これが本当に難しかった。
初回から、手足のタイミングは完璧に合っている、ってコーチに言われたのですが、どう頑張って泳いでも、全然進まないんですよね。
当時は今のようにyoutubeで映像を見る事なんかできなかったわけで、スウィミングスクールにあったヴィデオをダヴィングしてもらって、それをスロー再生して研究したり、連続写真で詳しく解説された『スイミング・ファースター』という本・・・・確か7000円位する高い本だったので、いつも本屋で立ち読みしてましたが・・・・を何回も見て研究したり・・・・
B型的執念で、とことん研究しましたねぇ・・・・でもね、上手くいかないんですよね。
ブレストストロークのクラスは1月もかからずに終ったのに、バタフライでは1年以上も悩み続け・・・・
ターザンに書いてあった通り、本当に難しかったけれど、落伍者になる事だけは避けたかった・・・・と言うより、なぜ上手くいかないのか、という原因究明に一生懸命になっていたのだと思います。
確か小学校の2年の時だったと思うけど、どうしても鉄棒の逆上がりができなくて、毎日夕方、親父と一緒に西小学校へ行って練習し、やっとでできるようになった事がありましたが、なんかあの時の事を思い出したりしていましたねぇ。
スポーツに限った事ではないのだろうけど、テクニックやスキルを身につけようとする時、どうしようもなく高い壁が立ちはだかる事がありますが、意外なきっかけから壁を打ち破れる事があります。
この時も、正にそんな感じでした。
ポートアイランドにあった市営プールは、休館日と店の定休日が同じだったので行った事がなかったのですが、祝日の関係で休みがずれた時、初めて行く事ができました。
で、泳いでいたら、すぐ隣で、おじいちゃんが孫らしい女の子にバタフライを教えていたのですが、その子もオレと同じように、バタフライで苦労しているようでした。
何気なくそっちを見ていた時、そのおじいちゃんが、こんな事を言っていたのです。
「もっと角度をつけて思いっきり頭から突っ込め。」
それはいわゆる『天啓』だったのだと思います。
バタフライの手足の動きは、クロールの動きを左右同時にしているようなものですが、クロールと決定的に違うのは、身体全体をうねらす事・・・・水面を縫うように泳ぐ事なんです。
それは充分過ぎるほど頭では理解していたのだけれど、身体はそのように動いていなかったわけで、うねりを出すために必要な、ある程度以上の角度で突っ込む事ができていなかったんですね。
それが分かればこっちのもの・・・・と言うほど簡単な事ではなく、動きにムダがあるせいもあって、結構疲れる泳ぎ方ではありましたが、なんとかバタフライを泳げるようになったわけです。
でもね、その事によって、スポーツが苦手、という子供の頃からのコンプレックスを、完全にとは言えないまでも、克服する事ができたのだと思います。
とにかく諦めずにやる事・・・・それしかないって感じですね。
ところで、競泳用の水着と言えば、今ではスパッツみたいなのが主流のようですが、オレが水泳を習っていた頃は、例外なくビキニ(いわゆる『競パン』)でした。
大人になってから水泳を習う場合、あの競泳用のビキニに抵抗を感じる人が結構多かったそうなのですが、その頃すでにオレは、下着はかなり小さいビキニを穿いていた(今でもそうですが)ので、全く抵抗がなかったし、そういう意味でも、すぐに馴染む事ができたんだと思います。
ちょうどその頃、西ドイツはミュンヒェンのスポーツ用品店 Schuster から取り寄せたカタログを見ていたら、ドイツのSpeedoのビキニが載っていて、それがスゴくカッコ良かったんですよ。
その頃のビキニって、横の部分の幅が5〜6cmくらいあったのだけれど、ドイツ製のそれは、その半分くらいしかなくて、その分、足が長く見えるんですね。
で、早速取り寄せて、プールではいつもそれを穿いていたのだけれど、結構インパクトがあったみたいで、練習終了後のサウナでいろいろ訊かれましたからね。
その後、80年代の終わりから90年代中頃までの日本の水泳界では、スウィマー達が、速さだけではなくビキニの小ささを競うような風潮がありましたが、オレはそれよりずっと前にやっていたわけです。
その後、抵抗を減らす、という事で、スパッツ型の水着や、全身水着まで出てきましたが・・・・確かに0.1秒を競うコンペティションスウィマーにとっては当然の選択なんでしょうけど・・・・なんか、水泳自体が面白くなくなりましたねぇ。
ソウルオリンピックの背泳のゴールドメダリスト、鈴木大地が、オリンピック前のインタヴューで、どんな水着で泳ぐのですか、と訊かれて、かなりちっちゃいヤツ、って答えていましたが、その言葉には、身体一つで戦う、という潔さがありました。
水着の面積が大きくなるとともに、そういうものが無くなってしまった事を残念に思うのはオレだけでしょうか。
以前は、ビキニじゃないと泳がせてもらえない競泳用のプールが結構ありましたが、今はスパッツやボックスタイプの水着が主流で、ビキニが少数派になっているのは残念な事だと思います。
欧米人に比べて足の短い日本人の場合、スパッツを穿くと余計に足が短く見える傾向にあるので、競技以外の時はビキニの方が見場がいいと思うんですけどねぇ。
 今でもヨーロッパでは、ビキニじゃないと入れないプールが多いのだそうですが、あるネット上の掲示板で見つけたこの画像はフランスのプールに掲示されているものだそうで、見ての通り、ビキニ以外は禁止ですね・・・・おそらくそれは、ヨーロッパにおけるヴァカンスの考え方によるものなのだろうと思います。
今でもヨーロッパでは、ビキニじゃないと入れないプールが多いのだそうですが、あるネット上の掲示板で見つけたこの画像はフランスのプールに掲示されているものだそうで、見ての通り、ビキニ以外は禁止ですね・・・・おそらくそれは、ヨーロッパにおけるヴァカンスの考え方によるものなのだろうと思います。
偉い人ほど長くヴァカンスを取る、と言われるヨーロッパでは、日焼けをしていないと尊敬されないという風潮があるようで・・・・イタリアの『経団連』の人達や歴代首相は、みんな見事に日焼けしています・・・・ヴァカンスに行ったら、他に何もしないで少しでも多く身体を陽にさらして遊ぼうとするわけですから、水着は身体を覆う面積が小さい方がいいというい考え方は当然であり、また「必然」なのでしょう。
オレは今でも、プールや海ではビキニしか穿かないし、できるだけ小さいサイズのものを穿く事にして(この歳になっても尻の割れ目が見えるビキニで泳いでいる事は以前にも書きましたが)、ビキニが似合わなくなったら終わりだ、って自分に言い聞かせながら、常に身体に緊張感を持たせているわけですが、まぁ、そういう『緊張感』のおかげで、体形が20代の頃からほとんど変わっていないのだと思うのですけどね。
男たるもの何かあった時には身体一つで飛び出して行く、くらいの気概は常に持っているべきだとオレは思っていますが、ダブダブのパンツを穿いてダラダラと歩いているようなヤツには絶対に無理だろうな。
まぁ、スポーツに目覚めたのは遅かったけれど、基本的な考え方は、完全に体育会系なんでしょうね。
オレの考え方の根本に not or all 的なところがある上、結構楽天的な性格もあってか、かなり極端な事を考え、実行してしまう人間ですから、バタフライを泳げるようになってスポーツ的コンプレックスがなくなった事で、それまでは「絶対に無理」と思っていた事でも、実際にできるんじゃないかと思い始めたんですよ。
で、ちょうどその頃から赤坂へ行く話が決まっていたので、東京へ行けばそれが本当にできるんじゃないかと思って、そのための準備として身体を作っておこう、なんて考えていましたからね。
オレには根本的に「ティームスポーツ」は向いていないと思います。
他人の所為で負けるのはイヤだし、自分の所為で負けたらもっとイヤですからね。
ラグビーの世界では、One for all, all for one. とよく言われるそうで、それが素晴らしい考え方である事は認めますが、面と向かって言われたら、オレは絶対逃げ出すと思いますね。
だから、オレは生涯ティームスポーツをやる事はないだろう、ってずっと思っていたのですが、そんなオレの考え方を根本から揺り動かしてしまうほどの魅力を持っていたのがフットボール(アメフト)なんですよ。
アメリカンフットボールというのは、いろんな意味において「特殊」なスポーツですから、いわゆる「草野球」というようなノリでやるのは絶対に無理で、身体作りから、その複雑なルールを覚える事まで、本気にならなければ無理、というか、安易にやれば危険だ、という事も良く分かっていました。
だから、たいしたスポーツ経験も無く、普通ならプレイヤー達が引退を考える年齢になって始めようという事が、もうムチャクチャな話なんですが、ちょうどその頃に読んだフットボール誌に、企業のフットボールティームの特集があり、オレと同じ年代でスポーツ経験の無いプレイヤーが意外といる事を知って、きっとオレにもできる、って勝手に思い込んだからなんですけどね。
東京へ行ってから、フットボール誌で見つけたプライヴェートティームに連絡を取り、練習に入れてもらったのですが、初めての練習で、入念なストレッチから準備体操を経て、ダッシュやステップ等の運動をした時は、ハードではあったけど、本当に面白かったですね。
自分の意識としては、それほどしんどいとは思わなかったのだけれど、身体の方は悲鳴を上げていたみたいで・・・・3回目くらいまでは、グラウンドの隅へ行って吐いたりした事もありましたからね。
でも、それ以降は問題なくついていけたのが、自分でも意外でした。
もっとも、フットボールをやるには些か細い体形のオレは、他の人達に比べて体重が軽かったから、身軽な分、走る事や敏捷性に関しては有利だったのだとは思いますが、全くのズブの素人が、自分よりずっと若いプレイヤー達についていけた事は、その後、体力的に大きな自信となりましたね・・・・って、案外自己満足だったりするんですが。
でも、後に後輩が、自分もやりたいと言ったので、練習に連れて行ったのですが、スポーツ経験もあり、オレより10歳近く若い後輩なのに、数回練習に行ったところで、身体が持ちません、と言ってギヴアップしてしまった事を考えると、オレの体力も結構捨てたもんじゃないな、って思いましたけどね。
以前に読んでいた『タッチダウン』誌に連載されていた、関学ファイターズ元監督の武田 健さんの話の中で、アメフトを始めたばかりの初心者に対し、まず手に入れるものはヘルメットだけでいいから、練習中はいつもヘルメットを被って慣れる事から始めるように、と書かれていた事を思い出し、すぐに渋谷のQBクラブへ行って、Pro AirⅡというヘルメットを買ってきたのですが、ヘルメットを被って練習するレヴェルまでいくのに、やはりそれなりの時間は必要でした。
そういえば、フットボールを始める一月ほど前に、社内のボウリング大会で優勝して賞金3万円を貰ったのですが、ちょうどその3万円がヘルメット購入資金になりました。
まぁ、そんなふうに毎週日曜日の練習に通っていたのですが、ある程度慣れたところで、ヘルメットとショルダーパッドを着けてブロッキングの練習が始まったら、完全に当たり負けしてしまうんですね。
敏捷性の面では有利だった体重の軽さが、ボディーコンタクトになると弱点になってしまい、同じ力でぶつかっても、体重の軽い方が押し返されてしまうわけです。
体重を増やさなければと思って、ウェイトゲインプロテイン、なんていうのをガバガバ飲んだりしましたが、体質のせいか全然体重が増えないんですよね。
この歳になると、そういう体質のおかげで、体形が変わっていない事をありがたく思いますが、当時はそういう体質を恨めしく思ったものでした。
10回くらい練習に行った頃だったか、いつも面倒を見てくれていた先輩が、少し離れたところからオレを見て「だいぶ様になってきたな、最初はどうなる事かと思ったけど」って言ったのですよ。
全身にプロテクターを着けたあのスタイルが最初から似合う人って、まずいないと思うけど、特にオレのような細い体形だと難しい・・・・だから、様になってきた、って言われた事は本当に嬉しかった。
多くの装備を身に着けるフットボールプレイヤーは、他のどのスポーツのプレイヤーよりも、ユニフォームが似合ってないとみっともないですからね。
もっとも、そのスタイルが様になっていれば上手い、とは言えません・・・・でも、仕事でもスポーツでも、上手い人は間違いなく制服やユニフォームが似合っている、というのは真理だと思いますね。
練習に通い始めて3ヶ月ほど経った時、練習試合をする事になって、江戸川の河川敷にある競技場へ行ったのですが、前夜の雨のせいで芝の状態が悪く、芝が傷むという理由で管理人から使用中止を言い渡されてしまい、仕方がないので、いつも練習している河川敷のグラウンドでやる事になったのです。
で、メンバーのクルマに分乗して近くまで行き、河川敷まで住宅地の中を歩いて行ったのですが、住宅地の道路を、ショルダーパッドを着けてヘルメットを抱えた男達が30人近く、クリートをカツカツと鳴らしながら歩いているのって、端から見れば異様な情景だっただろうと思いますが、その時オレは、絶対にやる事はないと思っていたティームスポーツを今自分がやっている、という事実を改めて不思議に思ったものです。
この日の試合では、勝ちがほぼ決まったフォース クウォーターの終わりの方で、まだナンバーのついていないジャージのまま、WR(ワイドレシーヴァー)として出場させてもらい、数回のプレイに参加しました。
明らかにビギナーだと分かるオレは全くマークされなかったので、誰にも邪魔されずQB(クウォーターバック)の指示通りのコースを走り、振り向くと、オレ以外のWRが完全にマークされていたので、QBがオレに向けてボールを投げようとしていたのですが、来る、と思って身構えた瞬間、QBがサックされて試合終了・・・・たったそれだけのプレイではあったけれど、なんか感動しましたね。
この頃になると、傷ついたり、腫れ上がったりした自分の腕を見て、充実感を感じていたりもしましたが。
さらにその後、横須賀の米軍基地でネイヴィーティームとの試合があり、基地内のフットボールフィールドに立った時の感動といったら・・・・ホント、世界が変わった、って気がしましたね。(その時の事は、ずっと以前のブログに書いたので、そちらを見て下さい。)
その後、夏休みに遊びに行ったスウェーデンで、足に怪我をした事と、店の定休日が変わった事が重なって、練習に行けなくなってしまい、アメフトから離れてしまったのですが、一番面白くなったところで止めなければならなかったせいもあってか、未だに心残りになってますね・・・・この歳になっても、またやりたいな、って思いますから。
元フットボーラーのお客さんと、アメフトの話で盛り上がる事がよくあります。
山ちゃんや、中京テレビ岐阜支局長のMさんと話をしていると、またアメフトやりてぇな、という言葉が出てくるんですが、バリバリの若い現役プレイヤーとは違うので、一部タックルを規制したり、アーリーホイッスルを採用した「シニアルール」でやれば、きっと今でも楽しめるでしょうね。
せっかく姉妹都市がデンヴァーなんだから、指導者に来てもらい、基礎からきっちり教わってティームを作り、アメフトで交流なんてのもいいと思いますね。
さらには、ブロンコスのプレイヤーを何人か呼んで、ビッグアリーナでクリニックとイヴェントでもやれば、日本中からフットボールプレイヤーやコアなフットボールファンが、間違いなく集まります。
日本中、どこの町へ行っても、というか、地方へ行くほど、野球とサッカーくらいしかスポーツの選択肢がないのは寂しいですよね。
だから、敢えて地方の小都市である高山でアメフトをやって、それを発信していったら、きっと面白いと思うし、他にはやっていない事ですから、町おこしとしても効果的だと思いますね。
ここまで書いてきて考えてみたら、アメフトをやっていた時の写真というものがない事に気がついた・・・・まぁ、みんなに付いて行くのに精一杯だった事もあって、写真を撮るヒマもなかったのだと思うのだけれど。
そういえば横須賀の基地へ行った時、ティーム全員で写真を撮った事があったけど、その写真を貰っていないんですよね。
アウェイ用のホワイトのジャージで撮ったのだけれど、その時オレはまだアウェイ用ジャージを持っていなくて、ひとりブルーのジャージで写っているはずなのだけど・・・・
(田中さん、もしその写真があったら、スキャニングして送って下さい。)
さて、フットボールから離れてしばらくした頃、店の後輩から、一緒にスクーバ ダイヴィングをやりませんか、って誘われたんですよ。
しばらく情報収集した上で考えて、やろうって決めた時、その後輩はもう別の事を始めていて、結局オレ一人でダイヴィングショップへ行き、伊豆大島でオープンウォーターの講習を受けました。
 伊豆大島の『パームビーチ』のプールサイドで、一緒に受講した仲間達、そしてインストラクターのみっちゃんと。
伊豆大島の『パームビーチ』のプールサイドで、一緒に受講した仲間達、そしてインストラクターのみっちゃんと。
スクーバ ダイヴィングと言えば、いわゆる「レジャー」の代表みたいなイメージがあって、ダイヴィング誌のアンケートの結果を見ても、ダイヴィングの一番の目的は「魚を見る事」という答えが一番多いのですが、オレは「地形派」で、トンネルをくぐったり、洞窟へ入ったり、ドロップオフの上で浮遊したり、というのが好きでしたね。
だからオレは、なだらかな地形が多い東伊豆よりも、険しい西伊豆の海の方が好きです。
土肥の『白根』の、深度70mの海底から立ち上がるドロップオフもすごかったけど、雲見の『牛付岩』へ初めて行った時は、本当に感動しましたねぇ・・・・もう、岩の間を通り抜けながら泳いでいる間中、ワクワクし通しでしたから。
ただ、雲見って、伊豆半島の中で東京から一番遠いところなので、2回しか行けなかったのですけどね。
スクーバダイヴィングに関しても、オレはいつのまにかスポーツとしてのダイヴィングを目指していたのだと思います。
とにかくスキルアップのための講習を受け、ある意味で「危険度」の高い、より深いところ、より流れのあるポイントを求めて、海へ行っていましたからね。
新しいスキルを身につけるために、スペシャリティーコースを受講するのですが、その中でも『サーチ アンド リカヴァリー』、要するに「海の中でものを探し、引き上げる」という技術のコースを受けたいと思っていたのです。
ところが、そのコースを受けたいという人がいないんですよね・・・・かなりマニアックな技術ですから。
正月に大島へ行った時、まわりの人達を説得して何とか人数を揃え、そのコースを受講する事ができたのですが、(他の人はどう思ったかは分からないけど)オレはそれまでに受けた他のどのコースよりも面白いと思いましたね。
やっぱり、目指すものが他の人達とは、ちょっと違っていたんでしょうね。
結局は仕事が忙しくなって諦めたのだけれど、一時はプロを目指した事があって、その時はプールに通って長距離を泳ぐ練習をしたり、ダイヴィング用プールで、二人で泳ぎながら一つのレギュレイターで交互に呼吸したり、水底で装着している機材を全部外し、もう一度着け直したり・・・・そんな事を結構楽しんでやってましたから、完全に体育会系のノリですよね。
時間が無い人間ですから、沖縄や海外の海なんて考える事もなく、ひたすら伊豆の海で潜っていましたが、約3年で130本ほど潜りました。
一応、アマチュアの最高ランクであるMSD(マスター スクーバ ダイヴァー)の認定を受けましたが、ホント、よくあれだけ潜ったものだと、今になっても感心します。
ただ一つ、未だに残念に思っているのが、御蔵島でイルカと一緒に泳ぐ、というツアーに行き損ねた事・・・・仕事の都合とはいえ、あれだけは本当に行きたかったなぁ。
一度一緒のツアーに行って以来気が合って、いつも一緒に潜りに行っていた仲間達とは、高山へ帰って来てからも付き合いがつづいていますが、そういう仲間を作る事ができた事も、ありがたかったですね。

オレの100本記念のツアーをやってくれたのもその仲間達だったし、一緒にあちこちへ行ったし、ホント楽しかったですねぇ。
今でもハッキリと憶えているのは、そのメンバーで初めて土肥へ行った時の事。
 メンバーの1人が水鉄砲を持ってきたのだけれど、それがウケて、THE101のプールサイドでハシャギまくっていました。
メンバーの1人が水鉄砲を持ってきたのだけれど、それがウケて、THE101のプールサイドでハシャギまくっていました。
この時34歳のオレ(左)と、37歳のパパ(右、グループのリーダー)が、無邪気に水鉄砲で遊んでいるこの写真・・・・「計71歳の戦い」ってタイトルをつけたらバカウケしましたが。
最後に海に潜ったのは、その仲間達と、一番仲の良かったインストラクターのみっちゃんの「1000本記念ツアー」に行った時でしたが、予定していた海が荒れたため、急遽変更して行った伊東の『白根』で、空前絶後とも言えるようなイナダの大群に囲まれて・・・・今でもあの時の感動はハッキリと思い出せますね。
その後は仕事に追われ、海へ行く時間がなかなか取れず、結局ダイヴィングからも離れてしまったのですが、今でも機会があれば、また海へ行きたいなぁ、って思っていますけどね。
(カネもヒマもないんですけど・・・・)
さて、ダイヴィングからも遠ざかり、しばらくは何もしない時期があったのですが、次に見えて来たのが自転車です。
街中での足として、原宿のオッシュマンズで Scott のMTBを買ってきたのですが、コレが実に具合がいいんですね。
赤坂のような坂の多いところでも全然苦にならないし、世田谷くらいまでなら、別にどうって事なく往復してましたからね。
 東京へ引っ越す時、大事にしていた本や雑誌を大量に処分したのですが、これだけは残しておこうと思ってとっておいたターザンのバックナンバーの中に、MTBの特集号があったので、そこに載っていた「都会を快適に走れるルートを探せ」という特集を参考に、夜仕事が終わってから、赤坂から六本木、麻布と廻るコースを走ってましたねぇ。
東京へ引っ越す時、大事にしていた本や雑誌を大量に処分したのですが、これだけは残しておこうと思ってとっておいたターザンのバックナンバーの中に、MTBの特集号があったので、そこに載っていた「都会を快適に走れるルートを探せ」という特集を参考に、夜仕事が終わってから、赤坂から六本木、麻布と廻るコースを走ってましたねぇ。
でも、そうして走っているうちに、何か物足りないものを感じるようになっていたのですよ。
で、ある日、昼の休憩時間に渋谷まで行った帰り、渋谷2丁目の交差点でサイクルコンピューターをリセットして走り出したのですが、赤坂ツインタワーの前に着いた時、きっかり8分を示していたんです。
まぁ、すべての信号が青だった、という事もあったのですが、かなりのアップダウンを繰り返す六本木通りを、これだけの時間で駆け抜けるのは、かなり速いんじゃないかな、って思ったわけです。
その時、結局のところオレはスピードを求めているんだ、って気がついたんですね。
考えてみれば、MTBのフロントギアは、アウターしか使った事がなかったし・・・・
そうなると、行き着くところ、ロードバイクしかないわけですよ。
と言っても、詳しい事は何も分からないので、『サイクルスポーツ』誌を買って来て読んだのですが、その付録に付いていた『ジーロ ディターリア』の特集冊子で、優勝したマルコ パンターニ Marco Pantani が乗っていた、メルカトーネ ウーノ仕様のビアンキが、すごくカッコよく見えたので、取扱店を調べて、輸入元でもあるサガミサイクルセンターへ行ってみたのです。
全くの初心者がいきなり専門店に行くのって、結構勇気がいるものですが、とにかく店に入って中を見回すと、天井から吊り下げて展示されているフレームの中に、そのビアンキがありました。
やっぱりカッコイイ・・・・でもね、全くのビギナーが、プロと全く同じ自転車に乗ってもいいのだろうか、って思ったんですよ。
明らかにオーヴァークオリティーなわけですからね。
で、店の人に、自分のそういう状況や、思っている事を話して、意見を聞いてみたわけです。
そんなオレの突拍子も無い質問に丁寧に応えてくれたその人は、社長の平林さんだったのですが、話を聞いているうちに、心の中では買う事に決まっていましたね。
翌週にもう一度来てサイズやパーツを決める事にして、その日は帰りましたが、それからの1週間はワクワクし通しでしたね。
こっちは全くの素人ですから、基本的な部分は店のお薦めパーツセットで組んでもらい、どうしても拘りたいところだけ、いくつかの選択肢の中から選ぶ、というやり方で、自分の思う通りのバイクになったと思います。
ついでに、メルカトーネ ウーノのジャージとパンツ、それにヴィットーリアのシューズも揃える事にしました。
後になって分かった事なんですが、オレがこのロードバイクを注文した日の夜、同じカラーリングのビアンキでトゥール ド フランスに出場していたパンターニが、マイヨジョーヌ(個人総合成績1位の選手に与えられる黄色のリーダージャージ)のヤン ウルリヒに8分以上の差をつけて超難関山岳ステージで優勝し、ウルリヒからマイヨジョーヌを奪取したのでした。
パンターニは、そのまま最後までマイヨジョーヌを守り通し、イタリア人としては33年ぶりの優勝と、ダブルトゥールを達成しましたが、偶然とはいえ、なんか嬉しかったですね。
偶然といえば、そのロードバイクに初めて乗った日が8月8日・・・・オレがスポーツに目覚めるきっかけになった、ターザンの取材日と同じ日だったんですよ。
なにか運命みたいなものを感じた、と言ったら大袈裟ですかね。
その数日後のお盆休みに、ロードバイクを抱えて高山へ帰ってきたのですが、古川の親戚へ行く用事ができたので、初の遠乗りとして、ロードバイクで行く事にしました。
少し下りになっているせいで、ちょっと踏んでやれば40km/hくらいはすぐに出ますから(逆に帰りは32〜3km/hくらいしか出ませんが)、極めて順調に走っていたんですが、国道から横道へ入って、回りを見回しながら走っていたら、前輪が何かに(おそらく小石だと思いますが)乗り上げたようなショックを感じて、しばらく走ると、前輪の空気が抜けている事が分かったんですよ・・・・初の遠乗りで、目的地直前にパンク、しかも雨が降り出して、なんて出来過ぎですね。
降り出した雨の中で初のパンク修理も済ませ(空気が漏れていて、後で2回ほどやり直しましたが)、親戚へ行って用を済ませた後、久しぶりに古川の町中を見てみようと、ゆっくり走っていたら、駅の近くで、なにか強い視線を感じたのですよ。
で、振り向いてみると、ある家の駐車場から、こっちをじっと見ている人がいて、その横にはドイチェテレコム(トゥール ド フランスでパンターニに負けて2位になったヤン ウルリヒの所属ティーム)のカラーリングのロードバイクがあって・・・・
いや、こんな飛騨の山の中でも、こういうマニアックな人がいるんだなぁ、って驚くとともに嬉しくなりましたね。
東京へ戻ってからは、街乗りはMTB、遠乗りはロードって使い分けていたのですが、そのうちだんだんロードバイクに乗る比率が多くなってきたのは、やはりオレがロード指向の人間だったんでしょうね。
そのうち、マンションの駐輪場からMTBが盗まれ、ロードバイクだけになったのですが、そうなるとどこへ行くにもロードバイクで、行った先でクリートの付いたシューズでペンギン歩きするのも全然苦になりませんでした。
タベルナ デル コッレオーニが閉店し、中目黒にトラットリーア ラ フェニーチェ(実はそれがラ フェニーチェの1号店です)をオープンした後、赤坂6丁目から目黒2丁目へ引っ越したので、目黒から恵比寿、代官山を廻るコースでよく走っていました。
その後、仕事場が目白に変わり、引っ越す事になった時、自転車通勤に適した距離を考えて、世田谷区弦巻3丁目に引っ越したのですが、目白まで片道14km、時間にして35〜40分というのは、距離的にちょうど良かったと思いますね。
雨の日以外は自転車通勤でしたから、その頃は月に700kmくらいは走っていたわけです。
2000年代に入った頃は「エコブーム」のはしりで、自転車通勤が話題にのぼり始めた頃でしたが、そんな事もあってか、いつも参加していた『クリティカルマス』に新聞や雑誌の記者が、取材に来た事がよくあり、新聞や雑誌に写真が載った事がよくありました。
確か2000年の3月だったと思うけど、ある英字新聞の一面のど真ん中に、すごく大きな写真でオレが走っているところが載った事がありましたが、残念な事に、その新聞を持っていないんですよ。
でも、東京を離れる半年ほど前に、読売新聞の取材を受けて、載った写真がコレ。

この写真を取るために、新宿南口の坂を20回くらい登りましたが、東京を離れる前のいい記念になったと思います。(ここに写っているのが、最初に手に入れたメルカトーネ ウーノ仕様のビアンキです)
高山へ帰ってきて、クルマの免許を取ったら、自転車に乗る機会が減ってしまった事は確かですね。
高山は盆地ですから、ある程度走ると絶対に登りがあるわけで、登りが苦手なオレとしては、辛いところがある事も事実なんですが、それでも、乗鞍青年の家まで登って行った事もあるし、黒雷鳥さんと一緒に乗鞍スカイラインを登って行った事もあるし・・・・まぁ、苦手だとは言いながらも、結構やっている事は確かなんですけどね。
でもね、こういう仕事をしていると、なかなかスポーツをする時間って作りにくい事は確かなんですが、特にウチみたいにオレが1人で店をやっている場合、本当に難しいですね。
まぁ、オレは楽器を演奏する事もスポーツの一種だと思ってますから、今はヴァイオリンとヴィオラを弾いてますけどね。
でもね、「演奏家」という人達は、間違いなく「アスリート」だと思いますね。
そういえば、料理好きで知られたピアニストの中村紘子さんが、包丁で手を切ったら危ない、と心配したファンに、包丁で手を切るような運動神経ではピアノは弾けませんのよ、と答えたそうですが、確かにその通りではありますね。
オレも今のところは一応、体形も体重も若い頃からほとんど変わっていないので、バランスはとれているのだと思いますが、定期的に運動をする事は必要でしょうね。
この歳になれば、いつ体形が崩れても不思議じゃないわけですからね。
だから、ビキニの話のところでも書いたけど、常に身体に「緊張感」を与えて、身体を引き締めるように心がけてはいますけどね。
フィットネスブームが始まった80年代の中頃は、男も女も例外なくタイトなウェアに身を包んでいましたねぇ。
根本的にタイトなものを身に着ける事を好むオレの場合、身体を動かす事に興味を持った理由の一つに「タイトなウェア」があった事は否めません。
ところが80年代の終わり頃、マイケル ジョーダンらのNBAプレイヤー達がダブダブの長いパンツでプレイし始めた頃から急速にルーズなウェアに変わっていき、日本にもすぐに伝わって来ましたが、日本人の場合、ダブダブの長いパンツを穿くと、欧米人に比べてただでさえ短い足がさらに短く見える上、すごくだらしなく見えるんですよね。
オレにしてみれば、すごく残念と言うか、イヤな流れだなぁ、って思ってましたねぇ。
考えてみると、ターザンの取材を受けた後にオレがやった4つのスポーツは、見事なまでにタイトなウェアを使うスポーツばかりなんですよね。
別にそれを意識してスポーツを選んだわけではないのだけれど、ダブダブのウェアを使うスポーツだったら、おそらくやっていなかったでしょうね。
どうしてオレがタイトなウェアを好むのか、って考えてみた事があるのですが、それは、その「タイトなフォルム」が、機能的な必然性からムダなものを削ぎ取って作られたものであり、そこから生まれる「緊張感」に惹かれるからなんだと思います。
競泳用の水着の場合、身体一つでコンマ何秒を競うわけですから、極限まで水の抵抗を減らさなければならないわけだし、ロードバイク用のジャージとパンツの場合は、当然、空気の抵抗が問題になりますが、ロードのレースでは、山岳ステージの下りで、曲がりくねった道を100km/hを超えるスピードで駆け下りる事を考えれば、風によるウェアのバタつきが非常に危険で、もしそれによってバランスを崩したら、命にかかわる事が分かるでしょう。
アメフトの場合は人間という、とてつもなく大きな抵抗・・・・自分を潰そうと掴み掛かってくる敵であったり、敵の動きを抑えて味方が作ってくれる狭い隙間をすり抜ける事だったり・・・・を避けなければならないわけですよ。
タイトなフォルムでなければ命に関わる、というと大袈裟な書き方だと思われるかもしれないけれど、それは事実だし、それ故、余計なものを削ぎ落としたタイトなフォルムからは、ギリギリまで突き詰めた、あるいは、命をかけた「緊張感」が滲み出ている・・・・オレは、そういうものに惹かれるんですね。
オレがイタリアの「古典的な料理」に拘るのも、長い年月の間に余計なものを削ぎ落とされ、必要最低限の素材の組み合わせで作られる飾り気のないシンプルな料理である事に惹かれるからなんですが、まったく同じ理由なんだと思いますね。
こんな事を書くと、やっている人に怒られるかもしれないけれど、バスケットボールやサッカーのルーズなユニフォームからは全然緊張感が感じられないし、チャラいと言うか、軟弱に見えてしまうんですよね。
もちろん、ルーズなスタイルである事にもそれなりの「美学」があるんでしょうけど、少なくともスポーツウェアとして使う事に関しては、オレには全く理解不能ですね。
渋谷にバスケットボールストリートができた時のニュースの画像で、BJリーグのプレイヤー達がユニフォームでパレードをやっているのを見て驚いたのだけれど・・・・
 このユルさ、というか緊張感の無さはなんなんでしょう・・・・昔、夏にオッチャン達がステテコにランニングシャツでうろうろしていたのと同じレヴェルじゃありませんか。
このユルさ、というか緊張感の無さはなんなんでしょう・・・・昔、夏にオッチャン達がステテコにランニングシャツでうろうろしていたのと同じレヴェルじゃありませんか。
ダラッとしたシャツや、もうショーツとは呼べないほど長く、間違いなくまとわりつくであろうダブダブなパンツに、どういう必然性があるのか、オレにはまったく理解できません。
こう言っちゃ悪いけど、オレには「だらしない」としか思えないし、「戦う者」としての緊張感がまったく感じられないんですよね。
 下は、バレーボール ワールドカップでの日本ティームの画像なのだけれど、同じアメリカ生まれの室内競技で、同じようにスリーヴレスのユニフォームを使っていながら、受ける印象はまったく違いますね。
下は、バレーボール ワールドカップでの日本ティームの画像なのだけれど、同じアメリカ生まれの室内競技で、同じようにスリーヴレスのユニフォームを使っていながら、受ける印象はまったく違いますね。
適度にタイトで、動きを妨げる要素が全くないスタイルからは、緊張感を感じるし、こうでなければならないと、オレは思います。
いつだったかターザンに載っていた、着こなしと仕草でベテランに見られる裏ワザ集という記事を読んだ事があったけど、野球に関しては、試合前や試合中の態度についてのみ書かれていたのに対し、サッカーでは大部分がウェアの着こなしについて書かれ、さらにバスケットボールでは、ウェアをファッションとして捉えてNBAプレイヤーになりきれ、というような事が書かれていて、この違いは何なのだろうと考えたのですが・・・・ファッションとして捉えてあの程度ならば、オレには「ファッション」は関係ないな、と思いましたけどね。
ただね、NBAのプレイヤー達が、試合後の会見の時にスーツを完璧に着こなして現れるのを見ると、ホントにカッコイイと思うのだけれど、そういう一面を持っているからこそ、ダブダブのユニフォームが成り立つのかもしれません。
日本のプレイヤー達も、真似するのならユルユルのところばかりではなく、きちんとするべきところも見習うべきだと、オレは思うのですけどね。
古い話ではありますが、ジェローム フリーマンが活躍していた1975年頃の松下電器スーパーカンガルーズのユニフォームは、本当にスタイリッシュだった。(残念ながら画像がみつからなかったのだけれど)
中学生の時、バスケットボール部員のクラスメイトが見せてくれた当時のバスパンは、ファスナーがついた前開きになっていて驚きましたが、そうなっていた理由はシルエットをきれいに見せるためだったと後に本で読んで知り、そこまで考えられていたのかと感心したものです。
そういう事を知っているだけに、そして当時のスタイリッシュなバスケットボールプレイヤー達を知っているだけに、ただダブダブなだけの現在のユニフォームって、本当にヘンだと思うのです。
もちろん、異論もあるでしょう。
オレがタイトなウェアを好むのと同様に、ルーズなウェアを好む人もいるわけで、服装文化史の研究家によると、世の中が平和になるとゆったりとした服装になり、世の中がキナ臭くなるとタイトな服装になるのだそうですから、「平和ボケ」とも言われる昨今においては、ルーズなものを好む人の方が多いのだろうし、それ故に、そもそもはのんびりと過ごすためのゆったりとしたウェアを、戦いの場にまで持ち込んだのかもしれません。
でもね、競技会に出場する者が全裸で戦った古代ギリシャやローマの時代から「アスリートは肉体を曝してナンボのもの」だったわけですよ。
現代においても、いわゆる「ご当地キャラ」を見れば、「ゆるキャラ」と呼ばれるものは呼ばれるものはデブでゆったりとしたコスチュームのものが多いけど、「何とか戦隊○○レンジャー」は全身タイツにヘルメットとプロテクターというスタイル(アメフトのノリ?)ですよね。
スーパーマンやスパイダーマンも全身タイツだし・・・・
「戦う者」にはタイトなスタイルが似合う・・・・それが感覚的に自然な事なのだと思います。
かつて、スノーボードのオリンピック代表になり、その後MTBに転向してMTB界を風靡したショーン パーマーは、あのピタピタのサイクルパンツを散々バカにして穿かなかったのだけれど、優勝がかかった世界選手権の時にサイクルパンツを穿いて出場した、というエピソードがありますが、結局のところ、極限まで追い詰めていくと、機能を優先するしかないわけですよ。
逆に言えば、機能より見た目を優先していられる状態というのは、やはりどこか軟弱と言うか、ギリギリまで追求した厳しさを感じられないんですよね。
このスポーツウェアの「機能」という面から見れば、日本のレヴェルは間違いなく世界一だと思います。
それぞれのスポーツ特有の動きを解析して、それに合ったデザインをする、というところまでは、世界中のどこのメイカーでもやっているけれど、ポジションに合わせて細かく合わせていく事までやったのは、日本のメイカーが最初だとと思います。
たとえば、ここ2〜3年の間に、NFLのラインマン達のジャージが、腋の下の空いたタイプに変わってきたけれど、5年前のアメフト世界選手権の時に、日本ティームでは既に使われていたのですよ。
これって、日本のアマチュアのために作られたものを、本場のプロ達が真似したという事なんでしょうけど、日本の技術ってそこまでスゴいわけですよ。
だから、闇雲に「本場」の真似をするのではなく、きちんと体形に合い、なおかつ機能的なウェアを世界に発信していく方がカッコイイと思うんですけどねぇ。
どんなスポーツであっても、常に戦いの場にいるアスリートこそ、タイトなウェアを身に着けて、肉体を誇示しながら戦うべきだと、オレは思いますね。
誰でも、歳を取って代謝量が落ちるとともに、体形は崩れていくわけですよ。
引き締まった身体を持っている若いうちは、どんなスタイルでいようとも問題はないのでしょうが、それ以降は、緊張感を持てるかどうかで、体形の変化は全く違ったものになると思うのです。
だから、著名なアスリートが、引退後に見るも無惨な体形になっているのを見ると、本当に「残念」という気がしますが、やはり、日頃の意識の持ち方に問題があるんじゃないでしょうかねぇ。
街中で、ジャージの上下を着た運動部員らしい中高校生達が、全く緊張感を感じさせずにダラダラと歩いているのを見ると、こいつらの20年後の身体はブヨブヨになっているんじゃないかって、人事ながら心配してますけど、ホント、大丈夫なんでしょうかねぇ。
中には、ジャージのパンツをずり下げて穿いているヤツもいるけれど、スポーツウェアをそういうふうに着るのは、だらしないのを通り越して「醜悪」としか言いようがないですね。(そういう格好をしているヤツらの中に、賢そうな顔や品の良い顔を見た事はありませんがね)
ジャージを着た姿から緊張感を感じさせる事ができなかったら、その人の体形は間違いなく崩れる・・・・と断言してもいい。
ジャージのように、どんな体形の人でも着てしまえるものを着て、緊張感がなかったら、体形が崩れていくのは当然の事です。
でもね、ジャージの上下を着て、きちんとスポーツウェアを着た時の「緊張感」を感じさせる事ができる人がどれだけいるか実際に調べてみたら、おそらく10人に1人もいないんじゃないでしょうかね。
ひとつ言わせてもらうなら、正月の新聞のチラシに載っていた「福袋」が、軒並みジャージの上下セットだったスポーツ用品店の売り方にも問題があると思うんですけどね・・・・まぁ、商売だから、売れればいいんでしょうけど。
実を言うと、オレは高校の体育の授業の時以来、ジャージを着た事がないんですよ。
なぜかと言えば、絶望的なまでに似合わないから。
オレと同じような体形をしている甥の大地も同じ事を言っていますから、おそらくは体形的に似合わないのだと思いますが、ジャージを着て緊張感を感じさせる事ができるタイプでない事は確かですね。
かく言うオレは、自分が「アスリート」だなんて間違っても言えませんが、前にも書いたように、常に緊張感を維持できるよう、いつもタイトなスタイルでいるように心がけているわけです。
でもオレの場合、頭がデカイ上にO脚という、どう見ても見た目がいいとは言えない体形なので、タイトなウェアを身に着けるのには、いささか問題があるんですよ。
で、試行錯誤の結果、考えついたのが、パーカとフットボールパンツの組み合わせなんですが、トップはフードのついたパーカにする事で頭の大きさを目立たないようにし、ボトムは下手にタイツとかレギンズなんか穿くとO脚が目立ってしまうので、膝下でロングソックスと切替えになるフットボールパンツにする事で、それを目立ちにくくしているわけです。
その組み合わせを普段着にする事で得る「緊張感」はすごいものですよ。
あの超タイトなパンツは体形がモロに出てしまうので、あれを穿いてダラダラしていたら、本当にみっともなく見えてしまいますから、スーパーでレジ待ちしている時でも、図書館で本を探している時でも、常に意識して尻を引き締め、背筋を伸ばしている必要があるわけです。(それに慣れてしまったら、普通の格好をしていても、無意識に尻を引き締めている事に気がついて笑ってしまいますけど)
でも、オレは常に緊張感を持っている方がリラックスできるタイプらしく、その方が落着きますから、全然苦にならないどころか、一番ラクなスタイルですけどね。
そういうスタイルをしている春から秋にかけては、体形が締まったままですから、すごく効果がある事は間違いないのですが、この歳になって代謝量が少し落ちた今、寒さでそのスタイルができない冬の間に体形が少し丸みを帯びてくるという事実・・・・それが問題なんですよね。
夏にプールで小さいビキニを穿くために、春から夏の間に、その丸みを帯びた体形を締める努力をする、というのも身体のためにはいい事だと思いますけど。
まぁね、オレのそういうスタイルを、中にはカッコイイと言ってくれる人もいるけれど、多くの人には突拍子もないものに見えるだろうし、笑う人も多いと思いますが・・・・実際、大笑いされた事もあるし・・・・オレは全く気にしません。
そもそも、自分の生き方や趣味、言い換えれば「自分のスタイル」を他人に理解してもらう必要なんて全くないわけで、理解されたいのだったら、流行を追って、他人と同じ事をしていればいいんですから。
もっとも、「流行を追う」というのは、自分がどう生きるかをしっかりと考える事ができない人、あるいは、考える事を放棄してしまった人がする事だと、オレは思ってますけどね。
そういう意味では、無闇に流行を追わず、あくまでも自分のスタイルを押し通す、ヨーロッパの人達の生き方って、いいと思います。
「他人は他人、自分は自分」というスタンスを崩さず、その上でエレガンスというものを大切にする生き方・・・・いいですねぇ。
「エレガンス」という言葉に対して、日本では「優雅さ、上品さ」というスタティックなイメージを持たれる事が普通だと思うけど、ヨーロッパの人達の持つエレガンスの概念は、もっとダイナミックなもので、フットワークの軽さとでも言うか、ある種の好戦的な要素が含まれているようです。
昼の第一礼装である「モーニングコート」が、本来は朝の乗馬の時に着るための服・・・・要するにスポーツウェアであったという意外な事実も、そう考えれば納得できます。
戦の朝、兜に香を焚き込めてから出かけた戦国の武将がいたそうですが、洋の東西を問わず、戦いの場にエレガンスを見出すことができるのは、偶然ではないのかもしれません。
だから、貴族階級の人達や、大企業の会長や社長なんかがレースに参加して、自分でレースカーを運転するのは普通の事だし、イタリアの首相がロードバイクで遠乗りし、首相公邸の門の前で帰ってくるのを待ち構えていたマスコミに取り囲まれて、サイクルジャージ姿でインタヴューを受けるなんて事もありますが、そういうふうに動けるからこそ尊敬されるわけですよ。
(どこかの国のお偉いさんや政治家みたいに、運転手付きのクルマの後ろでふんぞり返っているようでは、間違っても尊敬されないし、第一カッコワルイですよね。)
オレはそういうダイナミックな「エレガンス」に憧れるし、そういうエレガンスを目指しながら歳を重ねていけたらいいと思いますね。
どう頑張ったところで、歳を取ってジイさんになる事は避けられないけれど、同じ歳を取るならみずみずしく歳を取りたいし、「渋い」なんて言葉が似合わない人間だから、最後までピカピカでいたいと思うのだけれど、ジジイになってもタイトなウェアが似合う身体でいられたら幸せだと思います。
そういえば、いつだったか、ウチの大切なお客さんで、祖父の家のお向かいさんでもある吉村広己君と話していた時、たまたま祖父の話が出たのですが、その時に広己君が何気なく「八千久のじいちゃんは、着物を着たところしか見た事がない。」と言ったのを聞いて、ふと気がついた事がありました。
料理人だった祖父は、昔気質の職人らしく、いつも「半纏に股引に紺の足袋」という格好をしていましたが、晩年は難病を患い、第一線を退いて、日がな一日、奥の座敷の籐の椅子に座って外の庭を眺めるようになっても、ずーっと同じ格好をしていました。
と、そんな事を思い出した時、オレの「パーカにフットボールパンツにロングソックス」というスタイルと、祖父の「半纏に股引に紺の足袋」というスタイルの間に、何か共通したものがある事に気がついたのですが、それは無意識のうちに祖父のスタイルをオレ流にアレンジしたものなんじゃないか、って思ったわけですよ。
子供の頃のオレにとって祖父は近寄りがたい人のように思えて、あまり話をする事もないうちに亡くなってしまった事を、今はすごく残念に思っているのですが、その「職人の血」は、木工職人だった親父を経て、間違いなく受け継いでいると思っています。
こうして考えてみると、祖父と同じ料理人の道を選んだオレは、無意識のうちに祖父の生き方を辿っているのかもしれません。
親父も祖父も、死ぬ直前まで「職人意識」を持ち続けていたと思うのですが、オレも最後までそういう意識を持って生きたいと思うし、最後まで自分のスタイルを変える事なく生きれたらいいと思いますね。
まぁね、この先オレは何年生きられるか分かりませんが・・・・男性の平均寿命まで生きるとして30年ほどですが・・・・結婚も諦めたわけじゃないし、子供が欲しいとも思うけど、このまま独りで生きていくのかもしれません。
でもね、どういう人生であろうと、元気に明るく生きていきたいですね。
「こち亀」に出てくる両さんのじいさん・・・・あんなのが理想なんですけどね。
さて、オレのスポーツ体験から、スポーツウェア論、自分のスタイル論と、思った事を思いのままに書いてきましたが、こんな事を書く事ができるのも、25年前にターザンと出会ったおかげであり、こんな楽しい人生を過ごして来れたきっかけを作ってくれた事に、改めて感謝したいと思います。
でも、ここまで書いた以上、体形を崩す事は許されませんね。
ここしばらくターザンとは疎遠になっていたけれど、この辺ででもう一度自分の身体を見直すために、また読んでみたいと思っているところですが、これから50代、60代、さらにその先で元気でうるさいジジイになれるように、今からやっておく事は、まだまだたくさんありそうです。
まぁ、今できる事からやっていきましょうかね。
では、また。
Ciao. Arrivederci!!
久しぶりの更新です・・・・って、前回から、もう7週間も経ったのですね。
なんせ、今年初の更新ですから。
12月の後半、特に23日以降は予約がびっしりと詰まっていたため(こんな事はオープン以来初めてでしたが)、年賀状を書くヒマもなく、年賀状を頂いた方には御無礼をしたままになっていますが、いつか近況報告的なはがきを出そうと思っているところです。
まぁ、忙しかったのは本当にありがたい事ですが、必ずしも「忙しい=儲けが多い」とはならないところが辛いところなんですけどね。
1月はその反動か、全くヒマで、1月としては最低なんじゃないかと思うのですが、そんなヒマな時でも、やる事は少なくならないんですよね。
その上、2月のヴァイオリンの発表会の曲に「難曲」を選んだ(習い始めて2年そこそこでクライスラーを弾こうというのが異常な事なのかもしれませんが)事もあって、そっちにも時間を取らなければならないし・・・・
まぁ、そんなこんなで、相変わらずバタバタしてますけど、充実した日々を過ごしている事には間違いないと思います。
あ、遅くなりましたが、今年もよろしくお願いします。
考えてみたら、このブログを書き始めて、もう5年経ったんですよね。
2007年の1月、劇団無尽舍の新年会に参加した時に、団員の1人から「ひだっち」という名前を聞き、それでこのブログを知って書き始めたわけです。
最初は当然、料理やワインの事を書くつもりでいたのだけれど、書き始めてみたら、料理の事は少しで、音楽やスポーツ、クルマの事ばかり書く事になりましたけどね。
もちろん、このブログに書いた料理の話を読んで、予約を入れて下さる方もおられますから、料理の事を書くのが宣伝になっている事は確かです。
でもね、自分の作る料理に関しては、どんなに詳しく書いたところで、実際に食べてもらわなければ解らないわけで・・・・逆に言えば、料理を食べてもらえば解る事なんですよ。
それ故、料理について書く事には、あまり気が乗らない事も確かなんですよね。
まぁ、根本的に捻くれた人間ですから、余計にそう思うのかもしれませんが。
でもね、こんなマニアックな一般的ではないブログ・・・・言い換えれば、不人気ブログ・・・・ですが、現在11人もの方に読者登録して頂いている事は、本当にありがたい事です。
ウチの料理と同じで、一般受けはしないけど「解る人には解る」という事なんだと思います。
これからも、超マニアックなブログを書いて行こうと思っていますので、引き続きご愛読のほど、よろしくお願いします。
さて今回は、極め付けのマニアック超長編です。
覚悟して読んで下さい。(笑)
この前(といっても去年の事なんだけれど)何気なくカレンダーを見ていて、ふと、あれから25年も経ったんだなぁ、と気がついたのですが、それはオレの人生を大きく変えた出来事でした。
その事をきっかけに生き方が180度変わった、と言ったら大袈裟かもしれないけれど、それくらいオレにとっては大きな出来事だったのです。
今回はその事について、思い出しながら書いてみます。
また、かなり長くなりそう・・・・というか、過去最長のブログになりそうですが。
今でこそ、アメフトだ、自転車だ、水泳だ、って言っているけれど、オレ、子供の頃は「スポーツ大嫌い少年」だったんですよね。
まぁ、球技が全くヘタ・・・・というか、球技というものに対して、ホンの僅かな興味さえ持つ事が無かったんで、経験もないし、上手くなろうなんて気持ちもないから、いきなり体育の時間にやらされても、できるわけがない。
それが、スポーツ嫌いになった原因だったわけです。
当時は、スポーツが得意なヤツは例外なくなく野球をやっていたけれど、オレは今でも、あんな小さい球をあんな細いバットで打つ、という行為が異常としか思えませんからね。
サッカーも体育の時間に結構やらされたけど、全員が右に左に大移動しているだけのつまらなさ、あるいは不毛さを、どうすれば面白く思えるのか、いまだに理解不能です。
やりたいという気持ちが全く無い人間が、(体育の時間という限られた時間であっても)無理やりやらされる事ほど悲惨な事はないわけですよ。
小学3年の時、体育の授業でキックベースボールというのをやったのですが、転がってきたボールを目で追っていたら、先生が飛んで来て、何をしてる、って言われて思いっきり背中を叩かれた事がありました。
今思えば、そのボールを拾ってランナーにぶつけなければならなかったのだが、その頃は、そうしなければいけないという事も知らなかったし、そうしようという気もなかったわけです。
まぁ、そんな事もあって、自然にというより、必然的にスポーツ嫌いになっていったのだと思います。
とは言っても、身体能力は人並み以上にあったみたいで、クラスで北山へ走りに行った時も、1位になった事が何回かあったから、持久力も結構あったのだと思うし、後に肺活量を量ったら5000ccありましたから、他の人よりラクに走っていたのかもしれません。
50m走の記録なんかでは、たいていクラスで5番前後だったから、『選手リレー』なんていうのには出た事はなかったけれど、速い、普通、遅い、と分ければ、速い方には入ったと思いますね。
だから、運動会は結構楽しめたけど、球技大会なんて、苦痛以外の何物でもなかったですね。
まぁね、下手なりにそういう事を分析できていた事が、その後スポーツに興味を持ち始めた時の、進むべき指針になった事は確かだと思いますけどね。
ただ、スポーツはやらないけれど、見るのが好きなスポーツもあったわけで、そういう好みを分析すると、性格的な自分の好き嫌いというものがハッキリと見えてくるんですね。
オレの場合、1回動き出すごとにハッキリと結果の出るもの、を好む傾向にあるんですよ。
で、なおかつ、進行がスピーディーなものじゃないとダメなんです。
だから、サッカーみたいに、常にダラダラと動いているのは生理的に合わないし、野球は、ピッチャーだけは動いているけれど、肝心のバッターが動くまでに時間がかかりすぎるので、面白さが持続しない。
バレーボールなんかが合っていそうな気もしたけど、当時はバレーボール人気が最高の時代だったので、臍曲りなオレは見る気にもならず、むしろスピーディーなバスケットボールの方が面白いと思ってましたね。(とは言っても、あまり見る機会はなかったけど)
ゴルフなんかは、1回打った後、ダラダラと歩いているのがうっとおしい・・・・走っていけばいいのにねぇ。(スピードも得点に入れたら面白いと思うけど。)
一番面白いと思って見ていたのがボウリングでしたけどね。
そんな時、たまたまテレビで見て興味を持ったのがフットボール(アメフト)でした。
当時はフットボールの試合がテレビで中継される事なんて、年に2〜3回もあればいいところでしたが、そういう時はテレビの前で、ルールもよく分からないまま、真剣に見てましたからね。
日米選抜ティームの試合が日本であり、それで来日したボブ・ヘイズ(東京オリンピックの100メートル金メダリスト。その後、ダラス カウボーイズのWRとしてプレイし、72年のスーパーボウル制覇。誰も追いつく事ができないヘイズをカヴァーするために「ゾーン ディフェンス」が発達した。)がフルスタイルで『徹子の部屋』に出演したのもこの頃の事でした。(フルスタイルで登場したヘイズを見て黒柳徹子が「このお衣装はアメリカンフットボールの・・・・」って言ったのが笑えましたけど)
ただ、フットボールの情報なんて全然ないわけで、たまに週刊誌の特集なんかの記事があると、切り抜いて保存し、そういう少ない情報の中でルールを覚えていったわけですが、高校3年のある日、たまたま立ち寄った本町の中田書店で『アメリカンフットボールマガジン』という雑誌を見つけたのです。
すぐに買って帰りましたねぇ。
当時高山で、その雑誌を扱っていたのは中田書店だけで、月に3冊だけしか入らなかったので、発売日には必ず買いに行って、貪るように読んでいましたが、残りの2冊は、いつも売れ残っていたみたいでした。(笑)
まぁね、子供の頃から、他人と同じことはやりたくない、という性格でしたから、そういう状況も楽しんでいたのかもしれませんが。
見るスポーツは、そんな状態でしたが、実際にスポーツをやろうと思う事は全くなかったので、スポーツとは全く無縁の生き方をしていましたが、そんな中で、やるスポーツとして唯一興味を持てたのがボウリングでした。
投げればすぐに結果が出るし、交互に投げるのですから、緊張感を維持したまま速いペースで進める事ができる・・・・オレの求めるものがあったわけです。
高校生の頃は、ちょうどボウリングブームが過ぎ去った時期だったので、投げ放題500円、なんてのもありましたから、結構やりに行ってましたね。
社会人になり、20代の初めの頃、自分の投げ方に合うレーンコンディションのボウリング場を大阪で見つけたので、神戸から毎週通っているうちにボールを作る事になり、休日のたびに15ポンドのボールをかかえて大阪へ通ってました。
ボールを入れたバッグをかかえて一日中歩き回っていたのですから、今考えると、体力があり余っていたんだなぁ、って思いますが、ウデの方はあまり上達せず、ハイゲームが208でしたから、まぁ、そんな程度のものだったんでしょうね。
ボウリング熱が冷めた後、しばらくは何をする事もなかったのですが、20代から老化は始まる、なんて聞いていましたから、なんか運動をしないとダメだ、って意識だけはありました。
「25歳はお肌の曲がり角」なんてCMがありましたが、同様に体力も落ちていくはずですからね。
でも、そうは思いながらも、何をしたらいいのか、皆目見当もつかずにいる状態が続いていました。
そんなある日・・・・忘れもしない1986年8月8日でしたが、当時働いていた『ベルゲン』に、ある雑誌が取材に来たのです。
その雑誌は、創刊されて間もない『ターザン』で、「パスタでダイエット」という特集のための取材でした。

こんな封筒で送られて来たのを、今でも大切に保管しています。

その時作ったのが『イカ墨入りタリアテッレのカルディナーレ風』で、その作り方まで紹介されています。

 25年前のオレです。
25年前のオレです。その2日前に、店の仲間で夜中にクルマをとばして日本海まで行き、竹野浜で海水浴をして来たばかりだったので、日に焼けて顔が赤いんですけどね。
当時オレはセカンドをやってましたが、なぜかシェフとしてオレの写真が出る事になり、初めて全国紙に載ったわけです。(支店のチーフをやっていた先輩から、なんでお前が載るんだ、ってイヤミを言われたりもしましたけどね。)
取材にみえたのが、グーフィー森さんと、カメラマンの村林真叉夫さんでしたが、その時、見本紙として置いていかれた『ターザン』が、その後のオレの生き方を変えたのだと思います。
ちょうどその頃は、いわゆる『フィットネス』のブームが始まった頃で、その牽引役となったのが『ターザン』でした。
当時は、レオタードにレッグウォーマーとリーボックでエアロビクス、というのが流行りましたからね。
身体を動かさなければ、と考えていたオレにとって、ターザンは格好の指針となったわけです。
近所の本屋へ、ターザンのバックナンバーを全部注文し、ターザンを毎号買って読んでいました。
で、載っていた広告を見て、エクスサイズマシーンを注文し、筋トレを始めたのですが、想像していたほど筋肉が付かないんですよね。
いろいろ調べた結果、体質的にムキムキになるタイプではないようだ、という事が分かったのはずっと後の事ですが、その頃は諦めずに、しまいにはソロフレックスまで手に入れて、一生懸命やってましたけどね。
ちなみに、そのソロフレックスは、その後の度重なる引っ越しにも手放す事無く、今もウチにありますが。
で、その後届いたバックナンバー(本屋の手違いで2冊だけ入手できなかったけれど)の第6号の中に、『見栄を張るならバタフライ』という特集があって、見開きで載っていた、当時の世界記録保持者ミヒャエル・グロスが泳いでいる写真を見て「わぁー、カッコエエ!!」って思いましたね。

それはミーハー的なカッコよさではなく、人間の身体の躍動感が、見開き2ページの写真いっぱいに表れていたんですよ。
で、その内容を読むと、バタフライの難しさについて書いてあり、スウィミングスクールでもバタフライのクラスになると急に落伍者が続出する、と書かれていたのですが、もともと捻くれた人間ですから、難しいって言われると、敢えて挑戦したくなるんですよね・・・・で、水泳を習いに行くことにしたのです。
週に一度、休日の夜にスクールに通い、初歩の水慣れから、クロールとバック、ブレストストロークを修了するのに5ヶ月・・・・週一にしては結構早く進んだと思います。
特にブレストストロークは、コーチから「速いですねぇ」というお褒めの言葉をもらって4回で修了しましたが、根本的にオレはブレストストローカーなんだと思います。
今でもプールに行くと、ブレストストロークしかやりませんからね。
で、いよいよバタフライのコースに入ったのですが、これが本当に難しかった。
初回から、手足のタイミングは完璧に合っている、ってコーチに言われたのですが、どう頑張って泳いでも、全然進まないんですよね。
当時は今のようにyoutubeで映像を見る事なんかできなかったわけで、スウィミングスクールにあったヴィデオをダヴィングしてもらって、それをスロー再生して研究したり、連続写真で詳しく解説された『スイミング・ファースター』という本・・・・確か7000円位する高い本だったので、いつも本屋で立ち読みしてましたが・・・・を何回も見て研究したり・・・・
B型的執念で、とことん研究しましたねぇ・・・・でもね、上手くいかないんですよね。
ブレストストロークのクラスは1月もかからずに終ったのに、バタフライでは1年以上も悩み続け・・・・
ターザンに書いてあった通り、本当に難しかったけれど、落伍者になる事だけは避けたかった・・・・と言うより、なぜ上手くいかないのか、という原因究明に一生懸命になっていたのだと思います。
確か小学校の2年の時だったと思うけど、どうしても鉄棒の逆上がりができなくて、毎日夕方、親父と一緒に西小学校へ行って練習し、やっとでできるようになった事がありましたが、なんかあの時の事を思い出したりしていましたねぇ。
スポーツに限った事ではないのだろうけど、テクニックやスキルを身につけようとする時、どうしようもなく高い壁が立ちはだかる事がありますが、意外なきっかけから壁を打ち破れる事があります。
この時も、正にそんな感じでした。
ポートアイランドにあった市営プールは、休館日と店の定休日が同じだったので行った事がなかったのですが、祝日の関係で休みがずれた時、初めて行く事ができました。
で、泳いでいたら、すぐ隣で、おじいちゃんが孫らしい女の子にバタフライを教えていたのですが、その子もオレと同じように、バタフライで苦労しているようでした。
何気なくそっちを見ていた時、そのおじいちゃんが、こんな事を言っていたのです。
「もっと角度をつけて思いっきり頭から突っ込め。」
それはいわゆる『天啓』だったのだと思います。
バタフライの手足の動きは、クロールの動きを左右同時にしているようなものですが、クロールと決定的に違うのは、身体全体をうねらす事・・・・水面を縫うように泳ぐ事なんです。
それは充分過ぎるほど頭では理解していたのだけれど、身体はそのように動いていなかったわけで、うねりを出すために必要な、ある程度以上の角度で突っ込む事ができていなかったんですね。
それが分かればこっちのもの・・・・と言うほど簡単な事ではなく、動きにムダがあるせいもあって、結構疲れる泳ぎ方ではありましたが、なんとかバタフライを泳げるようになったわけです。
でもね、その事によって、スポーツが苦手、という子供の頃からのコンプレックスを、完全にとは言えないまでも、克服する事ができたのだと思います。
とにかく諦めずにやる事・・・・それしかないって感じですね。
ところで、競泳用の水着と言えば、今ではスパッツみたいなのが主流のようですが、オレが水泳を習っていた頃は、例外なくビキニ(いわゆる『競パン』)でした。
大人になってから水泳を習う場合、あの競泳用のビキニに抵抗を感じる人が結構多かったそうなのですが、その頃すでにオレは、下着はかなり小さいビキニを穿いていた(今でもそうですが)ので、全く抵抗がなかったし、そういう意味でも、すぐに馴染む事ができたんだと思います。
ちょうどその頃、西ドイツはミュンヒェンのスポーツ用品店 Schuster から取り寄せたカタログを見ていたら、ドイツのSpeedoのビキニが載っていて、それがスゴくカッコ良かったんですよ。
その頃のビキニって、横の部分の幅が5〜6cmくらいあったのだけれど、ドイツ製のそれは、その半分くらいしかなくて、その分、足が長く見えるんですね。
で、早速取り寄せて、プールではいつもそれを穿いていたのだけれど、結構インパクトがあったみたいで、練習終了後のサウナでいろいろ訊かれましたからね。
その後、80年代の終わりから90年代中頃までの日本の水泳界では、スウィマー達が、速さだけではなくビキニの小ささを競うような風潮がありましたが、オレはそれよりずっと前にやっていたわけです。
その後、抵抗を減らす、という事で、スパッツ型の水着や、全身水着まで出てきましたが・・・・確かに0.1秒を競うコンペティションスウィマーにとっては当然の選択なんでしょうけど・・・・なんか、水泳自体が面白くなくなりましたねぇ。
ソウルオリンピックの背泳のゴールドメダリスト、鈴木大地が、オリンピック前のインタヴューで、どんな水着で泳ぐのですか、と訊かれて、かなりちっちゃいヤツ、って答えていましたが、その言葉には、身体一つで戦う、という潔さがありました。
水着の面積が大きくなるとともに、そういうものが無くなってしまった事を残念に思うのはオレだけでしょうか。
以前は、ビキニじゃないと泳がせてもらえない競泳用のプールが結構ありましたが、今はスパッツやボックスタイプの水着が主流で、ビキニが少数派になっているのは残念な事だと思います。
欧米人に比べて足の短い日本人の場合、スパッツを穿くと余計に足が短く見える傾向にあるので、競技以外の時はビキニの方が見場がいいと思うんですけどねぇ。
 今でもヨーロッパでは、ビキニじゃないと入れないプールが多いのだそうですが、あるネット上の掲示板で見つけたこの画像はフランスのプールに掲示されているものだそうで、見ての通り、ビキニ以外は禁止ですね・・・・おそらくそれは、ヨーロッパにおけるヴァカンスの考え方によるものなのだろうと思います。
今でもヨーロッパでは、ビキニじゃないと入れないプールが多いのだそうですが、あるネット上の掲示板で見つけたこの画像はフランスのプールに掲示されているものだそうで、見ての通り、ビキニ以外は禁止ですね・・・・おそらくそれは、ヨーロッパにおけるヴァカンスの考え方によるものなのだろうと思います。偉い人ほど長くヴァカンスを取る、と言われるヨーロッパでは、日焼けをしていないと尊敬されないという風潮があるようで・・・・イタリアの『経団連』の人達や歴代首相は、みんな見事に日焼けしています・・・・ヴァカンスに行ったら、他に何もしないで少しでも多く身体を陽にさらして遊ぼうとするわけですから、水着は身体を覆う面積が小さい方がいいというい考え方は当然であり、また「必然」なのでしょう。
オレは今でも、プールや海ではビキニしか穿かないし、できるだけ小さいサイズのものを穿く事にして(この歳になっても尻の割れ目が見えるビキニで泳いでいる事は以前にも書きましたが)、ビキニが似合わなくなったら終わりだ、って自分に言い聞かせながら、常に身体に緊張感を持たせているわけですが、まぁ、そういう『緊張感』のおかげで、体形が20代の頃からほとんど変わっていないのだと思うのですけどね。
男たるもの何かあった時には身体一つで飛び出して行く、くらいの気概は常に持っているべきだとオレは思っていますが、ダブダブのパンツを穿いてダラダラと歩いているようなヤツには絶対に無理だろうな。
まぁ、スポーツに目覚めたのは遅かったけれど、基本的な考え方は、完全に体育会系なんでしょうね。
オレの考え方の根本に not or all 的なところがある上、結構楽天的な性格もあってか、かなり極端な事を考え、実行してしまう人間ですから、バタフライを泳げるようになってスポーツ的コンプレックスがなくなった事で、それまでは「絶対に無理」と思っていた事でも、実際にできるんじゃないかと思い始めたんですよ。
で、ちょうどその頃から赤坂へ行く話が決まっていたので、東京へ行けばそれが本当にできるんじゃないかと思って、そのための準備として身体を作っておこう、なんて考えていましたからね。
オレには根本的に「ティームスポーツ」は向いていないと思います。
他人の所為で負けるのはイヤだし、自分の所為で負けたらもっとイヤですからね。
ラグビーの世界では、One for all, all for one. とよく言われるそうで、それが素晴らしい考え方である事は認めますが、面と向かって言われたら、オレは絶対逃げ出すと思いますね。
だから、オレは生涯ティームスポーツをやる事はないだろう、ってずっと思っていたのですが、そんなオレの考え方を根本から揺り動かしてしまうほどの魅力を持っていたのがフットボール(アメフト)なんですよ。
アメリカンフットボールというのは、いろんな意味において「特殊」なスポーツですから、いわゆる「草野球」というようなノリでやるのは絶対に無理で、身体作りから、その複雑なルールを覚える事まで、本気にならなければ無理、というか、安易にやれば危険だ、という事も良く分かっていました。
だから、たいしたスポーツ経験も無く、普通ならプレイヤー達が引退を考える年齢になって始めようという事が、もうムチャクチャな話なんですが、ちょうどその頃に読んだフットボール誌に、企業のフットボールティームの特集があり、オレと同じ年代でスポーツ経験の無いプレイヤーが意外といる事を知って、きっとオレにもできる、って勝手に思い込んだからなんですけどね。
東京へ行ってから、フットボール誌で見つけたプライヴェートティームに連絡を取り、練習に入れてもらったのですが、初めての練習で、入念なストレッチから準備体操を経て、ダッシュやステップ等の運動をした時は、ハードではあったけど、本当に面白かったですね。
自分の意識としては、それほどしんどいとは思わなかったのだけれど、身体の方は悲鳴を上げていたみたいで・・・・3回目くらいまでは、グラウンドの隅へ行って吐いたりした事もありましたからね。
でも、それ以降は問題なくついていけたのが、自分でも意外でした。
もっとも、フットボールをやるには些か細い体形のオレは、他の人達に比べて体重が軽かったから、身軽な分、走る事や敏捷性に関しては有利だったのだとは思いますが、全くのズブの素人が、自分よりずっと若いプレイヤー達についていけた事は、その後、体力的に大きな自信となりましたね・・・・って、案外自己満足だったりするんですが。
でも、後に後輩が、自分もやりたいと言ったので、練習に連れて行ったのですが、スポーツ経験もあり、オレより10歳近く若い後輩なのに、数回練習に行ったところで、身体が持ちません、と言ってギヴアップしてしまった事を考えると、オレの体力も結構捨てたもんじゃないな、って思いましたけどね。
以前に読んでいた『タッチダウン』誌に連載されていた、関学ファイターズ元監督の武田 健さんの話の中で、アメフトを始めたばかりの初心者に対し、まず手に入れるものはヘルメットだけでいいから、練習中はいつもヘルメットを被って慣れる事から始めるように、と書かれていた事を思い出し、すぐに渋谷のQBクラブへ行って、Pro AirⅡというヘルメットを買ってきたのですが、ヘルメットを被って練習するレヴェルまでいくのに、やはりそれなりの時間は必要でした。
そういえば、フットボールを始める一月ほど前に、社内のボウリング大会で優勝して賞金3万円を貰ったのですが、ちょうどその3万円がヘルメット購入資金になりました。
まぁ、そんなふうに毎週日曜日の練習に通っていたのですが、ある程度慣れたところで、ヘルメットとショルダーパッドを着けてブロッキングの練習が始まったら、完全に当たり負けしてしまうんですね。
敏捷性の面では有利だった体重の軽さが、ボディーコンタクトになると弱点になってしまい、同じ力でぶつかっても、体重の軽い方が押し返されてしまうわけです。
体重を増やさなければと思って、ウェイトゲインプロテイン、なんていうのをガバガバ飲んだりしましたが、体質のせいか全然体重が増えないんですよね。
この歳になると、そういう体質のおかげで、体形が変わっていない事をありがたく思いますが、当時はそういう体質を恨めしく思ったものでした。
10回くらい練習に行った頃だったか、いつも面倒を見てくれていた先輩が、少し離れたところからオレを見て「だいぶ様になってきたな、最初はどうなる事かと思ったけど」って言ったのですよ。
全身にプロテクターを着けたあのスタイルが最初から似合う人って、まずいないと思うけど、特にオレのような細い体形だと難しい・・・・だから、様になってきた、って言われた事は本当に嬉しかった。
多くの装備を身に着けるフットボールプレイヤーは、他のどのスポーツのプレイヤーよりも、ユニフォームが似合ってないとみっともないですからね。
もっとも、そのスタイルが様になっていれば上手い、とは言えません・・・・でも、仕事でもスポーツでも、上手い人は間違いなく制服やユニフォームが似合っている、というのは真理だと思いますね。
練習に通い始めて3ヶ月ほど経った時、練習試合をする事になって、江戸川の河川敷にある競技場へ行ったのですが、前夜の雨のせいで芝の状態が悪く、芝が傷むという理由で管理人から使用中止を言い渡されてしまい、仕方がないので、いつも練習している河川敷のグラウンドでやる事になったのです。
で、メンバーのクルマに分乗して近くまで行き、河川敷まで住宅地の中を歩いて行ったのですが、住宅地の道路を、ショルダーパッドを着けてヘルメットを抱えた男達が30人近く、クリートをカツカツと鳴らしながら歩いているのって、端から見れば異様な情景だっただろうと思いますが、その時オレは、絶対にやる事はないと思っていたティームスポーツを今自分がやっている、という事実を改めて不思議に思ったものです。
この日の試合では、勝ちがほぼ決まったフォース クウォーターの終わりの方で、まだナンバーのついていないジャージのまま、WR(ワイドレシーヴァー)として出場させてもらい、数回のプレイに参加しました。
明らかにビギナーだと分かるオレは全くマークされなかったので、誰にも邪魔されずQB(クウォーターバック)の指示通りのコースを走り、振り向くと、オレ以外のWRが完全にマークされていたので、QBがオレに向けてボールを投げようとしていたのですが、来る、と思って身構えた瞬間、QBがサックされて試合終了・・・・たったそれだけのプレイではあったけれど、なんか感動しましたね。
この頃になると、傷ついたり、腫れ上がったりした自分の腕を見て、充実感を感じていたりもしましたが。
さらにその後、横須賀の米軍基地でネイヴィーティームとの試合があり、基地内のフットボールフィールドに立った時の感動といったら・・・・ホント、世界が変わった、って気がしましたね。(その時の事は、ずっと以前のブログに書いたので、そちらを見て下さい。)
その後、夏休みに遊びに行ったスウェーデンで、足に怪我をした事と、店の定休日が変わった事が重なって、練習に行けなくなってしまい、アメフトから離れてしまったのですが、一番面白くなったところで止めなければならなかったせいもあってか、未だに心残りになってますね・・・・この歳になっても、またやりたいな、って思いますから。
元フットボーラーのお客さんと、アメフトの話で盛り上がる事がよくあります。
山ちゃんや、中京テレビ岐阜支局長のMさんと話をしていると、またアメフトやりてぇな、という言葉が出てくるんですが、バリバリの若い現役プレイヤーとは違うので、一部タックルを規制したり、アーリーホイッスルを採用した「シニアルール」でやれば、きっと今でも楽しめるでしょうね。
せっかく姉妹都市がデンヴァーなんだから、指導者に来てもらい、基礎からきっちり教わってティームを作り、アメフトで交流なんてのもいいと思いますね。
さらには、ブロンコスのプレイヤーを何人か呼んで、ビッグアリーナでクリニックとイヴェントでもやれば、日本中からフットボールプレイヤーやコアなフットボールファンが、間違いなく集まります。
日本中、どこの町へ行っても、というか、地方へ行くほど、野球とサッカーくらいしかスポーツの選択肢がないのは寂しいですよね。
だから、敢えて地方の小都市である高山でアメフトをやって、それを発信していったら、きっと面白いと思うし、他にはやっていない事ですから、町おこしとしても効果的だと思いますね。
ここまで書いてきて考えてみたら、アメフトをやっていた時の写真というものがない事に気がついた・・・・まぁ、みんなに付いて行くのに精一杯だった事もあって、写真を撮るヒマもなかったのだと思うのだけれど。
そういえば横須賀の基地へ行った時、ティーム全員で写真を撮った事があったけど、その写真を貰っていないんですよね。
アウェイ用のホワイトのジャージで撮ったのだけれど、その時オレはまだアウェイ用ジャージを持っていなくて、ひとりブルーのジャージで写っているはずなのだけど・・・・
(田中さん、もしその写真があったら、スキャニングして送って下さい。)
さて、フットボールから離れてしばらくした頃、店の後輩から、一緒にスクーバ ダイヴィングをやりませんか、って誘われたんですよ。
しばらく情報収集した上で考えて、やろうって決めた時、その後輩はもう別の事を始めていて、結局オレ一人でダイヴィングショップへ行き、伊豆大島でオープンウォーターの講習を受けました。
 伊豆大島の『パームビーチ』のプールサイドで、一緒に受講した仲間達、そしてインストラクターのみっちゃんと。
伊豆大島の『パームビーチ』のプールサイドで、一緒に受講した仲間達、そしてインストラクターのみっちゃんと。スクーバ ダイヴィングと言えば、いわゆる「レジャー」の代表みたいなイメージがあって、ダイヴィング誌のアンケートの結果を見ても、ダイヴィングの一番の目的は「魚を見る事」という答えが一番多いのですが、オレは「地形派」で、トンネルをくぐったり、洞窟へ入ったり、ドロップオフの上で浮遊したり、というのが好きでしたね。
だからオレは、なだらかな地形が多い東伊豆よりも、険しい西伊豆の海の方が好きです。
土肥の『白根』の、深度70mの海底から立ち上がるドロップオフもすごかったけど、雲見の『牛付岩』へ初めて行った時は、本当に感動しましたねぇ・・・・もう、岩の間を通り抜けながら泳いでいる間中、ワクワクし通しでしたから。
ただ、雲見って、伊豆半島の中で東京から一番遠いところなので、2回しか行けなかったのですけどね。
スクーバダイヴィングに関しても、オレはいつのまにかスポーツとしてのダイヴィングを目指していたのだと思います。
とにかくスキルアップのための講習を受け、ある意味で「危険度」の高い、より深いところ、より流れのあるポイントを求めて、海へ行っていましたからね。
新しいスキルを身につけるために、スペシャリティーコースを受講するのですが、その中でも『サーチ アンド リカヴァリー』、要するに「海の中でものを探し、引き上げる」という技術のコースを受けたいと思っていたのです。
ところが、そのコースを受けたいという人がいないんですよね・・・・かなりマニアックな技術ですから。
正月に大島へ行った時、まわりの人達を説得して何とか人数を揃え、そのコースを受講する事ができたのですが、(他の人はどう思ったかは分からないけど)オレはそれまでに受けた他のどのコースよりも面白いと思いましたね。
やっぱり、目指すものが他の人達とは、ちょっと違っていたんでしょうね。
結局は仕事が忙しくなって諦めたのだけれど、一時はプロを目指した事があって、その時はプールに通って長距離を泳ぐ練習をしたり、ダイヴィング用プールで、二人で泳ぎながら一つのレギュレイターで交互に呼吸したり、水底で装着している機材を全部外し、もう一度着け直したり・・・・そんな事を結構楽しんでやってましたから、完全に体育会系のノリですよね。
時間が無い人間ですから、沖縄や海外の海なんて考える事もなく、ひたすら伊豆の海で潜っていましたが、約3年で130本ほど潜りました。
一応、アマチュアの最高ランクであるMSD(マスター スクーバ ダイヴァー)の認定を受けましたが、ホント、よくあれだけ潜ったものだと、今になっても感心します。
ただ一つ、未だに残念に思っているのが、御蔵島でイルカと一緒に泳ぐ、というツアーに行き損ねた事・・・・仕事の都合とはいえ、あれだけは本当に行きたかったなぁ。
一度一緒のツアーに行って以来気が合って、いつも一緒に潜りに行っていた仲間達とは、高山へ帰って来てからも付き合いがつづいていますが、そういう仲間を作る事ができた事も、ありがたかったですね。

オレの100本記念のツアーをやってくれたのもその仲間達だったし、一緒にあちこちへ行ったし、ホント楽しかったですねぇ。
今でもハッキリと憶えているのは、そのメンバーで初めて土肥へ行った時の事。
 メンバーの1人が水鉄砲を持ってきたのだけれど、それがウケて、THE101のプールサイドでハシャギまくっていました。
メンバーの1人が水鉄砲を持ってきたのだけれど、それがウケて、THE101のプールサイドでハシャギまくっていました。この時34歳のオレ(左)と、37歳のパパ(右、グループのリーダー)が、無邪気に水鉄砲で遊んでいるこの写真・・・・「計71歳の戦い」ってタイトルをつけたらバカウケしましたが。
最後に海に潜ったのは、その仲間達と、一番仲の良かったインストラクターのみっちゃんの「1000本記念ツアー」に行った時でしたが、予定していた海が荒れたため、急遽変更して行った伊東の『白根』で、空前絶後とも言えるようなイナダの大群に囲まれて・・・・今でもあの時の感動はハッキリと思い出せますね。
その後は仕事に追われ、海へ行く時間がなかなか取れず、結局ダイヴィングからも離れてしまったのですが、今でも機会があれば、また海へ行きたいなぁ、って思っていますけどね。
(カネもヒマもないんですけど・・・・)
さて、ダイヴィングからも遠ざかり、しばらくは何もしない時期があったのですが、次に見えて来たのが自転車です。
街中での足として、原宿のオッシュマンズで Scott のMTBを買ってきたのですが、コレが実に具合がいいんですね。
赤坂のような坂の多いところでも全然苦にならないし、世田谷くらいまでなら、別にどうって事なく往復してましたからね。
 東京へ引っ越す時、大事にしていた本や雑誌を大量に処分したのですが、これだけは残しておこうと思ってとっておいたターザンのバックナンバーの中に、MTBの特集号があったので、そこに載っていた「都会を快適に走れるルートを探せ」という特集を参考に、夜仕事が終わってから、赤坂から六本木、麻布と廻るコースを走ってましたねぇ。
東京へ引っ越す時、大事にしていた本や雑誌を大量に処分したのですが、これだけは残しておこうと思ってとっておいたターザンのバックナンバーの中に、MTBの特集号があったので、そこに載っていた「都会を快適に走れるルートを探せ」という特集を参考に、夜仕事が終わってから、赤坂から六本木、麻布と廻るコースを走ってましたねぇ。でも、そうして走っているうちに、何か物足りないものを感じるようになっていたのですよ。
で、ある日、昼の休憩時間に渋谷まで行った帰り、渋谷2丁目の交差点でサイクルコンピューターをリセットして走り出したのですが、赤坂ツインタワーの前に着いた時、きっかり8分を示していたんです。
まぁ、すべての信号が青だった、という事もあったのですが、かなりのアップダウンを繰り返す六本木通りを、これだけの時間で駆け抜けるのは、かなり速いんじゃないかな、って思ったわけです。
その時、結局のところオレはスピードを求めているんだ、って気がついたんですね。
考えてみれば、MTBのフロントギアは、アウターしか使った事がなかったし・・・・
そうなると、行き着くところ、ロードバイクしかないわけですよ。
と言っても、詳しい事は何も分からないので、『サイクルスポーツ』誌を買って来て読んだのですが、その付録に付いていた『ジーロ ディターリア』の特集冊子で、優勝したマルコ パンターニ Marco Pantani が乗っていた、メルカトーネ ウーノ仕様のビアンキが、すごくカッコよく見えたので、取扱店を調べて、輸入元でもあるサガミサイクルセンターへ行ってみたのです。
全くの初心者がいきなり専門店に行くのって、結構勇気がいるものですが、とにかく店に入って中を見回すと、天井から吊り下げて展示されているフレームの中に、そのビアンキがありました。
やっぱりカッコイイ・・・・でもね、全くのビギナーが、プロと全く同じ自転車に乗ってもいいのだろうか、って思ったんですよ。
明らかにオーヴァークオリティーなわけですからね。
で、店の人に、自分のそういう状況や、思っている事を話して、意見を聞いてみたわけです。
そんなオレの突拍子も無い質問に丁寧に応えてくれたその人は、社長の平林さんだったのですが、話を聞いているうちに、心の中では買う事に決まっていましたね。
翌週にもう一度来てサイズやパーツを決める事にして、その日は帰りましたが、それからの1週間はワクワクし通しでしたね。
こっちは全くの素人ですから、基本的な部分は店のお薦めパーツセットで組んでもらい、どうしても拘りたいところだけ、いくつかの選択肢の中から選ぶ、というやり方で、自分の思う通りのバイクになったと思います。
ついでに、メルカトーネ ウーノのジャージとパンツ、それにヴィットーリアのシューズも揃える事にしました。
後になって分かった事なんですが、オレがこのロードバイクを注文した日の夜、同じカラーリングのビアンキでトゥール ド フランスに出場していたパンターニが、マイヨジョーヌ(個人総合成績1位の選手に与えられる黄色のリーダージャージ)のヤン ウルリヒに8分以上の差をつけて超難関山岳ステージで優勝し、ウルリヒからマイヨジョーヌを奪取したのでした。
パンターニは、そのまま最後までマイヨジョーヌを守り通し、イタリア人としては33年ぶりの優勝と、ダブルトゥールを達成しましたが、偶然とはいえ、なんか嬉しかったですね。
偶然といえば、そのロードバイクに初めて乗った日が8月8日・・・・オレがスポーツに目覚めるきっかけになった、ターザンの取材日と同じ日だったんですよ。
なにか運命みたいなものを感じた、と言ったら大袈裟ですかね。
その数日後のお盆休みに、ロードバイクを抱えて高山へ帰ってきたのですが、古川の親戚へ行く用事ができたので、初の遠乗りとして、ロードバイクで行く事にしました。
少し下りになっているせいで、ちょっと踏んでやれば40km/hくらいはすぐに出ますから(逆に帰りは32〜3km/hくらいしか出ませんが)、極めて順調に走っていたんですが、国道から横道へ入って、回りを見回しながら走っていたら、前輪が何かに(おそらく小石だと思いますが)乗り上げたようなショックを感じて、しばらく走ると、前輪の空気が抜けている事が分かったんですよ・・・・初の遠乗りで、目的地直前にパンク、しかも雨が降り出して、なんて出来過ぎですね。
降り出した雨の中で初のパンク修理も済ませ(空気が漏れていて、後で2回ほどやり直しましたが)、親戚へ行って用を済ませた後、久しぶりに古川の町中を見てみようと、ゆっくり走っていたら、駅の近くで、なにか強い視線を感じたのですよ。
で、振り向いてみると、ある家の駐車場から、こっちをじっと見ている人がいて、その横にはドイチェテレコム(トゥール ド フランスでパンターニに負けて2位になったヤン ウルリヒの所属ティーム)のカラーリングのロードバイクがあって・・・・
いや、こんな飛騨の山の中でも、こういうマニアックな人がいるんだなぁ、って驚くとともに嬉しくなりましたね。
東京へ戻ってからは、街乗りはMTB、遠乗りはロードって使い分けていたのですが、そのうちだんだんロードバイクに乗る比率が多くなってきたのは、やはりオレがロード指向の人間だったんでしょうね。
そのうち、マンションの駐輪場からMTBが盗まれ、ロードバイクだけになったのですが、そうなるとどこへ行くにもロードバイクで、行った先でクリートの付いたシューズでペンギン歩きするのも全然苦になりませんでした。
タベルナ デル コッレオーニが閉店し、中目黒にトラットリーア ラ フェニーチェ(実はそれがラ フェニーチェの1号店です)をオープンした後、赤坂6丁目から目黒2丁目へ引っ越したので、目黒から恵比寿、代官山を廻るコースでよく走っていました。
その後、仕事場が目白に変わり、引っ越す事になった時、自転車通勤に適した距離を考えて、世田谷区弦巻3丁目に引っ越したのですが、目白まで片道14km、時間にして35〜40分というのは、距離的にちょうど良かったと思いますね。
雨の日以外は自転車通勤でしたから、その頃は月に700kmくらいは走っていたわけです。
2000年代に入った頃は「エコブーム」のはしりで、自転車通勤が話題にのぼり始めた頃でしたが、そんな事もあってか、いつも参加していた『クリティカルマス』に新聞や雑誌の記者が、取材に来た事がよくあり、新聞や雑誌に写真が載った事がよくありました。
確か2000年の3月だったと思うけど、ある英字新聞の一面のど真ん中に、すごく大きな写真でオレが走っているところが載った事がありましたが、残念な事に、その新聞を持っていないんですよ。
でも、東京を離れる半年ほど前に、読売新聞の取材を受けて、載った写真がコレ。

この写真を取るために、新宿南口の坂を20回くらい登りましたが、東京を離れる前のいい記念になったと思います。(ここに写っているのが、最初に手に入れたメルカトーネ ウーノ仕様のビアンキです)
高山へ帰ってきて、クルマの免許を取ったら、自転車に乗る機会が減ってしまった事は確かですね。
高山は盆地ですから、ある程度走ると絶対に登りがあるわけで、登りが苦手なオレとしては、辛いところがある事も事実なんですが、それでも、乗鞍青年の家まで登って行った事もあるし、黒雷鳥さんと一緒に乗鞍スカイラインを登って行った事もあるし・・・・まぁ、苦手だとは言いながらも、結構やっている事は確かなんですけどね。
でもね、こういう仕事をしていると、なかなかスポーツをする時間って作りにくい事は確かなんですが、特にウチみたいにオレが1人で店をやっている場合、本当に難しいですね。
まぁ、オレは楽器を演奏する事もスポーツの一種だと思ってますから、今はヴァイオリンとヴィオラを弾いてますけどね。
でもね、「演奏家」という人達は、間違いなく「アスリート」だと思いますね。
そういえば、料理好きで知られたピアニストの中村紘子さんが、包丁で手を切ったら危ない、と心配したファンに、包丁で手を切るような運動神経ではピアノは弾けませんのよ、と答えたそうですが、確かにその通りではありますね。
オレも今のところは一応、体形も体重も若い頃からほとんど変わっていないので、バランスはとれているのだと思いますが、定期的に運動をする事は必要でしょうね。
この歳になれば、いつ体形が崩れても不思議じゃないわけですからね。
だから、ビキニの話のところでも書いたけど、常に身体に「緊張感」を与えて、身体を引き締めるように心がけてはいますけどね。
フィットネスブームが始まった80年代の中頃は、男も女も例外なくタイトなウェアに身を包んでいましたねぇ。
根本的にタイトなものを身に着ける事を好むオレの場合、身体を動かす事に興味を持った理由の一つに「タイトなウェア」があった事は否めません。
ところが80年代の終わり頃、マイケル ジョーダンらのNBAプレイヤー達がダブダブの長いパンツでプレイし始めた頃から急速にルーズなウェアに変わっていき、日本にもすぐに伝わって来ましたが、日本人の場合、ダブダブの長いパンツを穿くと、欧米人に比べてただでさえ短い足がさらに短く見える上、すごくだらしなく見えるんですよね。
オレにしてみれば、すごく残念と言うか、イヤな流れだなぁ、って思ってましたねぇ。
考えてみると、ターザンの取材を受けた後にオレがやった4つのスポーツは、見事なまでにタイトなウェアを使うスポーツばかりなんですよね。
別にそれを意識してスポーツを選んだわけではないのだけれど、ダブダブのウェアを使うスポーツだったら、おそらくやっていなかったでしょうね。
どうしてオレがタイトなウェアを好むのか、って考えてみた事があるのですが、それは、その「タイトなフォルム」が、機能的な必然性からムダなものを削ぎ取って作られたものであり、そこから生まれる「緊張感」に惹かれるからなんだと思います。
競泳用の水着の場合、身体一つでコンマ何秒を競うわけですから、極限まで水の抵抗を減らさなければならないわけだし、ロードバイク用のジャージとパンツの場合は、当然、空気の抵抗が問題になりますが、ロードのレースでは、山岳ステージの下りで、曲がりくねった道を100km/hを超えるスピードで駆け下りる事を考えれば、風によるウェアのバタつきが非常に危険で、もしそれによってバランスを崩したら、命にかかわる事が分かるでしょう。
アメフトの場合は人間という、とてつもなく大きな抵抗・・・・自分を潰そうと掴み掛かってくる敵であったり、敵の動きを抑えて味方が作ってくれる狭い隙間をすり抜ける事だったり・・・・を避けなければならないわけですよ。
タイトなフォルムでなければ命に関わる、というと大袈裟な書き方だと思われるかもしれないけれど、それは事実だし、それ故、余計なものを削ぎ落としたタイトなフォルムからは、ギリギリまで突き詰めた、あるいは、命をかけた「緊張感」が滲み出ている・・・・オレは、そういうものに惹かれるんですね。
オレがイタリアの「古典的な料理」に拘るのも、長い年月の間に余計なものを削ぎ落とされ、必要最低限の素材の組み合わせで作られる飾り気のないシンプルな料理である事に惹かれるからなんですが、まったく同じ理由なんだと思いますね。
こんな事を書くと、やっている人に怒られるかもしれないけれど、バスケットボールやサッカーのルーズなユニフォームからは全然緊張感が感じられないし、チャラいと言うか、軟弱に見えてしまうんですよね。
もちろん、ルーズなスタイルである事にもそれなりの「美学」があるんでしょうけど、少なくともスポーツウェアとして使う事に関しては、オレには全く理解不能ですね。
渋谷にバスケットボールストリートができた時のニュースの画像で、BJリーグのプレイヤー達がユニフォームでパレードをやっているのを見て驚いたのだけれど・・・・
 このユルさ、というか緊張感の無さはなんなんでしょう・・・・昔、夏にオッチャン達がステテコにランニングシャツでうろうろしていたのと同じレヴェルじゃありませんか。
このユルさ、というか緊張感の無さはなんなんでしょう・・・・昔、夏にオッチャン達がステテコにランニングシャツでうろうろしていたのと同じレヴェルじゃありませんか。ダラッとしたシャツや、もうショーツとは呼べないほど長く、間違いなくまとわりつくであろうダブダブなパンツに、どういう必然性があるのか、オレにはまったく理解できません。
こう言っちゃ悪いけど、オレには「だらしない」としか思えないし、「戦う者」としての緊張感がまったく感じられないんですよね。
 下は、バレーボール ワールドカップでの日本ティームの画像なのだけれど、同じアメリカ生まれの室内競技で、同じようにスリーヴレスのユニフォームを使っていながら、受ける印象はまったく違いますね。
下は、バレーボール ワールドカップでの日本ティームの画像なのだけれど、同じアメリカ生まれの室内競技で、同じようにスリーヴレスのユニフォームを使っていながら、受ける印象はまったく違いますね。適度にタイトで、動きを妨げる要素が全くないスタイルからは、緊張感を感じるし、こうでなければならないと、オレは思います。
いつだったかターザンに載っていた、着こなしと仕草でベテランに見られる裏ワザ集という記事を読んだ事があったけど、野球に関しては、試合前や試合中の態度についてのみ書かれていたのに対し、サッカーでは大部分がウェアの着こなしについて書かれ、さらにバスケットボールでは、ウェアをファッションとして捉えてNBAプレイヤーになりきれ、というような事が書かれていて、この違いは何なのだろうと考えたのですが・・・・ファッションとして捉えてあの程度ならば、オレには「ファッション」は関係ないな、と思いましたけどね。
ただね、NBAのプレイヤー達が、試合後の会見の時にスーツを完璧に着こなして現れるのを見ると、ホントにカッコイイと思うのだけれど、そういう一面を持っているからこそ、ダブダブのユニフォームが成り立つのかもしれません。
日本のプレイヤー達も、真似するのならユルユルのところばかりではなく、きちんとするべきところも見習うべきだと、オレは思うのですけどね。
古い話ではありますが、ジェローム フリーマンが活躍していた1975年頃の松下電器スーパーカンガルーズのユニフォームは、本当にスタイリッシュだった。(残念ながら画像がみつからなかったのだけれど)
中学生の時、バスケットボール部員のクラスメイトが見せてくれた当時のバスパンは、ファスナーがついた前開きになっていて驚きましたが、そうなっていた理由はシルエットをきれいに見せるためだったと後に本で読んで知り、そこまで考えられていたのかと感心したものです。
そういう事を知っているだけに、そして当時のスタイリッシュなバスケットボールプレイヤー達を知っているだけに、ただダブダブなだけの現在のユニフォームって、本当にヘンだと思うのです。
もちろん、異論もあるでしょう。
オレがタイトなウェアを好むのと同様に、ルーズなウェアを好む人もいるわけで、服装文化史の研究家によると、世の中が平和になるとゆったりとした服装になり、世の中がキナ臭くなるとタイトな服装になるのだそうですから、「平和ボケ」とも言われる昨今においては、ルーズなものを好む人の方が多いのだろうし、それ故に、そもそもはのんびりと過ごすためのゆったりとしたウェアを、戦いの場にまで持ち込んだのかもしれません。
でもね、競技会に出場する者が全裸で戦った古代ギリシャやローマの時代から「アスリートは肉体を曝してナンボのもの」だったわけですよ。
現代においても、いわゆる「ご当地キャラ」を見れば、「ゆるキャラ」と呼ばれるものは呼ばれるものはデブでゆったりとしたコスチュームのものが多いけど、「何とか戦隊○○レンジャー」は全身タイツにヘルメットとプロテクターというスタイル(アメフトのノリ?)ですよね。
スーパーマンやスパイダーマンも全身タイツだし・・・・
「戦う者」にはタイトなスタイルが似合う・・・・それが感覚的に自然な事なのだと思います。
かつて、スノーボードのオリンピック代表になり、その後MTBに転向してMTB界を風靡したショーン パーマーは、あのピタピタのサイクルパンツを散々バカにして穿かなかったのだけれど、優勝がかかった世界選手権の時にサイクルパンツを穿いて出場した、というエピソードがありますが、結局のところ、極限まで追い詰めていくと、機能を優先するしかないわけですよ。
逆に言えば、機能より見た目を優先していられる状態というのは、やはりどこか軟弱と言うか、ギリギリまで追求した厳しさを感じられないんですよね。
このスポーツウェアの「機能」という面から見れば、日本のレヴェルは間違いなく世界一だと思います。
それぞれのスポーツ特有の動きを解析して、それに合ったデザインをする、というところまでは、世界中のどこのメイカーでもやっているけれど、ポジションに合わせて細かく合わせていく事までやったのは、日本のメイカーが最初だとと思います。
たとえば、ここ2〜3年の間に、NFLのラインマン達のジャージが、腋の下の空いたタイプに変わってきたけれど、5年前のアメフト世界選手権の時に、日本ティームでは既に使われていたのですよ。
これって、日本のアマチュアのために作られたものを、本場のプロ達が真似したという事なんでしょうけど、日本の技術ってそこまでスゴいわけですよ。
だから、闇雲に「本場」の真似をするのではなく、きちんと体形に合い、なおかつ機能的なウェアを世界に発信していく方がカッコイイと思うんですけどねぇ。
どんなスポーツであっても、常に戦いの場にいるアスリートこそ、タイトなウェアを身に着けて、肉体を誇示しながら戦うべきだと、オレは思いますね。
誰でも、歳を取って代謝量が落ちるとともに、体形は崩れていくわけですよ。
引き締まった身体を持っている若いうちは、どんなスタイルでいようとも問題はないのでしょうが、それ以降は、緊張感を持てるかどうかで、体形の変化は全く違ったものになると思うのです。
だから、著名なアスリートが、引退後に見るも無惨な体形になっているのを見ると、本当に「残念」という気がしますが、やはり、日頃の意識の持ち方に問題があるんじゃないでしょうかねぇ。
街中で、ジャージの上下を着た運動部員らしい中高校生達が、全く緊張感を感じさせずにダラダラと歩いているのを見ると、こいつらの20年後の身体はブヨブヨになっているんじゃないかって、人事ながら心配してますけど、ホント、大丈夫なんでしょうかねぇ。
中には、ジャージのパンツをずり下げて穿いているヤツもいるけれど、スポーツウェアをそういうふうに着るのは、だらしないのを通り越して「醜悪」としか言いようがないですね。(そういう格好をしているヤツらの中に、賢そうな顔や品の良い顔を見た事はありませんがね)
ジャージを着た姿から緊張感を感じさせる事ができなかったら、その人の体形は間違いなく崩れる・・・・と断言してもいい。
ジャージのように、どんな体形の人でも着てしまえるものを着て、緊張感がなかったら、体形が崩れていくのは当然の事です。
でもね、ジャージの上下を着て、きちんとスポーツウェアを着た時の「緊張感」を感じさせる事ができる人がどれだけいるか実際に調べてみたら、おそらく10人に1人もいないんじゃないでしょうかね。
ひとつ言わせてもらうなら、正月の新聞のチラシに載っていた「福袋」が、軒並みジャージの上下セットだったスポーツ用品店の売り方にも問題があると思うんですけどね・・・・まぁ、商売だから、売れればいいんでしょうけど。
実を言うと、オレは高校の体育の授業の時以来、ジャージを着た事がないんですよ。
なぜかと言えば、絶望的なまでに似合わないから。
オレと同じような体形をしている甥の大地も同じ事を言っていますから、おそらくは体形的に似合わないのだと思いますが、ジャージを着て緊張感を感じさせる事ができるタイプでない事は確かですね。
かく言うオレは、自分が「アスリート」だなんて間違っても言えませんが、前にも書いたように、常に緊張感を維持できるよう、いつもタイトなスタイルでいるように心がけているわけです。
でもオレの場合、頭がデカイ上にO脚という、どう見ても見た目がいいとは言えない体形なので、タイトなウェアを身に着けるのには、いささか問題があるんですよ。
で、試行錯誤の結果、考えついたのが、パーカとフットボールパンツの組み合わせなんですが、トップはフードのついたパーカにする事で頭の大きさを目立たないようにし、ボトムは下手にタイツとかレギンズなんか穿くとO脚が目立ってしまうので、膝下でロングソックスと切替えになるフットボールパンツにする事で、それを目立ちにくくしているわけです。
その組み合わせを普段着にする事で得る「緊張感」はすごいものですよ。
あの超タイトなパンツは体形がモロに出てしまうので、あれを穿いてダラダラしていたら、本当にみっともなく見えてしまいますから、スーパーでレジ待ちしている時でも、図書館で本を探している時でも、常に意識して尻を引き締め、背筋を伸ばしている必要があるわけです。(それに慣れてしまったら、普通の格好をしていても、無意識に尻を引き締めている事に気がついて笑ってしまいますけど)
でも、オレは常に緊張感を持っている方がリラックスできるタイプらしく、その方が落着きますから、全然苦にならないどころか、一番ラクなスタイルですけどね。
そういうスタイルをしている春から秋にかけては、体形が締まったままですから、すごく効果がある事は間違いないのですが、この歳になって代謝量が少し落ちた今、寒さでそのスタイルができない冬の間に体形が少し丸みを帯びてくるという事実・・・・それが問題なんですよね。
夏にプールで小さいビキニを穿くために、春から夏の間に、その丸みを帯びた体形を締める努力をする、というのも身体のためにはいい事だと思いますけど。
まぁね、オレのそういうスタイルを、中にはカッコイイと言ってくれる人もいるけれど、多くの人には突拍子もないものに見えるだろうし、笑う人も多いと思いますが・・・・実際、大笑いされた事もあるし・・・・オレは全く気にしません。
そもそも、自分の生き方や趣味、言い換えれば「自分のスタイル」を他人に理解してもらう必要なんて全くないわけで、理解されたいのだったら、流行を追って、他人と同じ事をしていればいいんですから。
もっとも、「流行を追う」というのは、自分がどう生きるかをしっかりと考える事ができない人、あるいは、考える事を放棄してしまった人がする事だと、オレは思ってますけどね。
そういう意味では、無闇に流行を追わず、あくまでも自分のスタイルを押し通す、ヨーロッパの人達の生き方って、いいと思います。
「他人は他人、自分は自分」というスタンスを崩さず、その上でエレガンスというものを大切にする生き方・・・・いいですねぇ。
「エレガンス」という言葉に対して、日本では「優雅さ、上品さ」というスタティックなイメージを持たれる事が普通だと思うけど、ヨーロッパの人達の持つエレガンスの概念は、もっとダイナミックなもので、フットワークの軽さとでも言うか、ある種の好戦的な要素が含まれているようです。
昼の第一礼装である「モーニングコート」が、本来は朝の乗馬の時に着るための服・・・・要するにスポーツウェアであったという意外な事実も、そう考えれば納得できます。
戦の朝、兜に香を焚き込めてから出かけた戦国の武将がいたそうですが、洋の東西を問わず、戦いの場にエレガンスを見出すことができるのは、偶然ではないのかもしれません。
だから、貴族階級の人達や、大企業の会長や社長なんかがレースに参加して、自分でレースカーを運転するのは普通の事だし、イタリアの首相がロードバイクで遠乗りし、首相公邸の門の前で帰ってくるのを待ち構えていたマスコミに取り囲まれて、サイクルジャージ姿でインタヴューを受けるなんて事もありますが、そういうふうに動けるからこそ尊敬されるわけですよ。
(どこかの国のお偉いさんや政治家みたいに、運転手付きのクルマの後ろでふんぞり返っているようでは、間違っても尊敬されないし、第一カッコワルイですよね。)
オレはそういうダイナミックな「エレガンス」に憧れるし、そういうエレガンスを目指しながら歳を重ねていけたらいいと思いますね。
どう頑張ったところで、歳を取ってジイさんになる事は避けられないけれど、同じ歳を取るならみずみずしく歳を取りたいし、「渋い」なんて言葉が似合わない人間だから、最後までピカピカでいたいと思うのだけれど、ジジイになってもタイトなウェアが似合う身体でいられたら幸せだと思います。
そういえば、いつだったか、ウチの大切なお客さんで、祖父の家のお向かいさんでもある吉村広己君と話していた時、たまたま祖父の話が出たのですが、その時に広己君が何気なく「八千久のじいちゃんは、着物を着たところしか見た事がない。」と言ったのを聞いて、ふと気がついた事がありました。
料理人だった祖父は、昔気質の職人らしく、いつも「半纏に股引に紺の足袋」という格好をしていましたが、晩年は難病を患い、第一線を退いて、日がな一日、奥の座敷の籐の椅子に座って外の庭を眺めるようになっても、ずーっと同じ格好をしていました。
と、そんな事を思い出した時、オレの「パーカにフットボールパンツにロングソックス」というスタイルと、祖父の「半纏に股引に紺の足袋」というスタイルの間に、何か共通したものがある事に気がついたのですが、それは無意識のうちに祖父のスタイルをオレ流にアレンジしたものなんじゃないか、って思ったわけですよ。
子供の頃のオレにとって祖父は近寄りがたい人のように思えて、あまり話をする事もないうちに亡くなってしまった事を、今はすごく残念に思っているのですが、その「職人の血」は、木工職人だった親父を経て、間違いなく受け継いでいると思っています。
こうして考えてみると、祖父と同じ料理人の道を選んだオレは、無意識のうちに祖父の生き方を辿っているのかもしれません。
親父も祖父も、死ぬ直前まで「職人意識」を持ち続けていたと思うのですが、オレも最後までそういう意識を持って生きたいと思うし、最後まで自分のスタイルを変える事なく生きれたらいいと思いますね。
まぁね、この先オレは何年生きられるか分かりませんが・・・・男性の平均寿命まで生きるとして30年ほどですが・・・・結婚も諦めたわけじゃないし、子供が欲しいとも思うけど、このまま独りで生きていくのかもしれません。
でもね、どういう人生であろうと、元気に明るく生きていきたいですね。
「こち亀」に出てくる両さんのじいさん・・・・あんなのが理想なんですけどね。
さて、オレのスポーツ体験から、スポーツウェア論、自分のスタイル論と、思った事を思いのままに書いてきましたが、こんな事を書く事ができるのも、25年前にターザンと出会ったおかげであり、こんな楽しい人生を過ごして来れたきっかけを作ってくれた事に、改めて感謝したいと思います。
でも、ここまで書いた以上、体形を崩す事は許されませんね。
ここしばらくターザンとは疎遠になっていたけれど、この辺ででもう一度自分の身体を見直すために、また読んでみたいと思っているところですが、これから50代、60代、さらにその先で元気でうるさいジジイになれるように、今からやっておく事は、まだまだたくさんありそうです。
まぁ、今できる事からやっていきましょうかね。
では、また。
Ciao. Arrivederci!!
2011年06月23日
ホント or ウソ
Ciao. spockです。
今回は珍しく、短い間隔での更新です。(笑)
たまたま、アップしやすい素材があったので・・・・
梅雨だから当然とはいえ、ハッキリしない天気が続きますねぇ。
まぁ、夏至も過ぎた事だし、梅雨が明ければ、大好きな夏が待っていますけどね。
カレンダーを見ていて、ふと気がつきました。
ちょうど20年前の6月23日、ダイエーの中内 功CEOに呼ばれて、赤坂のタベルナ・デル・コッレオーニをオープンさせるため、店のメンバーと、5人のイタリア人を引き連れて、朝6時過ぎの新幹線で、神戸から東京へ向かいました。
それまで一度も東京へ行った事のなかった人間が、いきなり東京に住んで店をオープンさせるわけですから、どうなる事かと思っていましたが、なんだかんだで、結局東京には13年以上もいましたね。
20年といえば『ふた昔』という事ですが、まぁ、それだけ歳をとった、という事で、『ダイエット』というものには全く無縁で、20代の頃から変わっていなかった体形が、このところ少し太くなったみたい・・・・
プールでみっともない身体を曝すのはイヤだし、競泳用のビキニが似合わなくなったら終わり、って思ってますから、夏までには身体を絞っておかないと・・・・
まぁね、将来、枯れた爺さんにはなりたくないんで、いつまでも生臭いジジイ、を目指してますけどね。
先日、NFL.com の記事を見て、あれからもう4年も経つのか、と時の流れの速さを痛感したのですが、第4回アメリカンフットボール世界選手権オーストリア大会2011 (The Fourth World Championship of American Football, Austria 2011) が、7月の8日から開催されます。(概要はこちら)

オーストリアで開催される事が決まった時、何となく不思議に思ったものですが、ヨーロッパでもドイツ語圏では、結構アメフトの人気がありますね。
ラグビーが普及しなかった事が一番大きな理由のようですが、システマティックなものを好む国民性、という事も理由のひとつのようです。
前回の2007年は日本で開催されましたが、決勝は日本対アメリカと予想して、決勝戦のティケットを手に入れ、台風の中、川崎の等々力陸上競技場まで出かけ、雨に降られながらの観戦。
前半は日本ペースで進んだものの、後半に追い上げられ、延長戦での逆転負け・・・・帰りの電車に乗っている時、急に射して来た陽の光の中で、急に悔しさがこみ上げてきた事を覚えています。
アメフトのワールド・チャンピオンシップについてはこちらに、その決勝戦の事はこちらに書いています。
今回の出場国と組み合わせを見る限りでは、Aグループは問題なくアメリカが勝ち上がるだろうし、Bグループは日本・・・・と言いたいところだけれど、カナダが強そうだし・・・・
今回も日本とアメリカの決勝戦になったら面白いと思いますけどね。
たぶんアメリカは、前回の決勝戦でかなりてこずったので、もっとレヴェルの高いティームで来ると思いますから、アメリカが優勝すると思いますが、まぁ、プロとは違う意味で興味の持てるゲームになるだろうと思います。
さて、では本題に入りましょう。
以前から、アメフトファンの間では有名な動画があります。
NFL Fantasy Files です。
これらの動画については、いろいろと言われているのですが、まぁ、とにかく見てもらいましょう。
まずは『総集編』的な Deluxe Version から。
その他にも、こんなのがあります。
この他にも、かなりのヴァージョンが出ているようなので、Youtube で探してみるのも面白いと思いますが、まぁ、なんと言うか、超人的な『技』の連続で、思わず見入ってしまいますね。
この前ランチに来た、元フットボーラーの山ちゃんに見せたら、食べるのも忘れて見てましたからね。
アメフトは『専門職のスポーツ』ですから、自分のポジションに必要なスキルを、ひたすら磨いていくわけです。
そんな中でもNFLのプロ達は、肉体的にも頭脳的にもトップクラスのプレイヤーが集まっているわけですから、これくらいの事はやって当然、みたいな気もします。(一部の画像には、Do not attempt unless you are an NFL athlete. と注意が出ますが、真似する気にもなりません。)
そう思いながらも、これは本当なのだろうか、という疑いを持ってしまうのも事実。
アメリカ本国でも、インターネット上で、あれは本物か、それともCGか、というような論議がなされています。
たとえば、一番最後のジョー・フラッコの動画では、クレーの割れ方が不自然だとか、クレーはフットボールが当たったくらいでは割れない、とか言われてますが、実際のところどうなんでしょうね。
また、メイソン・クロスビーの、蹴ったボールで鐘をならす動画も、ボールが当たっただけであれだけの音が出るのか、という疑問が出ていましたが、これもどうなんでしょう。
でも、サントニオ・ホームズの、ボールをキャッチしたあと張ったロープの上で静止する動画は、サイドライン近くでボールをキャッチした時、どんな体勢になっても両足をサイドライン内に残さなければならないWR(ワイドレシーヴァー)なら当然の能力のようにも思えます。
ローレンス・マロニー(現デンヴァー・ブロンコス)の、クルマのウィンドウから飛び込んで反対側に抜ける動画では、撮影のためにこんな危険な事をするだろうか、という疑問の声もありましたが、プロのRB(ランニングバック)ならこれくらいできても当然、という気もします。
でも、180cm、100kgの身体が、あの狭い空間を通り抜けるって、すごい事ですよね。
以前Youtubeで見つけた動画で、ちょうどNHKの『目シリーズ』(四つの目、レンズはさぐる、ウルトラアイ、アインシュタインの眼)のような内容のアメリカのTV番組があり(動画を探してみたけれど見つからなかった)、NFLのプレイヤーの能力を、あるゆる角度から撮影して分析していましたが、そこで見たQB(クォーターバック)のボール・コントロール能力はすごいもので、文字通りの『百発百中』でした。
そう考えると、ジェイソン・キャンベルの、続けて投げた2つのボールを空中でぶつけて、2人のWRにキャッチさせる動画も、(一発で成功したとは言えませんが)本物だろうと思いますね。
結果的に、全てが本物とは断言できないにしても、おそらくは本物のパフォーマンスだろう、と言うのがオレの意見です。
ホント or ウソ・・・・皆さんはどう思いますか?
この動画を見た人が、こういうのを見るとアメリカでサッカーの人気がない理由が良く分かる、とインターネット上に書いていましたが、オレも全くその通りだと思います。
現在NFLは、労使問題のこじれからロックアウトが続いているため、今年のシーズンが正常に行われるのか危惧されていますが、なんとか解決して、プロの圧倒的パフォーマンスを見せてもらいたいものです。
 ところで、この動画に出てくるプレイヤーたちが、揃いも揃ってダブダブのショーツ(中にはスカートにみえるくらいのもありますが)を穿いているのを見ると、試合の時に、筋肉の形が分かるほどタイトなパンツを着けているのと比べて、すごいギャップを感じてしまいます。
ところで、この動画に出てくるプレイヤーたちが、揃いも揃ってダブダブのショーツ(中にはスカートにみえるくらいのもありますが)を穿いているのを見ると、試合の時に、筋肉の形が分かるほどタイトなパンツを着けているのと比べて、すごいギャップを感じてしまいます。
まぁ、本番と練習は別、という事なのかもしれませんが。
でもね、バスケットボールやサッカーなんかで、やたらとダブダブしたユニフォームでプレイしているのを見た時にも感じるのだけれど、アスリートは肉体をさらけ出してナンボのものだろう、って思うのはオレだけでしょうか。
では、また。
Ciao. Arrivederci!!
今回は珍しく、短い間隔での更新です。(笑)
たまたま、アップしやすい素材があったので・・・・
梅雨だから当然とはいえ、ハッキリしない天気が続きますねぇ。
まぁ、夏至も過ぎた事だし、梅雨が明ければ、大好きな夏が待っていますけどね。
カレンダーを見ていて、ふと気がつきました。
ちょうど20年前の6月23日、ダイエーの中内 功CEOに呼ばれて、赤坂のタベルナ・デル・コッレオーニをオープンさせるため、店のメンバーと、5人のイタリア人を引き連れて、朝6時過ぎの新幹線で、神戸から東京へ向かいました。
それまで一度も東京へ行った事のなかった人間が、いきなり東京に住んで店をオープンさせるわけですから、どうなる事かと思っていましたが、なんだかんだで、結局東京には13年以上もいましたね。
20年といえば『ふた昔』という事ですが、まぁ、それだけ歳をとった、という事で、『ダイエット』というものには全く無縁で、20代の頃から変わっていなかった体形が、このところ少し太くなったみたい・・・・
プールでみっともない身体を曝すのはイヤだし、競泳用のビキニが似合わなくなったら終わり、って思ってますから、夏までには身体を絞っておかないと・・・・
まぁね、将来、枯れた爺さんにはなりたくないんで、いつまでも生臭いジジイ、を目指してますけどね。
先日、NFL.com の記事を見て、あれからもう4年も経つのか、と時の流れの速さを痛感したのですが、第4回アメリカンフットボール世界選手権オーストリア大会2011 (The Fourth World Championship of American Football, Austria 2011) が、7月の8日から開催されます。(概要はこちら)

オーストリアで開催される事が決まった時、何となく不思議に思ったものですが、ヨーロッパでもドイツ語圏では、結構アメフトの人気がありますね。
ラグビーが普及しなかった事が一番大きな理由のようですが、システマティックなものを好む国民性、という事も理由のひとつのようです。
前回の2007年は日本で開催されましたが、決勝は日本対アメリカと予想して、決勝戦のティケットを手に入れ、台風の中、川崎の等々力陸上競技場まで出かけ、雨に降られながらの観戦。
前半は日本ペースで進んだものの、後半に追い上げられ、延長戦での逆転負け・・・・帰りの電車に乗っている時、急に射して来た陽の光の中で、急に悔しさがこみ上げてきた事を覚えています。
アメフトのワールド・チャンピオンシップについてはこちらに、その決勝戦の事はこちらに書いています。
今回の出場国と組み合わせを見る限りでは、Aグループは問題なくアメリカが勝ち上がるだろうし、Bグループは日本・・・・と言いたいところだけれど、カナダが強そうだし・・・・
今回も日本とアメリカの決勝戦になったら面白いと思いますけどね。
たぶんアメリカは、前回の決勝戦でかなりてこずったので、もっとレヴェルの高いティームで来ると思いますから、アメリカが優勝すると思いますが、まぁ、プロとは違う意味で興味の持てるゲームになるだろうと思います。
さて、では本題に入りましょう。
以前から、アメフトファンの間では有名な動画があります。
NFL Fantasy Files です。
これらの動画については、いろいろと言われているのですが、まぁ、とにかく見てもらいましょう。
まずは『総集編』的な Deluxe Version から。
その他にも、こんなのがあります。
この他にも、かなりのヴァージョンが出ているようなので、Youtube で探してみるのも面白いと思いますが、まぁ、なんと言うか、超人的な『技』の連続で、思わず見入ってしまいますね。
この前ランチに来た、元フットボーラーの山ちゃんに見せたら、食べるのも忘れて見てましたからね。
アメフトは『専門職のスポーツ』ですから、自分のポジションに必要なスキルを、ひたすら磨いていくわけです。
そんな中でもNFLのプロ達は、肉体的にも頭脳的にもトップクラスのプレイヤーが集まっているわけですから、これくらいの事はやって当然、みたいな気もします。(一部の画像には、Do not attempt unless you are an NFL athlete. と注意が出ますが、真似する気にもなりません。)
そう思いながらも、これは本当なのだろうか、という疑いを持ってしまうのも事実。
アメリカ本国でも、インターネット上で、あれは本物か、それともCGか、というような論議がなされています。
たとえば、一番最後のジョー・フラッコの動画では、クレーの割れ方が不自然だとか、クレーはフットボールが当たったくらいでは割れない、とか言われてますが、実際のところどうなんでしょうね。
また、メイソン・クロスビーの、蹴ったボールで鐘をならす動画も、ボールが当たっただけであれだけの音が出るのか、という疑問が出ていましたが、これもどうなんでしょう。
でも、サントニオ・ホームズの、ボールをキャッチしたあと張ったロープの上で静止する動画は、サイドライン近くでボールをキャッチした時、どんな体勢になっても両足をサイドライン内に残さなければならないWR(ワイドレシーヴァー)なら当然の能力のようにも思えます。
ローレンス・マロニー(現デンヴァー・ブロンコス)の、クルマのウィンドウから飛び込んで反対側に抜ける動画では、撮影のためにこんな危険な事をするだろうか、という疑問の声もありましたが、プロのRB(ランニングバック)ならこれくらいできても当然、という気もします。
でも、180cm、100kgの身体が、あの狭い空間を通り抜けるって、すごい事ですよね。
以前Youtubeで見つけた動画で、ちょうどNHKの『目シリーズ』(四つの目、レンズはさぐる、ウルトラアイ、アインシュタインの眼)のような内容のアメリカのTV番組があり(動画を探してみたけれど見つからなかった)、NFLのプレイヤーの能力を、あるゆる角度から撮影して分析していましたが、そこで見たQB(クォーターバック)のボール・コントロール能力はすごいもので、文字通りの『百発百中』でした。
そう考えると、ジェイソン・キャンベルの、続けて投げた2つのボールを空中でぶつけて、2人のWRにキャッチさせる動画も、(一発で成功したとは言えませんが)本物だろうと思いますね。
結果的に、全てが本物とは断言できないにしても、おそらくは本物のパフォーマンスだろう、と言うのがオレの意見です。
ホント or ウソ・・・・皆さんはどう思いますか?
この動画を見た人が、こういうのを見るとアメリカでサッカーの人気がない理由が良く分かる、とインターネット上に書いていましたが、オレも全くその通りだと思います。
現在NFLは、労使問題のこじれからロックアウトが続いているため、今年のシーズンが正常に行われるのか危惧されていますが、なんとか解決して、プロの圧倒的パフォーマンスを見せてもらいたいものです。
 ところで、この動画に出てくるプレイヤーたちが、揃いも揃ってダブダブのショーツ(中にはスカートにみえるくらいのもありますが)を穿いているのを見ると、試合の時に、筋肉の形が分かるほどタイトなパンツを着けているのと比べて、すごいギャップを感じてしまいます。
ところで、この動画に出てくるプレイヤーたちが、揃いも揃ってダブダブのショーツ(中にはスカートにみえるくらいのもありますが)を穿いているのを見ると、試合の時に、筋肉の形が分かるほどタイトなパンツを着けているのと比べて、すごいギャップを感じてしまいます。まぁ、本番と練習は別、という事なのかもしれませんが。
でもね、バスケットボールやサッカーなんかで、やたらとダブダブしたユニフォームでプレイしているのを見た時にも感じるのだけれど、アスリートは肉体をさらけ出してナンボのものだろう、って思うのはオレだけでしょうか。
では、また。
Ciao. Arrivederci!!
2008年08月22日
私的エコ論? Rollerbradingの話!!(その1)
Ciao. spockです。
久しぶりの更新です。
前回アップしたのは7月の初めだったけれど、気がついてみれば、もう8月も終わりかぁ・・・
夏大好き人間としては、夏の終わりが一番寂しいですね。
まぁ、2週間後にはNFLが開幕しますから、秋はそれを楽しみにしているのですけど・・・
先日、TVの取材を受けました。
ウチもやっと、取材を受けれるようになったかぁ・・・・と、しばし感慨に耽る事はさておき、準備から、調理、説明、撮影後のスタッフ9人の食事まで、全部一人でやったので、大忙しでした。
あらかじめ台本は貰っていたのですが、そんなのは無視してアドリブで喋りまくり・・・・
主役の高山厳さんより多く喋ったのではないかと・・・・
まぁ、大部分はカットされるんでしょうけど・・・・
23日の14:00から、岐阜放送の『第11回飛騨高山高根歌謡祭』という番組の中で放送されます。
さて、本題に入りましょう。
この前、32年ぶりに白川郷へ行ってきました。
行きは156号線を通り、帰りは先日開通した道を通ったのですが、大喰らいのウチの化け猫も、信号や渋滞の無い道を走ると燃費はかなり良くなり、ガソリン消費量は街中を這いずり回っている時の約半分になります。
とは言っても、燃費の悪い事には変わりがないわけですが・・・・
このところ、原油価格は暴落しているのに、ガゾリンの値段は高いまま・・・・以前のような値段に戻る事はないのでしょうかね。
とにかくガソリンの消費量を抑える事、要するにクルマに頼り切らないことが必要ですよね。
まぁ、オレはもともと自転車乗りですから、荷物を運ぶのでなければ、自転車だけでも事足りるのですけど・・・・
今から2ヵ月ほど前の事、クルマに頼らず自分の足で移動するなら、自転車の他に『アレ』もあったよなぁ・・・・って考えていた時に、TVを見ていて、あるCMに思わず見入ってしまいました。
それは、キリンのSONiQのCFです。(わりと短い期間だけ放映されて終わりましたが、近々復活するそうです)

ちょうどその時考えていた『アレ』というのが『ローラー・ブレイド』の事だったせいもあって、そのCFに思わず見入ってしまったのですが、それと同時に、いくつもの意味で『なつかしさ』のようなものを感じた・・・・というか、いろいろ思い出させられましたねぇ。
まぁ、そんなふうに感じるのは、オレだけなんでしょうけど・・・・
(注・ウィールが一列に並んだ『インライン・スケート』の中で、ローラー・ブレイド社製のものが『ローラー・ブレイド』と呼ばれるのですが、「インライン・スケートをする事」は メーカーに関係なく "Rollerbrading"『ローラーブレイディング』で通用するようです。)
 あの螺旋状の駐車場(だそうです)の雰囲気は『ブレイド ランナー』を思い出させられますねぇ。
あの螺旋状の駐車場(だそうです)の雰囲気は『ブレイド ランナー』を思い出させられますねぇ。
20年以上も前、LDを発売と同時に手に入れて、毎晩のように観てましたから、何となく、なつかしい気がしたのかもしれません。
そんな場所をインライン・スケートでボディー・チェックしながら駆け下りて行くのを見て、オレが中学生の頃に一世を風靡した『ローラーゲーム』を思い出しました。
あの頃はみんな、毎週TVの前にかじり付いて『東京ボンバーズ』を応援してましたねぇ。
特に、スレンダーな身体でストレートのロングヘアーをなびかせながら果敢に戦っていた、佐々木ヨーコがカッコよかった。
後に『ローラーボール』なんて映画もできましたね。
実を言うとですねぇ・・・・10数年前、オレはローラー・ブレイドに入れ込んでいた事があるんですよ。
とは言っても、ローラー・ブレイドを、スポーティング・ギアとは考えずに使っていたわけなんですが・・・・
ローラー・ブレイドが正式に輸入されたのは92年の春で、最初に輸入されたのは2種類だけだったし、情報誌等での扱いも大きいものではなかったので、あんまり売れなかったんだろうなぁ、とは思っていましたが、オレは興味を持って見ていたのですよ。
東京に限らず大都市はみんなそうだと思うのですが、地下鉄やバスに乗れば、だいたい行きたいところへは行けるのだけれど、駅から目的地までが遠い場合が多いんですよね。
そういう時に使える移動手段はないものか、と考えていたのですが、自転車じゃ電車の中に持ち込むわけにはいかないし・・・・で、簡単に持ち運びのできるローラー・ブレイドなら、移動手段として使えるんじゃないかと考えたわけです。
でも、よく考えてみると、階段の昇り降りや、乗り物に乗る時なんかは脱着が大変なんですよ。
あぁ、これもダメかぁ、って思っていたのですが、翌93年の春、アメリカ本国で発売されている殆どの機種が輸入されることになり、その中に『メトロ・ブレイド』を見つけたのです。
 文字通り、メトロ(地下鉄)にも乗れるローラー・ブレイド、という事からつけた名前なんでしょう、本体からシューズが取り外せる構造になっていて、必要のない時は本体を外して歩けるようになっているんですよ。
文字通り、メトロ(地下鉄)にも乗れるローラー・ブレイド、という事からつけた名前なんでしょう、本体からシューズが取り外せる構造になっていて、必要のない時は本体を外して歩けるようになっているんですよ。
カタログには
車よりも自転車よりも速く とか
新たなライフスタイルを志向した都市型トランスポーテーションギア って書いてありました。
 オレが求めていたのはこれだ、と思って、すぐにその当時ローラー・ブレイドを一番多く扱っていた新宿の『フィールド』へ行って予約しました。
オレが求めていたのはこれだ、と思って、すぐにその当時ローラー・ブレイドを一番多く扱っていた新宿の『フィールド』へ行って予約しました。
値段は結構高かった事を憶えているのですが、当時のカタログで調べてみると、なんと55000円!! こんな高い物を買ってたんだなぁ、と、しばし考え込みました。
メトロ・ブレイドが発売されたのは、93年と94年だけでしたから、ある意味『レア・アイテム』ではありますが、96年頃、1万円位で投げ売りされていたようですから、よっぽど売れなかったんでしょう。
ちょうどこの頃、コカ・コーラのCFで、近未来の都市を謎のローラー・ブレイド集団が駆け巡る、というのがありましたが、ローラー・ブレイドの発売に合わせて作られたCFだったのかもしれませんね。
発売日の休憩時間に受け取りにいき、予想外に大きな箱を抱えて戻って来たのですが、実はそれ以上に大きな問題を抱えていたのですよ。
オレはスケートというものを、生まれてから一度もやった事がない・・・・
ズーッと昔、TVでプロのスケーターが、スケート靴を履いて歩く事ができればスグに滑れるようになる、って言ってましたから、何とかなるだろうと思ってはいたものの、本当にできるのだろうか・・・・
その日、部屋に帰って早速装着し、とりあえず立って歩いてみると、ちゃんと歩けたのですよ・・・・いつだったか伯母が「雪の積もるところで育った人は、自然にバランス感覚が身に付いているんだから、スケートができない筈がない」って言ってましたが、納得しましたね。
次の日の休憩時間に、スケートの得意な後輩に見てもらってアドヴァイスを受け、タベルナ・デル・コッレオーニがあった赤坂ツインタワーの裏口横の空地(ローラー・ブレイドをやるには打ってつけのスゴくなめらかなコンクリートの空地でした。でも何のための空地だったんでしょうね)で練習していたら、3日目位には「昔からスケートやってました」みたいな顔をして滑れるようになったのですよ。
で、実際に移動手段として使えるか、という事になると・・・・やはり問題がありますね。
アメリカのように、広い道が延々と続くところならいいのでしょうけど・・・・
日本の場合、車道を走るのは無理なので、歩道を走るしかないのですが、狭くて段差ばかりの上、当然の事ながら歩行者が優先ですから、駆け抜けるというわけにはいきません。
慣れていないうちは咄嗟のブレーキングが難しい、という事もあります。
まぁね、道路交通法から見れば、かなりグレーな部分に入る事も確かなので、控えめな存在でいる事も必要なんですね。
それから、オレがその当時住んでいた赤坂もそうでしたが、東京には結構坂が多いので、登り坂は体力が続く限り登ればいいのですが、急な下り坂では制御できない事があり、ハッキリ言って怖い!!
その当時オレの部屋は、結構急な『南部坂』のちょうど真ん中にありましたから、前の道に出ると、すぐ上に向かって登り、遠回りしながら、ゆるやかな坂を下るという方法を選択するしかなかったですね。
あと、本当に怖かったのは、ある朝、ローラー・ブレイドで仕事場へ向かっている途中に、急に雨が降って来た時の事です。
ザラっぽい舗装道路ならいいのですが、表面が滑らかな場所だと、雨で濡れ始めた途端、ローラー・ブレイドのウィールは、グリップする事を放棄してしまう・・・・要するに、止まろうとしても動こうとしても、スリップするんですよ。
仕方なく、転ばないようにバランスをとりながら、縁石に擦り付けるようにして止まりましたが・・・・
ローラー・ブレイドを移動手段として使うのには、難しい点も結構あるけれど、うまく条件が合えば意外と使える、というのが、最終的な結論でした。
まぁ、なんだかんだ言いながら、それでも結構、移動手段として使いましたから、充分楽しませてもらった事は確かなんですが・・・・
丁度その頃は、スクーバ・ダイヴィングにもハマり込んでいたのですが、他のみんなは金曜日の晩に出かけるのに、オレは仕事があったので、ダイヴィング機材だけ預けて運んでもらい、土曜日の朝イチの電車で、みんなを追いかけた事がありました。
で、その時、赤坂から新橋の駅までローラー・ブレイドで走ったのですよ。
早朝で、歩行者がいなかったとはいえ、歩道の段差や、いきなり横道から顔を出すクルマに阻まれて、あまりスピードは出せなかったのですが、当然、歩くよりかなり早く駅に着きました。
でも、電車に乗ってから点検してみると、ウィールは傷だらけだし、ベアリングに(微かではありますが)ガタが出ているような・・・・やはり、段差の多い歩道を走るのは、かなりハードな事なんでしょうね。
その日、海に潜った後、宿泊した富戸の『シーフロント』のそばにある、いつもガラガラに空いている広大な駐車場へ行って、みんなで交代しながら滑ったのですが、みんな大喜びでしたね。
この日は海が荒れて、みんなが期待していた伊豆海洋公園の『2番の根』に潜れなかった所為もあってか、ログブックには、海の事よりローラー・ブレイドの事が多く書かれていました。
その後も、ダイヴィングに限らず、人の集まる時にローラー・ブレイドで行くと、盛り上がりましたねぇ・・・・やはり、一度やってみたいと思っている人が多いんでしょうね。
そんなに入れ込んでいたローラーブレイドなんですが、いつの間にか疎遠になってしまった理由は、移動手段として期待していた程使えなかった事の他に、もう1つあるのです。
一言で言えば、スタイルの問題、という事でしょうか。
当時のスケーター達は、例外無くダブダブのウェアを着て滑っていました。
下にプロテクターを着ける必要があったから、という理由もあったのでしょうけど、片方に脚が3本位入りそうなパンツに、2サイズくらい大きめのTシャツ・・・・そんな格好が普通だったのですが、オレはダブダブのウェアというのが生理的にダメなんですよ。
端から見れは、実にたわいない理由なんでしょうけど、そんなわけでローラーブレイドから遠ざかってしまったわけです。
(同じ理由で、以前はよく見ていたバスケットボールも、全然見なくなりました)
ところが、最近見たいくつかのVTRの中で、ストリート/パーク系のアグレッシヴ・スケーター達が、タイトなウェアを身に着けて滑っているのを見て、最近の流れが、ルーズ系からタイト系に変わって来た事を知ったのですよ。(いつかそうなるだろう、という確信は持っていましたが)
タイトなウェアを通して見る、彼らの身体の躍動感と、スタイリッシュなスケーティングに、思わず感嘆の声をあげてしまいましたね。
タイトなウェアでアグレッシヴ・スケーティングをするためには、プロテクターを着ける必要が無いだけのスケーティング・テクニックと、ダメージの小さい転び方のテクニックを持っている事が最低条件ではありますが、そのあまりのカッコよさに、オレもアグレッシヴ・スケーティングの練習を始めました。
とりあえず、バックスケーティングとジャンプから・・・・
HOW TO AGGRESSIVE INLINE SKATE というDVDも手に入れて見てますけど・・・・
VTR等で、高度なテクニックを持ったスケーター達が、あらゆる場所を自由自在に走り回っているのを見るにつけ、それなりのテクニックを身に付ければ、街中の移動手段として、インライン・スケートってスゴくいいんじゃないかって思うようになったのですよ。
というか、今の時代こそ、こういう考え方があってもいいのではないかと思うのです。
もちろん「周りに迷惑をかけない事」や「すべて自己責任で行動する事」という最低限のルールを守る事が前提なんですが・・・・
自分自身のバランス感覚の上で成り立つローラーブレイディングでは、常に周りの状況を見ながら、少し先を予測していなければ、まともに滑る事はできません。
そう考えると、少なくとも、周りの状況を全く考えないで走っている自転車(一時停止する事なく交差点に突っ込んで行ったり、右側を逆走したり、携帯電話を見ながら走ったり)よりは安全だと、オレは断言します。
荷物がある時は別ですが、例えばウチから雷鳥屋さんへ行く位の距離だったら、駐車・駐輪スペースも要らないし、ちょうどいいのではないでしょうかね。
駐車・駐輪スペースが必要ないというメリットの他、身体のためにも、エコの面からも、いいと思うのですけどね。
まぁ、どこまでできるかは、やってみないと分かりませんが・・・・
さて、まだまだ長くなりそうなので、続きは(その2)で・・・・
次回は、インライン・スケートをハード面から書いてみます。
では、また。
Ciao. Arrivederci!!
久しぶりの更新です。
前回アップしたのは7月の初めだったけれど、気がついてみれば、もう8月も終わりかぁ・・・
夏大好き人間としては、夏の終わりが一番寂しいですね。
まぁ、2週間後にはNFLが開幕しますから、秋はそれを楽しみにしているのですけど・・・
先日、TVの取材を受けました。
ウチもやっと、取材を受けれるようになったかぁ・・・・と、しばし感慨に耽る事はさておき、準備から、調理、説明、撮影後のスタッフ9人の食事まで、全部一人でやったので、大忙しでした。
あらかじめ台本は貰っていたのですが、そんなのは無視してアドリブで喋りまくり・・・・
主役の高山厳さんより多く喋ったのではないかと・・・・
まぁ、大部分はカットされるんでしょうけど・・・・
23日の14:00から、岐阜放送の『第11回飛騨高山高根歌謡祭』という番組の中で放送されます。
さて、本題に入りましょう。
この前、32年ぶりに白川郷へ行ってきました。
行きは156号線を通り、帰りは先日開通した道を通ったのですが、大喰らいのウチの化け猫も、信号や渋滞の無い道を走ると燃費はかなり良くなり、ガソリン消費量は街中を這いずり回っている時の約半分になります。
とは言っても、燃費の悪い事には変わりがないわけですが・・・・
このところ、原油価格は暴落しているのに、ガゾリンの値段は高いまま・・・・以前のような値段に戻る事はないのでしょうかね。
とにかくガソリンの消費量を抑える事、要するにクルマに頼り切らないことが必要ですよね。
まぁ、オレはもともと自転車乗りですから、荷物を運ぶのでなければ、自転車だけでも事足りるのですけど・・・・
今から2ヵ月ほど前の事、クルマに頼らず自分の足で移動するなら、自転車の他に『アレ』もあったよなぁ・・・・って考えていた時に、TVを見ていて、あるCMに思わず見入ってしまいました。
それは、キリンのSONiQのCFです。(わりと短い期間だけ放映されて終わりましたが、近々復活するそうです)

ちょうどその時考えていた『アレ』というのが『ローラー・ブレイド』の事だったせいもあって、そのCFに思わず見入ってしまったのですが、それと同時に、いくつもの意味で『なつかしさ』のようなものを感じた・・・・というか、いろいろ思い出させられましたねぇ。
まぁ、そんなふうに感じるのは、オレだけなんでしょうけど・・・・
(注・ウィールが一列に並んだ『インライン・スケート』の中で、ローラー・ブレイド社製のものが『ローラー・ブレイド』と呼ばれるのですが、「インライン・スケートをする事」は メーカーに関係なく "Rollerbrading"『ローラーブレイディング』で通用するようです。)
 あの螺旋状の駐車場(だそうです)の雰囲気は『ブレイド ランナー』を思い出させられますねぇ。
あの螺旋状の駐車場(だそうです)の雰囲気は『ブレイド ランナー』を思い出させられますねぇ。20年以上も前、LDを発売と同時に手に入れて、毎晩のように観てましたから、何となく、なつかしい気がしたのかもしれません。
そんな場所をインライン・スケートでボディー・チェックしながら駆け下りて行くのを見て、オレが中学生の頃に一世を風靡した『ローラーゲーム』を思い出しました。
あの頃はみんな、毎週TVの前にかじり付いて『東京ボンバーズ』を応援してましたねぇ。
特に、スレンダーな身体でストレートのロングヘアーをなびかせながら果敢に戦っていた、佐々木ヨーコがカッコよかった。
後に『ローラーボール』なんて映画もできましたね。
実を言うとですねぇ・・・・10数年前、オレはローラー・ブレイドに入れ込んでいた事があるんですよ。
とは言っても、ローラー・ブレイドを、スポーティング・ギアとは考えずに使っていたわけなんですが・・・・
ローラー・ブレイドが正式に輸入されたのは92年の春で、最初に輸入されたのは2種類だけだったし、情報誌等での扱いも大きいものではなかったので、あんまり売れなかったんだろうなぁ、とは思っていましたが、オレは興味を持って見ていたのですよ。
東京に限らず大都市はみんなそうだと思うのですが、地下鉄やバスに乗れば、だいたい行きたいところへは行けるのだけれど、駅から目的地までが遠い場合が多いんですよね。
そういう時に使える移動手段はないものか、と考えていたのですが、自転車じゃ電車の中に持ち込むわけにはいかないし・・・・で、簡単に持ち運びのできるローラー・ブレイドなら、移動手段として使えるんじゃないかと考えたわけです。
でも、よく考えてみると、階段の昇り降りや、乗り物に乗る時なんかは脱着が大変なんですよ。
あぁ、これもダメかぁ、って思っていたのですが、翌93年の春、アメリカ本国で発売されている殆どの機種が輸入されることになり、その中に『メトロ・ブレイド』を見つけたのです。
カタログには
車よりも自転車よりも速く とか
新たなライフスタイルを志向した都市型トランスポーテーションギア って書いてありました。
値段は結構高かった事を憶えているのですが、当時のカタログで調べてみると、なんと55000円!! こんな高い物を買ってたんだなぁ、と、しばし考え込みました。
メトロ・ブレイドが発売されたのは、93年と94年だけでしたから、ある意味『レア・アイテム』ではありますが、96年頃、1万円位で投げ売りされていたようですから、よっぽど売れなかったんでしょう。
ちょうどこの頃、コカ・コーラのCFで、近未来の都市を謎のローラー・ブレイド集団が駆け巡る、というのがありましたが、ローラー・ブレイドの発売に合わせて作られたCFだったのかもしれませんね。
発売日の休憩時間に受け取りにいき、予想外に大きな箱を抱えて戻って来たのですが、実はそれ以上に大きな問題を抱えていたのですよ。
オレはスケートというものを、生まれてから一度もやった事がない・・・・
ズーッと昔、TVでプロのスケーターが、スケート靴を履いて歩く事ができればスグに滑れるようになる、って言ってましたから、何とかなるだろうと思ってはいたものの、本当にできるのだろうか・・・・
その日、部屋に帰って早速装着し、とりあえず立って歩いてみると、ちゃんと歩けたのですよ・・・・いつだったか伯母が「雪の積もるところで育った人は、自然にバランス感覚が身に付いているんだから、スケートができない筈がない」って言ってましたが、納得しましたね。
次の日の休憩時間に、スケートの得意な後輩に見てもらってアドヴァイスを受け、タベルナ・デル・コッレオーニがあった赤坂ツインタワーの裏口横の空地(ローラー・ブレイドをやるには打ってつけのスゴくなめらかなコンクリートの空地でした。でも何のための空地だったんでしょうね)で練習していたら、3日目位には「昔からスケートやってました」みたいな顔をして滑れるようになったのですよ。
で、実際に移動手段として使えるか、という事になると・・・・やはり問題がありますね。
アメリカのように、広い道が延々と続くところならいいのでしょうけど・・・・
日本の場合、車道を走るのは無理なので、歩道を走るしかないのですが、狭くて段差ばかりの上、当然の事ながら歩行者が優先ですから、駆け抜けるというわけにはいきません。
慣れていないうちは咄嗟のブレーキングが難しい、という事もあります。
まぁね、道路交通法から見れば、かなりグレーな部分に入る事も確かなので、控えめな存在でいる事も必要なんですね。
それから、オレがその当時住んでいた赤坂もそうでしたが、東京には結構坂が多いので、登り坂は体力が続く限り登ればいいのですが、急な下り坂では制御できない事があり、ハッキリ言って怖い!!
その当時オレの部屋は、結構急な『南部坂』のちょうど真ん中にありましたから、前の道に出ると、すぐ上に向かって登り、遠回りしながら、ゆるやかな坂を下るという方法を選択するしかなかったですね。
あと、本当に怖かったのは、ある朝、ローラー・ブレイドで仕事場へ向かっている途中に、急に雨が降って来た時の事です。
ザラっぽい舗装道路ならいいのですが、表面が滑らかな場所だと、雨で濡れ始めた途端、ローラー・ブレイドのウィールは、グリップする事を放棄してしまう・・・・要するに、止まろうとしても動こうとしても、スリップするんですよ。
仕方なく、転ばないようにバランスをとりながら、縁石に擦り付けるようにして止まりましたが・・・・
ローラー・ブレイドを移動手段として使うのには、難しい点も結構あるけれど、うまく条件が合えば意外と使える、というのが、最終的な結論でした。
まぁ、なんだかんだ言いながら、それでも結構、移動手段として使いましたから、充分楽しませてもらった事は確かなんですが・・・・
丁度その頃は、スクーバ・ダイヴィングにもハマり込んでいたのですが、他のみんなは金曜日の晩に出かけるのに、オレは仕事があったので、ダイヴィング機材だけ預けて運んでもらい、土曜日の朝イチの電車で、みんなを追いかけた事がありました。
で、その時、赤坂から新橋の駅までローラー・ブレイドで走ったのですよ。
早朝で、歩行者がいなかったとはいえ、歩道の段差や、いきなり横道から顔を出すクルマに阻まれて、あまりスピードは出せなかったのですが、当然、歩くよりかなり早く駅に着きました。
でも、電車に乗ってから点検してみると、ウィールは傷だらけだし、ベアリングに(微かではありますが)ガタが出ているような・・・・やはり、段差の多い歩道を走るのは、かなりハードな事なんでしょうね。
その日、海に潜った後、宿泊した富戸の『シーフロント』のそばにある、いつもガラガラに空いている広大な駐車場へ行って、みんなで交代しながら滑ったのですが、みんな大喜びでしたね。
この日は海が荒れて、みんなが期待していた伊豆海洋公園の『2番の根』に潜れなかった所為もあってか、ログブックには、海の事よりローラー・ブレイドの事が多く書かれていました。
その後も、ダイヴィングに限らず、人の集まる時にローラー・ブレイドで行くと、盛り上がりましたねぇ・・・・やはり、一度やってみたいと思っている人が多いんでしょうね。
そんなに入れ込んでいたローラーブレイドなんですが、いつの間にか疎遠になってしまった理由は、移動手段として期待していた程使えなかった事の他に、もう1つあるのです。
一言で言えば、スタイルの問題、という事でしょうか。
当時のスケーター達は、例外無くダブダブのウェアを着て滑っていました。
下にプロテクターを着ける必要があったから、という理由もあったのでしょうけど、片方に脚が3本位入りそうなパンツに、2サイズくらい大きめのTシャツ・・・・そんな格好が普通だったのですが、オレはダブダブのウェアというのが生理的にダメなんですよ。
端から見れは、実にたわいない理由なんでしょうけど、そんなわけでローラーブレイドから遠ざかってしまったわけです。
(同じ理由で、以前はよく見ていたバスケットボールも、全然見なくなりました)
ところが、最近見たいくつかのVTRの中で、ストリート/パーク系のアグレッシヴ・スケーター達が、タイトなウェアを身に着けて滑っているのを見て、最近の流れが、ルーズ系からタイト系に変わって来た事を知ったのですよ。(いつかそうなるだろう、という確信は持っていましたが)
タイトなウェアを通して見る、彼らの身体の躍動感と、スタイリッシュなスケーティングに、思わず感嘆の声をあげてしまいましたね。
タイトなウェアでアグレッシヴ・スケーティングをするためには、プロテクターを着ける必要が無いだけのスケーティング・テクニックと、ダメージの小さい転び方のテクニックを持っている事が最低条件ではありますが、そのあまりのカッコよさに、オレもアグレッシヴ・スケーティングの練習を始めました。
とりあえず、バックスケーティングとジャンプから・・・・
HOW TO AGGRESSIVE INLINE SKATE というDVDも手に入れて見てますけど・・・・
VTR等で、高度なテクニックを持ったスケーター達が、あらゆる場所を自由自在に走り回っているのを見るにつけ、それなりのテクニックを身に付ければ、街中の移動手段として、インライン・スケートってスゴくいいんじゃないかって思うようになったのですよ。
というか、今の時代こそ、こういう考え方があってもいいのではないかと思うのです。
もちろん「周りに迷惑をかけない事」や「すべて自己責任で行動する事」という最低限のルールを守る事が前提なんですが・・・・
自分自身のバランス感覚の上で成り立つローラーブレイディングでは、常に周りの状況を見ながら、少し先を予測していなければ、まともに滑る事はできません。
そう考えると、少なくとも、周りの状況を全く考えないで走っている自転車(一時停止する事なく交差点に突っ込んで行ったり、右側を逆走したり、携帯電話を見ながら走ったり)よりは安全だと、オレは断言します。
荷物がある時は別ですが、例えばウチから雷鳥屋さんへ行く位の距離だったら、駐車・駐輪スペースも要らないし、ちょうどいいのではないでしょうかね。
駐車・駐輪スペースが必要ないというメリットの他、身体のためにも、エコの面からも、いいと思うのですけどね。
まぁ、どこまでできるかは、やってみないと分かりませんが・・・・
さて、まだまだ長くなりそうなので、続きは(その2)で・・・・
次回は、インライン・スケートをハード面から書いてみます。
では、また。
Ciao. Arrivederci!!
2007年07月17日
アメフト・ワールドカップ 決勝戦
Ciao. spockです。
台風の中、クルマとバスを乗り継いで、川崎の等々力陸上競技場まで行って来ました。
最悪の場合、試合の延期もあるかもしれない状態だったので、出来る限り、そうなった時のための準備はしてから出かけたのですが、東京へ着いてすぐに千葉の友人のところへ電話し、大会の公式ウェブサイトを見てもらったところ、予定通り決行という事だったので、昼飯を食べる間もなく、台風の影響でダイヤがガタガタになった電車を乗り継ぎ、何とか武蔵小杉の駅までたどり着きました。

ティケットと、競技場で貰ったガイドブックとうちわです。
いや〜、スゴかった!!本当にいい試合だった。
台風の中、苦労してわざわざ出かけて行っただけの価値がありました。
ゲームが始まって最初の日本の攻撃、パスをいきなりインターセプトされ攻守交替。
そのあとの数プレイで押し込まれ、先制点を取られてしまったのです。
何か、いや〜な始まり方でしたが、そこからは日本のペースでゲームが進み、セカンド・クォーターには49ヤードのフィールドゴールまで決め、前半終了時には10−7と逆転していました。
途中で雨が降り出し、びしょぬれになりながらの観戦でしたが、まわりの人達もみんな、そんな事を気にすることなく応援してましたね。

ところが、ハーフタイムを挟んで後半に入ると、今度はアメリカが優勢になってきたのですよ。
日本は立て続けにQBサックを受けましたからね。
でも、ロングパスやインターセプトを決めて場内を沸かせてくれました。
ただ、充分フィールドゴールが狙える距離でパントを選択したのが不思議に思えましたけどね・・・
その後、どっちも譲らずの熱戦でした。本当に面白かった。
一時は日本が優勝を決めたかと思ったのですが、終ってみると17−17の同点。
延長戦はアメリカの先攻で始まり、3−3の同点で、再延長戦になりました。
先攻の日本は34ヤードのフィールドゴールを右に外し、後攻のアメリカはフィールドゴールを決めた。
その時点でアメリカの優勝が決まりました。
 フィールドの中央で、両ティームのプレイヤー達が一列になって、すれ違いながら順番に握手を交わしている時、また雨が降って来ました。
フィールドの中央で、両ティームのプレイヤー達が一列になって、すれ違いながら順番に握手を交わしている時、また雨が降って来ました。
このあと表彰式が始まります、というアナウンスが流れた途端、オレは席を立って出口に向かいました。
表彰式も見たいけど、今まで見ていたゲームのスゴさを自分の中にそのまま残したかったからなのだと思います。
今回、全日本ティームは、本当に素晴らしいゲームを見せてくれました。
でも、問題点もいくつか見えて来ました。
スピードと纏まりの良さでは、あきらかにアメリカより上だったと思います。
対スウェーデン戦のあと、IFAF のウェブサイトに Speed over Size という見出しがありましたが、アメリカ・ティームに対しては、スピードだけではダメだったわけです。
パワーでは完全に負けていましたからね。
立て続けに QBサックを喰らった事や、ケガ人(タンカが使われる程のケガではなかったのですが)が続出した事、ランやパスが決まった時に多量のゲインを許してしまう事などが、そのことを顕著に物語っています。
あとは体格的な事でしょうか。決勝戦を見ていたスウェーデンやドイツのプレイヤー達のデカかったこと!!こんなのを相手にして勝ったのか、って思いましたね。
でも、体格的な問題は日本人である以上どうしようもないですかね。
でも、今回これだけの接戦になった以上、次回のアメリカ・ティームはもっと上のレヴェル(プロも含めて)のプレイヤーを選ぶ事になるでしょうから、スゴく大きい仕事をしたのだと評価するべきでしょうね。
インターネット上の掲示板を覗いてみると「本当に良くやった」という書き込みが多くある反面「世界一というには参加国が少な過ぎる」「NFL とやらなきゃ意味がない」「どうせアマチュアだろ」というような書き込みも結構ありますね。
どうも『世界』とか『プロ/アマチュア』という観点で否定的な意見を書くのは『他のフットボール』のファンらしいのですが、そもそも NFL と比べるのがおかしな話ですね。
世界一のスポーツ大国アメリカのトップアスリート中のトップアスリート、さらにその中の頂点とも言えるプレイヤーが集まっているのが NFL ですよ。
高校生から社会人まで全て合わせても18000人強の競技人口で、(こう言ってはなんですが)その全てがトップアスリートというわけでもない日本のフットボーラーとでは、試合が成立するわけがない。
考えれば分かる事ですよね。
逆に言わせて貰うなら、競技人口81万人の頂点に立つプロの中から選ばれた日本代表ティームが、散々税金から強化費を捻出させた挙げ句の果てに、QBK みたいな言い訳をして世界ランキング48位だって。
そんな生ぬるいプロよりも、この真剣に戦ったアマチュア達の方がよっぽどスゴい事をやったと、オレは心底思いますね。
実を言うと、今回の観戦は店のお客さんであるTさんと一緒でした。
Tさんは、友達に会うために前日から東京にいたのですが、オレより先に競技場へ行って席を取っていてくれました。(台風のために電車の接続がメチャメチャで、オレは予定よりかなり遅れましたが)
で、席に着くと、彼女はガイドブックのルールのところを読んでいたのです。
「あれ、ルール・・・知らんの?」 「初めて見るんです」 「えーっ!!」という会話のあと、基本的なルールとオーロラヴィジョンの数字の見方を説明したところで試合開始。
初めのうちは「今のは何でみんな喜んでいるんですか?」などと質問してきたTさんも、ファースト・クォーターの終り頃にはゲームの見方が分かって来たようで、1プレイごとに一喜一憂してましたね。
試合が終わって席を立つ時、彼女が言った「こんなに面白いものだったなんて知りませんでした」という言葉に、オレは「これを知ってしまうと・・・・(ここから後に言った事を書くと『他のフットボール』のファンが怒りそうですから止めておきましょう)
インターネット上の掲示板にフットボールの話が出ると「アメフトはルールが複雑で分からない」と書き込むヤツが必ずいますが、それに対するオレの答えはこうです。
「それはあなたがバカだからです。普通のアタマを持っている人なら理解できます。」
今回初めて見たTさんが、あれだけ喜んでいた事でも、それが証明されたと思います。
たぶん彼女は、NFL のシーズンが始まる秋頃、ウチの店のスクリーンで NFL のゲームを見に来る事になるだろうと思います。
まぁ、これでフットボール・ファンがひとり増えましたね。
ところで、今回のワールドカップが始まる少し前に、NFLヨーロッパのアムステルダム・アドミラルズに所属していた木下典明が、NFLのアトランタ・ファルコンズとフリーエージェント選手として2年契約を結び、トレーニングキャンプに参加することが決まりました。
木下がファルコンズの最終ロースターに残ることができれば、日本人初のNFL選手が誕生するわけですが、ファルコンズのウェブサイトのニュースのところを見ると、こんなふうに書かれています。
The Atlanta Falcons today signed wide receiver Noriaki Kinoshita (pronounced Nor-ee-ah-key Key-no-she-ta), a native of Osaka, Japan. Kinoshita graduated from Ritsumeikan University in Kyoto, Japan and spent the last three years with the Amsterdam Admirals of NFL Europa.
わざわざ名前の発音の仕方まで書いてあるところを見ると、ファルコンズは木下を高く評価しているのだろうと思います。
以前、このブログで『NFLに日本人プレイヤーが登場するのは、ズ〜ッと先のことだろうと思います。』と書いた事がありました(一糸乱れず 2/7)が、思っていたよりも早く実現するかもしれませんね。
今回の決勝戦の、文字どおりの『接戦』を観るにつけ、『日本のフットボール』の実力と評価が上がって行く事を、オレは心から願っていますよ。
今回、川崎まで行ってナマで決勝戦を観る事ができたわけですが、最後に今思っている事を書いて終りにします。
日本が三連覇するところを観たかった!!
では、また。
Ciao. Arrivederci!!
台風の中、クルマとバスを乗り継いで、川崎の等々力陸上競技場まで行って来ました。
最悪の場合、試合の延期もあるかもしれない状態だったので、出来る限り、そうなった時のための準備はしてから出かけたのですが、東京へ着いてすぐに千葉の友人のところへ電話し、大会の公式ウェブサイトを見てもらったところ、予定通り決行という事だったので、昼飯を食べる間もなく、台風の影響でダイヤがガタガタになった電車を乗り継ぎ、何とか武蔵小杉の駅までたどり着きました。

ティケットと、競技場で貰ったガイドブックとうちわです。
いや〜、スゴかった!!本当にいい試合だった。
台風の中、苦労してわざわざ出かけて行っただけの価値がありました。
ゲームが始まって最初の日本の攻撃、パスをいきなりインターセプトされ攻守交替。
そのあとの数プレイで押し込まれ、先制点を取られてしまったのです。
何か、いや〜な始まり方でしたが、そこからは日本のペースでゲームが進み、セカンド・クォーターには49ヤードのフィールドゴールまで決め、前半終了時には10−7と逆転していました。
途中で雨が降り出し、びしょぬれになりながらの観戦でしたが、まわりの人達もみんな、そんな事を気にすることなく応援してましたね。

ところが、ハーフタイムを挟んで後半に入ると、今度はアメリカが優勢になってきたのですよ。
日本は立て続けにQBサックを受けましたからね。
でも、ロングパスやインターセプトを決めて場内を沸かせてくれました。
ただ、充分フィールドゴールが狙える距離でパントを選択したのが不思議に思えましたけどね・・・
その後、どっちも譲らずの熱戦でした。本当に面白かった。
一時は日本が優勝を決めたかと思ったのですが、終ってみると17−17の同点。
延長戦はアメリカの先攻で始まり、3−3の同点で、再延長戦になりました。
先攻の日本は34ヤードのフィールドゴールを右に外し、後攻のアメリカはフィールドゴールを決めた。
その時点でアメリカの優勝が決まりました。
 フィールドの中央で、両ティームのプレイヤー達が一列になって、すれ違いながら順番に握手を交わしている時、また雨が降って来ました。
フィールドの中央で、両ティームのプレイヤー達が一列になって、すれ違いながら順番に握手を交わしている時、また雨が降って来ました。このあと表彰式が始まります、というアナウンスが流れた途端、オレは席を立って出口に向かいました。
表彰式も見たいけど、今まで見ていたゲームのスゴさを自分の中にそのまま残したかったからなのだと思います。
今回、全日本ティームは、本当に素晴らしいゲームを見せてくれました。
でも、問題点もいくつか見えて来ました。
スピードと纏まりの良さでは、あきらかにアメリカより上だったと思います。
対スウェーデン戦のあと、IFAF のウェブサイトに Speed over Size という見出しがありましたが、アメリカ・ティームに対しては、スピードだけではダメだったわけです。
パワーでは完全に負けていましたからね。
立て続けに QBサックを喰らった事や、ケガ人(タンカが使われる程のケガではなかったのですが)が続出した事、ランやパスが決まった時に多量のゲインを許してしまう事などが、そのことを顕著に物語っています。
あとは体格的な事でしょうか。決勝戦を見ていたスウェーデンやドイツのプレイヤー達のデカかったこと!!こんなのを相手にして勝ったのか、って思いましたね。
でも、体格的な問題は日本人である以上どうしようもないですかね。
でも、今回これだけの接戦になった以上、次回のアメリカ・ティームはもっと上のレヴェル(プロも含めて)のプレイヤーを選ぶ事になるでしょうから、スゴく大きい仕事をしたのだと評価するべきでしょうね。
インターネット上の掲示板を覗いてみると「本当に良くやった」という書き込みが多くある反面「世界一というには参加国が少な過ぎる」「NFL とやらなきゃ意味がない」「どうせアマチュアだろ」というような書き込みも結構ありますね。
どうも『世界』とか『プロ/アマチュア』という観点で否定的な意見を書くのは『他のフットボール』のファンらしいのですが、そもそも NFL と比べるのがおかしな話ですね。
世界一のスポーツ大国アメリカのトップアスリート中のトップアスリート、さらにその中の頂点とも言えるプレイヤーが集まっているのが NFL ですよ。
高校生から社会人まで全て合わせても18000人強の競技人口で、(こう言ってはなんですが)その全てがトップアスリートというわけでもない日本のフットボーラーとでは、試合が成立するわけがない。
考えれば分かる事ですよね。
逆に言わせて貰うなら、競技人口81万人の頂点に立つプロの中から選ばれた日本代表ティームが、散々税金から強化費を捻出させた挙げ句の果てに、QBK みたいな言い訳をして世界ランキング48位だって。
そんな生ぬるいプロよりも、この真剣に戦ったアマチュア達の方がよっぽどスゴい事をやったと、オレは心底思いますね。
実を言うと、今回の観戦は店のお客さんであるTさんと一緒でした。
Tさんは、友達に会うために前日から東京にいたのですが、オレより先に競技場へ行って席を取っていてくれました。(台風のために電車の接続がメチャメチャで、オレは予定よりかなり遅れましたが)
で、席に着くと、彼女はガイドブックのルールのところを読んでいたのです。
「あれ、ルール・・・知らんの?」 「初めて見るんです」 「えーっ!!」という会話のあと、基本的なルールとオーロラヴィジョンの数字の見方を説明したところで試合開始。
初めのうちは「今のは何でみんな喜んでいるんですか?」などと質問してきたTさんも、ファースト・クォーターの終り頃にはゲームの見方が分かって来たようで、1プレイごとに一喜一憂してましたね。
試合が終わって席を立つ時、彼女が言った「こんなに面白いものだったなんて知りませんでした」という言葉に、オレは「これを知ってしまうと・・・・(ここから後に言った事を書くと『他のフットボール』のファンが怒りそうですから止めておきましょう)
インターネット上の掲示板にフットボールの話が出ると「アメフトはルールが複雑で分からない」と書き込むヤツが必ずいますが、それに対するオレの答えはこうです。
「それはあなたがバカだからです。普通のアタマを持っている人なら理解できます。」
今回初めて見たTさんが、あれだけ喜んでいた事でも、それが証明されたと思います。
たぶん彼女は、NFL のシーズンが始まる秋頃、ウチの店のスクリーンで NFL のゲームを見に来る事になるだろうと思います。
まぁ、これでフットボール・ファンがひとり増えましたね。
ところで、今回のワールドカップが始まる少し前に、NFLヨーロッパのアムステルダム・アドミラルズに所属していた木下典明が、NFLのアトランタ・ファルコンズとフリーエージェント選手として2年契約を結び、トレーニングキャンプに参加することが決まりました。
木下がファルコンズの最終ロースターに残ることができれば、日本人初のNFL選手が誕生するわけですが、ファルコンズのウェブサイトのニュースのところを見ると、こんなふうに書かれています。
The Atlanta Falcons today signed wide receiver Noriaki Kinoshita (pronounced Nor-ee-ah-key Key-no-she-ta), a native of Osaka, Japan. Kinoshita graduated from Ritsumeikan University in Kyoto, Japan and spent the last three years with the Amsterdam Admirals of NFL Europa.
わざわざ名前の発音の仕方まで書いてあるところを見ると、ファルコンズは木下を高く評価しているのだろうと思います。
以前、このブログで『NFLに日本人プレイヤーが登場するのは、ズ〜ッと先のことだろうと思います。』と書いた事がありました(一糸乱れず 2/7)が、思っていたよりも早く実現するかもしれませんね。
今回の決勝戦の、文字どおりの『接戦』を観るにつけ、『日本のフットボール』の実力と評価が上がって行く事を、オレは心から願っていますよ。
今回、川崎まで行ってナマで決勝戦を観る事ができたわけですが、最後に今思っている事を書いて終りにします。
日本が三連覇するところを観たかった!!
では、また。
Ciao. Arrivederci!!
2007年07月14日
アメフト・ワールドカップ その1
Ciao. spockです。
7月7日から川崎で開催されているアメフトのワールドカップも決勝戦を残すだけとなりました。
同じ7月7日にトゥール ド フランスも始まりましたから、両方の情報集めに忙しい毎日でしたが・・・・
今回の大会では日本の3連覇が懸かっているわけですが、本家のアメリカが出場するのは今回が初めてですから、本当の意味での最初のワールドカップだとオレは思っています。

我が日本ティームは、初戦の対フランス戦、2戦目の対スウェーデン戦ともに48−0で圧勝し(日本が相手を0点におさえたのは、ワールドカップでは4回目)決勝進出を決めましたが、まぁ、予想通りの結果になりましたね。
 スウェーデン・ティームは体格的には圧倒的に有利な上、NFLヨーロッパの現役プレイヤーが何人かいる事もあって、ひょっとしたら苦戦になるかも、とも思っていましたが全くの杞憂に終りました。
スウェーデン・ティームは体格的には圧倒的に有利な上、NFLヨーロッパの現役プレイヤーが何人かいる事もあって、ひょっとしたら苦戦になるかも、とも思っていましたが全くの杞憂に終りました。
国際アメリカンフットボール連盟 IFAFのウェブサイトを見ると Speed over Size という見出しが目につきます。
決勝戦は日本対アメリカになるだろうと予想して、決勝戦のティケットを手に入れていたのですが、予想通りの組合わせになった事はいいとしても、台風の影響がどうなるかが心配です。
まぁ、普通のブログなら、ここで終るのでしょうが、まだまだ続くのが『ラ フェニーチェのチューボーから』なんですよね。
今回は、世界的アメフト事情について書いてみましょう。
今回のブログは『7月7日から川崎で開催されているアメフトのワールドカップも・・・』と書き出したわけですが、「へぇ〜、知らなかった」と言われる方が結構多いんじゃないかと思います。
出場国も6カ国だけ(予選があったのは当然ですが)の上、マスコミもほとんど話題にしてませんから、まぁ、こんなものと言えばこんなものなんですけどね。
今回出場するのは、開催国の日本、パン・アメリカ大陸代表のアメリカ、ヨーロッパ大陸代表のスウェーデン、ドイツ、フランス、アジア・オセアニア大陸代表の韓国の6カ国です。
そもそも、アメリカン・フットボール(以後フットボールと書きます)というスポーツは、当然の事ながら、それ以上ないほどアメリカのスポーツなんです。
だから、アメリカ人にすれば、他の国がやろうがやらまいが気にしていないようですね。
前2回の大会に本家のアメリカが出場しなかった理由が『アメリカを代表するアマチュア・フットボールの組織がなかったから』という事でも分かりますね。
世界で一番成功したスポーツ・ビジネスであるNFLは、ある程度地盤のあったヨーロッパにNFLEuropeを作りましたが(何人かの日本人プレイヤーもいます)、今年一杯で撤退する事が決まっています。
そういえばバブルの頃、東京にNFLのティーム『東京サムライズ』を作る計画もあったようですが、バブル崩壊と共に消え去りました。
国際アメリカンフットボール連盟(IFAF)に加盟している国を挙げてみましょうか。
ヨーロッパ大陸では、ドイツ、イタリア、フィンランド、スウェーデン、デンマーク、オランダ、フランス、イギリス、オーストリア、スイス、ベルギー、ノルウェー、スペイン、ロシア、チェコ、ハンガリー、ルクセンブルグ、スロヴァキア、トルコ、ポルトガル、ポーランド、ギリシャ、ウクライナ、エストニア、モルダヴィア、モロッコ、セルビア・モンテネグロ。
パン・アメリカ大陸では、アメリカ、カナダ、メキシコ、ブラジル、アルゼンチン、バハマ、コスタリカ、グァテマラ、ホンジュラス、ウルグアイ。
アジア・オセアニア大陸では、日本、韓国、オーストラリア、ニュージーランド、イスラエル、タイ。
その中でも特に盛んな国を挙げれば、本家のアメリカと、プロリーグのあるカナダ、メキシコを別にすれば、ドイツ(NFLEの6ティームの内、5ティームがドイツにある)と日本くらいでしょう。
競技人口から言えば、日本が約18600人、ドイツが約16500人、フランスは約6000人、スウェーデンは約2000人だという事です。(ただし、競技人口率では、アメリカ0.5%、スウェーデン0.022%、ドイツ0.020%、日本0.015%、フランス0.006%の順になります)
ヨーロッパの中でドイツの競技人口が特別多いのは、ラグビーが普及していないからなのだそうですが、そのドイツと、それより競技人口の多い日本にしてもマイナーなスポーツですから、世界的マイナースポーツである事は間違いないですね。
まぁ、アメリカとカナダ以外では、絶対にメジャーなスポーツになる事はないだろうと思いますけどね。(その事について、改めて書きます)
でも、こうして見てみると、日本とドイツでフットボールが盛ん(あくまでも他の国に比べてですが)なのは、何となく解る気がしませんか?
世界中で、列車の運行時間が一番正確なのが日本とドイツなのだそうです。
緻密な規則を作り、それをきちんと守るという国民性というか性格は、システマティックな戦略・戦術を組立て、各個人が自分の役割を確実に実行しながら敵陣に攻め込んで行くというフットボールの競技的特性にピッタリ合っているのだと思います。
また、日本とドイツは『物づくり』の国でもあります。言い換えれば『職人』の国という事です。
そういう意味でも『専門職のスポーツ』言い換えれば『職人技のスポーツ』であるフットボールが合っているのは当然だとオレは思っているのですけどね。
今から30年くらい前には「身体の小さい日本人にはラグビーやアメフトは絶対無理」とよく言われていました。
でも、オレはある時から、フットボールで世界のトップクラスにまで行けるんじゃないか、と思い始めたのですよ。勿論、それには理由があります。
過去に、日本人が世界のスタンダードになるような技術や戦略を考え出したスポーツでは世界一になっているんですよ。
たとえば、バレーボールの回転レシーヴ、水泳のバタフライ、それと平泳ぎの潜水泳法、これらは日本人が考え出し、その競技で世界一になっていますね。
ではフットボールでは、と言うと『ショットガン・フォーメイション』があります。
日大の篠竹幹夫監督が編み出したオフェンス陣形ですが、これが今ではプロが普通に使うフォーメイションのひとつになっています。
フットボールの場合は、NFL という飛び抜けて高い『世界最高峰』がありますから、世界一というのは難しいと思いますが、ワールドカップで3連覇を目指している現状を考えると、オレの考えは正しかったのじゃないかな、と思うのです。
身体的に不利だと言われ続けた日本人がここまでやっている事を考えると、やっぱりフットボールは日本人に合ったスポーツだったんだな、って思いますね。
あと、もうひとつ書いておかなければならない事があります。
前回のワールドカップの時、日本のフットボールについて、すべての国から賞賛された事があるのです。
それは日本のバックアップ体制です。
プレイヤーのトレーニングや食事、ボディーケア、マネージメントなどに関して、紛れもなく日本が世界一だと評価されたのですよ。
アマチュア・スポーツとしては世界最高のレヴェルにあると断言してもいいでしょう。
つくづく、日本のフットボールってスゴイと思います。
ここでついでにオレの意見を言わせてもらうなら、散々大騒ぎして税金まで投入したあげくに全く成果の出せないサッカーにばかりでなく、フットボールをはじめ頑張っているマイナースポーツにも国が助成するべきだと思うのですが、皆さんはどう思いますか?
さて、日本とドイツの事を書いた後にイタリアのことを書くのは矛盾しているような気もしますが、書いておく必要がありそうですね。
今大会には出場していませんが、かつてヨーロッパ選手権でダントツの優勝回数を誇っていたのがイタリアだと言うと、意外に思われる方が多いのではないでしょうか。
第1回のワールドカップが開催されたのもシチリアのパレルモでした。
イタリアでフットボールと言えば間違いなく Calcio であり、Football americano の認知度はずーっと低いうえ、競技人口は約3000人です。
でも、そんなイタリアが強いのですよ。
FIAF.NET を見てみると、こう言ってはなんですが、日本アメリカンフットボール協会のウェブサイトより、ずーっと充実した内容ですよ。
驚くのは、競技人口が日本の6分の1以下のイタリアで、Serie A1 からジュニア、ユース、キッズまで、きちんとしたピラミッドが出来ている事なんですよ。
何事につけ適当な事で有名なイタリア人が、スポーツに関する限り、実に緻密な組織を作り上げてしまうのは不思議ですね。
これはオレの持論なんですが、日本が工業製品でやっている事を、イタリアはスポーツでやっているのだと思うのです。
日本では、外国で開発された機械や電気器具などの工業製品を、世界のトップクラスの機能と品質に改良して輸出する。
イタリアでは、サッカー・バスケットボール・バレーボールなどの外国のスポーツで、世界のトップクラスのリーグを作り上げ、そこで活躍するプレイヤーを海外に送り出す。
おそらく、フットボールでも同じノリでリーグを作ってしまったのではないかと思います。
イタリア最強で最も人気があるのは Bergamo LIONS です。
ちなみに、ベルガモという街は、オレの料理の基本になっている Taverna del Colleoni があり、また自転車競技に関しても有名な街であり、そしてフットボールの街でもあります。
オレにとってはイタリアで一番大切な街なんですよ。
このブログを書いている14日の夜現在、明日の決勝戦が予定通り行われるのか分かりません。
でもオレは、明日の朝イチで出かけます。
何とか明日中に帰って来たいのですが、もし、それが無理なら、明後日のランチは臨時休業と言う事になるでしょうね。
まぁ、台風の進路次第なんですけどね・・・・・
次回の『その2』では、世界に広まらないフットボールの話、を書く予定です。
では、また。
Ciao. Arrivederci!!
7月7日から川崎で開催されているアメフトのワールドカップも決勝戦を残すだけとなりました。
同じ7月7日にトゥール ド フランスも始まりましたから、両方の情報集めに忙しい毎日でしたが・・・・
今回の大会では日本の3連覇が懸かっているわけですが、本家のアメリカが出場するのは今回が初めてですから、本当の意味での最初のワールドカップだとオレは思っています。

我が日本ティームは、初戦の対フランス戦、2戦目の対スウェーデン戦ともに48−0で圧勝し(日本が相手を0点におさえたのは、ワールドカップでは4回目)決勝進出を決めましたが、まぁ、予想通りの結果になりましたね。
 スウェーデン・ティームは体格的には圧倒的に有利な上、NFLヨーロッパの現役プレイヤーが何人かいる事もあって、ひょっとしたら苦戦になるかも、とも思っていましたが全くの杞憂に終りました。
スウェーデン・ティームは体格的には圧倒的に有利な上、NFLヨーロッパの現役プレイヤーが何人かいる事もあって、ひょっとしたら苦戦になるかも、とも思っていましたが全くの杞憂に終りました。国際アメリカンフットボール連盟 IFAFのウェブサイトを見ると Speed over Size という見出しが目につきます。
決勝戦は日本対アメリカになるだろうと予想して、決勝戦のティケットを手に入れていたのですが、予想通りの組合わせになった事はいいとしても、台風の影響がどうなるかが心配です。
まぁ、普通のブログなら、ここで終るのでしょうが、まだまだ続くのが『ラ フェニーチェのチューボーから』なんですよね。
今回は、世界的アメフト事情について書いてみましょう。
今回のブログは『7月7日から川崎で開催されているアメフトのワールドカップも・・・』と書き出したわけですが、「へぇ〜、知らなかった」と言われる方が結構多いんじゃないかと思います。
出場国も6カ国だけ(予選があったのは当然ですが)の上、マスコミもほとんど話題にしてませんから、まぁ、こんなものと言えばこんなものなんですけどね。
今回出場するのは、開催国の日本、パン・アメリカ大陸代表のアメリカ、ヨーロッパ大陸代表のスウェーデン、ドイツ、フランス、アジア・オセアニア大陸代表の韓国の6カ国です。
そもそも、アメリカン・フットボール(以後フットボールと書きます)というスポーツは、当然の事ながら、それ以上ないほどアメリカのスポーツなんです。
だから、アメリカ人にすれば、他の国がやろうがやらまいが気にしていないようですね。
前2回の大会に本家のアメリカが出場しなかった理由が『アメリカを代表するアマチュア・フットボールの組織がなかったから』という事でも分かりますね。
世界で一番成功したスポーツ・ビジネスであるNFLは、ある程度地盤のあったヨーロッパにNFLEuropeを作りましたが(何人かの日本人プレイヤーもいます)、今年一杯で撤退する事が決まっています。
そういえばバブルの頃、東京にNFLのティーム『東京サムライズ』を作る計画もあったようですが、バブル崩壊と共に消え去りました。
国際アメリカンフットボール連盟(IFAF)に加盟している国を挙げてみましょうか。
ヨーロッパ大陸では、ドイツ、イタリア、フィンランド、スウェーデン、デンマーク、オランダ、フランス、イギリス、オーストリア、スイス、ベルギー、ノルウェー、スペイン、ロシア、チェコ、ハンガリー、ルクセンブルグ、スロヴァキア、トルコ、ポルトガル、ポーランド、ギリシャ、ウクライナ、エストニア、モルダヴィア、モロッコ、セルビア・モンテネグロ。
パン・アメリカ大陸では、アメリカ、カナダ、メキシコ、ブラジル、アルゼンチン、バハマ、コスタリカ、グァテマラ、ホンジュラス、ウルグアイ。
アジア・オセアニア大陸では、日本、韓国、オーストラリア、ニュージーランド、イスラエル、タイ。
その中でも特に盛んな国を挙げれば、本家のアメリカと、プロリーグのあるカナダ、メキシコを別にすれば、ドイツ(NFLEの6ティームの内、5ティームがドイツにある)と日本くらいでしょう。
競技人口から言えば、日本が約18600人、ドイツが約16500人、フランスは約6000人、スウェーデンは約2000人だという事です。(ただし、競技人口率では、アメリカ0.5%、スウェーデン0.022%、ドイツ0.020%、日本0.015%、フランス0.006%の順になります)
ヨーロッパの中でドイツの競技人口が特別多いのは、ラグビーが普及していないからなのだそうですが、そのドイツと、それより競技人口の多い日本にしてもマイナーなスポーツですから、世界的マイナースポーツである事は間違いないですね。
まぁ、アメリカとカナダ以外では、絶対にメジャーなスポーツになる事はないだろうと思いますけどね。(その事について、改めて書きます)
でも、こうして見てみると、日本とドイツでフットボールが盛ん(あくまでも他の国に比べてですが)なのは、何となく解る気がしませんか?
世界中で、列車の運行時間が一番正確なのが日本とドイツなのだそうです。
緻密な規則を作り、それをきちんと守るという国民性というか性格は、システマティックな戦略・戦術を組立て、各個人が自分の役割を確実に実行しながら敵陣に攻め込んで行くというフットボールの競技的特性にピッタリ合っているのだと思います。
また、日本とドイツは『物づくり』の国でもあります。言い換えれば『職人』の国という事です。
そういう意味でも『専門職のスポーツ』言い換えれば『職人技のスポーツ』であるフットボールが合っているのは当然だとオレは思っているのですけどね。
今から30年くらい前には「身体の小さい日本人にはラグビーやアメフトは絶対無理」とよく言われていました。
でも、オレはある時から、フットボールで世界のトップクラスにまで行けるんじゃないか、と思い始めたのですよ。勿論、それには理由があります。
過去に、日本人が世界のスタンダードになるような技術や戦略を考え出したスポーツでは世界一になっているんですよ。
たとえば、バレーボールの回転レシーヴ、水泳のバタフライ、それと平泳ぎの潜水泳法、これらは日本人が考え出し、その競技で世界一になっていますね。
ではフットボールでは、と言うと『ショットガン・フォーメイション』があります。
日大の篠竹幹夫監督が編み出したオフェンス陣形ですが、これが今ではプロが普通に使うフォーメイションのひとつになっています。
フットボールの場合は、NFL という飛び抜けて高い『世界最高峰』がありますから、世界一というのは難しいと思いますが、ワールドカップで3連覇を目指している現状を考えると、オレの考えは正しかったのじゃないかな、と思うのです。
身体的に不利だと言われ続けた日本人がここまでやっている事を考えると、やっぱりフットボールは日本人に合ったスポーツだったんだな、って思いますね。
あと、もうひとつ書いておかなければならない事があります。
前回のワールドカップの時、日本のフットボールについて、すべての国から賞賛された事があるのです。
それは日本のバックアップ体制です。
プレイヤーのトレーニングや食事、ボディーケア、マネージメントなどに関して、紛れもなく日本が世界一だと評価されたのですよ。
アマチュア・スポーツとしては世界最高のレヴェルにあると断言してもいいでしょう。
つくづく、日本のフットボールってスゴイと思います。
ここでついでにオレの意見を言わせてもらうなら、散々大騒ぎして税金まで投入したあげくに全く成果の出せないサッカーにばかりでなく、フットボールをはじめ頑張っているマイナースポーツにも国が助成するべきだと思うのですが、皆さんはどう思いますか?
さて、日本とドイツの事を書いた後にイタリアのことを書くのは矛盾しているような気もしますが、書いておく必要がありそうですね。
今大会には出場していませんが、かつてヨーロッパ選手権でダントツの優勝回数を誇っていたのがイタリアだと言うと、意外に思われる方が多いのではないでしょうか。
第1回のワールドカップが開催されたのもシチリアのパレルモでした。
イタリアでフットボールと言えば間違いなく Calcio であり、Football americano の認知度はずーっと低いうえ、競技人口は約3000人です。
でも、そんなイタリアが強いのですよ。
FIAF.NET を見てみると、こう言ってはなんですが、日本アメリカンフットボール協会のウェブサイトより、ずーっと充実した内容ですよ。
驚くのは、競技人口が日本の6分の1以下のイタリアで、Serie A1 からジュニア、ユース、キッズまで、きちんとしたピラミッドが出来ている事なんですよ。
何事につけ適当な事で有名なイタリア人が、スポーツに関する限り、実に緻密な組織を作り上げてしまうのは不思議ですね。
これはオレの持論なんですが、日本が工業製品でやっている事を、イタリアはスポーツでやっているのだと思うのです。
日本では、外国で開発された機械や電気器具などの工業製品を、世界のトップクラスの機能と品質に改良して輸出する。
イタリアでは、サッカー・バスケットボール・バレーボールなどの外国のスポーツで、世界のトップクラスのリーグを作り上げ、そこで活躍するプレイヤーを海外に送り出す。
おそらく、フットボールでも同じノリでリーグを作ってしまったのではないかと思います。
イタリア最強で最も人気があるのは Bergamo LIONS です。
ちなみに、ベルガモという街は、オレの料理の基本になっている Taverna del Colleoni があり、また自転車競技に関しても有名な街であり、そしてフットボールの街でもあります。
オレにとってはイタリアで一番大切な街なんですよ。
このブログを書いている14日の夜現在、明日の決勝戦が予定通り行われるのか分かりません。
でもオレは、明日の朝イチで出かけます。
何とか明日中に帰って来たいのですが、もし、それが無理なら、明後日のランチは臨時休業と言う事になるでしょうね。
まぁ、台風の進路次第なんですけどね・・・・・
次回の『その2』では、世界に広まらないフットボールの話、を書く予定です。
では、また。
Ciao. Arrivederci!!
2007年02月22日
銀行へ行く時に
Ciao. spockです。
前回の投稿から間が空いてしまいました。
出かけていたり、Mac がフリーズしたり(長い文なので記憶をもとに書き直すのが大変なのですよ)と、いろいろありまして・・・・
その間も覗いて下さった方々、ありがとうございます。
では、8日ぶりの spock の Blog です。
この土・日と東京へ行って来ました。以前ここに書いた『講習』の最後の回を受講してきたのです。
事前の話では、最後に認定証がもらえると聞いていたのですが、オレはそんな事はありえないと思っていました。
なぜなら、オレは技術系の人間ですから、技術というものは経験を積む事によって初めて身に付くものであって、習ってスグにできるものではない事をよく分っているからです。
最後にもらえたのは、思っていたとおり修了証でした。
先生曰く「協力者を見つけて、とにかく経験を積む事。プロとしてやれるようになった時にはサインが現れますよ。」
オレは先生を全面的に信頼していますから、早速、協力者探しから始めようと思っています。
さて、今回の話は、前々回の最後に書いたように、アメフトの装備のひとつを日常生活の中で使ってしまうという話です。
自分では結構いいアイディアだと思っているのですが、端から見るとどうなんでしょうね。
ところで、この Blog を書きかけで東京へ行ったのですが、ホテルで『所さんのメガテン』を観ていたら、この中に書いていた事が出てきたのですよ。驚きましたねぇ。
今から13年も前の事、池袋のサンシャインシティーにあるミプロ(製品輸入促進協会)で、アメリカのスポーツショップのカタログを見つけ、個人輸入でいろいろ取り寄せたのです。その後も年に2〜3回、日本では手に入らないような物を中心に取り寄せていました。

これは去年の夏と秋のカタログです。
今はウェブサイトを見てインターネットでオーダーしますが、たまに送られてくるカタログを見るのも、何かワクワクしますね。
他人の持って居ない物を手に入れる事に喜びを感じるオレとしては、年に数回送られてくるカタログ(今はウェブサイトですが)を見て、ワクワクしてましたねぇ。
なので、ナイキのエアーマックスがブレイクした時、日本からのオーダーが急増したからなのでしょうが、急にカタログに日本語の解説書が付いてきた時には何か寂しいものを感じましたね。
とは言っても、気になっていた物が製造中止になってメチャメチャ安く出ていたりすると、すぐにオーダーを入れるわけです。送料を少しでも安くするために、後輩達にも声をかけて共同購入の形で取り寄せていました。
今ではインターネットでオーダーできますから簡単なものですが、シューズやウェアといった定番の他に、見逃せない項目があるのですよ。それは Football Equipment(フットボールの装備)です。
前々回の Blog の中に、『アメフトというスポーツの性格上、装備や機材から審判やトレーニング方に至るまで、最新の技術を惜しげもなく投入し、それを他のスポーツや、さらには一般社会にもフィードバックしている』と書いていますが、その事が一番良く解るのが、この Football Eqipment なのです。
過去の事例から解りやすい例をあげてみましょうか。
オレと同じ世代の人ならきっと憶えていると思うのですが『象がふんでもこわれない アーム筆入れ』 ポリカーボネイト製の本当に丈夫な筆入れでした。(オレは10年位使ってました)
ドイツのバイエル社が開発したポリカーボネイトは、最初は軍事用(例えば空軍のパイロット用ヘルメット)として使われたようですが、コンシューマー(一般消費者)用として最初に使われたのはフットボールのヘルメットだったようで、その強さが認められて世の中に広まっていった、というわけです。
70年代初頭の写真器材用ハードケースの広告に『フットボールのヘルメットに使われている頑丈なポリカーボネート使用』って書かれていたのを憶えていますが、その当時の日本でのフットボールの認知度を考えると、どの位の人が理解したのかは解りませんね。
それから、今ではユニクロでも普通に売っている、ドライTシャツ。
これもコンシューマー用として最初に発売されたのは、フットボール用インナーウェアとしてでした。
普通ではありえない装備を全身に着けて無酸素運動を繰り返すスポーツ故に、いかに素早く汗を放出できるかというのは最重要問題のひとつだったわけで、最初にフットボール用として使われたのは当然と言えば当然の事だったのでしょう。
10年程前にフットボール用のインナーを取り寄せたのですが、オレはそれを自転車に乗る時に着ていました。(快適でしたよ)
それから何年か経って、日本のメーカーも自転車用のインナーを発売したのですが、材質はほぼ同じでしたから、それもフットボールからのフィードバックだったのだと思います。
そんなわけで、Football Eqipment の中から何か使えそうな物や、これから世の中に広がっていく可能性のある物を探す事が、オレにとっては本当に興味深い事なのですが、前回のオーダーで手に入れたのがコレ

ナイキのマグニグリップ・フォース(Nike Magnigrip Force)
早い話が、フットボール用グローブです。
このグローブ、掌側に少し粘着性のあるゴム系の素材が使われているのです。
WR(ワイドレシーヴァー)がボールを確実にレシーヴするために絶対必要な装備であり、また、オフェンスの有捕球資格者(ボールにさわれないラインの5人(50〜79番)以外のプレイヤーを指す)はボールを持った瞬間からタックルの標的になり、ボールをファンブルした上にディフェンス側にリカヴァーされると、その瞬間から攻守が入れ替わってしまいますから、絶対にボールを離さないために、こんなグローブができたわけです。
1年前にも別のグローブを手に入れていたのですが、その時は自転車に乗る時に使うつもりでした。ハンドルをしっかりとグリップできそうですからね。
実際にやってみると、じつにしっかりとグリップできます。これなら疲れた時にはハンドルに手を添えているだけで大丈夫だ、と思ったのですが、とっさに手を離そうと思った時、離れにくいのですよ。
これでは逆に危険だと思い、他に使いみちはないかと考えていたら・・・・・ありました。
うちの店に大した売上げはありませんが、銀行(信用金庫ですけど)へ預けに行く時には売上金の入ったバッグをしっかりと抱えて行きます。
そんな時にこのグローブを使えばいいのですよ。

実際にやってみたところ、このグローブを着けて片手で持ったバッグを、両手(素手)で掴んで引っ張られてもバッグが手から離れる事はありません。
さらにはRB(ランニングバック)がボールを抱えて走る時のように持てば(画像参照)引ったくられる可能性はゼロだと言っていいと思います。(オレはいつもこんなふうに持っています)
そのうちに日本のどこかのメーカーが、この素材を使って『ひったくり防止手袋』なんていうのを売り出すんじゃないかと思うんですが・・・・・(ないか)
ただ、冬は防寒をかねてちょうどいいのですが、夏に使うのはチョットね・・・・・orz
近々、次のオーダーを出す予定なのですが、今度は何にするか・・・・ウェブサイトを見ながら考え込んでいる今日この頃です。
では、また。
Ciao. Arrivederci!!
前回の投稿から間が空いてしまいました。
出かけていたり、Mac がフリーズしたり(長い文なので記憶をもとに書き直すのが大変なのですよ)と、いろいろありまして・・・・
その間も覗いて下さった方々、ありがとうございます。
では、8日ぶりの spock の Blog です。
この土・日と東京へ行って来ました。以前ここに書いた『講習』の最後の回を受講してきたのです。
事前の話では、最後に認定証がもらえると聞いていたのですが、オレはそんな事はありえないと思っていました。
なぜなら、オレは技術系の人間ですから、技術というものは経験を積む事によって初めて身に付くものであって、習ってスグにできるものではない事をよく分っているからです。
最後にもらえたのは、思っていたとおり修了証でした。
先生曰く「協力者を見つけて、とにかく経験を積む事。プロとしてやれるようになった時にはサインが現れますよ。」
オレは先生を全面的に信頼していますから、早速、協力者探しから始めようと思っています。
さて、今回の話は、前々回の最後に書いたように、アメフトの装備のひとつを日常生活の中で使ってしまうという話です。
自分では結構いいアイディアだと思っているのですが、端から見るとどうなんでしょうね。
ところで、この Blog を書きかけで東京へ行ったのですが、ホテルで『所さんのメガテン』を観ていたら、この中に書いていた事が出てきたのですよ。驚きましたねぇ。
今から13年も前の事、池袋のサンシャインシティーにあるミプロ(製品輸入促進協会)で、アメリカのスポーツショップのカタログを見つけ、個人輸入でいろいろ取り寄せたのです。その後も年に2〜3回、日本では手に入らないような物を中心に取り寄せていました。

これは去年の夏と秋のカタログです。
今はウェブサイトを見てインターネットでオーダーしますが、たまに送られてくるカタログを見るのも、何かワクワクしますね。
他人の持って居ない物を手に入れる事に喜びを感じるオレとしては、年に数回送られてくるカタログ(今はウェブサイトですが)を見て、ワクワクしてましたねぇ。
なので、ナイキのエアーマックスがブレイクした時、日本からのオーダーが急増したからなのでしょうが、急にカタログに日本語の解説書が付いてきた時には何か寂しいものを感じましたね。
とは言っても、気になっていた物が製造中止になってメチャメチャ安く出ていたりすると、すぐにオーダーを入れるわけです。送料を少しでも安くするために、後輩達にも声をかけて共同購入の形で取り寄せていました。
今ではインターネットでオーダーできますから簡単なものですが、シューズやウェアといった定番の他に、見逃せない項目があるのですよ。それは Football Equipment(フットボールの装備)です。
前々回の Blog の中に、『アメフトというスポーツの性格上、装備や機材から審判やトレーニング方に至るまで、最新の技術を惜しげもなく投入し、それを他のスポーツや、さらには一般社会にもフィードバックしている』と書いていますが、その事が一番良く解るのが、この Football Eqipment なのです。
過去の事例から解りやすい例をあげてみましょうか。
オレと同じ世代の人ならきっと憶えていると思うのですが『象がふんでもこわれない アーム筆入れ』 ポリカーボネイト製の本当に丈夫な筆入れでした。(オレは10年位使ってました)
ドイツのバイエル社が開発したポリカーボネイトは、最初は軍事用(例えば空軍のパイロット用ヘルメット)として使われたようですが、コンシューマー(一般消費者)用として最初に使われたのはフットボールのヘルメットだったようで、その強さが認められて世の中に広まっていった、というわけです。
70年代初頭の写真器材用ハードケースの広告に『フットボールのヘルメットに使われている頑丈なポリカーボネート使用』って書かれていたのを憶えていますが、その当時の日本でのフットボールの認知度を考えると、どの位の人が理解したのかは解りませんね。
それから、今ではユニクロでも普通に売っている、ドライTシャツ。
これもコンシューマー用として最初に発売されたのは、フットボール用インナーウェアとしてでした。
普通ではありえない装備を全身に着けて無酸素運動を繰り返すスポーツ故に、いかに素早く汗を放出できるかというのは最重要問題のひとつだったわけで、最初にフットボール用として使われたのは当然と言えば当然の事だったのでしょう。
10年程前にフットボール用のインナーを取り寄せたのですが、オレはそれを自転車に乗る時に着ていました。(快適でしたよ)
それから何年か経って、日本のメーカーも自転車用のインナーを発売したのですが、材質はほぼ同じでしたから、それもフットボールからのフィードバックだったのだと思います。
そんなわけで、Football Eqipment の中から何か使えそうな物や、これから世の中に広がっていく可能性のある物を探す事が、オレにとっては本当に興味深い事なのですが、前回のオーダーで手に入れたのがコレ

ナイキのマグニグリップ・フォース(Nike Magnigrip Force)
早い話が、フットボール用グローブです。
このグローブ、掌側に少し粘着性のあるゴム系の素材が使われているのです。
WR(ワイドレシーヴァー)がボールを確実にレシーヴするために絶対必要な装備であり、また、オフェンスの有捕球資格者(ボールにさわれないラインの5人(50〜79番)以外のプレイヤーを指す)はボールを持った瞬間からタックルの標的になり、ボールをファンブルした上にディフェンス側にリカヴァーされると、その瞬間から攻守が入れ替わってしまいますから、絶対にボールを離さないために、こんなグローブができたわけです。
1年前にも別のグローブを手に入れていたのですが、その時は自転車に乗る時に使うつもりでした。ハンドルをしっかりとグリップできそうですからね。
実際にやってみると、じつにしっかりとグリップできます。これなら疲れた時にはハンドルに手を添えているだけで大丈夫だ、と思ったのですが、とっさに手を離そうと思った時、離れにくいのですよ。
これでは逆に危険だと思い、他に使いみちはないかと考えていたら・・・・・ありました。
うちの店に大した売上げはありませんが、銀行(信用金庫ですけど)へ預けに行く時には売上金の入ったバッグをしっかりと抱えて行きます。
そんな時にこのグローブを使えばいいのですよ。

実際にやってみたところ、このグローブを着けて片手で持ったバッグを、両手(素手)で掴んで引っ張られてもバッグが手から離れる事はありません。
さらにはRB(ランニングバック)がボールを抱えて走る時のように持てば(画像参照)引ったくられる可能性はゼロだと言っていいと思います。(オレはいつもこんなふうに持っています)
そのうちに日本のどこかのメーカーが、この素材を使って『ひったくり防止手袋』なんていうのを売り出すんじゃないかと思うんですが・・・・・(ないか)
ただ、冬は防寒をかねてちょうどいいのですが、夏に使うのはチョットね・・・・・orz
近々、次のオーダーを出す予定なのですが、今度は何にするか・・・・ウェブサイトを見ながら考え込んでいる今日この頃です。
では、また。
Ciao. Arrivederci!!
2007年02月10日
世界中で役に立っているもの
Ciao. spockです。
前々回、スーパーボウルに絡んで、延々とアメフトの話を書きましたが、以前からいろいろな人達に聞いてみたところでは、どうも多くの人は、アメフトを『特殊なスポーツ』だと思っているようなのです。
この『特殊な』というのも漠然としていて、解釈の仕方もいろいろありそうなのですが・・・
まぁ、アメフト側のオレとしては、人類が進化する過程で他の動物との違いを決定づけた『機能』を使う事を全面的に禁じているスポーツの方が、よっぽど『特殊』だと思うのですがね。
知らない人が見れば、複雑怪奇としか見えないだろうルールも然る事ながら(と言っても、ルールブックのページ数は野球のほうがずーっと多いのですが)、やはりアメフトを『特殊』に見せている一番の原因は、あのスタイルというか装備でしょうね。
かく言うオレも、前々回にはあの装備を身に付けた画像をアップした上に、前回からはそれをプロフィールの画像に転用していますから 『アイシールドでうまく顔が隠れているから』というのが一番の理由だったとはいえ、意識の中に『他にこんな画像を使うヤツはおらんやろう』という、特殊性を肯定した気持ちがあった事は否めませんね。
アメフトの装備の中でも特徴的なのはヘルメットとショルダーパッドだと思いますが、今回は、そのヘルメットの話です。

オレの使っていたヘルメットです。
オレはバックスだったので、それ程あたる事はなかったのですが、相手のヘルメットとあたって付いた塗料の痕が残っています。
ヘルメットは当然頭を保護するために被るものですが、では、その構造はと聞かれたら、どう答えますか?
大抵は『強化プラスティックのシェル(帽体)の内側に緩衝材(クッション)をつけたもの』とか『シェルとあたまの間に隙間を空けてある』と答えるでしょう。実際、そう答えるしかないですね。
半世紀以上も前なら『鉄かぶと』と呼ばれていたように、重い鉄製のものだったのでしょうが、現代では誰もが、ヘルメットは強化プラスティック製であると認識していると思います。
では、強化プラスティック製のヘルメットは、いつ、どのように作られたのでしょうか。
強化プラスティック製のヘルメットは、1939年にアメリカのRiddell (リデル)社によって作られました。
Riddell のウェブサイト http://riddell.com/は極めてマニアックで(オレが言うのだから本当です)、ヘルメットの歴史などが詳しく書かれています。(勿論英語ですけど) この中の動画も結構面白いですよ。
以前はこのウェブサイトのトップページに、先日のスーパーボウルのMVP、ペイトン・マニングがコールしているところのアップの画像がつかわれていました。マニングは Riddell の Revolution というヘルメットを使っていますから、それがハッキリと写っていたのです。
おわかりですね、Riddell はフットボール ヘルメットのメーカーなのです。
この話をすると、大抵「へぇ〜」って言われるのですが、現在世界中で使われている強化プラスティック製のヘルメットは、アメフトのために作られたものが転用され、世界に広まったものなのです。
1939年というと第二次世界大戦が始まった年でもありますが、アメフト用に作られた新型のヘルメットの事を知ったアメリカ政府は、すぐに軍隊のためにそれを導入したのです。
その後、機能性に優れたこのヘルメットが世界中に広まった事は言うまでもありません。
ヘルメットのおかげで命拾いしたそこのアナタ、もうアメフトには足を向けて寝られませんよ。これからはアメフトを観るんですよ!! って、霊感商法かよっ・・・・・orz
アメフトの事を、アメリカだけでしか通用しないマイナースポーツだと言う人がいます。オレはその事を否定しません。でも、その事を認めた上で、これ程世の中の役に立っているスポーツは他にないと思うのです。
それは、ここまで書いてきたヘルメットの事例でも解ってもらえると思いますが、アメフトというスポーツの性格上、装備や機材から審判やトレーニング方に至るまで、最新の技術を惜しげもなく投入し、それを他のスポーツや、さらには一般社会にもフィードバックしているという、紛れもない事実があるからです。
まぁ、ここまで言うと、贔屓の引き倒しだと言われるかもしれませんが・・・・
(追記に、アメフトのヘルメットの起源と最新作の話があります)
この Blog のプロフィールに使っている画像では、スモークのアイシールドのせいで顔が見えませんが、現在の日本のルールでは、クリア以外のアイシールドは禁止されていますから、これを試合に使う事はできません。
もともとアイシールドには、眼を保護するという役割の他に、眼を隠す事で、視線の動きから次のプレイを見破られる事を防ぐという、さらに重要な役割があったのです。クリアのものしか使えないのでは、あまり意味がないと思うのはオレだけではないでしょうね。
アメリカでは、そんな規制はありませんから、サングラス並みにいろんな種類のアイシールドを売っています。でも、それだけの種類をどう使い分けるんでしょうね。
そんな事を考えながら某ウェブサイトを見ていたら、見つけました。
 ミラード・アイシールド。
ミラード・アイシールド。
思わず「カッコえぇー」って
言ってしまいましたね。
画像はグリーンミラーだけど
やっぱりシルヴァーがいい。
値段は約$50。オークリーの
イリディウムミラーは、なん
と$250!! ヘルメット本体が
2つ買えますよ。
オレがプレーヤーだった頃に
これがあったら、ゼーッタイ
使っていたでしょうね。
そういえば、東洋人と欧米人では頭の形が違い、上から見ると、東洋人は真円に近く、欧米人は前後に長い楕円形だと言われています。
そのため、東洋人がヘルメットを脱ぐ時は両手でシェルを横に広げながら脱がなければならないのですが、欧米人は片手でフェイスガードを持って引き上げるだけで脱げるのです。
それがまたカッコよく見えるのですよ。
どういうわけか、オレは頭が前後に長いので、片手で脱げるんです。
みんなが両手で脱いでいる時、オレはさり気なく片手で脱いで、内心ニンマリしていましたね。
まぁ、大人気ないと言えば大人気ないのですが・・・・・
次にアメフトの話を書く時のテーマは、もう決まっているのですよ。
あの装備の中のある物を、普段の生活に使うという話です。
人によっては、使える裏技(?)だと思うのですがね。
では、また。
Ciao. Arrivederci!! 続きを読む
前々回、スーパーボウルに絡んで、延々とアメフトの話を書きましたが、以前からいろいろな人達に聞いてみたところでは、どうも多くの人は、アメフトを『特殊なスポーツ』だと思っているようなのです。
この『特殊な』というのも漠然としていて、解釈の仕方もいろいろありそうなのですが・・・
まぁ、アメフト側のオレとしては、人類が進化する過程で他の動物との違いを決定づけた『機能』を使う事を全面的に禁じているスポーツの方が、よっぽど『特殊』だと思うのですがね。
知らない人が見れば、複雑怪奇としか見えないだろうルールも然る事ながら(と言っても、ルールブックのページ数は野球のほうがずーっと多いのですが)、やはりアメフトを『特殊』に見せている一番の原因は、あのスタイルというか装備でしょうね。
かく言うオレも、前々回にはあの装備を身に付けた画像をアップした上に、前回からはそれをプロフィールの画像に転用していますから 『アイシールドでうまく顔が隠れているから』というのが一番の理由だったとはいえ、意識の中に『他にこんな画像を使うヤツはおらんやろう』という、特殊性を肯定した気持ちがあった事は否めませんね。
アメフトの装備の中でも特徴的なのはヘルメットとショルダーパッドだと思いますが、今回は、そのヘルメットの話です。

オレの使っていたヘルメットです。
オレはバックスだったので、それ程あたる事はなかったのですが、相手のヘルメットとあたって付いた塗料の痕が残っています。
ヘルメットは当然頭を保護するために被るものですが、では、その構造はと聞かれたら、どう答えますか?
大抵は『強化プラスティックのシェル(帽体)の内側に緩衝材(クッション)をつけたもの』とか『シェルとあたまの間に隙間を空けてある』と答えるでしょう。実際、そう答えるしかないですね。
半世紀以上も前なら『鉄かぶと』と呼ばれていたように、重い鉄製のものだったのでしょうが、現代では誰もが、ヘルメットは強化プラスティック製であると認識していると思います。
では、強化プラスティック製のヘルメットは、いつ、どのように作られたのでしょうか。
強化プラスティック製のヘルメットは、1939年にアメリカのRiddell (リデル)社によって作られました。
Riddell のウェブサイト http://riddell.com/は極めてマニアックで(オレが言うのだから本当です)、ヘルメットの歴史などが詳しく書かれています。(勿論英語ですけど) この中の動画も結構面白いですよ。
以前はこのウェブサイトのトップページに、先日のスーパーボウルのMVP、ペイトン・マニングがコールしているところのアップの画像がつかわれていました。マニングは Riddell の Revolution というヘルメットを使っていますから、それがハッキリと写っていたのです。
おわかりですね、Riddell はフットボール ヘルメットのメーカーなのです。
この話をすると、大抵「へぇ〜」って言われるのですが、現在世界中で使われている強化プラスティック製のヘルメットは、アメフトのために作られたものが転用され、世界に広まったものなのです。
1939年というと第二次世界大戦が始まった年でもありますが、アメフト用に作られた新型のヘルメットの事を知ったアメリカ政府は、すぐに軍隊のためにそれを導入したのです。
その後、機能性に優れたこのヘルメットが世界中に広まった事は言うまでもありません。
ヘルメットのおかげで命拾いしたそこのアナタ、もうアメフトには足を向けて寝られませんよ。これからはアメフトを観るんですよ!! って、霊感商法かよっ・・・・・orz
アメフトの事を、アメリカだけでしか通用しないマイナースポーツだと言う人がいます。オレはその事を否定しません。でも、その事を認めた上で、これ程世の中の役に立っているスポーツは他にないと思うのです。
それは、ここまで書いてきたヘルメットの事例でも解ってもらえると思いますが、アメフトというスポーツの性格上、装備や機材から審判やトレーニング方に至るまで、最新の技術を惜しげもなく投入し、それを他のスポーツや、さらには一般社会にもフィードバックしているという、紛れもない事実があるからです。
まぁ、ここまで言うと、贔屓の引き倒しだと言われるかもしれませんが・・・・
(追記に、アメフトのヘルメットの起源と最新作の話があります)
この Blog のプロフィールに使っている画像では、スモークのアイシールドのせいで顔が見えませんが、現在の日本のルールでは、クリア以外のアイシールドは禁止されていますから、これを試合に使う事はできません。
もともとアイシールドには、眼を保護するという役割の他に、眼を隠す事で、視線の動きから次のプレイを見破られる事を防ぐという、さらに重要な役割があったのです。クリアのものしか使えないのでは、あまり意味がないと思うのはオレだけではないでしょうね。
アメリカでは、そんな規制はありませんから、サングラス並みにいろんな種類のアイシールドを売っています。でも、それだけの種類をどう使い分けるんでしょうね。
そんな事を考えながら某ウェブサイトを見ていたら、見つけました。
 ミラード・アイシールド。
ミラード・アイシールド。思わず「カッコえぇー」って
言ってしまいましたね。
画像はグリーンミラーだけど
やっぱりシルヴァーがいい。
値段は約$50。オークリーの
イリディウムミラーは、なん
と$250!! ヘルメット本体が
2つ買えますよ。
オレがプレーヤーだった頃に
これがあったら、ゼーッタイ
使っていたでしょうね。
そういえば、東洋人と欧米人では頭の形が違い、上から見ると、東洋人は真円に近く、欧米人は前後に長い楕円形だと言われています。
そのため、東洋人がヘルメットを脱ぐ時は両手でシェルを横に広げながら脱がなければならないのですが、欧米人は片手でフェイスガードを持って引き上げるだけで脱げるのです。
それがまたカッコよく見えるのですよ。
どういうわけか、オレは頭が前後に長いので、片手で脱げるんです。
みんなが両手で脱いでいる時、オレはさり気なく片手で脱いで、内心ニンマリしていましたね。
まぁ、大人気ないと言えば大人気ないのですが・・・・・
次にアメフトの話を書く時のテーマは、もう決まっているのですよ。
あの装備の中のある物を、普段の生活に使うという話です。
人によっては、使える裏技(?)だと思うのですがね。
では、また。
Ciao. Arrivederci!! 続きを読む
2007年02月07日
一糸乱れず
Ciao. spockです。
Super Bowl XLIも終りました。
雨の中の試合で、プレイヤーも観客も大変だったようですが、ベアーズの守備力をコルツの攻撃力が上回ったという結果になりましたね。
今回は、アメフトを通してspockが見た、アメリカとアメリカ人の話です。
スーパーボウルを世界最大のスポーツイヴェントだと言うと、異を唱える人もいるだろうけれど、1日で動く、カネ・モノ・ヒトを考えると、あながち間違いではないと思います。
この1試合だけで、NFLに入る放送権料はいくらになるんでしょうね。世界中の他のスポーツが束になっても敵わない額である事は間違いないようです。
ただ、NFLがスゴいと思うのは、それだけの放送権料を動かしていながら、TVが観客動員数を減らさない為のルールをきちんと作っている事なんです。『ブラックアウト』なんかは、その最も解りやすい例でしょう。
ブラックアウトというのは、ゲーム開始の72時間前までに、あるゲームのティケットが完売しなかった場合、出場ティームのフランチャイズ地区及び75マイル圏内のホーム地区では、そのゲームのTV中継が行われず、他の地区のゲームが放送されるわけです。
『地元ではファンにスタジアムに来てもらう事が最優先事項』という、NFLのポリシーに則ったものになっているのです。
このやり方をそのまま持って来るのは無理だとしても、観客動員数や視聴率の低下に対して、何の打開策も持たないでいる日本のプロ野球やサッカーは、少しは参考にして考えたらいいと思うのです。
スーパーボウルを生で観るというのは不可能かもしれませんが、NFLのゲームを一度観てみたいですね。インベスコ・フィールド・アト・マイルハイ(デンヴァー)に行って、ブロンコスのゲームを観てみたいとは思っているのですがね・・・・
ところで、最近、NHLに日本人プレイヤーが登場したので、アメリカの4大スポーツで、日本人がプレイした事がないのはNFLだけになりました。でも、NFLに日本人プレイヤーが登場するのは、ズ〜ッと先のことだろうと思います。
運動能力や体格の事なら、ポジションによっては日本人でも通用するプレイヤーは出てくると思います。問題は他にあるのです。
アメフトの競技としての性格上、日本のアマチュアティームでも、プレイブックには、専門用語・特殊用語の羅列で、一般人には理解不能でしょう。プレイコールだって、何を言っているのか解らないと思います。
それが、トップレヴェルのプロだったらどうでしょう。ネイティヴ同様の言語力がない限り、通用しないでしょうね。そこが、他のスポーツとの一番大きな違いであり、難しさなのでしょう。
さて、ここまでタイトルに関連した話が出て来ていませんが、ここからですよ。
1984年、ロサンジェルスでオリンピックが開催されました。ド派手な開会式もさる事ながら、一番印象に残ったのは、日本とアメリカの選手団の入場の仕方の違いについてなのです。
お揃いのスーツをキチッと着て、歩幅さえ統一された状態で行進した日本選手団に対し、ユニフォームを着ている事以外、一人一人が全く違う事をしながら入場したアメリカ選手団。
この違いは何なのだろうと考えましたねぇ。
あれ以来、日本人に対しては『一糸乱れぬ団体行動』、アメリカ人に対しては『バラバラで適当な個人的行動』というイメージが、自分の中にできていたように思います。スポーツ以外の事から見ても、そのイメージは間違っていないと・・・・
15年前の7月初め、フットボールのゲームのため、ある場所へ行きました。
普通ならありえない環境の中で、ある種の感動をしながら、サイドラインに立ってゲームを観ていました。
その場所とは、横須賀米軍基地内のフットボール・フィールド。
ウチのティームの関係者以外は全員アメリカ人で、スピーカーから流れるアナウンスは勿論英語、サイドラインのベンチの上には、大きなゲータレイドのタンクが3本(今回のスーパーボウルでも、勝利が決まる直前に、コルツのプレイヤー達がそのタンクを持ち上げて、ヘッドコーチのトニー・ダンジーにドリンクシャワーを浴びせていましたね)。あぁ、アメリカだなぁ、って思いましたね。
4ヵ月前にフットボールを始めたばかりのオレは、その前の週にゲームデヴューしていました。といっても、勝ちの決まったゲームの終盤に、戦略上それ程重要ではないポジションで(一応WRでしたが)出してもらったわけなのですが・・・
相手はネイヴィー(海軍)のティームとはいえ、臨時の寄せ集めティームですから、こっちが勝つとみんな思っていたようです。(実際、前年は勝ったそうですから)
で、オレも、またゲームに出れるなぁ、って思っていたのですよ。
ところが相手は強かった。キックオフ直後からむこうが優勢なのが解りましたから。そのうち、こっちのLBが足を骨折してアンビュランスで運ばれて行き、こりゃダメだというムードができてしまったのですよ。
そんな中、オレがゲームに出る事はないなぁ、と思いながらサイドラインに立ってゲームを観ていたのですが、ふと、ある事に気が付いて、感動しましたねぇ。
そのある事とは、スクリメイジライン上でのプレイヤー達の動きなのです。
そこのところを解説すると、QBの"Ready"のコールでそれぞれの位置に着き、"Set"のコールで規定のポジション(姿勢)をとって1秒以上静止し(ここで動くと反則です)、次の決められたコールで飛び出すわけです。
で、その"Set"のコールに反応しての動き。『一糸乱れず』なんてものではなく、動く距離といい、角度といい、まるでひとつの生き物のように思えるのです。これ、臨時編成のティームですよ。
この時、アメリカ人に対する、『バラバラで適当』というイメージは完全に壊れ去り、尊敬の念さえ抱きました。
試合後のパーティーは、フライドチキン(もも1本丸ごと)にグリーンピースにポテト、バドワイザーにコーラという、いかにもアメリカなパーティーでしたが、そこで見る彼らは、どう見ても『ひとつの生き物』ではなく、見事なまでに『バラバラで適当』だったのが面白かったですね。
帰る時、動き始めたバスに向かって、全員で声を揃えて「マタネ」と言ってくれた事を、今でもハッキリと憶えています。
昔読んだ血液型の本のO型のところに、普段は仲が悪かったりライバル意識を持っていても、共通の目標を見つけると一致団結して物事にあたる、とありました。その本には、アメリカ人は大半がO型であるとも書いてありました。それを思い出して、何かスゴく納得しましたね。
アメリカがスポーツや戦争に強いのは、そういう国民性のためなのだろうな、ってね。 (追記に続きの血液型の話があります)
そんなアメリカを象徴しているのがNFLなのですが、NFLは最近急増しているヒスパニック系の移民(彼らはサッカーしか知らないわけです)のために、NFLの面白さを知らせるキャンペーンを始めました。そういう戦略を見るにつけ、『世界で最も成功したスポーツビジネス』の座をNFLが維持し続けるのは間違いないだろうと思うのです。
こんな話を延々とかいていたら、フットボールをやりたくなってきましたね。まぁ、この歳になって身体が動くかどうか・・・でも、ネイヴィーティームの最高齢者は56歳だとQBがパーティーの時に言っていましたから、身体さえ作っていればできるのかもしれません。
てなわけで、今回の画像はコレ!!

アイシールド32 ってとこですかね。
この装備を身に付けたのは何年ぶりでしょう。
まぁ、体型が変わっていない事だけは確認できましたけどね・・・・
では、また。
Ciao. Arrivederci!! 続きを読む
Super Bowl XLIも終りました。
雨の中の試合で、プレイヤーも観客も大変だったようですが、ベアーズの守備力をコルツの攻撃力が上回ったという結果になりましたね。
今回は、アメフトを通してspockが見た、アメリカとアメリカ人の話です。
スーパーボウルを世界最大のスポーツイヴェントだと言うと、異を唱える人もいるだろうけれど、1日で動く、カネ・モノ・ヒトを考えると、あながち間違いではないと思います。
この1試合だけで、NFLに入る放送権料はいくらになるんでしょうね。世界中の他のスポーツが束になっても敵わない額である事は間違いないようです。
ただ、NFLがスゴいと思うのは、それだけの放送権料を動かしていながら、TVが観客動員数を減らさない為のルールをきちんと作っている事なんです。『ブラックアウト』なんかは、その最も解りやすい例でしょう。
ブラックアウトというのは、ゲーム開始の72時間前までに、あるゲームのティケットが完売しなかった場合、出場ティームのフランチャイズ地区及び75マイル圏内のホーム地区では、そのゲームのTV中継が行われず、他の地区のゲームが放送されるわけです。
『地元ではファンにスタジアムに来てもらう事が最優先事項』という、NFLのポリシーに則ったものになっているのです。
このやり方をそのまま持って来るのは無理だとしても、観客動員数や視聴率の低下に対して、何の打開策も持たないでいる日本のプロ野球やサッカーは、少しは参考にして考えたらいいと思うのです。
スーパーボウルを生で観るというのは不可能かもしれませんが、NFLのゲームを一度観てみたいですね。インベスコ・フィールド・アト・マイルハイ(デンヴァー)に行って、ブロンコスのゲームを観てみたいとは思っているのですがね・・・・
ところで、最近、NHLに日本人プレイヤーが登場したので、アメリカの4大スポーツで、日本人がプレイした事がないのはNFLだけになりました。でも、NFLに日本人プレイヤーが登場するのは、ズ〜ッと先のことだろうと思います。
運動能力や体格の事なら、ポジションによっては日本人でも通用するプレイヤーは出てくると思います。問題は他にあるのです。
アメフトの競技としての性格上、日本のアマチュアティームでも、プレイブックには、専門用語・特殊用語の羅列で、一般人には理解不能でしょう。プレイコールだって、何を言っているのか解らないと思います。
それが、トップレヴェルのプロだったらどうでしょう。ネイティヴ同様の言語力がない限り、通用しないでしょうね。そこが、他のスポーツとの一番大きな違いであり、難しさなのでしょう。
さて、ここまでタイトルに関連した話が出て来ていませんが、ここからですよ。
1984年、ロサンジェルスでオリンピックが開催されました。ド派手な開会式もさる事ながら、一番印象に残ったのは、日本とアメリカの選手団の入場の仕方の違いについてなのです。
お揃いのスーツをキチッと着て、歩幅さえ統一された状態で行進した日本選手団に対し、ユニフォームを着ている事以外、一人一人が全く違う事をしながら入場したアメリカ選手団。
この違いは何なのだろうと考えましたねぇ。
あれ以来、日本人に対しては『一糸乱れぬ団体行動』、アメリカ人に対しては『バラバラで適当な個人的行動』というイメージが、自分の中にできていたように思います。スポーツ以外の事から見ても、そのイメージは間違っていないと・・・・
15年前の7月初め、フットボールのゲームのため、ある場所へ行きました。
普通ならありえない環境の中で、ある種の感動をしながら、サイドラインに立ってゲームを観ていました。
その場所とは、横須賀米軍基地内のフットボール・フィールド。
ウチのティームの関係者以外は全員アメリカ人で、スピーカーから流れるアナウンスは勿論英語、サイドラインのベンチの上には、大きなゲータレイドのタンクが3本(今回のスーパーボウルでも、勝利が決まる直前に、コルツのプレイヤー達がそのタンクを持ち上げて、ヘッドコーチのトニー・ダンジーにドリンクシャワーを浴びせていましたね)。あぁ、アメリカだなぁ、って思いましたね。
4ヵ月前にフットボールを始めたばかりのオレは、その前の週にゲームデヴューしていました。といっても、勝ちの決まったゲームの終盤に、戦略上それ程重要ではないポジションで(一応WRでしたが)出してもらったわけなのですが・・・
相手はネイヴィー(海軍)のティームとはいえ、臨時の寄せ集めティームですから、こっちが勝つとみんな思っていたようです。(実際、前年は勝ったそうですから)
で、オレも、またゲームに出れるなぁ、って思っていたのですよ。
ところが相手は強かった。キックオフ直後からむこうが優勢なのが解りましたから。そのうち、こっちのLBが足を骨折してアンビュランスで運ばれて行き、こりゃダメだというムードができてしまったのですよ。
そんな中、オレがゲームに出る事はないなぁ、と思いながらサイドラインに立ってゲームを観ていたのですが、ふと、ある事に気が付いて、感動しましたねぇ。
そのある事とは、スクリメイジライン上でのプレイヤー達の動きなのです。
そこのところを解説すると、QBの"Ready"のコールでそれぞれの位置に着き、"Set"のコールで規定のポジション(姿勢)をとって1秒以上静止し(ここで動くと反則です)、次の決められたコールで飛び出すわけです。
で、その"Set"のコールに反応しての動き。『一糸乱れず』なんてものではなく、動く距離といい、角度といい、まるでひとつの生き物のように思えるのです。これ、臨時編成のティームですよ。
この時、アメリカ人に対する、『バラバラで適当』というイメージは完全に壊れ去り、尊敬の念さえ抱きました。
試合後のパーティーは、フライドチキン(もも1本丸ごと)にグリーンピースにポテト、バドワイザーにコーラという、いかにもアメリカなパーティーでしたが、そこで見る彼らは、どう見ても『ひとつの生き物』ではなく、見事なまでに『バラバラで適当』だったのが面白かったですね。
帰る時、動き始めたバスに向かって、全員で声を揃えて「マタネ」と言ってくれた事を、今でもハッキリと憶えています。
昔読んだ血液型の本のO型のところに、普段は仲が悪かったりライバル意識を持っていても、共通の目標を見つけると一致団結して物事にあたる、とありました。その本には、アメリカ人は大半がO型であるとも書いてありました。それを思い出して、何かスゴく納得しましたね。
アメリカがスポーツや戦争に強いのは、そういう国民性のためなのだろうな、ってね。 (追記に続きの血液型の話があります)
そんなアメリカを象徴しているのがNFLなのですが、NFLは最近急増しているヒスパニック系の移民(彼らはサッカーしか知らないわけです)のために、NFLの面白さを知らせるキャンペーンを始めました。そういう戦略を見るにつけ、『世界で最も成功したスポーツビジネス』の座をNFLが維持し続けるのは間違いないだろうと思うのです。
こんな話を延々とかいていたら、フットボールをやりたくなってきましたね。まぁ、この歳になって身体が動くかどうか・・・でも、ネイヴィーティームの最高齢者は56歳だとQBがパーティーの時に言っていましたから、身体さえ作っていればできるのかもしれません。
てなわけで、今回の画像はコレ!!

アイシールド32 ってとこですかね。
この装備を身に付けたのは何年ぶりでしょう。
まぁ、体型が変わっていない事だけは確認できましたけどね・・・・
では、また。
Ciao. Arrivederci!! 続きを読む
2007年01月31日
アメフトです。サッカーではなく。
Ciao. spockです。
前回から、画像入りのBlogになったわけですが、PHS(携帯電話より通話の音質がいいという理由で使い続けているのですが)のカメラを使うというのも初めてだったので、手当たり次第、店の中を撮りまくってみました。
その中の1枚が、今回のテーマになったわけです。
ホールのワイン棚の上に、オレの過去から現在に至る『趣味の物』を飾っています。
左の棚は本類。オペラのスコアやスクーバ・ダイヴィングのエンサイクロペディア、12気筒ジャガーのヘインズのマニュアルなどが並んでいます。
そして、右の棚はコレ!!

左のぬいぐるみは、いつも行っていた、サガミ・サイクルセンターの社長さんが餞別にくれた、ジーロ ディターリア(イタリアを一周する、世界最高峰の自転車レース)のマスコットです。これを見て、カワイイと言う人と、全くカワイクナイと言う人とにハッキリ別れるのが不思議です。
で、そのとなりが、見てのとおりアメフトのボールとヘルメットです。ヘルメットはオレが使っていたもので、ボールは、所属していたティームのものを借りているうちに私物化(結果的にはネコババですかね)してしまったものです。
いつだったか、お客さんに「イタリアならサッカーじゃないの?」と言われた事があるのですが、オレはサッカーに対して、シンパシーというものが全くないのですよ。
おそらく、サッカーファンから見れば、アメフトは無駄に複雑な動きをしているように見えるのだろうと思います。逆に、アメフトファンから見れば、サッカーは単純すぎてつまらないのです。
こんな事を書くと、サッカーファンの人に怒られるかもしれないけれど、以前読んだ本に書いてあった、あるアメリカ人の言葉「サッカーの試合を見るのは、塗ったペンキが乾くのを見ているようなもの」というのに、オレは同感です。
ところで、もうすぐスーパーボウルですね。
QBマニング率いるハイパワーオフェンスのインディアナポリス・コルツと、LBアーラッカーを中心とする鉄壁のディフェンスのシカゴ・ベアーズ。レギュラーシーズンスタッツやプレイヤーの変動からみて、ティームの力に大きな差はなさそうですから、どちらが勝つか、予想は難しいでしょうね。
実を言うと、2月5日は、店でパーティーをやろうかと思っていたのです。去年手に入れたプロジェクターと120インチのスクリーンで、スーパーボウルを見ながら騒ぐのもいいかなと。ついでに、オレの誕生日(7日)のパーティーも兼ねて、と思っていたのですよ。
でも、よ〜く考えてみたら、衛星生中継って、朝の8時からやるんですよね。勿論、夜に再放送がありますが、みんなが結果を知っているのに、パーティーで騒ぐというのもいかがなものかと・・・・orz
もし、それでもいいからパーティーをやりたい、という奇特な方がいらっしゃればやりますので、ご連絡下さい。必要なら、イクウィップメント(装備、ヘルメット・ショルダーパッド・その他一式)も2人分ありますよ。
まぁ、5日は今のところ予約が入っていませんから、このまま入らなければ、18時15分からスクリーンに映して観ていると思います。
スーパーボウルを大画面で観たいという方、どうぞいらして下さい。(予約が入った場合はできませんので、電話で確認して下さい)
アメフトについては、一家言持っている方達が、いろいろなところで書いておられるので、普通は書かれないマニアックな話を、何回かに分けて書こうと思っています。
では、また。
Ciao. Arrivederci!!
前回から、画像入りのBlogになったわけですが、PHS(携帯電話より通話の音質がいいという理由で使い続けているのですが)のカメラを使うというのも初めてだったので、手当たり次第、店の中を撮りまくってみました。
その中の1枚が、今回のテーマになったわけです。
ホールのワイン棚の上に、オレの過去から現在に至る『趣味の物』を飾っています。
左の棚は本類。オペラのスコアやスクーバ・ダイヴィングのエンサイクロペディア、12気筒ジャガーのヘインズのマニュアルなどが並んでいます。
そして、右の棚はコレ!!

左のぬいぐるみは、いつも行っていた、サガミ・サイクルセンターの社長さんが餞別にくれた、ジーロ ディターリア(イタリアを一周する、世界最高峰の自転車レース)のマスコットです。これを見て、カワイイと言う人と、全くカワイクナイと言う人とにハッキリ別れるのが不思議です。
で、そのとなりが、見てのとおりアメフトのボールとヘルメットです。ヘルメットはオレが使っていたもので、ボールは、所属していたティームのものを借りているうちに私物化(結果的にはネコババですかね)してしまったものです。
いつだったか、お客さんに「イタリアならサッカーじゃないの?」と言われた事があるのですが、オレはサッカーに対して、シンパシーというものが全くないのですよ。
おそらく、サッカーファンから見れば、アメフトは無駄に複雑な動きをしているように見えるのだろうと思います。逆に、アメフトファンから見れば、サッカーは単純すぎてつまらないのです。
こんな事を書くと、サッカーファンの人に怒られるかもしれないけれど、以前読んだ本に書いてあった、あるアメリカ人の言葉「サッカーの試合を見るのは、塗ったペンキが乾くのを見ているようなもの」というのに、オレは同感です。
ところで、もうすぐスーパーボウルですね。
QBマニング率いるハイパワーオフェンスのインディアナポリス・コルツと、LBアーラッカーを中心とする鉄壁のディフェンスのシカゴ・ベアーズ。レギュラーシーズンスタッツやプレイヤーの変動からみて、ティームの力に大きな差はなさそうですから、どちらが勝つか、予想は難しいでしょうね。
実を言うと、2月5日は、店でパーティーをやろうかと思っていたのです。去年手に入れたプロジェクターと120インチのスクリーンで、スーパーボウルを見ながら騒ぐのもいいかなと。ついでに、オレの誕生日(7日)のパーティーも兼ねて、と思っていたのですよ。
でも、よ〜く考えてみたら、衛星生中継って、朝の8時からやるんですよね。勿論、夜に再放送がありますが、みんなが結果を知っているのに、パーティーで騒ぐというのもいかがなものかと・・・・orz
もし、それでもいいからパーティーをやりたい、という奇特な方がいらっしゃればやりますので、ご連絡下さい。必要なら、イクウィップメント(装備、ヘルメット・ショルダーパッド・その他一式)も2人分ありますよ。
まぁ、5日は今のところ予約が入っていませんから、このまま入らなければ、18時15分からスクリーンに映して観ていると思います。
スーパーボウルを大画面で観たいという方、どうぞいらして下さい。(予約が入った場合はできませんので、電話で確認して下さい)
アメフトについては、一家言持っている方達が、いろいろなところで書いておられるので、普通は書かれないマニアックな話を、何回かに分けて書こうと思っています。
では、また。
Ciao. Arrivederci!!