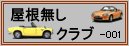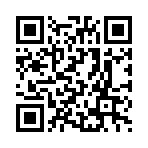スポンサーリンク
この広告は一定期間(1ヶ月以上)更新のないブログに表示されます。
ブログ記事の情報が古い場合がありますのでご注意下さい。
(ブログオーナーが新しい記事を投稿すると非表示になります。)
ブログ記事の情報が古い場合がありますのでご注意下さい。
(ブログオーナーが新しい記事を投稿すると非表示になります。)
2013年02月15日
北イタリアのパスタ2種
Ciao. spockです。
先週の終わりから、右手人差し指の第一関節のあたりが腫れて、指が曲げられない状態になっていました。
なぜそうなったのか、原因が全く分からないのだけれど、連休明けの火曜日、近所のクリニックで診てもらったら、今はどうしようもないので、薬を飲んでしばらく様子を見るように、と言われた。
で、2日後に行ったら、膿を出しましょうと言われて、麻酔を打って手術・・・・でも、30分で麻酔が切れたので、ランチの営業に影響がなかったのがありがたかったですね。
オレは左利きなので、仕事をする上では特に影響はありませんが、実は困った事になっているんです。
24日にヴァイオリンの発表会があるので、本来なら今が一番練習しなければならない時なんですが、弓が握れないので、全然練習できない・・・・
17日には、ピアノと合わせて先生に見てもらう事になっているのだけれど、それまでに間に合うか。
まぁね、トラブルというのは最悪のタイミングでやって来るものだ、という事を、改めて思い知らされたわけなんですけどね。
先日、いつもカウンターに来て下さるお客さんがみえたのですが、いつものように生ハムとワインをオーダーした後、パスタを何にするかしばらく考えてから、その時に仕込んでいたトマトソースを見て、それを使ったパスタが食べたいと言われた。
で、いくつかソースを考えたのだけれど、シンプルなものがいいとの事なので、スパゲッティ アッラ ナポレターナ Spaghetti alla napoletana. を作る事にしました。
前回のブログでも書いたけれど、南イタリアの料理(南イタリアの地名のついた料理)が北イタリアで作られる場合は、北イタリアの人達が南イタリアのイメージで作った料理、と考えた方がいいのですが、この『ナポリ風スパゲッティ』も、その代表例と言っていいでしょうね。
北イタリアのナポレターナはコレです。

ナポリに限らず、南イタリアを代表するパスタと言ってもいい、トマトソースのスパゲッティ Spaghetti al pomodoro. は、中世から食べられていたパスタとして有名ですが、トマトとオリーヴオイルとニンニクで作った、シンプルそのもののソースとスパゲッティをあわせた、基本中の基本、とも言えるパスタです。
中世のナポリの街角では、このスパゲッティを作って売っていて、当時はまだ食事用のフォークがなかったので、みんな手づかみで食べていたそうです。
(当時は、先が三叉になった調理用のフォークしかなく、後に、先が4つに分かれた食事用のフォークが考案された事で、パスタを食卓で食べる事ができるようになったそうです。)
そのトマトソース作り方を簡単に言うと、こんなふうになります。
オリーヴオイルに潰したニンニクを入れて弱火にかけ、香りをオイルに移したら、ニンニクを取り出し、そこへ軽く潰したトマトを入れてひと煮立ちさせ、塩で味を調える。
好みや、使う料理によって、バジリコやオリガノで香りをつける。
(ニンニクと一緒にトウガラシを入れて辛味をつけてやると、アッラッビアータになります。)
極めてシンプルなソースですが、シンプルだからこそ、毎日食べても飽きないのだと思います。
それに比べると、北イタリアのナポレターナは、もう少し手間のかかったものになります。
まず、トマトソース自体が全く違うのです。
ニンニクだけしか使わない南イタリアと違って、タマネギを使うんです。
作る人によって違いはありますが、ウチのトマトソースの作り方を、順を追って書いてみましょう。
まず、鍋にオイルを入れ、ニンニクのみじん切りを軽く炒め、スライスしたタマネギとバジリコを加えてじっくり炒め、甘味を出します。

生のバジリコがある時は生を使いますが、今の時期はないので、乾燥のものを使っています。
そこへ、潰したトマトを加え、香味野菜と香辛料を入れて、しばらく煮込みます。

濃度が丁度いい状態まで煮たら、香味野菜と香辛料を取り出し、荒い網で漉し、さらに裏漉しします。

すると、こんなサラサラのトマトソースになります。

これが北イタリアのトマトソースです。
北と南では根本的なソースからして違うのですから、出来上がる料理も違ってくることがお解かりでしょう。
さて、では、このソースを使って、北イタリア風ナポレターナを作ってみましょう。
まず、フライパンにバターとトウガラシを入れ、火にかけて少し焦がし、そこへトマトソースを加えます。

ここへウースターソースを加えて、味を調えます。(必要なら、塩も加えます)
オレが習った本来の方法では、リーペリンのウースターソースとタバスコで味付けするのですが、オレはタバスコを好まないので、バターを焦がす時にトウガラシを入れる事で辛味をつけています。
パルミジャーノ レッジャーノをタップリと加えます。

茹で上がったスパゲッティを入れて合わせ、皿に盛って、パルミジャーノ レッジャーノをふります。

オレは、トマトソースのスパゲッティが大好きですが、この北イタリアのナポレターナも大好きです。
スパゲッティ ナポレターナ、というと、喫茶店出てくる『スパゲッティ ナポリタン』を思い浮かべる人も多いと思いますが、どこかあの味を連想させるものがあるんですよ。
『スパゲッティ ナポリタン』は、シナモンスティックでかき回して飲む『カプチーノ』と共に、日本発の『似非イタリアン』の双璧だと思いますが(実際にイタリア人に食べさせてみたら、大喜びで食べていたし)、スパゲッティ ナポリタンを考えた人は、ひょっとしたら、北イタリアのナポレターナを知っていたんじゃないかな、って思ったりもします。(実際は、単にトマトケチャップを使っただけなんでしょうけど)
そういう理由からも、北イタリアのスパゲッティ ナポレターナは、日本人好みの味なんだろうと思います。
もともとがシンプルなソースですから、何か具材を加える事も可能で、ゆでた野菜をいれてもいいですね。
そういえば、オレがこのスパゲッティを教わった『ベルゲン』の安田さんは、体調が良くない時に、このスパゲッティを作らせて、すりおろしたニンニクを混ぜて食べていましたが、まぁニオイはともかく、確かに効きそうではありましたね。
さて、話は最初に戻って、カウンターに来られたお客さんから、もう一品、ポルチーニを使ったパスタを作ってほしいと言われた。
ちょうど、乾燥ポルチーニを戻したものがあったので、それを使って何を作ろうかと思った時、思い出した料理がありました。
フォイアデのベルガモ風 Foiade alla bergamasca. です。
フォイアデというのは、幅が3cmくらいの幅広パスタで(この時は急だったので、フェットゥッチーネで代用しましたが)、それを牛乳でゆでて作るのが特徴です。
パスタを牛乳でゆでて作るのは、オレが知っている限りでは、有名なリストランテ ジャンニーノ Giannino のスペシャルで、ハムを使ったソースと合わせる、ホウレン草入りタリアテッレのジャンニーノ風 Tagliatelle verdi alla Giannino と、このフォイアデのベルガモ風くらいしかありませんが、そういう意味でも珍しい料理だと言っていいでしょうね。
ちなみに、ウチでフォイアデを作ったのは、オープン以来初めての事です。
その作り方は、バターでニンニクの小片とポルチーニを炒め、白ワインを加え、アルコールを飛ばします。

フォイアデは、塩を入れた牛乳でゆでます。

硬めにゆでたフォイアデをポルチーニと合わせ、ゆでるのに使った牛乳を加えて煮込み、生クリームとパルミジャーノ レッジャーノを入れて仕上げ、皿に盛ってパルミジャーノ レッジャーノをふります。

使う材料といい、コッテリとした味といい、これぞ北イタリアのパスタ、という感じですね。
特に寒い時期に食べると、寒い地方の料理だという事が実感できますね。
今回紹介した2種類のパスタは、日本ではあまり知られていないと思いますが、北イタリアのパスタとして、実に特徴的ですね。
でも、日本人に好まれるパスタだと思います。
ぜひ、一度食べてみて下さい。
コースに組み込む事もできますが、とりあえずパスタだけ食べたいという場合は、夜、カウンターへ来て頂ければ、食べてもらえますよ。
来られる前に、電話で空席状況を確認してから来て下さい。
お待ちしております。
では、また。
Ciao. Arrivederci!!
先週の終わりから、右手人差し指の第一関節のあたりが腫れて、指が曲げられない状態になっていました。
なぜそうなったのか、原因が全く分からないのだけれど、連休明けの火曜日、近所のクリニックで診てもらったら、今はどうしようもないので、薬を飲んでしばらく様子を見るように、と言われた。
で、2日後に行ったら、膿を出しましょうと言われて、麻酔を打って手術・・・・でも、30分で麻酔が切れたので、ランチの営業に影響がなかったのがありがたかったですね。
オレは左利きなので、仕事をする上では特に影響はありませんが、実は困った事になっているんです。
24日にヴァイオリンの発表会があるので、本来なら今が一番練習しなければならない時なんですが、弓が握れないので、全然練習できない・・・・
17日には、ピアノと合わせて先生に見てもらう事になっているのだけれど、それまでに間に合うか。
まぁね、トラブルというのは最悪のタイミングでやって来るものだ、という事を、改めて思い知らされたわけなんですけどね。
先日、いつもカウンターに来て下さるお客さんがみえたのですが、いつものように生ハムとワインをオーダーした後、パスタを何にするかしばらく考えてから、その時に仕込んでいたトマトソースを見て、それを使ったパスタが食べたいと言われた。
で、いくつかソースを考えたのだけれど、シンプルなものがいいとの事なので、スパゲッティ アッラ ナポレターナ Spaghetti alla napoletana. を作る事にしました。
前回のブログでも書いたけれど、南イタリアの料理(南イタリアの地名のついた料理)が北イタリアで作られる場合は、北イタリアの人達が南イタリアのイメージで作った料理、と考えた方がいいのですが、この『ナポリ風スパゲッティ』も、その代表例と言っていいでしょうね。
北イタリアのナポレターナはコレです。
ナポリに限らず、南イタリアを代表するパスタと言ってもいい、トマトソースのスパゲッティ Spaghetti al pomodoro. は、中世から食べられていたパスタとして有名ですが、トマトとオリーヴオイルとニンニクで作った、シンプルそのもののソースとスパゲッティをあわせた、基本中の基本、とも言えるパスタです。
中世のナポリの街角では、このスパゲッティを作って売っていて、当時はまだ食事用のフォークがなかったので、みんな手づかみで食べていたそうです。
(当時は、先が三叉になった調理用のフォークしかなく、後に、先が4つに分かれた食事用のフォークが考案された事で、パスタを食卓で食べる事ができるようになったそうです。)
そのトマトソース作り方を簡単に言うと、こんなふうになります。
オリーヴオイルに潰したニンニクを入れて弱火にかけ、香りをオイルに移したら、ニンニクを取り出し、そこへ軽く潰したトマトを入れてひと煮立ちさせ、塩で味を調える。
好みや、使う料理によって、バジリコやオリガノで香りをつける。
(ニンニクと一緒にトウガラシを入れて辛味をつけてやると、アッラッビアータになります。)
極めてシンプルなソースですが、シンプルだからこそ、毎日食べても飽きないのだと思います。
それに比べると、北イタリアのナポレターナは、もう少し手間のかかったものになります。
まず、トマトソース自体が全く違うのです。
ニンニクだけしか使わない南イタリアと違って、タマネギを使うんです。
作る人によって違いはありますが、ウチのトマトソースの作り方を、順を追って書いてみましょう。
まず、鍋にオイルを入れ、ニンニクのみじん切りを軽く炒め、スライスしたタマネギとバジリコを加えてじっくり炒め、甘味を出します。
生のバジリコがある時は生を使いますが、今の時期はないので、乾燥のものを使っています。
そこへ、潰したトマトを加え、香味野菜と香辛料を入れて、しばらく煮込みます。
濃度が丁度いい状態まで煮たら、香味野菜と香辛料を取り出し、荒い網で漉し、さらに裏漉しします。
すると、こんなサラサラのトマトソースになります。
これが北イタリアのトマトソースです。
北と南では根本的なソースからして違うのですから、出来上がる料理も違ってくることがお解かりでしょう。
さて、では、このソースを使って、北イタリア風ナポレターナを作ってみましょう。
まず、フライパンにバターとトウガラシを入れ、火にかけて少し焦がし、そこへトマトソースを加えます。
ここへウースターソースを加えて、味を調えます。(必要なら、塩も加えます)
オレが習った本来の方法では、リーペリンのウースターソースとタバスコで味付けするのですが、オレはタバスコを好まないので、バターを焦がす時にトウガラシを入れる事で辛味をつけています。
パルミジャーノ レッジャーノをタップリと加えます。
茹で上がったスパゲッティを入れて合わせ、皿に盛って、パルミジャーノ レッジャーノをふります。
オレは、トマトソースのスパゲッティが大好きですが、この北イタリアのナポレターナも大好きです。
スパゲッティ ナポレターナ、というと、喫茶店出てくる『スパゲッティ ナポリタン』を思い浮かべる人も多いと思いますが、どこかあの味を連想させるものがあるんですよ。
『スパゲッティ ナポリタン』は、シナモンスティックでかき回して飲む『カプチーノ』と共に、日本発の『似非イタリアン』の双璧だと思いますが(実際にイタリア人に食べさせてみたら、大喜びで食べていたし)、スパゲッティ ナポリタンを考えた人は、ひょっとしたら、北イタリアのナポレターナを知っていたんじゃないかな、って思ったりもします。(実際は、単にトマトケチャップを使っただけなんでしょうけど)
そういう理由からも、北イタリアのスパゲッティ ナポレターナは、日本人好みの味なんだろうと思います。
もともとがシンプルなソースですから、何か具材を加える事も可能で、ゆでた野菜をいれてもいいですね。
そういえば、オレがこのスパゲッティを教わった『ベルゲン』の安田さんは、体調が良くない時に、このスパゲッティを作らせて、すりおろしたニンニクを混ぜて食べていましたが、まぁニオイはともかく、確かに効きそうではありましたね。
さて、話は最初に戻って、カウンターに来られたお客さんから、もう一品、ポルチーニを使ったパスタを作ってほしいと言われた。
ちょうど、乾燥ポルチーニを戻したものがあったので、それを使って何を作ろうかと思った時、思い出した料理がありました。
フォイアデのベルガモ風 Foiade alla bergamasca. です。
フォイアデというのは、幅が3cmくらいの幅広パスタで(この時は急だったので、フェットゥッチーネで代用しましたが)、それを牛乳でゆでて作るのが特徴です。
パスタを牛乳でゆでて作るのは、オレが知っている限りでは、有名なリストランテ ジャンニーノ Giannino のスペシャルで、ハムを使ったソースと合わせる、ホウレン草入りタリアテッレのジャンニーノ風 Tagliatelle verdi alla Giannino と、このフォイアデのベルガモ風くらいしかありませんが、そういう意味でも珍しい料理だと言っていいでしょうね。
ちなみに、ウチでフォイアデを作ったのは、オープン以来初めての事です。
その作り方は、バターでニンニクの小片とポルチーニを炒め、白ワインを加え、アルコールを飛ばします。
フォイアデは、塩を入れた牛乳でゆでます。
硬めにゆでたフォイアデをポルチーニと合わせ、ゆでるのに使った牛乳を加えて煮込み、生クリームとパルミジャーノ レッジャーノを入れて仕上げ、皿に盛ってパルミジャーノ レッジャーノをふります。
使う材料といい、コッテリとした味といい、これぞ北イタリアのパスタ、という感じですね。
特に寒い時期に食べると、寒い地方の料理だという事が実感できますね。
今回紹介した2種類のパスタは、日本ではあまり知られていないと思いますが、北イタリアのパスタとして、実に特徴的ですね。
でも、日本人に好まれるパスタだと思います。
ぜひ、一度食べてみて下さい。
コースに組み込む事もできますが、とりあえずパスタだけ食べたいという場合は、夜、カウンターへ来て頂ければ、食べてもらえますよ。
来られる前に、電話で空席状況を確認してから来て下さい。
お待ちしております。
では、また。
Ciao. Arrivederci!!
2013年02月07日
イタリア料理の本質
Ciao. spockです。
新年を迎えたばかり、と思っていたら、もう2月です。
ほんと、月日の経つのは早いものですねぇ。
このブログも、1月は「お知らせ」を書いただけでしたから、実質的には、今回が今年の1回目という事になりますが、なかなか更新できないのが辛いところです。
中身を軽くすれば、更新頻度は上がるんでしょうけど、1回1回、ぎっしりと中身の詰まったものを書きたいと思っているので、時間がかかるのは仕方がないんですが・・・・
でも、もう少し、更新の頻度を上げる事ができればいいんですけどね。
先日、某ひだっちブロガーと一緒に店に来られた方が、帰り際に、こう言われました。
「シェフのブログを読むと、寿司屋の主人のような怖い人なんじゃないかと思って、一人では来れなかったので、連れてきてもらったんです。」
そういえば、以前ディナーに来てもらったお客さんにも、こんな事を言われた。
「シェフのブログを読んでいたら、この店ではマナーに外れたことをすると、手をピシッと叩かれるんじゃないかと思って、なかなか予約する勇気がなかったのだけれど、実際に来てみたら全然違ったので、もっと早く来ればよかった。」
う~ん、どうもオレは「クソ真面目で怖い人」と思われているらしい・・・・でも実際は、ダジャレと悪ふざけが大好きなオッサンなんですけどねぇ。
食事の後にお客さんと話していて、盛り上がった挙句、食事の時間より長く話をしている事も結構あるのだけれど、そういうノリの良さは、実際に来てもらえれば、すぐに分かる事なんですが・・・・
この前、飲食関係のジャーナリストの方が来られて、その時の事をブログに書かれているのだけれど、その中でオレについて、「優しく、人なつっこい笑顔で」と書かれているところを見て、そういうふうに見てもらえるんだな、と安心した次第なんですけどね。
自分なりに分析するなら、常に緊張感を維持していたい、と考えているオレの場合、その緊張感が表面に出てしまうんじゃないかと思います。
まぁ、そういうところが、人によっては近寄り難いと思われるのかもしれないのですが、それがオレの根本にあるものなのだから、隠しようがないし、仕方がないとしか言えませんね。
でもね、オレのこの性格は、ウチのような店の場合、絶対に必要なものだと思うのです・・・・と言うより、こういう性格だから、コース料理専門の店になった、と言うべきでしょうか。
コースで料理を食べる場合、守らなければならないルールやマナーというものがあり、さらには、料理と料理の間での会話のタイミングとか、他の人と食べるペースを合わせる事とか、常に周りの状況を感じつつ考えながら食事をする事が要求されるわけで、それをきちんとこなすためには、ある種の緊張感が必要不可欠なんです。
「酒を楽しむ事」を目的に構成された日本の『会席料理』と比べても、「食べる事」の比重が大きい西洋料理のコースの場合、しっかりとしたルールが存在する分、そうならざるを得ないわけです。
だから、緊張しながら食事をするなんて真平御免だ、と言う人はコース料理を食べようなんて思わない方がいいんです。
こんな事を書くと、なおさら行き難い店だと思われるかもしれませんが・・・・
でもね、特別な日や、特別な人との食事の時に、いつもより少しだけいい格好をして、少しだけ緊張しながら食事をする事は、人生を楽しむ最高の方法のひとつだとオレは確信しています。
イタリアでは、コースの形できちんと料理を食べるところがリストランテ Ristorante なんですが、この ristorante という単語が、「食事で元気を回復する」という意味の ristorare の現在分詞である事を見ると、イタリアでは古くから、きちんとした食事をする事が活力を取り戻す最良の方法、と考えられていたようですね。
それだからこそ、一度そういう経験をしてほしいと思うわけです。
確かに、初めてコースで料理を食べる時は、どうしたらいいか分からず、戸惑う事もあると思いますが、別に難しく考えることはありません。
「知的なゲーム」だと思って、楽しんでしまえばいいんです。
だから、分からない事は遠慮せずにサーヴィスする人に訊けばいいわけで(そのためにいるんですから)、一応プロであるオレだって、初めて食べる料理で食べ方が分からない時は、素直に訊きます。(もちろん、スマートな訊き方、というのがありますが)
サーヴィスする側から言えば、知ったかぶりして目茶苦茶な食べ方をされるより、食べ方を訊いて正しく食べてもらう方がうれしいですからね。
コースで料理を食べる場合、サーヴィスする人との会話、さらには駆引きが出来るようになると、ずっと楽しいものになります。
もちろんそれには、それなりの経験というか、場数を踏む事が必要ですが、コツとでも言うべき事を知っているのと知らないのとでは、大きな差が出ます。
例えば、料理でもワインでも、「お薦めは?」って訊く人がよくいますが、単に「お薦めは?」と訊けば、その日一番多く仕込んだ(仕入れた)物を薦められるに決まっています。
本当に美味いと思うものを食べたいのであれば、自分の好みを伝えた上で「お薦めは?」と訊けばいいわけで、そういう訊き方ができるお客さんに対しては、サーヴィスする側も「この客はできるな」と思って、気をつけてサーヴィスするものです。
ウチでは、そういう事もできるだけお話しするし、要望があれば、いくらでもお教えしますよ。
以前、初めてヨーロッパへ行くので、予行演習としてウチへ食べに来られたという老夫婦がおられましたが、コースは初めてとお聞きしたので、必要最低限の一通りのマナーをお教えしましたが、ヨーロッパへ行っても、食事で困ることはなかっただろうと思います。
ウチでは一組ごとの貸切になるので、他のお客さんの目を気にする事もありませんから、そういう使い方をしてもらうのもいいと思うし、また、子供にマナーを教える、あるいは、子供と一緒にマナーを憶える、というのもいいと思いますよ。
コースで料理を食べる事を躊躇しておられる方は、ぜひ、最初の一歩を踏み出して、コースの楽しみというものを実感してほしいと思いますね。
お待ちしております。
さて、マクラが長くなりましたが、本題に入りましょうか。
以前からこのブログで、「イタリア料理はシンプルな料理だ」と書いてきましたが、この「シンプルな」という言葉は、単純に「飾り気がない」とか「質素な」という意味ではなく、「突き詰めた結果として、余計なものを削ぎ落として核心だけを濃縮した簡潔さ」という意味で使っているわけです。
オレは、イタリア料理を「最小限の素材の組み合わせで、素材の特徴を最大限に味あわせてくれる料理」だと考えているのですが、それこそがイタリア料理の真髄だと思うのです。
何事においても、物事を突き詰めていくと、どんどんいろいろな要素を取り入れて複雑になる場合と、逆に余計なものを削ぎとって簡潔になる場合がありますが、イタリアは根本的に、余計なものを削ぎ落としていくという気質を持った国だと思います。
同じラテンの血を引く国ながら、お隣のフランスは、逆にどんどん複雑というか豪華になっていく国ですから、その対比が面白いですね。
たとえば、オレの大好きなオペラを見ても、その事が良く解ります。
オペラという「総合芸術」に於いてさえ、人間の声の凄さを聴かせるために、ひたすら余計なものを削ぎ落としていったイタリアオペラと、バレエや大合唱などを加えて『グランドオペラ』という豪華なスペクタクルを作っていったフランスオペラは、全く別の進化をしていったわけです。
また、そのオペラを上演する劇場を見ても、全く地味な外観と、過度に豪華にならない品の良い内装を持ち、オペラを上演するために理想的な大きさと設備を持つミラノのスカラ座 Teatro alla Scala と、豪華この上ない内外装を持ち、社交の場として贅の極みとも言える『階段室』を作ったために、劇場部分が少し手狭になってしまったパリのオペラ座 L'opera de Paris を比べても、考え方の違いが良く表れていると思います。
そういえば以前、日本人として初めてフェッラーリのデザインにも係わったカーデザイナーの内田盾男さんの文章に、こんな事が書かれてました。
デザイン画から立体にするのに、クレイモデルを作るわけですが、イタリア以外の国では、クレイ(粘土)を付けたり削ったりして形を作っていきます。
でもイタリアでは、絶対にクレイを付足す事はせず、ひたすらクレイの塊から形を削り出していくのですが、それだからこそ、あの素晴らしいデザインが生まれるのです。
なるほど、と思いましたね。
イタリアが世界一の「デザイン」の国である事は、誰もが認めるところだと思いますが、イタリア人の、無駄を削ぎ落として突き詰めていく、という気質があるからこそ、あの素晴らしいイタリアのデザインが成り立っているんだと、オレは思います。
そういう国民的気質というものが一番表れるのが『食文化』だと思うのですが、余計なものを削ぎ落として本質を追求したい、という考え方を根本に持っているオレが、食のプロの道へ進もうとした時、イタリア料理を選んだのは当然の事だったのだと思います。
もう3分の1世紀も前の事ですが、オレが調理師学校へ入学してすぐに、学園長の授業というのがあって、約2時間の授業のうち、半分以上は自慢話を聞かされたようなものだったのだけれど、その中でひとつ、今でもハッキリと憶えている話があります。
「フランス人の食に対する貪欲さはすごいもので、たとえばコンソメの色ひとつにしても、カラメルを加えて美しい黄金色を出そうとする。その貪欲さがあるからこそ、フランス料理は世界一と言われるんだ。」
オレはその話を聞いた時、カラメルで色をつけるなんて、なんてウソくさい事をするんだろう、って思ったんです。
オレはイタリア料理がやりたくて調理師学校へ行ったわけですが、当時は、フランス料理こそ世界一、という風潮が料理界を席巻していたわけで、「フランス料理は美的感覚のある人間ほど上手く出来るが、イタリア料理は美的感覚のないヤツの方が上手く出来る」と言ったフランス料理の先生がいましたが、とにかく美しく豪華に飾り付ける事が重要なフランス料理の感覚からすれば、そう思われる事に不思議はなかったのだと思います。
でもやっぱり、オレはフランス料理向きではないんだろうな、って、その頃からオレはすごく実感していたんです。
まぁ、それから30年以上イタリア料理一筋でやってきたわけだけれど、自分の店で自分の思うように料理を作っている今、コンソメに関しては、自分なりに「ウソくさくないもの」・・・・要するに、カラメルや化学調味料のような余計なものを一切使わず、必要最小限の天然の素材だけで、黄金色のコンソメを作れるようになったと思います。(こちらを参照して下さい)
そのために、朝の7:30から夜中の12:00過ぎまで時間をかける事が必要ですが、そこまでして、余計なものをすべて削ぎ落として濃縮されたコンソメを作ろう、という思いが基本にあるからこそ、イタリアっぽい料理ではなく、本当のイタリア料理を作っているんだと自負できるのだと思います。
でも何故か、やたらと飾り立てたイタリア料理が持て囃されている事が、オレには理解できません。
ヘンに飾り立てた「イタリア料理」を見ると、手間をかけるべきところを間違えているんじゃないの、って思ってしまうし、綺麗に飾り立てた料理を作りたいのなら、別にイタリア料理でなくてもいいんじゃないの、って思うんですよね。
ムダを削ぎ落とした本来のイタリア料理は、日本の「わび・さび」の世界にも通ずる、日本人には一番共感できる料理だと思うのですが、日本人の癖ともいえる、日本風にアレンジする、という被害を一番被っている料理でもあると思います。
もちろん、日本風アレンジを全て否定するつもりはないし、そういう日本人の改良(改悪?)癖があるからこそ、本家の中国でさえ作り出せなかった、インスタントラーメンという傑作を作り出せたのだと思うのですが、少なくともイタリア料理においては、余計なことはしないでほしいと、オレは心底思うのです。
ひねくれた見方だと言われるかもしれないけど、値段を上げるために見てくれを良くしているんじゃないか、と思う事があります。
以前、松本へ行った時、昼飯を食べようと行ったイタリア料理店で、店の前に出ていたメニューを見て、思わず、バカじゃねえの、と言ってしまったのですが、そのメニューに並んでいたスパゲッティの値段が、すべて1300円以上だったんですよ。
ナスとトマトのスパゲッティが1400円て、ぼったくり以外の何物でもないし、そんな値段で出す店も店なら、そんな値段で納得する客も客だと思いますね。
パスタ一皿にしても、イタリアには、パスタを美味く食べるために絶対守らなければならないルール、言い替えれば「美学」というものがあるわけですよ。
以前にも書いた事があるけれど、パスタの茹で加減、パスタとソースの兼合い、ソースの量、サーヴィスの仕方、そういった事に必ず必然的な理由があるわけで、それを突き詰めていった結果が、シンプルで飾り気のない料理になったわけです。
そういうシンプルな料理であるパスタで、カネを取ろうとすることが間違いなんです。
もちろん、高い材料(たとえばポルチーニや、特殊なチーズなど)を使えば、当然値段は高くなりますが、ありきたりの材料を使って作ったパスタ料理の一皿は、どう考えても1000円がいいところ。
断言してもいい・・・・特殊な材料を使ったのでもないパスタが一皿1000円を超えていたら、それは、ぼったくっているか、余計なものを加えすぎているか、だと。
さて、そんなシンプルさを身上とするイタリア料理にも、当然の事ながら、手間のかかる料理はあります。
それは多くの場合、北イタリアのプロの作る料理、と言ってもいいのですが、それには、こんな理由があります。
南イタリアでは、気候が温暖で、まわりが海に囲まれているという、食材の宝庫でありますが、そのため、料理は本当にシンプルなものが多いですね。
食材自体が最高なんですから、わざわざ複雑な料理にする必要がないわけで、そんな事をしたら食材がもったいないですね。
そんなわけで、南イタリアでは、家庭の料理であっても、プロが作る料理であっても、料理は極めてシンプルであり、あまり差がないわけです。
それに比べて北イタリアでは、家庭の料理とプロの作る料理との差が大きいですね。
南イタリアに比べて、見た目も含めて、どうしても食材の点で劣る北イタリアでは、プロはその分手間をかけた料理を作るわけです。
もちろん、手間をかけながらも、無駄なものは使わない、という基本はキッチリと押さえていますけどね。
で、今回は、そういう手間をかけた、これぞ北イタリアのリストランテの料理、というのを、作り方も一緒に紹介します。
多様な食材を使い、渾然一体となりながらも、それぞれの食材が自分の存在を主張するあたりが、イタリア的だなぁ、って思いますね。
その料理は、『子牛骨付きロースのヴァッレダオスタ風チーズ焼き』 Costoletta di vitello alla valdostana といいます。

ヴァッレダオスタ Valle d'Aosta というのは、スイス及びフランスとの国境に囲まれた州で、

そういう寒い土地の料理だけあって、カロリーの塊みたいな料理ですが、カロリーの高い料理ほど美味い、という原則で考えるなら、最高に美味い料理だと言ってもいいでしょうね。
では、作る手順を、画像で追っていきましょう。
子牛の骨付きロースは、こんなふうに薄くのばします。

この状態にするまでの下準備は、こちらを見て下さい。
卵をつけて焼いたのが、この状態。下には、バターとサルヴィア(セージ)が敷いてあります。

戻した乾燥ポルチーニをバターで炒め、生クリームと和えたものを載せます。

そこへ生ハムを載せます。

さらに、この地方特産のフォンティーナ

をスライスして載せ、

デミソース(デミグラスソースのずーっと濃いやつ)を少量塗り、

これをオーヴンで焼きます。
焼けたら皿に盛り付け、パルミジャーノ レッジャーノをふりかけ、そこへサルヴィア入りの焦がしバターをかけて完成です。

この焦がしバターをパンにつけて食べても美味いですよ。
ただし、これだけバターやチーズを使う料理ですから、冷めると美味くないんですよ。
だから、熱いうちに食べてもらわなければならないので、食べるのが遅い人には、お薦めしません。
この料理には、鶏のムネ肉を使ったヴァージョン Petto di pollo alla valdostana もありますが、その場合は、チーズをエメンタールに替えます。
そういう決まり事を守って作るからこそ alla valdostana という名前を名乗る事ができるわけで、それを守らないで作った料理は、単なる、それっぽい料理、という事です。
この鶏のチーズ焼きの画像がないかと思って探していたら、画像がある事を思い出しました。
コレです。

実はこれ、『肉・野菜料理辞典』というプロ用の専門書

に載っている画像なんですが、21年前、赤坂の店にいた時に、作り方を書いたものなんです。

この本の中でも、きれいに飾り付けたフランス料理の画像が大半を占めているのですが、その中でこの画像は、異彩を放っています。
プロ用の専門書に自分の料理が載ったなんて、後にも先にもこれ1回だけですが、今となってはいい「記念」です。
さて、今回のブログでは、前半で自分の思った事を、後半では料理について延々と書いてきましたが、すべて本音で書きました。
そういうオレの考え方には、合う人と、合わない人が、ハッキリと分かれるでしょうね。
マーケッティングの本を読めば、お客さんの要望にいかに応えるか、という事がやたらと書かれていますが、いくらお客さんの要望であっても、変えてはいけない事、というものがあるわけですよ。
イタリア料理はシンプルな料理である、という事をオレは守っていきたいし、それが解らない人には、来てもらわなくていいと思っています。
先日、テレビの某番組で、海外の日本料理店を紹介していましたが、ある国の寿司屋では、油で揚げた寿司が大人気だと報じていました。
その地の人達が喜んでいるのなら、それでいいのかもしれないけれど、日本人としては、どう考えてもおかしいとしか思えませんね。
でもね、日本でも、イタリア人が見れば驚くような料理を出している「イタリア料理」の店がたくさんあるんですよ。
オレはあくまでもオリジナルにこだわりたいし、イタリアで作り続けられてきた料理を食べてもらいたいわけです。
日本風にアレンジされたイタリア料理を、全て否定するつもりはないけれど、少なくともオレはやるつもりはないし、そういう料理を求める人は、ウチのお客さんじゃないと思っています。
多くの人に理解されようと思ったら、誰にでも解るところまでレヴェルを下げなければなりません。
でも、オレはそれをしたくない。
オレは、レヴェルを下げて多くの人に来てもらうより、レヴェルを保ったまま、解る人にだけ来てもらえる事を選びます。
まぁ、こんな事を言っているから、流行る店にはならないと思うけど、それがオレの生き方なんだから仕方がないですね。
オレはこれからも、イタリアっぽい料理ではなく、本当のイタリア料理を作り続けていきます。
ただ、本当のイタリア料理を少しでも多くの人に解ってもらいたいという気持ちは、強く持っています。
そのために今後は、今回書いたような、料理を詳しく解説するブログを書いていこうと思っているので、興味のある方は、期待していて下さい。
では、また。
Ciao. Arrivederci!!
新年を迎えたばかり、と思っていたら、もう2月です。
ほんと、月日の経つのは早いものですねぇ。
このブログも、1月は「お知らせ」を書いただけでしたから、実質的には、今回が今年の1回目という事になりますが、なかなか更新できないのが辛いところです。
中身を軽くすれば、更新頻度は上がるんでしょうけど、1回1回、ぎっしりと中身の詰まったものを書きたいと思っているので、時間がかかるのは仕方がないんですが・・・・
でも、もう少し、更新の頻度を上げる事ができればいいんですけどね。
先日、某ひだっちブロガーと一緒に店に来られた方が、帰り際に、こう言われました。
「シェフのブログを読むと、寿司屋の主人のような怖い人なんじゃないかと思って、一人では来れなかったので、連れてきてもらったんです。」
そういえば、以前ディナーに来てもらったお客さんにも、こんな事を言われた。
「シェフのブログを読んでいたら、この店ではマナーに外れたことをすると、手をピシッと叩かれるんじゃないかと思って、なかなか予約する勇気がなかったのだけれど、実際に来てみたら全然違ったので、もっと早く来ればよかった。」
う~ん、どうもオレは「クソ真面目で怖い人」と思われているらしい・・・・でも実際は、ダジャレと悪ふざけが大好きなオッサンなんですけどねぇ。
食事の後にお客さんと話していて、盛り上がった挙句、食事の時間より長く話をしている事も結構あるのだけれど、そういうノリの良さは、実際に来てもらえれば、すぐに分かる事なんですが・・・・
この前、飲食関係のジャーナリストの方が来られて、その時の事をブログに書かれているのだけれど、その中でオレについて、「優しく、人なつっこい笑顔で」と書かれているところを見て、そういうふうに見てもらえるんだな、と安心した次第なんですけどね。
自分なりに分析するなら、常に緊張感を維持していたい、と考えているオレの場合、その緊張感が表面に出てしまうんじゃないかと思います。
まぁ、そういうところが、人によっては近寄り難いと思われるのかもしれないのですが、それがオレの根本にあるものなのだから、隠しようがないし、仕方がないとしか言えませんね。
でもね、オレのこの性格は、ウチのような店の場合、絶対に必要なものだと思うのです・・・・と言うより、こういう性格だから、コース料理専門の店になった、と言うべきでしょうか。
コースで料理を食べる場合、守らなければならないルールやマナーというものがあり、さらには、料理と料理の間での会話のタイミングとか、他の人と食べるペースを合わせる事とか、常に周りの状況を感じつつ考えながら食事をする事が要求されるわけで、それをきちんとこなすためには、ある種の緊張感が必要不可欠なんです。
「酒を楽しむ事」を目的に構成された日本の『会席料理』と比べても、「食べる事」の比重が大きい西洋料理のコースの場合、しっかりとしたルールが存在する分、そうならざるを得ないわけです。
だから、緊張しながら食事をするなんて真平御免だ、と言う人はコース料理を食べようなんて思わない方がいいんです。
こんな事を書くと、なおさら行き難い店だと思われるかもしれませんが・・・・
でもね、特別な日や、特別な人との食事の時に、いつもより少しだけいい格好をして、少しだけ緊張しながら食事をする事は、人生を楽しむ最高の方法のひとつだとオレは確信しています。
イタリアでは、コースの形できちんと料理を食べるところがリストランテ Ristorante なんですが、この ristorante という単語が、「食事で元気を回復する」という意味の ristorare の現在分詞である事を見ると、イタリアでは古くから、きちんとした食事をする事が活力を取り戻す最良の方法、と考えられていたようですね。
それだからこそ、一度そういう経験をしてほしいと思うわけです。
確かに、初めてコースで料理を食べる時は、どうしたらいいか分からず、戸惑う事もあると思いますが、別に難しく考えることはありません。
「知的なゲーム」だと思って、楽しんでしまえばいいんです。
だから、分からない事は遠慮せずにサーヴィスする人に訊けばいいわけで(そのためにいるんですから)、一応プロであるオレだって、初めて食べる料理で食べ方が分からない時は、素直に訊きます。(もちろん、スマートな訊き方、というのがありますが)
サーヴィスする側から言えば、知ったかぶりして目茶苦茶な食べ方をされるより、食べ方を訊いて正しく食べてもらう方がうれしいですからね。
コースで料理を食べる場合、サーヴィスする人との会話、さらには駆引きが出来るようになると、ずっと楽しいものになります。
もちろんそれには、それなりの経験というか、場数を踏む事が必要ですが、コツとでも言うべき事を知っているのと知らないのとでは、大きな差が出ます。
例えば、料理でもワインでも、「お薦めは?」って訊く人がよくいますが、単に「お薦めは?」と訊けば、その日一番多く仕込んだ(仕入れた)物を薦められるに決まっています。
本当に美味いと思うものを食べたいのであれば、自分の好みを伝えた上で「お薦めは?」と訊けばいいわけで、そういう訊き方ができるお客さんに対しては、サーヴィスする側も「この客はできるな」と思って、気をつけてサーヴィスするものです。
ウチでは、そういう事もできるだけお話しするし、要望があれば、いくらでもお教えしますよ。
以前、初めてヨーロッパへ行くので、予行演習としてウチへ食べに来られたという老夫婦がおられましたが、コースは初めてとお聞きしたので、必要最低限の一通りのマナーをお教えしましたが、ヨーロッパへ行っても、食事で困ることはなかっただろうと思います。
ウチでは一組ごとの貸切になるので、他のお客さんの目を気にする事もありませんから、そういう使い方をしてもらうのもいいと思うし、また、子供にマナーを教える、あるいは、子供と一緒にマナーを憶える、というのもいいと思いますよ。
コースで料理を食べる事を躊躇しておられる方は、ぜひ、最初の一歩を踏み出して、コースの楽しみというものを実感してほしいと思いますね。
お待ちしております。
さて、マクラが長くなりましたが、本題に入りましょうか。
以前からこのブログで、「イタリア料理はシンプルな料理だ」と書いてきましたが、この「シンプルな」という言葉は、単純に「飾り気がない」とか「質素な」という意味ではなく、「突き詰めた結果として、余計なものを削ぎ落として核心だけを濃縮した簡潔さ」という意味で使っているわけです。
オレは、イタリア料理を「最小限の素材の組み合わせで、素材の特徴を最大限に味あわせてくれる料理」だと考えているのですが、それこそがイタリア料理の真髄だと思うのです。
何事においても、物事を突き詰めていくと、どんどんいろいろな要素を取り入れて複雑になる場合と、逆に余計なものを削ぎとって簡潔になる場合がありますが、イタリアは根本的に、余計なものを削ぎ落としていくという気質を持った国だと思います。
同じラテンの血を引く国ながら、お隣のフランスは、逆にどんどん複雑というか豪華になっていく国ですから、その対比が面白いですね。
たとえば、オレの大好きなオペラを見ても、その事が良く解ります。
オペラという「総合芸術」に於いてさえ、人間の声の凄さを聴かせるために、ひたすら余計なものを削ぎ落としていったイタリアオペラと、バレエや大合唱などを加えて『グランドオペラ』という豪華なスペクタクルを作っていったフランスオペラは、全く別の進化をしていったわけです。
また、そのオペラを上演する劇場を見ても、全く地味な外観と、過度に豪華にならない品の良い内装を持ち、オペラを上演するために理想的な大きさと設備を持つミラノのスカラ座 Teatro alla Scala と、豪華この上ない内外装を持ち、社交の場として贅の極みとも言える『階段室』を作ったために、劇場部分が少し手狭になってしまったパリのオペラ座 L'opera de Paris を比べても、考え方の違いが良く表れていると思います。
そういえば以前、日本人として初めてフェッラーリのデザインにも係わったカーデザイナーの内田盾男さんの文章に、こんな事が書かれてました。
デザイン画から立体にするのに、クレイモデルを作るわけですが、イタリア以外の国では、クレイ(粘土)を付けたり削ったりして形を作っていきます。
でもイタリアでは、絶対にクレイを付足す事はせず、ひたすらクレイの塊から形を削り出していくのですが、それだからこそ、あの素晴らしいデザインが生まれるのです。
なるほど、と思いましたね。
イタリアが世界一の「デザイン」の国である事は、誰もが認めるところだと思いますが、イタリア人の、無駄を削ぎ落として突き詰めていく、という気質があるからこそ、あの素晴らしいイタリアのデザインが成り立っているんだと、オレは思います。
そういう国民的気質というものが一番表れるのが『食文化』だと思うのですが、余計なものを削ぎ落として本質を追求したい、という考え方を根本に持っているオレが、食のプロの道へ進もうとした時、イタリア料理を選んだのは当然の事だったのだと思います。
もう3分の1世紀も前の事ですが、オレが調理師学校へ入学してすぐに、学園長の授業というのがあって、約2時間の授業のうち、半分以上は自慢話を聞かされたようなものだったのだけれど、その中でひとつ、今でもハッキリと憶えている話があります。
「フランス人の食に対する貪欲さはすごいもので、たとえばコンソメの色ひとつにしても、カラメルを加えて美しい黄金色を出そうとする。その貪欲さがあるからこそ、フランス料理は世界一と言われるんだ。」
オレはその話を聞いた時、カラメルで色をつけるなんて、なんてウソくさい事をするんだろう、って思ったんです。
オレはイタリア料理がやりたくて調理師学校へ行ったわけですが、当時は、フランス料理こそ世界一、という風潮が料理界を席巻していたわけで、「フランス料理は美的感覚のある人間ほど上手く出来るが、イタリア料理は美的感覚のないヤツの方が上手く出来る」と言ったフランス料理の先生がいましたが、とにかく美しく豪華に飾り付ける事が重要なフランス料理の感覚からすれば、そう思われる事に不思議はなかったのだと思います。
でもやっぱり、オレはフランス料理向きではないんだろうな、って、その頃からオレはすごく実感していたんです。
まぁ、それから30年以上イタリア料理一筋でやってきたわけだけれど、自分の店で自分の思うように料理を作っている今、コンソメに関しては、自分なりに「ウソくさくないもの」・・・・要するに、カラメルや化学調味料のような余計なものを一切使わず、必要最小限の天然の素材だけで、黄金色のコンソメを作れるようになったと思います。(こちらを参照して下さい)
そのために、朝の7:30から夜中の12:00過ぎまで時間をかける事が必要ですが、そこまでして、余計なものをすべて削ぎ落として濃縮されたコンソメを作ろう、という思いが基本にあるからこそ、イタリアっぽい料理ではなく、本当のイタリア料理を作っているんだと自負できるのだと思います。
でも何故か、やたらと飾り立てたイタリア料理が持て囃されている事が、オレには理解できません。
ヘンに飾り立てた「イタリア料理」を見ると、手間をかけるべきところを間違えているんじゃないの、って思ってしまうし、綺麗に飾り立てた料理を作りたいのなら、別にイタリア料理でなくてもいいんじゃないの、って思うんですよね。
ムダを削ぎ落とした本来のイタリア料理は、日本の「わび・さび」の世界にも通ずる、日本人には一番共感できる料理だと思うのですが、日本人の癖ともいえる、日本風にアレンジする、という被害を一番被っている料理でもあると思います。
もちろん、日本風アレンジを全て否定するつもりはないし、そういう日本人の改良(改悪?)癖があるからこそ、本家の中国でさえ作り出せなかった、インスタントラーメンという傑作を作り出せたのだと思うのですが、少なくともイタリア料理においては、余計なことはしないでほしいと、オレは心底思うのです。
ひねくれた見方だと言われるかもしれないけど、値段を上げるために見てくれを良くしているんじゃないか、と思う事があります。
以前、松本へ行った時、昼飯を食べようと行ったイタリア料理店で、店の前に出ていたメニューを見て、思わず、バカじゃねえの、と言ってしまったのですが、そのメニューに並んでいたスパゲッティの値段が、すべて1300円以上だったんですよ。
ナスとトマトのスパゲッティが1400円て、ぼったくり以外の何物でもないし、そんな値段で出す店も店なら、そんな値段で納得する客も客だと思いますね。
パスタ一皿にしても、イタリアには、パスタを美味く食べるために絶対守らなければならないルール、言い替えれば「美学」というものがあるわけですよ。
以前にも書いた事があるけれど、パスタの茹で加減、パスタとソースの兼合い、ソースの量、サーヴィスの仕方、そういった事に必ず必然的な理由があるわけで、それを突き詰めていった結果が、シンプルで飾り気のない料理になったわけです。
そういうシンプルな料理であるパスタで、カネを取ろうとすることが間違いなんです。
もちろん、高い材料(たとえばポルチーニや、特殊なチーズなど)を使えば、当然値段は高くなりますが、ありきたりの材料を使って作ったパスタ料理の一皿は、どう考えても1000円がいいところ。
断言してもいい・・・・特殊な材料を使ったのでもないパスタが一皿1000円を超えていたら、それは、ぼったくっているか、余計なものを加えすぎているか、だと。
さて、そんなシンプルさを身上とするイタリア料理にも、当然の事ながら、手間のかかる料理はあります。
それは多くの場合、北イタリアのプロの作る料理、と言ってもいいのですが、それには、こんな理由があります。
南イタリアでは、気候が温暖で、まわりが海に囲まれているという、食材の宝庫でありますが、そのため、料理は本当にシンプルなものが多いですね。
食材自体が最高なんですから、わざわざ複雑な料理にする必要がないわけで、そんな事をしたら食材がもったいないですね。
そんなわけで、南イタリアでは、家庭の料理であっても、プロが作る料理であっても、料理は極めてシンプルであり、あまり差がないわけです。
それに比べて北イタリアでは、家庭の料理とプロの作る料理との差が大きいですね。
南イタリアに比べて、見た目も含めて、どうしても食材の点で劣る北イタリアでは、プロはその分手間をかけた料理を作るわけです。
もちろん、手間をかけながらも、無駄なものは使わない、という基本はキッチリと押さえていますけどね。
で、今回は、そういう手間をかけた、これぞ北イタリアのリストランテの料理、というのを、作り方も一緒に紹介します。
多様な食材を使い、渾然一体となりながらも、それぞれの食材が自分の存在を主張するあたりが、イタリア的だなぁ、って思いますね。
その料理は、『子牛骨付きロースのヴァッレダオスタ風チーズ焼き』 Costoletta di vitello alla valdostana といいます。
ヴァッレダオスタ Valle d'Aosta というのは、スイス及びフランスとの国境に囲まれた州で、

そういう寒い土地の料理だけあって、カロリーの塊みたいな料理ですが、カロリーの高い料理ほど美味い、という原則で考えるなら、最高に美味い料理だと言ってもいいでしょうね。
では、作る手順を、画像で追っていきましょう。
子牛の骨付きロースは、こんなふうに薄くのばします。

この状態にするまでの下準備は、こちらを見て下さい。
卵をつけて焼いたのが、この状態。下には、バターとサルヴィア(セージ)が敷いてあります。
戻した乾燥ポルチーニをバターで炒め、生クリームと和えたものを載せます。
そこへ生ハムを載せます。
さらに、この地方特産のフォンティーナ
をスライスして載せ、
デミソース(デミグラスソースのずーっと濃いやつ)を少量塗り、
これをオーヴンで焼きます。
焼けたら皿に盛り付け、パルミジャーノ レッジャーノをふりかけ、そこへサルヴィア入りの焦がしバターをかけて完成です。
この焦がしバターをパンにつけて食べても美味いですよ。
ただし、これだけバターやチーズを使う料理ですから、冷めると美味くないんですよ。
だから、熱いうちに食べてもらわなければならないので、食べるのが遅い人には、お薦めしません。
この料理には、鶏のムネ肉を使ったヴァージョン Petto di pollo alla valdostana もありますが、その場合は、チーズをエメンタールに替えます。
そういう決まり事を守って作るからこそ alla valdostana という名前を名乗る事ができるわけで、それを守らないで作った料理は、単なる、それっぽい料理、という事です。
この鶏のチーズ焼きの画像がないかと思って探していたら、画像がある事を思い出しました。
コレです。
実はこれ、『肉・野菜料理辞典』というプロ用の専門書
に載っている画像なんですが、21年前、赤坂の店にいた時に、作り方を書いたものなんです。
この本の中でも、きれいに飾り付けたフランス料理の画像が大半を占めているのですが、その中でこの画像は、異彩を放っています。
プロ用の専門書に自分の料理が載ったなんて、後にも先にもこれ1回だけですが、今となってはいい「記念」です。
さて、今回のブログでは、前半で自分の思った事を、後半では料理について延々と書いてきましたが、すべて本音で書きました。
そういうオレの考え方には、合う人と、合わない人が、ハッキリと分かれるでしょうね。
マーケッティングの本を読めば、お客さんの要望にいかに応えるか、という事がやたらと書かれていますが、いくらお客さんの要望であっても、変えてはいけない事、というものがあるわけですよ。
イタリア料理はシンプルな料理である、という事をオレは守っていきたいし、それが解らない人には、来てもらわなくていいと思っています。
先日、テレビの某番組で、海外の日本料理店を紹介していましたが、ある国の寿司屋では、油で揚げた寿司が大人気だと報じていました。
その地の人達が喜んでいるのなら、それでいいのかもしれないけれど、日本人としては、どう考えてもおかしいとしか思えませんね。
でもね、日本でも、イタリア人が見れば驚くような料理を出している「イタリア料理」の店がたくさんあるんですよ。
オレはあくまでもオリジナルにこだわりたいし、イタリアで作り続けられてきた料理を食べてもらいたいわけです。
日本風にアレンジされたイタリア料理を、全て否定するつもりはないけれど、少なくともオレはやるつもりはないし、そういう料理を求める人は、ウチのお客さんじゃないと思っています。
多くの人に理解されようと思ったら、誰にでも解るところまでレヴェルを下げなければなりません。
でも、オレはそれをしたくない。
オレは、レヴェルを下げて多くの人に来てもらうより、レヴェルを保ったまま、解る人にだけ来てもらえる事を選びます。
まぁ、こんな事を言っているから、流行る店にはならないと思うけど、それがオレの生き方なんだから仕方がないですね。
オレはこれからも、イタリアっぽい料理ではなく、本当のイタリア料理を作り続けていきます。
ただ、本当のイタリア料理を少しでも多くの人に解ってもらいたいという気持ちは、強く持っています。
そのために今後は、今回書いたような、料理を詳しく解説するブログを書いていこうと思っているので、興味のある方は、期待していて下さい。
では、また。
Ciao. Arrivederci!!