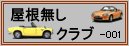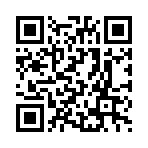スポンサーリンク
この広告は一定期間(1ヶ月以上)更新のないブログに表示されます。
ブログ記事の情報が古い場合がありますのでご注意下さい。
(ブログオーナーが新しい記事を投稿すると非表示になります。)
ブログ記事の情報が古い場合がありますのでご注意下さい。
(ブログオーナーが新しい記事を投稿すると非表示になります。)
2010年12月30日
今年も終わりかぁ・・・・
Ciao. spockです。
クリスマスが終わると、大晦日まではアッと言う間・・・・速いものです。
今年も1年、ありがとうございました。
まったく明るい話が聞こえてこないこの時期に、何とかつぶれる事もなくやって来れたのも、ご来店頂いたお客様のおかげです。
来年も、よろしくお願いします。
例によって、年賀状はまったく手付かずで、さらに悪い事には、住所録の入ったパソコンが起動不能になり・・・・どうなるやら分かりません。
さて、LA FENICE の年内の営業は、29日で終了しました。
新年の営業は、ランチは5日から、ディナーは予約を頂いた日から始めます。
以上、お知らせでした。
って、これで終わっては意味がない。
かといって、あまり長くなるのもどうかと思うので、クリスマスの事を書きます。
今年のクリスマスは、例年になく静かでした。
とは言っても、予約を受けた数が少なかっただけで、お断りした件数が多かった、という事なんですが。
ウチがクリスマスの広告を出さなくなってから、もう3年になります。
それ以前は、できるだけ多くの予約を受けるようにしていたのですが・・・・この仕事を始めてから、クリスマスとはそういうもの、という概念の中で生きてきましたからね・・・・でも、それはウチのやり方じゃない、って思うようになったんですよね。
ウチは普段、一組ごとの貸切りでやっているのに、クリスマスだけ違うのはおかしい・・・・しかも、いつもより高い値段の料理を出すのに。
で、クリスマスも普段と同じように、お客さんが重ならないように予約を受けることにしたわけです。
去年、一昨年と、早い時間から遅い時間まで、上手く時間がずれて予約が入ったので、わりと多くの予約を受ける事ができたのですが、今年は何故か、時間的制約の多いお客さんばかりだったようで、同じような時間に集中したため、お断りせざるをえなかったわけです。
でも、今年来て頂いたお客さんには、本当にゆっくりと、クリスマスのディナーを楽しんで頂けたと思います。
その内容を紹介しておきましょう。
まず、薪ストーヴの火と、

庭のイルミネーションを楽しんで頂き、

前菜は、生ハムメロンとキーウィ、コッパ、ミラノ風サラミ、ソプレッサータの盛り合わせ。

次は、特製コンソメ。
今回も16時間かけてとった、超濃厚コンソメです。

次は、手作りマカロニのソーセージ入りトマトソース。
一本一本手作りのマカロニに、生ソーセージとトマトのソースを合わせました。

魚料理は、オマール海老と魚介類のワイン蒸し。
シンプルそのものの料理ですが、それ故に奥が深い料理だと思います。

この、ワイン蒸しのスープには、海老と魚介類の味が凝縮されていて、本当に美味いですよ。
鶏料理は、ヴァッレダオスタ風のチーズ焼き。
鶏肉に卵をつけて焼いた上に、炒めてクリームで和えたポルチーニをのせ、生ハムとチーズをのせて焼き、さらにパルミジャーノ レッジャーノをふり、セージ入りの焦がしバターをかけてあります。

この料理には、子牛ヴァージョンもありますが、使うチーズが違うのですよ。
名前に地名の付いた料理は、そういう決まりを守ってこそ、その名前を名乗れるわけです。
肉料理は、シンプルに、子牛のミラノ風カツレツです。
子牛の中でも一番高級な、骨付きロースを使っています。

イタリアで最高の格式を持ち、またミラノ料理の最高峰でもある リストランテ サヴィーニ(Savini)のやり方をそのままに作っていますから、正真正銘の『ミラノ風カツレツ』です。
デザートは、5種類を盛り合わせにしました。

ティラミス、パンナコッタ、カボチャのプリン、ブラッディオレンジのジェラート、アーモンドとカラメルのジェラートです。
ティラミスは、ビスキュイから焼いて組み立てた、完全手作りのティラミスで、パンナコッタは、これ以上濃く作る事のできない、超濃厚パンナコッタです。
カボチャのプリンは、なめらかさよりも、カボチャの味をしっかりと感じられる、ずっしりとしたプリンです。
ジェラート2種は、ウチの定番ですね。
そこに、エスプレッソがつきます。
こうやって画像を並べると、あいかわらず見た目の素っ気無さでは天下一品ですね。
そもそもイタリア料理はシンプルさが身上の料理であり、それだから、飽きずに食べる事ができるわけです。
余計な飾りつけは邪魔なだけ・・・・見た目が重要なら、はなからイタリア料理を選ぶべきではないんですよ。
料理に限らず、シンプルなものをきちんと作る事が一番難しい、という事を分かっておられる方なら、シンプルさにこだわる、オレの気持ちも分かってもらえると思いますけどね。
来年も、こういうスタンスを変えることなく、古典的なイタリア料理を作り続けていきます。
話は急に変わりますが、昨晩、テノール歌手の水口聡が、高山でのマネージャーを自認する西先生と一緒に立ち寄ってくれました。
来年も、NHKニューイヤー・オペラコンサートに出演するそうです。

1月3日の19:00から、教育テレビで生放送がありますよ。
では、来年もよろしくお願いします。
皆様、良いお年を。
では、また。
Ciao. Arrivederci!!
クリスマスが終わると、大晦日まではアッと言う間・・・・速いものです。
今年も1年、ありがとうございました。
まったく明るい話が聞こえてこないこの時期に、何とかつぶれる事もなくやって来れたのも、ご来店頂いたお客様のおかげです。
来年も、よろしくお願いします。
例によって、年賀状はまったく手付かずで、さらに悪い事には、住所録の入ったパソコンが起動不能になり・・・・どうなるやら分かりません。
さて、LA FENICE の年内の営業は、29日で終了しました。
新年の営業は、ランチは5日から、ディナーは予約を頂いた日から始めます。
以上、お知らせでした。
って、これで終わっては意味がない。
かといって、あまり長くなるのもどうかと思うので、クリスマスの事を書きます。
今年のクリスマスは、例年になく静かでした。
とは言っても、予約を受けた数が少なかっただけで、お断りした件数が多かった、という事なんですが。
ウチがクリスマスの広告を出さなくなってから、もう3年になります。
それ以前は、できるだけ多くの予約を受けるようにしていたのですが・・・・この仕事を始めてから、クリスマスとはそういうもの、という概念の中で生きてきましたからね・・・・でも、それはウチのやり方じゃない、って思うようになったんですよね。
ウチは普段、一組ごとの貸切りでやっているのに、クリスマスだけ違うのはおかしい・・・・しかも、いつもより高い値段の料理を出すのに。
で、クリスマスも普段と同じように、お客さんが重ならないように予約を受けることにしたわけです。
去年、一昨年と、早い時間から遅い時間まで、上手く時間がずれて予約が入ったので、わりと多くの予約を受ける事ができたのですが、今年は何故か、時間的制約の多いお客さんばかりだったようで、同じような時間に集中したため、お断りせざるをえなかったわけです。
でも、今年来て頂いたお客さんには、本当にゆっくりと、クリスマスのディナーを楽しんで頂けたと思います。
その内容を紹介しておきましょう。
まず、薪ストーヴの火と、

庭のイルミネーションを楽しんで頂き、

前菜は、生ハムメロンとキーウィ、コッパ、ミラノ風サラミ、ソプレッサータの盛り合わせ。

次は、特製コンソメ。
今回も16時間かけてとった、超濃厚コンソメです。

次は、手作りマカロニのソーセージ入りトマトソース。
一本一本手作りのマカロニに、生ソーセージとトマトのソースを合わせました。

魚料理は、オマール海老と魚介類のワイン蒸し。
シンプルそのものの料理ですが、それ故に奥が深い料理だと思います。

この、ワイン蒸しのスープには、海老と魚介類の味が凝縮されていて、本当に美味いですよ。
鶏料理は、ヴァッレダオスタ風のチーズ焼き。
鶏肉に卵をつけて焼いた上に、炒めてクリームで和えたポルチーニをのせ、生ハムとチーズをのせて焼き、さらにパルミジャーノ レッジャーノをふり、セージ入りの焦がしバターをかけてあります。

この料理には、子牛ヴァージョンもありますが、使うチーズが違うのですよ。
名前に地名の付いた料理は、そういう決まりを守ってこそ、その名前を名乗れるわけです。
肉料理は、シンプルに、子牛のミラノ風カツレツです。
子牛の中でも一番高級な、骨付きロースを使っています。

イタリアで最高の格式を持ち、またミラノ料理の最高峰でもある リストランテ サヴィーニ(Savini)のやり方をそのままに作っていますから、正真正銘の『ミラノ風カツレツ』です。
デザートは、5種類を盛り合わせにしました。

ティラミス、パンナコッタ、カボチャのプリン、ブラッディオレンジのジェラート、アーモンドとカラメルのジェラートです。
ティラミスは、ビスキュイから焼いて組み立てた、完全手作りのティラミスで、パンナコッタは、これ以上濃く作る事のできない、超濃厚パンナコッタです。
カボチャのプリンは、なめらかさよりも、カボチャの味をしっかりと感じられる、ずっしりとしたプリンです。
ジェラート2種は、ウチの定番ですね。
そこに、エスプレッソがつきます。
こうやって画像を並べると、あいかわらず見た目の素っ気無さでは天下一品ですね。
そもそもイタリア料理はシンプルさが身上の料理であり、それだから、飽きずに食べる事ができるわけです。
余計な飾りつけは邪魔なだけ・・・・見た目が重要なら、はなからイタリア料理を選ぶべきではないんですよ。
料理に限らず、シンプルなものをきちんと作る事が一番難しい、という事を分かっておられる方なら、シンプルさにこだわる、オレの気持ちも分かってもらえると思いますけどね。
来年も、こういうスタンスを変えることなく、古典的なイタリア料理を作り続けていきます。
話は急に変わりますが、昨晩、テノール歌手の水口聡が、高山でのマネージャーを自認する西先生と一緒に立ち寄ってくれました。
来年も、NHKニューイヤー・オペラコンサートに出演するそうです。

1月3日の19:00から、教育テレビで生放送がありますよ。
では、来年もよろしくお願いします。
皆様、良いお年を。
では、また。
Ciao. Arrivederci!!
Posted by spock at
17:26
│Comments(0)
2010年12月29日
演奏会無事終了 後編
Ciao. spockです。
まだ使えるTVを捨てるのはもったいない、と思いながらも、地デジ化の流れには逆らえず・・・・新しいTVが届きました・・・・42インチのプラズマTVです。
届いた日の夜、BSでNFLのゲームをやっていたので、見てみたのですが・・・・いいわぁコレ。
録画機能も付いているので、録画しておいて、ヒマな時に見る事ができますね。
ところでデンヴァー・ブロンコスは、QBティム・ティーボウの先発出場2戦目で、やっと連敗を止める事ができました。
ティーボウはパスだけではなく、自らTDランを決めたり、結構見せてくれます。
絶対的に左利きが不利なアメフトで、左腕一本で頑張っているティーボウを、オレは同じ左利きとして応援しています。
それに、WRロイドの獲得ヤードが1位に返り咲いたのも、少し期待を持たせてくれますね。
第16週の『TOP5キャッチ』にも、ロイドは入ってますよ。
次のゲームが楽しみですねぇ。
さて、前回からの続きです。
2日目の19日は、高山市民文化会館での公演です。
朝、9:20に、3階の講堂へ行くと、もうセッティングが始まっていました。
去年までは、入口から入って左側にオーケストラが並びましたが、今年は正面に並ぶ事になりました。
オーケストラの席を作った後は、照明を合わせ、客席を作っていきます。
前日の神岡で、予想以上にお客さんが来て下さったので、客席は多めに作っておきます。
あれだけのお客さんが来てくれたのは、あのポスターのお陰なんじゃないかという話が、楽団員の間で出ていたのですが、

こういうポスターだったからこそ、行ってみようと思った人が多くなったのではないか、という意見は、案外、的を射ているのかもしれませんね。
次回も、こんな感じのポスターにする方がいいのでしょうね。
前日に一度本番をやっているだけに、ゲネプロは、問題がありそうなところだけやって早めに切り上げたので、食事や着替えの時間が十分にとれました・・・・とは言っても、のんびりとはしていられないのですが。
うどんを食べに行こう、って誘われて、1階のトムさんのところへ行き、うどんで慌しく食事を済ませ、後は着替えです。
何故か、控え室が確保できてなかったので、急遽、男性は倉庫で着替えをする事に・・・・
講堂の前で待機していると、お客さんが次々と講堂へ入っていくのが見えるのですが、客席が一杯になり、急遽席を増やしたとの事・・・・前日に続き満員です。
本当にありがたい事ですが、その分、緊張が高まってきますね。
ソロを弾く、二人の女子高生も、前日と同じく、肩を出したサンタクロースのドレスで待機しています。
後ろから、そーっと近づいて、冷たい手で肩に触ってみたら・・・・なーんて考えていたらセクハラになりますかね。(笑)
全員揃ったところで、この日もオレが最初にホールへ入りました。
客席の間の通路を通ってステージへ向かうのですが、なぜか通路の真ん中に小さな子供がいて、その子をよけながら歩いて、自分の席へ向かいます。
席に着き、客席を見ると、満員の状態で、お客さんの数は、神岡の公演よりかなり多そうです。
指揮者が登場し、演奏が始まります。

1曲目は、前日と同じく『もろびとこぞりて』で始まり、2曲目に、前日は時間の都合で演奏しなかった『神の御子は今宵しも』を演奏しました。
この曲は、テンポもゆっくりだし、旋律の流れも穏やかなので、オレにとってはありがたいですね。
続いて、バッハの2つのヴァイオリンのための協奏曲を演奏し、いよいよ『動物の謝肉祭』です。
前日に比べ、お客さんが多いせいか、ちょっと緊張気味・・・・曲目解説の小淵さんが話している間、頭の中の血流が早くなっている事が分かります。
ちょっとヤバイかな、と思い始めたところで、小淵さんから、リレーでバトンを渡すときのようにマイクが差し出されました。
そのマイクをしっかりと受け取り、自分の席に戻ったところで、ふと思いついて、アドリブで話し始めました。
「マイクを受け取りました私、高山室内合奏団に入団してまだ2ヶ月の見習い団員ですが、そんな見習いが、なぜかナレーターをやる事になりまして・・・・」
案外すらすらと言葉が出てきたのですが、緊張気味だったせいか、自分の声が一番よく響く音域より、少し高めの声を出してしまったようです。
そんな事もあって、少し噛み気味・・・・でも、急に声の高さを変えるわけにはいきませんから、そのまま続けます。
1曲目のナレーションの最後に、指揮者の方に目で合図を送りながら、アドリブでナレーションを付け加えました。
「この行進曲、楽譜にはフランス語で Marche Royale du Lion と書かれていますが、これを現代風に訳すなら・・・・ライオンキングのマーチ、というところでしょうか。」(フランス語の発音が合っていたのか、自信はないですけど)
指揮者の鴨宮さんは、一瞬驚いたようですが、しょうがねえなぁ、みたいな顔をして、ナレーションが終わるのを待ってくれました。
ここまで話をしてしまえば、後は同じ事・・・・もう、こっちのペースで進めるだけです。
ただ、前日に比べ、少し緊張していたのか、4回ほど噛みましたけどね。
無事、演奏は終了し、休憩に入ります。
この日のお客さんには、サプライズのプレゼントがありました・・・・ホールの外で、できたてのポップコーンを配ったのですよ。
以前、株式会社なべしまの社長さんがウチに来られた時、このコンサートの話をしたら、ポップコーンを協賛したい、と言って下さったので、文化会館と交渉した結果、講堂前の廊下にポップコーンの機械を持ち込んで、その場で作ってもらう事になったのです。
キャラメルの甘い香りが漂う中、お客さんがポップコーンの機械の前に列を作っていました。
なべしまさんは、200人分のポップコーンを用意して下さったそうで、社長自ら休憩時間終了後にも作り続けて、演奏会から帰る人にも配って下さったようです。
なべしまさん、ありがとうございました。
(ちなみに、なべしまさんは、各種イヴェントにポップコーンを協賛しているそうで、文化会館の人も見に来て話をされていたようですが、3月の催しにも協賛する事が決まったそうです。)
後半は、管楽器のメンバーによる、バッハの『羊は安らかに草を食み』で始まり、続いて、子供たちも加わって、ベートーヴェンの『歓喜の歌』と『トルコ行進曲』の演奏です。
演奏終了後、子供たちは最後に演奏する『きよしこの夜』まで、客席で待機するのですが、その席が、上手の最前列、ちょうどオレの席のすぐ後ろなんですよ。
これってヤバイよなぁ・・・・オレがごまかしながら弾いているのが、全部見えてしまうもの。
まぁ、そんな状況の中、『ザ・サウンド・オヴ・ミュージック』ハイライツ、ヴィヴァルディの『四季』から『冬』と続きます。
でも、この『四季』という曲、名曲である事は分かっていたけれど、実際に弾いてみると、本当によくできた曲だと実感します。
自分が弾いているのは、単に一音ずつの刻みなんだけれど、それが集まってオーケストラの響きになっていくプロセスを体感すると、曲そのものに対する共感度や理解度が、一気に上がりますね。
ソロは前日と同じく、ドイツから来て下さった村中一夫さんで、やっぱりプロはすごい、と思わせる演奏を聞かせてもらえました。
解説の小淵さんも言ってみえたけど、実際にこういう演奏を見て、ヴァイオリンを習いたいと思い始めた人がいるかもしれませんね。
ヴィオラの人数が少ないので、このソロの時以外は、ヴィオラで参加してもらっているのですが、いきなりサイズの違うヴァイオリンに持ち替えてソロを弾けるんですから、すごいものですね。
実を言うと、オレは村中さんに対して、『孤高の人』的なイメージを持っていたのです。
それは、リハーサルの時の話し方や、休憩時間に一人離れて物思いに耽っておられるところを見たりしたからなんですが、この日の休憩時間に、眼鏡を捜しに控え室に入ってきた村中さんが、眼鏡を忘れてステージに向かった時の事を、ニコニコしながら話してくれたのを見て、オレの勝手な思い込みだったんだなぁ、って思いましたね。
最後は『クリスマス・フェスティヴァル』で、クリスマス気分を盛り上げ、次に、子供たちも加わったオーケストラの伴奏でお客さんが『きよしこの夜』を歌い、プログラムを終了しました。
この日は時間があったので、アンコールに、フォーレの『ラシーヌ雅歌』を演奏しました。
この曲は、技術的には難しくない(オレが初見で7割方弾けたくらいですから)曲ですが、表情を付けるとなると難しい・・・・
最後の音が消え入るように終わり、お客さんからの拍手が聞こえてきた時、やり終えた、という気持ちが湧き上がってきましたね。
オレは、技術的に追いつかないところを結構ごまかして弾いている程度の団員ですけど、そのオレでさえそう感じたのですから、トップの方でバリバリ弾いている人達の感じる充実感は、きっとすごく大きいものなのだろうと思います。
オレも、ごまかす事なく弾けるように頑張らなければ・・・・
今回、オレは末席ながら参加させてもらい、本当にいい経験をさせてもらいました。
と同時に、本当に楽しかった。
高山室内合奏団の団員の方々、手伝って下さった方々、そして来場して下さったお客さんに、御礼申し上げます。
ありがとうございました。
明らかな技術不足のせいで、足を引っ張ってしまったところもあったと思うのですが、ナレーションで少しは挽回できたのではないかと・・・・
次回の公演では、言い訳せずに演奏できるように、最大限の努力をしなければなりませんね。
オレはまた、終わったらすぐに店に帰り、夜の準備・・・・この日の夜は、ウチで打ち上げのパーティーが開かれました。
立食のパーティーでしたが、店は満杯。
音楽の話で盛り上がり、10時過ぎまで、皆さん楽しんでいかれました。
来年は、1月の中旬から、夏のコンサートに向けての練習が始まるし、3月にはヴァイオリンの発表会もあるので、仕事以外は音楽漬け、の日々になりそう・・・・
まぁ、でも、なんやかんや言いながら、好きな事をやるのは楽しいですね。
仕事も含めて、好きな事をできる、という事が、本当に幸せな事なんだと、実感している今日この頃です。
ちなみに、来年の『定期演奏会』は、9月4日に飛騨芸術堂で、クリスマスコンサートは、12月18日に文化会館講堂で行われる事が決まっていますので、是非お出で下さい。
お待ちしております。
19日は何故か写真を撮るのを忘れていたので、今回は画像なしになりました。
では、また。
Ciao. Arrivederci!!
まだ使えるTVを捨てるのはもったいない、と思いながらも、地デジ化の流れには逆らえず・・・・新しいTVが届きました・・・・42インチのプラズマTVです。
届いた日の夜、BSでNFLのゲームをやっていたので、見てみたのですが・・・・いいわぁコレ。
録画機能も付いているので、録画しておいて、ヒマな時に見る事ができますね。
ところでデンヴァー・ブロンコスは、QBティム・ティーボウの先発出場2戦目で、やっと連敗を止める事ができました。
ティーボウはパスだけではなく、自らTDランを決めたり、結構見せてくれます。
絶対的に左利きが不利なアメフトで、左腕一本で頑張っているティーボウを、オレは同じ左利きとして応援しています。
それに、WRロイドの獲得ヤードが1位に返り咲いたのも、少し期待を持たせてくれますね。
第16週の『TOP5キャッチ』にも、ロイドは入ってますよ。
次のゲームが楽しみですねぇ。
さて、前回からの続きです。
2日目の19日は、高山市民文化会館での公演です。
朝、9:20に、3階の講堂へ行くと、もうセッティングが始まっていました。
去年までは、入口から入って左側にオーケストラが並びましたが、今年は正面に並ぶ事になりました。
オーケストラの席を作った後は、照明を合わせ、客席を作っていきます。
前日の神岡で、予想以上にお客さんが来て下さったので、客席は多めに作っておきます。
あれだけのお客さんが来てくれたのは、あのポスターのお陰なんじゃないかという話が、楽団員の間で出ていたのですが、

こういうポスターだったからこそ、行ってみようと思った人が多くなったのではないか、という意見は、案外、的を射ているのかもしれませんね。
次回も、こんな感じのポスターにする方がいいのでしょうね。
前日に一度本番をやっているだけに、ゲネプロは、問題がありそうなところだけやって早めに切り上げたので、食事や着替えの時間が十分にとれました・・・・とは言っても、のんびりとはしていられないのですが。
うどんを食べに行こう、って誘われて、1階のトムさんのところへ行き、うどんで慌しく食事を済ませ、後は着替えです。
何故か、控え室が確保できてなかったので、急遽、男性は倉庫で着替えをする事に・・・・
講堂の前で待機していると、お客さんが次々と講堂へ入っていくのが見えるのですが、客席が一杯になり、急遽席を増やしたとの事・・・・前日に続き満員です。
本当にありがたい事ですが、その分、緊張が高まってきますね。
ソロを弾く、二人の女子高生も、前日と同じく、肩を出したサンタクロースのドレスで待機しています。
後ろから、そーっと近づいて、冷たい手で肩に触ってみたら・・・・なーんて考えていたらセクハラになりますかね。(笑)
全員揃ったところで、この日もオレが最初にホールへ入りました。
客席の間の通路を通ってステージへ向かうのですが、なぜか通路の真ん中に小さな子供がいて、その子をよけながら歩いて、自分の席へ向かいます。
席に着き、客席を見ると、満員の状態で、お客さんの数は、神岡の公演よりかなり多そうです。
指揮者が登場し、演奏が始まります。

1曲目は、前日と同じく『もろびとこぞりて』で始まり、2曲目に、前日は時間の都合で演奏しなかった『神の御子は今宵しも』を演奏しました。
この曲は、テンポもゆっくりだし、旋律の流れも穏やかなので、オレにとってはありがたいですね。
続いて、バッハの2つのヴァイオリンのための協奏曲を演奏し、いよいよ『動物の謝肉祭』です。
前日に比べ、お客さんが多いせいか、ちょっと緊張気味・・・・曲目解説の小淵さんが話している間、頭の中の血流が早くなっている事が分かります。
ちょっとヤバイかな、と思い始めたところで、小淵さんから、リレーでバトンを渡すときのようにマイクが差し出されました。
そのマイクをしっかりと受け取り、自分の席に戻ったところで、ふと思いついて、アドリブで話し始めました。
「マイクを受け取りました私、高山室内合奏団に入団してまだ2ヶ月の見習い団員ですが、そんな見習いが、なぜかナレーターをやる事になりまして・・・・」
案外すらすらと言葉が出てきたのですが、緊張気味だったせいか、自分の声が一番よく響く音域より、少し高めの声を出してしまったようです。
そんな事もあって、少し噛み気味・・・・でも、急に声の高さを変えるわけにはいきませんから、そのまま続けます。
1曲目のナレーションの最後に、指揮者の方に目で合図を送りながら、アドリブでナレーションを付け加えました。
「この行進曲、楽譜にはフランス語で Marche Royale du Lion と書かれていますが、これを現代風に訳すなら・・・・ライオンキングのマーチ、というところでしょうか。」(フランス語の発音が合っていたのか、自信はないですけど)
指揮者の鴨宮さんは、一瞬驚いたようですが、しょうがねえなぁ、みたいな顔をして、ナレーションが終わるのを待ってくれました。
ここまで話をしてしまえば、後は同じ事・・・・もう、こっちのペースで進めるだけです。
ただ、前日に比べ、少し緊張していたのか、4回ほど噛みましたけどね。
無事、演奏は終了し、休憩に入ります。
この日のお客さんには、サプライズのプレゼントがありました・・・・ホールの外で、できたてのポップコーンを配ったのですよ。
以前、株式会社なべしまの社長さんがウチに来られた時、このコンサートの話をしたら、ポップコーンを協賛したい、と言って下さったので、文化会館と交渉した結果、講堂前の廊下にポップコーンの機械を持ち込んで、その場で作ってもらう事になったのです。
キャラメルの甘い香りが漂う中、お客さんがポップコーンの機械の前に列を作っていました。
なべしまさんは、200人分のポップコーンを用意して下さったそうで、社長自ら休憩時間終了後にも作り続けて、演奏会から帰る人にも配って下さったようです。
なべしまさん、ありがとうございました。
(ちなみに、なべしまさんは、各種イヴェントにポップコーンを協賛しているそうで、文化会館の人も見に来て話をされていたようですが、3月の催しにも協賛する事が決まったそうです。)
後半は、管楽器のメンバーによる、バッハの『羊は安らかに草を食み』で始まり、続いて、子供たちも加わって、ベートーヴェンの『歓喜の歌』と『トルコ行進曲』の演奏です。
演奏終了後、子供たちは最後に演奏する『きよしこの夜』まで、客席で待機するのですが、その席が、上手の最前列、ちょうどオレの席のすぐ後ろなんですよ。
これってヤバイよなぁ・・・・オレがごまかしながら弾いているのが、全部見えてしまうもの。
まぁ、そんな状況の中、『ザ・サウンド・オヴ・ミュージック』ハイライツ、ヴィヴァルディの『四季』から『冬』と続きます。
でも、この『四季』という曲、名曲である事は分かっていたけれど、実際に弾いてみると、本当によくできた曲だと実感します。
自分が弾いているのは、単に一音ずつの刻みなんだけれど、それが集まってオーケストラの響きになっていくプロセスを体感すると、曲そのものに対する共感度や理解度が、一気に上がりますね。
ソロは前日と同じく、ドイツから来て下さった村中一夫さんで、やっぱりプロはすごい、と思わせる演奏を聞かせてもらえました。
解説の小淵さんも言ってみえたけど、実際にこういう演奏を見て、ヴァイオリンを習いたいと思い始めた人がいるかもしれませんね。
ヴィオラの人数が少ないので、このソロの時以外は、ヴィオラで参加してもらっているのですが、いきなりサイズの違うヴァイオリンに持ち替えてソロを弾けるんですから、すごいものですね。
実を言うと、オレは村中さんに対して、『孤高の人』的なイメージを持っていたのです。
それは、リハーサルの時の話し方や、休憩時間に一人離れて物思いに耽っておられるところを見たりしたからなんですが、この日の休憩時間に、眼鏡を捜しに控え室に入ってきた村中さんが、眼鏡を忘れてステージに向かった時の事を、ニコニコしながら話してくれたのを見て、オレの勝手な思い込みだったんだなぁ、って思いましたね。
最後は『クリスマス・フェスティヴァル』で、クリスマス気分を盛り上げ、次に、子供たちも加わったオーケストラの伴奏でお客さんが『きよしこの夜』を歌い、プログラムを終了しました。
この日は時間があったので、アンコールに、フォーレの『ラシーヌ雅歌』を演奏しました。
この曲は、技術的には難しくない(オレが初見で7割方弾けたくらいですから)曲ですが、表情を付けるとなると難しい・・・・
最後の音が消え入るように終わり、お客さんからの拍手が聞こえてきた時、やり終えた、という気持ちが湧き上がってきましたね。
オレは、技術的に追いつかないところを結構ごまかして弾いている程度の団員ですけど、そのオレでさえそう感じたのですから、トップの方でバリバリ弾いている人達の感じる充実感は、きっとすごく大きいものなのだろうと思います。
オレも、ごまかす事なく弾けるように頑張らなければ・・・・
今回、オレは末席ながら参加させてもらい、本当にいい経験をさせてもらいました。
と同時に、本当に楽しかった。
高山室内合奏団の団員の方々、手伝って下さった方々、そして来場して下さったお客さんに、御礼申し上げます。
ありがとうございました。
明らかな技術不足のせいで、足を引っ張ってしまったところもあったと思うのですが、ナレーションで少しは挽回できたのではないかと・・・・
次回の公演では、言い訳せずに演奏できるように、最大限の努力をしなければなりませんね。
オレはまた、終わったらすぐに店に帰り、夜の準備・・・・この日の夜は、ウチで打ち上げのパーティーが開かれました。
立食のパーティーでしたが、店は満杯。
音楽の話で盛り上がり、10時過ぎまで、皆さん楽しんでいかれました。
来年は、1月の中旬から、夏のコンサートに向けての練習が始まるし、3月にはヴァイオリンの発表会もあるので、仕事以外は音楽漬け、の日々になりそう・・・・
まぁ、でも、なんやかんや言いながら、好きな事をやるのは楽しいですね。
仕事も含めて、好きな事をできる、という事が、本当に幸せな事なんだと、実感している今日この頃です。
ちなみに、来年の『定期演奏会』は、9月4日に飛騨芸術堂で、クリスマスコンサートは、12月18日に文化会館講堂で行われる事が決まっていますので、是非お出で下さい。
お待ちしております。
19日は何故か写真を撮るのを忘れていたので、今回は画像なしになりました。
では、また。
Ciao. Arrivederci!!
2010年12月23日
演奏会無事終了 前編
Ciao. spock です。
このところ、話をした何人もの人から、今年は12月の気忙しさがない、と言う言葉を聞きましたが、オレも同じように思います。
仕事の面では結構バタバタしているのに、そう感じるのは、例年ほど寒くないせいもあるんでしょうかね。
ウチがクリスマス・メニューの広告を出さなくなってからかなり経ちますが、それでも予約を入れて下さる方がおられる事を、本当にありがたいと思いますね。
今年は例年になくクリスマスの予約が少ないのですが(毎年、直前になって席が埋まるというパターンが多いのですけどね)、その分、前の週に大きいパーティーが続き、そして、その週末に、高山室内合奏団のクリスマス・ファミリーコンサートの本番がありました。

一番忙しい週にぶつかってしまったので、練習もままならず・・・・ちょうどスッポリと予約が空いていた本番前日の夜、合わせる事が出来たのは、ラッキーだったと言ってもいいでしょう。
『動物の謝肉祭』のナレーターという大役も貰っていたのですが、自分で原稿を書いていた事もあって、その時初めて声に出したくらいで・・・・まぁ、ほとんど『ぶっつけ本番』状態ですね。
ぶっつけ本番に強いタイプだと言う自信はあるものの、今回は、オレがミスれば他の人達に迷惑がかかるわけですから、それなりのプレッシャーは感じましたね。
1日目は神岡の『船津座』で、2日目は『高山市民文化会館』での公演でだったのですが、両日とも、夜に大きい予約が入っていたので、ひたすら準備に追われる日々でした。
1日目。
朝8時半過ぎに出発し、41号線をひたすら走って神岡へ。
船津座へは1時間と少しで到着しました。
会場の設営や、譜面台の飾り付けなど、分担して行います。


その後、ゲネプロに入りましたが、上手くいかないところは繰り返しましたから、時間は延びるばかり・・・・
ナレーションを入れての練習を忘れていて、最後のところを少しだけやっただけで、本番に向かう事になりました。
ほんと、文字通りの「ぶっつけ本番」です。
ふと気がつくと、開演15分前になっていた・・・・慌てて練習を打ち切り、控え室に入って、食事をする暇もなく着替えをすませ、チューニングをして、ホールの入口へ向かう。
差し入れしてもらった、みたらし団子を2本だけ食べましたが、その団子のありがたかった事。
ホールの扉を少し開けて中を覗くと、ほぼ満席!!
みんな驚いてましたねぇ。
全員揃ったところで、いよいよ入場です。
席順の関係で、オレが一番最初に出る事になり、へっぴり腰にならないように、胸を張って客席の前を歩いて行き、席に着く。
オレは一番ヘタな団員なので、セカンド・ヴァイオリン最後列のウラ(内側)に座ります。
弾けないところを、かなりごまかして弾いているのが、オモテ(客席側)だと見えてしまいますからね。(笑)
全員が着席し、コンサートミストレスのAの音に合わせてチューニングし、指揮者が登場して、演奏が始まります。
『もろびとこぞりて』で始まりましたが、音符を追いながらついていくのだけで精一杯で、訳の分からんうちに終了しました。
次は、バッハの『2つのヴァイオリンのための協奏曲ニ短調』の第一楽章です。
ソリストは2人とも女子高生で、肩をむき出しのサンタクロースのコスチュームで演奏するというサーヴィス(?)付き。
その時だけ、その女子高生の座っていた前から2番目の席にオレが移る事になっているのですが、前の方はヴェテランばかりで、オレのヘタさが余計に目立ちそう。
この曲は、16分音符の細かい音型が繰り返される上、やたらと臨時記号が多く、楽譜を見ながら弾けるような曲ではないので、曲の頭から身体で覚えたのですが、途中で分からなくなる事もしばしば。
自信のないところは、できるだけ音を出さないようにして、音を長く伸ばすところや、同じ音が繰り返されるところで音を出す・・・・そんな方法で、なんとか乗り切りました。
次はいよいよ『動物の謝肉祭』から10曲の抜粋版です・・・・ナレーターとしての役割を、上手く果たす事ができるかどうか。
絶対にドキドキするだろうと思っていたけれど、自分でも不思議なくらい落ち着いてました。
曲目解説の小淵さんからマイクを受け取り、自分の席に戻ってまず一声・・・・うわずる事なく、思った通りの声が出ました。
これでもう大丈夫、あとは自分のペースで話すだけです。
自分で書いたナレーションの原稿が、例によって「長過ぎる」と言われたので、極力短くしたのですが、それでも長いのではないか、という気持ちも働いて、ナレーションがだんだん速くなりそうなんですよね。
そこを押さえて、できるだけゆっくりと話す。
以前ナレーターをやった人の話では、ナレーションと演奏の切り替えが難しい、との事でしたが、オレの場合、はなから完璧に演奏できるわけがない、という開き直りがあったせいか、全く気にする事なくやり通す事ができました。
途中、1回だけかんだところがありましたが、ナレーションは無事終了。
最後の2曲は続けて演奏するのですが、ほっとしたせいか、意外なほどあっけなく終わってしまったような気がしましたねぇ。
演奏を終了したところで、マイクを取って休憩の案内をして、前半は終わりました。
一度控え室へ戻った後、ホールへ戻ってみると、結構知った顔が見えます。
で、挨拶して、ちょっと話したり・・・・
何人かの人から、いい声でしたよ、って言われたのですが、たとえお世辞であっても嬉しいものですね。
お茶を一杯飲んで、後半の準備を始めます。
後半は、団友として参加してくれた、管楽器奏者の人達のための曲目、バッハの『羊は安らかに草を食み』で始まります。
演奏に参加しない、ほとんどの楽団員は、入口の近くで演奏を見守っていました。
団員が席に着き、そこへヴァイオリンを習っている子供達が加わって、ベートーヴェンの『歓喜の歌』と『トルコ行進曲』の演奏です。
子供達にも演奏できる簡単な曲、という事で選ばれたのだそうですが、まだファーストポジションしか使えないオレにとって、トルコ行進曲は結構難物でしたね。
子供達が客席へ移動し、次は『ザ サウンド オヴ ミュージック』ハイライトです。
文字通り、サウンド オヴ ミュージックのメロディーが次々に出てくるのですが、セカンドヴァイオリンとして弾くと、結構不思議なメロディー進行があったりします。
ドレミの歌も、ファーストヴァイオリンの3度下を弾くと、メロディーが短調になるわけだし、自分が今弾いているのが、何のメロディーなのか分からない事もありますが、オーケストラ全体の響きとして聞くと、あぁ、いいなぁ、って思ってしまいますね。
まぁ、そんなこともあって、セカンドヴァイオリンが主旋律を弾くところでは、ついつい大きめの音を出しそうになって、思いとどまる事もありますけど。
次は、今回のメインとも言える、ヴィヴァルディの『四季』から『冬』です。
ソロを弾くのは、神岡出身で、ハノーファー北ドイツ放送フィルハーモニー管弦楽団のヴァイオリニスト、村中一夫さんです。
村中さんは、このコンサートのために帰国されたそうで、このソロ以外では、ヴィオラで参加して下さっているのですが、やっぱりプロは違いますね。
調整ができていない安物の楽器でも、いい音を出せるんですから。
もしオレが、ストラディヴァーリやグァルネーリの楽器を弾いても、それ以下の音しか出せないでしょうね。
この曲でのセカンドヴァイオリンは、同じ音を続けて刻むパターンが多いので、オレにとってはありがたいですね・・・・なんて言っているうちに、メチャメチャ速い刻みが出てきて、追いつけなくなったりしますが。
でも、実際に弾いてみて、改めていい曲だと思いますね。
第2楽章の、分散和音のピッツィカートは、指が追いつかなくて、音を出せたのは半分以下でしたが、まぁ、間違った音を出すよりは良かったのではないかと。
次は、アンダーソンの『クリスマス・フェスティヴァル』です。
クリスマスに因んだメロディーをつないで、最後は派手に盛り上がる曲なんですが、目紛しくテンポが変わるので、結構難儀な曲です。
でも、クリスマスコンサートの最後を飾るには、うってつけの曲ですね
ここでも、しっかりと弾けるところは、目一杯弾きましたが・・・・音程は合ってたんだろうな・・・・
コンサートの最後は、『きよしこの夜』・・・・子供たちも加わったオーケストラの伴奏で、お客さんが歌います。
この曲だけは、完全に弾けるのですが、コンサートも終わり、という気持ちと一緒になって、自分の中で、気持ちが盛り上がってくるのを感じましたね。
コンサートは無事終了しましたが、オレは仕事があるので、すぐに帰らなければならないのです。
ひとりバタバタと、譜面台を片付けていたら、takechiくんと奥さんが、花束を持って来てくれました。
今回、団友としてファゴットで参加してくれた上仲貴子さんの送迎で来られたようですが、オレにまで花束を用意してもらえたなんて、感激です。
その花束を持って控え室に戻ったら、ひとりだけ花束を貰ってる、ってみんなに言われましたけど、やっぱり嬉しいものですね。
あわてて着替え、みんなに挨拶して、船津座をあとにしました。
その日は、シェ・ボアさんで打ち上げがあり、オレも本当に行きたかったのだけれど、16人のお客さんが待っていますからね・・・・未練がましい気持ちを振り切って、帰途に着きます。
41号線に入ったら、前を行く積載車がかなりのペースで走ってくれたおかげで、思ったより早く高山に着く事ができました。
takechiくんから貰った花束は、花瓶に生けて、店に飾ってあります。

高山での公演については、後編で。
では、また。
Ciao. Arrivederci!!
このところ、話をした何人もの人から、今年は12月の気忙しさがない、と言う言葉を聞きましたが、オレも同じように思います。
仕事の面では結構バタバタしているのに、そう感じるのは、例年ほど寒くないせいもあるんでしょうかね。
ウチがクリスマス・メニューの広告を出さなくなってからかなり経ちますが、それでも予約を入れて下さる方がおられる事を、本当にありがたいと思いますね。
今年は例年になくクリスマスの予約が少ないのですが(毎年、直前になって席が埋まるというパターンが多いのですけどね)、その分、前の週に大きいパーティーが続き、そして、その週末に、高山室内合奏団のクリスマス・ファミリーコンサートの本番がありました。

一番忙しい週にぶつかってしまったので、練習もままならず・・・・ちょうどスッポリと予約が空いていた本番前日の夜、合わせる事が出来たのは、ラッキーだったと言ってもいいでしょう。
『動物の謝肉祭』のナレーターという大役も貰っていたのですが、自分で原稿を書いていた事もあって、その時初めて声に出したくらいで・・・・まぁ、ほとんど『ぶっつけ本番』状態ですね。
ぶっつけ本番に強いタイプだと言う自信はあるものの、今回は、オレがミスれば他の人達に迷惑がかかるわけですから、それなりのプレッシャーは感じましたね。
1日目は神岡の『船津座』で、2日目は『高山市民文化会館』での公演でだったのですが、両日とも、夜に大きい予約が入っていたので、ひたすら準備に追われる日々でした。
1日目。
朝8時半過ぎに出発し、41号線をひたすら走って神岡へ。
船津座へは1時間と少しで到着しました。
会場の設営や、譜面台の飾り付けなど、分担して行います。


その後、ゲネプロに入りましたが、上手くいかないところは繰り返しましたから、時間は延びるばかり・・・・
ナレーションを入れての練習を忘れていて、最後のところを少しだけやっただけで、本番に向かう事になりました。
ほんと、文字通りの「ぶっつけ本番」です。
ふと気がつくと、開演15分前になっていた・・・・慌てて練習を打ち切り、控え室に入って、食事をする暇もなく着替えをすませ、チューニングをして、ホールの入口へ向かう。
差し入れしてもらった、みたらし団子を2本だけ食べましたが、その団子のありがたかった事。
ホールの扉を少し開けて中を覗くと、ほぼ満席!!
みんな驚いてましたねぇ。
全員揃ったところで、いよいよ入場です。
席順の関係で、オレが一番最初に出る事になり、へっぴり腰にならないように、胸を張って客席の前を歩いて行き、席に着く。
オレは一番ヘタな団員なので、セカンド・ヴァイオリン最後列のウラ(内側)に座ります。
弾けないところを、かなりごまかして弾いているのが、オモテ(客席側)だと見えてしまいますからね。(笑)
全員が着席し、コンサートミストレスのAの音に合わせてチューニングし、指揮者が登場して、演奏が始まります。
『もろびとこぞりて』で始まりましたが、音符を追いながらついていくのだけで精一杯で、訳の分からんうちに終了しました。
次は、バッハの『2つのヴァイオリンのための協奏曲ニ短調』の第一楽章です。
ソリストは2人とも女子高生で、肩をむき出しのサンタクロースのコスチュームで演奏するというサーヴィス(?)付き。
その時だけ、その女子高生の座っていた前から2番目の席にオレが移る事になっているのですが、前の方はヴェテランばかりで、オレのヘタさが余計に目立ちそう。
この曲は、16分音符の細かい音型が繰り返される上、やたらと臨時記号が多く、楽譜を見ながら弾けるような曲ではないので、曲の頭から身体で覚えたのですが、途中で分からなくなる事もしばしば。
自信のないところは、できるだけ音を出さないようにして、音を長く伸ばすところや、同じ音が繰り返されるところで音を出す・・・・そんな方法で、なんとか乗り切りました。
次はいよいよ『動物の謝肉祭』から10曲の抜粋版です・・・・ナレーターとしての役割を、上手く果たす事ができるかどうか。
絶対にドキドキするだろうと思っていたけれど、自分でも不思議なくらい落ち着いてました。
曲目解説の小淵さんからマイクを受け取り、自分の席に戻ってまず一声・・・・うわずる事なく、思った通りの声が出ました。
これでもう大丈夫、あとは自分のペースで話すだけです。
自分で書いたナレーションの原稿が、例によって「長過ぎる」と言われたので、極力短くしたのですが、それでも長いのではないか、という気持ちも働いて、ナレーションがだんだん速くなりそうなんですよね。
そこを押さえて、できるだけゆっくりと話す。
以前ナレーターをやった人の話では、ナレーションと演奏の切り替えが難しい、との事でしたが、オレの場合、はなから完璧に演奏できるわけがない、という開き直りがあったせいか、全く気にする事なくやり通す事ができました。
途中、1回だけかんだところがありましたが、ナレーションは無事終了。
最後の2曲は続けて演奏するのですが、ほっとしたせいか、意外なほどあっけなく終わってしまったような気がしましたねぇ。
演奏を終了したところで、マイクを取って休憩の案内をして、前半は終わりました。
一度控え室へ戻った後、ホールへ戻ってみると、結構知った顔が見えます。
で、挨拶して、ちょっと話したり・・・・
何人かの人から、いい声でしたよ、って言われたのですが、たとえお世辞であっても嬉しいものですね。
お茶を一杯飲んで、後半の準備を始めます。
後半は、団友として参加してくれた、管楽器奏者の人達のための曲目、バッハの『羊は安らかに草を食み』で始まります。
演奏に参加しない、ほとんどの楽団員は、入口の近くで演奏を見守っていました。
団員が席に着き、そこへヴァイオリンを習っている子供達が加わって、ベートーヴェンの『歓喜の歌』と『トルコ行進曲』の演奏です。
子供達にも演奏できる簡単な曲、という事で選ばれたのだそうですが、まだファーストポジションしか使えないオレにとって、トルコ行進曲は結構難物でしたね。
子供達が客席へ移動し、次は『ザ サウンド オヴ ミュージック』ハイライトです。
文字通り、サウンド オヴ ミュージックのメロディーが次々に出てくるのですが、セカンドヴァイオリンとして弾くと、結構不思議なメロディー進行があったりします。
ドレミの歌も、ファーストヴァイオリンの3度下を弾くと、メロディーが短調になるわけだし、自分が今弾いているのが、何のメロディーなのか分からない事もありますが、オーケストラ全体の響きとして聞くと、あぁ、いいなぁ、って思ってしまいますね。
まぁ、そんなこともあって、セカンドヴァイオリンが主旋律を弾くところでは、ついつい大きめの音を出しそうになって、思いとどまる事もありますけど。
次は、今回のメインとも言える、ヴィヴァルディの『四季』から『冬』です。
ソロを弾くのは、神岡出身で、ハノーファー北ドイツ放送フィルハーモニー管弦楽団のヴァイオリニスト、村中一夫さんです。
村中さんは、このコンサートのために帰国されたそうで、このソロ以外では、ヴィオラで参加して下さっているのですが、やっぱりプロは違いますね。
調整ができていない安物の楽器でも、いい音を出せるんですから。
もしオレが、ストラディヴァーリやグァルネーリの楽器を弾いても、それ以下の音しか出せないでしょうね。
この曲でのセカンドヴァイオリンは、同じ音を続けて刻むパターンが多いので、オレにとってはありがたいですね・・・・なんて言っているうちに、メチャメチャ速い刻みが出てきて、追いつけなくなったりしますが。
でも、実際に弾いてみて、改めていい曲だと思いますね。
第2楽章の、分散和音のピッツィカートは、指が追いつかなくて、音を出せたのは半分以下でしたが、まぁ、間違った音を出すよりは良かったのではないかと。
次は、アンダーソンの『クリスマス・フェスティヴァル』です。
クリスマスに因んだメロディーをつないで、最後は派手に盛り上がる曲なんですが、目紛しくテンポが変わるので、結構難儀な曲です。
でも、クリスマスコンサートの最後を飾るには、うってつけの曲ですね
ここでも、しっかりと弾けるところは、目一杯弾きましたが・・・・音程は合ってたんだろうな・・・・
コンサートの最後は、『きよしこの夜』・・・・子供たちも加わったオーケストラの伴奏で、お客さんが歌います。
この曲だけは、完全に弾けるのですが、コンサートも終わり、という気持ちと一緒になって、自分の中で、気持ちが盛り上がってくるのを感じましたね。
コンサートは無事終了しましたが、オレは仕事があるので、すぐに帰らなければならないのです。
ひとりバタバタと、譜面台を片付けていたら、takechiくんと奥さんが、花束を持って来てくれました。
今回、団友としてファゴットで参加してくれた上仲貴子さんの送迎で来られたようですが、オレにまで花束を用意してもらえたなんて、感激です。
その花束を持って控え室に戻ったら、ひとりだけ花束を貰ってる、ってみんなに言われましたけど、やっぱり嬉しいものですね。
あわてて着替え、みんなに挨拶して、船津座をあとにしました。
その日は、シェ・ボアさんで打ち上げがあり、オレも本当に行きたかったのだけれど、16人のお客さんが待っていますからね・・・・未練がましい気持ちを振り切って、帰途に着きます。
41号線に入ったら、前を行く積載車がかなりのペースで走ってくれたおかげで、思ったより早く高山に着く事ができました。
takechiくんから貰った花束は、花瓶に生けて、店に飾ってあります。

高山での公演については、後編で。
では、また。
Ciao. Arrivederci!!
2010年12月09日
リハーサルの話 その2
Ciao. spockです。
いや〜、もう12月も中旬かぁ・・・・今年も残すところ、あと3週間ですね。
夜、店を閉める時に、天気予報の最低気温を見て、低くなりそうだと、店の前に置いているゼラニウムのプランターを中へ入れるのですが、もうそろそろ、中へ入れっぱなしになりそうです。
冬に向かう今の時期、気持ちが滅入らないように楽しいことを考えるのが一番いいのですが、あんまりいい話題はないですよねぇ。
まぁ、そんな中で、今の時期の楽しみといえばNFLですよ。
でも、どういうわけかBSで放映されるのは、興味がないと言うか、話題性が無いと言うか、そんなゲームばかりで・・・・仕方が無いので、NFL JAPAN.COMの動画で情報を得てますけど。
今年は全く期待していなかったデンヴァー・ブロンコスですが、今のところ予想通りと言うか、全くの低迷状態です。
去年は、開幕6連勝の後の低迷で、結局プレイオフ進出を逃してしまった事を考えると、後半で上り調子になる方がいいんですが、すでに9敗となると、もう期待できませんね。
ついにマクダニエルス・ヘッドコーチも解任されてしまいましたが・・・・
パスに関しては、QBオートンとWRロイドのホットラインが、NFLでも1位2位を争う好調さを見せているのに対し、ランがNFL最下位と全く振るわないせいもあってか、あと少しのところで負けるパターンに陥っているようです。(第11週のラムズ戦でも、いいところまで追い上げたのに3点届かなかったし、第12週のチーフス戦は、最後の最後に逆転負け。)
でも、上記のNFL JAPAN.COMの動画で、第6週の『TOP5キャッチ』には、ブロンコスから、ロイドとトーマスの2人が、第8週の『TOP5キャッチ』では、TOP1にロイドのレシーヴが選ばれているくらいだし、ロイドの獲得ヤード数やアヴェレイジはダントツの1位なんですから、なんとか勝利に繋げてほしいものですね。(いつも動画を見て思うけど、どんな体勢からでも絶対にエンドゾーン内に両足を残すレシーヴァーって、本当にすごいですね。余談ながら、第6週TOP1のガーソンのレシーヴは、凄すぎてわけが分かりませんが。)
今年はもう、ティームの成績は望まないけど、こういう記録だけは伸ばしてほしいと思います。
まぁ、来期を見据えて、ティームのシステムをしっかりと構築してほしいものですね。
さて、ここで「お知らせ」です。
前回にも書きましたが、高山室内合奏団のクリスマス・ファミリーコンサートが、18日に船津座で、19日に高山文化会館で、14時から行われます。
入場無料の上、休憩時間にはお茶やお菓子も出ますので、ぜひお出で下さい。
一応オレも、セカンド・ヴァイオリンの一番後ろで、弾けるところだけ弾かせてもらいます。
『動物の謝肉祭』のナレーター、という大役も頂いているのですが・・・・ちゃんと出来るんだろうか・・・・
まぁ、やってみないと分かりませんが。
というわけで、18日のランチの営業はお休みさせて頂きますので、よろしくお願いします。
では、本題に入りましょう。
前回の『その1』からの続きです。
この前、あるリハーサルを見せてもらいました。

布袋台のからくりです。
去年、からくりを操っている親友の千葉茂が誘ってくれたので、リハーサルにお邪魔して見せてもらったのですが、今年は去年に続いて2回目です。(布袋台組の人達からは、物好きなヤツだと思われているでしょうね)
今年はメンバーが一部替わり、それぞれが担当する部所も変わっていたけれど、この日は最後のリハーサルという事もあり、そういう事を全く感じさせない、スムースな動きを見る事ができました。
この布袋台のからくりは、40年以上も前、明治百年祭全国からくりコンクールで1位になりましたが、本当にそれだけの内容を持ったからくりだと思います。
以前、からくり人形について調べた事があるのですが、多くのからくり人形が残っている三河地方には、布袋台の唐子のような『綾渡り』も多くあって、綾渡り自体は珍しいものではないようですが、布袋台のからくりがすごいのは、それだけで完結している『綾渡り』を、布袋さんの動きと組み合わせた事で、綾を渡る唐子を、下で布袋さんが喜んで見ているという、二つのストーリーが同時進行するわけです。

この布袋台のからくりが他を圧してスゴいのは、最後に布袋さんが、肩と右手の上に唐子を受け取る事ですね。
綾を渡った人形を別の人形が受け取るというのは、日本広しといえど、布袋台のからくりが唯一無二のものであり、さらに布袋さんの上に乗った唐子が首を振るというその巧妙さは、他のからくりが束になってかかっても敵わないでしょう。
実際に中の構造を見せてもらうと、よくここまで作ったものだと感心してしまいます。
布袋さんの上に載った唐子が首を振り始めると、見ている人は一様に感嘆の声をあげますが、その接合させる部分と、首を動かす仕掛けを組み合わせた接合部の、何と巧妙な仕組み・・・・
布袋さんの脚が動く事は見れば分かりますが、それがただ単に前後に動くのではなく、腰と膝に関節があって、膝を持ち上げながら動くようになっていて、その動きのリアルさを追求した構造に、思わず感嘆の溜息が出てしまいます。
それにしても、ここまで凝りに凝った構造のからくりを作り上げた事に、ある種の執念を感じてしまうのはオレだけでしょうか。
でも、これだけの動きを、たった36本の糸で操っているのはすごい事ですね。
千葉は、長い年月の間に、からくりの調整と、操る人達の試行錯誤が繰り返された結果、現在の完成された動きができるようになったのだろう、と言います。
先年、唐子の人形が新調された時、寸分違わぬ大きさに作られたはずなのに、動きが上手く噛み合わず、人形師が付きっきりで調整を繰り返したけれど、本来の動きにはならなかったと、千葉が話していたのですが、今ではそんな事を全く感じさせないスムースな動きをしているのを見ると、過去にもそういう事が繰り返された結果、今のからくりがあるのだという事を実感させられる話だと思います。
本来は9人で操るからくりを、この日のリハーサルでは7人で操っていましたが、子供の頃からからくりに触れ、分担された部所を順番にこなして来た人達ですから、掛け持ち状態でも、難なくこなせるのでしょうね。
去年まで布袋さんの頭を操っていた千葉も、今年は布袋さんの胴体を担当していましたが、見ていて全く違和感がなかったですからね。
ずーっとからくりをやってきた千葉の息子は、今年の祭当日が野球の遠征のため参加できず、今年から再参加した有巣君が、その分をカヴァーしていました。
以前、何かの本で、からくりを操るには長年の経験と勘が必要で、一朝一夕にできるものではない、と書かれているのを読んだ事があったので、千葉に訊いてみた事があります・・・・からくりの練習って、どれくらいやるのか、って。
それに対する千葉の答えは、祭の前に3回だけ、というものでした。
えっ、そんなに少ないの、と聞き返したオレに、千葉は言いました。
子供の頃からずーっとやっている事なんだから、本番の前にカンを取り戻しておけば大丈夫。それに、何回も練習したら、からくりが壊れてしまう。
なるほど・・・・言われてみれば、そのとおりかもしれません。
そういう『経験とカン』があるからこそ、自分の持ち場が変わっても、すぐに対応できるわけですね。
各人が持ち場に着き、リハーサルが始まります。
ディジタルプレイヤーにつないだスピーカーから、『六段』を崩したといわれる囃子が流れると、それに合わせて布袋さんが動き出します。
始めのうちは、動き具合を確かめながら動かしている、という感じで、各人が調子を合わせているようにも見えますが、冗談を言いながら、和気藹々と進みます。
そんな和やかな雰囲気で進みながらも、お互いに動きを合わせる事に神経を使っていることが分かります。
特に、布袋さんが唐子を受け取るところでは、唐子と布袋さんの位置と向きが合わなければ、うまく受け取れませんから、みんなで声を掛け合いながら、微妙な位置調整をするわけです。

本当にこの時は、見ていても緊張しますね。
唐子がきちんと載って結合が上手くいき、首を振り始めると、ほっとした空気が流れます。
唐子が布袋さんにきちんと載った事を確認した上で綾から離すのですが、最悪の場合には落ちてしまう事もあるわけです。
滅多にない事とはいえ、そういう時のために、屋台の下には受け止める役の人が待機しているそうですが、唐子の人形は、必ず足を下にして落ちるように作られているのだそうです。
2体の唐子が布袋さんの肩と右手の上に載り、布袋さんが軍配を振ると、中から紙吹雪とともに幟が出て、からくりは終わりです。
この日のリハーサルでは、『綾元』の要望で、真ん中の綾から唐子を布袋さんに移す、という試みが最後に行われました。

本来の位置ではないので、綾と人形が干渉しないように、少しずつ位置を調整しながらではありましたが、初めての試みを一発で成功させたのには、流石と言うべきでしょうね。
話を聞いている限りでは、唐子が最後の綾まで行けなかった場合を想定してやったみたいですが、ひょっとしたら、何らかの不具合を抱えているのかもしれません。
終了後に、簡単な片付けがされたのですが、さりげなく話をしながら束ねて編み上げられた糸を見ると、操っている人達の『年期』というものが、よく分かりますね。

この日は、最後のリハーサルという事もあって、その後、皆さんで飲みに出かけられましたが、去年見せてもらった時には、綾元の鍋島勝雄さんから、いろんな話を聞かせてもらいました。
からくりについては詳しく調べた事があるので、知っている話も結構ありましたが、布袋台組に伝わっている話を、直接布袋台組の人から聞くと、その『歴史』というものを重く感じる事ができます。
からくりの伴奏に使われている『六段崩し』は、祇園の芸妓を牛の背に乗せて招き、滞留させて組内の者に伝習させた、という話を本で読んだ時には、漠然と、そんなものかなぁ、って思ってましたが、組内に伝わっている話として綾元から聞くと、史実として実感できるのがおもしろいところですね。
話の中で綾元が、こんな事を言われました。
からくりを見に来る人の中には、失敗する事を期待している人が必ずいる筈だから、上手くいっている時でも、わざと動かなくなったように見せる事もある。
なるほどねぇ・・・・まぁ、そんな事ができるのも、長年の経験があるからなんでしょうけどね。
綾元は、36本の糸のうち、綾に関する14本をひとりで担当するわけですが、このからくりの全てに精通しているからこそできる事なんでしょう。
また、以前、依頼を受けて、あるホールのステージでからくりの実演をする事になったそうですが、緞帳が上がる時に、綾が巻き込まれて破損してしまい、それ以降は、そういう場所での実演は一切断っている、という話を聞いたのですが、破損した部分が修復できたから良かったものの、そうでなければ大変な事になっていたわけですよ。
からくりは、屋台の上で演じているのを下から見るように作られているのですから、詰まるところ「祭の時に屋台の下で見る」のが一番だと思いますね。
今年の祭は、一日目が雨に降られ、全ての行事が中止になったせいもあって、本楽祭のからくり奉納では、八幡の境内に人が入りきれず、早い時間から、まわりの道が通行止めになっていました。
オレは毎年、下一通りで見る事にしているのですが、今年は早めに行ったにもかかわらず、かなりの人が集まっていましたね。

天気は良かったのに、待っているうちに雨が降りそうな気配になってきたので、少し早めに始まる事になったのですが、ディジタルプレイヤーの調子が悪いらしく、伴奏の音楽が流れない・・・・
結局、伴奏なしで始まったのですが、やっぱり、なんか変ですね。
操っている人も、音楽の進み方をたよりに、人形の位置や動きを調整している部分もあるわけですから、やりにくかったでしょうね。

でも、途中から音楽が鳴り出し、そのまま無事終了しましたから、まぁ、良かったんだと思います。
その後、屋台とからくりの人形は、屋台蔵に仕舞われます。
来年は、秋の晴天の下、八幡の境内でのからくり奉納も、夜祭りも見る事ができるように、今から祈っておきましょう。
最後になりましたが、心良くリハーサルを見せて下さった布袋台組の方々に、お礼を申し上げます。
ありがとうございました。
迷惑でなければ、また来年も・・・・
では、また。
Ciao. Arrivederci!!
いや〜、もう12月も中旬かぁ・・・・今年も残すところ、あと3週間ですね。
夜、店を閉める時に、天気予報の最低気温を見て、低くなりそうだと、店の前に置いているゼラニウムのプランターを中へ入れるのですが、もうそろそろ、中へ入れっぱなしになりそうです。
冬に向かう今の時期、気持ちが滅入らないように楽しいことを考えるのが一番いいのですが、あんまりいい話題はないですよねぇ。
まぁ、そんな中で、今の時期の楽しみといえばNFLですよ。
でも、どういうわけかBSで放映されるのは、興味がないと言うか、話題性が無いと言うか、そんなゲームばかりで・・・・仕方が無いので、NFL JAPAN.COMの動画で情報を得てますけど。
今年は全く期待していなかったデンヴァー・ブロンコスですが、今のところ予想通りと言うか、全くの低迷状態です。
去年は、開幕6連勝の後の低迷で、結局プレイオフ進出を逃してしまった事を考えると、後半で上り調子になる方がいいんですが、すでに9敗となると、もう期待できませんね。
ついにマクダニエルス・ヘッドコーチも解任されてしまいましたが・・・・
パスに関しては、QBオートンとWRロイドのホットラインが、NFLでも1位2位を争う好調さを見せているのに対し、ランがNFL最下位と全く振るわないせいもあってか、あと少しのところで負けるパターンに陥っているようです。(第11週のラムズ戦でも、いいところまで追い上げたのに3点届かなかったし、第12週のチーフス戦は、最後の最後に逆転負け。)
でも、上記のNFL JAPAN.COMの動画で、第6週の『TOP5キャッチ』には、ブロンコスから、ロイドとトーマスの2人が、第8週の『TOP5キャッチ』では、TOP1にロイドのレシーヴが選ばれているくらいだし、ロイドの獲得ヤード数やアヴェレイジはダントツの1位なんですから、なんとか勝利に繋げてほしいものですね。(いつも動画を見て思うけど、どんな体勢からでも絶対にエンドゾーン内に両足を残すレシーヴァーって、本当にすごいですね。余談ながら、第6週TOP1のガーソンのレシーヴは、凄すぎてわけが分かりませんが。)
今年はもう、ティームの成績は望まないけど、こういう記録だけは伸ばしてほしいと思います。
まぁ、来期を見据えて、ティームのシステムをしっかりと構築してほしいものですね。
さて、ここで「お知らせ」です。
前回にも書きましたが、高山室内合奏団のクリスマス・ファミリーコンサートが、18日に船津座で、19日に高山文化会館で、14時から行われます。
入場無料の上、休憩時間にはお茶やお菓子も出ますので、ぜひお出で下さい。
一応オレも、セカンド・ヴァイオリンの一番後ろで、弾けるところだけ弾かせてもらいます。
『動物の謝肉祭』のナレーター、という大役も頂いているのですが・・・・ちゃんと出来るんだろうか・・・・
まぁ、やってみないと分かりませんが。
というわけで、18日のランチの営業はお休みさせて頂きますので、よろしくお願いします。
では、本題に入りましょう。
前回の『その1』からの続きです。
この前、あるリハーサルを見せてもらいました。

布袋台のからくりです。
去年、からくりを操っている親友の千葉茂が誘ってくれたので、リハーサルにお邪魔して見せてもらったのですが、今年は去年に続いて2回目です。(布袋台組の人達からは、物好きなヤツだと思われているでしょうね)
今年はメンバーが一部替わり、それぞれが担当する部所も変わっていたけれど、この日は最後のリハーサルという事もあり、そういう事を全く感じさせない、スムースな動きを見る事ができました。
この布袋台のからくりは、40年以上も前、明治百年祭全国からくりコンクールで1位になりましたが、本当にそれだけの内容を持ったからくりだと思います。
以前、からくり人形について調べた事があるのですが、多くのからくり人形が残っている三河地方には、布袋台の唐子のような『綾渡り』も多くあって、綾渡り自体は珍しいものではないようですが、布袋台のからくりがすごいのは、それだけで完結している『綾渡り』を、布袋さんの動きと組み合わせた事で、綾を渡る唐子を、下で布袋さんが喜んで見ているという、二つのストーリーが同時進行するわけです。
この布袋台のからくりが他を圧してスゴいのは、最後に布袋さんが、肩と右手の上に唐子を受け取る事ですね。
綾を渡った人形を別の人形が受け取るというのは、日本広しといえど、布袋台のからくりが唯一無二のものであり、さらに布袋さんの上に乗った唐子が首を振るというその巧妙さは、他のからくりが束になってかかっても敵わないでしょう。
実際に中の構造を見せてもらうと、よくここまで作ったものだと感心してしまいます。
布袋さんの上に載った唐子が首を振り始めると、見ている人は一様に感嘆の声をあげますが、その接合させる部分と、首を動かす仕掛けを組み合わせた接合部の、何と巧妙な仕組み・・・・
布袋さんの脚が動く事は見れば分かりますが、それがただ単に前後に動くのではなく、腰と膝に関節があって、膝を持ち上げながら動くようになっていて、その動きのリアルさを追求した構造に、思わず感嘆の溜息が出てしまいます。
それにしても、ここまで凝りに凝った構造のからくりを作り上げた事に、ある種の執念を感じてしまうのはオレだけでしょうか。
でも、これだけの動きを、たった36本の糸で操っているのはすごい事ですね。
千葉は、長い年月の間に、からくりの調整と、操る人達の試行錯誤が繰り返された結果、現在の完成された動きができるようになったのだろう、と言います。
先年、唐子の人形が新調された時、寸分違わぬ大きさに作られたはずなのに、動きが上手く噛み合わず、人形師が付きっきりで調整を繰り返したけれど、本来の動きにはならなかったと、千葉が話していたのですが、今ではそんな事を全く感じさせないスムースな動きをしているのを見ると、過去にもそういう事が繰り返された結果、今のからくりがあるのだという事を実感させられる話だと思います。
本来は9人で操るからくりを、この日のリハーサルでは7人で操っていましたが、子供の頃からからくりに触れ、分担された部所を順番にこなして来た人達ですから、掛け持ち状態でも、難なくこなせるのでしょうね。
去年まで布袋さんの頭を操っていた千葉も、今年は布袋さんの胴体を担当していましたが、見ていて全く違和感がなかったですからね。
ずーっとからくりをやってきた千葉の息子は、今年の祭当日が野球の遠征のため参加できず、今年から再参加した有巣君が、その分をカヴァーしていました。
以前、何かの本で、からくりを操るには長年の経験と勘が必要で、一朝一夕にできるものではない、と書かれているのを読んだ事があったので、千葉に訊いてみた事があります・・・・からくりの練習って、どれくらいやるのか、って。
それに対する千葉の答えは、祭の前に3回だけ、というものでした。
えっ、そんなに少ないの、と聞き返したオレに、千葉は言いました。
子供の頃からずーっとやっている事なんだから、本番の前にカンを取り戻しておけば大丈夫。それに、何回も練習したら、からくりが壊れてしまう。
なるほど・・・・言われてみれば、そのとおりかもしれません。
そういう『経験とカン』があるからこそ、自分の持ち場が変わっても、すぐに対応できるわけですね。
各人が持ち場に着き、リハーサルが始まります。
ディジタルプレイヤーにつないだスピーカーから、『六段』を崩したといわれる囃子が流れると、それに合わせて布袋さんが動き出します。
始めのうちは、動き具合を確かめながら動かしている、という感じで、各人が調子を合わせているようにも見えますが、冗談を言いながら、和気藹々と進みます。
そんな和やかな雰囲気で進みながらも、お互いに動きを合わせる事に神経を使っていることが分かります。
特に、布袋さんが唐子を受け取るところでは、唐子と布袋さんの位置と向きが合わなければ、うまく受け取れませんから、みんなで声を掛け合いながら、微妙な位置調整をするわけです。

本当にこの時は、見ていても緊張しますね。
唐子がきちんと載って結合が上手くいき、首を振り始めると、ほっとした空気が流れます。
唐子が布袋さんにきちんと載った事を確認した上で綾から離すのですが、最悪の場合には落ちてしまう事もあるわけです。
滅多にない事とはいえ、そういう時のために、屋台の下には受け止める役の人が待機しているそうですが、唐子の人形は、必ず足を下にして落ちるように作られているのだそうです。
2体の唐子が布袋さんの肩と右手の上に載り、布袋さんが軍配を振ると、中から紙吹雪とともに幟が出て、からくりは終わりです。
この日のリハーサルでは、『綾元』の要望で、真ん中の綾から唐子を布袋さんに移す、という試みが最後に行われました。

本来の位置ではないので、綾と人形が干渉しないように、少しずつ位置を調整しながらではありましたが、初めての試みを一発で成功させたのには、流石と言うべきでしょうね。
話を聞いている限りでは、唐子が最後の綾まで行けなかった場合を想定してやったみたいですが、ひょっとしたら、何らかの不具合を抱えているのかもしれません。
終了後に、簡単な片付けがされたのですが、さりげなく話をしながら束ねて編み上げられた糸を見ると、操っている人達の『年期』というものが、よく分かりますね。

この日は、最後のリハーサルという事もあって、その後、皆さんで飲みに出かけられましたが、去年見せてもらった時には、綾元の鍋島勝雄さんから、いろんな話を聞かせてもらいました。
からくりについては詳しく調べた事があるので、知っている話も結構ありましたが、布袋台組に伝わっている話を、直接布袋台組の人から聞くと、その『歴史』というものを重く感じる事ができます。
からくりの伴奏に使われている『六段崩し』は、祇園の芸妓を牛の背に乗せて招き、滞留させて組内の者に伝習させた、という話を本で読んだ時には、漠然と、そんなものかなぁ、って思ってましたが、組内に伝わっている話として綾元から聞くと、史実として実感できるのがおもしろいところですね。
話の中で綾元が、こんな事を言われました。
からくりを見に来る人の中には、失敗する事を期待している人が必ずいる筈だから、上手くいっている時でも、わざと動かなくなったように見せる事もある。
なるほどねぇ・・・・まぁ、そんな事ができるのも、長年の経験があるからなんでしょうけどね。
綾元は、36本の糸のうち、綾に関する14本をひとりで担当するわけですが、このからくりの全てに精通しているからこそできる事なんでしょう。
また、以前、依頼を受けて、あるホールのステージでからくりの実演をする事になったそうですが、緞帳が上がる時に、綾が巻き込まれて破損してしまい、それ以降は、そういう場所での実演は一切断っている、という話を聞いたのですが、破損した部分が修復できたから良かったものの、そうでなければ大変な事になっていたわけですよ。
からくりは、屋台の上で演じているのを下から見るように作られているのですから、詰まるところ「祭の時に屋台の下で見る」のが一番だと思いますね。
今年の祭は、一日目が雨に降られ、全ての行事が中止になったせいもあって、本楽祭のからくり奉納では、八幡の境内に人が入りきれず、早い時間から、まわりの道が通行止めになっていました。
オレは毎年、下一通りで見る事にしているのですが、今年は早めに行ったにもかかわらず、かなりの人が集まっていましたね。

天気は良かったのに、待っているうちに雨が降りそうな気配になってきたので、少し早めに始まる事になったのですが、ディジタルプレイヤーの調子が悪いらしく、伴奏の音楽が流れない・・・・
結局、伴奏なしで始まったのですが、やっぱり、なんか変ですね。
操っている人も、音楽の進み方をたよりに、人形の位置や動きを調整している部分もあるわけですから、やりにくかったでしょうね。

でも、途中から音楽が鳴り出し、そのまま無事終了しましたから、まぁ、良かったんだと思います。
その後、屋台とからくりの人形は、屋台蔵に仕舞われます。
来年は、秋の晴天の下、八幡の境内でのからくり奉納も、夜祭りも見る事ができるように、今から祈っておきましょう。
最後になりましたが、心良くリハーサルを見せて下さった布袋台組の方々に、お礼を申し上げます。
ありがとうございました。
迷惑でなければ、また来年も・・・・
では、また。
Ciao. Arrivederci!!
Posted by spock at
20:32
│Comments(2)