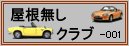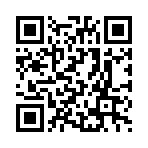スポンサーリンク
この広告は一定期間(1ヶ月以上)更新のないブログに表示されます。
ブログ記事の情報が古い場合がありますのでご注意下さい。
(ブログオーナーが新しい記事を投稿すると非表示になります。)
ブログ記事の情報が古い場合がありますのでご注意下さい。
(ブログオーナーが新しい記事を投稿すると非表示になります。)
2008年04月19日
曳き別れを観に・・・・
Ciao. spockです。
このところ少し調子の悪かったiBook G4が、起動できなくなりました。
そんな時に限って、ハードウェア診断ソフトが行方不明だったりして・・・・
サブのiMacを使っていますが、違うキーボードは使いにくいものですね。
さて、ひだっちブログでも春祭の話が出尽くしたようなので、そろそろ祭の話をアップすることにしましょうか。(笑)
14日の夜は、予約が入ってなかったので、曳き別れを観に行きました。
まぁ、祭の日は、たいていヒマですからね・・・・

今まで、観たいと思いながら観れなかった事を、今年こそ観てやろうと思うのですが、今年の道順だと、観れるのは1回だけですから、見逃さないようにタイミングを見計らなければ・・・・
とっぷりと暗くなった7:30に家を出て、まずは本町通りを南へ向かいます。
丁度、大黒台が筏橋へ向けて向きを変えるところでしたが、それ以上進めそうにないので、少し戻って柳橋を渡り、上三之町を通ってさんまち通りへ出ると、目の前を麒麟台が通ります。
でも、何かおかしい・・・・よく見ると、瓔珞がひとつ余分についています。

そういえば、どこかで見た画像にも、そういうのがありましたが、あれは何なんでしょうね。
でも、麒麟台はいつ見てもきれいです。
オレは、麒麟台についていつも思う事があるのですが、ここに書くと長くなるので、次回に書く事にしましょう。
最終的には、順道場の前で観るつもりですが、まだまだ時間がかかりそうなので、上二之町を通って安川通りへ出てみると、一之町の交差点で獅子舞をやっていました。
獅子舞が終わって神楽台が動き出すのを見て、順道場へ向かいます。
順道場の前には、すでに何人かの人達が待っていました。
宮本のテントの中も、まだのんびりした雰囲気で、結構酔っぱらっている人もみえます。
でも、神楽台が二之町へ入った、と声がかかると、緊張した空気が走り、宮本の人達が所定の位置に着きます。
あ、一番前に座っているのは、ウチの料理を気に入って、いつも来て下さるHさんです。
声をかけて挨拶し、屋台が見やすそうな場所に立って待ちます。
太鼓の音を響かせながら、神楽台が近づいてくると、慌ただしく順道場の前が広く開けられ、照明が点灯されて、獅子舞が始まりました。

群衆の拍手の中、神楽台が動き出すと、次に来たのは三番叟です。
前日の火事には驚きましたが、無事だったのが何よりです・・・・今年の祭の報道の主役、と言ったら大袈裟でしょうか。
屋台組の人が、宮本の前で押印し、挨拶の言葉を交わし、酒を受け取ると、屋台は囃子を『高い山から』に変えて出発です。

次に来たのは龍神台です。
からくり奉納の時と同じように、からくり樋を突き出し、先端に龍神が立っています。
龍神台が動き出す時に、龍神が足を踏み鳴らして舞い始めると、観衆がどよめきました。
次に見えて来たのは、大きな鳳凰と反りの大きい屋根・・・・石橋台です。
前の龍神台がからくりを動かしてくれたのを見ると、石橋台や三番叟も何かやってほしいと思ってしまうのは、欲というものでしょうか。
去年の秋祭りの曳き別れでも、向きを変える時に、わざわざ1回転して観客を沸かせた組がありましたが、祭の進行には関係なくても、そういうサーヴィスがあるとうれしいですよね。
さて、しばらく間を空けて(後に聞いた話では、二之町入り口の提灯のところで、石橋台が提灯を引っかけて壊したからだとか)見えて来たのは金色の三本幣、崑崗台です。
囃子の生演奏というのはいいですね。(組によっては出来ないところもあるのでしょうけど)
たまに笛がずれたりしても、それがまた良かったりして・・・・
続いて、五台山がやって来ました。
組の人が挨拶の中で、新調した幕の事を言ってみえましたが、その幕が提灯に隠れて見えないのは、仕方がないところですね。
つづいて、やって来たのは恵比須台です。
子供が多く乗っているようですが、囃子を演奏している人も多いのでしょう、一際囃子を大きく響かせています。
やはり、生演奏の囃子と、子供たちの歌声があってこそ、曳き別れの雰囲気が出るんでしょうね。
次に来たのは琴高台です。
この屋台の中段欄間の鯉の彫刻は、いつ見ても、そのリアルさに感心してしまいます。
さて、琴高台が動き始めたところで、その先をみると、恵比須台が向きを変えるところだったので、オレは順道場の前を離れ、恵比寿台を追いかけました。
最初の方に『今年こそ観てやろう』と書いたのは、上三之町のさんまち通りより上を屋台が通るところを観る事なんですよ。
あの、低い庇が両側から出ている狭い道を通る時、屋台が一番美しく見えるとオレは思います。(屋台は、そういうふうに設計されているはずですから)
でも、オレは長い間高山を離れていましたから、30年以上も見ていないのですよ。
ただ、今年の曳き別れの道順では、ここを通るのは恵比須台だけですから、恵比須台の動きを気にしていたわけです。
先回りして三之町へ入り、一番狭いのは原田酒造と船坂酒造の間のようなので、船坂酒造の前で待つ事にしました。
通りには、オレの他に殆ど人がいません、たまに観光客が通るくらいです。
折角これから最高のショーが始まるというのに・・・・
やがて、恵比須台がさんまち通りの角から現れました。
向きを変える時、少し廻しすぎたようで、

向きを修正して、三之町に入って来ました。
軒との間10cm、みたいなところを、恵比須台は進みます。

今にもぶつかりそうで、ハラハラしながら観ていると

恵比須台は、前を通り過ぎて行きました。
本当にぶつかりそうです。

でも、この美しさを何と表現すればいいのでしょう。
誤解を恐れず、敢えて言います。
屋台そのものの美しさなら、麒麟台の妖しいまでの美しさが一番だと誰もが認めるでしょう。
それに比べると恵比須台は、渋い美しさというか、いささか地味に思えます。
でも、この古い町並みを通る時の美しさ(町並みとの調和)では、間違いなく恵比須台が一番だと思います。
通り過ぎた恵比須台を追って歩き始めると、すぐ横からオレを呼ぶ声がしたので、見ると、良く知っているMさんでした。
Mさんを良く見ると、陣笠に腹掛けで・・・・えっ、大梃子ですか・・・・
並んで歩きながら、この狭い町並みの中で見る屋台が一番きれいだろうと思って待っていた事を話し、ここを通るのは大変なんでしょう、と訊くと、意外な事を言われました。
確かにここを通るのは大変だが、もっと大変なのが二之町の提灯だ、と言うのです。
道幅の狭い三之町は、軒下に提灯を吊るしてありますが、道幅の広い二之町は、棹を立てて提灯を吊るし、さらに花飾りのついた傘をさしてあります。
そういえば順道場の前で観ていた時、屋台の曳子が、提灯の棹を押し広げながら曳いていました。
意外な敵(?)があるものですね。
恵比須台は、屋台蔵の前を通り過ぎて通りの端まで行き、その後、屋台蔵の前まで戻って来ました。

屋台から、子供たちが降りてきましたが、やはりかなりの人数ですね。
笛を持った子も何人かいました。
子供達は、お菓子と飲み物をもらい、集まった屋台組の人達や家族に、興奮した様子で話しています。
さっきMさんに「オレは屋台のない町で育ったから、屋台のある町の人が羨ましくてしょうがない」と話したのですが、こういうところを見ると、さらに痛切にその事を思いますね。
もう40年近く前、親戚の小父さんに頼んで曳き別れの屋台に乗せてもらった時、降りてからキャラメルをもらった事を、ふと思い出しました。
屋台のない町で育った屋台好きの少年は、大人になっても屋台を追いかけてしまうのです。
オレと同様に屋台とアメフトが大好きな たけち君(やどっち15号)も、どこかで屋台を曳いているはずです。
今年の秋祭りには、東京からダイヴィング仲間達が来る事になっているのですが、ウチでのディナーを早めに済ませて、一緒に曳き別れを観に行こうと思っているのです。
今から楽しみにしているんですよ。
次回は上にも書いたように、麒麟台について、オレの思っている事を書くつもりです。
では、また。
Ciao. Arrivederci!!
このところ少し調子の悪かったiBook G4が、起動できなくなりました。
そんな時に限って、ハードウェア診断ソフトが行方不明だったりして・・・・
サブのiMacを使っていますが、違うキーボードは使いにくいものですね。
さて、ひだっちブログでも春祭の話が出尽くしたようなので、そろそろ祭の話をアップすることにしましょうか。(笑)
14日の夜は、予約が入ってなかったので、曳き別れを観に行きました。
まぁ、祭の日は、たいていヒマですからね・・・・
今まで、観たいと思いながら観れなかった事を、今年こそ観てやろうと思うのですが、今年の道順だと、観れるのは1回だけですから、見逃さないようにタイミングを見計らなければ・・・・
とっぷりと暗くなった7:30に家を出て、まずは本町通りを南へ向かいます。
丁度、大黒台が筏橋へ向けて向きを変えるところでしたが、それ以上進めそうにないので、少し戻って柳橋を渡り、上三之町を通ってさんまち通りへ出ると、目の前を麒麟台が通ります。
でも、何かおかしい・・・・よく見ると、瓔珞がひとつ余分についています。
そういえば、どこかで見た画像にも、そういうのがありましたが、あれは何なんでしょうね。
でも、麒麟台はいつ見てもきれいです。
オレは、麒麟台についていつも思う事があるのですが、ここに書くと長くなるので、次回に書く事にしましょう。
最終的には、順道場の前で観るつもりですが、まだまだ時間がかかりそうなので、上二之町を通って安川通りへ出てみると、一之町の交差点で獅子舞をやっていました。
獅子舞が終わって神楽台が動き出すのを見て、順道場へ向かいます。
順道場の前には、すでに何人かの人達が待っていました。
宮本のテントの中も、まだのんびりした雰囲気で、結構酔っぱらっている人もみえます。
でも、神楽台が二之町へ入った、と声がかかると、緊張した空気が走り、宮本の人達が所定の位置に着きます。
あ、一番前に座っているのは、ウチの料理を気に入って、いつも来て下さるHさんです。
声をかけて挨拶し、屋台が見やすそうな場所に立って待ちます。
太鼓の音を響かせながら、神楽台が近づいてくると、慌ただしく順道場の前が広く開けられ、照明が点灯されて、獅子舞が始まりました。
群衆の拍手の中、神楽台が動き出すと、次に来たのは三番叟です。
前日の火事には驚きましたが、無事だったのが何よりです・・・・今年の祭の報道の主役、と言ったら大袈裟でしょうか。
屋台組の人が、宮本の前で押印し、挨拶の言葉を交わし、酒を受け取ると、屋台は囃子を『高い山から』に変えて出発です。
次に来たのは龍神台です。
からくり奉納の時と同じように、からくり樋を突き出し、先端に龍神が立っています。
龍神台が動き出す時に、龍神が足を踏み鳴らして舞い始めると、観衆がどよめきました。
次に見えて来たのは、大きな鳳凰と反りの大きい屋根・・・・石橋台です。
前の龍神台がからくりを動かしてくれたのを見ると、石橋台や三番叟も何かやってほしいと思ってしまうのは、欲というものでしょうか。
去年の秋祭りの曳き別れでも、向きを変える時に、わざわざ1回転して観客を沸かせた組がありましたが、祭の進行には関係なくても、そういうサーヴィスがあるとうれしいですよね。
さて、しばらく間を空けて(後に聞いた話では、二之町入り口の提灯のところで、石橋台が提灯を引っかけて壊したからだとか)見えて来たのは金色の三本幣、崑崗台です。
囃子の生演奏というのはいいですね。(組によっては出来ないところもあるのでしょうけど)
たまに笛がずれたりしても、それがまた良かったりして・・・・
続いて、五台山がやって来ました。
組の人が挨拶の中で、新調した幕の事を言ってみえましたが、その幕が提灯に隠れて見えないのは、仕方がないところですね。
つづいて、やって来たのは恵比須台です。
子供が多く乗っているようですが、囃子を演奏している人も多いのでしょう、一際囃子を大きく響かせています。
やはり、生演奏の囃子と、子供たちの歌声があってこそ、曳き別れの雰囲気が出るんでしょうね。
次に来たのは琴高台です。
この屋台の中段欄間の鯉の彫刻は、いつ見ても、そのリアルさに感心してしまいます。
さて、琴高台が動き始めたところで、その先をみると、恵比須台が向きを変えるところだったので、オレは順道場の前を離れ、恵比寿台を追いかけました。
最初の方に『今年こそ観てやろう』と書いたのは、上三之町のさんまち通りより上を屋台が通るところを観る事なんですよ。
あの、低い庇が両側から出ている狭い道を通る時、屋台が一番美しく見えるとオレは思います。(屋台は、そういうふうに設計されているはずですから)
でも、オレは長い間高山を離れていましたから、30年以上も見ていないのですよ。
ただ、今年の曳き別れの道順では、ここを通るのは恵比須台だけですから、恵比須台の動きを気にしていたわけです。
先回りして三之町へ入り、一番狭いのは原田酒造と船坂酒造の間のようなので、船坂酒造の前で待つ事にしました。
通りには、オレの他に殆ど人がいません、たまに観光客が通るくらいです。
折角これから最高のショーが始まるというのに・・・・
やがて、恵比須台がさんまち通りの角から現れました。
向きを変える時、少し廻しすぎたようで、
向きを修正して、三之町に入って来ました。
軒との間10cm、みたいなところを、恵比須台は進みます。
今にもぶつかりそうで、ハラハラしながら観ていると
恵比須台は、前を通り過ぎて行きました。
本当にぶつかりそうです。
でも、この美しさを何と表現すればいいのでしょう。
誤解を恐れず、敢えて言います。
屋台そのものの美しさなら、麒麟台の妖しいまでの美しさが一番だと誰もが認めるでしょう。
それに比べると恵比須台は、渋い美しさというか、いささか地味に思えます。
でも、この古い町並みを通る時の美しさ(町並みとの調和)では、間違いなく恵比須台が一番だと思います。
通り過ぎた恵比須台を追って歩き始めると、すぐ横からオレを呼ぶ声がしたので、見ると、良く知っているMさんでした。
Mさんを良く見ると、陣笠に腹掛けで・・・・えっ、大梃子ですか・・・・
並んで歩きながら、この狭い町並みの中で見る屋台が一番きれいだろうと思って待っていた事を話し、ここを通るのは大変なんでしょう、と訊くと、意外な事を言われました。
確かにここを通るのは大変だが、もっと大変なのが二之町の提灯だ、と言うのです。
道幅の狭い三之町は、軒下に提灯を吊るしてありますが、道幅の広い二之町は、棹を立てて提灯を吊るし、さらに花飾りのついた傘をさしてあります。
そういえば順道場の前で観ていた時、屋台の曳子が、提灯の棹を押し広げながら曳いていました。
意外な敵(?)があるものですね。
恵比須台は、屋台蔵の前を通り過ぎて通りの端まで行き、その後、屋台蔵の前まで戻って来ました。
屋台から、子供たちが降りてきましたが、やはりかなりの人数ですね。
笛を持った子も何人かいました。
子供達は、お菓子と飲み物をもらい、集まった屋台組の人達や家族に、興奮した様子で話しています。
さっきMさんに「オレは屋台のない町で育ったから、屋台のある町の人が羨ましくてしょうがない」と話したのですが、こういうところを見ると、さらに痛切にその事を思いますね。
もう40年近く前、親戚の小父さんに頼んで曳き別れの屋台に乗せてもらった時、降りてからキャラメルをもらった事を、ふと思い出しました。
屋台のない町で育った屋台好きの少年は、大人になっても屋台を追いかけてしまうのです。
オレと同様に屋台とアメフトが大好きな たけち君(やどっち15号)も、どこかで屋台を曳いているはずです。
今年の秋祭りには、東京からダイヴィング仲間達が来る事になっているのですが、ウチでのディナーを早めに済ませて、一緒に曳き別れを観に行こうと思っているのです。
今から楽しみにしているんですよ。
次回は上にも書いたように、麒麟台について、オレの思っている事を書くつもりです。
では、また。
Ciao. Arrivederci!!
Posted by spock at
10:24
│Comments(10)
2008年04月10日
車検が近づいて・・・・
Ciao. spockです。
4月になったとはいえ、朝晩の寒さは何なんだろうと思っていたら、やっと、この2〜3日は春らしい暖かさになってきましたね。
早いもので、ウチの化け猫

を高山に連れて来てから、もう2年経ちました。
また、車検を通さなければなりません。
で、前から気になっていた、クーラントとホースの交換をする事にしました。
と言っても、いつも見てもらっているKさんにお願いしたのですけど・・・・
去年の時点で、クーラントに錆が混じっているのが分かっていた上、エンジンからラジエーターへ繋がるアッパーホースを摘むと、パリパリと音がするので、クーラントと同時に、ホースも交換しようと思っていたのです。
ヘインズのマニュアルによると、このV12エンジンには21ℓ の冷却水が必要なので、18ℓ 缶入りのクーラントを用意しました。(半分の9ℓ を使うと、約43%の濃度になるので、ちょうどいいのです)

ホースは、新品のホースキットをイギリスから取り寄せる事も考えましたが、部品取り用のクーペについていたのが新しそうだったので、取り外して洗っておきました。
このクルマを見てもらっているKさんは、「趣味でやっているのだから」と言って、お礼を受け取ってくれないので、その代わりにワインを2本選んで持って行く事にしました。
Kさんがいなかったら、絶対にこんなクルマを持つ事はできなかったでしょうね。
6日の朝9時、Kさんのガレージで、作業開始です。
ジャッキアップしてウマをかませ、Kさんが潜り込んで、ロアーホースのホースバンドのネジを緩めます。
横から作業を見ていると、完全に『知恵の輪』状態です。
パイプやホースの隙間から手を入れ、ホースの通るところを探しながら、ラジエーターの下側からホースを抜くと

錆で茶色くなった冷却水が流れ出しました。
茶色い水が出てしまったところで、アッパーホース2本とロアーホースを交換します。
取り外したロアーホースの中を見ると、錆が固まっているようなので、逆さにして叩くと、錆がこんなに出てきました。

きれいな水を注入し、エンジンを回して、減った分を足しながら、サーモスタットが開くのを待ち、ロアーホースを外して中の水を流します。
それを3回繰り返しましたが、なかなか水がきれいになりません。
で、ロアーホースを外したまま、ホースを突っ込んで水を流してみると・・・・初めは濁っていた水も、すぐにきれいになりました。
このやり方が正解だったようです。

リザーヴァータンク

にもホースを突っ込んでみると、錆色の水が噴き出してきました。
まわりに飛び散って、茶色い痕が残っています。

錆の一番の原因は、ここにあったようです。
いつも見ているウェブサイトの『ジャガーメンテナンスコーナー』というBBSでも、タンクの錆について書かれていた事がありましたから、このタンクが錆の原因である事は間違いないようです。
流れ出す水がきれいになったところで、ロアーホースを取り付け、9ℓ のクーラントを注入し、その後、いっぱいになるまで水を入れます。

エンジンを回して、エアー抜きをしながら減った分を足し、リザーヴァータンクを満タンにして終了です。
しばらくは、乗った後に水の量を点検しなければいけませんね。
今回、こうして手を入れた事で、以前にこのクルマに手を入れた人が、かなり手の込んだ事をやっている事が分かりました。
ホースも交換したもののようで、熱の当たる部分には、古いホースを切り裂いたものが、タイラップで巻き付けてありました。
オレもこのクルマを大切に扱ってやらなければ・・・・
少し前から、ブレーキをかけた時、左前輪から微かな異音がする事が気になっていたので、それも見てもらったのですが・・・・原因は、全く意外な事でした。
何と、ホイールナットが緩んでいたのですよ。
以前、カーメンテナンスの本に、ホイールナットにはテーパーがついているので、体重をかけた程度に締めれば充分で、締め過ぎは良くない、と書かれていたのを読んで、その通りにしていたのですが、Kさんの話では、ジャガーのホイールナットはテーパーがついていないタイプなので、目一杯締めておかないと緩みやすいのだそうです。
ここは、完全に間違えていました。
まぁ、何分古いクルマですから、いつも音には注意しているのですが、そのおかげで早く気が付く事ができたと思います。
ところで、以前読んだ本によると、クルマの一年は、人間の2.5才にあたるのだそうです。
それが本当なら、ウチの化け猫とオレは、ちょうど今、ほぼ同じ年齢だという事になります。
で、来年からは、化け猫の方が早く歳をとる事になるわけです。
大切に、労ってやらなければいけませんね。
後は、夏までに、ガスが抜けてしまって、全く効かないエアコンの修理をする予定です。
高圧ホースを修理して付け替え、ドライヤーを新品に交換し、ガスを入れてやれば復活するはずです。
近いうちに、イギリスから部品を取り寄せる予定でいます。
イギリスのクルマの部品は、それがどんなに古いクルマの部品であっても、大抵手に入ります。
それに、値段も意外なほど安いのですよ。
それに対し、日本のクルマは、製造終了後8年経つと、部品の供給が止まります。
全く、考え方が違うのですね。
いつも思うのですが、こういう燃費の良くないクルマに手を入れながら長く乗るのと、もっと燃費がいいクルマを数年毎に買い替えながら乗るのでは、本当の意味で『エコ』なのはどっちなんでしょうね?
では、また。
Ciao. Arrivederci!!
4月になったとはいえ、朝晩の寒さは何なんだろうと思っていたら、やっと、この2〜3日は春らしい暖かさになってきましたね。
早いもので、ウチの化け猫

を高山に連れて来てから、もう2年経ちました。
また、車検を通さなければなりません。
で、前から気になっていた、クーラントとホースの交換をする事にしました。
と言っても、いつも見てもらっているKさんにお願いしたのですけど・・・・
去年の時点で、クーラントに錆が混じっているのが分かっていた上、エンジンからラジエーターへ繋がるアッパーホースを摘むと、パリパリと音がするので、クーラントと同時に、ホースも交換しようと思っていたのです。
ヘインズのマニュアルによると、このV12エンジンには21ℓ の冷却水が必要なので、18ℓ 缶入りのクーラントを用意しました。(半分の9ℓ を使うと、約43%の濃度になるので、ちょうどいいのです)
ホースは、新品のホースキットをイギリスから取り寄せる事も考えましたが、部品取り用のクーペについていたのが新しそうだったので、取り外して洗っておきました。
このクルマを見てもらっているKさんは、「趣味でやっているのだから」と言って、お礼を受け取ってくれないので、その代わりにワインを2本選んで持って行く事にしました。
Kさんがいなかったら、絶対にこんなクルマを持つ事はできなかったでしょうね。
6日の朝9時、Kさんのガレージで、作業開始です。
ジャッキアップしてウマをかませ、Kさんが潜り込んで、ロアーホースのホースバンドのネジを緩めます。
横から作業を見ていると、完全に『知恵の輪』状態です。
パイプやホースの隙間から手を入れ、ホースの通るところを探しながら、ラジエーターの下側からホースを抜くと
錆で茶色くなった冷却水が流れ出しました。
茶色い水が出てしまったところで、アッパーホース2本とロアーホースを交換します。
取り外したロアーホースの中を見ると、錆が固まっているようなので、逆さにして叩くと、錆がこんなに出てきました。
きれいな水を注入し、エンジンを回して、減った分を足しながら、サーモスタットが開くのを待ち、ロアーホースを外して中の水を流します。
それを3回繰り返しましたが、なかなか水がきれいになりません。
で、ロアーホースを外したまま、ホースを突っ込んで水を流してみると・・・・初めは濁っていた水も、すぐにきれいになりました。
このやり方が正解だったようです。
リザーヴァータンク
にもホースを突っ込んでみると、錆色の水が噴き出してきました。
まわりに飛び散って、茶色い痕が残っています。
錆の一番の原因は、ここにあったようです。
いつも見ているウェブサイトの『ジャガーメンテナンスコーナー』というBBSでも、タンクの錆について書かれていた事がありましたから、このタンクが錆の原因である事は間違いないようです。
流れ出す水がきれいになったところで、ロアーホースを取り付け、9ℓ のクーラントを注入し、その後、いっぱいになるまで水を入れます。
エンジンを回して、エアー抜きをしながら減った分を足し、リザーヴァータンクを満タンにして終了です。
しばらくは、乗った後に水の量を点検しなければいけませんね。
今回、こうして手を入れた事で、以前にこのクルマに手を入れた人が、かなり手の込んだ事をやっている事が分かりました。
ホースも交換したもののようで、熱の当たる部分には、古いホースを切り裂いたものが、タイラップで巻き付けてありました。
オレもこのクルマを大切に扱ってやらなければ・・・・
少し前から、ブレーキをかけた時、左前輪から微かな異音がする事が気になっていたので、それも見てもらったのですが・・・・原因は、全く意外な事でした。
何と、ホイールナットが緩んでいたのですよ。
以前、カーメンテナンスの本に、ホイールナットにはテーパーがついているので、体重をかけた程度に締めれば充分で、締め過ぎは良くない、と書かれていたのを読んで、その通りにしていたのですが、Kさんの話では、ジャガーのホイールナットはテーパーがついていないタイプなので、目一杯締めておかないと緩みやすいのだそうです。
ここは、完全に間違えていました。
まぁ、何分古いクルマですから、いつも音には注意しているのですが、そのおかげで早く気が付く事ができたと思います。
ところで、以前読んだ本によると、クルマの一年は、人間の2.5才にあたるのだそうです。
それが本当なら、ウチの化け猫とオレは、ちょうど今、ほぼ同じ年齢だという事になります。
で、来年からは、化け猫の方が早く歳をとる事になるわけです。
大切に、労ってやらなければいけませんね。
後は、夏までに、ガスが抜けてしまって、全く効かないエアコンの修理をする予定です。
高圧ホースを修理して付け替え、ドライヤーを新品に交換し、ガスを入れてやれば復活するはずです。
近いうちに、イギリスから部品を取り寄せる予定でいます。
イギリスのクルマの部品は、それがどんなに古いクルマの部品であっても、大抵手に入ります。
それに、値段も意外なほど安いのですよ。
それに対し、日本のクルマは、製造終了後8年経つと、部品の供給が止まります。
全く、考え方が違うのですね。
いつも思うのですが、こういう燃費の良くないクルマに手を入れながら長く乗るのと、もっと燃費がいいクルマを数年毎に買い替えながら乗るのでは、本当の意味で『エコ』なのはどっちなんでしょうね?
では、また。
Ciao. Arrivederci!!
2008年04月07日
ristoranteの矜持 その2
Ciao. spockです。
先日、パーティーが終わって後片付けをしている時、裏口から呼ぶ声がしたので覗いてみると、同級生のテノール歌手、水口 聡でした。
水口はいつも、高山へ帰ってくると、まずウチへ寄って、カウンターでワインを飲んでから家に帰るんですよ。
その時もカウンターでワインを飲みながら、一時間ほど話していたのですが、その時にウチの化け猫の写真を見せたら、ひと目で気に入ったようなんです。
で、オレがよく見るウェブサイトに出ている、92年式の後期型を薦めておきましたが、もし水口が本当にXJ-Sを買ったら、屋根無しクラブに入る事を勧めるつもりです。
水口が、3月27日のサッカーの試合の前に『君が代』を歌ったのをテレビで見ましたが、あんなところで独唱するのは、劇場で歌うより緊張するでしょうね。
でも、すごい事ですよね。(その後の試合は全くしょーもなかったそうですが・・・・)
さて、前回は『ristorante を名乗る以上は絶対外せないと思う事』2つのうちの1つ『非日常的空間である事』について書きました。
今回は、残りのもう1つ『コース料理だけを提供するために予約制にする事』について書きます。
前回、イタリアの飲食店には明確な区分があるという事を書きましたが、初めて知ったと言われる方も多いと思います
イタリア語の辞書の ristorante のところをスキャニングしてみました。
これで、大体の区分が解ると思います。

前回のブログのぷーさんのコメントに「多分、東京でも区分わけが明確にわからない方のほうが多いかもしれませんね。」とありますが、それは本当の事だと思います。
ただ、問題なのは、店側にもそういう事が解っていないところが多い事ですね。
ristorante でググって見ると、多くの店が出てきますが、ピッツァを出している店がいかに多いか・・・・
実際のところ、ristorante というのは、あまり儲かる営業形態ではないのですよ。
原価率は高いし、回転率は低いし、人件費はかかるし・・・・だから、ランチに限ってピッツァを出してお客さんを呼ぶ、というやり方は許されると思います。(背に腹は代えられませんからね)
でも、ディナーで、ましてや、コースの中にピッツァを入れるのは、イタリアの伝統をバカにしているとしか思えません。
それなら ristorante を名乗るなよ!!
何を考えているんでしょうね・・・・いや、何も考えてないか・・・・

さて、これはオレの料理の原点とも言える、ベルガモの Taverna del Colleoni のメニューです。
Taverna del Colleoni は、誰もが ristorante と認める店でしたが、由緒ある名前ということで、taverna を名乗っていたわけです。
古くからある店の場合、こういう事は結構あるようです。(ただし、この逆、営業形態が trattoria や taverna の店が ristorante を名乗る事はありませんよ)
中を見ると

gli Antipasti (前菜)、i Primi piatti (パスタ、スープ、リゾットなど)、le Carni (肉料理)、i Pesci (魚料理)とあって、それぞれ8〜9種の料理が並び、最後にチーズの盛り合わせが出ています。
店によっては、他に卵料理やサラダを書いているところもあります。
前回書いたように、ristorante では、前菜、プリーモピアット、セコンドピアット、ドルチェとオーダーするのが基本ですから、この中から料理を選んでオーダーし、自分のコースを作るわけです。
その時の体調によっては、前菜の後、肉料理で終りというのもアリですが・・・・
数年前に流行った『プリフィクス』というコースは、それを手軽にできるようにしたもので、それなりに意義はあったと思うのですが、また別の問題があるのですよ。
プリフィクスは、ある程度料理が解っている人には歓迎されましたが、料理に詳しくない人の場合、逆に戸惑ってしまってパニックに陥ったり、最初から最後まで似たような味付けの料理が並んでしまう事がありがちなんですよ。
選び方は『自己責任』と言ってしまえばそれまでですが、やはりそれは良くないですね。
それなら、予約の時に、お客さんの好みや希望を聞いた上で、きちんとしたコースを考えてお出しするのが最良の方法だと、オレは思ったのです。
で、オレ一人でそれをやり、きちんとした料理をお出しするには、予約制にするしか選択肢はなかったのですよ。
でも、実際にやってみた結果、LA FENICE のやり方として正解だったと思っています。
その事については、ちょうど1年前に、『ムダの美学』というタイトルで詳しく書いた事があるので、少し長くなりますが、その部分を再掲してみます。
でも、オレは今のやり方を変えるつもりはありません。
なぜなら、この店を始める時に決めた方針のうちの、一番大切な部分をなくしてしまう事になるからです。
その方針とは
1 食材の仕入れは必要最小限にする事。
2 自分で出来る事は自分でやる事。
3 お客さんに楽しんでもらうために必要なムダをなくさない事。
の3つなのですが、この3番目にある『必要なムダ』というのが LA FENICE の存在価値を生み出しているのだと思っているわけで、そのために、やり繰りと言うか努力をしているのです。
1に関しては、店を予約制にした事で食材の仕入れは必要最小限で済むわけで、他の店に比べれば、かなりムダを少なくする事ができていると思います。
2について、『自分で出来る事』はいろいろあります。
まず、料理に関しては、前菜からデザートまで、すべて『手作り』にする事。(手作りでないのは、イタリアから輸入している、乾燥トマトのオイル漬とロゼッタ(パン)とグリッシーニくらいでしょうか)
それから、上に書いたとおり確定申告も自分でやったし、機械類のメンテナンスもできるところは自分でやりますね。
店の看板やパンフレットも自分で作ったし、120インチのスクリーンも自分で天井に取り付けたし・・・・あと、ウェブサイトを作らなければいけないのだけれど、それはなかなか進みませんねぇ。(ドメインは2年前に取得済なんですけどね・・・・)
まぁ、料理については当然の事ですが、それ以外の事では、かなり経費の節約ができていると思います。
『食材のムダをなくす事』と『自分で出来る事は自分でやる事』で、料理の価格設定をかなり下げる事ができていると思うのです。
自分で言うのもなんですが、これ程良心的な値段の店は、そんなにはないと思いますよ。
ランチが950円というのも内容を考えればスゴく安いと思うし、5000円でお出ししているディナーのコースは、赤坂の店で10000円だったコースより品数が多いですから、場所代などを差し引いて考えたとしてもメチャメチャ安いと思います。
ムダを切り詰めて安価で提供するのは、商売をする上ではあたりまえのことなのでしょうが、LA FENICE の場合は、そこから先が違うのです。
まぁ、何事によらず『ムダが多いもの(効率の悪いもの)程楽しい』というのは事実だと思います。
サーヴィスする側から言い換えれば『楽しんでもらうためには、出来る限りムダを残す』と言う事になると思います。
ですから LA FENICE では、見えないところで切り詰めたムダを、見えるところで大放出しているんですよ。
ウチの店のオープン当初は、予約制にこだわっている事もあって『お高く留まっている』と思われていたようですが、だんだん理由を理解して下さる方が増えてきました。
オレが予約制にこだわった理由は、『一人で料理を作る以上、きちんとした料理を作るためには二組以上の料理を同時進行で作るのは絶対に避けるべきだ』と考えたからです。
ですから、一晩に二組以上の予約の申込みがあった場合は、一時間半以上間をあける事ができなければ、後のお客さんはお断りするのです。
せっかく電話して下さったのに、お断りするのは心苦しく思いますが、いい料理を出すためにはそうするしかないですからね。
まぁ、早い話が、LA FENICE では『予約=貸切り』だと思ってもらえばいいわけです。
で、その時間は、オレはお客さんの『専属料理人』というわけですから、お客さんの希望に出来る限り添った料理を作ります。
お客さんの人数が何人であろうとこのスタンスは変えませんから、二人でも、貸切りで希望の料理を味わえるわけです。
これがオレの考える『お客さんに楽しんでもらうために必要なムダ』なんですよ。
『利益の追求こそ経営の王道』と思っている人から見れば、狂気の沙汰としか思えないでしょうけどね・・・・・
こんな事を言っても、単なる自己満足だったらどうしようかと思っていたのですが、ウチに来てくれたお客さんの中で、この業界に詳しい人達・・・同業者や日本中を食べ歩いている人・・・から、「安過ぎるだろう」とか「儲けるつもりがあるのか」とか言われたところをみると、自己満足ではないんだろうな、と思います。
まぁ、言うならば、ristorante の料理を trattoria の値段で食べてもらえるのが LA FENICE だ、という事ですかね。
もう20年以上も前、その頃働いていた『ベルゲン』のオーナーの安田氏が、こんな事を話してくれました。
儲けるつもりなら ristorante はやるな、とイタリアでは言われている。
実際、パスタだけを出す方が、原価も安いし、回転もいいし、人を使わなくてもいいから、儲けが出る。
でも、この仕事をやる者ならだれもが、儲けは少なくても、いつかは ristorante をやりたい、と思うもの。
だから、独立する時は、まずパスタハウスをやって、カネを貯めてから、次に ristorante を始める事が多い。
オレは、カネも無いのに、いきなり ristorante を始めたわけですが、確かに全然儲けが出ないので、毎月やりくりに苦労しています。
まぁ、そんな事は解っていましたから、こんなものなんだろうなと思いながらやっていますが、でも、ristorante をやる事ができて、本当に幸せだと思いますね。
もっとも、オレの場合は、一番険しい道を選んでしまったのですけれど・・・・
まぁ、基本的に、人と同じ事をしたくない人間ですから、他の店と違う事を考えていたらこうなったわけですが、初めて来られたお客さんの中には、戸惑われる方もおられます。
二人だけでも貸切りで、BGMも流れていない店なんて、他にはないでしょうね。(BGMを流して欲しいと言われれば流しますけど)
でもオレは、料理を楽しんでもらうには、それが一番いい方法だと思っているんです。
だから、このやり方を変えるつもりはありませんよ。
ウチは ristorante を名乗っているのですから、気軽に来て下さいとは言いません。(社交辞令的に言った事はありますけど・・・・)
全ての人に愛される店にしようなんて、思いもしません。
誰かに本当に愛されるためには、他の誰かには嫌われなければならないのが当然の事なのですから・・・・
ウチの基本的姿勢は、お客さんと対等である事。
愛想も言わなければ、へりくだる事もないけれど、お客さんからは遠慮なく希望(あるいはワガママ)を言ってもらい、出来る限り応える・・・・これがウチのやり方なんですよ。
媚を売らず、常に自然体でいる事・・・・ristorante を名乗る LA FENICE の矜持です。
まぁ、ウチを愛して下さる方が、もう少し増えるといいんですけどね・・・・
大人の世界がきちんと確立している欧米では、ristorante のような場所に子供が行く事はありません。
だからウチでは、オープンする時、子供用の椅子を用意する事は全く考えませんでした。
(一応、厚みのあるクッションを置いていますが・・・・)
ところが、意外な事に、ウチには子供のファンが多いのですよ。
子供の誕生日に、どこへ行きたいか訊いたら、ラ フェニーチェと言うので・・・・という予約が結構あります。
ウチは一組毎の貸切りになりますから、子供連れで来られる方が結構おられるのですが、そういう時に一緒に来た子供さんが、ウチの料理を気に入ってくれたのでしょう。
ちゃんと解ってくれる小さなお客さんも、大切にしなければいけませんね。
小さなお客さん、と言えば、ウチの前菜に必ず出る Prosciutto crudo (生ハム)を、グリッシーニに巻き付けて食べるのが一番上手いのは、YちゃんとMちゃん、二人の女の子です。
二人は西小学校の同級生なのですが、担任の先生に、二人してLA FENICEの宣伝をしてくれたと聞きました。
ありがたい話です。(でも、先生は驚いたでしょうね・・・・)
こういうお客さんがいてくれる事を、幸せだと思います。
子供の話が出たついでに・・・・
オレは以前から、子供に迎合した料理を食べさせる事には反対でした。
カレーは辛いのがあたりまえだし、スパゲッティは固いのが普通なわけで、子供だからといって、甘ったるいカレーや、うどんみたいに柔らかいスパゲッティを食べさせるのは、絶対に間違いだと思います。
実際ウチでは、子供だからといって(メニューを変える事はあっても)料理を変える事はありませんが、子供はちゃんと評価してくれているわけですから、オレの考え方は間違っていないと思いますね。
さて、もう一度最初の画像を観て下さい。

ristorante の下に、ristorare という単語が出ていますね。
で、ristorare の意味を見ると、(食事、休養で)元気を回復する、とありますが、ristorare の現在分詞が ristorante なんです。
そう、ristorante は、食事で元気を回復してもらう場所なんですよ。
来て頂いたお客さんに、元気になって帰ってもらう事、それが ristorante の役目なんですね。
その役割を果たせるように、これからも、喜んでもらえる料理を作っていきますよ。
では、また。
Ciao. Arrivederci!!
先日、パーティーが終わって後片付けをしている時、裏口から呼ぶ声がしたので覗いてみると、同級生のテノール歌手、水口 聡でした。
水口はいつも、高山へ帰ってくると、まずウチへ寄って、カウンターでワインを飲んでから家に帰るんですよ。
その時もカウンターでワインを飲みながら、一時間ほど話していたのですが、その時にウチの化け猫の写真を見せたら、ひと目で気に入ったようなんです。
で、オレがよく見るウェブサイトに出ている、92年式の後期型を薦めておきましたが、もし水口が本当にXJ-Sを買ったら、屋根無しクラブに入る事を勧めるつもりです。
水口が、3月27日のサッカーの試合の前に『君が代』を歌ったのをテレビで見ましたが、あんなところで独唱するのは、劇場で歌うより緊張するでしょうね。
でも、すごい事ですよね。(その後の試合は全くしょーもなかったそうですが・・・・)
さて、前回は『ristorante を名乗る以上は絶対外せないと思う事』2つのうちの1つ『非日常的空間である事』について書きました。
今回は、残りのもう1つ『コース料理だけを提供するために予約制にする事』について書きます。
前回、イタリアの飲食店には明確な区分があるという事を書きましたが、初めて知ったと言われる方も多いと思います
イタリア語の辞書の ristorante のところをスキャニングしてみました。
これで、大体の区分が解ると思います。

前回のブログのぷーさんのコメントに「多分、東京でも区分わけが明確にわからない方のほうが多いかもしれませんね。」とありますが、それは本当の事だと思います。
ただ、問題なのは、店側にもそういう事が解っていないところが多い事ですね。
ristorante でググって見ると、多くの店が出てきますが、ピッツァを出している店がいかに多いか・・・・
実際のところ、ristorante というのは、あまり儲かる営業形態ではないのですよ。
原価率は高いし、回転率は低いし、人件費はかかるし・・・・だから、ランチに限ってピッツァを出してお客さんを呼ぶ、というやり方は許されると思います。(背に腹は代えられませんからね)
でも、ディナーで、ましてや、コースの中にピッツァを入れるのは、イタリアの伝統をバカにしているとしか思えません。
それなら ristorante を名乗るなよ!!
何を考えているんでしょうね・・・・いや、何も考えてないか・・・・
さて、これはオレの料理の原点とも言える、ベルガモの Taverna del Colleoni のメニューです。
Taverna del Colleoni は、誰もが ristorante と認める店でしたが、由緒ある名前ということで、taverna を名乗っていたわけです。
古くからある店の場合、こういう事は結構あるようです。(ただし、この逆、営業形態が trattoria や taverna の店が ristorante を名乗る事はありませんよ)
中を見ると
gli Antipasti (前菜)、i Primi piatti (パスタ、スープ、リゾットなど)、le Carni (肉料理)、i Pesci (魚料理)とあって、それぞれ8〜9種の料理が並び、最後にチーズの盛り合わせが出ています。
店によっては、他に卵料理やサラダを書いているところもあります。
前回書いたように、ristorante では、前菜、プリーモピアット、セコンドピアット、ドルチェとオーダーするのが基本ですから、この中から料理を選んでオーダーし、自分のコースを作るわけです。
その時の体調によっては、前菜の後、肉料理で終りというのもアリですが・・・・
数年前に流行った『プリフィクス』というコースは、それを手軽にできるようにしたもので、それなりに意義はあったと思うのですが、また別の問題があるのですよ。
プリフィクスは、ある程度料理が解っている人には歓迎されましたが、料理に詳しくない人の場合、逆に戸惑ってしまってパニックに陥ったり、最初から最後まで似たような味付けの料理が並んでしまう事がありがちなんですよ。
選び方は『自己責任』と言ってしまえばそれまでですが、やはりそれは良くないですね。
それなら、予約の時に、お客さんの好みや希望を聞いた上で、きちんとしたコースを考えてお出しするのが最良の方法だと、オレは思ったのです。
で、オレ一人でそれをやり、きちんとした料理をお出しするには、予約制にするしか選択肢はなかったのですよ。
でも、実際にやってみた結果、LA FENICE のやり方として正解だったと思っています。
その事については、ちょうど1年前に、『ムダの美学』というタイトルで詳しく書いた事があるので、少し長くなりますが、その部分を再掲してみます。
でも、オレは今のやり方を変えるつもりはありません。
なぜなら、この店を始める時に決めた方針のうちの、一番大切な部分をなくしてしまう事になるからです。
その方針とは
1 食材の仕入れは必要最小限にする事。
2 自分で出来る事は自分でやる事。
3 お客さんに楽しんでもらうために必要なムダをなくさない事。
の3つなのですが、この3番目にある『必要なムダ』というのが LA FENICE の存在価値を生み出しているのだと思っているわけで、そのために、やり繰りと言うか努力をしているのです。
1に関しては、店を予約制にした事で食材の仕入れは必要最小限で済むわけで、他の店に比べれば、かなりムダを少なくする事ができていると思います。
2について、『自分で出来る事』はいろいろあります。
まず、料理に関しては、前菜からデザートまで、すべて『手作り』にする事。(手作りでないのは、イタリアから輸入している、乾燥トマトのオイル漬とロゼッタ(パン)とグリッシーニくらいでしょうか)
それから、上に書いたとおり確定申告も自分でやったし、機械類のメンテナンスもできるところは自分でやりますね。
店の看板やパンフレットも自分で作ったし、120インチのスクリーンも自分で天井に取り付けたし・・・・あと、ウェブサイトを作らなければいけないのだけれど、それはなかなか進みませんねぇ。(ドメインは2年前に取得済なんですけどね・・・・)
まぁ、料理については当然の事ですが、それ以外の事では、かなり経費の節約ができていると思います。
『食材のムダをなくす事』と『自分で出来る事は自分でやる事』で、料理の価格設定をかなり下げる事ができていると思うのです。
自分で言うのもなんですが、これ程良心的な値段の店は、そんなにはないと思いますよ。
ランチが950円というのも内容を考えればスゴく安いと思うし、5000円でお出ししているディナーのコースは、赤坂の店で10000円だったコースより品数が多いですから、場所代などを差し引いて考えたとしてもメチャメチャ安いと思います。
ムダを切り詰めて安価で提供するのは、商売をする上ではあたりまえのことなのでしょうが、LA FENICE の場合は、そこから先が違うのです。
まぁ、何事によらず『ムダが多いもの(効率の悪いもの)程楽しい』というのは事実だと思います。
サーヴィスする側から言い換えれば『楽しんでもらうためには、出来る限りムダを残す』と言う事になると思います。
ですから LA FENICE では、見えないところで切り詰めたムダを、見えるところで大放出しているんですよ。
ウチの店のオープン当初は、予約制にこだわっている事もあって『お高く留まっている』と思われていたようですが、だんだん理由を理解して下さる方が増えてきました。
オレが予約制にこだわった理由は、『一人で料理を作る以上、きちんとした料理を作るためには二組以上の料理を同時進行で作るのは絶対に避けるべきだ』と考えたからです。
ですから、一晩に二組以上の予約の申込みがあった場合は、一時間半以上間をあける事ができなければ、後のお客さんはお断りするのです。
せっかく電話して下さったのに、お断りするのは心苦しく思いますが、いい料理を出すためにはそうするしかないですからね。
まぁ、早い話が、LA FENICE では『予約=貸切り』だと思ってもらえばいいわけです。
で、その時間は、オレはお客さんの『専属料理人』というわけですから、お客さんの希望に出来る限り添った料理を作ります。
お客さんの人数が何人であろうとこのスタンスは変えませんから、二人でも、貸切りで希望の料理を味わえるわけです。
これがオレの考える『お客さんに楽しんでもらうために必要なムダ』なんですよ。
『利益の追求こそ経営の王道』と思っている人から見れば、狂気の沙汰としか思えないでしょうけどね・・・・・
こんな事を言っても、単なる自己満足だったらどうしようかと思っていたのですが、ウチに来てくれたお客さんの中で、この業界に詳しい人達・・・同業者や日本中を食べ歩いている人・・・から、「安過ぎるだろう」とか「儲けるつもりがあるのか」とか言われたところをみると、自己満足ではないんだろうな、と思います。
まぁ、言うならば、ristorante の料理を trattoria の値段で食べてもらえるのが LA FENICE だ、という事ですかね。
もう20年以上も前、その頃働いていた『ベルゲン』のオーナーの安田氏が、こんな事を話してくれました。
儲けるつもりなら ristorante はやるな、とイタリアでは言われている。
実際、パスタだけを出す方が、原価も安いし、回転もいいし、人を使わなくてもいいから、儲けが出る。
でも、この仕事をやる者ならだれもが、儲けは少なくても、いつかは ristorante をやりたい、と思うもの。
だから、独立する時は、まずパスタハウスをやって、カネを貯めてから、次に ristorante を始める事が多い。
オレは、カネも無いのに、いきなり ristorante を始めたわけですが、確かに全然儲けが出ないので、毎月やりくりに苦労しています。
まぁ、そんな事は解っていましたから、こんなものなんだろうなと思いながらやっていますが、でも、ristorante をやる事ができて、本当に幸せだと思いますね。
もっとも、オレの場合は、一番険しい道を選んでしまったのですけれど・・・・
まぁ、基本的に、人と同じ事をしたくない人間ですから、他の店と違う事を考えていたらこうなったわけですが、初めて来られたお客さんの中には、戸惑われる方もおられます。
二人だけでも貸切りで、BGMも流れていない店なんて、他にはないでしょうね。(BGMを流して欲しいと言われれば流しますけど)
でもオレは、料理を楽しんでもらうには、それが一番いい方法だと思っているんです。
だから、このやり方を変えるつもりはありませんよ。
ウチは ristorante を名乗っているのですから、気軽に来て下さいとは言いません。(社交辞令的に言った事はありますけど・・・・)
全ての人に愛される店にしようなんて、思いもしません。
誰かに本当に愛されるためには、他の誰かには嫌われなければならないのが当然の事なのですから・・・・
ウチの基本的姿勢は、お客さんと対等である事。
愛想も言わなければ、へりくだる事もないけれど、お客さんからは遠慮なく希望(あるいはワガママ)を言ってもらい、出来る限り応える・・・・これがウチのやり方なんですよ。
媚を売らず、常に自然体でいる事・・・・ristorante を名乗る LA FENICE の矜持です。
まぁ、ウチを愛して下さる方が、もう少し増えるといいんですけどね・・・・
大人の世界がきちんと確立している欧米では、ristorante のような場所に子供が行く事はありません。
だからウチでは、オープンする時、子供用の椅子を用意する事は全く考えませんでした。
(一応、厚みのあるクッションを置いていますが・・・・)
ところが、意外な事に、ウチには子供のファンが多いのですよ。
子供の誕生日に、どこへ行きたいか訊いたら、ラ フェニーチェと言うので・・・・という予約が結構あります。
ウチは一組毎の貸切りになりますから、子供連れで来られる方が結構おられるのですが、そういう時に一緒に来た子供さんが、ウチの料理を気に入ってくれたのでしょう。
ちゃんと解ってくれる小さなお客さんも、大切にしなければいけませんね。
小さなお客さん、と言えば、ウチの前菜に必ず出る Prosciutto crudo (生ハム)を、グリッシーニに巻き付けて食べるのが一番上手いのは、YちゃんとMちゃん、二人の女の子です。
二人は西小学校の同級生なのですが、担任の先生に、二人してLA FENICEの宣伝をしてくれたと聞きました。
ありがたい話です。(でも、先生は驚いたでしょうね・・・・)
こういうお客さんがいてくれる事を、幸せだと思います。
子供の話が出たついでに・・・・
オレは以前から、子供に迎合した料理を食べさせる事には反対でした。
カレーは辛いのがあたりまえだし、スパゲッティは固いのが普通なわけで、子供だからといって、甘ったるいカレーや、うどんみたいに柔らかいスパゲッティを食べさせるのは、絶対に間違いだと思います。
実際ウチでは、子供だからといって(メニューを変える事はあっても)料理を変える事はありませんが、子供はちゃんと評価してくれているわけですから、オレの考え方は間違っていないと思いますね。
さて、もう一度最初の画像を観て下さい。

ristorante の下に、ristorare という単語が出ていますね。
で、ristorare の意味を見ると、(食事、休養で)元気を回復する、とありますが、ristorare の現在分詞が ristorante なんです。
そう、ristorante は、食事で元気を回復してもらう場所なんですよ。
来て頂いたお客さんに、元気になって帰ってもらう事、それが ristorante の役目なんですね。
その役割を果たせるように、これからも、喜んでもらえる料理を作っていきますよ。
では、また。
Ciao. Arrivederci!!
Posted by spock at
08:27
│Comments(4)