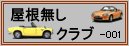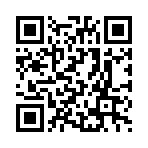スポンサーリンク
この広告は一定期間(1ヶ月以上)更新のないブログに表示されます。
ブログ記事の情報が古い場合がありますのでご注意下さい。
(ブログオーナーが新しい記事を投稿すると非表示になります。)
ブログ記事の情報が古い場合がありますのでご注意下さい。
(ブログオーナーが新しい記事を投稿すると非表示になります。)
2019年01月24日
BAR LA FENICE 始めます
Ciao. spock です。
寒い日が続きますねぇ。
まぁ、雪が少ない事がありがたいですが。
久しぶりの更新になりますが、今回は新しい営業形態についてのお知らせです・・・・と言っても、実質は変わらないんですけどね。
そして、最後に非常にうれしい事を報告しますので、最後まで読んで下さい。
ウチのディナーが予約制である事は、よ~く知ってもらっていると思います。
まぁ、それがウチの特徴であり、また特殊性でもあるのですが、初めての人にとって非常に取っ付きにくい店である事は、自分でもよく解っていたわけですよ。
だからといって、やり方を変えるつもりは毛頭なかったわけで、そのまま13年半続けてきたのだけれど、ここへ来て、自分の中に気持ちの変化が現れて来て、「現状のやり方を変える事無く、もっと取っ付きやすい店にする事はできないか」と考えていて思いついたのが、予約の入っていない日や予約が終った後の時間帯を、BAR として営業しようという事。
なので、BAR LA FENICE としての営業を始めます。
もっとも、やる事自体は今までもやっていた事で、そういう時間帯にカウンターは空けていたんだけれど、来られるのは、ウチの事をよく分かっている常連のお客さんが殆どで、初めてのお客さんが入ってこられる事は、まずなかったわけですよ。
それが何故かというと、メニューがなかったから・・・・というか、敢えてメニュー無しで、お客さんと相談しながら決める、というスタイルでやっているんだけれど、たいていのお客さんから「そんなに安くていいの」と言われるくらい、良心的な価格設定でやってはいるものの、その事を知らない「予約制の店=高級店」と思っている人から見れば、「いくら取られるかわからない」と思われても仕方がないのかなと・・・・
で、まずはメニューを作って、料理や飲み物の値段をハッキリと提示するところから始めようかと思っているわけですよ。
それで、作ってみたメニューが、こんな感じ。




まだ、抜けているところもあるし、訂正しなければならないところもあるんだけれど、だいたいこんな感じでやろうと思っているので、今週から始めていこうかと思います。
まぁ、実際に仕事をしていて、お客さんと話しながらするのが楽しいという事もあるし、わざわざコースをカウンターでオレと話しながら食べたいと言われる奇特な方も、それなりにみえるので、予約のコース以外のお客さんに来てもらうのもいいんじゃないかと・・・・あくまでも予約のコース料理が主体の店なので、そちらが優先になる事は今までどおりなんですけどね。
予約の入っていない日と、予約が終わった後、店の前にメニューは出しますが、電話で空席状況を訊いて頂ければ確実だと思います。
コースで食べるのとは別に、単品料理で気楽に食べてもらえればいいと思っていますので、他所の店で食べた後、ちょっと寄って、生ハムとチーズでワインを飲む、というのもいいし、締めのラーメンではなく、「締めのパスタ」もいいと思いますよ。
お待ちしております。
さて、以前からこのブログを読んでもらっている方の中には、オレが急に考え方を変えた事を不思議に思われる方がおられるかもしれませんね。
そういう方のために、蛇足ではあるけれど、その理由についても少し書いてみたいと思います。
オレが高校生の頃、落語家になりたいと思っていたという話は、以前にも書いた事があるんだけれど、当然、今でもYouTube なんかで落語はちょくちょく見ているのだが、11月のある日、故3代目古今亭志ん朝が、実父の5代目志ん生について語っているVTRを観て、すごく思うところがあったわけです。
昭和の大名人と言われた5代目古今亭志ん生は、全く売れない不遇の時代を長く過した人で、一向に売り出せない状況の打破を願う意味から(一説には借金を逃れるためだとも言われている)、10数回に及ぶ改名をした事でも有名だが、上のVTRの7:13あたりから志ん朝が語る、当時の志ん生の芸風や思いが、全然流行らない店を続けてきた今のオレ自身の考え方と重なる・・・・もちろん、大名人である志ん生とオレを同列に語れるわけではないんだけれど、そういう気持ちが痛いほどよく解るんですよ。
緻密で堅い芸をやっていた志ん生が、客を笑わせる芸をやろうと方向転換し、ついには「大名人」と言われる芸人になっていったという話は、オレにとって『天啓』なのかもしれない、と思ったわけなんです。
オレは職人である以上、すべてをきちんとした形で提供したいと考えて、今までやってきたのだけれど、それと同時に、もっと気楽に食べてもらうという考え方があってもいいのではないか・・・・大名人でさえが苦悩しながら芸風を変えていった事を考えると、一介の料理人であるオレが自分の考え方を変えるのはおかしい事ではない・・・・そんな風に思ったんですよ。
この3月で、オレがこの仕事を始めてから丸40年になるのだけれど、そんな事を考えてもいいだけの経験は積んできた・・・・問題は、それをどう生かすかという事になると思う。
志ん生は適当でズボラな人間みたいに言われているし、その芸風も「天衣無縫、融通無碍」のような面が強調されているけれど、実のところは、一点一画を疎かにしない、非常に緻密な芸をやる人なんだと思う。
十八番の『火焔太鼓』の終わりの方で、侍が道具屋に太鼓の素性を説明するところに、「火焔太鼓と申して、世にふたつというような名器であって、国宝に近いものである。」という台詞があるのだが、「世にふたつとない名器」ではなく、「世にふたつというような名器」と言っているのを不思議に思っていたら、火焔太鼓というのは、雅楽で使われる左右一対の太鼓だと知って、「あぁ、なるほどなぁ」と思ったのだけれど、そんな細かいところにまでこだわるほど緻密な芸を持ちながら、世間には適当で出たとこ勝負みたいな芸風だと思わせるなんていうのは、本当にすごい事なんだと思うし、それができたからこそ大名人と呼ばれるまでになったのだろう。
まぁ、凡人であるオレには、そんな芸当ができるとは思わないけれど、還暦が近づいてきた今、今まで直球勝負のようなストレートな生き方をしてきたオレも、変化球を取り入れて、余裕を持った生き方を考える時期にきているんじゃないかと・・・・まぁ、今回の事が、そのきっかけのひとつになればいいかな、と思っているわけです。
さて、最初のほうに書いた、「うれしいお知らせ」の事を書きます。
去年の夏、ミシュランガイドの人が取材をして行ったのだけれど、先日その人から、「あれからかなり経ちましたが、営業時間などの変更はないですか?」という電話がかかってきた。
ということは、この春に出る『ミシュランガイド東海版』に、ウチの事が載せてもらえるんだろう。
今までどういうわけか、TVとか雑誌に採り上げられる事には縁遠かったウチも、これで少しは知られるようになるんじゃないかと期待しているところで・・・・まぁ、ウチは根本的に、高山の(と言うか、飛騨の)人はあまり来ない店なので、県外からの人が増えてくれればな、と思っているのだけれど、これがオレの人生のひとつの転換点になるのではないかと、自分自身、期待しているのだが・・・・
これからも、LA FENICE をよろしくお願いします。
では、また。
Ciao. Arrivederci!!
寒い日が続きますねぇ。
まぁ、雪が少ない事がありがたいですが。
久しぶりの更新になりますが、今回は新しい営業形態についてのお知らせです・・・・と言っても、実質は変わらないんですけどね。
そして、最後に非常にうれしい事を報告しますので、最後まで読んで下さい。
ウチのディナーが予約制である事は、よ~く知ってもらっていると思います。
まぁ、それがウチの特徴であり、また特殊性でもあるのですが、初めての人にとって非常に取っ付きにくい店である事は、自分でもよく解っていたわけですよ。
だからといって、やり方を変えるつもりは毛頭なかったわけで、そのまま13年半続けてきたのだけれど、ここへ来て、自分の中に気持ちの変化が現れて来て、「現状のやり方を変える事無く、もっと取っ付きやすい店にする事はできないか」と考えていて思いついたのが、予約の入っていない日や予約が終った後の時間帯を、BAR として営業しようという事。
なので、BAR LA FENICE としての営業を始めます。
もっとも、やる事自体は今までもやっていた事で、そういう時間帯にカウンターは空けていたんだけれど、来られるのは、ウチの事をよく分かっている常連のお客さんが殆どで、初めてのお客さんが入ってこられる事は、まずなかったわけですよ。
それが何故かというと、メニューがなかったから・・・・というか、敢えてメニュー無しで、お客さんと相談しながら決める、というスタイルでやっているんだけれど、たいていのお客さんから「そんなに安くていいの」と言われるくらい、良心的な価格設定でやってはいるものの、その事を知らない「予約制の店=高級店」と思っている人から見れば、「いくら取られるかわからない」と思われても仕方がないのかなと・・・・
で、まずはメニューを作って、料理や飲み物の値段をハッキリと提示するところから始めようかと思っているわけですよ。
それで、作ってみたメニューが、こんな感じ。
まだ、抜けているところもあるし、訂正しなければならないところもあるんだけれど、だいたいこんな感じでやろうと思っているので、今週から始めていこうかと思います。
まぁ、実際に仕事をしていて、お客さんと話しながらするのが楽しいという事もあるし、わざわざコースをカウンターでオレと話しながら食べたいと言われる奇特な方も、それなりにみえるので、予約のコース以外のお客さんに来てもらうのもいいんじゃないかと・・・・あくまでも予約のコース料理が主体の店なので、そちらが優先になる事は今までどおりなんですけどね。
予約の入っていない日と、予約が終わった後、店の前にメニューは出しますが、電話で空席状況を訊いて頂ければ確実だと思います。
コースで食べるのとは別に、単品料理で気楽に食べてもらえればいいと思っていますので、他所の店で食べた後、ちょっと寄って、生ハムとチーズでワインを飲む、というのもいいし、締めのラーメンではなく、「締めのパスタ」もいいと思いますよ。
お待ちしております。
さて、以前からこのブログを読んでもらっている方の中には、オレが急に考え方を変えた事を不思議に思われる方がおられるかもしれませんね。
そういう方のために、蛇足ではあるけれど、その理由についても少し書いてみたいと思います。
オレが高校生の頃、落語家になりたいと思っていたという話は、以前にも書いた事があるんだけれど、当然、今でもYouTube なんかで落語はちょくちょく見ているのだが、11月のある日、故3代目古今亭志ん朝が、実父の5代目志ん生について語っているVTRを観て、すごく思うところがあったわけです。
昭和の大名人と言われた5代目古今亭志ん生は、全く売れない不遇の時代を長く過した人で、一向に売り出せない状況の打破を願う意味から(一説には借金を逃れるためだとも言われている)、10数回に及ぶ改名をした事でも有名だが、上のVTRの7:13あたりから志ん朝が語る、当時の志ん生の芸風や思いが、全然流行らない店を続けてきた今のオレ自身の考え方と重なる・・・・もちろん、大名人である志ん生とオレを同列に語れるわけではないんだけれど、そういう気持ちが痛いほどよく解るんですよ。
緻密で堅い芸をやっていた志ん生が、客を笑わせる芸をやろうと方向転換し、ついには「大名人」と言われる芸人になっていったという話は、オレにとって『天啓』なのかもしれない、と思ったわけなんです。
オレは職人である以上、すべてをきちんとした形で提供したいと考えて、今までやってきたのだけれど、それと同時に、もっと気楽に食べてもらうという考え方があってもいいのではないか・・・・大名人でさえが苦悩しながら芸風を変えていった事を考えると、一介の料理人であるオレが自分の考え方を変えるのはおかしい事ではない・・・・そんな風に思ったんですよ。
この3月で、オレがこの仕事を始めてから丸40年になるのだけれど、そんな事を考えてもいいだけの経験は積んできた・・・・問題は、それをどう生かすかという事になると思う。
志ん生は適当でズボラな人間みたいに言われているし、その芸風も「天衣無縫、融通無碍」のような面が強調されているけれど、実のところは、一点一画を疎かにしない、非常に緻密な芸をやる人なんだと思う。
十八番の『火焔太鼓』の終わりの方で、侍が道具屋に太鼓の素性を説明するところに、「火焔太鼓と申して、世にふたつというような名器であって、国宝に近いものである。」という台詞があるのだが、「世にふたつとない名器」ではなく、「世にふたつというような名器」と言っているのを不思議に思っていたら、火焔太鼓というのは、雅楽で使われる左右一対の太鼓だと知って、「あぁ、なるほどなぁ」と思ったのだけれど、そんな細かいところにまでこだわるほど緻密な芸を持ちながら、世間には適当で出たとこ勝負みたいな芸風だと思わせるなんていうのは、本当にすごい事なんだと思うし、それができたからこそ大名人と呼ばれるまでになったのだろう。
まぁ、凡人であるオレには、そんな芸当ができるとは思わないけれど、還暦が近づいてきた今、今まで直球勝負のようなストレートな生き方をしてきたオレも、変化球を取り入れて、余裕を持った生き方を考える時期にきているんじゃないかと・・・・まぁ、今回の事が、そのきっかけのひとつになればいいかな、と思っているわけです。
さて、最初のほうに書いた、「うれしいお知らせ」の事を書きます。
去年の夏、ミシュランガイドの人が取材をして行ったのだけれど、先日その人から、「あれからかなり経ちましたが、営業時間などの変更はないですか?」という電話がかかってきた。
ということは、この春に出る『ミシュランガイド東海版』に、ウチの事が載せてもらえるんだろう。
今までどういうわけか、TVとか雑誌に採り上げられる事には縁遠かったウチも、これで少しは知られるようになるんじゃないかと期待しているところで・・・・まぁ、ウチは根本的に、高山の(と言うか、飛騨の)人はあまり来ない店なので、県外からの人が増えてくれればな、と思っているのだけれど、これがオレの人生のひとつの転換点になるのではないかと、自分自身、期待しているのだが・・・・
これからも、LA FENICE をよろしくお願いします。
では、また。
Ciao. Arrivederci!!