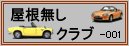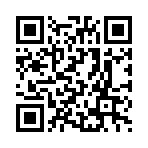スポンサーリンク
この広告は一定期間(1ヶ月以上)更新のないブログに表示されます。
ブログ記事の情報が古い場合がありますのでご注意下さい。
(ブログオーナーが新しい記事を投稿すると非表示になります。)
ブログ記事の情報が古い場合がありますのでご注意下さい。
(ブログオーナーが新しい記事を投稿すると非表示になります。)
2007年02月22日
銀行へ行く時に
Ciao. spockです。
前回の投稿から間が空いてしまいました。
出かけていたり、Mac がフリーズしたり(長い文なので記憶をもとに書き直すのが大変なのですよ)と、いろいろありまして・・・・
その間も覗いて下さった方々、ありがとうございます。
では、8日ぶりの spock の Blog です。
この土・日と東京へ行って来ました。以前ここに書いた『講習』の最後の回を受講してきたのです。
事前の話では、最後に認定証がもらえると聞いていたのですが、オレはそんな事はありえないと思っていました。
なぜなら、オレは技術系の人間ですから、技術というものは経験を積む事によって初めて身に付くものであって、習ってスグにできるものではない事をよく分っているからです。
最後にもらえたのは、思っていたとおり修了証でした。
先生曰く「協力者を見つけて、とにかく経験を積む事。プロとしてやれるようになった時にはサインが現れますよ。」
オレは先生を全面的に信頼していますから、早速、協力者探しから始めようと思っています。
さて、今回の話は、前々回の最後に書いたように、アメフトの装備のひとつを日常生活の中で使ってしまうという話です。
自分では結構いいアイディアだと思っているのですが、端から見るとどうなんでしょうね。
ところで、この Blog を書きかけで東京へ行ったのですが、ホテルで『所さんのメガテン』を観ていたら、この中に書いていた事が出てきたのですよ。驚きましたねぇ。
今から13年も前の事、池袋のサンシャインシティーにあるミプロ(製品輸入促進協会)で、アメリカのスポーツショップのカタログを見つけ、個人輸入でいろいろ取り寄せたのです。その後も年に2〜3回、日本では手に入らないような物を中心に取り寄せていました。

これは去年の夏と秋のカタログです。
今はウェブサイトを見てインターネットでオーダーしますが、たまに送られてくるカタログを見るのも、何かワクワクしますね。
他人の持って居ない物を手に入れる事に喜びを感じるオレとしては、年に数回送られてくるカタログ(今はウェブサイトですが)を見て、ワクワクしてましたねぇ。
なので、ナイキのエアーマックスがブレイクした時、日本からのオーダーが急増したからなのでしょうが、急にカタログに日本語の解説書が付いてきた時には何か寂しいものを感じましたね。
とは言っても、気になっていた物が製造中止になってメチャメチャ安く出ていたりすると、すぐにオーダーを入れるわけです。送料を少しでも安くするために、後輩達にも声をかけて共同購入の形で取り寄せていました。
今ではインターネットでオーダーできますから簡単なものですが、シューズやウェアといった定番の他に、見逃せない項目があるのですよ。それは Football Equipment(フットボールの装備)です。
前々回の Blog の中に、『アメフトというスポーツの性格上、装備や機材から審判やトレーニング方に至るまで、最新の技術を惜しげもなく投入し、それを他のスポーツや、さらには一般社会にもフィードバックしている』と書いていますが、その事が一番良く解るのが、この Football Eqipment なのです。
過去の事例から解りやすい例をあげてみましょうか。
オレと同じ世代の人ならきっと憶えていると思うのですが『象がふんでもこわれない アーム筆入れ』 ポリカーボネイト製の本当に丈夫な筆入れでした。(オレは10年位使ってました)
ドイツのバイエル社が開発したポリカーボネイトは、最初は軍事用(例えば空軍のパイロット用ヘルメット)として使われたようですが、コンシューマー(一般消費者)用として最初に使われたのはフットボールのヘルメットだったようで、その強さが認められて世の中に広まっていった、というわけです。
70年代初頭の写真器材用ハードケースの広告に『フットボールのヘルメットに使われている頑丈なポリカーボネート使用』って書かれていたのを憶えていますが、その当時の日本でのフットボールの認知度を考えると、どの位の人が理解したのかは解りませんね。
それから、今ではユニクロでも普通に売っている、ドライTシャツ。
これもコンシューマー用として最初に発売されたのは、フットボール用インナーウェアとしてでした。
普通ではありえない装備を全身に着けて無酸素運動を繰り返すスポーツ故に、いかに素早く汗を放出できるかというのは最重要問題のひとつだったわけで、最初にフットボール用として使われたのは当然と言えば当然の事だったのでしょう。
10年程前にフットボール用のインナーを取り寄せたのですが、オレはそれを自転車に乗る時に着ていました。(快適でしたよ)
それから何年か経って、日本のメーカーも自転車用のインナーを発売したのですが、材質はほぼ同じでしたから、それもフットボールからのフィードバックだったのだと思います。
そんなわけで、Football Eqipment の中から何か使えそうな物や、これから世の中に広がっていく可能性のある物を探す事が、オレにとっては本当に興味深い事なのですが、前回のオーダーで手に入れたのがコレ

ナイキのマグニグリップ・フォース(Nike Magnigrip Force)
早い話が、フットボール用グローブです。
このグローブ、掌側に少し粘着性のあるゴム系の素材が使われているのです。
WR(ワイドレシーヴァー)がボールを確実にレシーヴするために絶対必要な装備であり、また、オフェンスの有捕球資格者(ボールにさわれないラインの5人(50〜79番)以外のプレイヤーを指す)はボールを持った瞬間からタックルの標的になり、ボールをファンブルした上にディフェンス側にリカヴァーされると、その瞬間から攻守が入れ替わってしまいますから、絶対にボールを離さないために、こんなグローブができたわけです。
1年前にも別のグローブを手に入れていたのですが、その時は自転車に乗る時に使うつもりでした。ハンドルをしっかりとグリップできそうですからね。
実際にやってみると、じつにしっかりとグリップできます。これなら疲れた時にはハンドルに手を添えているだけで大丈夫だ、と思ったのですが、とっさに手を離そうと思った時、離れにくいのですよ。
これでは逆に危険だと思い、他に使いみちはないかと考えていたら・・・・・ありました。
うちの店に大した売上げはありませんが、銀行(信用金庫ですけど)へ預けに行く時には売上金の入ったバッグをしっかりと抱えて行きます。
そんな時にこのグローブを使えばいいのですよ。

実際にやってみたところ、このグローブを着けて片手で持ったバッグを、両手(素手)で掴んで引っ張られてもバッグが手から離れる事はありません。
さらにはRB(ランニングバック)がボールを抱えて走る時のように持てば(画像参照)引ったくられる可能性はゼロだと言っていいと思います。(オレはいつもこんなふうに持っています)
そのうちに日本のどこかのメーカーが、この素材を使って『ひったくり防止手袋』なんていうのを売り出すんじゃないかと思うんですが・・・・・(ないか)
ただ、冬は防寒をかねてちょうどいいのですが、夏に使うのはチョットね・・・・・orz
近々、次のオーダーを出す予定なのですが、今度は何にするか・・・・ウェブサイトを見ながら考え込んでいる今日この頃です。
では、また。
Ciao. Arrivederci!!
前回の投稿から間が空いてしまいました。
出かけていたり、Mac がフリーズしたり(長い文なので記憶をもとに書き直すのが大変なのですよ)と、いろいろありまして・・・・
その間も覗いて下さった方々、ありがとうございます。
では、8日ぶりの spock の Blog です。
この土・日と東京へ行って来ました。以前ここに書いた『講習』の最後の回を受講してきたのです。
事前の話では、最後に認定証がもらえると聞いていたのですが、オレはそんな事はありえないと思っていました。
なぜなら、オレは技術系の人間ですから、技術というものは経験を積む事によって初めて身に付くものであって、習ってスグにできるものではない事をよく分っているからです。
最後にもらえたのは、思っていたとおり修了証でした。
先生曰く「協力者を見つけて、とにかく経験を積む事。プロとしてやれるようになった時にはサインが現れますよ。」
オレは先生を全面的に信頼していますから、早速、協力者探しから始めようと思っています。
さて、今回の話は、前々回の最後に書いたように、アメフトの装備のひとつを日常生活の中で使ってしまうという話です。
自分では結構いいアイディアだと思っているのですが、端から見るとどうなんでしょうね。
ところで、この Blog を書きかけで東京へ行ったのですが、ホテルで『所さんのメガテン』を観ていたら、この中に書いていた事が出てきたのですよ。驚きましたねぇ。
今から13年も前の事、池袋のサンシャインシティーにあるミプロ(製品輸入促進協会)で、アメリカのスポーツショップのカタログを見つけ、個人輸入でいろいろ取り寄せたのです。その後も年に2〜3回、日本では手に入らないような物を中心に取り寄せていました。

これは去年の夏と秋のカタログです。
今はウェブサイトを見てインターネットでオーダーしますが、たまに送られてくるカタログを見るのも、何かワクワクしますね。
他人の持って居ない物を手に入れる事に喜びを感じるオレとしては、年に数回送られてくるカタログ(今はウェブサイトですが)を見て、ワクワクしてましたねぇ。
なので、ナイキのエアーマックスがブレイクした時、日本からのオーダーが急増したからなのでしょうが、急にカタログに日本語の解説書が付いてきた時には何か寂しいものを感じましたね。
とは言っても、気になっていた物が製造中止になってメチャメチャ安く出ていたりすると、すぐにオーダーを入れるわけです。送料を少しでも安くするために、後輩達にも声をかけて共同購入の形で取り寄せていました。
今ではインターネットでオーダーできますから簡単なものですが、シューズやウェアといった定番の他に、見逃せない項目があるのですよ。それは Football Equipment(フットボールの装備)です。
前々回の Blog の中に、『アメフトというスポーツの性格上、装備や機材から審判やトレーニング方に至るまで、最新の技術を惜しげもなく投入し、それを他のスポーツや、さらには一般社会にもフィードバックしている』と書いていますが、その事が一番良く解るのが、この Football Eqipment なのです。
過去の事例から解りやすい例をあげてみましょうか。
オレと同じ世代の人ならきっと憶えていると思うのですが『象がふんでもこわれない アーム筆入れ』 ポリカーボネイト製の本当に丈夫な筆入れでした。(オレは10年位使ってました)
ドイツのバイエル社が開発したポリカーボネイトは、最初は軍事用(例えば空軍のパイロット用ヘルメット)として使われたようですが、コンシューマー(一般消費者)用として最初に使われたのはフットボールのヘルメットだったようで、その強さが認められて世の中に広まっていった、というわけです。
70年代初頭の写真器材用ハードケースの広告に『フットボールのヘルメットに使われている頑丈なポリカーボネート使用』って書かれていたのを憶えていますが、その当時の日本でのフットボールの認知度を考えると、どの位の人が理解したのかは解りませんね。
それから、今ではユニクロでも普通に売っている、ドライTシャツ。
これもコンシューマー用として最初に発売されたのは、フットボール用インナーウェアとしてでした。
普通ではありえない装備を全身に着けて無酸素運動を繰り返すスポーツ故に、いかに素早く汗を放出できるかというのは最重要問題のひとつだったわけで、最初にフットボール用として使われたのは当然と言えば当然の事だったのでしょう。
10年程前にフットボール用のインナーを取り寄せたのですが、オレはそれを自転車に乗る時に着ていました。(快適でしたよ)
それから何年か経って、日本のメーカーも自転車用のインナーを発売したのですが、材質はほぼ同じでしたから、それもフットボールからのフィードバックだったのだと思います。
そんなわけで、Football Eqipment の中から何か使えそうな物や、これから世の中に広がっていく可能性のある物を探す事が、オレにとっては本当に興味深い事なのですが、前回のオーダーで手に入れたのがコレ

ナイキのマグニグリップ・フォース(Nike Magnigrip Force)
早い話が、フットボール用グローブです。
このグローブ、掌側に少し粘着性のあるゴム系の素材が使われているのです。
WR(ワイドレシーヴァー)がボールを確実にレシーヴするために絶対必要な装備であり、また、オフェンスの有捕球資格者(ボールにさわれないラインの5人(50〜79番)以外のプレイヤーを指す)はボールを持った瞬間からタックルの標的になり、ボールをファンブルした上にディフェンス側にリカヴァーされると、その瞬間から攻守が入れ替わってしまいますから、絶対にボールを離さないために、こんなグローブができたわけです。
1年前にも別のグローブを手に入れていたのですが、その時は自転車に乗る時に使うつもりでした。ハンドルをしっかりとグリップできそうですからね。
実際にやってみると、じつにしっかりとグリップできます。これなら疲れた時にはハンドルに手を添えているだけで大丈夫だ、と思ったのですが、とっさに手を離そうと思った時、離れにくいのですよ。
これでは逆に危険だと思い、他に使いみちはないかと考えていたら・・・・・ありました。
うちの店に大した売上げはありませんが、銀行(信用金庫ですけど)へ預けに行く時には売上金の入ったバッグをしっかりと抱えて行きます。
そんな時にこのグローブを使えばいいのですよ。

実際にやってみたところ、このグローブを着けて片手で持ったバッグを、両手(素手)で掴んで引っ張られてもバッグが手から離れる事はありません。
さらにはRB(ランニングバック)がボールを抱えて走る時のように持てば(画像参照)引ったくられる可能性はゼロだと言っていいと思います。(オレはいつもこんなふうに持っています)
そのうちに日本のどこかのメーカーが、この素材を使って『ひったくり防止手袋』なんていうのを売り出すんじゃないかと思うんですが・・・・・(ないか)
ただ、冬は防寒をかねてちょうどいいのですが、夏に使うのはチョットね・・・・・orz
近々、次のオーダーを出す予定なのですが、今度は何にするか・・・・ウェブサイトを見ながら考え込んでいる今日この頃です。
では、また。
Ciao. Arrivederci!!
2007年02月14日
北と南の違い
Ciao. spockです。
2月7日の『一糸乱れず』に頂いた、frog eyes さんのコメントに、北と南のパスタと人間のカタさの事があったので、今回はそれについて書きます。
こんな話があります。
ミラノに住んでいる一人の男が神様と会いました。神様はその男が気に入り、別れる時に言いました。
「お前の望みを3つ叶えてやろう。」
男はすかさず言いました。
「イタリアの南半分を海に沈めて下さい。」
神様は言葉を失いましたが、約束なので仕方がなく、イタリアの南半分を海に沈めました。
しばらくすると男は言いました。
「さっき沈めたところをもとに戻して下さい。」
神様は、この男にも良心というものがあったのだと、ホッとしながら、海に沈んだ南半分をもとに戻しました。
すると男は言いました。
「1日後にもう1度南半分を沈めて下さい。そうすれば、心配して南に帰ったヤツらも一緒に沈められますからね。」
北と南の人間の仲が悪い事は有名で、北では南の人間の事を『アフリカ人』と呼び、南では北の人間の事を『ポレンタ(とうもろこしの粉を練りながら煮上げた料理)を喰うヤツら』とよんで、お互いに軽蔑しあっていたのです。
まぁ、人種問題というのはどこでもあるのでしょうが、北と南では人種が違うという事もそうなった原因のひとつのようです。
北には金髪碧眼の白人が多いのに対し、南にはズングリとした色の黒い人が多い事は一目瞭然で、南には移民が多かったからだと言われています。(以前呼んだ本によると、イラン・イラク系の血が濃いので、南にマフィアが出来たのだという説もあるようです。)
前述の frog eyes さんのコメントに、『北の方はパスタはやわらかく人が堅い、南の方は人はやらかいけどパスタは堅いって?本当でしょうか』とありましたが、コレ、ある意味で『名言』かもしれません。
何事にも例外というものは結構あるので、一概には言い切れませんが、イメージとしては、結構鋭いところを突いているように思います。
北より南の方が、パスタの茹で加減が硬いというのは、個人差とか好みの問題を除外すれば、概ね正しいと思います.
その理由としては、気候の問題が関わってくるのですが、その前に、北と南の定義をハッキリさせておきましょう。
北と南の境はどこなんでしょうね。
オレは、厳密な境なんていうものがあるはずはない、と思っているのです.
同じように南北に長い日本の事を考えてみると解りますが、最低、北部・中部・南部の3つに分ける必要があると思います。

スイス・オーストリア国境から、ボローニャを州都とするエミリア・ロマーニャ州までを北部。
ナポリを州都とするカンパーニア州から南を南部。
その間を中部と呼ぶ事で間違いはないと思います。
中部でも、北へ行く程北の影響を、南へ行く程南の影響を、強く受ける事は言うまでもありません。
そんなわけで。敢えて北と南の境を断定するなら『北と南の文化が入り交じった中部のどこか』と言うしかないでしょうね。
それともうひとつ、偏西風の影響で、ナポリのあたりを境に気候が全く変わってしまう、という事を憶えておいて下さい。
さて、ではまず小麦の話です。
上に書いたとおり、北と南では気候がハッキリと違うため、穫れる小麦が違うのです。
北部で穫れる小麦は軟質小麦(グラーノ テーネロ)で、それを粉にしたものが、日本でも普通に売っている小麦粉です。
強力粉に卵を加えて練った『手打ちパスタ』が盛んに作られ、フェットゥッチーネ、タリアテッレ、リングイーネなどの手打ち麺、ラザーニェやカンネッローニを使ったグラタン、詰め物をしたトルテッローニやアニョレッティなどのラヴィオリなどが愛されているわけです。
南部で穫れる小麦は硬質小麦(グラーノ ドゥーロ)で、粉にしたものがセモリーノと呼ばれ、黄色くてザラザラしています。これを手で練るのは硬過ぎて不可能ですから、機械で練り、真空状態で混じった空気を抜き、高圧をかけて穴から押し出し、乾燥させたものが、スパゲッティやマカロニなどの乾麺なのです。当然、南イタリアでは、乾麺を多く使う事になりますね。
(グラーノ ドゥーロは世界の小麦の5%しか栽培されておらず、パスタ用としてだけ生産されている。イタリアでは、その大半を北米から輸入している。ちなみに、主要先進国の食料自給率をみると、下から1位と2位が日本とイタリア)
このような事から考えると、基本的に南の方がパスタ自体が硬い(と言うか、歯応えがしっかりしている)事が分ると思います。
さらに言うなら、南の人が北の手打ち麺を茹でる場合、いつもの乾麺の感覚で茹でれば、当然、北の人達が茹でるより硬めになるでしょうし、北の人が乾麺を茹でる場合は、逆の理由で柔らかめに茹でるだろう事は容易に想像できますね。
このような理由で、北より南の方がパスタの茹で加減が硬めなのだと、オレは考えています。
それからもうひとつ、パスタの硬さと、人の固さは反比例するかという事ですが、これも例外を除けば、概ね正しいと思います。
相対的に見た場合、北の人達は、都会的で洗練された感じがするのに対し、南の人達は、もっと素朴な感じがします。
過去に付き合った経験から言うと、南の人達は友人としてはすごくいいヤツです。でも、仕事を一緒にすると、友人・知人のために無理矢理融通をきかせようとして(早い話が依怙贔屓ですね)平気でルールを無視するので、しょっちゅう言い争いをしていました。
それが南イタリア風の付き合い方なのかもしれませんが、日本人のオレにとっては「もう少し節度を持ってよ」と言いたくなります。
そんな理由で、付き合うなら南の人もいいけれど、仕事のパートナーにするなら北の人、というのがオレの偽らざる気持ちです。
ここから話は変わりますが、オレが東京にいた頃、自転車仲間の何人かがオランダへ行って来たのです。自転車乗りにとって、見渡す限り平地が続くオランダは、興味をそそられる場所ですからね。
気ままに走りたいということで、みんなひとりか、せいぜいふたりで出かけて行ったのですが、話を聞かせてもらうと、その内の何人かから同じような話を聞いたのです。
それは、こんな話です。
オランダには、なぜかドイツ人が結構いて、こっちが日本人だとわかると話しかけてくる人が何人もいた。大抵が老人で、片言の英語や、身振り手振りを交えて話しかけてくるのだが、最後に意味ありげに笑いながらこんな事を言う。
「今度はイタリア抜きでやろうな」
まぁ、どれだけのドイツ人が本当にそんな事を思っているのかはわかりませんが、日本人とは真面目さや勤勉さという共通点を持つドイツ人にとって、イタリア人より日本人の方がパートナーとして信用できるのかもしれませんね。
でも、日本ではここ10数年来、イタリアブームが続いていると知ったら、ドイツの老人達はどう思うのでしょうね。
では、また。
Ciao. Arrivederci!!
2月7日の『一糸乱れず』に頂いた、frog eyes さんのコメントに、北と南のパスタと人間のカタさの事があったので、今回はそれについて書きます。
こんな話があります。
ミラノに住んでいる一人の男が神様と会いました。神様はその男が気に入り、別れる時に言いました。
「お前の望みを3つ叶えてやろう。」
男はすかさず言いました。
「イタリアの南半分を海に沈めて下さい。」
神様は言葉を失いましたが、約束なので仕方がなく、イタリアの南半分を海に沈めました。
しばらくすると男は言いました。
「さっき沈めたところをもとに戻して下さい。」
神様は、この男にも良心というものがあったのだと、ホッとしながら、海に沈んだ南半分をもとに戻しました。
すると男は言いました。
「1日後にもう1度南半分を沈めて下さい。そうすれば、心配して南に帰ったヤツらも一緒に沈められますからね。」
北と南の人間の仲が悪い事は有名で、北では南の人間の事を『アフリカ人』と呼び、南では北の人間の事を『ポレンタ(とうもろこしの粉を練りながら煮上げた料理)を喰うヤツら』とよんで、お互いに軽蔑しあっていたのです。
まぁ、人種問題というのはどこでもあるのでしょうが、北と南では人種が違うという事もそうなった原因のひとつのようです。
北には金髪碧眼の白人が多いのに対し、南にはズングリとした色の黒い人が多い事は一目瞭然で、南には移民が多かったからだと言われています。(以前呼んだ本によると、イラン・イラク系の血が濃いので、南にマフィアが出来たのだという説もあるようです。)
前述の frog eyes さんのコメントに、『北の方はパスタはやわらかく人が堅い、南の方は人はやらかいけどパスタは堅いって?本当でしょうか』とありましたが、コレ、ある意味で『名言』かもしれません。
何事にも例外というものは結構あるので、一概には言い切れませんが、イメージとしては、結構鋭いところを突いているように思います。
北より南の方が、パスタの茹で加減が硬いというのは、個人差とか好みの問題を除外すれば、概ね正しいと思います.
その理由としては、気候の問題が関わってくるのですが、その前に、北と南の定義をハッキリさせておきましょう。
北と南の境はどこなんでしょうね。
オレは、厳密な境なんていうものがあるはずはない、と思っているのです.
同じように南北に長い日本の事を考えてみると解りますが、最低、北部・中部・南部の3つに分ける必要があると思います。

スイス・オーストリア国境から、ボローニャを州都とするエミリア・ロマーニャ州までを北部。
ナポリを州都とするカンパーニア州から南を南部。
その間を中部と呼ぶ事で間違いはないと思います。
中部でも、北へ行く程北の影響を、南へ行く程南の影響を、強く受ける事は言うまでもありません。
そんなわけで。敢えて北と南の境を断定するなら『北と南の文化が入り交じった中部のどこか』と言うしかないでしょうね。
それともうひとつ、偏西風の影響で、ナポリのあたりを境に気候が全く変わってしまう、という事を憶えておいて下さい。
さて、ではまず小麦の話です。
上に書いたとおり、北と南では気候がハッキリと違うため、穫れる小麦が違うのです。
北部で穫れる小麦は軟質小麦(グラーノ テーネロ)で、それを粉にしたものが、日本でも普通に売っている小麦粉です。
強力粉に卵を加えて練った『手打ちパスタ』が盛んに作られ、フェットゥッチーネ、タリアテッレ、リングイーネなどの手打ち麺、ラザーニェやカンネッローニを使ったグラタン、詰め物をしたトルテッローニやアニョレッティなどのラヴィオリなどが愛されているわけです。
南部で穫れる小麦は硬質小麦(グラーノ ドゥーロ)で、粉にしたものがセモリーノと呼ばれ、黄色くてザラザラしています。これを手で練るのは硬過ぎて不可能ですから、機械で練り、真空状態で混じった空気を抜き、高圧をかけて穴から押し出し、乾燥させたものが、スパゲッティやマカロニなどの乾麺なのです。当然、南イタリアでは、乾麺を多く使う事になりますね。
(グラーノ ドゥーロは世界の小麦の5%しか栽培されておらず、パスタ用としてだけ生産されている。イタリアでは、その大半を北米から輸入している。ちなみに、主要先進国の食料自給率をみると、下から1位と2位が日本とイタリア)
このような事から考えると、基本的に南の方がパスタ自体が硬い(と言うか、歯応えがしっかりしている)事が分ると思います。
さらに言うなら、南の人が北の手打ち麺を茹でる場合、いつもの乾麺の感覚で茹でれば、当然、北の人達が茹でるより硬めになるでしょうし、北の人が乾麺を茹でる場合は、逆の理由で柔らかめに茹でるだろう事は容易に想像できますね。
このような理由で、北より南の方がパスタの茹で加減が硬めなのだと、オレは考えています。
それからもうひとつ、パスタの硬さと、人の固さは反比例するかという事ですが、これも例外を除けば、概ね正しいと思います。
相対的に見た場合、北の人達は、都会的で洗練された感じがするのに対し、南の人達は、もっと素朴な感じがします。
過去に付き合った経験から言うと、南の人達は友人としてはすごくいいヤツです。でも、仕事を一緒にすると、友人・知人のために無理矢理融通をきかせようとして(早い話が依怙贔屓ですね)平気でルールを無視するので、しょっちゅう言い争いをしていました。
それが南イタリア風の付き合い方なのかもしれませんが、日本人のオレにとっては「もう少し節度を持ってよ」と言いたくなります。
そんな理由で、付き合うなら南の人もいいけれど、仕事のパートナーにするなら北の人、というのがオレの偽らざる気持ちです。
ここから話は変わりますが、オレが東京にいた頃、自転車仲間の何人かがオランダへ行って来たのです。自転車乗りにとって、見渡す限り平地が続くオランダは、興味をそそられる場所ですからね。
気ままに走りたいということで、みんなひとりか、せいぜいふたりで出かけて行ったのですが、話を聞かせてもらうと、その内の何人かから同じような話を聞いたのです。
それは、こんな話です。
オランダには、なぜかドイツ人が結構いて、こっちが日本人だとわかると話しかけてくる人が何人もいた。大抵が老人で、片言の英語や、身振り手振りを交えて話しかけてくるのだが、最後に意味ありげに笑いながらこんな事を言う。
「今度はイタリア抜きでやろうな」
まぁ、どれだけのドイツ人が本当にそんな事を思っているのかはわかりませんが、日本人とは真面目さや勤勉さという共通点を持つドイツ人にとって、イタリア人より日本人の方がパートナーとして信用できるのかもしれませんね。
でも、日本ではここ10数年来、イタリアブームが続いていると知ったら、ドイツの老人達はどう思うのでしょうね。
では、また。
Ciao. Arrivederci!!
Posted by spock at
12:16
│Comments(6)
2007年02月10日
世界中で役に立っているもの
Ciao. spockです。
前々回、スーパーボウルに絡んで、延々とアメフトの話を書きましたが、以前からいろいろな人達に聞いてみたところでは、どうも多くの人は、アメフトを『特殊なスポーツ』だと思っているようなのです。
この『特殊な』というのも漠然としていて、解釈の仕方もいろいろありそうなのですが・・・
まぁ、アメフト側のオレとしては、人類が進化する過程で他の動物との違いを決定づけた『機能』を使う事を全面的に禁じているスポーツの方が、よっぽど『特殊』だと思うのですがね。
知らない人が見れば、複雑怪奇としか見えないだろうルールも然る事ながら(と言っても、ルールブックのページ数は野球のほうがずーっと多いのですが)、やはりアメフトを『特殊』に見せている一番の原因は、あのスタイルというか装備でしょうね。
かく言うオレも、前々回にはあの装備を身に付けた画像をアップした上に、前回からはそれをプロフィールの画像に転用していますから 『アイシールドでうまく顔が隠れているから』というのが一番の理由だったとはいえ、意識の中に『他にこんな画像を使うヤツはおらんやろう』という、特殊性を肯定した気持ちがあった事は否めませんね。
アメフトの装備の中でも特徴的なのはヘルメットとショルダーパッドだと思いますが、今回は、そのヘルメットの話です。

オレの使っていたヘルメットです。
オレはバックスだったので、それ程あたる事はなかったのですが、相手のヘルメットとあたって付いた塗料の痕が残っています。
ヘルメットは当然頭を保護するために被るものですが、では、その構造はと聞かれたら、どう答えますか?
大抵は『強化プラスティックのシェル(帽体)の内側に緩衝材(クッション)をつけたもの』とか『シェルとあたまの間に隙間を空けてある』と答えるでしょう。実際、そう答えるしかないですね。
半世紀以上も前なら『鉄かぶと』と呼ばれていたように、重い鉄製のものだったのでしょうが、現代では誰もが、ヘルメットは強化プラスティック製であると認識していると思います。
では、強化プラスティック製のヘルメットは、いつ、どのように作られたのでしょうか。
強化プラスティック製のヘルメットは、1939年にアメリカのRiddell (リデル)社によって作られました。
Riddell のウェブサイト http://riddell.com/は極めてマニアックで(オレが言うのだから本当です)、ヘルメットの歴史などが詳しく書かれています。(勿論英語ですけど) この中の動画も結構面白いですよ。
以前はこのウェブサイトのトップページに、先日のスーパーボウルのMVP、ペイトン・マニングがコールしているところのアップの画像がつかわれていました。マニングは Riddell の Revolution というヘルメットを使っていますから、それがハッキリと写っていたのです。
おわかりですね、Riddell はフットボール ヘルメットのメーカーなのです。
この話をすると、大抵「へぇ〜」って言われるのですが、現在世界中で使われている強化プラスティック製のヘルメットは、アメフトのために作られたものが転用され、世界に広まったものなのです。
1939年というと第二次世界大戦が始まった年でもありますが、アメフト用に作られた新型のヘルメットの事を知ったアメリカ政府は、すぐに軍隊のためにそれを導入したのです。
その後、機能性に優れたこのヘルメットが世界中に広まった事は言うまでもありません。
ヘルメットのおかげで命拾いしたそこのアナタ、もうアメフトには足を向けて寝られませんよ。これからはアメフトを観るんですよ!! って、霊感商法かよっ・・・・・orz
アメフトの事を、アメリカだけでしか通用しないマイナースポーツだと言う人がいます。オレはその事を否定しません。でも、その事を認めた上で、これ程世の中の役に立っているスポーツは他にないと思うのです。
それは、ここまで書いてきたヘルメットの事例でも解ってもらえると思いますが、アメフトというスポーツの性格上、装備や機材から審判やトレーニング方に至るまで、最新の技術を惜しげもなく投入し、それを他のスポーツや、さらには一般社会にもフィードバックしているという、紛れもない事実があるからです。
まぁ、ここまで言うと、贔屓の引き倒しだと言われるかもしれませんが・・・・
(追記に、アメフトのヘルメットの起源と最新作の話があります)
この Blog のプロフィールに使っている画像では、スモークのアイシールドのせいで顔が見えませんが、現在の日本のルールでは、クリア以外のアイシールドは禁止されていますから、これを試合に使う事はできません。
もともとアイシールドには、眼を保護するという役割の他に、眼を隠す事で、視線の動きから次のプレイを見破られる事を防ぐという、さらに重要な役割があったのです。クリアのものしか使えないのでは、あまり意味がないと思うのはオレだけではないでしょうね。
アメリカでは、そんな規制はありませんから、サングラス並みにいろんな種類のアイシールドを売っています。でも、それだけの種類をどう使い分けるんでしょうね。
そんな事を考えながら某ウェブサイトを見ていたら、見つけました。
 ミラード・アイシールド。
ミラード・アイシールド。
思わず「カッコえぇー」って
言ってしまいましたね。
画像はグリーンミラーだけど
やっぱりシルヴァーがいい。
値段は約$50。オークリーの
イリディウムミラーは、なん
と$250!! ヘルメット本体が
2つ買えますよ。
オレがプレーヤーだった頃に
これがあったら、ゼーッタイ
使っていたでしょうね。
そういえば、東洋人と欧米人では頭の形が違い、上から見ると、東洋人は真円に近く、欧米人は前後に長い楕円形だと言われています。
そのため、東洋人がヘルメットを脱ぐ時は両手でシェルを横に広げながら脱がなければならないのですが、欧米人は片手でフェイスガードを持って引き上げるだけで脱げるのです。
それがまたカッコよく見えるのですよ。
どういうわけか、オレは頭が前後に長いので、片手で脱げるんです。
みんなが両手で脱いでいる時、オレはさり気なく片手で脱いで、内心ニンマリしていましたね。
まぁ、大人気ないと言えば大人気ないのですが・・・・・
次にアメフトの話を書く時のテーマは、もう決まっているのですよ。
あの装備の中のある物を、普段の生活に使うという話です。
人によっては、使える裏技(?)だと思うのですがね。
では、また。
Ciao. Arrivederci!! 続きを読む
前々回、スーパーボウルに絡んで、延々とアメフトの話を書きましたが、以前からいろいろな人達に聞いてみたところでは、どうも多くの人は、アメフトを『特殊なスポーツ』だと思っているようなのです。
この『特殊な』というのも漠然としていて、解釈の仕方もいろいろありそうなのですが・・・
まぁ、アメフト側のオレとしては、人類が進化する過程で他の動物との違いを決定づけた『機能』を使う事を全面的に禁じているスポーツの方が、よっぽど『特殊』だと思うのですがね。
知らない人が見れば、複雑怪奇としか見えないだろうルールも然る事ながら(と言っても、ルールブックのページ数は野球のほうがずーっと多いのですが)、やはりアメフトを『特殊』に見せている一番の原因は、あのスタイルというか装備でしょうね。
かく言うオレも、前々回にはあの装備を身に付けた画像をアップした上に、前回からはそれをプロフィールの画像に転用していますから 『アイシールドでうまく顔が隠れているから』というのが一番の理由だったとはいえ、意識の中に『他にこんな画像を使うヤツはおらんやろう』という、特殊性を肯定した気持ちがあった事は否めませんね。
アメフトの装備の中でも特徴的なのはヘルメットとショルダーパッドだと思いますが、今回は、そのヘルメットの話です。

オレの使っていたヘルメットです。
オレはバックスだったので、それ程あたる事はなかったのですが、相手のヘルメットとあたって付いた塗料の痕が残っています。
ヘルメットは当然頭を保護するために被るものですが、では、その構造はと聞かれたら、どう答えますか?
大抵は『強化プラスティックのシェル(帽体)の内側に緩衝材(クッション)をつけたもの』とか『シェルとあたまの間に隙間を空けてある』と答えるでしょう。実際、そう答えるしかないですね。
半世紀以上も前なら『鉄かぶと』と呼ばれていたように、重い鉄製のものだったのでしょうが、現代では誰もが、ヘルメットは強化プラスティック製であると認識していると思います。
では、強化プラスティック製のヘルメットは、いつ、どのように作られたのでしょうか。
強化プラスティック製のヘルメットは、1939年にアメリカのRiddell (リデル)社によって作られました。
Riddell のウェブサイト http://riddell.com/は極めてマニアックで(オレが言うのだから本当です)、ヘルメットの歴史などが詳しく書かれています。(勿論英語ですけど) この中の動画も結構面白いですよ。
以前はこのウェブサイトのトップページに、先日のスーパーボウルのMVP、ペイトン・マニングがコールしているところのアップの画像がつかわれていました。マニングは Riddell の Revolution というヘルメットを使っていますから、それがハッキリと写っていたのです。
おわかりですね、Riddell はフットボール ヘルメットのメーカーなのです。
この話をすると、大抵「へぇ〜」って言われるのですが、現在世界中で使われている強化プラスティック製のヘルメットは、アメフトのために作られたものが転用され、世界に広まったものなのです。
1939年というと第二次世界大戦が始まった年でもありますが、アメフト用に作られた新型のヘルメットの事を知ったアメリカ政府は、すぐに軍隊のためにそれを導入したのです。
その後、機能性に優れたこのヘルメットが世界中に広まった事は言うまでもありません。
ヘルメットのおかげで命拾いしたそこのアナタ、もうアメフトには足を向けて寝られませんよ。これからはアメフトを観るんですよ!! って、霊感商法かよっ・・・・・orz
アメフトの事を、アメリカだけでしか通用しないマイナースポーツだと言う人がいます。オレはその事を否定しません。でも、その事を認めた上で、これ程世の中の役に立っているスポーツは他にないと思うのです。
それは、ここまで書いてきたヘルメットの事例でも解ってもらえると思いますが、アメフトというスポーツの性格上、装備や機材から審判やトレーニング方に至るまで、最新の技術を惜しげもなく投入し、それを他のスポーツや、さらには一般社会にもフィードバックしているという、紛れもない事実があるからです。
まぁ、ここまで言うと、贔屓の引き倒しだと言われるかもしれませんが・・・・
(追記に、アメフトのヘルメットの起源と最新作の話があります)
この Blog のプロフィールに使っている画像では、スモークのアイシールドのせいで顔が見えませんが、現在の日本のルールでは、クリア以外のアイシールドは禁止されていますから、これを試合に使う事はできません。
もともとアイシールドには、眼を保護するという役割の他に、眼を隠す事で、視線の動きから次のプレイを見破られる事を防ぐという、さらに重要な役割があったのです。クリアのものしか使えないのでは、あまり意味がないと思うのはオレだけではないでしょうね。
アメリカでは、そんな規制はありませんから、サングラス並みにいろんな種類のアイシールドを売っています。でも、それだけの種類をどう使い分けるんでしょうね。
そんな事を考えながら某ウェブサイトを見ていたら、見つけました。
 ミラード・アイシールド。
ミラード・アイシールド。思わず「カッコえぇー」って
言ってしまいましたね。
画像はグリーンミラーだけど
やっぱりシルヴァーがいい。
値段は約$50。オークリーの
イリディウムミラーは、なん
と$250!! ヘルメット本体が
2つ買えますよ。
オレがプレーヤーだった頃に
これがあったら、ゼーッタイ
使っていたでしょうね。
そういえば、東洋人と欧米人では頭の形が違い、上から見ると、東洋人は真円に近く、欧米人は前後に長い楕円形だと言われています。
そのため、東洋人がヘルメットを脱ぐ時は両手でシェルを横に広げながら脱がなければならないのですが、欧米人は片手でフェイスガードを持って引き上げるだけで脱げるのです。
それがまたカッコよく見えるのですよ。
どういうわけか、オレは頭が前後に長いので、片手で脱げるんです。
みんなが両手で脱いでいる時、オレはさり気なく片手で脱いで、内心ニンマリしていましたね。
まぁ、大人気ないと言えば大人気ないのですが・・・・・
次にアメフトの話を書く時のテーマは、もう決まっているのですよ。
あの装備の中のある物を、普段の生活に使うという話です。
人によっては、使える裏技(?)だと思うのですがね。
では、また。
Ciao. Arrivederci!! 続きを読む
2007年02月08日
『春の祭典』を振る
Ciao. spockです。
今回の話は Le sacre du printemps. あるいは The rite of spring.
ストラヴィンスキーの『春の祭典』(略称ハルサイ)を振る話です。
今回も、超マニアックな話ですよ。
今から6年くらい前、20世紀から21世紀に替わろうとしていた頃、音楽雑誌や音楽番組で、20世紀に作曲された曲のナンバーワンを選ぶ、というようなアンケートをやっていました。大抵の場合、ダントツで1位に選ばれていたのが『春の祭典』でした。
音楽の歴史を変えたというか、その後の音楽界に与えた影響を考えれば、当然の結果なのかもしれません。
オレが音楽にハマり始めた1970年代前半の頃は、この曲を振れる事が、プロの指揮者の条件のように言われていました。
去年亡くなった岩城宏之さんは、振り間違えて、一晩に2回もオーケストラを止めてしまった事を、ご自分の著書の中に書いておられるし、エピソードのデパート、山田一雄さんは、オーケストラが演奏を終っても、振リ続けていた事が知られています。(このお二人が共にB型なのは、何か関係があるんでしょうかね)
その当時の実況録音では、あのベルリン・フィルでさえ間違えているし、当時最高の技術を誇った、ショルティ/シカゴのスタジオ録音でも、簡単にミスを指摘する事ができます。
とにかく、振る事も演奏する事も憶える事も難しい曲だった事に間違いなかったのです。
でも、今ではアマチュアのオーケストラでさえ、当たり前に演奏しているのですよね。
当然指揮者も、ベートーヴェンやブラームスを振るのと同じように、苦もなく振っているようです。
あれは、2000年の春の事でした。
新宿のタワーレコードで、Dover(アメリカの出版社)のフルスコアを安く売っていたので、思わず3冊買ってしまったのですが、その中の1冊が『春の祭典』だったのです。
早速、CDを聴きながら見たのですが、何がなんやら分りません。スコアを読むのには慣れていたつもりだったのですが、追いつけないのです。
「わぁ、しまった。素人がこんな曲に手を出すんじゃなかった。」って後悔しましたね。でも、意地になって、聴きながら見ていたら、3回目にはついて行けるようになったんですよ。
そうなると面白くなって、手持ちのCDを取っ替え引っ替えしながら聴き比べ、新しい発見をしては喜んでいましたね。コレ、本人は面白がっているんですが、まわりから見れば、かなりヘンだったでしょうね。
そんな事をしているうちに、ふと、オレにも振れるんじゃないか、と思い始めたのですよ。
菜箸を持って来て、CDをかけ、スコアを見ながら振るのですが、コレが合わないんですよ。
この曲は1小節ごとに拍子が変わる、いわゆる変拍子がやたらと出てくるのですが、8分の4を2つに振るのは解ります。では、8分の5はどう振るのでしょう。
これはですね、頭で考えるよりも先に、身体の方が理解してきましたね。
8分の5は、やっぱり2つに振るのです。ただ、2つのうちの片方は、もう片方の1.5倍の長さにすればいいのです。要するに、12123あるいは12312の1のところを振ればいいのです。
この事が解れば、どんな変拍子でも振る事ができます。後は反射神経と運動神経の問題です。2日後には、全曲通して振れるようになっていました。
そうなってくると、ますます調子に乗り、いろんな演奏を聴いてみたくなって、CDを買い集めて来ましたねぇ。選ぶ基準は、特徴的な演奏、変わった演奏、そして評論家にこき下ろされている演奏でしたが・・・・
そういえば、その演奏を聴いたストラヴィンスキーが「冗談だろう」と言ったと伝えられるカラヤンの演奏も、ほとんどの評論家が貶していたけれど、オレは意外と好きだったりしますね。
まぁ、そんな事をして喜んでいたわけですが、この曲のCDが20枚を超えた頃、『ハルサイオタク』を自称する某評論家が、実演・録音含めて250種類以上は聴いた、と書いているのを見て、上には上があるものだと感心しましたね。
そんなある日、NHKの音楽番組で、デュトワがN響を振った『春の祭典』をやったのです。VTRに録って何回も見ましたねぇ。デュトワの振り方を見て、オレの考えたやり方と同じだと分った時はウレシかったですねぇ。その番組の解説で、デュトワが子供の頃、友達から借りたスコアを見ながら、並べたナベやヤカンを叩いてリズムを憶えた、と言っているのを聞いて、やっぱりな、と思いましたね。
さらにその後、ゲルギエフがN響を振ったのも放映されたので録画して観ましたが、8分の9をアクセントに合わせて121212123と振る(オレ)か、割り切って123123123と振る(ゲルギエフ)かの違いがあるだけで、あとは同じでした。この時もスゴ〜くウレシかったですね。
でも、コレって究極の自己満足の世界ですよね・・・・・orz
今でも時々、思い出したようにやってみる事があるのですが、リズム感を鈍らせない為のエクスサイズとして丁度いいと思います。
ちなみに、オレの『CDベスト3』は、シャイー/クリーヴランド、デイヴィス/ロイヤル・コンセルトヘボー、ゲルギエフ/キーロフです。

画像は、上記3枚と、カラヤンの78年ライヴです。
音楽が好きで、リズム感と運動神経に自信のある方(オレは全然自信ないですけど)挑戦してみませんか。パソコンゲームなんかよりも、ずっと知的な興奮を味わえる事請け合いですよ。(普通はやらないか・・・)
なお、Doverのフルスコア(この曲の場合、ミニチュアスコアは絶対止めた方がいい)は、Amazonで¥1500位で手に入りますよ。
ところで、この曲はもともとバレエ音楽なのですが、バレエ『春の祭典』が上演されるという話を滅多に聞く事がないし、VTRでも見た事がありません。バレエ『春の祭典』を観てみたいと、ズ〜ッと思っているのですが、どこかのバレエ団でやってくれないでしょうかね。
では、また。
Ciao. Arrivederci!!
今回の話は Le sacre du printemps. あるいは The rite of spring.
ストラヴィンスキーの『春の祭典』(略称ハルサイ)を振る話です。
今回も、超マニアックな話ですよ。
今から6年くらい前、20世紀から21世紀に替わろうとしていた頃、音楽雑誌や音楽番組で、20世紀に作曲された曲のナンバーワンを選ぶ、というようなアンケートをやっていました。大抵の場合、ダントツで1位に選ばれていたのが『春の祭典』でした。
音楽の歴史を変えたというか、その後の音楽界に与えた影響を考えれば、当然の結果なのかもしれません。
オレが音楽にハマり始めた1970年代前半の頃は、この曲を振れる事が、プロの指揮者の条件のように言われていました。
去年亡くなった岩城宏之さんは、振り間違えて、一晩に2回もオーケストラを止めてしまった事を、ご自分の著書の中に書いておられるし、エピソードのデパート、山田一雄さんは、オーケストラが演奏を終っても、振リ続けていた事が知られています。(このお二人が共にB型なのは、何か関係があるんでしょうかね)
その当時の実況録音では、あのベルリン・フィルでさえ間違えているし、当時最高の技術を誇った、ショルティ/シカゴのスタジオ録音でも、簡単にミスを指摘する事ができます。
とにかく、振る事も演奏する事も憶える事も難しい曲だった事に間違いなかったのです。
でも、今ではアマチュアのオーケストラでさえ、当たり前に演奏しているのですよね。
当然指揮者も、ベートーヴェンやブラームスを振るのと同じように、苦もなく振っているようです。
あれは、2000年の春の事でした。
新宿のタワーレコードで、Dover(アメリカの出版社)のフルスコアを安く売っていたので、思わず3冊買ってしまったのですが、その中の1冊が『春の祭典』だったのです。
早速、CDを聴きながら見たのですが、何がなんやら分りません。スコアを読むのには慣れていたつもりだったのですが、追いつけないのです。
「わぁ、しまった。素人がこんな曲に手を出すんじゃなかった。」って後悔しましたね。でも、意地になって、聴きながら見ていたら、3回目にはついて行けるようになったんですよ。
そうなると面白くなって、手持ちのCDを取っ替え引っ替えしながら聴き比べ、新しい発見をしては喜んでいましたね。コレ、本人は面白がっているんですが、まわりから見れば、かなりヘンだったでしょうね。
そんな事をしているうちに、ふと、オレにも振れるんじゃないか、と思い始めたのですよ。
菜箸を持って来て、CDをかけ、スコアを見ながら振るのですが、コレが合わないんですよ。
この曲は1小節ごとに拍子が変わる、いわゆる変拍子がやたらと出てくるのですが、8分の4を2つに振るのは解ります。では、8分の5はどう振るのでしょう。
これはですね、頭で考えるよりも先に、身体の方が理解してきましたね。
8分の5は、やっぱり2つに振るのです。ただ、2つのうちの片方は、もう片方の1.5倍の長さにすればいいのです。要するに、12123あるいは12312の1のところを振ればいいのです。
この事が解れば、どんな変拍子でも振る事ができます。後は反射神経と運動神経の問題です。2日後には、全曲通して振れるようになっていました。
そうなってくると、ますます調子に乗り、いろんな演奏を聴いてみたくなって、CDを買い集めて来ましたねぇ。選ぶ基準は、特徴的な演奏、変わった演奏、そして評論家にこき下ろされている演奏でしたが・・・・
そういえば、その演奏を聴いたストラヴィンスキーが「冗談だろう」と言ったと伝えられるカラヤンの演奏も、ほとんどの評論家が貶していたけれど、オレは意外と好きだったりしますね。
まぁ、そんな事をして喜んでいたわけですが、この曲のCDが20枚を超えた頃、『ハルサイオタク』を自称する某評論家が、実演・録音含めて250種類以上は聴いた、と書いているのを見て、上には上があるものだと感心しましたね。
そんなある日、NHKの音楽番組で、デュトワがN響を振った『春の祭典』をやったのです。VTRに録って何回も見ましたねぇ。デュトワの振り方を見て、オレの考えたやり方と同じだと分った時はウレシかったですねぇ。その番組の解説で、デュトワが子供の頃、友達から借りたスコアを見ながら、並べたナベやヤカンを叩いてリズムを憶えた、と言っているのを聞いて、やっぱりな、と思いましたね。
さらにその後、ゲルギエフがN響を振ったのも放映されたので録画して観ましたが、8分の9をアクセントに合わせて121212123と振る(オレ)か、割り切って123123123と振る(ゲルギエフ)かの違いがあるだけで、あとは同じでした。この時もスゴ〜くウレシかったですね。
でも、コレって究極の自己満足の世界ですよね・・・・・orz
今でも時々、思い出したようにやってみる事があるのですが、リズム感を鈍らせない為のエクスサイズとして丁度いいと思います。
ちなみに、オレの『CDベスト3』は、シャイー/クリーヴランド、デイヴィス/ロイヤル・コンセルトヘボー、ゲルギエフ/キーロフです。

画像は、上記3枚と、カラヤンの78年ライヴです。
音楽が好きで、リズム感と運動神経に自信のある方(オレは全然自信ないですけど)挑戦してみませんか。パソコンゲームなんかよりも、ずっと知的な興奮を味わえる事請け合いですよ。(普通はやらないか・・・)
なお、Doverのフルスコア(この曲の場合、ミニチュアスコアは絶対止めた方がいい)は、Amazonで¥1500位で手に入りますよ。
ところで、この曲はもともとバレエ音楽なのですが、バレエ『春の祭典』が上演されるという話を滅多に聞く事がないし、VTRでも見た事がありません。バレエ『春の祭典』を観てみたいと、ズ〜ッと思っているのですが、どこかのバレエ団でやってくれないでしょうかね。
では、また。
Ciao. Arrivederci!!
2007年02月07日
一糸乱れず
Ciao. spockです。
Super Bowl XLIも終りました。
雨の中の試合で、プレイヤーも観客も大変だったようですが、ベアーズの守備力をコルツの攻撃力が上回ったという結果になりましたね。
今回は、アメフトを通してspockが見た、アメリカとアメリカ人の話です。
スーパーボウルを世界最大のスポーツイヴェントだと言うと、異を唱える人もいるだろうけれど、1日で動く、カネ・モノ・ヒトを考えると、あながち間違いではないと思います。
この1試合だけで、NFLに入る放送権料はいくらになるんでしょうね。世界中の他のスポーツが束になっても敵わない額である事は間違いないようです。
ただ、NFLがスゴいと思うのは、それだけの放送権料を動かしていながら、TVが観客動員数を減らさない為のルールをきちんと作っている事なんです。『ブラックアウト』なんかは、その最も解りやすい例でしょう。
ブラックアウトというのは、ゲーム開始の72時間前までに、あるゲームのティケットが完売しなかった場合、出場ティームのフランチャイズ地区及び75マイル圏内のホーム地区では、そのゲームのTV中継が行われず、他の地区のゲームが放送されるわけです。
『地元ではファンにスタジアムに来てもらう事が最優先事項』という、NFLのポリシーに則ったものになっているのです。
このやり方をそのまま持って来るのは無理だとしても、観客動員数や視聴率の低下に対して、何の打開策も持たないでいる日本のプロ野球やサッカーは、少しは参考にして考えたらいいと思うのです。
スーパーボウルを生で観るというのは不可能かもしれませんが、NFLのゲームを一度観てみたいですね。インベスコ・フィールド・アト・マイルハイ(デンヴァー)に行って、ブロンコスのゲームを観てみたいとは思っているのですがね・・・・
ところで、最近、NHLに日本人プレイヤーが登場したので、アメリカの4大スポーツで、日本人がプレイした事がないのはNFLだけになりました。でも、NFLに日本人プレイヤーが登場するのは、ズ〜ッと先のことだろうと思います。
運動能力や体格の事なら、ポジションによっては日本人でも通用するプレイヤーは出てくると思います。問題は他にあるのです。
アメフトの競技としての性格上、日本のアマチュアティームでも、プレイブックには、専門用語・特殊用語の羅列で、一般人には理解不能でしょう。プレイコールだって、何を言っているのか解らないと思います。
それが、トップレヴェルのプロだったらどうでしょう。ネイティヴ同様の言語力がない限り、通用しないでしょうね。そこが、他のスポーツとの一番大きな違いであり、難しさなのでしょう。
さて、ここまでタイトルに関連した話が出て来ていませんが、ここからですよ。
1984年、ロサンジェルスでオリンピックが開催されました。ド派手な開会式もさる事ながら、一番印象に残ったのは、日本とアメリカの選手団の入場の仕方の違いについてなのです。
お揃いのスーツをキチッと着て、歩幅さえ統一された状態で行進した日本選手団に対し、ユニフォームを着ている事以外、一人一人が全く違う事をしながら入場したアメリカ選手団。
この違いは何なのだろうと考えましたねぇ。
あれ以来、日本人に対しては『一糸乱れぬ団体行動』、アメリカ人に対しては『バラバラで適当な個人的行動』というイメージが、自分の中にできていたように思います。スポーツ以外の事から見ても、そのイメージは間違っていないと・・・・
15年前の7月初め、フットボールのゲームのため、ある場所へ行きました。
普通ならありえない環境の中で、ある種の感動をしながら、サイドラインに立ってゲームを観ていました。
その場所とは、横須賀米軍基地内のフットボール・フィールド。
ウチのティームの関係者以外は全員アメリカ人で、スピーカーから流れるアナウンスは勿論英語、サイドラインのベンチの上には、大きなゲータレイドのタンクが3本(今回のスーパーボウルでも、勝利が決まる直前に、コルツのプレイヤー達がそのタンクを持ち上げて、ヘッドコーチのトニー・ダンジーにドリンクシャワーを浴びせていましたね)。あぁ、アメリカだなぁ、って思いましたね。
4ヵ月前にフットボールを始めたばかりのオレは、その前の週にゲームデヴューしていました。といっても、勝ちの決まったゲームの終盤に、戦略上それ程重要ではないポジションで(一応WRでしたが)出してもらったわけなのですが・・・
相手はネイヴィー(海軍)のティームとはいえ、臨時の寄せ集めティームですから、こっちが勝つとみんな思っていたようです。(実際、前年は勝ったそうですから)
で、オレも、またゲームに出れるなぁ、って思っていたのですよ。
ところが相手は強かった。キックオフ直後からむこうが優勢なのが解りましたから。そのうち、こっちのLBが足を骨折してアンビュランスで運ばれて行き、こりゃダメだというムードができてしまったのですよ。
そんな中、オレがゲームに出る事はないなぁ、と思いながらサイドラインに立ってゲームを観ていたのですが、ふと、ある事に気が付いて、感動しましたねぇ。
そのある事とは、スクリメイジライン上でのプレイヤー達の動きなのです。
そこのところを解説すると、QBの"Ready"のコールでそれぞれの位置に着き、"Set"のコールで規定のポジション(姿勢)をとって1秒以上静止し(ここで動くと反則です)、次の決められたコールで飛び出すわけです。
で、その"Set"のコールに反応しての動き。『一糸乱れず』なんてものではなく、動く距離といい、角度といい、まるでひとつの生き物のように思えるのです。これ、臨時編成のティームですよ。
この時、アメリカ人に対する、『バラバラで適当』というイメージは完全に壊れ去り、尊敬の念さえ抱きました。
試合後のパーティーは、フライドチキン(もも1本丸ごと)にグリーンピースにポテト、バドワイザーにコーラという、いかにもアメリカなパーティーでしたが、そこで見る彼らは、どう見ても『ひとつの生き物』ではなく、見事なまでに『バラバラで適当』だったのが面白かったですね。
帰る時、動き始めたバスに向かって、全員で声を揃えて「マタネ」と言ってくれた事を、今でもハッキリと憶えています。
昔読んだ血液型の本のO型のところに、普段は仲が悪かったりライバル意識を持っていても、共通の目標を見つけると一致団結して物事にあたる、とありました。その本には、アメリカ人は大半がO型であるとも書いてありました。それを思い出して、何かスゴく納得しましたね。
アメリカがスポーツや戦争に強いのは、そういう国民性のためなのだろうな、ってね。 (追記に続きの血液型の話があります)
そんなアメリカを象徴しているのがNFLなのですが、NFLは最近急増しているヒスパニック系の移民(彼らはサッカーしか知らないわけです)のために、NFLの面白さを知らせるキャンペーンを始めました。そういう戦略を見るにつけ、『世界で最も成功したスポーツビジネス』の座をNFLが維持し続けるのは間違いないだろうと思うのです。
こんな話を延々とかいていたら、フットボールをやりたくなってきましたね。まぁ、この歳になって身体が動くかどうか・・・でも、ネイヴィーティームの最高齢者は56歳だとQBがパーティーの時に言っていましたから、身体さえ作っていればできるのかもしれません。
てなわけで、今回の画像はコレ!!

アイシールド32 ってとこですかね。
この装備を身に付けたのは何年ぶりでしょう。
まぁ、体型が変わっていない事だけは確認できましたけどね・・・・
では、また。
Ciao. Arrivederci!! 続きを読む
Super Bowl XLIも終りました。
雨の中の試合で、プレイヤーも観客も大変だったようですが、ベアーズの守備力をコルツの攻撃力が上回ったという結果になりましたね。
今回は、アメフトを通してspockが見た、アメリカとアメリカ人の話です。
スーパーボウルを世界最大のスポーツイヴェントだと言うと、異を唱える人もいるだろうけれど、1日で動く、カネ・モノ・ヒトを考えると、あながち間違いではないと思います。
この1試合だけで、NFLに入る放送権料はいくらになるんでしょうね。世界中の他のスポーツが束になっても敵わない額である事は間違いないようです。
ただ、NFLがスゴいと思うのは、それだけの放送権料を動かしていながら、TVが観客動員数を減らさない為のルールをきちんと作っている事なんです。『ブラックアウト』なんかは、その最も解りやすい例でしょう。
ブラックアウトというのは、ゲーム開始の72時間前までに、あるゲームのティケットが完売しなかった場合、出場ティームのフランチャイズ地区及び75マイル圏内のホーム地区では、そのゲームのTV中継が行われず、他の地区のゲームが放送されるわけです。
『地元ではファンにスタジアムに来てもらう事が最優先事項』という、NFLのポリシーに則ったものになっているのです。
このやり方をそのまま持って来るのは無理だとしても、観客動員数や視聴率の低下に対して、何の打開策も持たないでいる日本のプロ野球やサッカーは、少しは参考にして考えたらいいと思うのです。
スーパーボウルを生で観るというのは不可能かもしれませんが、NFLのゲームを一度観てみたいですね。インベスコ・フィールド・アト・マイルハイ(デンヴァー)に行って、ブロンコスのゲームを観てみたいとは思っているのですがね・・・・
ところで、最近、NHLに日本人プレイヤーが登場したので、アメリカの4大スポーツで、日本人がプレイした事がないのはNFLだけになりました。でも、NFLに日本人プレイヤーが登場するのは、ズ〜ッと先のことだろうと思います。
運動能力や体格の事なら、ポジションによっては日本人でも通用するプレイヤーは出てくると思います。問題は他にあるのです。
アメフトの競技としての性格上、日本のアマチュアティームでも、プレイブックには、専門用語・特殊用語の羅列で、一般人には理解不能でしょう。プレイコールだって、何を言っているのか解らないと思います。
それが、トップレヴェルのプロだったらどうでしょう。ネイティヴ同様の言語力がない限り、通用しないでしょうね。そこが、他のスポーツとの一番大きな違いであり、難しさなのでしょう。
さて、ここまでタイトルに関連した話が出て来ていませんが、ここからですよ。
1984年、ロサンジェルスでオリンピックが開催されました。ド派手な開会式もさる事ながら、一番印象に残ったのは、日本とアメリカの選手団の入場の仕方の違いについてなのです。
お揃いのスーツをキチッと着て、歩幅さえ統一された状態で行進した日本選手団に対し、ユニフォームを着ている事以外、一人一人が全く違う事をしながら入場したアメリカ選手団。
この違いは何なのだろうと考えましたねぇ。
あれ以来、日本人に対しては『一糸乱れぬ団体行動』、アメリカ人に対しては『バラバラで適当な個人的行動』というイメージが、自分の中にできていたように思います。スポーツ以外の事から見ても、そのイメージは間違っていないと・・・・
15年前の7月初め、フットボールのゲームのため、ある場所へ行きました。
普通ならありえない環境の中で、ある種の感動をしながら、サイドラインに立ってゲームを観ていました。
その場所とは、横須賀米軍基地内のフットボール・フィールド。
ウチのティームの関係者以外は全員アメリカ人で、スピーカーから流れるアナウンスは勿論英語、サイドラインのベンチの上には、大きなゲータレイドのタンクが3本(今回のスーパーボウルでも、勝利が決まる直前に、コルツのプレイヤー達がそのタンクを持ち上げて、ヘッドコーチのトニー・ダンジーにドリンクシャワーを浴びせていましたね)。あぁ、アメリカだなぁ、って思いましたね。
4ヵ月前にフットボールを始めたばかりのオレは、その前の週にゲームデヴューしていました。といっても、勝ちの決まったゲームの終盤に、戦略上それ程重要ではないポジションで(一応WRでしたが)出してもらったわけなのですが・・・
相手はネイヴィー(海軍)のティームとはいえ、臨時の寄せ集めティームですから、こっちが勝つとみんな思っていたようです。(実際、前年は勝ったそうですから)
で、オレも、またゲームに出れるなぁ、って思っていたのですよ。
ところが相手は強かった。キックオフ直後からむこうが優勢なのが解りましたから。そのうち、こっちのLBが足を骨折してアンビュランスで運ばれて行き、こりゃダメだというムードができてしまったのですよ。
そんな中、オレがゲームに出る事はないなぁ、と思いながらサイドラインに立ってゲームを観ていたのですが、ふと、ある事に気が付いて、感動しましたねぇ。
そのある事とは、スクリメイジライン上でのプレイヤー達の動きなのです。
そこのところを解説すると、QBの"Ready"のコールでそれぞれの位置に着き、"Set"のコールで規定のポジション(姿勢)をとって1秒以上静止し(ここで動くと反則です)、次の決められたコールで飛び出すわけです。
で、その"Set"のコールに反応しての動き。『一糸乱れず』なんてものではなく、動く距離といい、角度といい、まるでひとつの生き物のように思えるのです。これ、臨時編成のティームですよ。
この時、アメリカ人に対する、『バラバラで適当』というイメージは完全に壊れ去り、尊敬の念さえ抱きました。
試合後のパーティーは、フライドチキン(もも1本丸ごと)にグリーンピースにポテト、バドワイザーにコーラという、いかにもアメリカなパーティーでしたが、そこで見る彼らは、どう見ても『ひとつの生き物』ではなく、見事なまでに『バラバラで適当』だったのが面白かったですね。
帰る時、動き始めたバスに向かって、全員で声を揃えて「マタネ」と言ってくれた事を、今でもハッキリと憶えています。
昔読んだ血液型の本のO型のところに、普段は仲が悪かったりライバル意識を持っていても、共通の目標を見つけると一致団結して物事にあたる、とありました。その本には、アメリカ人は大半がO型であるとも書いてありました。それを思い出して、何かスゴく納得しましたね。
アメリカがスポーツや戦争に強いのは、そういう国民性のためなのだろうな、ってね。 (追記に続きの血液型の話があります)
そんなアメリカを象徴しているのがNFLなのですが、NFLは最近急増しているヒスパニック系の移民(彼らはサッカーしか知らないわけです)のために、NFLの面白さを知らせるキャンペーンを始めました。そういう戦略を見るにつけ、『世界で最も成功したスポーツビジネス』の座をNFLが維持し続けるのは間違いないだろうと思うのです。
こんな話を延々とかいていたら、フットボールをやりたくなってきましたね。まぁ、この歳になって身体が動くかどうか・・・でも、ネイヴィーティームの最高齢者は56歳だとQBがパーティーの時に言っていましたから、身体さえ作っていればできるのかもしれません。
てなわけで、今回の画像はコレ!!

アイシールド32 ってとこですかね。
この装備を身に付けたのは何年ぶりでしょう。
まぁ、体型が変わっていない事だけは確認できましたけどね・・・・
では、また。
Ciao. Arrivederci!! 続きを読む
2007年02月05日
手作りマカロニの話
Ciao. spockです。
このBlogに、趣味の事は多く書いているけれど、料理の事はあまり書いていません。
オレはプロですから、Blogに事細かく書いたのを読んで「おいしそう」と言ってもらっても、あまり意味がないんですよ。食べた人に「うまい!!」と言ってもらえてナンボ、なんです。
失礼な言い方である事を承知の上で本音を言えば、『Blogを見てゴチャゴチャ言ってるヒマがあったら、食べに来い!!』って事です。
でも、今回は料理の話です。
月刊ブレスのちるちるさんの1月31日のBlogに、ウチの『手作りマカロニ』の事が書いてありました。
コレです。

これ、1本1本手で巻いて作るのですが、1人前に70〜80本必要ですから、どれだけの時間がかかるか予想してみて下さい。
カウンターに来られるお客さんは、大抵これを注文されますから、結構出るんですが、その分は一生懸命作ってますよ。
このマカロニを作り始めたきっかけは、20年も前に、イタリアから送られてきた、1枚の写真でした。
その写真を撮ったカメラマンは、一般の日本人なら、まず行く事のないような、イタリアの奥地の風景ばかり撮っている人でした。
ある時送られて来た写真の中に、どこかの村の広場で、オバちゃん達が集まってパスタを作っているところが写っていました。
その数枚の写真から作り方を想像し、試行錯誤しながらできたのが、このマカロニなのです。
実際、作るのは非常に面倒です。でもこの歯応えは、他にチョッと思いつかない類いのものなので、面倒でも作り続けているわけです。
そんな訳なので、このマカロニは、おそらく日本ではウチにしかないだろうと思います。
まぁ、手作りですから、結構長さにバラツキがあったり、1本ごとに微妙に歯応えが違っていたりする事を面白がってもらえればいいのですが、神経質すぎる人にはお勧めできませんね。
で、このマカロニに、ソーセージ入りの辛口トマトソースを合わせるのですが、ソースにバターを使っているせいか、ビールが合うんですよ。ウチでお出ししているビールは、ブラウマイスターの生ですが、その濃い味が、実によく合います。
勿論ワインも合うのですが、このマカロニをつまみにしてビールを飲まれる方が多い事をみると、やっぱりビールなんでしょうね。
出来上がった料理の画像は・・・・・ありません。
店に来て、実際に食べて下さい。
では、また。
Ciao. Arrivederci!!
このBlogに、趣味の事は多く書いているけれど、料理の事はあまり書いていません。
オレはプロですから、Blogに事細かく書いたのを読んで「おいしそう」と言ってもらっても、あまり意味がないんですよ。食べた人に「うまい!!」と言ってもらえてナンボ、なんです。
失礼な言い方である事を承知の上で本音を言えば、『Blogを見てゴチャゴチャ言ってるヒマがあったら、食べに来い!!』って事です。
でも、今回は料理の話です。
月刊ブレスのちるちるさんの1月31日のBlogに、ウチの『手作りマカロニ』の事が書いてありました。
コレです。

これ、1本1本手で巻いて作るのですが、1人前に70〜80本必要ですから、どれだけの時間がかかるか予想してみて下さい。
カウンターに来られるお客さんは、大抵これを注文されますから、結構出るんですが、その分は一生懸命作ってますよ。
このマカロニを作り始めたきっかけは、20年も前に、イタリアから送られてきた、1枚の写真でした。
その写真を撮ったカメラマンは、一般の日本人なら、まず行く事のないような、イタリアの奥地の風景ばかり撮っている人でした。
ある時送られて来た写真の中に、どこかの村の広場で、オバちゃん達が集まってパスタを作っているところが写っていました。
その数枚の写真から作り方を想像し、試行錯誤しながらできたのが、このマカロニなのです。
実際、作るのは非常に面倒です。でもこの歯応えは、他にチョッと思いつかない類いのものなので、面倒でも作り続けているわけです。
そんな訳なので、このマカロニは、おそらく日本ではウチにしかないだろうと思います。
まぁ、手作りですから、結構長さにバラツキがあったり、1本ごとに微妙に歯応えが違っていたりする事を面白がってもらえればいいのですが、神経質すぎる人にはお勧めできませんね。
で、このマカロニに、ソーセージ入りの辛口トマトソースを合わせるのですが、ソースにバターを使っているせいか、ビールが合うんですよ。ウチでお出ししているビールは、ブラウマイスターの生ですが、その濃い味が、実によく合います。
勿論ワインも合うのですが、このマカロニをつまみにしてビールを飲まれる方が多い事をみると、やっぱりビールなんでしょうね。
出来上がった料理の画像は・・・・・ありません。
店に来て、実際に食べて下さい。
では、また。
Ciao. Arrivederci!!
Posted by spock at
19:23
│Comments(0)
2007年02月02日
永遠の40番 ワルター/ウィーン 1952
Ciao. spockです。
今回は、オレの最も愛するモーツァルトとワルターの話です。
もう、3週間以上も前の事ですが、店のビールやワインをお願いしているキリンビールのMさんが、うちの担当のIさんと一緒に、年始の挨拶に来られました。
うちのような、大して売上げのない店にまでわざわざ来てもらった事に驚くと共にありがたく思いましたが、さらに驚いた事に「お年賀です。」と言って、大きな封筒を二つ折りにした包みを手渡してくれたのです。早速開けてみると、出てきたのがコレ

去年、ソニー・クラシカルが、プレミア・ゴールドと銘打って限定発売した、金蒸着CDシリーズの中の、ワルター/ウィーン・フィルによる、モーツァルトの交響曲40番と25番です。
去年の年賀状に、モーツァルト生誕250年の事を書いたついでに「ワルター/ニューヨークの演奏が一番好き」と書いたのを、Mさんは憶えていてくれたのです。
Mさんは「普通のCDより、コレの方が音がいいんです。」と、ニコニコしながら言われました。
この、ワルター/ウィーンの40番、1952年の5月18日、ウィーン・フィルの本拠地、ムズィークフェラインザールでの演奏会の実況録音なのですが、ナチから逃れ、亡命してアメリカへ渡ったワルターが、ウィーンへ里帰りしてウィーン・フィルを指揮した演奏会の録音です。
この演奏会では、40番の後にマーラーの『大地の歌』が演奏されていますが、この2曲はワルターの十八番中の十八番なのです。その時の『大地の歌』の録音が、5年前に初めてCDで発売されたので、手に入れて聴いてみましたが、これがまたスゴい演奏です。(この演奏会の前にDeccaが録音した演奏より、ずっと濃い演奏です)この2曲に関しては、このときの演奏を超えるものはないと確信しています。
こんな演奏会を実際に聴く事ができた人達が、羨ましくて仕方がありません。もし、タイムマシーンが本当に発明されて、過去のどこへでも行けるようになったら、オレは迷う事なく、真っ先にこの時の演奏会に行きます。
この演奏の内容について言うなら、あのテーマの最後にかけられた上向ポルタメントに集約されるでしょう。
普通ポルタメントは、弧を描くように、上品にかけられるものですが、この演奏では、直線的に力強くかけられています。頭で考えると、モーツァルトには合いそうもないのですが、実際に聴くと、思わず引き込まれてしまい、ゾクゾクしながら、最後まで聴いてしまいます。
それと、もう一カ所スゴいところがあるのです。フィナーレの第2主題を、クラリネットのソロが吹いていくところ。微妙なニュアンスの付け方も絶品ですが、ヴィーナー・クラリネットの柔らかい音を聴いているだけでも、幸せな気分になりますね。モーツァルトがクラリネットを加えた改訂版を書いた理由が良く解ります。この曲を聴いたシューベルトが『フィナーレから天使の歌が聞こえる』と言ったのは、この部分の事だとオレは確信しています。
ワルターがモーツァルトを演奏する前に、オーケストラに向かって言った『泣き伏したくなる程明るくなければなりません』という有名な言葉を、これ程実感させてくれる演奏を他に知りません。
勿論、この演奏に否定的な人(ロマンティック過ぎるという事らしいのですが)や、あのポルタメントを聴いて思わず笑ったという人がいる事も事実です。でも、オレにとっては、永遠に抱きしめていたい40番です。
実を言うと、今回頂いたCDは、3枚目なのです。つまり、他に同じ内容のものを2枚持っているのです。
最初の1枚は、ちょうど30年前、高校2年の時に買いました。勿論、CDではなくLPでしたが。
SOCO-110という番号まで憶えているそのLPは、ちょうど100枚目に買ったレコードでした。
買った日は1977年2月6日、盤面に針を落としたのは、7日の夜9時少し前の事です。(なぜ憶えているかというと、2月7日は誕生日なので、自分の生まれた時刻に合わせて針を落としたからなのですよ)
2枚目はCDです。いつ買ったのかハッキリとは憶えていません。でも、最初のLPより多く聴いた事は確かです。
そして、今回頂いたCDです。実はこのCD、まだ聴いていないのです。ゆっくりと落ち着いた時に聴こうと思っていたのですが、このところバタバタしていて、気分的に落ち着かない事が多かったものですから・・・・
今、この文を書いていて決めました。このCDは、2月7日の夜に聴く事にします。身体があいているなら、9時少し前に。
30年前、17歳になるのと同時に初めてこの演奏を聴いたオレは、47歳になるのと同時にこの演奏を聴いて、何を想うのでしょう。
では・・・・・また。
Arrivederci!!
今回は、オレの最も愛するモーツァルトとワルターの話です。
もう、3週間以上も前の事ですが、店のビールやワインをお願いしているキリンビールのMさんが、うちの担当のIさんと一緒に、年始の挨拶に来られました。
うちのような、大して売上げのない店にまでわざわざ来てもらった事に驚くと共にありがたく思いましたが、さらに驚いた事に「お年賀です。」と言って、大きな封筒を二つ折りにした包みを手渡してくれたのです。早速開けてみると、出てきたのがコレ

去年、ソニー・クラシカルが、プレミア・ゴールドと銘打って限定発売した、金蒸着CDシリーズの中の、ワルター/ウィーン・フィルによる、モーツァルトの交響曲40番と25番です。
去年の年賀状に、モーツァルト生誕250年の事を書いたついでに「ワルター/ニューヨークの演奏が一番好き」と書いたのを、Mさんは憶えていてくれたのです。
Mさんは「普通のCDより、コレの方が音がいいんです。」と、ニコニコしながら言われました。
この、ワルター/ウィーンの40番、1952年の5月18日、ウィーン・フィルの本拠地、ムズィークフェラインザールでの演奏会の実況録音なのですが、ナチから逃れ、亡命してアメリカへ渡ったワルターが、ウィーンへ里帰りしてウィーン・フィルを指揮した演奏会の録音です。
この演奏会では、40番の後にマーラーの『大地の歌』が演奏されていますが、この2曲はワルターの十八番中の十八番なのです。その時の『大地の歌』の録音が、5年前に初めてCDで発売されたので、手に入れて聴いてみましたが、これがまたスゴい演奏です。(この演奏会の前にDeccaが録音した演奏より、ずっと濃い演奏です)この2曲に関しては、このときの演奏を超えるものはないと確信しています。
こんな演奏会を実際に聴く事ができた人達が、羨ましくて仕方がありません。もし、タイムマシーンが本当に発明されて、過去のどこへでも行けるようになったら、オレは迷う事なく、真っ先にこの時の演奏会に行きます。
この演奏の内容について言うなら、あのテーマの最後にかけられた上向ポルタメントに集約されるでしょう。
普通ポルタメントは、弧を描くように、上品にかけられるものですが、この演奏では、直線的に力強くかけられています。頭で考えると、モーツァルトには合いそうもないのですが、実際に聴くと、思わず引き込まれてしまい、ゾクゾクしながら、最後まで聴いてしまいます。
それと、もう一カ所スゴいところがあるのです。フィナーレの第2主題を、クラリネットのソロが吹いていくところ。微妙なニュアンスの付け方も絶品ですが、ヴィーナー・クラリネットの柔らかい音を聴いているだけでも、幸せな気分になりますね。モーツァルトがクラリネットを加えた改訂版を書いた理由が良く解ります。この曲を聴いたシューベルトが『フィナーレから天使の歌が聞こえる』と言ったのは、この部分の事だとオレは確信しています。
ワルターがモーツァルトを演奏する前に、オーケストラに向かって言った『泣き伏したくなる程明るくなければなりません』という有名な言葉を、これ程実感させてくれる演奏を他に知りません。
勿論、この演奏に否定的な人(ロマンティック過ぎるという事らしいのですが)や、あのポルタメントを聴いて思わず笑ったという人がいる事も事実です。でも、オレにとっては、永遠に抱きしめていたい40番です。
実を言うと、今回頂いたCDは、3枚目なのです。つまり、他に同じ内容のものを2枚持っているのです。
最初の1枚は、ちょうど30年前、高校2年の時に買いました。勿論、CDではなくLPでしたが。
SOCO-110という番号まで憶えているそのLPは、ちょうど100枚目に買ったレコードでした。
買った日は1977年2月6日、盤面に針を落としたのは、7日の夜9時少し前の事です。(なぜ憶えているかというと、2月7日は誕生日なので、自分の生まれた時刻に合わせて針を落としたからなのですよ)
2枚目はCDです。いつ買ったのかハッキリとは憶えていません。でも、最初のLPより多く聴いた事は確かです。
そして、今回頂いたCDです。実はこのCD、まだ聴いていないのです。ゆっくりと落ち着いた時に聴こうと思っていたのですが、このところバタバタしていて、気分的に落ち着かない事が多かったものですから・・・・
今、この文を書いていて決めました。このCDは、2月7日の夜に聴く事にします。身体があいているなら、9時少し前に。
30年前、17歳になるのと同時に初めてこの演奏を聴いたオレは、47歳になるのと同時にこの演奏を聴いて、何を想うのでしょう。
では・・・・・また。
Arrivederci!!