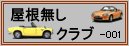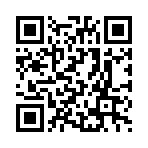スポンサーリンク
この広告は一定期間(1ヶ月以上)更新のないブログに表示されます。
ブログ記事の情報が古い場合がありますのでご注意下さい。
(ブログオーナーが新しい記事を投稿すると非表示になります。)
ブログ記事の情報が古い場合がありますのでご注意下さい。
(ブログオーナーが新しい記事を投稿すると非表示になります。)
2011年10月27日
定期演奏会、無事終了 その2
Ciao. spockです。
前回の更新からだいぶ時間が経ってしまいましたが、気がついてみれば、もう10月も終わりかぁ・・・・
店がヒマなわりには結構バタバタしていて、ブログに向かう時間がなかなかとれなかったのですが、前回の更新から1月半も経ってしまったんだなぁ、と改めて月日の過ぎる速さを実感していますけどね。
7月8月と忙しかったのに、9月に入った途端にヒマになり、10月は少し持ち直したという感じですが、同業者に聞くと同じような答えが返ってきますから、ヒマなのはウチだけではないのでしょうけど、世の中の流れ自体を寂しく感じてしまうのは残念です。
これからの行楽シーズンに合わせて、高山が盛り上がってほしいものですね。
さて、前回に続き、高山室内合奏団の第8回定期演奏会の事を書きますが、その前に、現在決まっている高山室内合奏団の今後の演奏予定をお知らせします。
12月17日(土)14:30 神岡 船津座
12月18日(日)14:00 文化会館
恒例の『クリスマス ファミリーコンサート』
アルビノーニのアダージョ
宮崎アニメの音楽から3曲
アンダーソンの『クリスマス フェスティヴァル』
バッハの『管弦楽組曲第2番 ロ短調』から4曲
アンサンブル ルシェッロのチェロ8重奏で『イエスタデイ』
その他
休憩時間に、お茶とお菓子が出ます。そして今年も (株)なべしま さんによる、ポップコーンの作製実演があり、できたてのポップコーンを食べてもらえますよ。
2012年8月26日(日) 世界生活文化センター 飛騨芸術堂
第9回定期演奏会
ベートーヴェンのピアノ協奏曲第4番ト長調 をメインとするプログラム
2013年夏 世界生活文化センター 飛騨芸術堂
第10回定期演奏会
ベートーヴェンの交響曲第5番ハ短調 をメインとするプログラム
現時点での予定は以上です。
では、本文に入りましょう。
前回の『その1』では、前日のゲネプロについて書きましたが、今回は演奏会当日の事を書きます。
さぁ、本番当日です。
10:30集合、という事になっていましたが、オレは30分前にホールに行きました。
というのも、毎年、演奏会の前日に、ドンマイヤーさんに楽器の調整をしてもらうのですが、今年はドンマイヤーさんが来るのが遅くなったため、前日にできなかったので、朝イチで行って、やってもらおうと思ったわけです。
で、ドンマイヤーさんの楽屋へ行くと、すでに2人の人が待っていて・・・・まぁ、みんな考える事は同じなんですね。
冷房の効いた部屋だというのに、汗だくになりながら、ドンマイヤーさんは楽器の調整をしていました。
調整してもらう前に、一度弾いて、音と感覚を身体で憶えておきます。
まず、弓の毛を緩めて、木の部分を磨いて汚れを落とすのですが、それだけの事なのに、弓を受け取って持ってみると、軽く感じるんですよ。
これは本当に不思議ですね。
次にヴァイオリン本体を磨いて汚れを落とします。
本当は、裏板だけのはずだったのですが、オレのヴァイオリンの表板が松脂で汚れていたので、表板も磨いてもらえました。
磨きながらドンマイヤーさんは、ストラディヴァーリやグァルネーリのような名器は、表面のニスに汚れがつかないので、それだからこそ300年経ってもいい状態で残っているのだ、と話してくれましたが、まぁ、すぐに汚れがついてしまうオレの楽器は、やっぱり安物という事なんでしょうね。
その後、魂柱を調整をしてもらいましたが、ほんの少し動かすだけで、音が違ってくるのが分かるんですよね。
まわりの人達から、どんな音がいいのか希望を言う方がいいよ、と言われたので、上手に聞こえるようにして下さい、って言ったら笑われましたけど。
いよいよ本番前の最後の練習、文字通りの『ゲネプロ』に入ります。
とにかく、ミスがあっても止まらずに最後まで行こう、という事で、気負う事なく、わりと気楽に演奏していたのですが、やはり集中力が上がってきているのか、ミスはあったものの、緊張感を持続しながら、一気に演奏してしまいましたからね。
未完成の最終練習に入る前の休憩中です。

最終練習の前という事で、みんな、自分のパートの弾き込みに一生懸命になってます。

管楽器の人達も、同じですね。

そのゲネプロが終って、楽屋へ引き上げようとしていたら、トランペットとトロンボーンが、未完成の第2楽章のフォルテッシモのところを吹き始めたのです。

ゲネプロの時に金管楽器のアンサンブルが少しずれたようで、その部分を金管楽器だけで合わせていたのですが、この時は、ほぼ完璧に合ってました。
いや、立派です。
楽屋へ戻ろうと、舞台裏の廊下を通っていたら、ファーストホルンの小笠原さんが、ホルンの手入れをしていました。
それが例のナチュラルホルンですか、って訊いたら、自分で溶接して作ったんです、と言って見せてくれたのですが、いかにも手作りという無骨なホルンでした。
そこでしばらく話をしたのですが、ふと思いついて、来年は『エロイカ』(ベートーヴェンの交響曲第3番『英雄』の事 第3楽章のトリオで3本のホルンが大活躍する)なんかどうでしょう、って言ったら、いいですねぇ あれならやれますよ、という答え。
大曲故に難しい点が多いとは思うけど、本当にできたらすごい事だと思うのですが。
下の階の楽屋へ戻り、昼飯を食べ、本番用の黒のスーツに着替え、開演までしばらく休憩します。
開演15分前にチューニングを始め、開演10分前にステージ袖に集合。
トップの人達は結構緊張しているようだし、指揮者の鴨宮さんも、かなり緊張しているみたい。
一番後ろで弾くオレは、全然緊張する事もなく構えてましたけど。
覗き窓から客席を見ると、結構席が埋まっていて、前の方には中学の同級生のN君の顔が見えます。
開演を知らせるアナウンスが流れ、客席が落着いたところで、舞台の上手からは、ヴィオラ、チェロ、コントラバスが、下手からは、ヴァイオリンが出ます。
全員が席に着いたところで、コンサートミストレスの出すAの音に合わせて、低音側から順にAの音を合わせ、全楽器がAを合わせたところで、さらに他の弦を合わせていきます。
このチューニングの完全5度の響きが聞こえると、コンサートの始まりを実感する人も多いようですが、弾く方としては、いよいよ緊張感が高まります。
指揮者が登場し、拍手が収まったところで指揮棒が上がり、全員が楽器を構えます。
最初の曲、ヴィヴァルディの『聖なる墓に』は、セカンドヴァイオリンの長いFis(ファ♯)の音で始まるので、その出だしには緊張します。
でも、音が出てしまえば、後はまわりの音を聴きながら合わせていけます。
この曲は、演奏時間にして5分程度の小品で、前半のゆっくりとした部分と、後半の速いフーガと、2つの部分からできていますが、当然、前半の方が弾き易い。
後半のフーガは、少しごまかしたところもあったけれど、フーガの掛け合いがピッタリ合うと気持ちがいいですね。
続いて、ヴィヴァルディのヴァイオリン協奏曲『夏』です。
去年のクリスマスコンサートで『冬』をやりましたが、『夏』の方が難しいですね。
この曲の編成は、前の曲に、ソロヴァイオリンとチェンバロが加わります。
ソロは井上先生です。
普通、ソリストは立って演奏するのですが、今回の井上先生が座って演奏した事を不思議に思った人がおられるかもしれません。
ソロと指揮を兼ねて演奏するのなら立って演奏するけど、指揮者がいるのだからオーケストラの一員として座って演奏する、というのが井上先生の意見。
なるほど、確かな見識だと思います。
曲は、夏の気怠さを表した、ゆっくりとしたテンポで始まりますが、チェロのソロとチェンバロを伴奏にヴァイオリンのソロが始まると、これは『ヴァイオリン コンチェルト』なんだという事を改めて思わされます。
ソロヴァイオリンは速いテンポで、キジバト、カッコウ、ごしきひわの鳴き交わす様子を弾いていきます。
やがてオーケストラが『穏やかな西風』を奏し、突然吹き始める『北風』に続くのですが、この北風のあたりになると、もうオレの技術では追いつけません。
左手の音階だけでも付いていけないし、2本の弦を速いテンポで交互に弾くところでは、リズムがグチャグチャになる上、まともな音にもなりません。
この辺は弾ける人にまかせて、オレは出せる音だけ出している、という感じですね。
ゆっくりとした第2楽章は、唯一完全に弾けるところですが、第3楽章の『嵐』になると、もうお手上げです。
速いテンポで細かい刻みが続くので、細かい動きのあるところは諦めて、リズムを崩さないように注意しながら同じ音が続くところだけを弾いたり、他の人が2本の弦を交互に弾いているところをオレは左手を目一杯広げて1本の弦だけで弾いたり、まぁとにかく、自分の技術で弾けるところは、できる限り弾いたつもりなんですが、曲がりなりにも音を出せたのは、4割から半分弱というところでしょうか。
もっとも、オレの両隣のエキストラの人達も、結構てこずっていたようですから、本当に難しい曲なんだと思いますけどね。
続いては、ハイドンの交響曲第42番 ニ長調です。
ハイドンの交響曲でも、初期から中期にかけて作曲された曲は、特別な機会でもないと、なかなか聴く事はありませんが、特にこの曲のように名前(標題)の付いていない曲は、この演奏会がなければ聴く事もなかったんだろうな、って思います。
この次の43番からは名前のついた曲が続くのですが、なぜこの曲に名前がつかなかったのか不思議なくらい、本当にいい曲だと思いますね。
オーボエとファゴット、それにホルンの人達が2人ずつ加わり、曲が始まります。
第1楽章は、楽譜には Moderato e maestoso (中庸のテンポで堂々と)とありますが、それにしてはかなり速いテンポで始まります。
曲自体はいい曲だと思うし、好きですが・・・・ただ、弾くのが難しい。
頭の中に出来上がった曲を一気に書き写した、と言われているモーツァルトの作曲法とは違い、考えながら作曲したハイドンの曲は、モーツァルトには無い技巧が凝らされているところが結構あり、楽器同士の掛け合いみたいなところは、お互いの音を聴いていないと合わせにくいですね。
技術的に難しいところになると、楽譜を追うだけで一杯一杯になってしまって、まわりの音を聴く余裕もなかったし、オレが一番苦手としている、移弦しながらの分散和音なんかは、かなりごまかしてましたけどね。
第2楽章は、Andantino e cantabile (アンダンテより少し速く、歌うように)、ヴァイオリンには con sordino (弱音器をつけて)と指示があり、独特の雰囲気が出ます。
この曲では、2本のファゴットが、常にコントラバスと同じ音を出すように書かれていますが、この楽章だけは出番がありません。
緩徐楽章なのでテンポはゆっくりめ、とはいっても、例によってかなり速いテンポの上、32分音符が続くところが結構多かったり、シンコペーションを含んだ掛け合いがあったりして、落着いて弾いているわけにはいきません。
エキストラの管楽器の人と話していたら、その人も、もっとゆっくりしたテンポで歌わせる方が好きだ、と言っていましたが、管楽器の人は息継ぎの問題から速めのテンポを好む、と聞いていたので意外に思いながらも、やはりゆっくりめのテンポを好む人は結構多いんだろうな、って思いましたね。
第3楽章は、3拍子の舞曲メヌエット。
メヌエットはゆっくりとした3拍子の舞曲、と言われていたのですが、その後の研究で、かなり速いテンポの舞曲だと言われるようになりました。
このメヌエットでは速いテンポの上、3連音が多用され、アクセントの位置がかなり変則的なところもあるので、演奏するには結構てこずりましたね。
フィナーレは、Scherzando e presto (戯れるように、急速に)
この発想標語が示すとおり、速いテンポで飛び跳ねるようなメロディーが、弦楽合奏で繰り返され、続いて2本ずつのオーボエ、ファゴット、ホルンによる管楽器の合奏が繰り返されます。
その後は、管弦楽が繰り広げられていくのですが、この楽章に関しては、オレの技術では全くのお手上げ状態・・・・まともに弾けたところは、途中に出てくる叙情的な2つの旋律と、最後の6小節くらいかな。(終り良ければ全て良し、と考えればいいのですが)
ホント、手強い曲でした。
この曲では、上にも書いたファーストホルンの小笠原さんが、ヴァルブのついていないナチュラルホルンを演奏していたのですが、セカンドホルンの古橋さんもそれに合わせて、ヴァルブ付きのホルンのヴァルブを使わずに、ナチュラルホルンとして演奏したのだそうです。
高山にも、スゴい人達がいるものですね。
ここで休憩をはさんで、後半はメインの『未完成』です。
休憩とは言っても、一度楽屋へ戻ってトイレに行き、楽器の手入れをしたら、もうステージ袖で待機する時間になっていました。
弦楽器奏者は人数が多いので、仮に1人が間違えたとしても、それほど目立たないのですが、それに比べると、管楽器や打楽器の人達はそれぞれがソロ奏者ですから、間違えれば一発で分かってしまうわけで、そういう意味でこういう場合、管楽器や打楽器の人達は緊張の度合いが高いのだろうな、って思います。
でも、一番緊張していたのは、指揮者の鴨宮さんだったのかもしれませんが。
管楽器の人達に続いてステージに出て自分の席に着き、コンサートミストレスの出すAの音に合わせてチューニングし、指揮者の登場を待つ・・・・まぁ、ある種の儀式のような感じですが、嫌が上にも緊張感が高まります。
第1楽章は Allegro moderato.(中庸のテンポで、快活に)
指揮者の振り下ろす棒に合わせて、チェロとコントラバスが、地の底から湧き上がるように、冒頭のメロディーを奏し始め、続いてヴァイオリンのさざ波に乗って、オーボエとクラリネットがユニゾンで、第1主題を吹き始める。
オレが音楽にのめり込むきっかけになった曲が、この『未完成』だった事は間違いないのですが、今でも大好きな曲であり、特別な感情を持っている曲なんです。
考えてみると、初めてこの曲を聴いてからちょうど40年目に自分がこの曲を弾いている事が、意外なような、不思議なような・・・・
しみじみとそんな事を思いながら弾いていると、事件発生・・・・ティンパニが1小節早く叩きだしたのですよ。
もう一度繰り返す事で帳尻は合いましたが、後でティンパニの小林先生が言われたのは、「いつもは記憶と感覚で叩いているのだけれど、本番では真面目に小節数を数えていたら間違えた。」
いや、それ、よく分かります・・・・オレも練習の時によくやりましたから。
そして、ホルンとファゴットの和音に導かれて、チェロと、続いてヴァイオリンで奏される第2主題は本当に素晴らしい・・・・大好きなメロディーなのだけれど、それだけに、思ったように演奏するのは本当に難しい。
この『未完成』という曲は、メロディーの美しさはもちろんの事ですが、その構成や展開に関しても、シューベルトの最高傑作なんじゃないかと、オレは思います。
ヴァイオリンを習い始めて2年にもならないオレでも、まがりなりにも8〜9割は弾く事ができましたから、技術的に『難曲』と言うわけではないのでしょうけど、演奏効果とでも言うのか、聞き映えのする事ではピカイチの上、構成の自在性とか表現の幅の広さ、奥行きの深さが尋常ではないんですよね。
実際、この後に書かれた『ザ・グレイト』と呼ばれている交響曲第8番は、曲の構成の立派さも、演奏に要する技術の難易度も未完成より上なのに、未完成と比べると、ただ単にメロディーを繰り返しをしているだけのように感じてしまう・・・・聴いていて、ゾッとするような瞬間がないんですね。
それくらい、この曲は、全曲を通じて、ある種『神がかり』的な、と言うか、『霊感』に満ちた、奇跡的な名曲なんだと思います。
それから、シューベルトは実際にオーケストラが演奏する現場に居て、新しい響きを得るための『実験』をしていたそうなのですが、この曲に3本のトロンボーンが使われているのも、新しい試みの成果なのかもしれません。
交響曲にトロンボーンを初めて使ったのはベートーヴェンですが、使い方はかなり限定的で、最後の第9番でも、2本のトロンボーンが、第2、第4楽章にだけ使われているくらいですが、それよりも前に作曲されたこの曲で、アルト、テノール、バスの3本のトロンボーンが全曲を通して使われているのは、シューベルトがかなり革新的な作曲をした、という事に他ならないでしょう。
この曲も、オレが初めて聴いた頃の演奏と、今の演奏では全く違ったものになっていて、以前に使われていた『旧版』の楽譜ではデクレッシェンドとして演奏されていたところが、『新版』ではアクセントとして演奏されるので、表現自体が全く替わってしまったわけです。
新版によって新しい表現が生まれた事は評価されるべきだとは思いますが、オレ自身は、旧版の表現を強調して儚くロマンティックに旋律を歌わせたブルーノ ワルターの演奏を最も好んでいるせいもあってか、旧版を使った演奏の方が遥かに好きですね。
まぁ、時代の流れだ、と言われればそれまでですが。
この後、本当に魅力的な展開部から再現部へ、そして終結部へと演奏は問題無く進んで、第1楽章が終わり、第2楽章 Andante con moto.(穏やかに、動きをもって)へ入ります。
この楽章も、オレの感覚からすれば、かなり速めのテンポで進みますが、でも、このオーケストラの技術からすれば、これより遅いと、逆に合わせるのが難しくなるかもしれません。
前期ロマン派の曲である事から、今回の演奏では、ロマンティックな表現より、古典派的な整ったスタイルを目指していたので、強弱などの表現は控えめだったし、弦楽器のヴィブラートもかけないで演奏しましたが、オレとしては、もう少しロマンティックにやってもいいのでは、と思いましたね。
弦のシンコペイションの伴奏の上で、オーボエとクラリネットが歌う第2主題では、伴奏につけられたクレッシェンドとデクレッシェンドを、思いっきり強調したい衝動にかられました。
と、こう書いても分かりにくい事だと思うので、この第2楽章を、前にも書いた『旧版』の代表とも言えるブルーノ ワルターの演奏と、『新版』の代表であるジョス ファン インマゼールの演奏で聴き比べてもらうと、テンポといい、表情の付け方といい、全く別物になっている事が分かると思います。
近い将来、この曲をもう一度プログラムに載せて、旧版を使って今回とは全く違った表現の演奏をするのも面白いだろうと、オレは思いますね。
この曲は転調が多いため、同じメロディーが出てきても、違う調になっている事が多いので、楽譜から目を離して弾いていると、違う音を出してしまう事があります。
そういう意味で、トラブりやすい曲だとも言えるのでしょうね。
第2楽章の最後の方に、ファーストヴァイオリンと管楽器が転調しながら呼び交すところがあって、サードトロンボーンにpppの最弱音が要求されている難所でもあるのですが、2回目に管楽器が応えるところで出るフルートが、1回目に出てしまったのですよ。
すぐに指揮者からの指示が出て、その音は止まりましたが、やはりドキッとしましたね。
最後の一音はフェルマータがついた長い音ですが、クレッシェンドして弓を返し、デクレッシェンドで消えるように終わります。
弓が止まり、拍手が聞こえてきた時、弾き切った、という気持ちで、文字通りの『感無量』でしたね。
前の2曲では、かなりごまかして弾いていたのですが、この曲に関しては、その大部分を弾く事ができたので、余計にそういう『実感』が湧いたのだと思います。
後は『アンコール』を残すのみですが、アンコールの曲は、同じくシューベルトの『軍隊行進曲』・・・・賑やかでノリのいい曲ですから、アンコールにはピッタリですね。
セカンドヴァイオリンは、伴奏の『刻み』と『後打ち』ばかりで、一度も旋律を弾く事はないのですが、それでも楽しいですからね。
行進曲らしく、小太鼓、大太鼓、シンバル、トライアングルといった打楽器が活躍しますが、それらの打楽器を小林先生が1人で演奏します。
演奏が始まると、これで最後、という安心感(?)もあってか、みんな結構ノリがいいですね。
で、演奏が進み、トリオをはさんで後半に入ってしばらくした時のこと。
自分の出している音の音程が、少しずれているような気がしだしたのですよ。
いつもそういう時は、隣の音を聴きながら合わせるのですが、この時はなぜか、余計な事を考えてしまったんです。
隣で弾いているドンマイヤーさんの奥さんが、今日は音程が下がり気味で、としきりに言ってみえたのは、オレが音程のずれた音を出している所為なんじゃないかな・・・・って一瞬思ったら、急に不安になってきたわけですよ。
こういう時って、考え始めると、悪い方へ向かってしまう事が多いので、何とか意識を他の方へ向けないと、と思うのですが、いつもと全然違う意識の状態で、まわりの音がハッキリと分からなくなって・・・・
どうしよう、と思った時、すぐ後ろで吹いているホルンの2番がセカンドヴァイオリンと同じ音を吹いている事に気がついて、それに合わせる事で事なきを得たわけですが、『落ちる』という事がこういうふうにして起こるのだと、実感しましたね。
最後のフェルマータのついた長い音が鳴り終わり、すべての演奏が終わりました。
コンサートミストレスの合図で、客席にお辞儀をし、舞台を後にしましたが、気になったのは、オレが声をかけて来てもらったお客さんの事。
お礼の挨拶をしたいと思い、楽屋で楽器をケースに入れて、すぐにホワイエに出てみたのですが、もう殆どのお客さんが帰られた後でした。
反省会の時に、お見送りをするべきだった、という意見が出ましたが、せっかく来て頂いたお客さんに挨拶できなかった事が、今回の演奏会で唯一心残りに思った事です。
楽屋を片付けた後、身の回りの物を持ってホールを出ようとすると、花がありますよ、と言われたので、見てみると、オレ宛にこんな花が・・・・

花を贈られるって、うれしいものですが、こういう時にもらう花には、格別のものがありますね。
この後、ホテル フォーシーズンでの打ち上げパーティーと、トニオへ場所を移しての2次会で、心行くまで話をしましたが、やっぱりみんな音楽が好きなんだなぁ、って事を改めて感じましたね。
さて、オレなりに今回の演奏について思った事を書いてみようと思うのですが、なんと言っても気になったのはテンポです。
この『テンポ』というのは、演奏者にとっては常について廻る問題で、『正解』というものが見つからないものなのかもしれませんが、今回演奏したヴィヴァルディの『夏』とハイドンに関しては、テンポが速すぎた、とオレは思います。
指揮者の鴨宮さんとは、テンポについて何回か話した事があるのですが、その時に聞いた話によると、ヴィヴァルディのテンポに関しては、ソリストの井上先生はもっと速いテンポを望んでみえたそうだし、また、ハイドンに関しても、わりと簡素に書かれている曲の構成上、ゆっくりと演奏するのは逆に難しいとの事ですから、ある意味で『妥協点』を探った上でのテンポだったのかな、とも思います。
でも、その速いテンポで弾く事で精一杯になってしまって、まわりの音を聴きながら弾くだけの余裕が無くなっていたように、オレには感じられたのです。
そう感じたのは、オレのような技術の無い者だからこそ思う事であって、速いテンポでも余裕を持って弾ける人達には、あまり実感の無い事なんだろうな、とも思っていたのですが、他のメンバーやエキストラの人達と話していても、やはり速すぎるという意見の人が結構いたので、オレだけの思いではないようです。
『古楽研究家』達による楽譜の見直しと、『古楽器』による演奏が主流になった70年代後半以降、演奏のテンポが速くなってきたため、現在手に入るCDでは、たいていの演奏がこんなテンポですから、これが普通だと言われればそれまでなんだけれど、現代と比べ、小さく軽い音しか出ない楽器を使い、オーケストラの編成も小さく、演奏会場もはるかに小さかった作曲当時には必然性があった速いテンポが、大きく豊かな音の出るモダーン楽器を使い、編成も大きく、はるかに大きい演奏会場で演奏する現代のオーケストラに合っているかは別問題だと思います。
プロの演奏のテンポを真似する、という事よりも、もう少し余裕をもったテンポで、お互いの音を聴きながら確実に演奏する方が、当然アンサンブル能力は上がるわけで、このオーケストラはもっと鳴るようになると思うし、それこそが『アマチュアオーケストラ』である、このオーケストラの目指すべき方向だと、オレは思うのです。
この事は、反省会の時に、オレの意見として発言したのですが、どれだけの人に理解してもらえ、賛同してもらえるかは全くの未知数で、かなり勇気のいる事ではありました。
でも、オブザーヴァーとして参加してもらったホルンの小笠原さんから、各自がそれぞれのパートをきちんと弾く事の重要性という意味で、オレの意見に賛意を表してもらえたので、発言して良かったと思うし、今後このオーケストラが発展していく上での一つの考え方として認知してもらえたらいいのではないかと思うのです。
これから、クリスマス ファミリーコンサートに向けての練習が続きますが、少しでもレヴェルアップできるように練習し、聴きに来てくれたお客さんに喜んでもらえるようにしたいものですね。
ところで、10月23日に南小学校の『ふれあい文化祭』で、『故郷』と『サウンド オヴ ミュージック ハイライト』を演奏してきましたが、今回初めてヴィオラで参加しました。
定期演奏会まではセカンドヴァイオリンを弾いていたのに、また何故、と思われるかもしれませんが、それには理由があって・・・・
その事については、また次の機会に書く事にしましょう。
では、また。
Ciao. Arrivederci!!
前回の更新からだいぶ時間が経ってしまいましたが、気がついてみれば、もう10月も終わりかぁ・・・・
店がヒマなわりには結構バタバタしていて、ブログに向かう時間がなかなかとれなかったのですが、前回の更新から1月半も経ってしまったんだなぁ、と改めて月日の過ぎる速さを実感していますけどね。
7月8月と忙しかったのに、9月に入った途端にヒマになり、10月は少し持ち直したという感じですが、同業者に聞くと同じような答えが返ってきますから、ヒマなのはウチだけではないのでしょうけど、世の中の流れ自体を寂しく感じてしまうのは残念です。
これからの行楽シーズンに合わせて、高山が盛り上がってほしいものですね。
さて、前回に続き、高山室内合奏団の第8回定期演奏会の事を書きますが、その前に、現在決まっている高山室内合奏団の今後の演奏予定をお知らせします。
12月17日(土)14:30 神岡 船津座
12月18日(日)14:00 文化会館
恒例の『クリスマス ファミリーコンサート』
アルビノーニのアダージョ
宮崎アニメの音楽から3曲
アンダーソンの『クリスマス フェスティヴァル』
バッハの『管弦楽組曲第2番 ロ短調』から4曲
アンサンブル ルシェッロのチェロ8重奏で『イエスタデイ』
その他
休憩時間に、お茶とお菓子が出ます。そして今年も (株)なべしま さんによる、ポップコーンの作製実演があり、できたてのポップコーンを食べてもらえますよ。
2012年8月26日(日) 世界生活文化センター 飛騨芸術堂
第9回定期演奏会
ベートーヴェンのピアノ協奏曲第4番ト長調 をメインとするプログラム
2013年夏 世界生活文化センター 飛騨芸術堂
第10回定期演奏会
ベートーヴェンの交響曲第5番ハ短調 をメインとするプログラム
現時点での予定は以上です。
では、本文に入りましょう。
前回の『その1』では、前日のゲネプロについて書きましたが、今回は演奏会当日の事を書きます。
さぁ、本番当日です。
10:30集合、という事になっていましたが、オレは30分前にホールに行きました。
というのも、毎年、演奏会の前日に、ドンマイヤーさんに楽器の調整をしてもらうのですが、今年はドンマイヤーさんが来るのが遅くなったため、前日にできなかったので、朝イチで行って、やってもらおうと思ったわけです。
で、ドンマイヤーさんの楽屋へ行くと、すでに2人の人が待っていて・・・・まぁ、みんな考える事は同じなんですね。
冷房の効いた部屋だというのに、汗だくになりながら、ドンマイヤーさんは楽器の調整をしていました。
調整してもらう前に、一度弾いて、音と感覚を身体で憶えておきます。
まず、弓の毛を緩めて、木の部分を磨いて汚れを落とすのですが、それだけの事なのに、弓を受け取って持ってみると、軽く感じるんですよ。
これは本当に不思議ですね。
次にヴァイオリン本体を磨いて汚れを落とします。
本当は、裏板だけのはずだったのですが、オレのヴァイオリンの表板が松脂で汚れていたので、表板も磨いてもらえました。
磨きながらドンマイヤーさんは、ストラディヴァーリやグァルネーリのような名器は、表面のニスに汚れがつかないので、それだからこそ300年経ってもいい状態で残っているのだ、と話してくれましたが、まぁ、すぐに汚れがついてしまうオレの楽器は、やっぱり安物という事なんでしょうね。
その後、魂柱を調整をしてもらいましたが、ほんの少し動かすだけで、音が違ってくるのが分かるんですよね。
まわりの人達から、どんな音がいいのか希望を言う方がいいよ、と言われたので、上手に聞こえるようにして下さい、って言ったら笑われましたけど。
いよいよ本番前の最後の練習、文字通りの『ゲネプロ』に入ります。
とにかく、ミスがあっても止まらずに最後まで行こう、という事で、気負う事なく、わりと気楽に演奏していたのですが、やはり集中力が上がってきているのか、ミスはあったものの、緊張感を持続しながら、一気に演奏してしまいましたからね。
未完成の最終練習に入る前の休憩中です。

最終練習の前という事で、みんな、自分のパートの弾き込みに一生懸命になってます。

管楽器の人達も、同じですね。

そのゲネプロが終って、楽屋へ引き上げようとしていたら、トランペットとトロンボーンが、未完成の第2楽章のフォルテッシモのところを吹き始めたのです。

ゲネプロの時に金管楽器のアンサンブルが少しずれたようで、その部分を金管楽器だけで合わせていたのですが、この時は、ほぼ完璧に合ってました。
いや、立派です。
楽屋へ戻ろうと、舞台裏の廊下を通っていたら、ファーストホルンの小笠原さんが、ホルンの手入れをしていました。
それが例のナチュラルホルンですか、って訊いたら、自分で溶接して作ったんです、と言って見せてくれたのですが、いかにも手作りという無骨なホルンでした。
そこでしばらく話をしたのですが、ふと思いついて、来年は『エロイカ』(ベートーヴェンの交響曲第3番『英雄』の事 第3楽章のトリオで3本のホルンが大活躍する)なんかどうでしょう、って言ったら、いいですねぇ あれならやれますよ、という答え。
大曲故に難しい点が多いとは思うけど、本当にできたらすごい事だと思うのですが。
下の階の楽屋へ戻り、昼飯を食べ、本番用の黒のスーツに着替え、開演までしばらく休憩します。
開演15分前にチューニングを始め、開演10分前にステージ袖に集合。
トップの人達は結構緊張しているようだし、指揮者の鴨宮さんも、かなり緊張しているみたい。
一番後ろで弾くオレは、全然緊張する事もなく構えてましたけど。
覗き窓から客席を見ると、結構席が埋まっていて、前の方には中学の同級生のN君の顔が見えます。
開演を知らせるアナウンスが流れ、客席が落着いたところで、舞台の上手からは、ヴィオラ、チェロ、コントラバスが、下手からは、ヴァイオリンが出ます。
全員が席に着いたところで、コンサートミストレスの出すAの音に合わせて、低音側から順にAの音を合わせ、全楽器がAを合わせたところで、さらに他の弦を合わせていきます。
このチューニングの完全5度の響きが聞こえると、コンサートの始まりを実感する人も多いようですが、弾く方としては、いよいよ緊張感が高まります。
指揮者が登場し、拍手が収まったところで指揮棒が上がり、全員が楽器を構えます。
最初の曲、ヴィヴァルディの『聖なる墓に』は、セカンドヴァイオリンの長いFis(ファ♯)の音で始まるので、その出だしには緊張します。
でも、音が出てしまえば、後はまわりの音を聴きながら合わせていけます。
この曲は、演奏時間にして5分程度の小品で、前半のゆっくりとした部分と、後半の速いフーガと、2つの部分からできていますが、当然、前半の方が弾き易い。
後半のフーガは、少しごまかしたところもあったけれど、フーガの掛け合いがピッタリ合うと気持ちがいいですね。
続いて、ヴィヴァルディのヴァイオリン協奏曲『夏』です。
去年のクリスマスコンサートで『冬』をやりましたが、『夏』の方が難しいですね。
この曲の編成は、前の曲に、ソロヴァイオリンとチェンバロが加わります。
ソロは井上先生です。
普通、ソリストは立って演奏するのですが、今回の井上先生が座って演奏した事を不思議に思った人がおられるかもしれません。
ソロと指揮を兼ねて演奏するのなら立って演奏するけど、指揮者がいるのだからオーケストラの一員として座って演奏する、というのが井上先生の意見。
なるほど、確かな見識だと思います。
曲は、夏の気怠さを表した、ゆっくりとしたテンポで始まりますが、チェロのソロとチェンバロを伴奏にヴァイオリンのソロが始まると、これは『ヴァイオリン コンチェルト』なんだという事を改めて思わされます。
ソロヴァイオリンは速いテンポで、キジバト、カッコウ、ごしきひわの鳴き交わす様子を弾いていきます。
やがてオーケストラが『穏やかな西風』を奏し、突然吹き始める『北風』に続くのですが、この北風のあたりになると、もうオレの技術では追いつけません。
左手の音階だけでも付いていけないし、2本の弦を速いテンポで交互に弾くところでは、リズムがグチャグチャになる上、まともな音にもなりません。
この辺は弾ける人にまかせて、オレは出せる音だけ出している、という感じですね。
ゆっくりとした第2楽章は、唯一完全に弾けるところですが、第3楽章の『嵐』になると、もうお手上げです。
速いテンポで細かい刻みが続くので、細かい動きのあるところは諦めて、リズムを崩さないように注意しながら同じ音が続くところだけを弾いたり、他の人が2本の弦を交互に弾いているところをオレは左手を目一杯広げて1本の弦だけで弾いたり、まぁとにかく、自分の技術で弾けるところは、できる限り弾いたつもりなんですが、曲がりなりにも音を出せたのは、4割から半分弱というところでしょうか。
もっとも、オレの両隣のエキストラの人達も、結構てこずっていたようですから、本当に難しい曲なんだと思いますけどね。
続いては、ハイドンの交響曲第42番 ニ長調です。
ハイドンの交響曲でも、初期から中期にかけて作曲された曲は、特別な機会でもないと、なかなか聴く事はありませんが、特にこの曲のように名前(標題)の付いていない曲は、この演奏会がなければ聴く事もなかったんだろうな、って思います。
この次の43番からは名前のついた曲が続くのですが、なぜこの曲に名前がつかなかったのか不思議なくらい、本当にいい曲だと思いますね。
オーボエとファゴット、それにホルンの人達が2人ずつ加わり、曲が始まります。
第1楽章は、楽譜には Moderato e maestoso (中庸のテンポで堂々と)とありますが、それにしてはかなり速いテンポで始まります。
曲自体はいい曲だと思うし、好きですが・・・・ただ、弾くのが難しい。
頭の中に出来上がった曲を一気に書き写した、と言われているモーツァルトの作曲法とは違い、考えながら作曲したハイドンの曲は、モーツァルトには無い技巧が凝らされているところが結構あり、楽器同士の掛け合いみたいなところは、お互いの音を聴いていないと合わせにくいですね。
技術的に難しいところになると、楽譜を追うだけで一杯一杯になってしまって、まわりの音を聴く余裕もなかったし、オレが一番苦手としている、移弦しながらの分散和音なんかは、かなりごまかしてましたけどね。
第2楽章は、Andantino e cantabile (アンダンテより少し速く、歌うように)、ヴァイオリンには con sordino (弱音器をつけて)と指示があり、独特の雰囲気が出ます。
この曲では、2本のファゴットが、常にコントラバスと同じ音を出すように書かれていますが、この楽章だけは出番がありません。
緩徐楽章なのでテンポはゆっくりめ、とはいっても、例によってかなり速いテンポの上、32分音符が続くところが結構多かったり、シンコペーションを含んだ掛け合いがあったりして、落着いて弾いているわけにはいきません。
エキストラの管楽器の人と話していたら、その人も、もっとゆっくりしたテンポで歌わせる方が好きだ、と言っていましたが、管楽器の人は息継ぎの問題から速めのテンポを好む、と聞いていたので意外に思いながらも、やはりゆっくりめのテンポを好む人は結構多いんだろうな、って思いましたね。
第3楽章は、3拍子の舞曲メヌエット。
メヌエットはゆっくりとした3拍子の舞曲、と言われていたのですが、その後の研究で、かなり速いテンポの舞曲だと言われるようになりました。
このメヌエットでは速いテンポの上、3連音が多用され、アクセントの位置がかなり変則的なところもあるので、演奏するには結構てこずりましたね。
フィナーレは、Scherzando e presto (戯れるように、急速に)
この発想標語が示すとおり、速いテンポで飛び跳ねるようなメロディーが、弦楽合奏で繰り返され、続いて2本ずつのオーボエ、ファゴット、ホルンによる管楽器の合奏が繰り返されます。
その後は、管弦楽が繰り広げられていくのですが、この楽章に関しては、オレの技術では全くのお手上げ状態・・・・まともに弾けたところは、途中に出てくる叙情的な2つの旋律と、最後の6小節くらいかな。(終り良ければ全て良し、と考えればいいのですが)
ホント、手強い曲でした。
この曲では、上にも書いたファーストホルンの小笠原さんが、ヴァルブのついていないナチュラルホルンを演奏していたのですが、セカンドホルンの古橋さんもそれに合わせて、ヴァルブ付きのホルンのヴァルブを使わずに、ナチュラルホルンとして演奏したのだそうです。
高山にも、スゴい人達がいるものですね。
ここで休憩をはさんで、後半はメインの『未完成』です。
休憩とは言っても、一度楽屋へ戻ってトイレに行き、楽器の手入れをしたら、もうステージ袖で待機する時間になっていました。
弦楽器奏者は人数が多いので、仮に1人が間違えたとしても、それほど目立たないのですが、それに比べると、管楽器や打楽器の人達はそれぞれがソロ奏者ですから、間違えれば一発で分かってしまうわけで、そういう意味でこういう場合、管楽器や打楽器の人達は緊張の度合いが高いのだろうな、って思います。
でも、一番緊張していたのは、指揮者の鴨宮さんだったのかもしれませんが。
管楽器の人達に続いてステージに出て自分の席に着き、コンサートミストレスの出すAの音に合わせてチューニングし、指揮者の登場を待つ・・・・まぁ、ある種の儀式のような感じですが、嫌が上にも緊張感が高まります。
第1楽章は Allegro moderato.(中庸のテンポで、快活に)
指揮者の振り下ろす棒に合わせて、チェロとコントラバスが、地の底から湧き上がるように、冒頭のメロディーを奏し始め、続いてヴァイオリンのさざ波に乗って、オーボエとクラリネットがユニゾンで、第1主題を吹き始める。
オレが音楽にのめり込むきっかけになった曲が、この『未完成』だった事は間違いないのですが、今でも大好きな曲であり、特別な感情を持っている曲なんです。
考えてみると、初めてこの曲を聴いてからちょうど40年目に自分がこの曲を弾いている事が、意外なような、不思議なような・・・・
しみじみとそんな事を思いながら弾いていると、事件発生・・・・ティンパニが1小節早く叩きだしたのですよ。
もう一度繰り返す事で帳尻は合いましたが、後でティンパニの小林先生が言われたのは、「いつもは記憶と感覚で叩いているのだけれど、本番では真面目に小節数を数えていたら間違えた。」
いや、それ、よく分かります・・・・オレも練習の時によくやりましたから。
そして、ホルンとファゴットの和音に導かれて、チェロと、続いてヴァイオリンで奏される第2主題は本当に素晴らしい・・・・大好きなメロディーなのだけれど、それだけに、思ったように演奏するのは本当に難しい。
この『未完成』という曲は、メロディーの美しさはもちろんの事ですが、その構成や展開に関しても、シューベルトの最高傑作なんじゃないかと、オレは思います。
ヴァイオリンを習い始めて2年にもならないオレでも、まがりなりにも8〜9割は弾く事ができましたから、技術的に『難曲』と言うわけではないのでしょうけど、演奏効果とでも言うのか、聞き映えのする事ではピカイチの上、構成の自在性とか表現の幅の広さ、奥行きの深さが尋常ではないんですよね。
実際、この後に書かれた『ザ・グレイト』と呼ばれている交響曲第8番は、曲の構成の立派さも、演奏に要する技術の難易度も未完成より上なのに、未完成と比べると、ただ単にメロディーを繰り返しをしているだけのように感じてしまう・・・・聴いていて、ゾッとするような瞬間がないんですね。
それくらい、この曲は、全曲を通じて、ある種『神がかり』的な、と言うか、『霊感』に満ちた、奇跡的な名曲なんだと思います。
それから、シューベルトは実際にオーケストラが演奏する現場に居て、新しい響きを得るための『実験』をしていたそうなのですが、この曲に3本のトロンボーンが使われているのも、新しい試みの成果なのかもしれません。
交響曲にトロンボーンを初めて使ったのはベートーヴェンですが、使い方はかなり限定的で、最後の第9番でも、2本のトロンボーンが、第2、第4楽章にだけ使われているくらいですが、それよりも前に作曲されたこの曲で、アルト、テノール、バスの3本のトロンボーンが全曲を通して使われているのは、シューベルトがかなり革新的な作曲をした、という事に他ならないでしょう。
この曲も、オレが初めて聴いた頃の演奏と、今の演奏では全く違ったものになっていて、以前に使われていた『旧版』の楽譜ではデクレッシェンドとして演奏されていたところが、『新版』ではアクセントとして演奏されるので、表現自体が全く替わってしまったわけです。
新版によって新しい表現が生まれた事は評価されるべきだとは思いますが、オレ自身は、旧版の表現を強調して儚くロマンティックに旋律を歌わせたブルーノ ワルターの演奏を最も好んでいるせいもあってか、旧版を使った演奏の方が遥かに好きですね。
まぁ、時代の流れだ、と言われればそれまでですが。
この後、本当に魅力的な展開部から再現部へ、そして終結部へと演奏は問題無く進んで、第1楽章が終わり、第2楽章 Andante con moto.(穏やかに、動きをもって)へ入ります。
この楽章も、オレの感覚からすれば、かなり速めのテンポで進みますが、でも、このオーケストラの技術からすれば、これより遅いと、逆に合わせるのが難しくなるかもしれません。
前期ロマン派の曲である事から、今回の演奏では、ロマンティックな表現より、古典派的な整ったスタイルを目指していたので、強弱などの表現は控えめだったし、弦楽器のヴィブラートもかけないで演奏しましたが、オレとしては、もう少しロマンティックにやってもいいのでは、と思いましたね。
弦のシンコペイションの伴奏の上で、オーボエとクラリネットが歌う第2主題では、伴奏につけられたクレッシェンドとデクレッシェンドを、思いっきり強調したい衝動にかられました。
と、こう書いても分かりにくい事だと思うので、この第2楽章を、前にも書いた『旧版』の代表とも言えるブルーノ ワルターの演奏と、『新版』の代表であるジョス ファン インマゼールの演奏で聴き比べてもらうと、テンポといい、表情の付け方といい、全く別物になっている事が分かると思います。
近い将来、この曲をもう一度プログラムに載せて、旧版を使って今回とは全く違った表現の演奏をするのも面白いだろうと、オレは思いますね。
この曲は転調が多いため、同じメロディーが出てきても、違う調になっている事が多いので、楽譜から目を離して弾いていると、違う音を出してしまう事があります。
そういう意味で、トラブりやすい曲だとも言えるのでしょうね。
第2楽章の最後の方に、ファーストヴァイオリンと管楽器が転調しながら呼び交すところがあって、サードトロンボーンにpppの最弱音が要求されている難所でもあるのですが、2回目に管楽器が応えるところで出るフルートが、1回目に出てしまったのですよ。
すぐに指揮者からの指示が出て、その音は止まりましたが、やはりドキッとしましたね。
最後の一音はフェルマータがついた長い音ですが、クレッシェンドして弓を返し、デクレッシェンドで消えるように終わります。
弓が止まり、拍手が聞こえてきた時、弾き切った、という気持ちで、文字通りの『感無量』でしたね。
前の2曲では、かなりごまかして弾いていたのですが、この曲に関しては、その大部分を弾く事ができたので、余計にそういう『実感』が湧いたのだと思います。
後は『アンコール』を残すのみですが、アンコールの曲は、同じくシューベルトの『軍隊行進曲』・・・・賑やかでノリのいい曲ですから、アンコールにはピッタリですね。
セカンドヴァイオリンは、伴奏の『刻み』と『後打ち』ばかりで、一度も旋律を弾く事はないのですが、それでも楽しいですからね。
行進曲らしく、小太鼓、大太鼓、シンバル、トライアングルといった打楽器が活躍しますが、それらの打楽器を小林先生が1人で演奏します。
演奏が始まると、これで最後、という安心感(?)もあってか、みんな結構ノリがいいですね。
で、演奏が進み、トリオをはさんで後半に入ってしばらくした時のこと。
自分の出している音の音程が、少しずれているような気がしだしたのですよ。
いつもそういう時は、隣の音を聴きながら合わせるのですが、この時はなぜか、余計な事を考えてしまったんです。
隣で弾いているドンマイヤーさんの奥さんが、今日は音程が下がり気味で、としきりに言ってみえたのは、オレが音程のずれた音を出している所為なんじゃないかな・・・・って一瞬思ったら、急に不安になってきたわけですよ。
こういう時って、考え始めると、悪い方へ向かってしまう事が多いので、何とか意識を他の方へ向けないと、と思うのですが、いつもと全然違う意識の状態で、まわりの音がハッキリと分からなくなって・・・・
どうしよう、と思った時、すぐ後ろで吹いているホルンの2番がセカンドヴァイオリンと同じ音を吹いている事に気がついて、それに合わせる事で事なきを得たわけですが、『落ちる』という事がこういうふうにして起こるのだと、実感しましたね。
最後のフェルマータのついた長い音が鳴り終わり、すべての演奏が終わりました。
コンサートミストレスの合図で、客席にお辞儀をし、舞台を後にしましたが、気になったのは、オレが声をかけて来てもらったお客さんの事。
お礼の挨拶をしたいと思い、楽屋で楽器をケースに入れて、すぐにホワイエに出てみたのですが、もう殆どのお客さんが帰られた後でした。
反省会の時に、お見送りをするべきだった、という意見が出ましたが、せっかく来て頂いたお客さんに挨拶できなかった事が、今回の演奏会で唯一心残りに思った事です。
楽屋を片付けた後、身の回りの物を持ってホールを出ようとすると、花がありますよ、と言われたので、見てみると、オレ宛にこんな花が・・・・

花を贈られるって、うれしいものですが、こういう時にもらう花には、格別のものがありますね。
この後、ホテル フォーシーズンでの打ち上げパーティーと、トニオへ場所を移しての2次会で、心行くまで話をしましたが、やっぱりみんな音楽が好きなんだなぁ、って事を改めて感じましたね。
さて、オレなりに今回の演奏について思った事を書いてみようと思うのですが、なんと言っても気になったのはテンポです。
この『テンポ』というのは、演奏者にとっては常について廻る問題で、『正解』というものが見つからないものなのかもしれませんが、今回演奏したヴィヴァルディの『夏』とハイドンに関しては、テンポが速すぎた、とオレは思います。
指揮者の鴨宮さんとは、テンポについて何回か話した事があるのですが、その時に聞いた話によると、ヴィヴァルディのテンポに関しては、ソリストの井上先生はもっと速いテンポを望んでみえたそうだし、また、ハイドンに関しても、わりと簡素に書かれている曲の構成上、ゆっくりと演奏するのは逆に難しいとの事ですから、ある意味で『妥協点』を探った上でのテンポだったのかな、とも思います。
でも、その速いテンポで弾く事で精一杯になってしまって、まわりの音を聴きながら弾くだけの余裕が無くなっていたように、オレには感じられたのです。
そう感じたのは、オレのような技術の無い者だからこそ思う事であって、速いテンポでも余裕を持って弾ける人達には、あまり実感の無い事なんだろうな、とも思っていたのですが、他のメンバーやエキストラの人達と話していても、やはり速すぎるという意見の人が結構いたので、オレだけの思いではないようです。
『古楽研究家』達による楽譜の見直しと、『古楽器』による演奏が主流になった70年代後半以降、演奏のテンポが速くなってきたため、現在手に入るCDでは、たいていの演奏がこんなテンポですから、これが普通だと言われればそれまでなんだけれど、現代と比べ、小さく軽い音しか出ない楽器を使い、オーケストラの編成も小さく、演奏会場もはるかに小さかった作曲当時には必然性があった速いテンポが、大きく豊かな音の出るモダーン楽器を使い、編成も大きく、はるかに大きい演奏会場で演奏する現代のオーケストラに合っているかは別問題だと思います。
プロの演奏のテンポを真似する、という事よりも、もう少し余裕をもったテンポで、お互いの音を聴きながら確実に演奏する方が、当然アンサンブル能力は上がるわけで、このオーケストラはもっと鳴るようになると思うし、それこそが『アマチュアオーケストラ』である、このオーケストラの目指すべき方向だと、オレは思うのです。
この事は、反省会の時に、オレの意見として発言したのですが、どれだけの人に理解してもらえ、賛同してもらえるかは全くの未知数で、かなり勇気のいる事ではありました。
でも、オブザーヴァーとして参加してもらったホルンの小笠原さんから、各自がそれぞれのパートをきちんと弾く事の重要性という意味で、オレの意見に賛意を表してもらえたので、発言して良かったと思うし、今後このオーケストラが発展していく上での一つの考え方として認知してもらえたらいいのではないかと思うのです。
これから、クリスマス ファミリーコンサートに向けての練習が続きますが、少しでもレヴェルアップできるように練習し、聴きに来てくれたお客さんに喜んでもらえるようにしたいものですね。
ところで、10月23日に南小学校の『ふれあい文化祭』で、『故郷』と『サウンド オヴ ミュージック ハイライト』を演奏してきましたが、今回初めてヴィオラで参加しました。
定期演奏会まではセカンドヴァイオリンを弾いていたのに、また何故、と思われるかもしれませんが、それには理由があって・・・・
その事については、また次の機会に書く事にしましょう。
では、また。
Ciao. Arrivederci!!