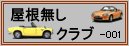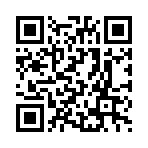2007年08月23日
高山室内合奏団定期演奏会
Ciao. spock です。
暑い日が続きますねぇ。
ここしばらく忙しい日が続いたので、このブログを更新するのも久しぶりです。
ウチの店は、7月末から今月の7日まで全く予約が入ってなかったのですが、そんな時にフラッとカウンターに立ち寄って下さるお客さんはありがたいですね。
で、8日からは予約がびっしりと入って、休みも無しで営業しましたが、おかげで何とか今月末の支払いは出来そうです。
いつも不思議に思うのですが、予約って重なるものなんですよね。
8日は2組の予約が入っていましたが、その前日と当日に6件の予約の電話があり、すべてお断りしたのです。
その前の1週間はズーッと空いていたのに・・・・本当にうまくいかないものですね。

忙しかった10日間を目一杯働いて過ごし、久しぶりの休日になった19日、高山室内合奏団第4回定期演奏会に行って来ました。
このオーケストラの演奏を聴くのは今回が初めてなので、期待感と共に、ある種の不安感を持っていた事も確かです。
でも、高山のような地方都市で、アマチュア・オーケストラが定期的に活動しているというのは凄い事ですよね。
もう30年も前の事ですが、ネスカフェ・ゴールドブレンドのCMで、指揮者の石丸寛さんが「急行列車の停まる町にはオーケストラがあるべきだ」というような事を言っておられたのを覚えていますが、高山でそれが実現できた事は、誇るべきだと思いますね。
東京にいた時、あるアマチュア・オーケストラの演奏会に何回か行きました。
日大オーケストラのOB.OGが中心になってできた『アンサンブルSAKURA』です。
年に2回の定期公演のうちの1回は音楽評論家の宇野功芳さんが指揮台に立ったのですが、その演奏を楽しみにしていたのです。
ワルターとクナッパーツブッシュとフルトヴェングラーを合わせたような、まぁ、やりたい放題の演奏でした。
テンポは曲想に合わせて自在に変わり、目一杯メロディーが歌われ、耳が痛いほどティンパニが打ち込まれ、聴いた事のないようなバランスで楽器が鳴り、本当に止まってしまったようなゲネラル・パウゼが出てくる・・・・とにかく何がおこるかわからない演奏でした。
最初から最後まで、次は何がおこるのだろうとワクワクし通しでしたね。
そもそもプロのようなテクニックはないのですから、指揮者のテンポの変化について行くだけでも大変なんでしょうが、そこに生まれるスリルはスゴかったですね。まぁ、その分アンサンブルは乱れまくりでしたけど・・・・・(その演奏会のライヴ録音のCDを何枚か持っていますが、今聴いても本当に面白い!!演奏会の興奮を思い出します)
そういう演奏を嫌う人(そういう演奏だと分かっているのに聴きに行き、インターネット上にボロクソに書くヤツって何を考えているのでしょうかね)が多い事も事実ですが、オレは大好きです。
きちんと纏まった演奏なら他にいくらでもあるのですから、そういうのはプロに任せて、自分達の思い入れを目一杯表現する。そういう事ができるのがアマチュアの強みなんじゃないかと思うのです。
高山室内合奏団もいつかそんな演奏をしてほしい、と思うのはオレだけでしょうかね。
さて、19日の話に戻しましょう。
せっかくの演奏会ですから、XJ-Sのトップを開けて、ゆったりとした気持ちで世界生活文化センターへ向かいました。
開場時間より早めに着きましたが、すでにホールの扉は開いていたので、早速中へ。左側の通路を前に進み、前から5列目の通路のすぐ右の席に着きました。
あまり前過ぎると聴こえ方のバランスが悪くなるけれど、でも直接的な音も聴きたい。となると、この辺かなと思ったのですが、みんな考える事はいっしょなのでしょうか、結局、オレの前の4列は誰も座る事無く空いたまま・・・・・
パンフレットを一通り読んだ後は、時間潰し用に持っていた『大地の歌』のスコアを読みながら待っていたのですが、やがて開演のブザーが鳴り、オーケストラのメンバーが舞台に並び、指揮者が登場し、演奏会の始まりです。
第1部は弦楽合奏の曲で構成されていますが、最初の曲は『アイネ・クライネ・ナハトムズィーク』の第1楽章です。
最初の和音が鳴った瞬間、感動しましたね。
今回初めてこのオーケストラを聴いたのですが、今までに上記のSAKURAの他にもにアマチュア・オーケストラの演奏は聴いていますから「だいたいこんなレヴェルなんじゃないかな」という想像をしていたのですよ。
でも実際は、オレが思っていたより、ずーっと響きがまとまっています。
たかだか人口9万の高山に、これだけのオーケストラがあるという事はスゴいと思いますね。
演奏が始まってすぐ、1stヴァイオリンの後ろの方から、1人だけすごく良く通る音が聴こえる事に気が付きました。(オレは音感が良くないので断言はできませんが、微妙にその人のピッチが高いのかもしれません)
明らかにコンサート・ミストレスとは違う、というか、コンサート・ミストレスより目立っている。
その音の方向からすると、1番後ろのプルトの裏で弾いている、口ひげにメガネの人です。
そう思って観ていると、他の人よりボウイングがゆったりしているし、ヴィブラートのかけ方も大きい。
すごい人がいるんだなぁ、と思いながら聴いていました。
1曲目が終り、指揮者が舞台袖に入ると、コントラバスを弾いていた人が指揮台に上がり、『フーガの技法』が始まりました。
オレはバッハを聴く事が滅多に無い人間なので、この曲は初めて聴いたのですが、それぞれのパートが独立して対位法的に絡むバッハのこういう曲は演奏のアラが目立ちやすい事は知っています。
敢えてこの曲を選んだのは、オーケストラの自信の表れなのでしょうか。
ただ、音量のバランスから言えば、ヴィオラがあと1プルト増えるといいと思いますね。
途中で、舞台袖から前の曲の指揮者がチェロを持って出て来て一緒に演奏していましたが、チェロと指揮って、トスカニーニを思い出しました。
『フーガの技法』からの3曲が終ると、最初の編成に戻り、シベリウスの『ロマンス』と『アンダンテ・フェスティーヴォ』が演奏されました。
この2曲も初めて聴きましたが、いい曲です。演奏も気合が入ってました。
シベリウスといえばヴァイオリン・コンチェルト(ベートーヴェン、メンデルスゾーン、ブラームスと並ぶ名曲中の名曲だとオレは思っています)くらいしか聴かないのですが、ずーっと以前に買ったまま一部だけしか聴いていない交響曲全集を聴いてみようかな、と思ったりしました。そんな事を思わせるというのは、やはり演奏に思いがこもっているからなのでしょうね。
ただ、この時思ったのですが、聴衆の拍手が短か過ぎますね。
オレはできるだけ長く拍手していましたが、すぐに消えてしまうのです。
せめて、指揮者が舞台袖に入るまでは拍手を続けるべきだと思います。
15分の休憩をはさんで第2部は、管楽器も加わって、モーツァルトの23番のピアノ・コンチェルトです。
オレはモーツァルトのピアノ・コンチェルトの中では、この23番が1番好きです。(オレの好きなベスト3は、23、22、20番です)
おそらく、オーケストラの編成の問題(後期のピアノ・コンチェルトの中では23番と27番の編成が1番小さい)もあったのだろうと思いますが、この曲が選ばれた事はうれしいですね。
演奏について言えば、とにかく一生懸命さが伝わってくる演奏でした。
意地の悪い聴き方をすれば、いくらでもミスや欠点を挙げる事は可能でしょう。でも、そんな聴き方をする気にはなりませんでしたね。
「いい曲だなぁ」と思わせてくれる演奏が名演奏だとオレは思っているのですが、この演奏を聴きながら、「いい曲だなぁ」って思いました。
特に、オレがいつもワクワクしながら聴くところ、フィナーレで2回出てくる、ピッツィカートの伴奏の上をピアノが駆け上がって降りて来る部分は、ピッツィカートの音が硬く響いた事で、逆にピアノがすごくチャーミングに聴こえたのですよ。
「あぁ、いいなぁ」って思いましたね。
さて、これはあくまでもオレが個人的に思う事なのですが、この曲の演奏について、いつも不思議に思うところがあるのです。(この曲はオレの大好きな曲ゆえに、余計にそう思うのかもしれませんが・・・・)
第2楽章の終りの方で、心臓の鼓動のような弦楽器の伴奏の上を、ピアノが愁いを帯びたメロディーを弾いていくところがあるのですが、以前は全ての弦楽器がピッツィカート(弦を指ではじく)だったのに(オレの持っているDoverのスコアもそうなっています)、新しいモーツァルト全集のスコアでは、ヴィオラとチェロとコントラバスがピッツィカートでヴァイオリンがアルコ(弓で弾く)になっているのですよ。
今回の演奏でもヴァイオリンはアルコでしたが、どう聴いてもオレには、全ての弦楽器がピッツィカートの方が自然に思えるのです。
ピアニストで指揮者のバレンボイムは、新しい全集が発表されてからの録音でも全ての弦楽器をピッツィカートで演奏させていますが、やはりバレンボイムもその方が自然だと感じているのではないかと思うのです。(その演奏のCDの解説書に、某評論家がその事をおかしいと書いていましたが、余計なお世話です)
ピアニストとしても指揮者としてもバレンボイムはあまり好きではありませんが、モーツァルトのピアノ・コンチェルトに関しては、バレンボイムの弾き振りによる演奏が感覚的に一番しっくり来る場合が多いですね。(曲にもよるんですが・・・・)
アンコールは、ピアノがメロディーを弾くところから始まったのですが、聞いた事があるメロディーなのに、何の曲だったか思い出せないのですよ。でも、途中で思い出しました。『グリーンスリーヴスによる幻想曲』です。
本来、木管楽器か演奏する序奏の部分をピアノが演奏するように編曲されていたので分からなかったのです。
弦楽器が、あの『グリーンスリーヴス』のメロディーを弾き始めた時、「いい曲だなぁ」って思いました。
今回、初めて高山室内合奏団の演奏を聴いたわけですが、こういうオーケストラが高山にある事は、本当にスゴい事だと思います。
次回の公演がいつなのかわかりませんが、絶対に聴きに行くつもりです。
その時には、できるだけ多くの人を誘って行きたいですね。
オレは何の力も持たない人間ですが、出来る事があるのなら、何らかの形で協力したいと思いますね。
演奏会から帰って来て、ふと思った事があります。
実を言うと、20年以上も前にヴァイオリンを齧った事があるのですが、自分の出す音と音程の酷さに耐えかねて止めてしまったのです。
でも今になって、あの時続けていればなぁ、って思いますね。
もしあの時続けていれば、このオーケストラに入って一緒に演奏する事ができたでしょうからね。
その時手に入れたヴァイオリン(未練がましく今でも持っている)を見て、そんな事を思う今日この頃です。
公演に出かける時はXJ−Sのトップを開けて、のんびりと会場へ向かいましたが、帰りはあの大雨のせいで、のんびりどころではありませんでした。
演奏会の印象と共に、その事もずーっと記憶に残るのでしょうね。
では、また。
Ciao. Arrivederci!!
暑い日が続きますねぇ。
ここしばらく忙しい日が続いたので、このブログを更新するのも久しぶりです。
ウチの店は、7月末から今月の7日まで全く予約が入ってなかったのですが、そんな時にフラッとカウンターに立ち寄って下さるお客さんはありがたいですね。
で、8日からは予約がびっしりと入って、休みも無しで営業しましたが、おかげで何とか今月末の支払いは出来そうです。
いつも不思議に思うのですが、予約って重なるものなんですよね。
8日は2組の予約が入っていましたが、その前日と当日に6件の予約の電話があり、すべてお断りしたのです。
その前の1週間はズーッと空いていたのに・・・・本当にうまくいかないものですね。

忙しかった10日間を目一杯働いて過ごし、久しぶりの休日になった19日、高山室内合奏団第4回定期演奏会に行って来ました。
このオーケストラの演奏を聴くのは今回が初めてなので、期待感と共に、ある種の不安感を持っていた事も確かです。
でも、高山のような地方都市で、アマチュア・オーケストラが定期的に活動しているというのは凄い事ですよね。
もう30年も前の事ですが、ネスカフェ・ゴールドブレンドのCMで、指揮者の石丸寛さんが「急行列車の停まる町にはオーケストラがあるべきだ」というような事を言っておられたのを覚えていますが、高山でそれが実現できた事は、誇るべきだと思いますね。
東京にいた時、あるアマチュア・オーケストラの演奏会に何回か行きました。
日大オーケストラのOB.OGが中心になってできた『アンサンブルSAKURA』です。
年に2回の定期公演のうちの1回は音楽評論家の宇野功芳さんが指揮台に立ったのですが、その演奏を楽しみにしていたのです。
ワルターとクナッパーツブッシュとフルトヴェングラーを合わせたような、まぁ、やりたい放題の演奏でした。
テンポは曲想に合わせて自在に変わり、目一杯メロディーが歌われ、耳が痛いほどティンパニが打ち込まれ、聴いた事のないようなバランスで楽器が鳴り、本当に止まってしまったようなゲネラル・パウゼが出てくる・・・・とにかく何がおこるかわからない演奏でした。
最初から最後まで、次は何がおこるのだろうとワクワクし通しでしたね。
そもそもプロのようなテクニックはないのですから、指揮者のテンポの変化について行くだけでも大変なんでしょうが、そこに生まれるスリルはスゴかったですね。まぁ、その分アンサンブルは乱れまくりでしたけど・・・・・(その演奏会のライヴ録音のCDを何枚か持っていますが、今聴いても本当に面白い!!演奏会の興奮を思い出します)
そういう演奏を嫌う人(そういう演奏だと分かっているのに聴きに行き、インターネット上にボロクソに書くヤツって何を考えているのでしょうかね)が多い事も事実ですが、オレは大好きです。
きちんと纏まった演奏なら他にいくらでもあるのですから、そういうのはプロに任せて、自分達の思い入れを目一杯表現する。そういう事ができるのがアマチュアの強みなんじゃないかと思うのです。
高山室内合奏団もいつかそんな演奏をしてほしい、と思うのはオレだけでしょうかね。
さて、19日の話に戻しましょう。
せっかくの演奏会ですから、XJ-Sのトップを開けて、ゆったりとした気持ちで世界生活文化センターへ向かいました。
開場時間より早めに着きましたが、すでにホールの扉は開いていたので、早速中へ。左側の通路を前に進み、前から5列目の通路のすぐ右の席に着きました。
あまり前過ぎると聴こえ方のバランスが悪くなるけれど、でも直接的な音も聴きたい。となると、この辺かなと思ったのですが、みんな考える事はいっしょなのでしょうか、結局、オレの前の4列は誰も座る事無く空いたまま・・・・・
パンフレットを一通り読んだ後は、時間潰し用に持っていた『大地の歌』のスコアを読みながら待っていたのですが、やがて開演のブザーが鳴り、オーケストラのメンバーが舞台に並び、指揮者が登場し、演奏会の始まりです。
第1部は弦楽合奏の曲で構成されていますが、最初の曲は『アイネ・クライネ・ナハトムズィーク』の第1楽章です。
最初の和音が鳴った瞬間、感動しましたね。
今回初めてこのオーケストラを聴いたのですが、今までに上記のSAKURAの他にもにアマチュア・オーケストラの演奏は聴いていますから「だいたいこんなレヴェルなんじゃないかな」という想像をしていたのですよ。
でも実際は、オレが思っていたより、ずーっと響きがまとまっています。
たかだか人口9万の高山に、これだけのオーケストラがあるという事はスゴいと思いますね。
演奏が始まってすぐ、1stヴァイオリンの後ろの方から、1人だけすごく良く通る音が聴こえる事に気が付きました。(オレは音感が良くないので断言はできませんが、微妙にその人のピッチが高いのかもしれません)
明らかにコンサート・ミストレスとは違う、というか、コンサート・ミストレスより目立っている。
その音の方向からすると、1番後ろのプルトの裏で弾いている、口ひげにメガネの人です。
そう思って観ていると、他の人よりボウイングがゆったりしているし、ヴィブラートのかけ方も大きい。
すごい人がいるんだなぁ、と思いながら聴いていました。
1曲目が終り、指揮者が舞台袖に入ると、コントラバスを弾いていた人が指揮台に上がり、『フーガの技法』が始まりました。
オレはバッハを聴く事が滅多に無い人間なので、この曲は初めて聴いたのですが、それぞれのパートが独立して対位法的に絡むバッハのこういう曲は演奏のアラが目立ちやすい事は知っています。
敢えてこの曲を選んだのは、オーケストラの自信の表れなのでしょうか。
ただ、音量のバランスから言えば、ヴィオラがあと1プルト増えるといいと思いますね。
途中で、舞台袖から前の曲の指揮者がチェロを持って出て来て一緒に演奏していましたが、チェロと指揮って、トスカニーニを思い出しました。
『フーガの技法』からの3曲が終ると、最初の編成に戻り、シベリウスの『ロマンス』と『アンダンテ・フェスティーヴォ』が演奏されました。
この2曲も初めて聴きましたが、いい曲です。演奏も気合が入ってました。
シベリウスといえばヴァイオリン・コンチェルト(ベートーヴェン、メンデルスゾーン、ブラームスと並ぶ名曲中の名曲だとオレは思っています)くらいしか聴かないのですが、ずーっと以前に買ったまま一部だけしか聴いていない交響曲全集を聴いてみようかな、と思ったりしました。そんな事を思わせるというのは、やはり演奏に思いがこもっているからなのでしょうね。
ただ、この時思ったのですが、聴衆の拍手が短か過ぎますね。
オレはできるだけ長く拍手していましたが、すぐに消えてしまうのです。
せめて、指揮者が舞台袖に入るまでは拍手を続けるべきだと思います。
15分の休憩をはさんで第2部は、管楽器も加わって、モーツァルトの23番のピアノ・コンチェルトです。
オレはモーツァルトのピアノ・コンチェルトの中では、この23番が1番好きです。(オレの好きなベスト3は、23、22、20番です)
おそらく、オーケストラの編成の問題(後期のピアノ・コンチェルトの中では23番と27番の編成が1番小さい)もあったのだろうと思いますが、この曲が選ばれた事はうれしいですね。
演奏について言えば、とにかく一生懸命さが伝わってくる演奏でした。
意地の悪い聴き方をすれば、いくらでもミスや欠点を挙げる事は可能でしょう。でも、そんな聴き方をする気にはなりませんでしたね。
「いい曲だなぁ」と思わせてくれる演奏が名演奏だとオレは思っているのですが、この演奏を聴きながら、「いい曲だなぁ」って思いました。
特に、オレがいつもワクワクしながら聴くところ、フィナーレで2回出てくる、ピッツィカートの伴奏の上をピアノが駆け上がって降りて来る部分は、ピッツィカートの音が硬く響いた事で、逆にピアノがすごくチャーミングに聴こえたのですよ。
「あぁ、いいなぁ」って思いましたね。
さて、これはあくまでもオレが個人的に思う事なのですが、この曲の演奏について、いつも不思議に思うところがあるのです。(この曲はオレの大好きな曲ゆえに、余計にそう思うのかもしれませんが・・・・)
第2楽章の終りの方で、心臓の鼓動のような弦楽器の伴奏の上を、ピアノが愁いを帯びたメロディーを弾いていくところがあるのですが、以前は全ての弦楽器がピッツィカート(弦を指ではじく)だったのに(オレの持っているDoverのスコアもそうなっています)、新しいモーツァルト全集のスコアでは、ヴィオラとチェロとコントラバスがピッツィカートでヴァイオリンがアルコ(弓で弾く)になっているのですよ。
今回の演奏でもヴァイオリンはアルコでしたが、どう聴いてもオレには、全ての弦楽器がピッツィカートの方が自然に思えるのです。
ピアニストで指揮者のバレンボイムは、新しい全集が発表されてからの録音でも全ての弦楽器をピッツィカートで演奏させていますが、やはりバレンボイムもその方が自然だと感じているのではないかと思うのです。(その演奏のCDの解説書に、某評論家がその事をおかしいと書いていましたが、余計なお世話です)
ピアニストとしても指揮者としてもバレンボイムはあまり好きではありませんが、モーツァルトのピアノ・コンチェルトに関しては、バレンボイムの弾き振りによる演奏が感覚的に一番しっくり来る場合が多いですね。(曲にもよるんですが・・・・)
アンコールは、ピアノがメロディーを弾くところから始まったのですが、聞いた事があるメロディーなのに、何の曲だったか思い出せないのですよ。でも、途中で思い出しました。『グリーンスリーヴスによる幻想曲』です。
本来、木管楽器か演奏する序奏の部分をピアノが演奏するように編曲されていたので分からなかったのです。
弦楽器が、あの『グリーンスリーヴス』のメロディーを弾き始めた時、「いい曲だなぁ」って思いました。
今回、初めて高山室内合奏団の演奏を聴いたわけですが、こういうオーケストラが高山にある事は、本当にスゴい事だと思います。
次回の公演がいつなのかわかりませんが、絶対に聴きに行くつもりです。
その時には、できるだけ多くの人を誘って行きたいですね。
オレは何の力も持たない人間ですが、出来る事があるのなら、何らかの形で協力したいと思いますね。
演奏会から帰って来て、ふと思った事があります。
実を言うと、20年以上も前にヴァイオリンを齧った事があるのですが、自分の出す音と音程の酷さに耐えかねて止めてしまったのです。
でも今になって、あの時続けていればなぁ、って思いますね。
もしあの時続けていれば、このオーケストラに入って一緒に演奏する事ができたでしょうからね。
その時手に入れたヴァイオリン(未練がましく今でも持っている)を見て、そんな事を思う今日この頃です。
公演に出かける時はXJ−Sのトップを開けて、のんびりと会場へ向かいましたが、帰りはあの大雨のせいで、のんびりどころではありませんでした。
演奏会の印象と共に、その事もずーっと記憶に残るのでしょうね。
では、また。
Ciao. Arrivederci!!
演奏会から帰ってしばらくした頃、このオーケストラのチェロ奏者の西先生から電話をもらいました。
その時に、例の目立ったヴァイオリニストの事を訊いてみたところ、その人はヴァイオリンを教えているプロなのだそうです。
どうりで上手いはずです。
でも、そういう人がトップに出るのではなく、一番後ろで弾き支えているというのは立派ですね。

その時に、例の目立ったヴァイオリニストの事を訊いてみたところ、その人はヴァイオリンを教えているプロなのだそうです。
どうりで上手いはずです。
でも、そういう人がトップに出るのではなく、一番後ろで弾き支えているというのは立派ですね。
スポンサーリンク

Posted by spock at 17:09│Comments(10)
この記事へのコメント
さすがspock さん!…と言うのもはばかられるくらいのレポートですね!
さすがです!!読んでいておもしろかったです。(ほとんど分かっていませんが…)
バイオリン弾いてくださいよ~♪
初めてカミングアウトしますが、私は二胡を習ってます。
音程がとりにくくて大変です。
さすがです!!読んでいておもしろかったです。(ほとんど分かっていませんが…)
バイオリン弾いてくださいよ~♪
初めてカミングアウトしますが、私は二胡を習ってます。
音程がとりにくくて大変です。
Posted by ふれっち at 2007年08月23日 18:59
じっくり読ませていただきました。
ふれっちさんと同じように、専門的な事は解らないけど
なるほど~って伝わってくるものがありますね。
音源があればspockさんに
解説してもらいながら聴いてみたいです。
私もバイオリン持ってるので一緒にやりませんか?
フェニーチェの予約状況なんですが
ネットでわかるようにすれば良いかも?
そうすれば、お客さんの方で調整できるからね~
ふれっちさんと同じように、専門的な事は解らないけど
なるほど~って伝わってくるものがありますね。
音源があればspockさんに
解説してもらいながら聴いてみたいです。
私もバイオリン持ってるので一緒にやりませんか?
フェニーチェの予約状況なんですが
ネットでわかるようにすれば良いかも?
そうすれば、お客さんの方で調整できるからね~
Posted by 黒雷鳥 at 2007年08月24日 13:25
ふれっちさん
例によって長い文を読んで頂き、ありがとうございます。
おもしろかったと書いてもらえて嬉しいですよ。
二胡を習っておられるのですか。
二胡もヴァイオリンと同じで、音と音程を自分で作らなければならないんですよね。
オレは、そこで諦めてしまって後悔してますから、ふれっちさんは頑張って続けて下さい。
今では、サイレント・ヴァイオリンを使って、騒音(?)を撒き散らさずに練習できるそうですから、もう1度やってみようかな・・・・
例によって長い文を読んで頂き、ありがとうございます。
おもしろかったと書いてもらえて嬉しいですよ。
二胡を習っておられるのですか。
二胡もヴァイオリンと同じで、音と音程を自分で作らなければならないんですよね。
オレは、そこで諦めてしまって後悔してますから、ふれっちさんは頑張って続けて下さい。
今では、サイレント・ヴァイオリンを使って、騒音(?)を撒き散らさずに練習できるそうですから、もう1度やってみようかな・・・・
Posted by spock at 2007年08月24日 14:02
黒雷鳥さん
いつも、ありがとうございます。
黒雷鳥さんは、ヴァイオリンも弾けるのですか?
ぜひ手解きをしてほしいですね。
ネット上で予約状況がわかるようにする事は以前から考えているのですが、技術的な面で二の足を踏んでいるのですよ。
今度、相談にのって下さい。
いつも、ありがとうございます。
黒雷鳥さんは、ヴァイオリンも弾けるのですか?
ぜひ手解きをしてほしいですね。
ネット上で予約状況がわかるようにする事は以前から考えているのですが、技術的な面で二の足を踏んでいるのですよ。
今度、相談にのって下さい。
Posted by spock at 2007年08月24日 15:07
こんばんは。
いろいろたてこんでいて、なかなか行く事ができないと以前お伝えしました「ぴう」ともうします。
クラシックは学校で聴いて以来、生演奏を聴いておりません。
未就学児の扱いが大きな壁に・・・
ネット上でわかるようにするには、、、難しいですね。
手動でよければ毎日予約帳を見ながら自分でサイトを書き換え更新でできますけど、リアルタイムとなると、プログラム組まないとまず無理ですよね・・・一日の予約客数がとても多いときはリアルタイムがいいですが、システム組むのは大きな出費を覚悟しないといけませんね。
いろいろたてこんでいて、なかなか行く事ができないと以前お伝えしました「ぴう」ともうします。
クラシックは学校で聴いて以来、生演奏を聴いておりません。
未就学児の扱いが大きな壁に・・・
ネット上でわかるようにするには、、、難しいですね。
手動でよければ毎日予約帳を見ながら自分でサイトを書き換え更新でできますけど、リアルタイムとなると、プログラム組まないとまず無理ですよね・・・一日の予約客数がとても多いときはリアルタイムがいいですが、システム組むのは大きな出費を覚悟しないといけませんね。
Posted by ぶーさん at 2007年08月28日 22:11
お久しぶりです。
高山は人口に対して、楽器の演奏者の需要が非常に多いといわれています。その中で、人それぞれが自分にあった団体に入って演奏したいと思っていても、なかなか気に入った団体で演奏できる人は少ないみたいです。
しかし、その中で今回の高山室内合奏団のヴァイオリン すごかったです!!!! ←と言うにはワタクシの妹です。(妹:ファゴット演奏者)(因みに、ワタクシ:トランペット少々・・)
妹が聴きに行ったみたいなのでどうだったのと聞いてみました。
ヴァイオリンに大絶賛でした。
ワタクシも去年、フィガロの結婚を聞きたく、岐阜へ行ってきました。メジャーな曲ばかりで飽きることなく楽しめました。
一度でいいので、東京の新国立劇場や国際ファーラムなど雰囲気を味わってみたいものです。
高山は人口に対して、楽器の演奏者の需要が非常に多いといわれています。その中で、人それぞれが自分にあった団体に入って演奏したいと思っていても、なかなか気に入った団体で演奏できる人は少ないみたいです。
しかし、その中で今回の高山室内合奏団のヴァイオリン すごかったです!!!! ←と言うにはワタクシの妹です。(妹:ファゴット演奏者)(因みに、ワタクシ:トランペット少々・・)
妹が聴きに行ったみたいなのでどうだったのと聞いてみました。
ヴァイオリンに大絶賛でした。
ワタクシも去年、フィガロの結婚を聞きたく、岐阜へ行ってきました。メジャーな曲ばかりで飽きることなく楽しめました。
一度でいいので、東京の新国立劇場や国際ファーラムなど雰囲気を味わってみたいものです。
Posted by たけち at 2007年08月29日 21:18
ぷーさん
確かに、小さな子供さんを連れて演奏会には行けませんね。
一時的に預かってくれる保育所って、出来ないものなんでしょうかね。
プログラムを組むのは無理なので、地道に手動でやるしかないでしょうね。
でも、その前にまずウェブサイトを作らないと・・・・(ずっと前にドメインは取得しているのですが・・・・)
ぜひ、子供さんを連れて来て下さい。お待ちしてますよ。
たけちさん
お久しぶりですね。
人口9万の地方都市で、アマチュア・オーケストラが定期的に演奏会を行うというのはスゴいですね。そして、演奏のレヴェルも高い。
いろいろ問題はあるんでしょうが、団体間の交流がふえれば、もっと大きな編成での演奏会も可能でしょうね。
ところで、マイケル・ヴィックが罪を認めたので、収監される事は確実なようですよ。でも、いつか復帰してほしいですね。(案外、RBとして復帰したりして・・・・)
木下は第1次ロースターカットに残ったようですが、ここまで来たら、ぜひ開幕ロースターに残ってほしいですね。
前からお訊きしようと思っていたのですが、『やどっち』のメンバーに『たけし』さんはあるのですが『たけち』さんはないですよね・・・・・
確かに、小さな子供さんを連れて演奏会には行けませんね。
一時的に預かってくれる保育所って、出来ないものなんでしょうかね。
プログラムを組むのは無理なので、地道に手動でやるしかないでしょうね。
でも、その前にまずウェブサイトを作らないと・・・・(ずっと前にドメインは取得しているのですが・・・・)
ぜひ、子供さんを連れて来て下さい。お待ちしてますよ。
たけちさん
お久しぶりですね。
人口9万の地方都市で、アマチュア・オーケストラが定期的に演奏会を行うというのはスゴいですね。そして、演奏のレヴェルも高い。
いろいろ問題はあるんでしょうが、団体間の交流がふえれば、もっと大きな編成での演奏会も可能でしょうね。
ところで、マイケル・ヴィックが罪を認めたので、収監される事は確実なようですよ。でも、いつか復帰してほしいですね。(案外、RBとして復帰したりして・・・・)
木下は第1次ロースターカットに残ったようですが、ここまで来たら、ぜひ開幕ロースターに残ってほしいですね。
前からお訊きしようと思っていたのですが、『やどっち』のメンバーに『たけし』さんはあるのですが『たけち』さんはないですよね・・・・・
Posted by spock at 2007年08月30日 09:59
やはりヴィックはだめでしたか?!
チームプレーを無視したようなQB、見ていて楽しかったですが、残念ですね~
QBは、ロスリスバーガーやトニー・ロモ が個人的には気になる選手です。
それにしても 木下もうちょいですね! 5/9の確立ですね~
是非WR枠の5人に入って欲しいです。
さて、「やどっち」のたけしですが、たけし=たけちです・・・・・・
ネット上では、「たけち」としていろいろな所に出没しているわけですが、「やどっち」の管理人が勝手に載せてしまいまして・・・・
たけしになってしまいました・・・・・
「やどっち」はリレー方式なので大体出番は半月に1回です。
またお暇なときにでも覗いてください。
チームプレーを無視したようなQB、見ていて楽しかったですが、残念ですね~
QBは、ロスリスバーガーやトニー・ロモ が個人的には気になる選手です。
それにしても 木下もうちょいですね! 5/9の確立ですね~
是非WR枠の5人に入って欲しいです。
さて、「やどっち」のたけしですが、たけし=たけちです・・・・・・
ネット上では、「たけち」としていろいろな所に出没しているわけですが、「やどっち」の管理人が勝手に載せてしまいまして・・・・
たけしになってしまいました・・・・・
「やどっち」はリレー方式なので大体出番は半月に1回です。
またお暇なときにでも覗いてください。
Posted by たけち at 2007年08月30日 12:16
やはりそうでしたか。
という事は、ウチの近くですね。
そのうちに、ジェラートでも持って伺いますよ。
という事は、ウチの近くですね。
そのうちに、ジェラートでも持って伺いますよ。
Posted by spock at 2007年08月31日 22:23
at 2007年08月31日 22:23
 at 2007年08月31日 22:23
at 2007年08月31日 22:23本当ですか!? 楽しみです・・・・と言う前に、お店にお邪魔したいと、ずぅと思っています^^
Posted by たけち at 2007年09月01日 11:50