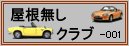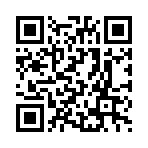2009年03月30日
群鳳>与鹿=麒麟台・・・?
Ciao. spockです。
完全に春になったと思っていたら、また寒くなり・・・・
まぁね、この時期は仕方が無いといえば仕方が無いんだけれど・・・・
2月の後半から、天気のいい日には、化け猫を引っ張りだしてトップ全開で走ってますけど、まだ少し寒いですね。
以前読んだ本によると、ヨーロッパで一番オープンカーが多いのはドイツなのだそうです。
長く厳しい冬が終わり、春の日差しを感じられるようになる頃、どこにこれだけ隠れていたのか不思議に思うくらいたくさんのトップを全開にしたクルマが、春の日差しを目一杯浴びるために、ドイツ中を走り回るのだそうです。
そういう気持ち、スゴく解るなぁ・・・・って、オレの場合、冬でもフルオープンで走ってますけどね。
冬が長く厳しい高山にも、もっとオープンカーが増えるといいと思うんですけどねぇ。
さて、本題に入る前に、お知らせです。
劇団無尽舎のブログにも書かれていますが、3月31日(火)、夜7:30から、世界生活文化センターのミニシアターで、劇団無尽舎が2006年に制作した、ヴィデオ映画『だいめいかい』が上映されます。(入場料は無料です)
そして、これが劇団無尽舎の最終公演(?)になります。
この上映会をもって、劇団無尽舎は、13年の歴史にピリオドをうちます。
映画の内容は、傾いた商店街を活性化するために青年部が講演会を企画し・・・・と、まぁ、どこにでもありそうな話だけれど、どこにもない結末に向かって行くのが、千葉作品の特徴であり、十分に楽しんでもらえる作品だと思います。
世界生活文化センターまでは遠いですが、ぜひご覧になって下さい。
また、上映会後、ラ フェニーチェでパーティーがあります。
ちなみに、約55分の映画ですが、その1/3は、ラ フェニーチェで撮影されました。
だからオレも出演しています。(一応、準劇団員だし・・・・)
先日、いつも灯油を入れに来てくれるMさん(去年の春祭の後に書いた『曳き別れを観に・・・・』の中にも書いたのですが、恵比須台の後の大梃子です)が来られた時、少し話をしたのですが、話が春祭の事になると、大変だ、大変だ、と言いながら、スゴく嬉しそうに話されるのを見て、Mさんも祭に関われる幸せを味わっておられるのだなぁ・・・・と、ある意味で羨ましく思いました。
『曳き別れを観に・・・・』では、古い町並みを通る夜祭りの恵比須台の美しさについて書いたのですが、最後に、次回は麒麟台の美しさについて書きます、と予告しながら、画像がうまく見つからなかったため、長くアップできずにいた文を、やっと今回公開できます。
今回は、高山祭の屋台の中でも屈指の美しさを誇る麒麟台について、オレの思っている事を書きます。
まぁ、麒麟台に何の関係もないオレがこういう事を書くと、ひょっとしたら麒麟台組の人に怒られるかもしれませんが・・・・でもね、こんな考え方があってもいいと思うのですよ。
では、始めましょうか。
麒麟台と言えば、誰もが谷口与鹿の名前を思い浮かべるでしょう。
実際、『麒麟台』でググってみると、必ずと言っていいほど谷口与鹿の名前が出てきますが、それはおそらく、麒麟台=唐子群遊彫刻=谷口与鹿、みたいな公式(?)が自然にできてしまっているからだと思います。
勿論それが間違っていると言うつもりはありませんが・・・・でも言わせてもらうなら、今の麒麟台においては、谷口与鹿<村山群鳳(初代)だと、オレは思うのです。
この画像を見てもらいましょう。
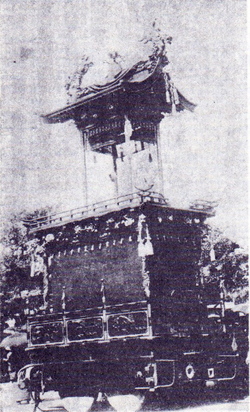 少し見にくいですが、長倉三朗さんの書かれた『高山祭屋台雑考』(1981年 慶友社刊)の中からスキャニングしたもので、大正10年の祭まで曳かれた、改修前の麒麟台です。
少し見にくいですが、長倉三朗さんの書かれた『高山祭屋台雑考』(1981年 慶友社刊)の中からスキャニングしたもので、大正10年の祭まで曳かれた、改修前の麒麟台です。
モノクロの古い画像からでは、いささか情報量が少ないのですが、これで見る旧麒麟台は『豪華絢爛』と評される現在の麒麟台に比べて、かなり地味な屋台だったようですね。
上記の長倉さんの本によると、唐子群遊彫刻は、ケヤキ材の銀杏文透かし彫の格子の隙間から見えるようになっていたそうで、その格子が曳き別れの時の喧嘩で割られてからは、金網が張られていたそうです。
弘化から大正まで約70年曳かれた旧麒麟台が、現在の豪華な麒麟台になったのは、大正10年からの改修によるもので、設計と彫刻が初代村山群鳳、工匠が広瀬石太郎、坂本吉右衛門、白川友吉、塗りが田近卯之助という人達により、昭和8年に完成しています。
この時の改修によって、屈指の美しさを誇る屋台になったわけですが、わけても賞賛されるべきなのは、村山群鳳さんだと思います。
この改修で増補した彫刻は、すべて村山群鳳さんの作品だそうですが、屋台彫刻の最高峰とも言える『唐子群遊』と同居しても負けないだけの作品にしなければならないのですから、その彫刻を彫る時の群鳳さんにかかるプレッシャーは、想像を絶するものだったろうと思います。
群鳳さんの手による麒麟台の彫刻を見る時、群鳳さんの『執念』を感じるのはオレだけでしょうか。
例えば、中段勾欄の飛龍の細いヒゲや、

長い尾羽の一枚一枚が彫り出されているのを見ると、

それがどんなに大変な仕事であったかは、容易に想像がつきます。
飛龍だけではなく、幣軸の昇降龍や、見送り上部の鳳凰も、与鹿の彫刻に負けない傑作だと、オレは思います。
そういえば、山本茂実さんの『高山祭』の中に、その当時の群鳳さんの事が書かれていました。
そういえば、麒麟台組の大沼富造(上一之町)から聞いた話が思い出される。
「初代群鳳さんが私どもの屋台の鳳凰を彫ったのは、確か大正10年ころだったと思います。今でもよく憶えているのは、毎月晦日になると鬱金(鮮黄色)のふろ敷包みを背負ってきて、これだけ彫れたからとまだ未完成の鳳凰を開いてみせました。それを能登屋の先代(上一之町・石川良吉・昭和5年没・62歳)が物差しで計り、今月は何寸彫ったからいくらだと計算して金を渡す。群鳳さんはまた彫りかけの作品をふろ敷に包んで家に持ち帰る。当時子供だった私は、その彫りをみるのが楽しみでしたが、あの彫りだけでも7、8ヶ月かかっていますね。今考えてみるとあのころの群鳳さんは、名工といわれながらも生活は苦しかったんでしょうね。」
やはり群鳳さんは、貧困の中、苦労して彫ったのですね。
でも、麒麟台を観る時、誰もがまず『唐子群遊』を観てしまい、麒麟台=谷口与鹿と思ってしまう事が、宿命とはいえ、群鳳さんの悲劇なのかもしれません。
でも、麒麟台の改修における群鳳さんの功績が、彫刻以上に評価されるべきなのは、設計の素晴らしさについてだと、オレは思います。
群鳳さんが新しい麒麟台を設計するにあたり、まず考えた事は、どのようにして唐子群遊彫刻を見せるか、という事だっただろうと想像するのですが、自身が彫刻家である群鳳さんは、この極めて精巧かつ繊細な唐子群遊彫刻を、網などで覆う事なく見せたいと考えたのではないか、と思うのですよ。
でも、この繊細な彫刻を剥き出しにするのは、非常に危険な事ですから、何らかの方法で保護する事が絶対に必要な条件です。
彫刻を保護しながら何の障害もなく見せる、という相反する条件を満たすために考えられたのが、彫刻を回廊の奥壁に取り付けるという、現在の麒麟台の方法なのだと思います。
その回廊と御所車を組み合わせた下段の構成は、高山の屋台中の白眉だと、オレは思いますね。
 高山の屋台の大半は、車輪に『内板車』を使っており、御所車は少数派です。
高山の屋台の大半は、車輪に『内板車』を使っており、御所車は少数派です。
おそらくその理由は、内板車の方が、下段の構成の自由度が大きい事だろうと思います。
ヴォリュームの大きい彫刻を取り付けている屋台、八幡の鳳凰台、石橋台、恵比須台などが、内板車を使っているのは、そういう理由からだと推測します。
(画像は、恵比須台の下段です)
 御所車は美しく典雅ではありますが、構造上、どうしても下段の一部が弧状にけられてしまうため、取り付ける彫刻のヴォリューム(特に上下幅)に制約ができてしまいます。
御所車は美しく典雅ではありますが、構造上、どうしても下段の一部が弧状にけられてしまうため、取り付ける彫刻のヴォリューム(特に上下幅)に制約ができてしまいます。
実際に御所車を使っている屋台、例えば神楽台、五台山、豊明台は、いずれも弧状の枠の上に獅子が乗っている形状ですね。
(画像は、五台山の飛獅子です)

八幡の神楽台の場合は、三輪のため特に大きな御所車を使っているせいもあり、下段の彫刻が車輪の枠に隠れてしまって、見えなくなっている部分がありますね。
 麒麟台の『唐子群遊』もヴォリュームの大きい彫刻ですが、この彫刻を納める下段の回廊の下に、最下段とでも言うべき青海波の彫刻を入れた間を作り、御所車を使う時にできる弧状のけられを、その最下段に納めてしまう事で、ヴォリュームの大きい彫刻と御所車を両立させる、非常に巧みな構成になっています。
麒麟台の『唐子群遊』もヴォリュームの大きい彫刻ですが、この彫刻を納める下段の回廊の下に、最下段とでも言うべき青海波の彫刻を入れた間を作り、御所車を使う時にできる弧状のけられを、その最下段に納めてしまう事で、ヴォリュームの大きい彫刻と御所車を両立させる、非常に巧みな構成になっています。
ただ、この巧みな下段の構成も、旧麒麟台の構造をうまく流用したもの、と考える事ができます。
画像から見る旧麒麟台は、古い形式(下段の上部がそのまま中段の勾欄になる)の屋台である事が分かります。
 現存する屋台の中で、古い形式を残しているのは布袋台だけですが、布袋台と旧麒麟台の画像を見てみると、共通した特徴があります。
現存する屋台の中で、古い形式を残しているのは布袋台だけですが、布袋台と旧麒麟台の画像を見てみると、共通した特徴があります。
それは、台輪と下段の間に、最下段とも言える部分がある事です。
布袋台のその部分には、朱塗りの雷文つなぎの浮き彫りが入っていますが、上記の長倉さんの本によると、旧麒麟台のその部分には、青海波の彫刻が入っていたそうです。
という事は、旧麒麟台の最下段を流用して、現在の麒麟台の最下段が作られたと推測できますね。
実に巧く考えられています。
麒麟台は、下段の下に最下段があるため、他の屋台に比べて、下段と中段の高さの比率が微妙に違っていて少し腰高に見えますが、下段の独特の構造を巧く使って、逆に安定感と引き締ったプロポーションを得る事に成功しています。
この画像を見てもらいましょう。
 台輪の上に、少し幅の広い最下段が載り、その上に、さらに幅の広い下段回廊が載り、その上に、さらに幅の広い中段勾欄が載って、逆台形状の形態になっています。
台輪の上に、少し幅の広い最下段が載り、その上に、さらに幅の広い下段回廊が載り、その上に、さらに幅の広い中段勾欄が載って、逆台形状の形態になっています。
その部分をよく見ると、台輪の上から中段の伊達柱まで一直線に通る柱によって作られた屋台本体の周りに、最下段、下段回廊、中段勾欄が付けられた形態である事が解ります。
こういう構造を持った屋台は、麒麟台と、おそらく同じ頃に群鳳さんが手掛けたと思われる、古川の青龍台の他にはありません。
 小学4年の春、曳き別れを観ていて、麒麟台のこの構造に気がついた時、唐子群遊彫刻よりも遥かに惹かれるものを感じて、ゾクゾクしながらしばらく麒麟台を追いかけた事を、今も憶えています。
小学4年の春、曳き別れを観ていて、麒麟台のこの構造に気がついた時、唐子群遊彫刻よりも遥かに惹かれるものを感じて、ゾクゾクしながらしばらく麒麟台を追いかけた事を、今も憶えています。
まぁ、その当時からマニアックな見方をする子供だったという事なんでしょうかね。
さて、話を戻して・・・・台輪から中段勾欄まで逆台形状に広がってきた上には、中段と上段が載るわけですが、麒麟台の場合、実際にそうなのか、あるいはそう見えるように設計されているのか分かりませんが、中段と上段が、他の屋台に比べてスリムに見えるのです。
そのため、台輪から中段勾欄まで広がって来たシルエットが、上段勾欄、屋根、千木と狭まっていくのがハッキリと分かり、非常に均整のとれた、引き締ったプロポーションに見えます。
この引き締ったプロポーションは、見た目がいいのはもちろんですが、もう一つ、重要な役割を果たしていると思います。
屋台の美しさに関しては、好みの問題もあると思いますが、例えば、五台山や石橋台のような、ある種の渋さを持った美しさを良しとする人からすれば、麒麟台は装飾過多という事になるでしょう。

実際、麒麟台には装飾が多いし、例えばこの羅網のように、色の組み合わせから言っても派手な屋台である事は間違いありません。
でも、それだけたくさんの装飾を付けていても、決してゴテゴテとした印象を与える事がないのは、この引き締ったプロポーションが、そう見せているからだと思います。
実に良く考えられた設計だと思いますね。
唐子群遊彫刻を効果的にみせるため、誰も思いつかなかった構造を考案し、与鹿に負けない彫刻を彫り、屈指の美しさを誇る屋台を造り上げた・・・・群鳳さんの功績は計り知れないものがあると思います。
だから、オレが麒麟台について考える時、与鹿の事より、群鳳さんの事を多く考えてしまいますね。
まあね、オレがどんなに 群鳳>与鹿@麒麟台 だと言っても、麒麟台=与鹿 という公式が覆る事は無いでしょう。
でも、麒麟台を語る時、絶対に、初代村山群鳳の事を忘れてはいけないと思うのですよ。
もし、今度の春祭に、オレがここに書いた事を思い出してもらえたら、麒麟台をじっくりと観て、群鳳さんの執念を感じ取ってほしいと思います。
きっと、オレがここに書いた事が決して間違っていない事を、解ってもらえると思います。
 ただ、もしも麒麟台に与鹿の唐子群遊彫刻がなかったとしたら、はたして群鳳さんは麒麟台をここまでに美しく仕上げる事が出来たのだろうか、と考える事があります。
ただ、もしも麒麟台に与鹿の唐子群遊彫刻がなかったとしたら、はたして群鳳さんは麒麟台をここまでに美しく仕上げる事が出来たのだろうか、と考える事があります。
上にも書いた古川の青龍台は、下段の構造や、屋根の千木の数が麒麟台と同じですから、おそらく、同じ頃に群鳳さんが手掛けた屋台だと推測できます。
もちろん、使えるお金や時間の違いもあったでしょうから、一概には言えませんが、麒麟台で感じられる壮絶なまでの執念は、残念な事に、青龍台では感じられない・・・・と思うのはオレだけでしょうか。
やはり、与鹿の作品があったからこそ全身全霊を打ち込んで麒麟台を仕上げた、と考えるべきなのだとオレは思います。
う〜ん、そう考えると、群鳳=与鹿@麒麟台 になるのかなぁ・・・・
ただ、完璧なまでの美を誇る麒麟台の中で、一カ所だけ、本当に惜しい、と思うところがあります。
 それは、下段前面の中央部分で、中央に立つ柱と枡組のせいで、真ん中の唐子の顔が全く見えなくなっているのですよ。
それは、下段前面の中央部分で、中央に立つ柱と枡組のせいで、真ん中の唐子の顔が全く見えなくなっているのですよ。
ここだけは、何とかならなかったものかと思いますね。
もっとも、日光東照宮の陽明門には『魔除けの逆柱』(魔除けのために、わざと1本の柱だけ彫刻が逆さにしてある)があるくらいですから、そういう意味では、完璧でない方が正解なのかもしれません。
いや、でも・・・・もしも群鳳さんが、そこまで考えて、わざとそういう設計をしたのだったら・・・・
それこそ『完璧』と言うしかないですね。
では、また。
Ciao. Arrivederci!!
完全に春になったと思っていたら、また寒くなり・・・・
まぁね、この時期は仕方が無いといえば仕方が無いんだけれど・・・・
2月の後半から、天気のいい日には、化け猫を引っ張りだしてトップ全開で走ってますけど、まだ少し寒いですね。
以前読んだ本によると、ヨーロッパで一番オープンカーが多いのはドイツなのだそうです。
長く厳しい冬が終わり、春の日差しを感じられるようになる頃、どこにこれだけ隠れていたのか不思議に思うくらいたくさんのトップを全開にしたクルマが、春の日差しを目一杯浴びるために、ドイツ中を走り回るのだそうです。
そういう気持ち、スゴく解るなぁ・・・・って、オレの場合、冬でもフルオープンで走ってますけどね。
冬が長く厳しい高山にも、もっとオープンカーが増えるといいと思うんですけどねぇ。
さて、本題に入る前に、お知らせです。
劇団無尽舎のブログにも書かれていますが、3月31日(火)、夜7:30から、世界生活文化センターのミニシアターで、劇団無尽舎が2006年に制作した、ヴィデオ映画『だいめいかい』が上映されます。(入場料は無料です)
そして、これが劇団無尽舎の最終公演(?)になります。
この上映会をもって、劇団無尽舎は、13年の歴史にピリオドをうちます。
映画の内容は、傾いた商店街を活性化するために青年部が講演会を企画し・・・・と、まぁ、どこにでもありそうな話だけれど、どこにもない結末に向かって行くのが、千葉作品の特徴であり、十分に楽しんでもらえる作品だと思います。
世界生活文化センターまでは遠いですが、ぜひご覧になって下さい。
また、上映会後、ラ フェニーチェでパーティーがあります。
ちなみに、約55分の映画ですが、その1/3は、ラ フェニーチェで撮影されました。
だからオレも出演しています。(一応、準劇団員だし・・・・)
先日、いつも灯油を入れに来てくれるMさん(去年の春祭の後に書いた『曳き別れを観に・・・・』の中にも書いたのですが、恵比須台の後の大梃子です)が来られた時、少し話をしたのですが、話が春祭の事になると、大変だ、大変だ、と言いながら、スゴく嬉しそうに話されるのを見て、Mさんも祭に関われる幸せを味わっておられるのだなぁ・・・・と、ある意味で羨ましく思いました。
『曳き別れを観に・・・・』では、古い町並みを通る夜祭りの恵比須台の美しさについて書いたのですが、最後に、次回は麒麟台の美しさについて書きます、と予告しながら、画像がうまく見つからなかったため、長くアップできずにいた文を、やっと今回公開できます。
今回は、高山祭の屋台の中でも屈指の美しさを誇る麒麟台について、オレの思っている事を書きます。
まぁ、麒麟台に何の関係もないオレがこういう事を書くと、ひょっとしたら麒麟台組の人に怒られるかもしれませんが・・・・でもね、こんな考え方があってもいいと思うのですよ。
では、始めましょうか。
麒麟台と言えば、誰もが谷口与鹿の名前を思い浮かべるでしょう。
実際、『麒麟台』でググってみると、必ずと言っていいほど谷口与鹿の名前が出てきますが、それはおそらく、麒麟台=唐子群遊彫刻=谷口与鹿、みたいな公式(?)が自然にできてしまっているからだと思います。
勿論それが間違っていると言うつもりはありませんが・・・・でも言わせてもらうなら、今の麒麟台においては、谷口与鹿<村山群鳳(初代)だと、オレは思うのです。
この画像を見てもらいましょう。
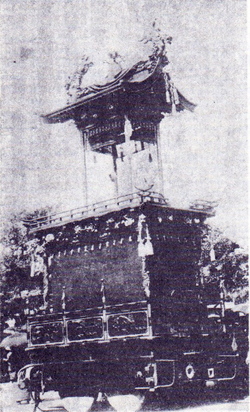 少し見にくいですが、長倉三朗さんの書かれた『高山祭屋台雑考』(1981年 慶友社刊)の中からスキャニングしたもので、大正10年の祭まで曳かれた、改修前の麒麟台です。
少し見にくいですが、長倉三朗さんの書かれた『高山祭屋台雑考』(1981年 慶友社刊)の中からスキャニングしたもので、大正10年の祭まで曳かれた、改修前の麒麟台です。モノクロの古い画像からでは、いささか情報量が少ないのですが、これで見る旧麒麟台は『豪華絢爛』と評される現在の麒麟台に比べて、かなり地味な屋台だったようですね。
上記の長倉さんの本によると、唐子群遊彫刻は、ケヤキ材の銀杏文透かし彫の格子の隙間から見えるようになっていたそうで、その格子が曳き別れの時の喧嘩で割られてからは、金網が張られていたそうです。
弘化から大正まで約70年曳かれた旧麒麟台が、現在の豪華な麒麟台になったのは、大正10年からの改修によるもので、設計と彫刻が初代村山群鳳、工匠が広瀬石太郎、坂本吉右衛門、白川友吉、塗りが田近卯之助という人達により、昭和8年に完成しています。
この時の改修によって、屈指の美しさを誇る屋台になったわけですが、わけても賞賛されるべきなのは、村山群鳳さんだと思います。
この改修で増補した彫刻は、すべて村山群鳳さんの作品だそうですが、屋台彫刻の最高峰とも言える『唐子群遊』と同居しても負けないだけの作品にしなければならないのですから、その彫刻を彫る時の群鳳さんにかかるプレッシャーは、想像を絶するものだったろうと思います。
群鳳さんの手による麒麟台の彫刻を見る時、群鳳さんの『執念』を感じるのはオレだけでしょうか。
例えば、中段勾欄の飛龍の細いヒゲや、

長い尾羽の一枚一枚が彫り出されているのを見ると、

それがどんなに大変な仕事であったかは、容易に想像がつきます。
飛龍だけではなく、幣軸の昇降龍や、見送り上部の鳳凰も、与鹿の彫刻に負けない傑作だと、オレは思います。
そういえば、山本茂実さんの『高山祭』の中に、その当時の群鳳さんの事が書かれていました。
そういえば、麒麟台組の大沼富造(上一之町)から聞いた話が思い出される。
「初代群鳳さんが私どもの屋台の鳳凰を彫ったのは、確か大正10年ころだったと思います。今でもよく憶えているのは、毎月晦日になると鬱金(鮮黄色)のふろ敷包みを背負ってきて、これだけ彫れたからとまだ未完成の鳳凰を開いてみせました。それを能登屋の先代(上一之町・石川良吉・昭和5年没・62歳)が物差しで計り、今月は何寸彫ったからいくらだと計算して金を渡す。群鳳さんはまた彫りかけの作品をふろ敷に包んで家に持ち帰る。当時子供だった私は、その彫りをみるのが楽しみでしたが、あの彫りだけでも7、8ヶ月かかっていますね。今考えてみるとあのころの群鳳さんは、名工といわれながらも生活は苦しかったんでしょうね。」
やはり群鳳さんは、貧困の中、苦労して彫ったのですね。
でも、麒麟台を観る時、誰もがまず『唐子群遊』を観てしまい、麒麟台=谷口与鹿と思ってしまう事が、宿命とはいえ、群鳳さんの悲劇なのかもしれません。
でも、麒麟台の改修における群鳳さんの功績が、彫刻以上に評価されるべきなのは、設計の素晴らしさについてだと、オレは思います。
群鳳さんが新しい麒麟台を設計するにあたり、まず考えた事は、どのようにして唐子群遊彫刻を見せるか、という事だっただろうと想像するのですが、自身が彫刻家である群鳳さんは、この極めて精巧かつ繊細な唐子群遊彫刻を、網などで覆う事なく見せたいと考えたのではないか、と思うのですよ。
でも、この繊細な彫刻を剥き出しにするのは、非常に危険な事ですから、何らかの方法で保護する事が絶対に必要な条件です。
彫刻を保護しながら何の障害もなく見せる、という相反する条件を満たすために考えられたのが、彫刻を回廊の奥壁に取り付けるという、現在の麒麟台の方法なのだと思います。
その回廊と御所車を組み合わせた下段の構成は、高山の屋台中の白眉だと、オレは思いますね。
 高山の屋台の大半は、車輪に『内板車』を使っており、御所車は少数派です。
高山の屋台の大半は、車輪に『内板車』を使っており、御所車は少数派です。おそらくその理由は、内板車の方が、下段の構成の自由度が大きい事だろうと思います。
ヴォリュームの大きい彫刻を取り付けている屋台、八幡の鳳凰台、石橋台、恵比須台などが、内板車を使っているのは、そういう理由からだと推測します。
(画像は、恵比須台の下段です)
 御所車は美しく典雅ではありますが、構造上、どうしても下段の一部が弧状にけられてしまうため、取り付ける彫刻のヴォリューム(特に上下幅)に制約ができてしまいます。
御所車は美しく典雅ではありますが、構造上、どうしても下段の一部が弧状にけられてしまうため、取り付ける彫刻のヴォリューム(特に上下幅)に制約ができてしまいます。実際に御所車を使っている屋台、例えば神楽台、五台山、豊明台は、いずれも弧状の枠の上に獅子が乗っている形状ですね。
(画像は、五台山の飛獅子です)

八幡の神楽台の場合は、三輪のため特に大きな御所車を使っているせいもあり、下段の彫刻が車輪の枠に隠れてしまって、見えなくなっている部分がありますね。
 麒麟台の『唐子群遊』もヴォリュームの大きい彫刻ですが、この彫刻を納める下段の回廊の下に、最下段とでも言うべき青海波の彫刻を入れた間を作り、御所車を使う時にできる弧状のけられを、その最下段に納めてしまう事で、ヴォリュームの大きい彫刻と御所車を両立させる、非常に巧みな構成になっています。
麒麟台の『唐子群遊』もヴォリュームの大きい彫刻ですが、この彫刻を納める下段の回廊の下に、最下段とでも言うべき青海波の彫刻を入れた間を作り、御所車を使う時にできる弧状のけられを、その最下段に納めてしまう事で、ヴォリュームの大きい彫刻と御所車を両立させる、非常に巧みな構成になっています。ただ、この巧みな下段の構成も、旧麒麟台の構造をうまく流用したもの、と考える事ができます。
画像から見る旧麒麟台は、古い形式(下段の上部がそのまま中段の勾欄になる)の屋台である事が分かります。
 現存する屋台の中で、古い形式を残しているのは布袋台だけですが、布袋台と旧麒麟台の画像を見てみると、共通した特徴があります。
現存する屋台の中で、古い形式を残しているのは布袋台だけですが、布袋台と旧麒麟台の画像を見てみると、共通した特徴があります。それは、台輪と下段の間に、最下段とも言える部分がある事です。
布袋台のその部分には、朱塗りの雷文つなぎの浮き彫りが入っていますが、上記の長倉さんの本によると、旧麒麟台のその部分には、青海波の彫刻が入っていたそうです。
という事は、旧麒麟台の最下段を流用して、現在の麒麟台の最下段が作られたと推測できますね。
実に巧く考えられています。
麒麟台は、下段の下に最下段があるため、他の屋台に比べて、下段と中段の高さの比率が微妙に違っていて少し腰高に見えますが、下段の独特の構造を巧く使って、逆に安定感と引き締ったプロポーションを得る事に成功しています。
この画像を見てもらいましょう。
 台輪の上に、少し幅の広い最下段が載り、その上に、さらに幅の広い下段回廊が載り、その上に、さらに幅の広い中段勾欄が載って、逆台形状の形態になっています。
台輪の上に、少し幅の広い最下段が載り、その上に、さらに幅の広い下段回廊が載り、その上に、さらに幅の広い中段勾欄が載って、逆台形状の形態になっています。その部分をよく見ると、台輪の上から中段の伊達柱まで一直線に通る柱によって作られた屋台本体の周りに、最下段、下段回廊、中段勾欄が付けられた形態である事が解ります。
こういう構造を持った屋台は、麒麟台と、おそらく同じ頃に群鳳さんが手掛けたと思われる、古川の青龍台の他にはありません。
 小学4年の春、曳き別れを観ていて、麒麟台のこの構造に気がついた時、唐子群遊彫刻よりも遥かに惹かれるものを感じて、ゾクゾクしながらしばらく麒麟台を追いかけた事を、今も憶えています。
小学4年の春、曳き別れを観ていて、麒麟台のこの構造に気がついた時、唐子群遊彫刻よりも遥かに惹かれるものを感じて、ゾクゾクしながらしばらく麒麟台を追いかけた事を、今も憶えています。まぁ、その当時からマニアックな見方をする子供だったという事なんでしょうかね。
さて、話を戻して・・・・台輪から中段勾欄まで逆台形状に広がってきた上には、中段と上段が載るわけですが、麒麟台の場合、実際にそうなのか、あるいはそう見えるように設計されているのか分かりませんが、中段と上段が、他の屋台に比べてスリムに見えるのです。
そのため、台輪から中段勾欄まで広がって来たシルエットが、上段勾欄、屋根、千木と狭まっていくのがハッキリと分かり、非常に均整のとれた、引き締ったプロポーションに見えます。
この引き締ったプロポーションは、見た目がいいのはもちろんですが、もう一つ、重要な役割を果たしていると思います。
屋台の美しさに関しては、好みの問題もあると思いますが、例えば、五台山や石橋台のような、ある種の渋さを持った美しさを良しとする人からすれば、麒麟台は装飾過多という事になるでしょう。

実際、麒麟台には装飾が多いし、例えばこの羅網のように、色の組み合わせから言っても派手な屋台である事は間違いありません。
でも、それだけたくさんの装飾を付けていても、決してゴテゴテとした印象を与える事がないのは、この引き締ったプロポーションが、そう見せているからだと思います。
実に良く考えられた設計だと思いますね。
唐子群遊彫刻を効果的にみせるため、誰も思いつかなかった構造を考案し、与鹿に負けない彫刻を彫り、屈指の美しさを誇る屋台を造り上げた・・・・群鳳さんの功績は計り知れないものがあると思います。
だから、オレが麒麟台について考える時、与鹿の事より、群鳳さんの事を多く考えてしまいますね。
まあね、オレがどんなに 群鳳>与鹿@麒麟台 だと言っても、麒麟台=与鹿 という公式が覆る事は無いでしょう。
でも、麒麟台を語る時、絶対に、初代村山群鳳の事を忘れてはいけないと思うのですよ。
もし、今度の春祭に、オレがここに書いた事を思い出してもらえたら、麒麟台をじっくりと観て、群鳳さんの執念を感じ取ってほしいと思います。
きっと、オレがここに書いた事が決して間違っていない事を、解ってもらえると思います。
 ただ、もしも麒麟台に与鹿の唐子群遊彫刻がなかったとしたら、はたして群鳳さんは麒麟台をここまでに美しく仕上げる事が出来たのだろうか、と考える事があります。
ただ、もしも麒麟台に与鹿の唐子群遊彫刻がなかったとしたら、はたして群鳳さんは麒麟台をここまでに美しく仕上げる事が出来たのだろうか、と考える事があります。上にも書いた古川の青龍台は、下段の構造や、屋根の千木の数が麒麟台と同じですから、おそらく、同じ頃に群鳳さんが手掛けた屋台だと推測できます。
もちろん、使えるお金や時間の違いもあったでしょうから、一概には言えませんが、麒麟台で感じられる壮絶なまでの執念は、残念な事に、青龍台では感じられない・・・・と思うのはオレだけでしょうか。
やはり、与鹿の作品があったからこそ全身全霊を打ち込んで麒麟台を仕上げた、と考えるべきなのだとオレは思います。
う〜ん、そう考えると、群鳳=与鹿@麒麟台 になるのかなぁ・・・・
ただ、完璧なまでの美を誇る麒麟台の中で、一カ所だけ、本当に惜しい、と思うところがあります。
 それは、下段前面の中央部分で、中央に立つ柱と枡組のせいで、真ん中の唐子の顔が全く見えなくなっているのですよ。
それは、下段前面の中央部分で、中央に立つ柱と枡組のせいで、真ん中の唐子の顔が全く見えなくなっているのですよ。ここだけは、何とかならなかったものかと思いますね。
もっとも、日光東照宮の陽明門には『魔除けの逆柱』(魔除けのために、わざと1本の柱だけ彫刻が逆さにしてある)があるくらいですから、そういう意味では、完璧でない方が正解なのかもしれません。
いや、でも・・・・もしも群鳳さんが、そこまで考えて、わざとそういう設計をしたのだったら・・・・
それこそ『完璧』と言うしかないですね。
では、また。
Ciao. Arrivederci!!
スポンサーリンク

Posted by spock at 17:35│Comments(4)
この記事へのコメント
その偉い人の孫は「もう彫らなくても一生食ってけるからいいや」てーな現在、
羨ましいですな。祖先の作った財産でいきてける人は羨ましいですな
羨ましいですな。祖先の作った財産でいきてける人は羨ましいですな
Posted by _~_ at 2009年04月06日 22:34
_~_さん、伝統を守るということはそんなに甘いもんじゃないですよ。毎回最高の物を作り続けることがどんなに難しいことか。
さて、マスター、久しぶりに拝見しましたら、私の得意な内容が。仰せの通り、群鳳さん、素晴らしいです。今度、谷口与鹿に続いて群鳳さんのことを書かないといけないと思っています。
さて、文中、ちょっと誤りが。古川の青龍台のことですが、残念ながら群鳳さんの作品ではありません。古川の大工中村房吉さんの作品なんです。
昭和8年に作られたということですから、おそらく、房吉さんは、高山の屋台の中で麒麟台を参考に作られたのではないかと思います。下段部分の構造はほとんど同じですよね。
私も勘違いしていたのですが、大正10年に麒麟台が改修されたときに、そこに与鹿の彫刻がはめ込まれました。与鹿さんの彫刻は、先日組の人がはずしてくださったのですが、それをみると、単なる板切れに彫られた彫刻に見えます。ところが、ああやって、枠の内側に入れた時に、影ができて微妙にコントラストができる。そうしますと、与鹿さんの彫刻が浮き上がって見えるんです。
群鳳さんが、その影を作ることで与鹿さんの彫刻が浮き上がって見えることを発見したとなれば、すごい人だったと思います。
組の人をして「はずしても見事なのは群鳳、とりつけて見事なのが与鹿」といわしめたように、屋台と言う物にとりつけて初めて、与鹿さんの彫刻は見事になります。
私のブログにも掲載しておりますので、ごらんください。
http://hidasaihakken.hida-ch.com/e98170.html
さて、マスター、久しぶりに拝見しましたら、私の得意な内容が。仰せの通り、群鳳さん、素晴らしいです。今度、谷口与鹿に続いて群鳳さんのことを書かないといけないと思っています。
さて、文中、ちょっと誤りが。古川の青龍台のことですが、残念ながら群鳳さんの作品ではありません。古川の大工中村房吉さんの作品なんです。
昭和8年に作られたということですから、おそらく、房吉さんは、高山の屋台の中で麒麟台を参考に作られたのではないかと思います。下段部分の構造はほとんど同じですよね。
私も勘違いしていたのですが、大正10年に麒麟台が改修されたときに、そこに与鹿の彫刻がはめ込まれました。与鹿さんの彫刻は、先日組の人がはずしてくださったのですが、それをみると、単なる板切れに彫られた彫刻に見えます。ところが、ああやって、枠の内側に入れた時に、影ができて微妙にコントラストができる。そうしますと、与鹿さんの彫刻が浮き上がって見えるんです。
群鳳さんが、その影を作ることで与鹿さんの彫刻が浮き上がって見えることを発見したとなれば、すごい人だったと思います。
組の人をして「はずしても見事なのは群鳳、とりつけて見事なのが与鹿」といわしめたように、屋台と言う物にとりつけて初めて、与鹿さんの彫刻は見事になります。
私のブログにも掲載しておりますので、ごらんください。
http://hidasaihakken.hida-ch.com/e98170.html
Posted by rekisy at 2011年06月02日 15:17
それと、先日、東勝廣さんの講演がありました。そのときに「恵比寿台の車輪は当初、御所車を作る計画があって、そのように予定していたが、通りがせまいために、御所車だとどうしても外輪にしないといけないので、屋台が入らない。そのために、従来通りの内輪とすることになった。しかし下段の外側部分については、すでに作ってあるので、御所車が入るように枠が切られていた。そのため、そこに急遽彫刻を入れることになり、作られたのが親子龍だったのではなかろうか」ということでした。
この話はこちらのブログに掲載しています。
http://hidasaihakken.hida-ch.com/e260145.html
ごらんになってください。とても面白かったです。
この話はこちらのブログに掲載しています。
http://hidasaihakken.hida-ch.com/e260145.html
ごらんになってください。とても面白かったです。
Posted by rekisy at 2011年06月02日 15:24
rekisy さん
ぜひ、初代群鳳さんの事、書いて下さい。
谷口与鹿については、もう書き尽くされている感もありますが、それに比べて、群鳳さんの事が書かれる事は、本当に少ないですね。
古川の青龍台は、群鳳さんの手によるものではないのですか・・・・意外ですね。
でも、下段の構成から千木の数まで同じですから、設計自体は群鳳さんがやった、あるいは、群鳳さんの了解を得て真似をした、というところではないでしょうか。
去年だったか、rekisyさんが店に来られた時の話の中で、「屋台に取り付けて見事なのが与鹿の彫刻、そのままでも見事なのが群鳳の彫刻」という、麒麟台組の人の言葉を聞いて、あぁなるほど、って思いました。
群鳳さんの彫刻は、圧倒的に「彫りが深い」・・・・だから、あえて影をつける必要がないのでしょうね。
高山の屋台における群鳳さんの業績が、再評価されることを、心底願うものです。
恵比須台の設計図(谷口家のものだったと思いますが)に、御所車が描かれているのを見た事がありますが、内板車に変更になったのは、そういう理由があったのですね。
あの狭い通りを通る時、屋台が一番美しく見えると思いますが、その狭さが変更の原因というのも、皮肉ではありますね。
もっとも、そのおかげて、与鹿の龍が残っているわけですが。
ただ、御所車の枠が作られていたので彫刻を入れた、というのは、少し違うように思います。
あくまでも素人考えですが、あの半丸窓に合う御所車を想像すると、どう考えてもバランス的におかしいし、枠の外に彫刻を入れるスペースが全く存在しないのも変ですね。
そう考えると、すでに作られていた枠を手直しして半丸窓に改造した、あるいは、一番無理の無い設計の変更が半丸窓だった、というのが正解なのではないかと思います。
まぁ、こんな事をいろいろ考えられるのも、屋台にそれだけの魅力があるという事なんでしょう。
またいつか、お話したいですね。
では、また。
ぜひ、初代群鳳さんの事、書いて下さい。
谷口与鹿については、もう書き尽くされている感もありますが、それに比べて、群鳳さんの事が書かれる事は、本当に少ないですね。
古川の青龍台は、群鳳さんの手によるものではないのですか・・・・意外ですね。
でも、下段の構成から千木の数まで同じですから、設計自体は群鳳さんがやった、あるいは、群鳳さんの了解を得て真似をした、というところではないでしょうか。
去年だったか、rekisyさんが店に来られた時の話の中で、「屋台に取り付けて見事なのが与鹿の彫刻、そのままでも見事なのが群鳳の彫刻」という、麒麟台組の人の言葉を聞いて、あぁなるほど、って思いました。
群鳳さんの彫刻は、圧倒的に「彫りが深い」・・・・だから、あえて影をつける必要がないのでしょうね。
高山の屋台における群鳳さんの業績が、再評価されることを、心底願うものです。
恵比須台の設計図(谷口家のものだったと思いますが)に、御所車が描かれているのを見た事がありますが、内板車に変更になったのは、そういう理由があったのですね。
あの狭い通りを通る時、屋台が一番美しく見えると思いますが、その狭さが変更の原因というのも、皮肉ではありますね。
もっとも、そのおかげて、与鹿の龍が残っているわけですが。
ただ、御所車の枠が作られていたので彫刻を入れた、というのは、少し違うように思います。
あくまでも素人考えですが、あの半丸窓に合う御所車を想像すると、どう考えてもバランス的におかしいし、枠の外に彫刻を入れるスペースが全く存在しないのも変ですね。
そう考えると、すでに作られていた枠を手直しして半丸窓に改造した、あるいは、一番無理の無い設計の変更が半丸窓だった、というのが正解なのではないかと思います。
まぁ、こんな事をいろいろ考えられるのも、屋台にそれだけの魅力があるという事なんでしょう。
またいつか、お話したいですね。
では、また。
Posted by spock at 2011年06月03日 20:15