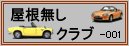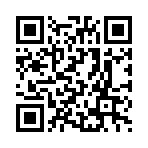2008年10月29日
久しぶりに・・・・
Ciao. spockです。
4月にジャガーの車検を受けた時、無料オイル交換券を貰ったのですが、期限が迫って来たので、慌ててヤフオクでオイルを落札しました。
 20W-50の鉱物油が指定されているので、選択肢はあまり無いのだけれど、選んだのはコレ・・・・
20W-50の鉱物油が指定されているので、選択肢はあまり無いのだけれど、選んだのはコレ・・・・
格安のシェヴロン・モーターオイル・・・・12クォートで4200円!!
でも、結果はバッチリ!!
久しぶりのオイル交換で、エンジンの音が軽くなりました。
20年目のV12エンジンは絶好調です。
(これで、もう少し燃費が良かったらなぁ・・・・)
え〜、ブログを更新するのも久しぶりです。
9月からこっち、何かとバタバタしていた所為もあるのですが、気がついてみれば、もう10月も終わりですねぇ。
9月はおかげさまで忙しかったし、10月はヒマだと思っていたら、後半になって急に予約が増えて来て・・・・
でもね、忙しい事はいいことですよね。
もっとも、9月は忙しかったとは言っても、支払いを全部すませてみたら、通帳の残高は大して増えていなかったんですよ・・・・orz
あの忙しさは何だったんでしょうね・・・・って、まぁ、根本的に儲からない店だという事なんでしょうけど・・・・(多分、10月も同じパターンなんだろうなぁ)
時々、常連のお客さんから、料理を出し過ぎじゃないの、って言われる事がありますが、まぁ、それで喜んでもらえればいいかな、って思うんですよ。
以前にも書いた事がありますが、やはり料理人だった祖父も、お客さんが驚くほど多くの料理を出したそうですから、オレはその血を受け継いだんでしょう。
この前、ある会合で初めてウチに来られたお客さんがえらく気に入って下さって、その場で予約を入れて、次の日に奥様と一緒に来られた事がありましたが、本当にうれしかったですね。
お客さんに喜んでもらえる事が一番ですから、そういう時は、儲ける事なんて全く考えなくなってしまいます。
まぁね、自分の好きな事をやってカネを貰っているんですから、それで儲けようなんて考えるのはムシが良すぎると思うんですけどね。
さて、今回は八幡祭の事を書こうと思っていたのだけれど・・・・って、もう半月も前の事だけど・・・・まぁ、いいか・・・・
ウチは飛騨総社の氏子ですから、山王祭の時も八幡祭の時も、たいていヒマです。
なので、予約が入っていなければ、夜は店を閉めて、夜祭りを見に行く事にしてますけど・・・・
でも、今年の八幡祭は結構忙しかったのですよ。
以前書いた事のある、ダイヴィング仲間が来る事になっていたからです。
みんな揃って来るという事だったので、半年も前から、たけちくん(やどっち15号)の所へ宿をお願いしていたのですが、仕事の都合やら何やらで人数が減ってしまい、迷惑をかけてしまいました。(たけちくん、ゴメンネ!!)
ちなみに、彼女達による宿の評価は「おばあちゃんの家に行ったみたいにくつろげた」との事で、かなり高いものでしたよ。
今年の祭は、一般の勤めの人には出掛けにくかっただろうと思います。
9日10日と休んだら、必然的にその後の3連休も休むわけですから、5連休を取る事になりますからね。
そんな難しい時にもかかわらず出掛けて来てくれた友人達を、夜祭りに連れて行きました。
安川通りを歩いて行くと、下二之町の角でそれ以上進めなくなったので、下三之町を下って、細い横道から二之町へ出ると、ちょうど目の前を豊明台が通り過ぎて行くところでした。
それを見た友人達は、歓声をあげていましたね。
子供の頃から何回も見ているオレでも、見るたびに感動するのですから、初めて見る人の感動の度合いは、はるかに大きいのでしょうね。
その後、鳩峰車、大八台と通るのを見たのですが、その時、40年近く前の事を思い出しました。
1969年の祭の曳き別れの時、親戚の小父さんに頼んで、大八台に乗せてもらった事があるのですよ。
小父さんの家で直衣を着て、小父さんと屋台のところまで行き、屋台に乗り込みました。
 大八台は他の屋台と違って、御殿造りの中段に乗るのですが、その時乗ったのはオレを含めて4人・・・・
大八台は他の屋台と違って、御殿造りの中段に乗るのですが、その時乗ったのはオレを含めて4人・・・・
本来なら、そこで子供達が『大八曲』(高山の屋台の半数以上は、大八曲を基にした『大八崩し』を屋台囃子として使っている)を演奏するのだそうですが、小さなオープンリールのテープレコーダーから囃子が流れるのを見て、寂しく思った事を憶えています。
初めての曳き別れ体験は感動的なもので、今でもハッキリと憶えているのですよ。
下二之町(三之町だったかもしれない)を上がって行く時、屋台を曳く人達が、東とか西とか、声をかけながら方向を修正していた事や、8ミリカメラを構えた観光客から「太鼓を叩いてくれ」って言われて一人の子が叩いたのだけれど、あまりにも機械的に叩いたので、もうちょっと何とかできるだろうと思った事、途中で中段の提灯が燃え出して、組の人が慌てて消したけど、金格子の天井にススの黒い跡が残った事、屋台を降りる時、屋台組の人が「はい、○○の代理人」ってキャラメルをくれた事・・・・
あれから39年も経ったというのに、あの時の思い出は全く色褪せる事がないですね。
屋台のない町で育ったから、余計に強く印象に残っているのかもしれませんが・・・・
その後、一之町へ出て、曳き別れを見たのですが、友人達は夜祭を堪能したようです。
で、店へ戻って食事をする事に・・・・
彼女達がウチの店に来るのは、3年ぶりです。
今回はカウンターでコースを食べる事に・・・・話しながら食べるので忙しかったでしょうけど、料理も会話も楽しんでくれたと思います。
この日、意外な事に、その後もう一組の予約がありました。
曳き別れの屋台を曳いた後に食事をしたいとの事だったので、喜んでお受けしました。
後で聞いた話では、その方の屋台組では、曳き別れの後、屋台蔵の前で中華そばを食べるのが習わしなのだそうですが、それを抜け出してウチに来られたそうです。
実にシャレた方ですね。
 ところで、このところ毎年、必ず布袋台のからくり奉納を観に行きます。
ところで、このところ毎年、必ず布袋台のからくり奉納を観に行きます。
昼の営業が終わってからしか行けませんから、9日の3時からの奉納を観に行く事にしているのですが、からくりが終わって屋台からからくりの装置が外され、曳き別れの準備のために町内へ戻るまでのしばらくの間、からくりの糸を引いている親友の千葉茂と、その日の出来具合について話すのですよ。
 千葉はもう長い事やっていますから、出来不出来を気にしながら見るような事はありませんが、唐子の首を動かしている息子の方は、毎年見る毎に動きが良くなっているのが分かります。
千葉はもう長い事やっていますから、出来不出来を気にしながら見るような事はありませんが、唐子の首を動かしている息子の方は、毎年見る毎に動きが良くなっているのが分かります。
「今年は、首の動きが音楽にピッタリ合っていたな」って言ったら、「音楽に合うように引いたから・・・・」って、少しはにかんだような顔をして答えました。
屋台組の人手不足が問題になる中、こういう後継者がいるのは心強い事ですね。
10日も3時から下一之町でからくりをやると聞いたので、昼の営業を終えてから見に行きました。
後で聞いた話では、去年より人は少なかったそうですが、それでも多くの人達がからくりの始まるのを待っていました。
いやぁ、何回見ても、このからくりはスゴいと思います。
これを操る人達の技術もスゴいのですが、何と言っても、こんなからくりを作った人がスゴい!!
千葉は、改良の繰り返しでここまで出来たのだろう、と言います。
多分それが正解なのでしょうが、こういう完成した形で残っているという事自体、奇跡的な事なんじゃないかとオレは思いますね。
以前、からくりについて調べた時に読んだ本に、布袋台の綾渡りのような所謂『離れからくり』は、名古屋近辺にも多く存在するそうですが、綾を渡り終わった人形を別の人形が受け取るというのは、布袋台のからくり以外には存在しないのだとありました。
要するに、世界で唯一のもの、と言う事ですね。
からくりが終わった後、なべしま銘茶の前で鍋島さんを見かけたので挨拶すると、お茶を飲んで行って下さいと言われたので、頂く事にしました。
鉄瓶でお湯が沸いている火鉢の前に座って待っていると、目の前に置かれたのは・・・・なんと抹茶でした。
オレはお茶が大好きで毎日多量に飲むのだけれど、『お茶の作法』は全く知らない無粋者ですから、思わず身構えてしまいましたが、以前テレビで見たのを思い出しながら頂きました。(後で母に聞いてみたら、概ね合っていましたが・・・・)
驚いたのは、その抹茶がスゴく甘かった事。
抹茶といえば、苦いというイメージしかなかったのですが、この抹茶は全く違う!!
挽きたての抹茶は甘いものなのだそうで、それが2日もすると苦みが出てくるのだそうです。
今まで苦いものと思っていた抹茶は、挽いてから時間が経ったお茶だったという事なんですね。
挽きたての抹茶なら、茶菓子など無くても、いくらでも飲めますね。
お茶の事などを聞きながら、抹茶を味わっていると、布袋台組の人達がやって来て、奥から木の箱を運び出してきました。
からくり人形をしまう箱のようです。
で、しばらくすると、いくつかに分解されたからくりの装置が運び込まれてきました。
どうぞ見て下さい、と言われたので、近くへ寄って見せてもらう事に・・・・
観光客の人達も入って来て、見物してました。
 からくりの構造については、以前から千葉にいろいろ聞いていたのですが、実物を間近に見るのは初めてなので、何か興奮しましたねぇ。
からくりの構造については、以前から千葉にいろいろ聞いていたのですが、実物を間近に見るのは初めてなので、何か興奮しましたねぇ。
ちょうど先日手に入れたばかりの、515万画素のカメラ付きケイタイを持っていたので、恐る恐る、写真を撮ってもいいですか、と訊くと、いいですよとの返事・・・・写真を撮りまくりました。
 千葉もやって来て片付けを始めたので、合間合間に質問をして、いろいろ教えてもらいました。
千葉もやって来て片付けを始めたので、合間合間に質問をして、いろいろ教えてもらいました。
それにしても、よくここまで、と思えるほど緻密に作られていますね。
ひたすら、ほーっ、へぇーっ、て言いながら、見せてもらいました。
1時間もしないうちに、からくりはすべて箱に納まり、屋台蔵へ運ばれる事に・・・・
千葉が、ひとつ持って来て、と言うので、手近にあった道具箱を持って蔵へむかったのですが、その道具箱は、かなり古いもののようで、蓋がすり減っているのですよ。
千葉の話では、以前はその箱に座って、からくりの糸を引いていたのだとの事。
ずっしりとした重さに、さらに歴史の重さが加わったようで、蔵に着くまで緊張しましたね。
からくりの箱は蔵の中に納められました。
次は屋台を蔵に入れる番です。
布袋台の蔵は、別院の前から下一通りへ抜ける坂道の途中にあるのですが、おそらく、高山の屋台蔵のなかで、一番屋台の出し入れにテクニックを要する蔵だろうと思います。
下一通りで向きを変えて、細い横道に入り、その先でさらに向きを変えて坂を上り、坂の途中で屋台が下がらないように止めながら向きを変えて蔵に入れるのです。
経験とカンが無ければ出来ない事ですね。
屋台が蔵に納まり、他の備品類も納まる所に納まった頃、仕事のある千葉と、夜の準備のあるオレは、一緒に蔵を離れました。
今年の八幡祭は、見るだけではなく、体験し、感じる祭でした。
本当にいい体験をさせてもらったと思います。
布袋台組の皆さんに、感謝感謝です!!
で、その次の日、たまたま店に来られた布袋台組の方と話した時、片付けを手伝った事のお礼を言われたので、「こちらこそ貴重な体験をさせてもらって」と答えたのですが、続けて勢いで「来年も手伝いに行こうかな」って言ったのですよ。
そしたら「ぜひ来て下さい。千葉さんにも言っておきますから、一緒に屋台を曳いて下さい。」って言われました。
ウチは祭の時はヒマですから、オレで良ければ、いくらでも行きますよ。
先日新聞に、屋台組の人手不足や後継者不足の事が書かれていましたが、かなり深刻な問題になっているようですね。
先日、カウンターに来てくれた某屋台組の同級生と話していて、祭の話が出たら、手伝いに来てよ、って言われましたからね。
オレは屋台の無い町で育った人間ですから、実際に歴史の積み重ねの中で続いて来た屋台組の人に、とやかく言える立場ではありませんが、屋台組外の屋台好きとして、考える事はいろいろあります。
将来の事を考えるのであれば、屋台の無い町の屋台好きの子供をスカウトするのが一番いいのではないかと思いますね。
そういう新風を吹き込む時期に来ているのではないかとオレは思うのですが、さて、屋台組の方々はどう思われるでしょうか。
では、また。
Ciao. Arrivederci!!
4月にジャガーの車検を受けた時、無料オイル交換券を貰ったのですが、期限が迫って来たので、慌ててヤフオクでオイルを落札しました。
格安のシェヴロン・モーターオイル・・・・12クォートで4200円!!
でも、結果はバッチリ!!
久しぶりのオイル交換で、エンジンの音が軽くなりました。
20年目のV12エンジンは絶好調です。
(これで、もう少し燃費が良かったらなぁ・・・・)
え〜、ブログを更新するのも久しぶりです。
9月からこっち、何かとバタバタしていた所為もあるのですが、気がついてみれば、もう10月も終わりですねぇ。
9月はおかげさまで忙しかったし、10月はヒマだと思っていたら、後半になって急に予約が増えて来て・・・・
でもね、忙しい事はいいことですよね。
もっとも、9月は忙しかったとは言っても、支払いを全部すませてみたら、通帳の残高は大して増えていなかったんですよ・・・・orz
あの忙しさは何だったんでしょうね・・・・って、まぁ、根本的に儲からない店だという事なんでしょうけど・・・・(多分、10月も同じパターンなんだろうなぁ)
時々、常連のお客さんから、料理を出し過ぎじゃないの、って言われる事がありますが、まぁ、それで喜んでもらえればいいかな、って思うんですよ。
以前にも書いた事がありますが、やはり料理人だった祖父も、お客さんが驚くほど多くの料理を出したそうですから、オレはその血を受け継いだんでしょう。
この前、ある会合で初めてウチに来られたお客さんがえらく気に入って下さって、その場で予約を入れて、次の日に奥様と一緒に来られた事がありましたが、本当にうれしかったですね。
お客さんに喜んでもらえる事が一番ですから、そういう時は、儲ける事なんて全く考えなくなってしまいます。
まぁね、自分の好きな事をやってカネを貰っているんですから、それで儲けようなんて考えるのはムシが良すぎると思うんですけどね。
さて、今回は八幡祭の事を書こうと思っていたのだけれど・・・・って、もう半月も前の事だけど・・・・まぁ、いいか・・・・
ウチは飛騨総社の氏子ですから、山王祭の時も八幡祭の時も、たいていヒマです。
なので、予約が入っていなければ、夜は店を閉めて、夜祭りを見に行く事にしてますけど・・・・
でも、今年の八幡祭は結構忙しかったのですよ。
以前書いた事のある、ダイヴィング仲間が来る事になっていたからです。
みんな揃って来るという事だったので、半年も前から、たけちくん(やどっち15号)の所へ宿をお願いしていたのですが、仕事の都合やら何やらで人数が減ってしまい、迷惑をかけてしまいました。(たけちくん、ゴメンネ!!)
ちなみに、彼女達による宿の評価は「おばあちゃんの家に行ったみたいにくつろげた」との事で、かなり高いものでしたよ。
今年の祭は、一般の勤めの人には出掛けにくかっただろうと思います。
9日10日と休んだら、必然的にその後の3連休も休むわけですから、5連休を取る事になりますからね。
そんな難しい時にもかかわらず出掛けて来てくれた友人達を、夜祭りに連れて行きました。
安川通りを歩いて行くと、下二之町の角でそれ以上進めなくなったので、下三之町を下って、細い横道から二之町へ出ると、ちょうど目の前を豊明台が通り過ぎて行くところでした。
それを見た友人達は、歓声をあげていましたね。
子供の頃から何回も見ているオレでも、見るたびに感動するのですから、初めて見る人の感動の度合いは、はるかに大きいのでしょうね。
その後、鳩峰車、大八台と通るのを見たのですが、その時、40年近く前の事を思い出しました。
1969年の祭の曳き別れの時、親戚の小父さんに頼んで、大八台に乗せてもらった事があるのですよ。
小父さんの家で直衣を着て、小父さんと屋台のところまで行き、屋台に乗り込みました。
本来なら、そこで子供達が『大八曲』(高山の屋台の半数以上は、大八曲を基にした『大八崩し』を屋台囃子として使っている)を演奏するのだそうですが、小さなオープンリールのテープレコーダーから囃子が流れるのを見て、寂しく思った事を憶えています。
初めての曳き別れ体験は感動的なもので、今でもハッキリと憶えているのですよ。
下二之町(三之町だったかもしれない)を上がって行く時、屋台を曳く人達が、東とか西とか、声をかけながら方向を修正していた事や、8ミリカメラを構えた観光客から「太鼓を叩いてくれ」って言われて一人の子が叩いたのだけれど、あまりにも機械的に叩いたので、もうちょっと何とかできるだろうと思った事、途中で中段の提灯が燃え出して、組の人が慌てて消したけど、金格子の天井にススの黒い跡が残った事、屋台を降りる時、屋台組の人が「はい、○○の代理人」ってキャラメルをくれた事・・・・
あれから39年も経ったというのに、あの時の思い出は全く色褪せる事がないですね。
屋台のない町で育ったから、余計に強く印象に残っているのかもしれませんが・・・・
その後、一之町へ出て、曳き別れを見たのですが、友人達は夜祭を堪能したようです。
で、店へ戻って食事をする事に・・・・
彼女達がウチの店に来るのは、3年ぶりです。
今回はカウンターでコースを食べる事に・・・・話しながら食べるので忙しかったでしょうけど、料理も会話も楽しんでくれたと思います。
この日、意外な事に、その後もう一組の予約がありました。
曳き別れの屋台を曳いた後に食事をしたいとの事だったので、喜んでお受けしました。
後で聞いた話では、その方の屋台組では、曳き別れの後、屋台蔵の前で中華そばを食べるのが習わしなのだそうですが、それを抜け出してウチに来られたそうです。
実にシャレた方ですね。
 ところで、このところ毎年、必ず布袋台のからくり奉納を観に行きます。
ところで、このところ毎年、必ず布袋台のからくり奉納を観に行きます。昼の営業が終わってからしか行けませんから、9日の3時からの奉納を観に行く事にしているのですが、からくりが終わって屋台からからくりの装置が外され、曳き別れの準備のために町内へ戻るまでのしばらくの間、からくりの糸を引いている親友の千葉茂と、その日の出来具合について話すのですよ。
「今年は、首の動きが音楽にピッタリ合っていたな」って言ったら、「音楽に合うように引いたから・・・・」って、少しはにかんだような顔をして答えました。
屋台組の人手不足が問題になる中、こういう後継者がいるのは心強い事ですね。
10日も3時から下一之町でからくりをやると聞いたので、昼の営業を終えてから見に行きました。
後で聞いた話では、去年より人は少なかったそうですが、それでも多くの人達がからくりの始まるのを待っていました。
いやぁ、何回見ても、このからくりはスゴいと思います。
これを操る人達の技術もスゴいのですが、何と言っても、こんなからくりを作った人がスゴい!!
千葉は、改良の繰り返しでここまで出来たのだろう、と言います。
多分それが正解なのでしょうが、こういう完成した形で残っているという事自体、奇跡的な事なんじゃないかとオレは思いますね。
以前、からくりについて調べた時に読んだ本に、布袋台の綾渡りのような所謂『離れからくり』は、名古屋近辺にも多く存在するそうですが、綾を渡り終わった人形を別の人形が受け取るというのは、布袋台のからくり以外には存在しないのだとありました。
要するに、世界で唯一のもの、と言う事ですね。
からくりが終わった後、なべしま銘茶の前で鍋島さんを見かけたので挨拶すると、お茶を飲んで行って下さいと言われたので、頂く事にしました。
鉄瓶でお湯が沸いている火鉢の前に座って待っていると、目の前に置かれたのは・・・・なんと抹茶でした。
オレはお茶が大好きで毎日多量に飲むのだけれど、『お茶の作法』は全く知らない無粋者ですから、思わず身構えてしまいましたが、以前テレビで見たのを思い出しながら頂きました。(後で母に聞いてみたら、概ね合っていましたが・・・・)
驚いたのは、その抹茶がスゴく甘かった事。
抹茶といえば、苦いというイメージしかなかったのですが、この抹茶は全く違う!!
挽きたての抹茶は甘いものなのだそうで、それが2日もすると苦みが出てくるのだそうです。
今まで苦いものと思っていた抹茶は、挽いてから時間が経ったお茶だったという事なんですね。
挽きたての抹茶なら、茶菓子など無くても、いくらでも飲めますね。
お茶の事などを聞きながら、抹茶を味わっていると、布袋台組の人達がやって来て、奥から木の箱を運び出してきました。
からくり人形をしまう箱のようです。
で、しばらくすると、いくつかに分解されたからくりの装置が運び込まれてきました。
どうぞ見て下さい、と言われたので、近くへ寄って見せてもらう事に・・・・
観光客の人達も入って来て、見物してました。
 からくりの構造については、以前から千葉にいろいろ聞いていたのですが、実物を間近に見るのは初めてなので、何か興奮しましたねぇ。
からくりの構造については、以前から千葉にいろいろ聞いていたのですが、実物を間近に見るのは初めてなので、何か興奮しましたねぇ。ちょうど先日手に入れたばかりの、515万画素のカメラ付きケイタイを持っていたので、恐る恐る、写真を撮ってもいいですか、と訊くと、いいですよとの返事・・・・写真を撮りまくりました。
 千葉もやって来て片付けを始めたので、合間合間に質問をして、いろいろ教えてもらいました。
千葉もやって来て片付けを始めたので、合間合間に質問をして、いろいろ教えてもらいました。それにしても、よくここまで、と思えるほど緻密に作られていますね。
ひたすら、ほーっ、へぇーっ、て言いながら、見せてもらいました。
1時間もしないうちに、からくりはすべて箱に納まり、屋台蔵へ運ばれる事に・・・・
千葉が、ひとつ持って来て、と言うので、手近にあった道具箱を持って蔵へむかったのですが、その道具箱は、かなり古いもののようで、蓋がすり減っているのですよ。
千葉の話では、以前はその箱に座って、からくりの糸を引いていたのだとの事。
ずっしりとした重さに、さらに歴史の重さが加わったようで、蔵に着くまで緊張しましたね。
からくりの箱は蔵の中に納められました。
次は屋台を蔵に入れる番です。
布袋台の蔵は、別院の前から下一通りへ抜ける坂道の途中にあるのですが、おそらく、高山の屋台蔵のなかで、一番屋台の出し入れにテクニックを要する蔵だろうと思います。
下一通りで向きを変えて、細い横道に入り、その先でさらに向きを変えて坂を上り、坂の途中で屋台が下がらないように止めながら向きを変えて蔵に入れるのです。
経験とカンが無ければ出来ない事ですね。
屋台が蔵に納まり、他の備品類も納まる所に納まった頃、仕事のある千葉と、夜の準備のあるオレは、一緒に蔵を離れました。
今年の八幡祭は、見るだけではなく、体験し、感じる祭でした。
本当にいい体験をさせてもらったと思います。
布袋台組の皆さんに、感謝感謝です!!
で、その次の日、たまたま店に来られた布袋台組の方と話した時、片付けを手伝った事のお礼を言われたので、「こちらこそ貴重な体験をさせてもらって」と答えたのですが、続けて勢いで「来年も手伝いに行こうかな」って言ったのですよ。
そしたら「ぜひ来て下さい。千葉さんにも言っておきますから、一緒に屋台を曳いて下さい。」って言われました。
ウチは祭の時はヒマですから、オレで良ければ、いくらでも行きますよ。
先日新聞に、屋台組の人手不足や後継者不足の事が書かれていましたが、かなり深刻な問題になっているようですね。
先日、カウンターに来てくれた某屋台組の同級生と話していて、祭の話が出たら、手伝いに来てよ、って言われましたからね。
オレは屋台の無い町で育った人間ですから、実際に歴史の積み重ねの中で続いて来た屋台組の人に、とやかく言える立場ではありませんが、屋台組外の屋台好きとして、考える事はいろいろあります。
将来の事を考えるのであれば、屋台の無い町の屋台好きの子供をスカウトするのが一番いいのではないかと思いますね。
そういう新風を吹き込む時期に来ているのではないかとオレは思うのですが、さて、屋台組の方々はどう思われるでしょうか。
では、また。
Ciao. Arrivederci!!
スポンサーリンク

Posted by spock at 17:33│Comments(2)
この記事へのコメント
どうも~ 昨日は、ありがとうございました。
楽しかったです。
10月9日もご利用いただきまして、ありがとうございます。
屋台組の件ですが、確かに同感です。
ただ伝統を守るには、ある程度なプライドも必要だと思いますし、難しいところですね~
前にもコメントしましたが、私もお祭り大好きで、総社の親子獅子に入りたかったのですが、親に猛反対され、その代わりに、小さいころから麒麟台に乗せてもらい、秋は布袋台。
今では、崑崗台です。
今年ですが、屋台を曳いているときに、観光客の会話で、「若い子もいるね~」 「どうせバイトでしょ」と言ってるのが聞こえてきて、かなり心外でした。
バイトなんかじゃないです! 好きで手伝ってるし、お金もらうどころか、お酒持参で参加させてもらっていますし、自分で言うのもなんですが、祭り行程・屋台に関しては、相当な知識を持っている自信があります。
崑崗台組は、いつでも手伝いに来てよ~といった歓迎ムードですが、そうじゃない屋台組もありますし、人手がないので、女性も・・・という新聞記事も今年ありましたね~
この件に関しては非常に、長くなるので、また口頭で(笑)
2年後の春祭りですが、担当の町内の友人から青竹やりませんか?といわれましたが、さすがに青竹は断りました。
すごく、やってみたいですけど・・・
いかがですか?(笑)
なんだか、長くなってまとまらないコメントですが、お店でゆっくり話したい話題ですね。
では、また♪
楽しかったです。
10月9日もご利用いただきまして、ありがとうございます。
屋台組の件ですが、確かに同感です。
ただ伝統を守るには、ある程度なプライドも必要だと思いますし、難しいところですね~
前にもコメントしましたが、私もお祭り大好きで、総社の親子獅子に入りたかったのですが、親に猛反対され、その代わりに、小さいころから麒麟台に乗せてもらい、秋は布袋台。
今では、崑崗台です。
今年ですが、屋台を曳いているときに、観光客の会話で、「若い子もいるね~」 「どうせバイトでしょ」と言ってるのが聞こえてきて、かなり心外でした。
バイトなんかじゃないです! 好きで手伝ってるし、お金もらうどころか、お酒持参で参加させてもらっていますし、自分で言うのもなんですが、祭り行程・屋台に関しては、相当な知識を持っている自信があります。
崑崗台組は、いつでも手伝いに来てよ~といった歓迎ムードですが、そうじゃない屋台組もありますし、人手がないので、女性も・・・という新聞記事も今年ありましたね~
この件に関しては非常に、長くなるので、また口頭で(笑)
2年後の春祭りですが、担当の町内の友人から青竹やりませんか?といわれましたが、さすがに青竹は断りました。
すごく、やってみたいですけど・・・
いかがですか?(笑)
なんだか、長くなってまとまらないコメントですが、お店でゆっくり話したい話題ですね。
では、また♪
Posted by takechi at 2008年10月29日 21:37
どうも〜
楽しんでもらえて良かった!!
次回は、ショルダーとヘルメット(オレのを持って行きます)を着けて、プレイコール&ダッシュをやりましょう。
確かにね、屋台組外の人間として、できる事はたかが知れていますが、でも、オレにできる事なら手伝わせてもらいますよ、という気持ちは持っていたいですからね。
また、ゆっくりと話しましょう。
青竹・・・・流石に荷が重過ぎますね。
では、また!!
楽しんでもらえて良かった!!
次回は、ショルダーとヘルメット(オレのを持って行きます)を着けて、プレイコール&ダッシュをやりましょう。
確かにね、屋台組外の人間として、できる事はたかが知れていますが、でも、オレにできる事なら手伝わせてもらいますよ、という気持ちは持っていたいですからね。
また、ゆっくりと話しましょう。
青竹・・・・流石に荷が重過ぎますね。
では、また!!
Posted by spock at 2008年10月29日 23:30
at 2008年10月29日 23:30
 at 2008年10月29日 23:30
at 2008年10月29日 23:30